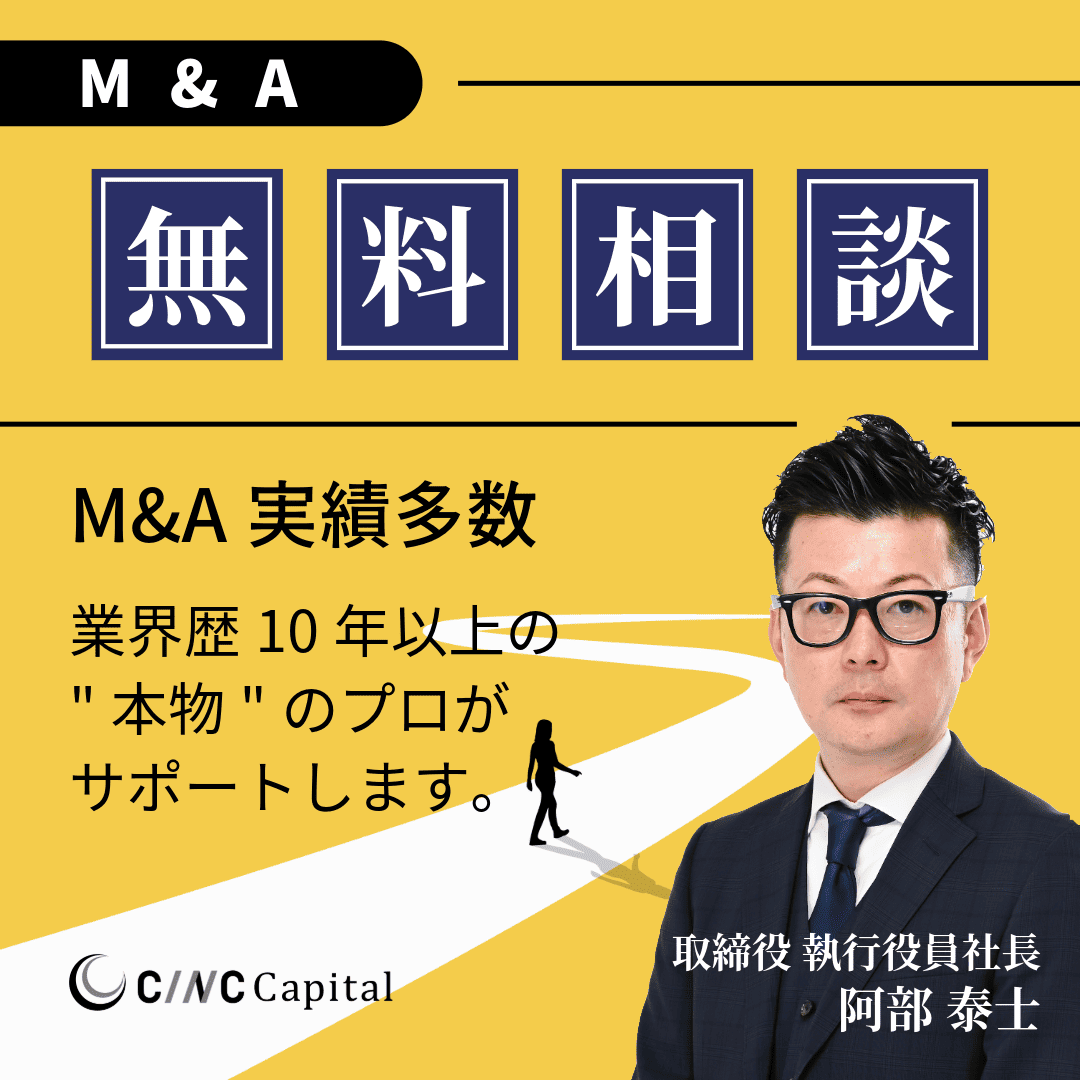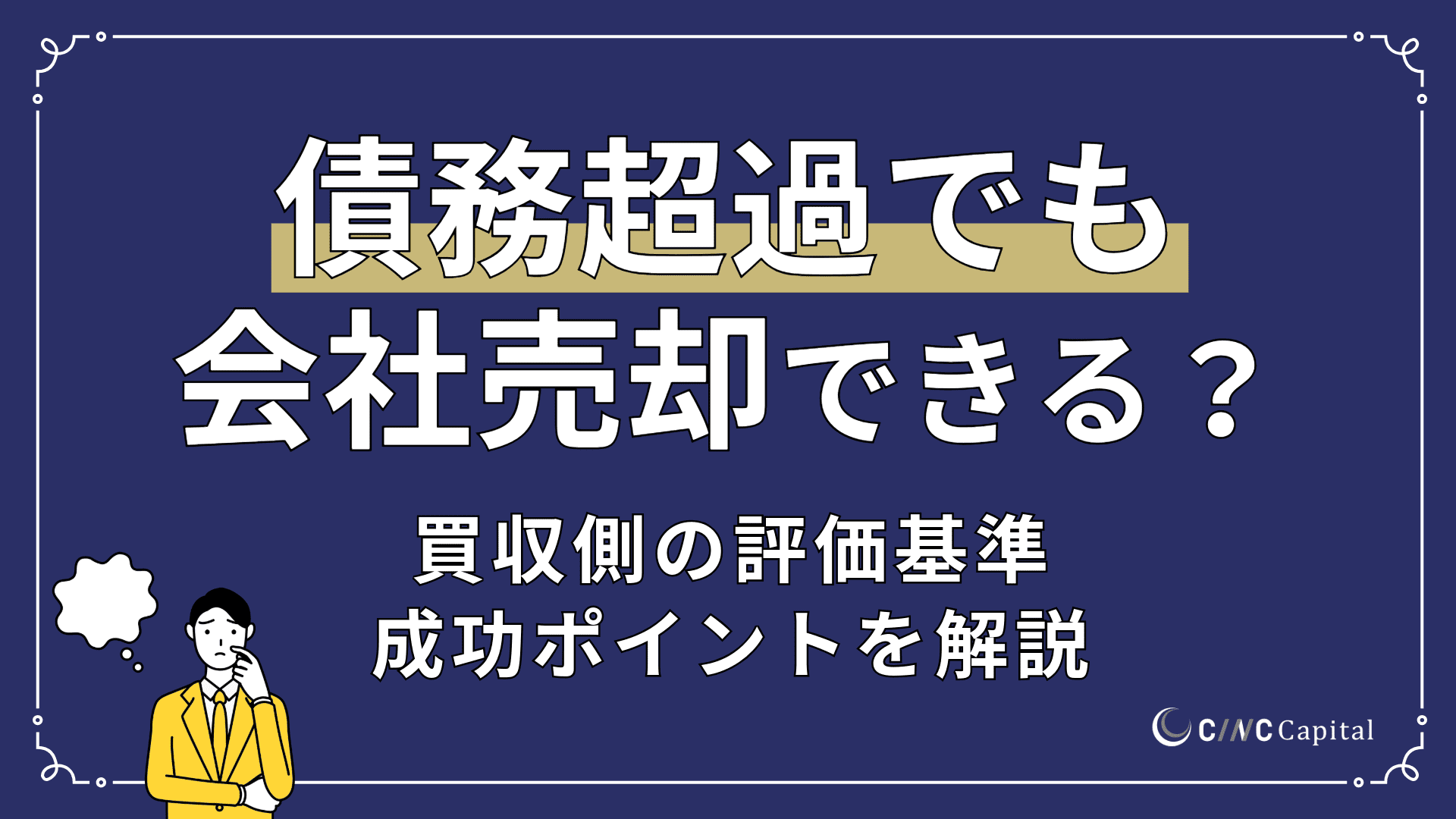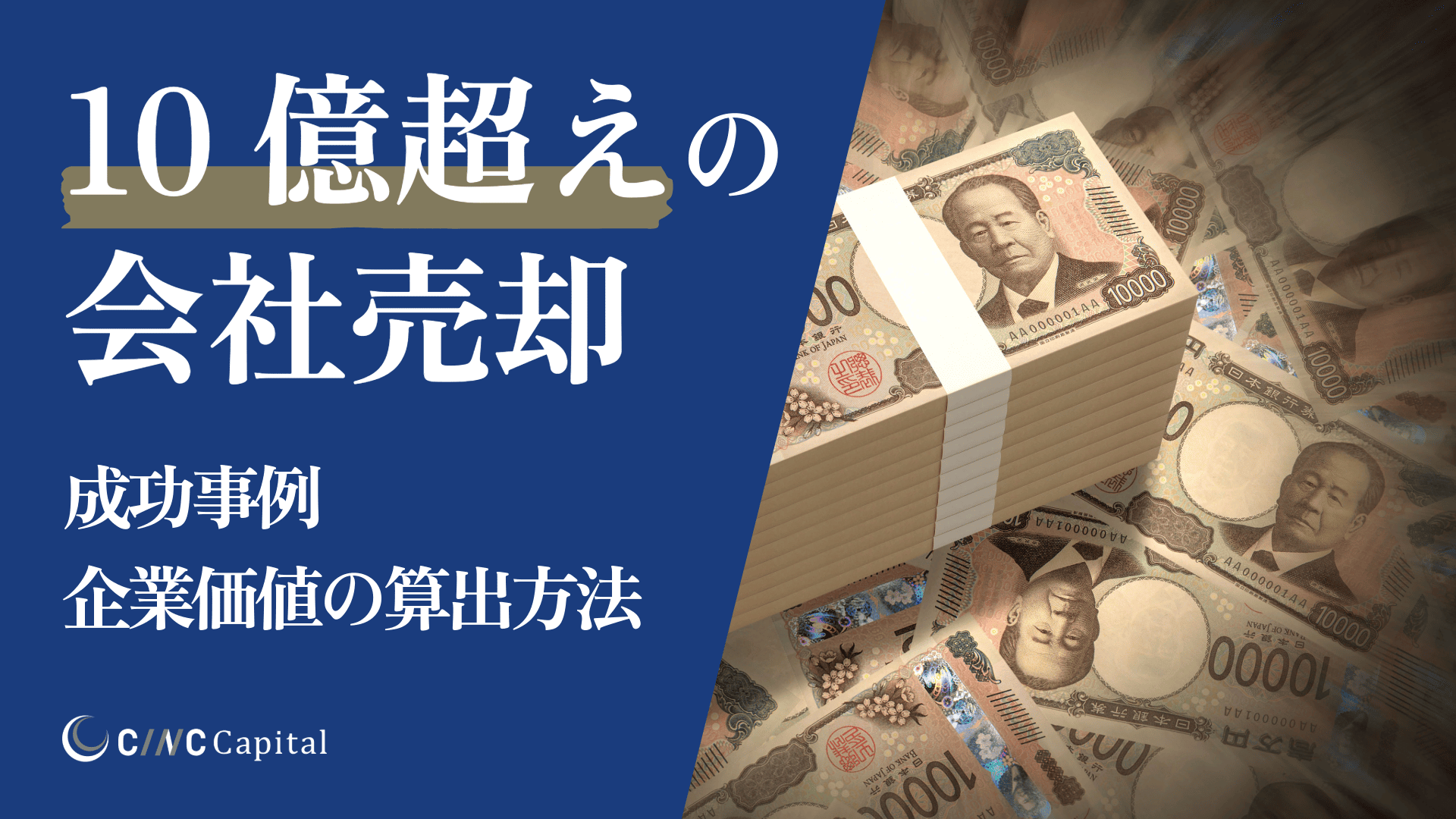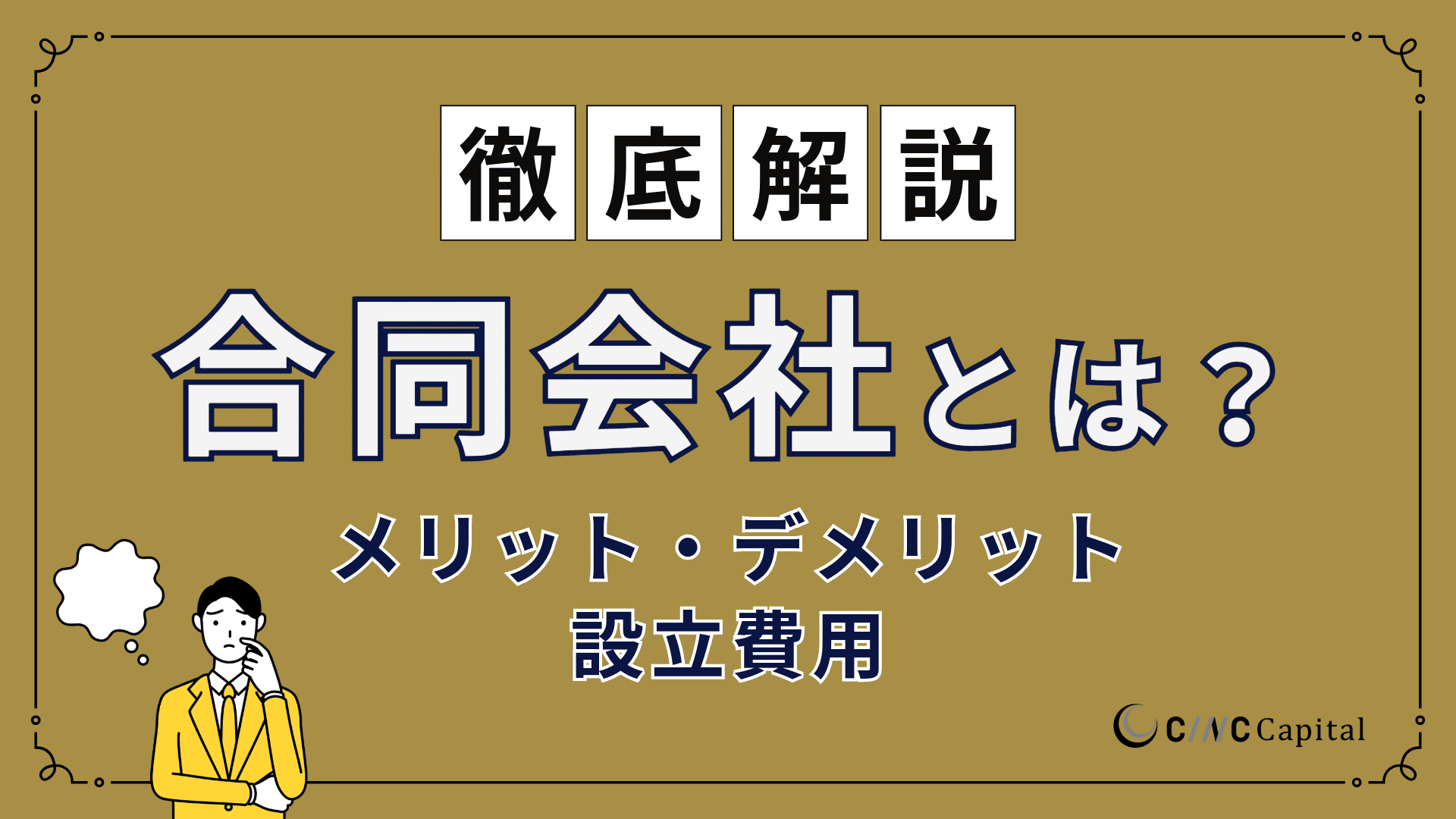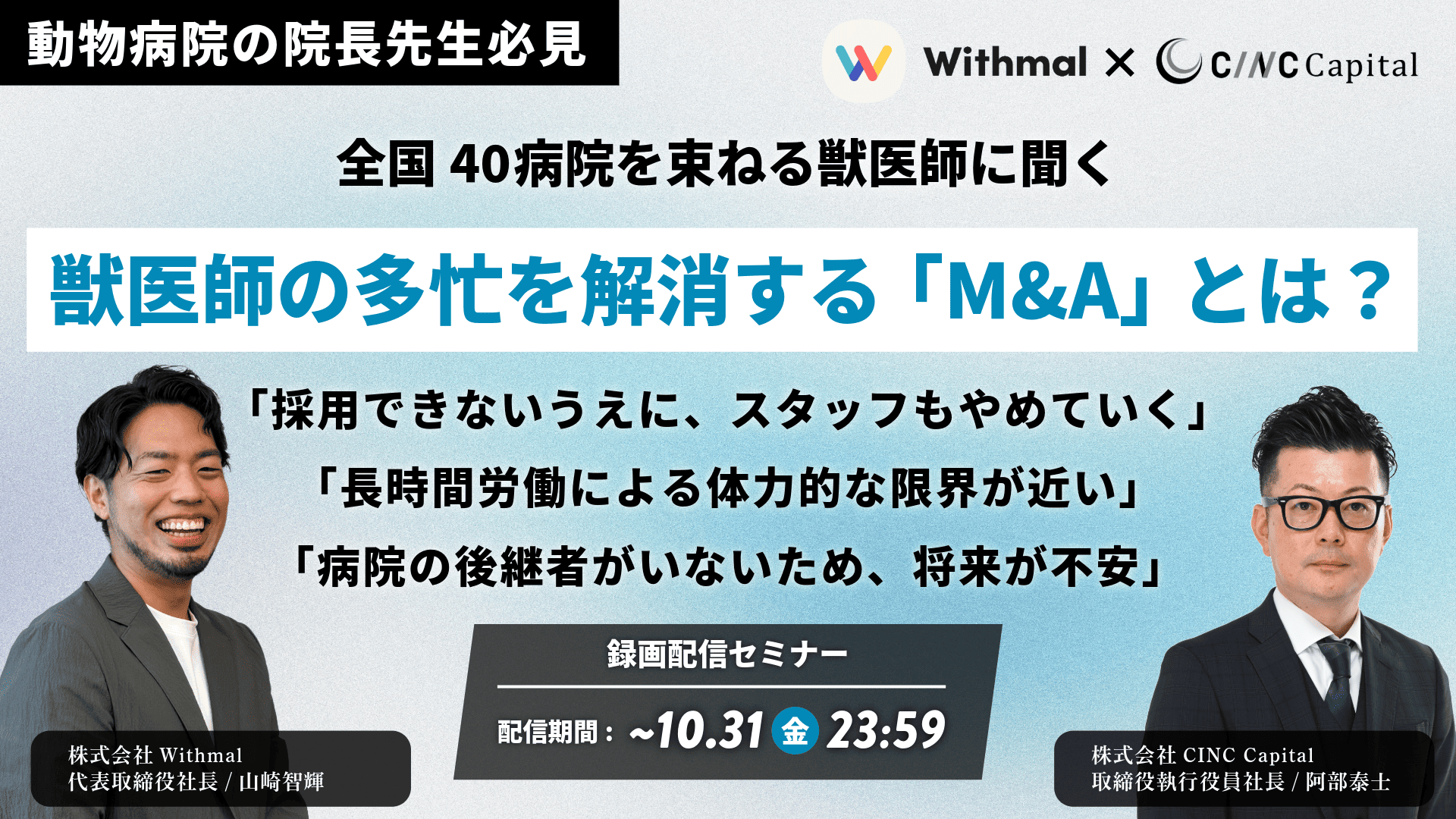CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
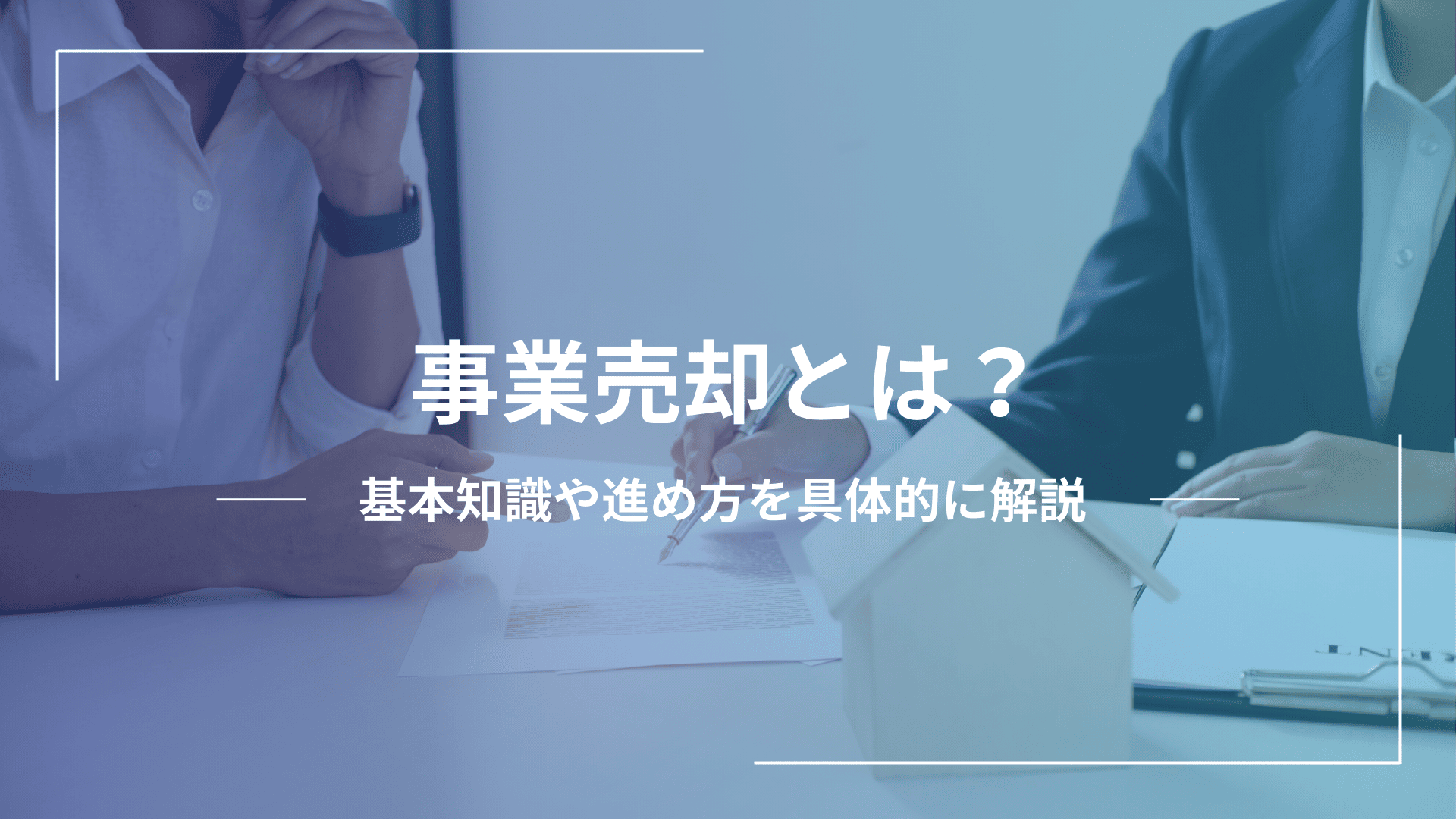
売却 / 事業売却
- 最終更新日2025.07.10
事業売却とは?目的やメリットデメリット、手続きの流れ、税金、事業価値の算出方法まで徹底解説
事業売却は、経営資源の集中や後継者問題の解決など、さまざまな目的で活用される重要な経営戦略の一つです。
この記事では、事業売却の基本から目的、メリット・デメリット、手続きの流れ、税務や事業価値の評価まで、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
事業売却とは?
事業売却は、会社が保有する特定の事業や部門を第三者に譲り渡す取引のことを指します。
株式譲渡が会社そのものを売るのに対し、事業売却はあくまで事業単位で行うため、売却範囲を柔軟に設定できるのが特徴です。
例えば、製造業が複数の工場を持つ場合、採算の取れない工場のみを切り離して売却することが可能です。
売却対象には設備、在庫、営業権、顧客との取引関係など多様な資産や権利が含まれます。
譲渡契約で具体的に対象範囲を定めるため、売り手と買い手で詳細に確認し合意する必要があります。
特に債務や雇用契約の引継ぎ、許認可の再取得など、実務面での調整が多い点は事業売却特有の難しさです。
一方で、資産の一部だけを手放すことで経営の柔軟性を保ちながら資金調達や経営資源の集中を図れるのは大きなメリットです。
事業売却は単なる撤退ではなく、将来に向けた戦略的な選択肢として多くの企業に活用されています。
事業売却を行う目的や理由
事業売却が行われる背景には、経営戦略や組織の事情などさまざまな理由があります。
ここでは、主な目的や考え方を具体例を交えて解説します。
経営資源を集中するため
事業売却には多様な目的や背景がありますが、最も多いのは、経営資源の集中です。
収益性が低い部門や成長が期待できない事業を手放し、その分の人材や資金を主力事業に振り向けることで、会社全体の競争力を高めることができます。
例えば、大手メーカーが地方工場を売却し、研究開発に経営資源を集中する事例が増えています。
後継者問題を解決するため
後継者問題を解決するために事業売却を選ぶ企業も少なくありません。
中小企業では経営者の高齢化が進む一方、親族や社内に後継者が見つからないことも多くあります。
この場合、第三者に事業を譲り渡すことで、従業員の雇用や取引先との関係を守りながら事業を継続できます。
業界再編や競争環境への対応
業界再編や競争環境の変化も、事業売却を検討する理由のひとつです。
単独では事業を維持するのが難しい場合、より規模の大きい企業に売却することで、顧客や従業員を守る選択が可能です。
資金調達や財務改善のため
さらに、資金調達を目的として、重要度の低い事業を売却するケースもあります。
売却益を成長投資や借入金返済に活用することで財務体質の改善を図れるため、大企業でも活発に行われています。
このように、事業売却は撤退だけを意味するものではなく、経営戦略の一環として前向きに活用される重要な手段です。
事業売却と類似スキームとの違い
事業売却は他のスキームと混同されやすい取引です。
ここではM&Aや事業譲渡、会社売却との違いを整理し、それぞれの特徴を解説します。
|
|
事業売却 |
M&A |
事業譲渡 |
会社売却 |
|
意味 |
会社の一部事業だけを第三者に売る |
企業の合併・買収全体を指す総称 |
事業売却とほぼ同じ |
株式を譲渡し会社全体を売る |
|
譲渡範囲 |
特定の事業のみ |
事業・会社など多様 |
特定の事業のみ |
会社の全資産・負債 |
|
法人格 |
継続する |
ケースにより異なる |
継続する |
買い手に経営権移転 |
|
契約 |
事業譲渡契約が必要 |
手法ごとに契約形態が異なる |
事業譲渡契約が必要 |
株式譲渡契約 |
事業売却とM&Aの違い
事業売却はM&A(企業の合併・買収)の一形態ですが、M&Aはより広い概念を指します。
M&Aには事業売却だけでなく、株式譲渡や会社分割、合併などさまざまな手法が含まれます。
例えば、M&Aで株式譲渡を選ぶと、会社そのものの経営権が移りますが、事業売却では会社は存続したまま一部の事業だけを切り離します。
つまり、M&Aは「企業の所有権や事業を移す行為の総称」であり、事業売却はその中でも特定の事業資産を譲渡する手段を指します。
目的や規模に応じてどの手法を採るかを検討することが重要です。
事業売却と事業譲渡の違い
事業売却と事業譲渡は、どちらも企業が自社の事業の一部または全部を第三者に引き渡す行為を指しますが、実務上では意味や手続きが異なります。
まず、事業売却は「事業そのものを財産や契約、営業権などと一緒に譲渡する行為」で、譲渡対象が明確に特定されるのが特徴です。
これに対して、事業譲渡は「会社の事業を包括的に他社へ移すこと」で、取引先との契約や従業員の雇用関係なども個別に承継の手続きが必要です。
例えば、事業売却の場合、特定の店舗やブランドのみを切り離して売るケースが多く、比較的スムーズに契約が進む傾向があります。
一方、事業譲渡は契約の承継や許認可の変更手続きが煩雑になりやすいのが実情です。
いずれも会社の成長戦略や事業再編を目的に行われますが、目的や引き継ぐ範囲によって最適な方法は変わるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。
事業売却と会社売却の違い
事業売却と会社売却は対象範囲が大きく異なります。
事業売却は会社が営む特定の事業のみを譲渡するのに対し、会社売却(株式譲渡)は会社そのものの経営権や資産・負債すべてを包括的に移す取引です。
例えば、会社売却では法人格や契約もすべて引き継がれるため、許認可や取引先との契約は原則そのまま有効です。
一方、事業売却では許認可や契約を個別に移管し直す必要があります。
このため、会社売却のほうが手続きは比較的シンプルですが、買い手が全体のリスクも引き受ける点が特徴です。
目的や事情に応じてどちらを選ぶか慎重に検討する必要があります。
事業売却のメリット
事業売却には、買い手・売り手双方にさまざまな利点があります。
ここでは主なメリットを整理し、それぞれの立場から具体的に解説します。
買い手側のメリット
買い手にとって事業売却は、短期間で新規事業を取得できる貴重な機会です。
既存のノウハウや顧客基盤を引き継ぐことで、ゼロから立ち上げるよりもリスクを抑えられます。
例えば、地域に根ざしたサービスを運営する会社を買収すれば、すでに確立されたブランドや取引先を活用できます。
また、競合他社の事業を取り込むことで市場シェアを拡大し、成長を加速する戦略も実現可能です。
こうした利点は、自社だけでは得られない経営資源を一括で獲得できる点にあります。
戦略的なM&Aの手段として活用する価値は大きいといえるでしょう。
売り手側のメリット
売り手にとっての最大のメリットは、不要となった事業を適正価格で現金化し、経営資源を重点分野に再配分できることです。
不採算事業を手放すことで経営効率が改善し、残った事業に注力しやすくなります。
例えば、中堅メーカーが非主力事業を売却し、主力の製品開発に投資を集中するケースは多いです。
また、後継者不在の企業では事業承継の手段としても有効です。
従業員の雇用や顧客との関係を維持したまま、経営を円滑に引き継げる点は大きな利点です。
このように、事業売却は財務・組織面の課題を同時に解決する手段になります。
事業売却のデメリット
事業売却には一定のデメリットやリスクも存在します。
事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵です。
買い手側のデメリット
買い手にとっての大きなリスクは、許認可の再取得や契約の個別移管など手続きが煩雑になることです。
また、事業譲渡により雇用契約や取引契約が一旦終了するため、主要な従業員や取引先が離脱するおそれがあります。
例えば、引き継いだ後に主要顧客との契約更新ができず、収益計画が崩れるケースもあります。
売り手側のデメリット
売り手側の最大のデメリットは、譲渡対価に消費税が課税されることです。
例えば、1億円の事業譲渡では1,000万円の消費税が加算され、買い手の実質負担が増加するため、結果的に売り手の手取り額に影響します。
また、個別の資産移転や従業員の転籍手続きなど、株式譲渡と比べて手続きが煩雑になる点も重要な課題です。
また、事業情報が外部に漏えいするおそれや、従業員・取引先に不安を与える点もデメリットです。
交渉の過程で詳細な情報を共有するため、秘密保持契約を結んでも完全なリスク回避は難しい場合があります。
さらに、交渉や条件調整に時間や労力を要し、経営資源を消耗することもあります。リスクを把握し、計画的に進めることが重要です。
事業売却の主なスキーム
事業売却は大きく分けて「事業譲渡」と「株式譲渡」の2つの方法があります。
それぞれの仕組みや特徴を理解することが重要です。
事業譲渡
事業譲渡は、会社が営む特定の事業や資産、負債、営業権などを個別に第三者へ譲り渡す方法です。
売り手は対象事業だけを切り離して移転できるため、不要な部門の整理や経営資源の集中を図る際に有効です。
例えば、製造業が不採算の工場部門を他社に譲渡し、収益性の高い事業に経営資源を集中するケースがあります。
事業譲渡では、許認可や契約を一つずつ移管する必要があるため手続きは煩雑になりがちです。
また、従業員の雇用契約も一度終了し、買い手との間で再締結する必要があります。柔軟性が高い反面、準備と調整に時間がかかる点を理解しておくことが大切です。
株式譲渡
株式譲渡は、会社の株主が保有する株式を買い手に譲渡することで、会社そのものの経営権を移転する方法です。
この方法では会社の法人格が存続し、事業、従業員、契約関係も原則としてそのまま引き継がれます。
例えば、IT企業が成長戦略の一環として別の会社の全株式を取得し、グループ会社化する事例が増えています。
株式譲渡は許認可や契約の再取得が不要な場合が多く、事業譲渡よりも手続きが簡便です。
ただし、買い手は会社全体の資産や負債、潜在的リスクを引き受けることになるため、事前に十分な調査が不可欠です。
全体を包括的に引き継ぎたい場合に適した手法といえます。
事業売却をすると社員や従業員はどうなる?
事業売却では、社員や従業員の雇用がどうなるかが大きな関心事です。
ここでは基本的な仕組みや実務上の流れを整理して解説します。
事業売却を行う場合、対象事業に従事していた従業員の雇用契約は、法律上は一度終了するのが原則です。
その後、買い手企業と新たに雇用契約を締結する必要があります。
実務では、事業継続のため多くの従業員が移籍しますが、形式上は退職扱いとなるため、さまざまな調整が必要です。
事業売却に伴う従業員への影響は、主に以下の通りです。
- 雇用契約の終了と再契約:事業譲渡では、従業員との雇用契約が一旦終了し、買い手と改めて契約を結ぶ必要があります。移籍が前提でも、この手続きが発生する点を理解しておくことが重要です。
- 退職金や有給休暇の精算:雇用が終了するため、退職金の支払いや有給残の清算が必要となる場合があります。どちらが負担するかは売却契約で定めます。
- 従業員の合意と説明責任:従業員の同意を得るプロセスが不可欠です。条件変更や将来の処遇について不安を感じやすいため、経営者は丁寧な説明や面談を行い理解を促します。
- 労働条件の調整:給与・勤務場所・福利厚生など、買い手企業での労働条件が変わる場合は、就業規則や労働条件通知書を整備して共有することが求められます。
例えば、あるIT企業が一部の事業を売却した際、買い手企業は全社員を新たに雇用する意向を示し、同等の条件で契約を再締結しました。
このように、実務では雇用が継続されるケースが多い一方、従業員にとっては環境が変わる不安がつきものです。
どのスキームを選ぶかによって従業員への影響が大きく異なるため、売り手・買い手が事前に従業員の処遇について十分に協議し、適切な移行計画を策定することが重要です。
売り手・買い手が協力し、適切な情報共有と準備を行うことで、従業員の不安を減らし円滑な引き継ぎが可能になります。
事業売却は経営だけでなく、従業員の人生にも関わる大きな決断です。
専門家の助言を得ながら進めることが、安心できる移行を実現する鍵となります。
事業売却の手続きの流れ
事業売却は複数のステップを経て進めます。
ここでは検討から契約締結、引き渡しまでの流れを段階ごとに解説します。
- 売却の検討・決定
- 売却内容の整理
- 売却先の選定・交渉
- 基本合意の締結
- デューデリジェンス
- 承認手続き
- 契約締結と移転
- 関係者への通知や届け出
1. 売却の検討・決定
事業売却の第一歩は、そもそも売却を行うべきかを検討し、方針を決定することです。
目的やタイミング、対象事業の選定を社内で十分に議論し、経営戦略との整合性を確認します。
例えば、資金調達を急ぐケースと、事業の将来性を慎重に見極めたいケースでは進め方が異なります。
この段階で目的が不明確だと、後の手続きで軸がぶれるおそれがあります。
将来の成長や従業員の雇用への影響を考慮し、社内の合意形成を図ることが重要です。
2. 売却内容の整理
売却する範囲や条件を明確にする作業は、スムーズな交渉のために欠かせません。
対象となる資産・負債・契約・人材などを一覧化し、どこまで移転するかを整理します。
例えば、設備のみを売るのか、営業権やノウハウも含めるのかで譲渡価格や手続きは大きく変わります。
この整理が不十分だと、契約書作成やデューデリジェンスで齟齬が生じるリスクがあります。
弁護士や会計士の支援を得ながら、対象を正確に把握することが大切です。
3. 売却先の選定・交渉
売却先を選定する段階では、複数の候補をリストアップし、条件交渉を進めます。
信頼性や資金力、事業の親和性を確認し、将来的にトラブルが起きない相手を選ぶことが重要です。
例えば、業界再編を目的とする売却では、同業他社が有力な候補になります。
交渉では価格だけでなく、従業員の処遇や取引継続の条件も詰める必要があります。
早い段階から情報を整理し、候補者と十分に意見交換することが成功のポイントです。
4. 基本合意の締結
交渉が進んだら、主要事項を整理し基本合意書を締結します。
基本合意書は、譲渡価格の目安や対象範囲、スケジュール、独占交渉権などを記載し、後の詳細契約に向けた土台を作ります。
例えば、買い手がデューデリジェンスを行う前に独占交渉権を設定することで、他社との競合を避けることができます。
基本合意書は法的拘束力の範囲が限定される場合もあるため、弁護士の確認を受けて締結することが重要です。
5. デューデリジェンス
デューデリジェンスでは、買い手が財務・法務・労務・人事などの詳細調査を行います。
売却対象のリスクを把握し、最終契約に反映させる重要な工程です。
例えば、未払債務や契約上の問題が見つかれば、条件変更や価格調整が必要になります。
調査には一定の期間がかかり、売り手も資料準備や質問対応を求められます。
透明性を高めるため、誠実に情報を開示し、調査をサポートする姿勢が信頼構築につながります。
6. 承認手続き
最終契約を進める前に、社内で必要な承認を得る必要があります。
取締役会での決議、さらに重要な事業譲渡にあたる場合は株主総会の特別決議が求められます。
例えば、会社法上、譲渡する資産が総資産の一定割合を超える場合は株主総会決議が義務づけられます。
承認を得ずに契約を進めると無効や損害賠償リスクが生じるおそれがあります。
法的要件を確認し、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。
また、上場会社の場合、譲渡対象が会社法上の「重要な財産処分」に該当したり、譲渡後にTOB(公開買付け)規制や適時開示規則が作動するケースがあります。
そのため、金融商品取引法および取引所規則に基づく情報開示やスケジュール調整が必須です。
証券会社・弁護士と連携しつつ、取締役会資料・適時開示書類の準備を並行して進めてください。
7. 契約締結と移転
承認が完了したら最終契約書を取り交わし、事業の引き渡しを行います。
契約書には譲渡対象の詳細、価格、支払方法、リスク分担、表明保証など多岐にわたる内容を明記します。
例えば、引き継ぎ期間のサポート義務を明記することで、移行期間中のトラブルを防止できます。
契約締結後、資産や権利義務の移転を実行し、買い手へ正式に引き渡します。この段階をもって取引が完了します。
8. 関係者への通知や届け出
事業売却が完了したら、株主や従業員、取引先、官公庁への通知や届け出を行います。
従業員には新しい雇用契約や勤務条件を説明し、取引先には契約変更や口座変更などの手続きを案内します。
例えば、許認可が必要な事業では行政への変更届出が必要です。
周知や手続きを怠ると混乱や信用低下を招くおそれがあります。
関係者に配慮し、計画的に進めることが重要です。
事業価値の算定方法
事業売却では、適正な価格を決めるために客観的な評価が欠かせません。
ここでは代表的な4つの事業価値の算定方法を解説します。
マルチプル法
マルチプル法は、類似企業の取引事例や市場データを基に、収益指標に倍率(マルチプル)を掛けて企業価値を算出する手法です。
例えば、EBITDA(税引前利益+減価償却費)に業界平均のマルチプルを乗じて評価額を算定します。
例えば、EBITDAが1億円、同業のマルチプルが5倍なら企業価値は5億円となります。
この方法は市場性を反映しやすく、M&Aで広く用いられています。
ただし、収益の安定性や事業規模、成長性など個別要素に注意し、単純比較に頼らないことが重要です。
複数の指標を組み合わせることでより精度の高い評価が可能です。
時価純資産法
時価純資産法は、資産と負債を時価評価し、その差額を企業価値とする方法です。
特に資産の割合が大きい会社や清算価値を重視する場面で用いられます。
例えば、不動産や機械設備を多く保有する企業の場合、帳簿価額ではなく現時点での市場価値に置き換えて純資産を算出します。
この方法は財務内容が明確になりやすい反面、収益性や将来性を十分に評価できない点がデメリットです。
資産価値を重視する場合は有効ですが、事業の収益力を反映させたいときは他の手法と併用することが推奨されます。
年買法(年倍法)
年買法は、将来の収益を一定年数分まとめて評価するシンプルな方法です。
過去実績を基に標準利益を算出し、それに年数倍率を掛けて企業価値を計算します。
例えば、標準利益が2,000万円で年数倍率が3なら評価額は6,000万円です。主に中小企業の取引で用いられ、簡便性が高いのが特徴です。
ただし、収益が不安定な場合や将来の成長性を織り込みたい場合には適さないことがあります。
算定根拠や年数倍率の設定が重要で、業種や市場状況に応じて慎重に決める必要があります。
DCF法
DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)は、将来得られるキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法です。
最も理論的で精緻な算定が可能ですが、前提となる収益予測や割引率の設定が難しい面もあります。
例えば、5年間の予想キャッシュフローと最終年度の残余価値を計算し、一定の割引率で現在価値に換算します。
将来性を重視するスタートアップの評価にも適しており、投資家や専門家が用いることが多いです。
ただし、前提が不正確だと大きく評価がぶれるおそれがあるため、慎重なシナリオ設定が必要です。
事業価値が高い事業の特徴
事業売却で高い評価を受ける事業には共通した特徴があります。
ここでは、買い手から評価されやすいポイントを解説します。
利益率が高い
利益率が高い事業は、安定した収益を生む力があるため、評価が上がりやすい傾向にあります。
利益率が高いほど、投資回収までの期間が短くなり、買い手にとって魅力的です。
例えば、同じ売上規模でも利益率が5%の事業と20%の事業では、後者のほうが評価額は大きくなるのが一般的です。
さらに、高利益率の事業は価格競争に巻き込まれにくく、市場変化に強いと判断されます。
売却を検討する場合は、コスト構造を見直して収益性を高める取り組みが重要です。
事業の強みを明確にし、利益率を維持できる仕組みを整えることが高評価につながります。
独自性が高い
他社にはない独自性を持つ事業は、差別化ができているため価値が高く評価されます。
独自の技術やブランド、特許、ノウハウなどは競争優位性を築く大きな要素です。
例えば、特許を活用した製品を持つメーカーや、地域に強いブランドを持つサービス業は、買い手が取得後に他社と差別化しやすく、事業成長が期待できます。
独自性が強い事業は価格交渉でも優位に立てるため、売却前に強みを整理し、買い手に明確に伝える準備が重要です。
競争優位を証明する具体的な資料や実績を用意しておくことが信頼を高めます。
財務状況が整理されている
財務状況が整理されている事業は、リスクが少なく透明性が高いため、買い手に安心感を与えます。
帳簿や契約関係が明確に管理されていることは、デューデリジェンスの負担を減らし、スムーズな取引に直結します。
例えば、月次決算が整備されている会社や、債務や未収入金の管理が行き届いている事業は、買い手が引き継ぎ後に問題を抱えにくいと評価されます。
反対に、帳簿が煩雑だったり契約書が不備だったりすると、評価が下がるおそれがあります。
売却を検討する際は、早い段階で専門家に相談し、財務体制を整備しておくことが重要です。
事業売却にかかる税金
事業売却では、買い手・売り手の双方に税金が発生します。
ここでは、主な税負担の種類と注意点を解説します。
買い手側
買い手は取得する資産や不動産に応じて、複数の税金を支払う必要があります。
主な税金は次の通りです。
- 消費税:事業譲渡で取得する有形固定資産や在庫には消費税が課税されます。例えば、1億円分の資産を取得する場合、10%の消費税が発生し、支払額は1億1,000万円になります。
- 不動産取得税:不動産が含まれる場合、取得税が課税されます。取得価額に応じて計算されるため、資産規模が大きいほど負担が増えます。
- 登録免許税:不動産や権利の移転登記を行う際に課税されます。税率は不動産の評価額などで変わるため注意が必要です。
これらの税金は取引完了後すぐに発生するため、資金計画に織り込み、専門家と相談しながら準備を進めることが重要です。
売り手側
売り手には譲渡益に対する法人税などの税負担が発生します。
代表的な税金は以下の通りです。
- 法人税・地方税:売却によって生じた譲渡益が課税対象になります。例えば、帳簿価額5,000万円の事業を1億円で売却した場合、5,000万円が課税対象です。
- 消費税:課税事業者の場合、譲渡代金に対して消費税を申告・納付する必要があります。
- 不動産譲渡所得税・登録免許税:不動産が含まれる場合、登記に伴う登録免許税が発生します。なお、法人が保有する不動産を譲渡する場合、譲渡益は法人税等の課税所得に算入され、個人のような分離課税の不動産譲渡所得税は適用されません。
こうした税金を見落とすと手取りが減少するおそれがあります。
売却前に税理士と相談し、納税資金を確保しておくことが大切です。
事業売却における会計処理
【買い手側】事業買収に関する会計処理
続いて、譲受側の会計処理を見ていきましょう。
事業譲受の際、譲り受けされる資産は時価で受け入れることになります。
ただし、事業売却価格は売主買主との契約で定められますので、時価譲渡価格の合計と事業売却価格の合計は一致しないことが、しばしば見受けられます。
この差額は、その会社の持つ営業権であると考えられますので、「のれん」として計上します。のれん代により売却価格が時価総額を下回る「負ののれん」が発生する場合もありますが、そのまま処理をすることになります。
譲渡資産・負債は以下の通りです。(譲渡価格:500,000)
【仕訳例】
|
|
簿価 |
時価 |
差額 |
|
棚卸資産 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
土地 |
200,000 |
300,000 |
100,000 |
|
建物 |
50,000 |
30,000 |
-20,000 |
|
機械装置 |
100,000 |
90,000 |
-10,000 |
|
特許権 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
商標権 |
1,000 |
500 |
-500 |
|
(合計) |
363,000 |
432,500 |
69,500 |
棚卸資産 10,000 / 現金預金 500,000
土地 300,000
建物 30,000
機械装置 90,000
特許権 2,000
商標権 500
のれん 67,500
【売り手側】事業売却に関する会計処理
事業売却では、内容に応じた会計処理が求められます。まずは、譲渡側の会計処理から見ていきましょう。
事業譲渡の際は、譲渡される資産を簿価で、自社の貸借対照表から消去します。その資産を譲受側に移転する仕訳は、時価で売却価格を決めなければなりません。これは税務上も要請されており、この差額は「事業譲渡益(損)」と認識されます。
譲渡資産・負債は以下の通りです。(譲渡価格:500,000)
【仕訳例】
|
|
簿価 |
時価 |
差額 |
|
棚卸資産 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
土地 |
200,000 |
300,000 |
100,000 |
|
建物 |
50,000 |
30,000 |
-20,000 |
|
機械装置 |
100,000 |
90,000 |
-10,000 |
|
特許権 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
商標権 |
1,000 |
500 |
-500 |
|
(合計) |
363,000 |
432,500 |
69,500 |
現金預金 500,000 / 棚卸資産 10,000
土地 200,000
建物 50,000
機械装置 100,000
特許権 2,000
商標権 1,000
事業譲渡益 137,000
事業譲渡契約書の必要項目
事業譲渡契約書に必要な項目は、以下の通りです。
- 事業譲渡の目的
- 事業譲渡の対象
- 支払条件・支払方法
- 譲渡金額
- 譲渡資産の範囲
- 善管注意義務
- 従業員の引き継ぎ
- クロージング条件
- 表明保証
- 競業避止義務
- 租税公課の精算
- 損害賠償
- 契約解除
- その他一般条項(秘密保持、譲渡期日、合意管轄など)
事業譲渡契約書の雛形
事業場地契約書に雛形につきましては、経済産業省が公開している資料があります。こちらに準拠いただいて、作成してみてください。
【参考】(参考資料 7)各種契約書等サンプル 【本文 35ページ以下】
事業売却の成功事例
事業売却の成功事例を確認し、自社で事業売却を行う際の参考にしてみてください。
買収企業を子会社化し、グループ経営で収益を拡大
- 売却企業の概要:印刷会社 従業員50人未満 印刷事業を営む。 特に衛生管理を徹底しており、食品パッケージ・医薬品関連の印刷に強み
- 買収企業の概要:印刷会社 従業員300人未満 印刷事業、メディア事業、デジタルソリューション事業
- 事業買収の背景・目的:譲渡側の救済を目的ではあるが、将来的にはグループ経営を指向
- 事業買収が成立に至った経緯:M&Aによる売上・コストシナジーの創出や、 両者製品/サービスのクロスセルによる新たな価値提供を期待
中型レストラン経営へ、新たな業務展開
- 売却企業の概要:飲食店経営
- 買収企業の概要:アパレル企画・小売業 従業員数10人未満 靴 / アパレル等の輸出入および企画 ・ 小売
- 事業買収の背景・目的:双方のM&A目的が一致したことにより既存事業のシナジーを狙う
- 事業買収が成立に至った経緯:飲食店運営にかかる人員の確保とコストシナジーの実効性検証に向けた経営管理方法の見直し
生産力と開発力を統合し、両者が一致団結できるWin-Winの協力体制の構築
- 売却企業の概要:電気電子に関わる設計・製造業 従業員数50人未満 プリント配線基板の設計、 製造を中心に、 実装までサポート
- 買収企業の概要:製造業 従業員数50人未満 プリント配線基板の設計、製造、実装・組立および銘板の製造
- 事業買収の背景・目的:譲受側は、数社の取引先に依存する請負体質であり、経営構造を変革できない点に課題を感じていた。そこで、自社の強みである生産力と、譲渡側の強みである開発力を掛け合わせることで、設計・製造・販売の総合力を高め、顧客に提供する製品品質および付加価値の向上が実現できると見込み、譲渡側を譲り受けることとなった
- 事業買収が成立に至った経緯:統合シナジーの発揮に向けて、社長が議論のベースで準備し、その後、現場担当者同士でありたい事業ビジョンを協議した結果、意見が一致。事業買収へとつながった
【引用】経済産業省「(参考資料4)中小 M&A の事例 【本文24ページ】」
事業売却を検討するときの注意点
事業売却を成功させるためには、事前に注意すべきポイントを押さえることが重要です。
ここでは検討段階で特に大切な4つの視点を解説します。
売却の目的をはっきりさせる
事業売却を始める際は、なぜ売却するのかを明確にすることが重要です。
目的が曖昧なまま進めると、条件設定や交渉で軸がぶれてしまうおそれがあります。
例えば、資金調達を最優先にするのか、従業員の雇用維持を重視するのかで進め方が変わります。
目的がはっきりすれば、買い手候補の選定やスケジュール調整もスムーズです。
売却理由を社内で共有し、目標を具体的にすることで、意思決定の質が高まり、トラブルを防ぎやすくなります。
事業価値を客観的に確認する
事業の価値を正確に把握せずに売却を進めると、適正価格で取引できないリスクが高まります。
例えば、収益力や資産の評価が甘いまま相場より低い金額で売却してしまう事例も珍しくありません。
客観的な評価を行うためには、マルチプル法やDCF法など複数の算定手法を活用することが有効です。
専門家に依頼して査定書を作成することで、根拠のある価格を提示できます。
適正価値を把握することは交渉の強みになるため、早い段階で準備することが大切です。
情報漏えいを防ぐ準備を行う
事業売却では、財務情報や顧客リストなど重要な機密情報を共有する必要があります。
適切な管理を怠ると、情報漏えいや信用低下のおそれがあります。
例えば、交渉段階で情報が取引先に漏れ、事業に悪影響が出るケースもあります。
こうしたリスクを避けるため、秘密保持契約(NDA)を必ず締結し、情報提供の範囲や利用目的を明確に定めましょう。
また、社内の情報管理体制を整備し、関係者への教育も徹底することが重要です。
準備を怠らないことが信頼構築につながります。
専門家へ早めに相談する
事業売却は法務、税務、会計が複雑に絡む取引です。自己判断だけで進めると、後から問題が発覚しやすくなります。
例えば、契約書の不備や税務処理の誤りによって、想定外の負担が発生するケースがあります。
弁護士や税理士、M&Aアドバイザーなど専門家に早期に相談することで、リスクを低減し、取引を円滑に進めることが可能です。
特に初めての売却では、専門家の支援が大きな安心材料になります。
時間に余裕を持ち、準備段階から助言を受けることをおすすめします。
事業売却についてよくある質問
事業売却を検討する際、手続きや売却後の働き方などについて多くの疑問が寄せられます。
ここでは代表的な質問にお答えします。
事業売却にかかる期間はどのくらい?
事業売却の期間はケースによって異なりますが、平均的には6か月から1年程度かかることが多いです。
売却の検討や条件整理、買い手候補の選定、交渉、デューデリジェンス、契約締結といった各ステップに時間が必要です。
例えば、従業員や取引先の調整が多い場合や、買い手候補が複数いる場合はさらに期間が延びます。
一方、急ぎの売却で条件がシンプルであれば数か月で完了するケースもあります。
余裕を持って準備を進めることがトラブルを防ぐポイントです。
具体的なスケジュールは専門家と相談しながら計画しましょう。
事業売却後に元オーナーが事業に関わることはできる?
事業売却後も元オーナーが一定期間事業に関わることは可能です。
実際、買い手企業がスムーズに事業を引き継ぐため、一定期間はオーナーに経営支援や顧客引き継ぎを依頼するケースが多く見られます。
例えば、売却後1年間は顧問として残り、運営のサポートを行う契約を結ぶ方法があります。
ただし、契約で役割や期間、報酬を明確に定める必要があります。
また、競業避止義務を設定される場合もあり、同じ事業を新たに立ち上げることは制限されるケースがあります。
事業への関わり方は交渉次第で柔軟に調整できますので、売却前に買い手としっかり相談することが大切です。
まとめ|事業売却について正しく理解し適切な選択を
事業売却は、経営資源の集中や後継者問題の解消、資金調達など多様な目的で活用される重要な経営手段です。
売却には事業譲渡や株式譲渡など複数の方法があり、それぞれ手続きや影響が異なります。
適正な事業価値を算定し、税務や会計の準備を整えた上で進めることが、安心して取引を進めるための基本です。
また、従業員や取引先への影響を最小限に抑えるため、丁寧な説明や誠実な対応が欠かせません。
CINC Capitalでは、豊富なM&A支援の実績をもとに、事業売却に関する戦略立案から売却先の選定、条件交渉、手続き完了まで一貫してサポートしています。
初めて事業売却を検討される方も、専門家が丁寧に対応し、適切な方法をご提案します。
将来の安定と成長を見据えた事業売却をお考えの際は、ぜひCINC Capitalへお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

税理士/米国税理士
竹中 啓倫
竹中啓倫税理士事務所代表。M&Aなどの事業再編を得意とし、財務分析だけでなく、資金調達やリスクマネジメントのコンサルなども担当している。また、セミナーや研修会講師としても活動。税務系の資格のほか、認定心理士・宅地建物取引士・1級FP技能士・CFPなどの資格も保有している。