CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
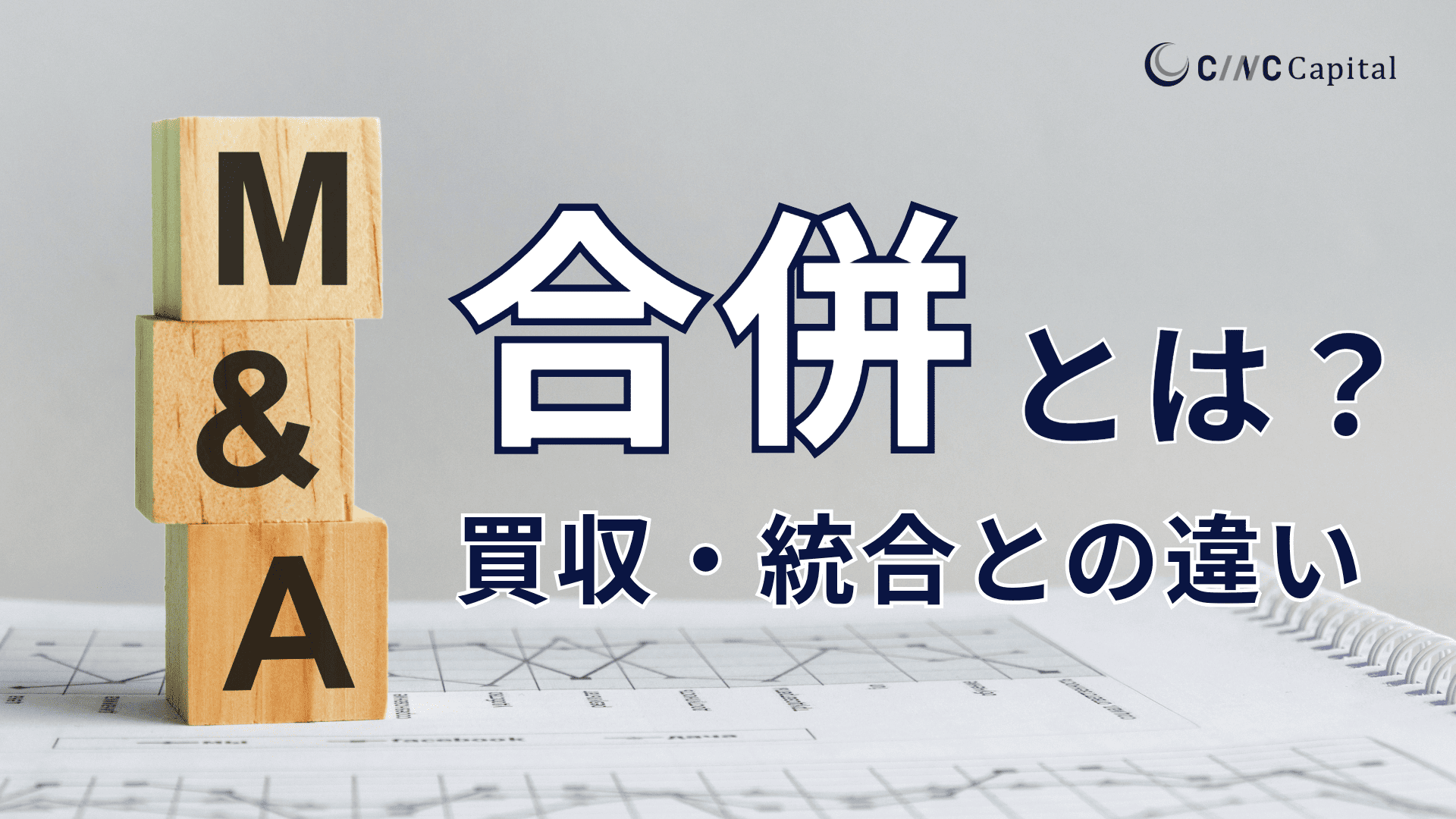
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
合併とは?意味や種類、買収や統合との違い、メリット、手続きをわかりやすく解説
合併は、企業の成長戦略として有効ですが、手続きの煩雑さや財務・法務リスク、組織統合の難しさなど、慎重に進めるべきポイントが多くあります。適切な準備と戦略がなければ、想定したメリットを得られない可能性もあります。
本記事では、合併の基本から、メリット・デメリット、必要な手続き、成功のためのポイントまで詳しく解説します。
目次
合併とは?
合併とは、2つ以上の企業が統合し、一つの法人となることを指します。M&Aの代表的な手法のひとつであり、企業の経営資源が一本化され、より強力な組織体制を構築できるメリットがあります。ここでは、合併と買収や統合との違い、合併時の株式の扱いについて説明します。
買収との違い
合併と買収はどちらも企業の統合手法ですが、根本的な違いがあります。合併は2つ以上の企業が統合し、1つの法人となるのに対し、買収は一方の企業が他方の企業を支配する形で経営権を取得する手法です。
合併では法人格が消滅する場合があり、企業のアイデンティティが統一される点が特徴です。一方で買収では、株式譲渡や事業譲渡などの手法があり、買収される企業の法人格が存続する場合と、消滅する場合があります。
例えば、株式譲渡では買収対象企業の法人格は存続しますが、事業譲渡では事業の売却により、売り手企業が清算されることもあります。したがって、企業の経営戦略に応じて、どちらの手法が適しているか慎重に検討する必要があります。
統合との違い
合併と統合は似た概念ですが、企業の存続形態に違いがあります。合併では消滅会社が法人格を失い、存続会社や新設会社に統合されます。一方、統合は持株会社の設立などを通じて、複数の企業がグループとして一体化する仕組みを指します。
統合の場合、各企業は法人格を維持したまま協力体制を築くため、ブランドや組織文化を保ちやすいです。そのため、企業が統合のメリットを享受しながら独自性を維持したい場合は、持株会社の設立などの統合手法が適しています。
合併すると株式はどうなる?
合併が行われると、消滅会社の株式は無効となり、存続会社や新設会社の株式が交付されます。これにより、消滅会社の株主は存続会社や新設会社の株主となるか、場合によっては合併対価として現金を受け取ることもあります。
特に上場企業同士の合併では、合併後の企業の株価や株式比率の変動が株主に影響を与えるため、合併契約の内容や合併比率が重要です。株主にとっては、合併による株式の価値や企業の将来性を見極めることが求められます。
合併の種類
企業の合併には「吸収合併」と「新設合併」の2つの主要な種類があります。吸収合併では、一方の会社が他方を吸収し、法人格を存続させます。一方、新設合併では複数の会社が統合され、新たな会社が設立されます。それぞれの手法には異なるメリットとデメリットがあり、企業の状況や目的に応じて適切な手法を選ぶ必要があります。以下では、それぞれの合併方法について詳しく説明します。
吸収合併
吸収合併は、存続会社が消滅会社を吸収し、すべての権利義務を承継する手法です。この形式では、消滅会社の法人格は消失し、存続会社が契約や資産、負債を引き継ぎます。
この手法が選ばれる理由は、手続きの簡便さにあります。新設合併と異なり、新しい法人を設立する必要がないため、登記や許認可の手続きを簡素化できます。また、存続会社が持つブランドや事業運営の枠組みを維持しやすいため、事業の継続性を確保しやすい点も特徴です。
一方で、存続会社は消滅会社の負債やリスクをすべて引き継ぐことになるため、事前のデューデリジェンスが重要になります。特に、簿外債務や訴訟リスクを見落とすと、合併後に経営上の大きな問題となる可能性があります。こうしたリスクを最小限に抑えるためにも、合併前の財務・法務調査を慎重に行うことが求められます。
新設合併
新設合併は、複数の会社が解散し、新たな法人を設立して統合する方法です。この場合、旧会社の法人格は消滅し、新会社がすべての権利義務を引き継ぎます。
この方式のメリットは、企業文化や経営体制をゼロから設計できることにあります。異なる組織文化や経営方針を持つ企業同士が統合する際、それぞれの強みを活かしながら新たな組織を構築できます。また、各企業の影響力を均等に保ちやすいため、対等な立場での統合が可能です。
しかし、新会社の設立には登記や許認可の手続きが必要になり、吸収合併よりも時間とコストがかかります。また、消滅会社が持つ許認可やライセンスが自動的に引き継がれないケースもあり、新たに取得し直す必要が生じることがあります。そのため、事前の計画やスケジュール管理が欠かせません。
合併のメリット
合併には、統合する双方の企業にメリットがあります。売り手側は、事業の成長機会を得たり、包括承継によってスムーズな経営移譲が可能になったりする利点があります。一方、買い手側はコスト削減や新規市場へのスムーズな参入を実現しやすくなります。ここでは、それぞれの視点から合併のメリットを詳しく解説します。
【売り手側】合併のメリット
まずは売り手側の合併のメリットについて解説していきます。
シナジー効果が期待できる
合併により、企業同士の経営資源を統合することで、シナジー効果が生まれます。例えば、技術力の高い企業と販売力の強い企業が合併すれば、製品開発と市場展開の両方を強化できます。また、供給網の共有や生産拠点の最適化を行うことで、業務の効率化が進みます。シナジー効果を最大限に引き出すには、合併後の経営戦略を明確にし、各企業の強みを活かす統合計画を策定することが重要です。
包括承継による円滑な譲渡ができる
合併では、契約や資産、負債、人材などを包括的に引き継ぐことが可能です。事業譲渡のように契約ごとに再締結する必要がないため、取引先や従業員への影響を抑えながらスムーズな移行が実現できます。また、企業が持つブランドや信用も維持されやすいため、取引関係を継続しやすい点も魅力です。特に、長年の取引先を抱える企業にとって、包括承継によるスムーズな事業移行は大きなメリットになります。
【買い手側】合併のメリット
次に買い手側の合併のメリットについて解説していきます。
コスト削減につながる
合併によって重複する業務や部門を統合すれば、全体的な運営コストを削減できます。例えば、管理部門を一本化することで、人件費やオフィスの賃料を減らすことが可能です。また、サプライチェーンを統合することで、原材料の調達コストを抑えたり、生産効率を向上させたりできます。
新規事業への進出がしやすい
合併を活用すれば、新たな市場や事業領域にスムーズに参入できます。ゼロから事業を立ち上げるのに比べ、既に市場で確立された企業と合併することで、短期間で事業展開が可能になります。例えば、海外市場へ進出したい場合、現地企業を合併すれば、既存の販路やブランドを活用できるため、リスクを抑えながら事業を拡大できます。
合併のデメリット
合併には多くのメリットがありますが、一方で売り手側・買い手側の双方にとって一定のリスクやデメリットが伴います。売り手側は、手続きの煩雑さや企業文化の統合の難しさに直面することが多く、買い手側は、簿外債務の引き継ぎリスクや株価の変動といった問題を抱える可能性があります。ここでは、それぞれの立場における具体的なデメリットについて説明します。
【売り手側】合併のデメリット
まずは売り手側の合併によるデメリットについて解説していきます。
手続きが煩雑で時間がかかる
合併には多くの法的手続きが伴い、完了までに時間がかかることが一般的です。具体的には、取締役会や株主総会の承認、合併契約の締結、債権者保護手続き、登記申請などが必要になります。特に、債権者保護手続きでは、一定の公告期間を設ける必要があり、手続きがスムーズに進まなければ合併のスケジュールが長引くことがあります。
さらに、許認可事業を行っている企業の場合、行政手続きが加わることで、より多くの時間と労力が必要になります。これらの手続きを円滑に進めるためには、事前に詳細な計画を立て、専門家の支援を受けながら進めることが重要です。
文化統合が課題となる
合併によって異なる企業文化が統合されるため、組織の一体感を醸成することが難しくなることがあります。特に、経営方針や働き方に大きな違いがある場合、従業員のモチベーション低下や退職者の増加につながる可能性があります。
また、管理体制の違いによって業務プロセスの統一が困難になるケースもあります。このような問題を防ぐためには、合併前から文化統合に向けた計画を策定し、合併後も継続的にコミュニケーションを図ることが重要です。
【買い手側】合併のデメリット
次に買い手側の合併によるデメリットについて解説していきます。
簿外債務を引き継ぐリスクがある
合併では、存続会社が消滅会社のすべての資産・負債を包括的に承継するため、簿外債務や未認識の法的リスクを引き継ぐ可能性があります。例えば、未払いの税金や訴訟リスクが後から発覚すると、存続会社の財務負担が増大し、経営に大きな影響を与えかねません。
これを回避するためには、合併前に十分なデューデリジェンスを実施し、財務や法務のリスクを徹底的に洗い出すことが重要です。特に、簿外債務の可能性がある場合、適切な契約条項を設定し、合併後のリスク管理体制を整えておく必要があります。
株価が下がるおそれがある
合併は将来的な成長に向けた重要な戦略ですが、実行の過程で株価が下落するリスクを伴います。特に、合併によるシナジー効果が想定よりも発揮されない場合や、経営統合(PMI、ポスト・マージャー・インテグレーション)が難航する場合、市場の期待を下回る結果となり、投資家の不安感から株価が下落することがあります。
加えて、合併に伴う統合コストが予想以上に膨らみ、短期的な収益を圧迫する場合も、株価にネガティブな印象を与える要因となります。また、企業文化の違いによる組織内の摩擦が大きいと、重要な人材の流出や生産性の低下を招き、将来性への疑念が株価に反映される可能性があります。
さらに、買収価格が過大になると「のれん」の金額が膨らみ、後に減損処理を余儀なくされるケースもあります。これにより企業の財務健全性が疑問視され、株価の下落につながることもあります。
また、合併時に存続会社が新株を大量に発行する場合、株式の希薄化だけでなく、市場での需給バランスが崩れることでも株価に下押し圧力がかかることがあります。こうしたリスクを抑えるには、合併の狙いや将来の戦略を明確にし、タイムリーかつ丁寧な情報開示を通じて投資家の理解と信頼を得ることが重要です。
人材流出のリスクがある
合併後、企業文化や待遇の変化によって、被合併企業側のキーパーソンや優秀な人材が流出することがあります。例えば、従業員に対する説明不足や評価制度の変更が原因で、モチベーション低下や退職につながるケースもあります。
これを防ぐには、合併後も従業員との信頼関係を保ち、処遇やキャリアの見通しを明確にすることが大切です。
顧客離れのリスクがある
合併によってサービス内容や体制に変化が生じると、顧客が不安を感じて他社に流れるリスクがあります。特にBtoBビジネスでは、担当者の変更や契約条件の見直しが原因で信頼を失うこともあります。顧客離れを防ぐには、事前に影響を説明し、合併後の対応方針を共有することが求められます。
統合に時間とコストがかかる
合併後の組織統合は、思った以上に複雑で時間がかかります。システムの統合、業務フローの見直し、人員配置の最適化など、多くの工数が必要となるため、想定よりもコストや工期が膨らむケースもあります。計画段階からPMIを見据えた準備を進めることが、成功の鍵を握ります。
シナジーが実現しないリスクがある
合併の目的として掲げたシナジー効果が、必ずしも期待通りに得られるとは限りません。例えば、組織文化の違いや部門間の連携不足により、効率化や売上向上が実現しないこともあります。こうしたリスクに備えて、合併後の効果測定と継続的な改善策を講じる体制を整えておくことが大切です。

吸収合併の流れ・必要な手続き
吸収合併を実施するには、複数の法的手続きを経る必要があります。企業間の合意から始まり、取締役会や株主総会の決議、債権者への対応、登記手続きまで、適切な段階を踏まなければなりません。それぞれのプロセスには法的要件があり、計画的に進めることが重要です。ここでは、吸収合併の流れと必要な手続きを順を追って解説します。
事前準備
吸収合併を進める前に、対象企業との基本合意を形成し、詳細な調査を実施することが求められます。特に財務・法務デューデリジェンスを徹底することで、簿外債務や契約上のリスクを事前に把握できます。また、合併の目的や方針を明確にし、シナジー効果を最大化するための計画を策定することも欠かせません。これらの準備を怠ると、合併後に想定外の問題が発生し、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
取締役会の決議
合併を正式に進めるためには、各社の取締役会で合併契約を承認する必要があります。取締役会では、合併の基本条件や存続会社・消滅会社の役割、合併比率、株式交付の有無などが審議されます。この決議を経て、合併契約が締結されるため、慎重な検討が求められます。特に上場企業の場合、株主や投資家への影響が大きいため、透明性のある議論が不可欠です。
事前開示手続き
合併契約を締結した後、株主や債権者が内容を確認できるように、一定期間、関係書類を開示する必要があります。この開示期間は、株主総会の2週間前から開始され、合併後も一定期間継続されます。主な開示書類には、合併契約書、財務諸表、経営計画などが含まれます。開示を適切に行うことで、株主や債権者の理解を得やすくなり、後の手続きが円滑に進みます。
債権者保護手続き
合併では、存続会社が消滅会社のすべての債務を引き継ぐため、債権者に対して異議申し立ての機会を設ける必要があります。これに対応するため、企業は官報に公告を掲載し、個別の債権者に対しても通知を行います。債権者が異議を申し立てた場合、適切な保証措置や弁済を行わなければなりません。この手続きを怠ると、法的トラブルにつながるため、慎重に対応することが重要です。
株主総会決議
合併契約は株主総会での特別決議によって承認される必要があります。特別決議には、議決権の3分の2以上の賛成が求められます。存続会社側では一定の条件を満たせば株主総会の省略が可能ですが、消滅会社側では原則として開催が義務付けられています。この総会では、合併の目的や条件、今後の経営方針について説明し、株主の理解を得ることが求められます。
反対株主への株式買取請求対応
合併に反対する株主は、一定の条件下で、企業に対して自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求する権利(株式買取請求権)を行使できます。これは、合併後の経営方針や条件に納得できない株主を保護するための制度です。
ただし、すべての合併形態で買取請求権が発生するわけではありません。たとえば、簡易合併(後述)の場合は、存続会社側で株主総会が不要となるため、存続会社の株主には買取請求権が発生しません(会社法第796条)。
また、略式合併(後述)においても、一定の支配関係(議決権の90%以上保有など)がある場合には、株主総会自体が不要とされるため、買取請求権も発生しないケースがあります(会社法第784条)。
一方で、消滅会社の株主は、たとえ簡易合併や略式合併であっても株主総会決議が必要な場合には、原則として買取請求権を有します(会社法第785条)。
企業側は、該当する株主から買取請求があった場合、適正な価格で株式を買い取る必要があります。請求が多発すると財務負担が増える可能性があるため、合併前に株主に対して合併の目的やメリットを十分に説明し、理解を得ることが重要です。
合併効力発生
合併契約に定められた効力発生日を迎えると、法的に合併が成立します。この時点で、消滅会社の法人格は失われ、存続会社がすべての権利義務を引き継ぎます。合併の効力が発生した後は、存続会社と消滅会社の業務プロセスを統合し、経営体制を一本化することが求められます。効力発生後は、従業員の雇用や取引契約の履行など、統合プロセスを円滑に進めることが重要です。
合併登記申請
合併の効力が発生した後、法務局に合併登記を申請する必要があります。この手続きにより、公的記録上も合併が成立したことが確認され、存続会社と消滅会社の情報が正式に更新されます。登記手続きの遅れは、取引関係や契約手続きに影響を与えるため、速やかに完了させることが求められます。
各種届出・手続き
合併後には、税務署や自治体、社会保険機関などへの届出が必要になります。また、許認可事業を行っている場合、所管官庁への名義変更手続きが求められることがあります。これらの手続きを怠ると、行政上の問題が発生する可能性があるため、早めに対応することが重要です。さらに、取引先や金融機関にも合併の通知を行い、新たな契約関係を適切に管理する必要があります。
合併を実施するうえでの注意点
合併を成功させるには、単に手続きを完了させるだけでなく、適切な会計処理、法的手続きの理解、統合プロセス(PMI)の適用が必要です。特に、合併の種類によって異なる会計処理や、株主総会を省略できる特例制度(簡易合併・略式合併)について理解することが求められます。
また、合併後の統合作業(PMI)を適切に進めなければ、シナジー効果を十分に発揮できません。ここでは、合併を円滑に進めるための注意点について詳しく説明します。
会計処理について理解が必要
合併の会計処理は、存続会社と消滅会社の関係や合併形態によって異なります。特に重要なのが、「取得法(パーチェス法)」に基づく処理です。
現在の会計基準では、「持分プーリング法」が廃止されており、取得法が唯一の方法として採用されています(企業会計基準第21号)。取得法では、消滅会社の資産や負債を時価で評価し、存続会社の財務諸表に計上します。このとき、取得対価が純資産を上回る部分については「のれん」として資産に計上されます。一方で、下回る場合には「負ののれん」として特別利益として処理されるケースもあります。
こうした処理は、企業の貸借対照表や損益計算書に与える影響が大きいため、事前に専門家と相談の上で適切に判断することが重要です。特に、のれんの金額や減損リスクは、将来の財務負担にも直結するため、慎重な検討が求められます。
また、税務上は適格合併と非適格合併の区別があり、適格合併では譲渡損益が繰り延べられ、法人税の負担を抑えられます。しかし、非適格合併では消滅会社の資産が時価評価されるため、譲渡益課税が発生する可能性があります。こうした税務処理の違いは、企業の財務状況に大きく影響するため、税理士や会計士と相談しながら進めることが重要です。
簡易合併と略式合併
合併には株主総会の承認が必要ですが、一定の条件を満たす場合、手続きを簡略化できる制度が存在します。それが簡易合併と略式合併です。これらの制度を活用することで、合併プロセスを迅速に進めることが可能になります。
簡易合併
簡易合併とは、会社法第796条第2項に基づき、存続会社が消滅会社の株主に交付する合併対価の帳簿価額が、存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合に、存続会社の株主総会の承認を省略できる制度です。これにより、存続会社側の合併手続きが簡略化され、実行までのスピードを早めることができます。
特に、吸収する側の企業が大規模で、吸収される側の規模が小さい場合に適しており、株主総会の開催にかかる手間やコストを削減するのに有効です。ただし、消滅会社側では原則として株主総会の決議が必要であるため、両社の手続き要件を事前に確認しておくことが重要です。債権者保護手続きや開示義務は依然として求められるため、合併契約の内容を十分に検討する必要があります。
略式合併
略式合併とは、合併を行う会社間で一定の支配関係がある場合に、株主総会の承認を省略できる制度です。会社法においては、以下の2つのケースが定められています。
1つ目は、存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合(会社法第784条第1項)で、この場合は消滅会社の株主総会の承認が不要になります。2つ目は、消滅会社が存続会社の議決権の90%以上を保有している場合(会社法第796条第1項)で、このケースでは存続会社の株主総会の承認が不要とされます。
いずれのケースも、会社間に強い支配関係があることから、通常必要とされる株主総会手続きを省略できる点が特徴です。特に、親会社が子会社を吸収合併する場面で活用されることが多く、手続きを迅速に進めることが可能になります。
ただし、少数株主が存在する場合には、適正な情報開示や合併条件の説明、株式買取請求権の行使への配慮が求められます。事前に十分な説明や協議を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
PMIを意識したM&Aの実施
合併が成功するかどうかは、PMI(Post Merger Integration:合併後の統合プロセス)の実施にかかっています。PMIが適切に行われなければ、合併によるシナジー効果を十分に発揮できません。統合が不完全なまま進むと、組織の混乱や従業員のモチベーション低下を招き、最悪の場合、業績の悪化につながる恐れがあります。
PMIの成功には、組織・業務・文化の統合が不可欠です。まず、業務の標準化やシステムの統合を進めることで、スムーズなオペレーションを確立できます。特に、財務・会計システムやITインフラの統一は、合併後の経営管理を円滑にするために不可欠です。
また、企業文化の違いによる軋轢を防ぐためには、従業員の不安を取り除く施策を講じる必要があります。経営陣が合併の目的を明確に伝え、統合後のビジョンを共有することで、組織内の結束を強められます。さらに、PMIの進捗を定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行うことで、持続的な成長を実現できます。
まとめ|合併はメリットが豊富。M&A仲介会社の支援をもらい、円滑に合併を進めよう
合併は、シナジー効果やコスト削減、新規市場への進出など多くのメリットをもたらします。しかし、手続きの煩雑さや統合の難しさといった課題も伴うため、慎重な準備が不可欠です。
M&A仲介会社等の支援を活用すれば、適切な相手企業の選定や手続きの円滑化が可能になります。専門家のサポートを受けながら、計画的に進めることで、合併を成功に導きましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















