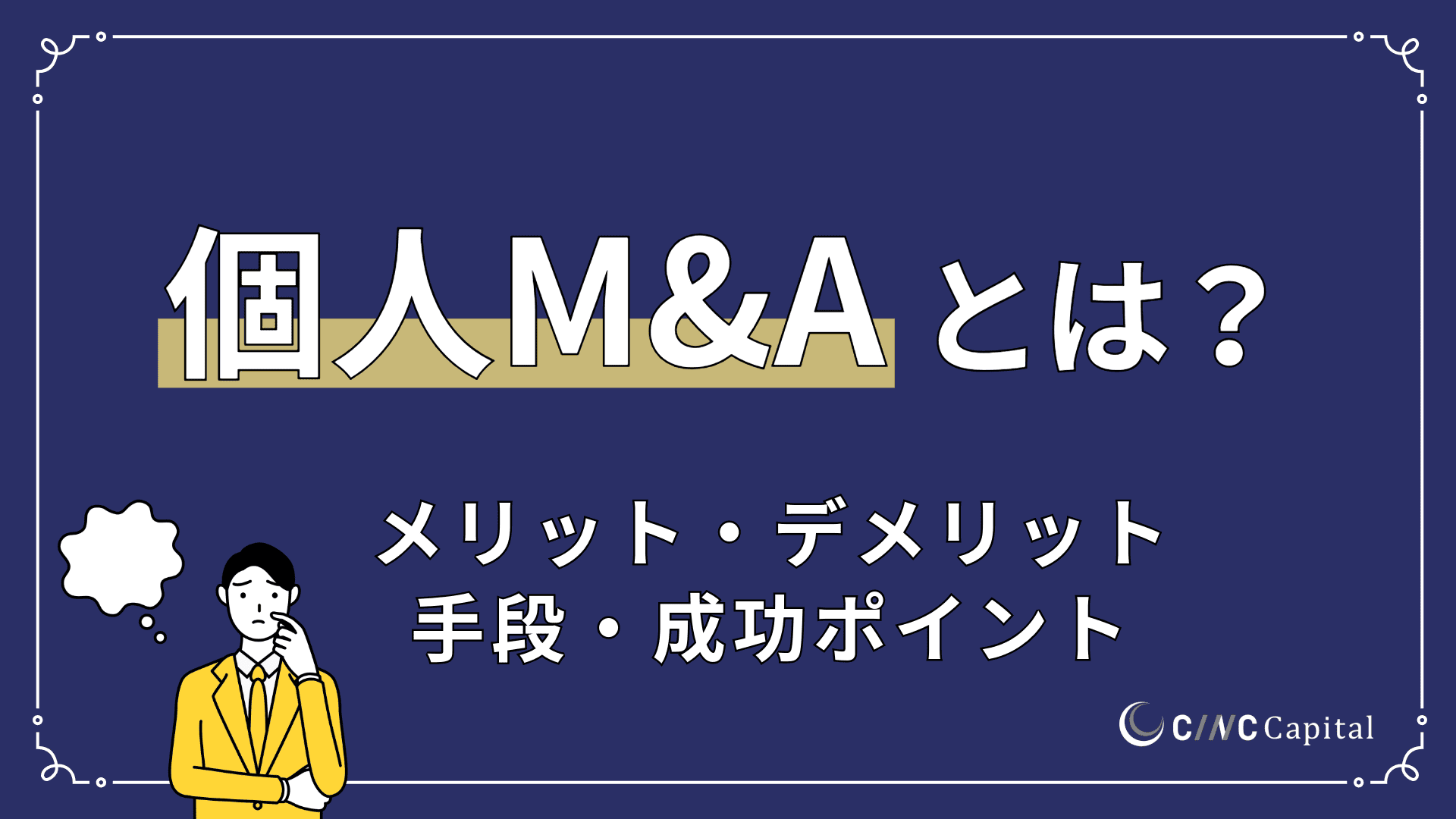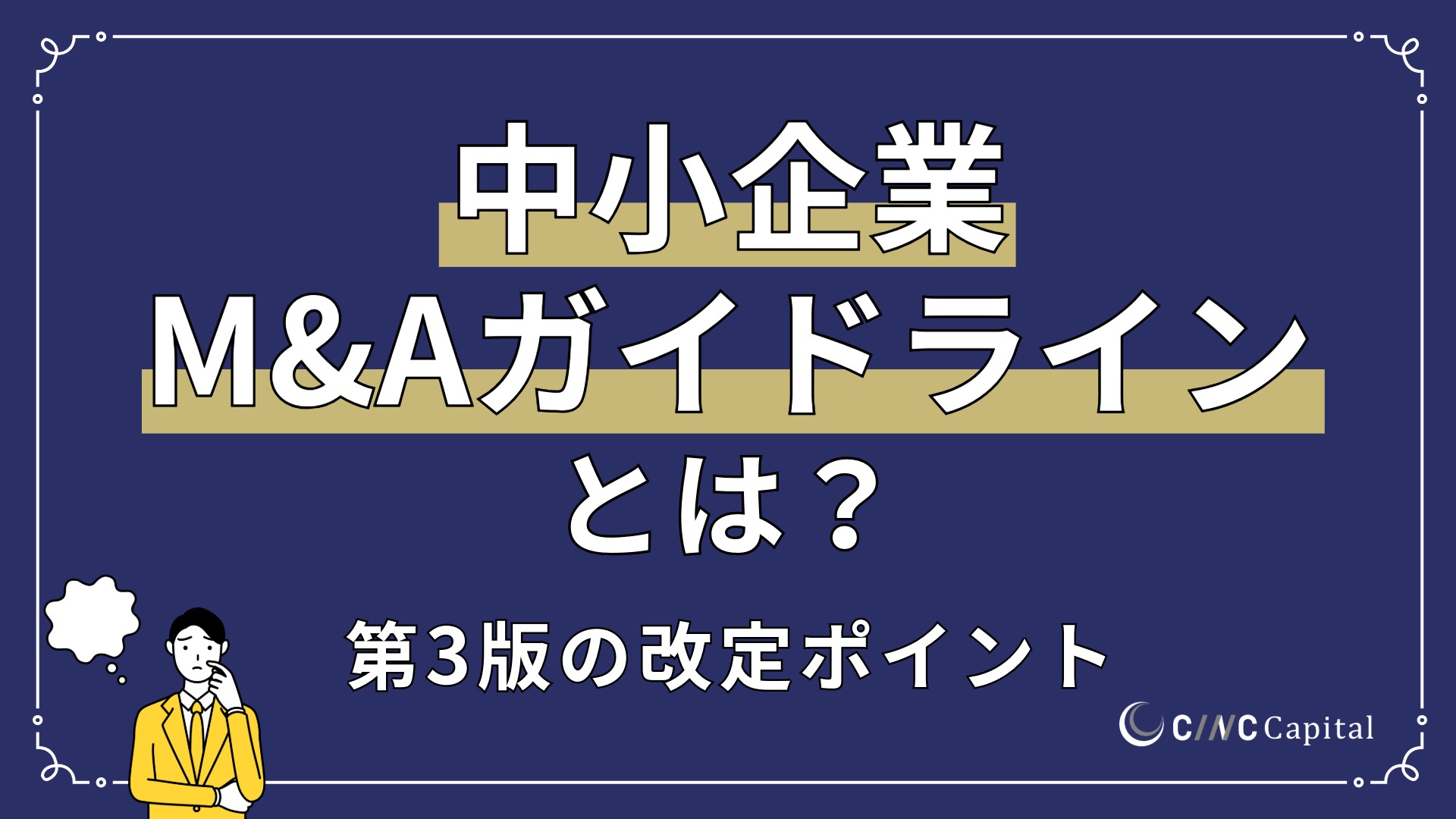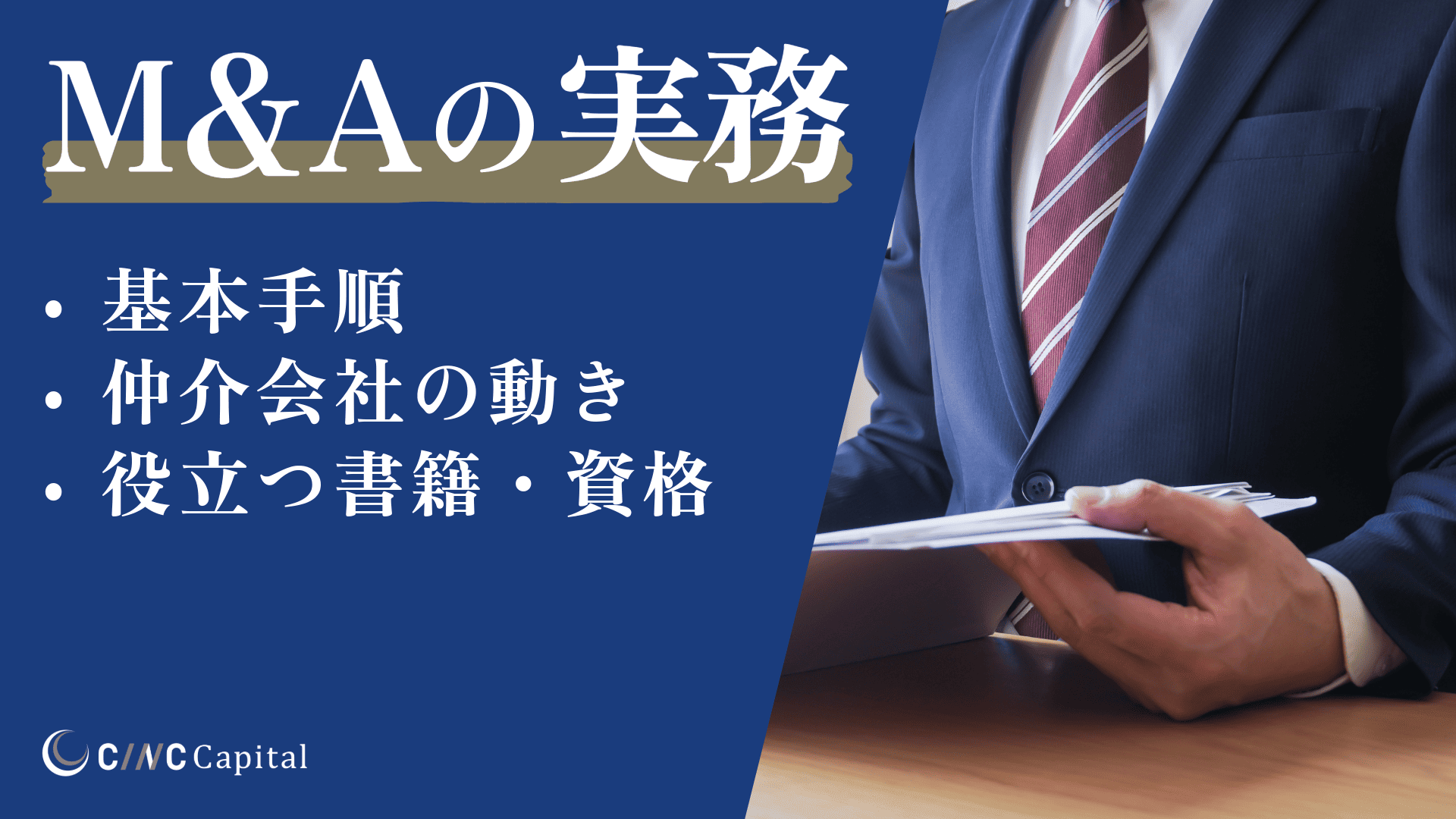CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.06.26
【事例あり】スタートアップのM&Aとは?買い手と売り手のメリットデメリットを解説
経営資源の不足に陥ることがあります。一方で、スタートアップが持つ技術やノウハウを魅力的に感じている大企業も多いです。
こうしたスタートアップと大企業の持つニーズを両方満たす可能性のある手段がM&Aです。M&Aは、売却する側にとっては持続可能な成長を実現する手段として、買収する側にとっては新しい技術や市場の迅速な獲得手段として、用いられています。
今回では、スタートアップM&Aの重要性を買う側と売る側の両方の視点から解説し、成功するためのポイントを紹介します。
目次
スタートアップにおけるM&Aの重要性
スタートアップでM&Aが重要視される理由は、多くの戦略的な利点があるからです。M&Aによって、スタートアップは速やかに規模を拡大し、市場シェアを獲得することができます。この戦略は競争の激しい市場で素早く優位に立つために有効です。
例えば、大手企業が技術力に優れたスタートアップを買収することで、その技術を自社のサービスに組み込んで高い競争力を持つ製品を提供するといったことができます。
スタートアップにとってM&Aは成長と市場拡大が実現できる手段として有効なのです。
【買収する側】スタートアップをM&Aをするメリット
スタートアップをM&Aをすることで、買収する側は多くのメリットが得られます。ここからは、スタートアップをM&Aをすることによる具体的なメリットについて解説します。
既存事業のさらなる成長が期待できる
スタートアップをM&Aすることで、既存事業の成長が期待できます。新しい技術や革新を既存事業に取り入れることで、成長戦略を加速させられるからです。
競争力を高めたい大規模なヘルスケア企業が革新的な医療技術を持つスタートアップを買収するといったケースが例として挙げられます。
大規模なヘルスケア企業が持つ既存の医療サービスに革新的な技術を加え、より優れた医療サービスの提供が可能になるというわけです。
スタートアップのM&Aは、既存事業の成長を加速させる強力な手段となります。また、スタートアップの持つ独自のノウハウや企業文化を取り入れることで、組織全体が新たな視点から物事を考えるきっかけとなります。
ハードルを低くして新規事業に参入できる
新規事業をゼロから立ち上げる場合、大量の設備投資や市場調査、マーケティング活動が不可欠です。こうした工程は時間とコストの両方がかかるため、多くの企業にとって大きな負担となります。
しかし、既に確立されたスタートアップを買収すれば、時間とコストを大幅に削減することが可能です。
事業として成熟していなかったとしても、ある程度はスタートアップが既に進めているからです。こうした理由から、M&Aは新規事業参入のハードルを低くし、迅速かつ効果的な市場参入を実現させる有効な手段となります。
買収先のアイデアを獲得できる
他にはないクリエイティブで革新的なアイデアを持っているスタートアップ企業を買収すれば、新しいアイデアを自らのビジネスに活用できるようになります。
スタートアップのアイデアを活用することで、自社のビジネスに新しい風を入れ、多様な視点からのアプローチが可能です。これにより、競争力が強化され、業界内でのポジションを更に向上することが期待できます。
【買収する側】スタートアップをM&Aをするデメリット
買収によって得られるメリットが多い一方で、買収する側にもいくつかのデメリットが存在します。これらを理解しないままM&Aを行うと、期待した成果を得られないばかりか、損失が生じかねません。
以下では、特に注意が必要なデメリットについて詳しく解説します。
人材流出が起こる可能性がある
M&Aが成立した後、買収した企業に在籍していた人材が流出する可能性があります。これは、買収先の従業員が企業文化や経営方針の変更に適応できなかったり、不信感を抱いたりすることが主な原因です。
具体的には、自由奔放な企業文化が特色だった企業を買収した場合、企業文化の変化に対する不満を理由に人材が流出する可能性があります。
このような人材流出を防ぐためにも、M&A前から従業員とのコミュニケーションを強化し、不安を取り除くための対策を講じることが重要です。
従業員が抱える疑問や不安に真摯に対応することで、リスクを極力減らせます。従業員が安心して新しい環境で働けるようになれば、人材流出を最低限に抑えることができるでしょう。
買収先で起きている問題を引き継ぐことになる
買収先が何かしらの問題を抱えていた場合、内容によっては買収した企業にも引き継がれるからです。
例えば買収先が簿外債務を抱えている場合、その債務は買収した企業が引き継ぐことになります。簿外債務とは、財務諸表に記載されていない未公開の負債のことです。買収後に簿外債務が発覚すると、予期せぬ財務負担が発生する可能性があります。
このようなリスクを回避するためには、デューデリジェンス(買収する企業の財務状況や法律面のリスクなどを調査すること)が大切です。デューデリジェンスを行うことで、買収先の潜在的な問題やリスクを事前に把握できます。
【売り手側】スタートアップがM&Aの戦略を選ぶメリット
スタートアップにとって、M&Aは生き残りや事業成長のための重要な戦略の1つです。
ここからは、買収される側のスタートアップがM&Aの戦略を選ぶメリットについて詳しく解説します。
買収する側の経営資源を事業に活用できる
スタートアップがM&Aを選ぶメリットの1つは、買収する側の経営資源を活用できることです。買収する側の企業は多くの場合、資金力に余裕がある大企業です。大企業が持つ経営資源を活用して事業展開ができるようになります。
大企業が持つリソースを活用すれば、スタートアップは新しい市場に迅速に進出したり、技術革新を加速したりできます。大企業のリソースを活用して事業をスケールアップし、競争力を強化することが可能です。
単独では達成が難しい市場シェアの拡大や、効果的なマーケティング戦略の実施、大規模なインフラの整備などが実現できます。
企業が赤字でも成立する
スタートアップが赤字経営だったとしてもM&Aは成立することがあります。買収側がスタートアップの将来性や独自の技術、ノウハウに価値を見出しているからです。赤字であろうとも、その企業の持つ魅力や成長ポテンシャルが評価される場合があります。
例えば、まだ利益が満足に出ていないものの、画期的な技術や強力な特許を所有しているスタートアップがあったとして、こうした点に目をつけた大手企業が買収を決定することがあるかもしれません。
つまり、スタートアップが赤字であることはM&A成立の障害にはならず、買収側にとっては依然として魅力的な投資対象となり得るのです。
【関連記事】赤字会社の売却は可能?価格の計算方法や成功のポイント
【売り手側】スタートアップがM&Aの戦略を選ぶデメリット
スタートアップがM&Aの戦略を選ぶ際には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、買収される側が直面する可能性のある主なデメリットについて、詳細に解説します。
必ず希望額で売却できるとは限らない
スタートアップをM&Aで売却する際、必ずしも希望する金額での売却が実現するとは限りません。M&Aプロセスにおいて、買収する側はリスクとリターンを評価し、適正価格を提示します。そのため、売却希望額よりも低い金額でのオファーが提示されることもあります。
買収側が適正価格を提示する際、いくつかの要素が影響しています。主な要素は、企業の成長性、現在の市場環境、買収先の財務状況、そして競合他社との比較などです。
例えば、市場全体が停滞している時期に売却を試みると、成長性が認められにくく、買収者がリスクを感じて低い価格を提示することがあります。M&Aの選択肢に入ってくる競合他社が同じ市場に多く存在する場合も、希望価格での売却は難しくなる傾向があります。
適正価格の設定は、買収する側が自社の利益を確保しつつ、合理的な投資判断を下すために行われます。スタートアップ経営者としては、期待した額での売却が実現しない可能性があることを念頭に置いておきましょう。
【関連記事】事業価値とは?計算方法や企業価値との違い、価値を高める方法を解説
【関連記事】会社売却は儲かる?金持ちになれる?売却益の相場や計算方法を解説
経営権を失う
スタートアップがM&Aを選んだ場合、経営権を失うリスクがあります。M&Aによって買収されると、新たな経営者や経営チームが会社の運営を引き継ぐことが一般的だからです。場合によっては、オーナーや創業者がこれまで大切にしてきた経営理念や方針が変更される可能性があります。
経営権を失うリスクを回避するためには、契約の際に明確な条件を設けることや、交渉の段階で自らの意見をしっかりと伝えることが求められます。経営権の喪失が企業の成長にどう影響するのかを理解し、最善の判断ができるように努めましょう。
従業員が退職するリスクがある
スタートアップがM&Aを選んだ結果、従業員の退職が相次ぐケースもあります。M&Aを機に変わった新しい経営体制や企業文化に馴染めない従業員が不満を持ち、退職を決意することがあるからです。特に小規模な組織では、独自の文化やチームワークが強く影響するため、こうした変化に敏感な従業員が多い傾向にあります。
M&Aを進める際には、従業員の満足度維持や退職リスクを慎重に考慮しておきましょう。適切なコミュニケーションを行って従業員のモチベーションを管理することもM&Aには欠かせない要素です。
【関連記事】売却された会社の社員はどうなる?影響や社員とのトラブルを防ぐための注意点について解説
スタートアップのM&Aを成功させるためのポイント
スタートアップのM&Aは、成長戦略の一環として重要な手段ですが、成功させるためには適切な準備と戦略が不可欠です。ここでは、適正な企業価値の算定、最適な買い手の選定、従業員やステークホルダーへの対応といった主要なポイントを解説します。
適正な企業価値を算定する
M&Aを成功させるためには、まず自社の適正な企業価値を把握することが不可欠です。適切なバリュエーションを行うことで、買い手にとって魅力的な取引条件を提示しつつ、自社の価値を最大限に評価してもらうことが可能になります。
財務データや市場分析を基に、企業価値の算定を行う際は、売上や利益だけでなく、成長率や市場シェア、競争環境などを評価することが重要です。一般的なバリュエーション手法としては、DCF法(割引キャッシュフロー法)、市場比較法、純資産法などがあります。
特にスタートアップでは将来の成長性が重視されるため、財務データだけでなく、事業のスケーラビリティや市場のポテンシャルも考慮することが求められます。
また、M&Aでは買い手に対して企業の成長性や独自性を明確にアピールすることが重要です。特に競争優位性のある技術やビジネスモデル、強固なユーザーベースを持つ企業は、買い手にとって魅力的な対象となります。
例えば、SaaS企業であれば、LTV(顧客生涯価値)やCAC(顧客獲得コスト)などの指標を示し、将来の収益性を具体的に伝えるとよいでしょう。
さらに、買い手はM&Aの意思決定前にデューデリジェンス(DD)を実施し、対象企業の財務・法務・税務などを詳細に確認します。この際、未整理の財務データや契約上のリスクがあると、M&Aの進行に大きな影響を及ぼす可能性があります。
知的財産権の未整理、未払いの税金、従業員との労務問題などが発覚すると、取引が破談になることもあるため、事前に財務・法務の整理を徹底し、潜在的なリスクを洗い出しておくことが重要です。
【関連記事】企業価値とは?計算方法や株式価値との違い、企業価値を高める方法も解説
適切な買い手を選定する
M&Aの成功は、適切な買い手を選定できるかどうかに大きく左右されます。自社の成長戦略や企業文化に合致した買い手を見つけることで、シナジー効果を最大化し、円滑な統合が可能となります。
買い手には、大企業や同業他社、投資ファンドなどさまざまな選択肢があります。しかし、単に資金力のある企業を選ぶのではなく、自社の事業戦略や企業文化と合致するかどうかを慎重に見極めることが重要です。例えば、事業の継続性を重視する場合、買収後も経営の独立性を尊重する企業を選ぶことが適しています。
一方で、成長資金の確保を優先する場合は、戦略的投資家やベンチャーキャピタルとの提携も視野に入れるべきでしょう。
また、M&Aではシナジー効果が重要なポイントとなります。例えば、買収企業が自社の技術を活用して新たな市場を開拓できる場合や、既存の販売チャネルを活用して事業を拡大できる場合などが考えられます。
買い手との交渉では、こうしたシナジーを具体的に示し、双方にとってメリットのある取引となるよう進めることが大切です。
適切な買い手を見つけるためには、M&A仲介会社や専門家の活用も有効です。業界に精通したアドバイザーがいれば、適切な買い手候補の紹介や交渉のサポートを受けることができます。
また、M&Aプロセスには法務・財務・税務などの専門知識が必要となるため、弁護士や公認会計士などの専門家と連携することで、スムーズな取引が可能になります。
従業員やステークホルダーへ適切に対応する
M&Aは企業の存続に関わる大きな決断であり、従業員や取引先、顧客などのステークホルダーに対して適切な対応を行うことが不可欠です。
M&Aによって、従業員の雇用形態や役割が変わるケースがあります。これに対する不安を軽減するため、事前に処遇を明確にし、必要な説明を行うことが重要です。特に、経営陣が明確な方針を示し、社員のキャリアに配慮した措置を講じることで、組織の安定性を保つことができます。
また、M&Aによる事業の変化は、取引先や顧客にも影響を与えます。特に、サービス内容の変更や契約条件の見直しが発生する場合、事前に説明を行い、信頼関係を維持することが重要です。
適切なタイミングで透明性のある情報開示を行い、不安を払拭することで、取引先や顧客との関係を維持しやすくなります。
さらに、M&Aに伴う組織変化は混乱を招く可能性があるため、事前に明確なコミュニケーション戦略を策定することが求められます。
特に、従業員や取引先に対しては、経営陣が積極的に説明を行い、不安を解消することが不可欠です。誤った情報が広まると、企業のブランド価値や市場での信頼性にも影響を及ぼすため、適切なタイミングと方法で情報を発信することが重要です。
スタートアップの最新M&A事例
【事例1】凸版印刷、ブルックマンテクノロジを子会社化
2021年3月、凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス)は、CMOSイメージセンサの開発・販売を手掛ける静岡大学発のベンチャー企業、株式会社ブルックマンテクノロジの発行済み株式89.1%を取得し、子会社化しました。
両社は2017年より資本業務提携を締結し、3Dイメージセンシング技術の研究・開発を共同で進めていました。近年、スマートフォンやゲーム機、自律自走ロボットの進化に伴い、高性能な3Dセンサの市場が拡大しており、特にToF(Time of Flight)方式の3D距離画像センサは、小型・低消費電力という特長から幅広い機器に採用が進んでいます。
このM&Aを通じて、凸版印刷はブルックマンテクノロジの持つToFセンサ設計技術と、自社の半導体回路設計技術を組み合わせ、高性能な3Dイメージセンサの開発を推進し、同市場への本格参入を目指しています。また、DX推進においても、センシング技術を活用し、新規事業の創出にも取り組んでいく方針です。
このM&Aは、3Dセンシング技術を核とした新たな事業領域の開拓を目的とした戦略的M&Aであり、今後のさらなる成長が期待されます。
【事例2】マイナビ、FacePeerを子会社化
2021年3月、株式会社マイナビは、企業向けビデオ通話プラットフォーム「FACEHUB」などを開発・運営するFacePeer株式会社の全株式を取得し、子会社化しました。
FacePeerは、オンライン面接や商談、遠隔サポートなど多様な用途に対応するビデオ通話ツールを提供し、1,000社以上の企業に導入されています。マイナビは2017年に同社へ初回出資を行い、各事業部門との連携を深めていました。特に、新型コロナウイルス感染拡大を背景に、マイナビの就職情報事業とFacePeerのオンライン面接ツールの活用が急速に拡大していました。
このM&Aにより、マイナビはオンライン採用支援の強化を図り、求職者と企業の円滑なコミュニケーションを促進するサービスの提供を加速させる方針です。オンライン採用市場が拡大する中、本M&Aは、デジタル技術を活用した人材サービスのさらなる進化を目的とした戦略的な取り組みといえます。
【事例3】お金のデザイン、第一種金融商品取引業をSMBC日興証券へ承継
株式会社お金のデザインは、2021年8月1日付で、第一種金融商品取引業に関わる事業をSMBC日興証券株式会社へ承継する会社分割(吸収分割)を実施しました。本M&Aにより、お金のデザインが運営するロボアドバイザー「THEO[テオ]」の証券口座管理業務をSMBC日興証券が担うこととなりました。
お金のデザインは、テクノロジーを活用した資産運用サービスを提供するフィンテック企業として、個人投資家向けの自動運用プラットフォームを展開してきました。一方、SMBC日興証券は、大手証券会社として堅牢な口座管理基盤を有しており、両社の連携によってサービスの安定性と利便性の向上が期待されます。
本件は、お金のデザインが自社完結型のビジネスモデルから脱却し、パートナーシップを活用した成長戦略へ移行する一環として行われました。これにより、同社は資産運用アルゴリズムやテクノロジーの開発に経営資源を集中させ、一方でSMBC日興証券は、証券口座の提供と金融商品の拡充を担う形となります。
本M&Aは、デジタル金融サービスのさらなる発展と顧客への付加価値向上を目的とした戦略的な取り組みといえます。
【出典】SMBC日興証券株式会社との会社分割(吸収分割)契約締結に関するお知らせ
【事例4】シーエーシー、スカイプロデュースジャパンを子会社化
2024年2月、株式会社シーエーシー(CAC)は、ソフトウェア開発およびシステムエンジニアリングサービス(SES)を提供する株式会社スカイプロデュースジャパン(SPJ)の全株式を取得し、子会社化する契約を締結し、2月末に株式取得が完了しました。
SPJは、特に生損保業界向けのシステム開発で豊富な実績を持ち、業界特有の業務ノウハウを蓄積しています。一方、CACは金融・医薬業界向けのシステム構築や運用管理を主力事業とし、デジタル技術を活用したサービスの拡充を進めています。今回の買収により、CACはコア事業における人的リソースの強化を図り、より高度なITソリューションの提供を目指しています。
本M&Aは、金融・保険業界向けのシステム開発需要の高まりを背景に、技術力と専門知識の強化を目的とした戦略的な取り組みといえます。今後、両社のシナジーを活かし、競争力のあるITサービスの提供が期待されます。
【出典】株式会社スカイプロデュースジャパンの株式取得(子会社化)のお知らせ
【事例5】オイシックス・ラ・大地、アグリゲートを連結子会社化
2024年3月、オイシックス・ラ・大地株式会社は、「旬八青果店」を運営する株式会社アグリゲートの新株予約権を行使し、既存株主からの株式取得も行うことで、同社を連結子会社化しました。
アグリゲートは、契約生産者や全国の市場と連携し、ストーリー性のある農産品の開発・販売を行う企業で、東京都内に地域密着型の青果店を展開しています。2023年5月にはオイシックス・ラ・大地の関連会社となり、規格外野菜の流通促進や共同商品開発などの連携を進めていました。
当初から子会社化を視野に入れていた本件により、両社はフードロス削減の取り組みを加速させ、グループ全体での商品流通の効率化を図る方針です。
本M&Aは、持続可能な食品流通の実現に向けた戦略的な一手であり、食品ロス削減や生産者支援といった社会課題の解決に寄与すると期待されます。
【出典】オイシックス・ラ・大地 旬八青果店を運営するアグリゲート社を連結子会社化 ~青果や食品流通での社会課題解決に向けてグループ全体でシナジーを創出~
まとめ丨スタートアップM&Aは双方にメリットがある
今回はスタートアップM&Aの具体的なメリットとデメリットを解説しました。M&Aは買収する側と買収される側の双方に多くのメリットがあります。そのため多くの企業でM&Aの戦略が採用されています。
しかしM&Aは計画の開始から完了まで複雑なプロセスを伴います。そのため、経験豊富な仲介会社やM&Aアドバイザーの力を借りながら進めることがほとんどです。詳細を知りたい場合は、専門家へ相談してみてください。