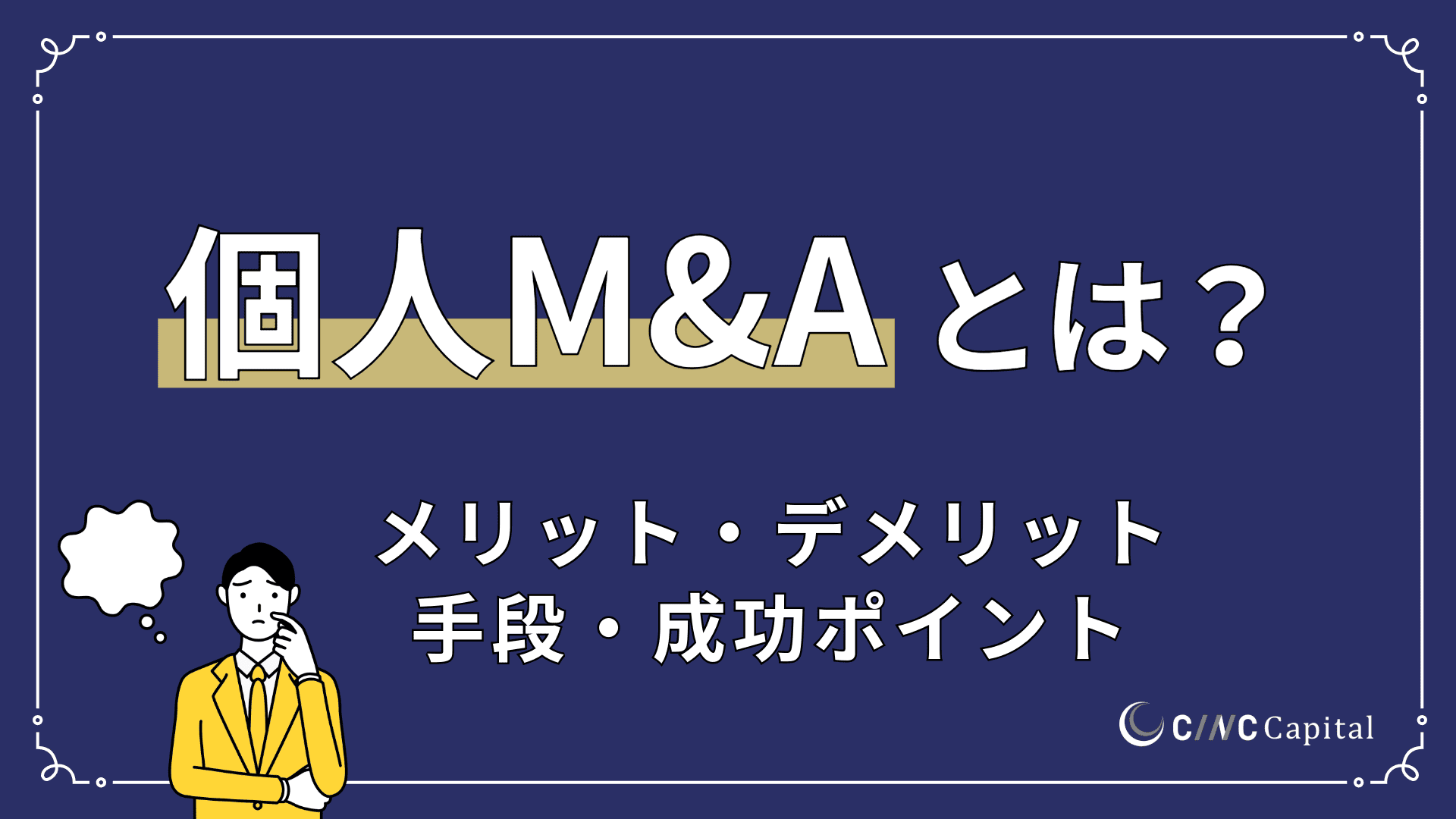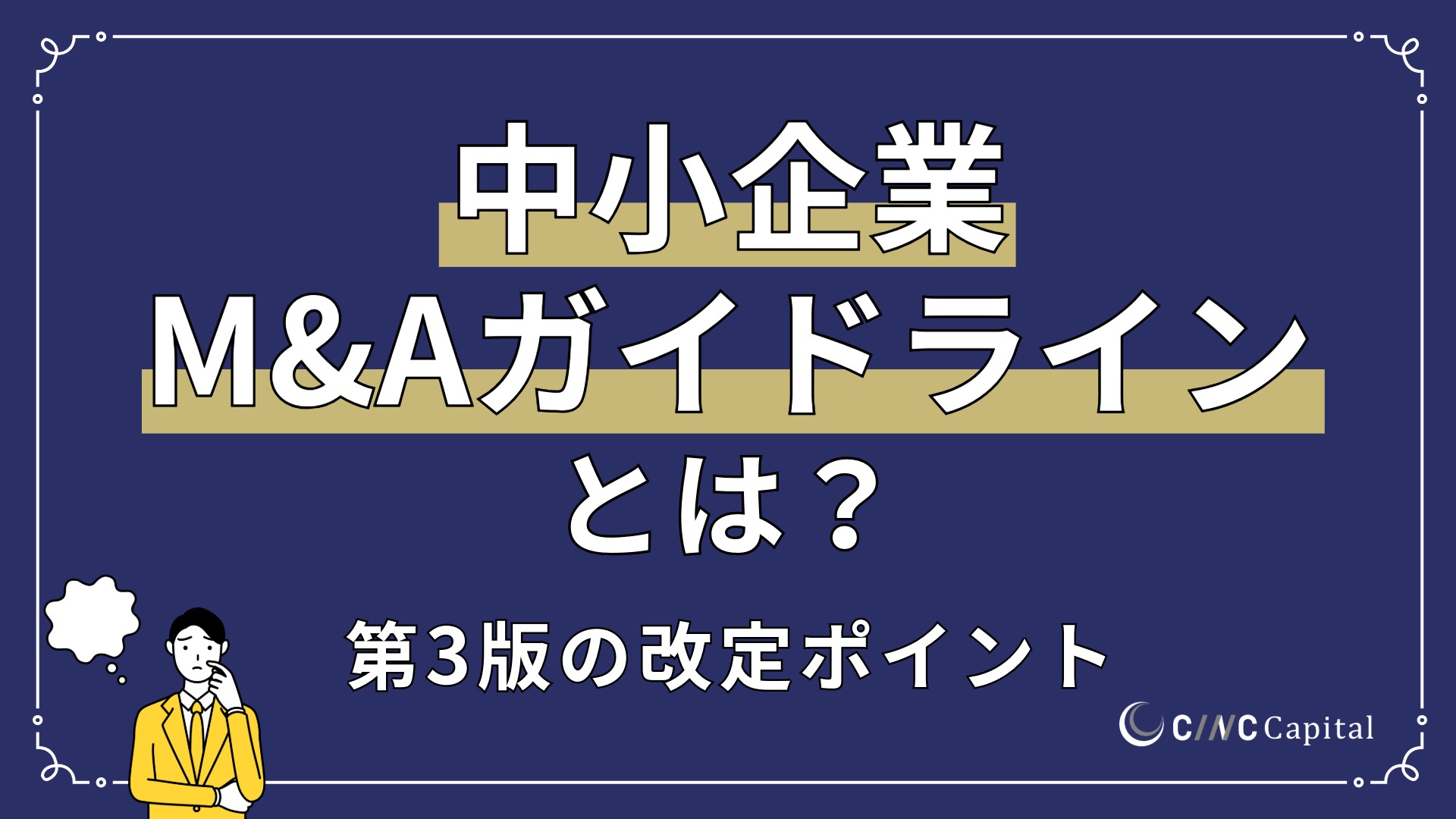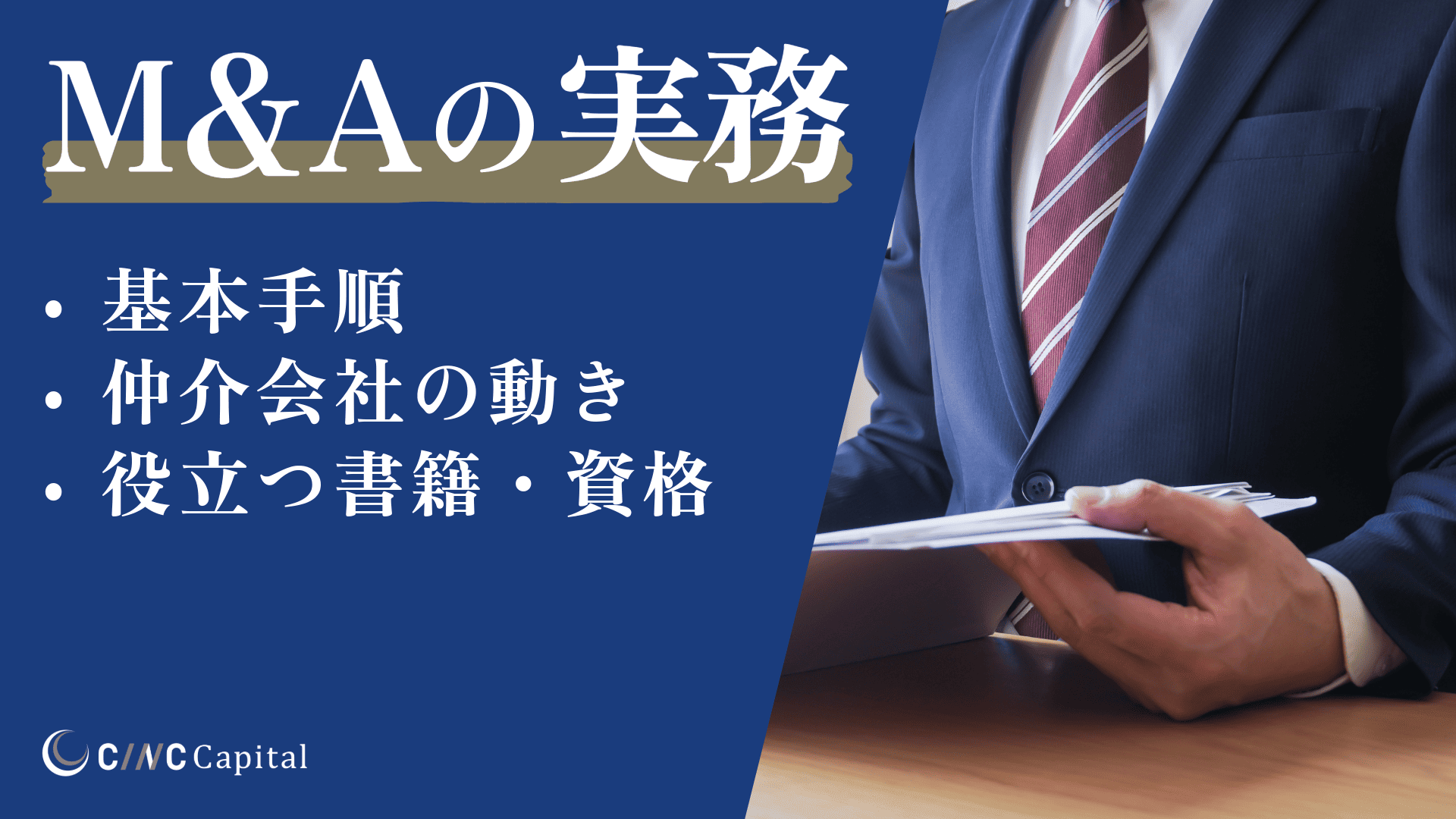CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
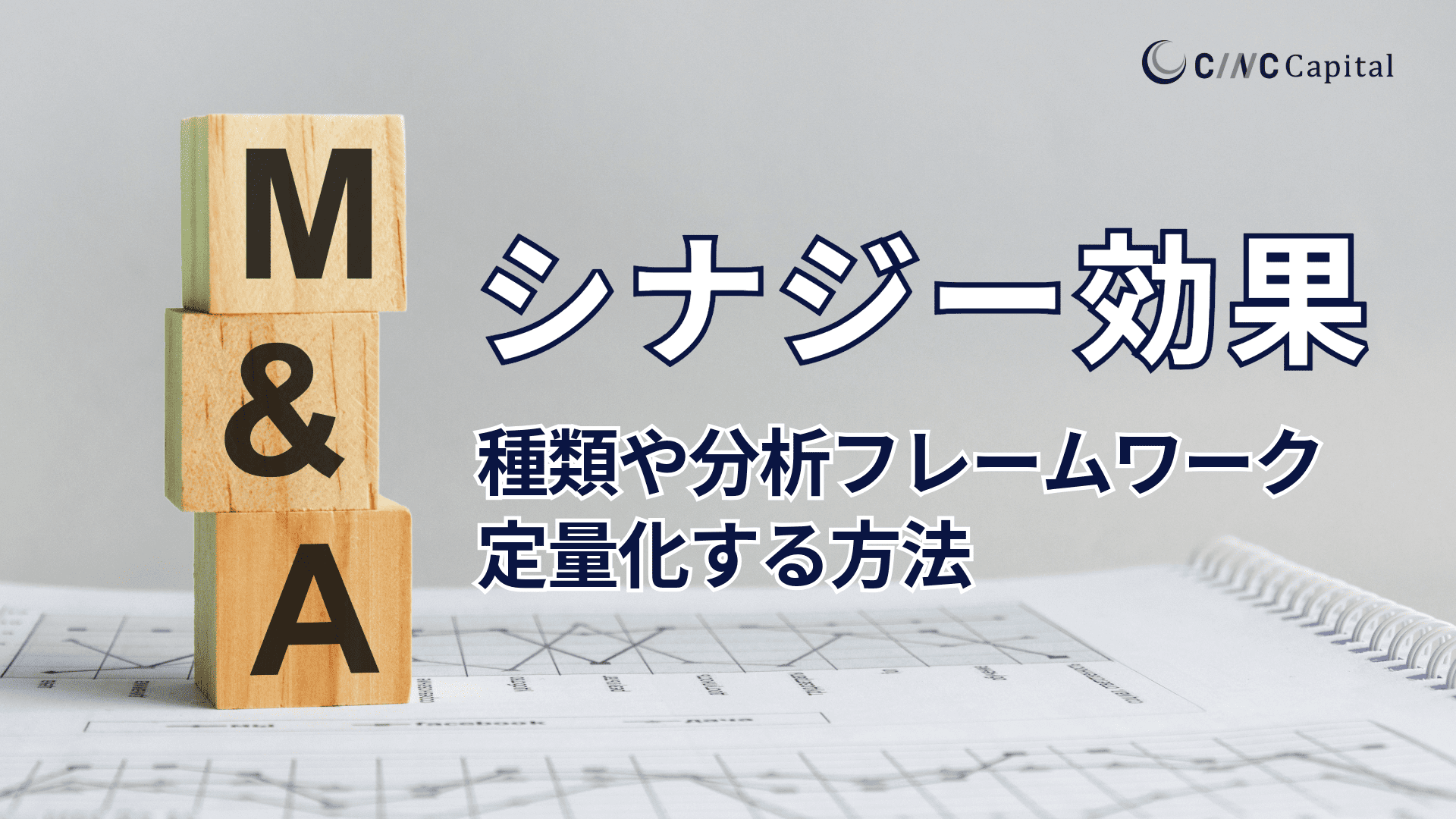
M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.06.26
M&Aのシナジー効果とは?種類や分析フレームワーク、定量化する方法を解説
自社の売却を検討しているが、買い手にとって魅力的な企業と言えるのか不安に感じていませんか?M&Aは単なる事業承継手段ではなく、買い手との間に高いシナジー効果が見込める企業であれば、売却価格や条件が有利になる可能性があります。さらに、売り手自身がシナジー効果を意識した準備を進めることで、自社の企業価値を高めることも可能です。
本記事では、M&Aにおけるシナジー効果の種類や定量的な評価方法、買い手との相性を高めるポイントについて詳しく解説します。
目次
M&Aにおけるシナジー効果とは?
M&Aでは、統合によって生まれるシナジー効果(相乗効果)が重要視されます。シナジー効果とは、複数の企業が統合することで、個別に経営するよりも大きな成果を生み出す現象を指します。具体的には、コスト削減や売上の向上、資金調達力の強化、ブランド価値の向上などです。
シナジー効果が発生することで、企業の競争力が高まり、経営の効率化や市場での影響力強化につながります。ただし、統合が適切に行われなければ、期待した効果が得られず、逆に負のシナジーが生じる可能性もあります。
そのため、M&Aを成功させるためには、シナジーの種類や発生要因を正しく理解し、統合後の計画を適切に立てることが不可欠です。
M&Aにおけるシナジーの種類
M&Aにおけるシナジー効果は、統合によって生まれる相乗効果を指しますが、具体的な種類によって得られるメリットは異なります。
主に「コスト削減」「売上向上」「資金調達力の強化」「経営資源の活用」の4つがあり、統合の形態や目的によってどのシナジーを重視するかが変わります。
一方で、期待に反して統合が企業価値を損なう「負のシナジー」が発生する場合もあります。
ここでは、それぞれのシナジーの特徴と、M&Aの成功にどのように寄与するのかを解説します。
コストシナジー(コスト削減効果)
M&Aにおけるコストシナジーとは、統合によって重複するコストを削減し、経営の効率化を図る効果です。統合により、管理部門の統一、拠点の集約、購買の一元化などが可能になり、経費の削減につながります。
例えば、同業種の企業同士が合併することで、共通するバックオフィス業務(経理・人事・総務など)を一本化し、人件費やオペレーションコストを削減できます。
また、製造業においては、調達先を統合することで仕入れコストを抑え、大量購入によるスケールメリットを享受できます。
ただし、統合の過程で予想外のコストが発生することもあるため、事前に統合コストと削減可能な経費を詳細に試算することが重要です。
収益シナジー(売上向上効果)
収益シナジーとは、M&Aによって売上が拡大し、利益の増加が期待できる効果です。企業統合により、販売チャネルの拡大、製品ラインナップの強化、顧客基盤の共有などが可能になります。
例えば、異なる地域で事業を展開する2社が統合すると、それぞれの顧客層に相手企業の商品を販売できます。また、ブランド力を活かし、新たな顧客獲得や市場開拓を進めることで、売上成長が期待されます。
しかし、事業モデルが異なりすぎる場合、統合後のシナジーが想定通り発揮されない可能性があるため、事前に市場分析を行い、適切な事業戦略を立てることが重要です。
財務シナジー(資金調達・税制メリット)
財務シナジーとは、M&Aによって企業の資金調達力が向上し、財務基盤が強化される効果です。統合後の企業規模が大きくなることで、銀行からの融資条件が改善し、低金利での資金調達が可能になるケースがあります。
また、税制面でもメリットがあります。例えば、被買収企業が繰越欠損金を抱えている場合、統合によって買収企業の利益と相殺することで、税負担を軽減し、キャッシュフローを改善できます。さらに、企業グループとしての法人税の最適化や、内部取引の効率化による財務メリットも期待できます。
ただし、財務シナジーを最大化するためには、M&A前に財務デューデリジェンスを行い、負債やリスクを適切に評価することが重要です。
経営資源シナジー(技術・ブランド・人材の活用)
経営資源シナジーとは、M&Aによって相手企業が持つ技術、ブランド、人材などを活用し、競争力を強化する効果です。特に、技術力の高い企業を買収することで、自社の研究開発力を向上させ、新製品の開発スピードを加速できます。
また、強いブランド力を持つ企業を統合することで、市場での認知度が向上し、新規顧客の獲得につながるケースもあります。さらに、専門知識を持つ人材を獲得することで、事業の専門性を高め、組織の競争力を強化することも可能です。
企業文化の違いが統合後の組織に摩擦を生むことがあるため、事前に統合計画を策定し、適切な組織マネジメントを行うことが求められます。
負のシナジー(期待に反した悪影響)
M&Aにはシナジー効果が期待される一方で、統合後に逆効果となる「負のシナジー」が発生することがあります。これは、企業文化の違い、統合プロセスの遅れ、組織の混乱などによって生じるものです。
例えば、買収先の企業文化が異なる場合、従業員のモチベーション低下や人材の流出が発生し、業績に悪影響を与える可能性があります。また、ブランドイメージが統合によって損なわれることで、顧客の信頼を失い、売上が減少するケースもあります。
負のシナジーを防ぐためには、M&Aの前段階で適切なデューデリジェンスを行い、統合後のリスクを想定しながら計画を立てることが重要です。統合プロセスをスムーズに進めることで、企業価値を最大化できるでしょう。

シナジー効果を定量化する方法
M&Aにおいてシナジー効果を正確に測定することは、成功の可否を判断する上で重要です。シナジー効果がどの程度発現しているのかを数値で示すことで、統合後の事業運営の改善点を明確にし、さらなる成長へとつなげられます。
そのためには、財務指標やKPI(重要業績評価指標)を活用し、M&Aの成果を客観的に評価することが求められます。
以下では、財務指標とKPIをどのように活用し、シナジー効果を測定するかを解説します。
財務指標
シナジー効果を定量的に評価するためには、財務指標の活用が欠かせません。
財務指標は企業の業績や収益性を数値化し、統合の効果を明確にするために活用されます。具体的には、売上高、営業利益、EBITDA(利払い・税引き・償却前利益)、ROE(自己資本利益率)、ROA(総資産利益率)などが挙げられます。
例えば、M&A後に売上高が増加しているかを確認することで、収益シナジーが発現しているかを判断できます。また、営業利益率が向上していれば、コストシナジーによる経費削減が順調に進んでいると考えられます。
さらに、EBITDAの増加は、企業の本業の収益力が強化されていることを示し、統合による競争力向上の指標となります。
ただし、短期間では統合効果が表れにくいため、長期的な視点で財務指標を追跡することが重要です。M&A前後の数値を比較し、実際に期待通りの成果が出ているかを分析することで、統合戦略の改善点を明確にできます。
KPI
KPI(重要業績評価指標)は、財務指標と並んでシナジー効果を測定するために活用されます。KPIは企業の成長や経営目標の達成度を評価するための指標であり、M&A後の成果をより具体的に把握するのに役立ちます。
例えば、コストシナジーを測定する場合、「統合後○年以内に固定費を△%削減」といったKPIを設定することで、コスト削減効果を定量的に管理できます。また、収益シナジーの評価には「新規顧客獲得数」「クロスセルの売上増加率」などのKPIが活用されます。
さらに、財務シナジーに関しては、「資金調達コストの削減率」「キャッシュフローの改善度」といった指標を用いることで、統合後の財務状況を明確にできます。
KPIを設定する際には、具体的かつ測定可能な目標を定めることが重要です。あいまいな指標では、実際にシナジー効果が発揮されているかを適切に判断できません。そのため、達成すべき目標を数値化し、定期的にモニタリングすることで、統合戦略の調整や改善につなげることができます。
シナジー効果を分析するためのフレームワーク
M&Aによるシナジー効果を最大化するためには、統合後の事業展開を適切に分析し、効果的な戦略を立てることが求められます。そのためには、経営戦略で用いられるフレームワークを活用し、シナジーの発現を体系的に評価することが重要です。
主に用いられるフレームワークには、「アンゾフの成長マトリックス」「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」「バリューチェーン分類のフレームワーク」があります。
これらを活用することで、M&Aの目的に応じた成長戦略や事業の最適化を進められるでしょう。
アンゾフの成長マトリックス
アンゾフの成長マトリックスは、企業の成長戦略を「市場」と「製品」の2つの軸で分析し、適切な戦略を決定するためのフレームワークです。M&Aにおいては、買収する企業がどの成長戦略を目指しているのかを整理し、統合後の戦略を明確にするために活用されます。
このマトリックスでは、成長戦略を「市場浸透」「新市場開拓」「新製品開発」「多角化」の4つに分類します。
例えば、市場浸透戦略を狙うM&Aでは、競合企業を買収して市場シェアを拡大することが目的となります。一方、多角化戦略では、異業種の企業を買収し、新たな市場や事業領域へ進出することが目的となります。
M&Aを成功させるためには、どの戦略が自社にとって最適かを見極めることが不可欠です。成長マトリックスを活用することで、シナジー効果が最大限発揮される方向性を明確にし、統合後の戦略を合理的に設計できます。
PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)
PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、企業が持つ事業や製品を「市場成長率」と「市場シェア」の2軸で分類し、資源配分を最適化するためのフレームワークです。
M&Aにおいては、統合後の事業ポートフォリオを整理し、どの分野に経営資源を重点的に投入すべきかを判断する際に活用されます。
PPMでは、事業を「花形(成長率・シェアともに高い)」「金のなる木(成長率は低いがシェアが高い)」「問題児(成長率は高いがシェアが低い)」「負け犬(成長率・シェアともに低い)」の4つに分類します。
例えば、買収した企業の事業が「問題児」に該当する場合、積極的な投資によって市場シェアを拡大させるべきか、それとも撤退すべきかの判断が求められます。
PPMを活用することで、統合後の事業戦略をデータに基づいて決定でき、経営リソースを効率的に配分することが可能になります。
バリューチェーン分類のフレームワーク
バリューチェーン分類のフレームワークは、企業の事業活動を「主活動」と「支援活動」に分け、それぞれの段階で付加価値を生み出せるかを分析する手法です。M&Aでは、統合後にどの業務プロセスでシナジーを発揮できるかを判断する際に活用されます。
具体的には、主活動として「購買」「製造」「物流」「販売」「サービス」があり、支援活動として「経営管理」「人事」「技術開発」「調達」などがあります。
例えば、製造業のM&Aでは、製造プロセスの統合によるコスト削減や、販売ネットワークの共有による売上向上が期待できます。また、技術開発の統合により、新商品の開発スピードを向上させることも可能です。
バリューチェーン分析を用いることで、統合後の事業運営の最適化が可能になります。シナジー効果を最大化するためには、どの活動が統合のメリットを生むのかを明確にし、重点的に強化することが重要です。
M&Aでシナジー効果を発揮するためのポイント
M&Aを成功させるためには、統合後にシナジー効果を最大限に発揮できる企業を選定し、適切な統合戦略を立てることが重要です。単に規模を拡大するだけではなく、技術やブランド、統合のタイミングを慎重に見極めることで、シナジー効果を高められます。
特に、技術の相性が良い企業を選ぶこと、市場での影響力を持つブランドを活用すること、最適なタイミングでM&Aを実施することの3つが、統合の成功を左右する要素となります。
以下では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
技術の相性が良い企業を選び競争力を高める
M&Aでは、統合後の競争力を向上させるために、技術の相性が良い企業を選ぶことが不可欠です。技術力が補完し合える企業同士が統合すれば、新製品開発や業務効率化が進み、競争優位性を確立できます。
例えば、ソフトウェア開発企業がハードウェアメーカーを買収するケースでは、ソフトとハードの統合によって、一貫した製品開発が可能になります。また、医薬品企業がバイオテクノロジー企業を買収すれば、革新的な治療法を開発できる可能性が高まります。
ただし、技術の融合がうまくいかなければ、開発プロセスの遅れや品質の低下が発生するリスクがあります。そのため、統合前に技術の相性を綿密に分析し、開発チームの統合計画を明確にしておくことが重要です。
ブランド力のある企業を選び市場での影響力を拡大する
M&Aにおいては、ブランド力のある企業を買収することで、市場での影響力を強化できるというメリットがあります。特に、顧客からの認知度が高く、信頼されているブランドを統合することで、競争優位性を確立しやすくなります。
例えば、外資系の高級ブランドが国内の販売網を持つ企業を買収することで、新たな市場への参入がスムーズに進みます。また、大手食品メーカーが地域密着型のブランドを統合すれば、消費者のロイヤルティを維持しつつ、全国規模での販売展開が可能になります。
しかし、ブランド統合の過程で既存顧客の信頼を損なうリスクもあります。特に、ブランドイメージが異なる企業を無計画に統合すると、既存のブランド価値が低下する可能性があります。そのため、ブランド戦略を明確にし、消費者の認識を適切に管理することが求められます。
M&Aを行う適切なタイミングを見極め成功確率を高める
M&Aを成功させるためには、実施のタイミングを見極めることが重要です。市場環境や企業の成長段階を考慮し、適切な時期に統合を行うことで、シナジー効果を最大化できます。
例えば、経済が低迷している時期に成長企業を買収することで、将来的に大きなリターンを得ることが期待できます。
一方で、市場が成熟し競争が激化しているタイミングでのM&Aは、統合後の成長が見込めないリスクを伴います。また、企業内部の準備が整っていない段階でM&Aを実施すると、統合プロセスが混乱し、シナジー効果が発揮されにくくなります。そのため、デューデリジェンス(企業の詳細な調査)を十分に行い、M&A後の統合計画を綿密に策定することが不可欠です。
まとめ|シナジーを見極め、M&Aのタイミングを見極めましょう
M&Aにおけるシナジー効果は、統合によって企業の成長を加速させ、競争力を強化する重要な要素です。コスト削減や売上向上、財務面の強化、経営資源の活用など、適切な戦略を立てることでシナジーを最大限に活かせます。
一方で、統合が適切に進まなければ負のシナジーが生じ、期待した成果が得られない可能性もあります。
シナジー効果を確実に発揮するためには、定量的な評価指標を活用し、事業の方向性を分析するフレームワークを活かすことが重要です。さらに、技術の相性やブランドの影響力を見極め、最適なタイミングでM&Aを実行することで、統合の成功率を高められます。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。