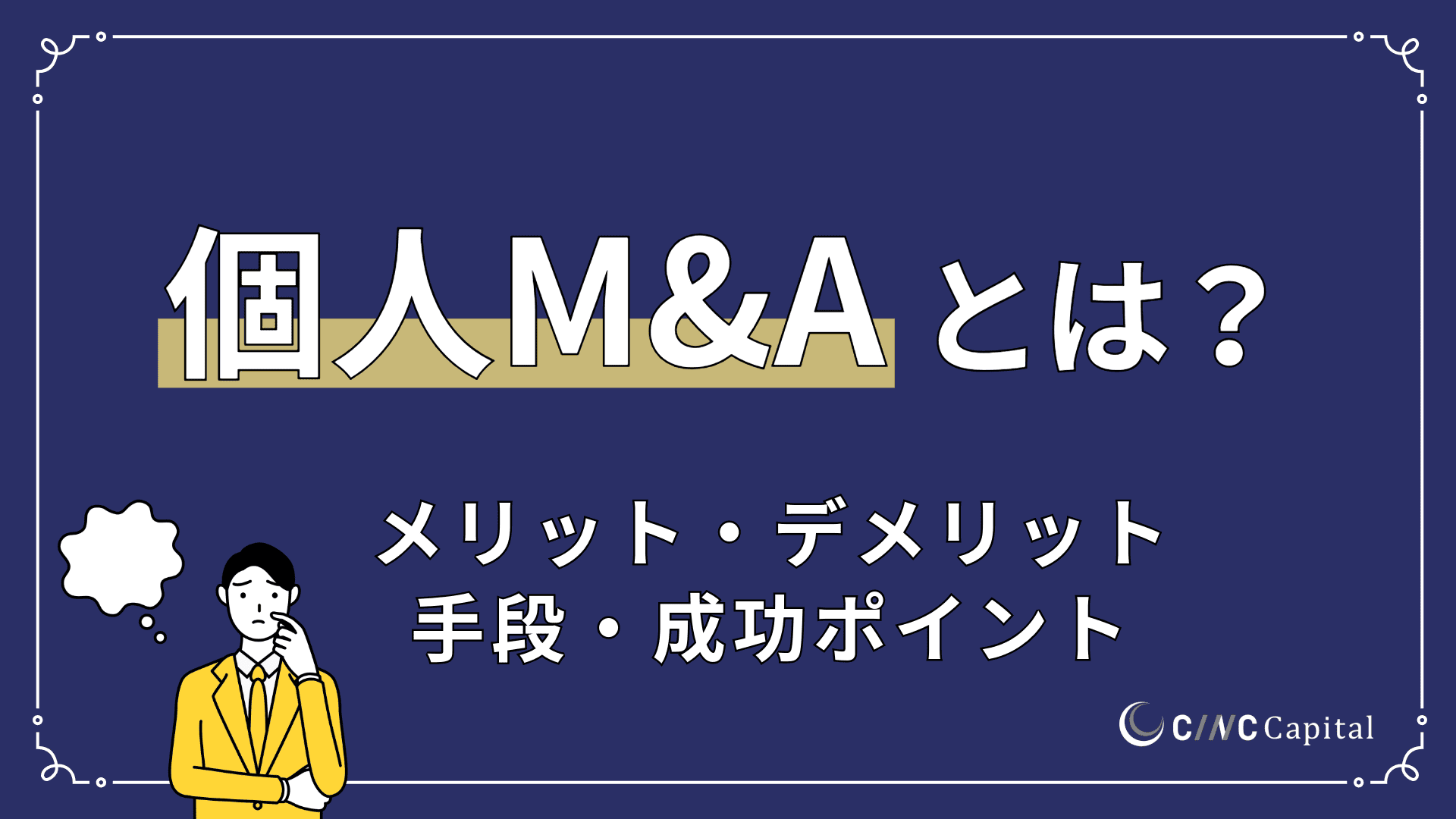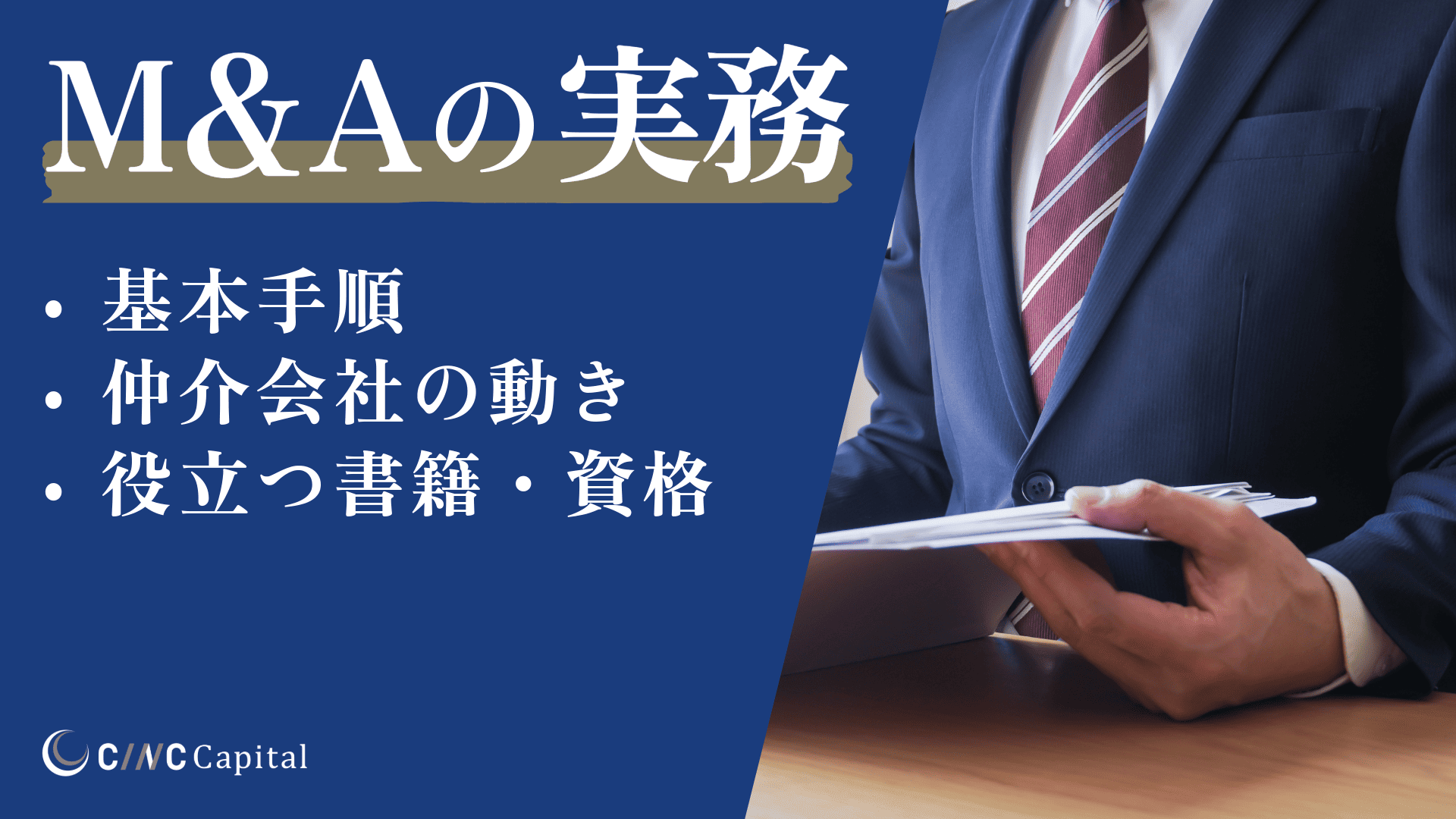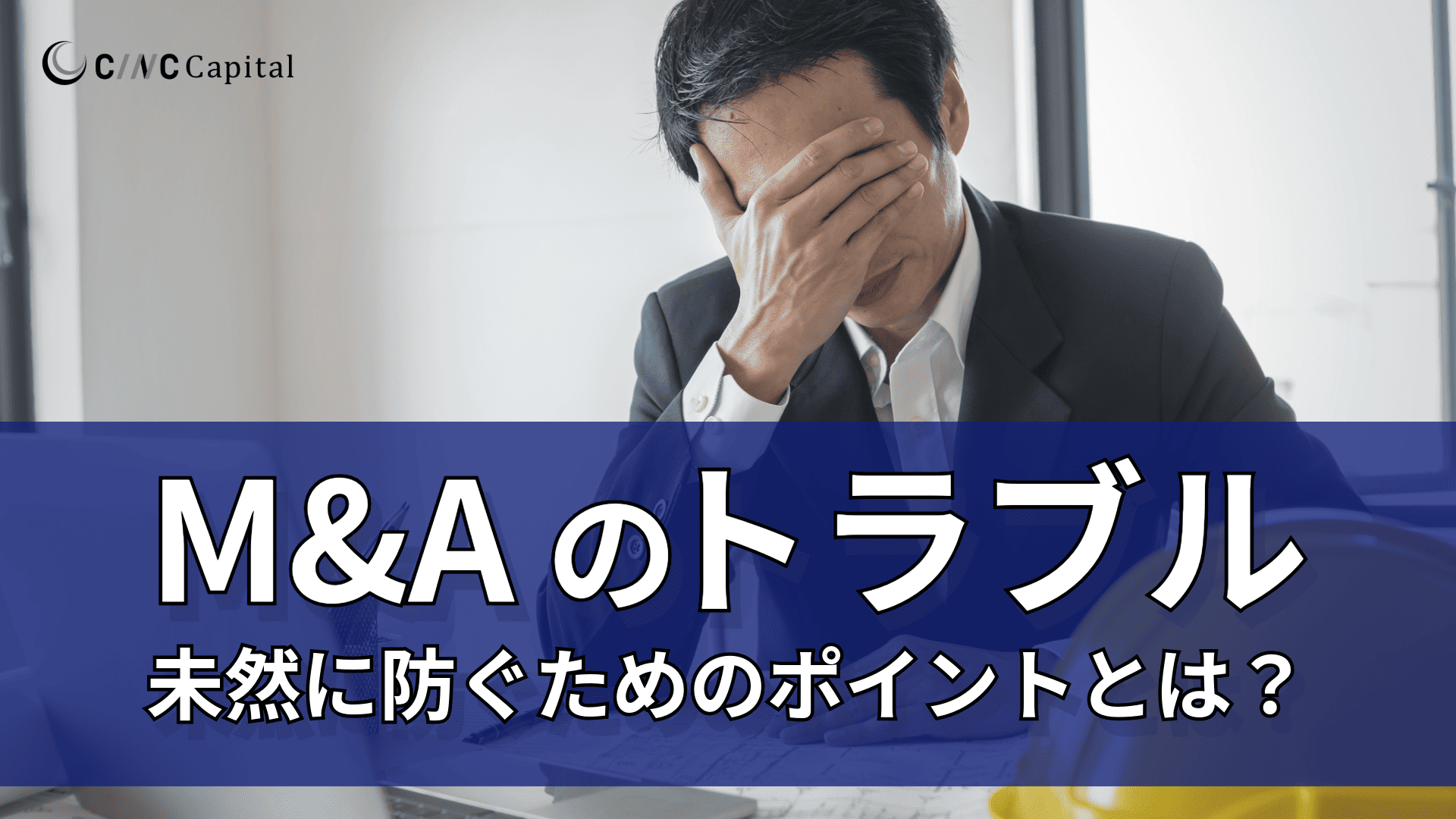CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
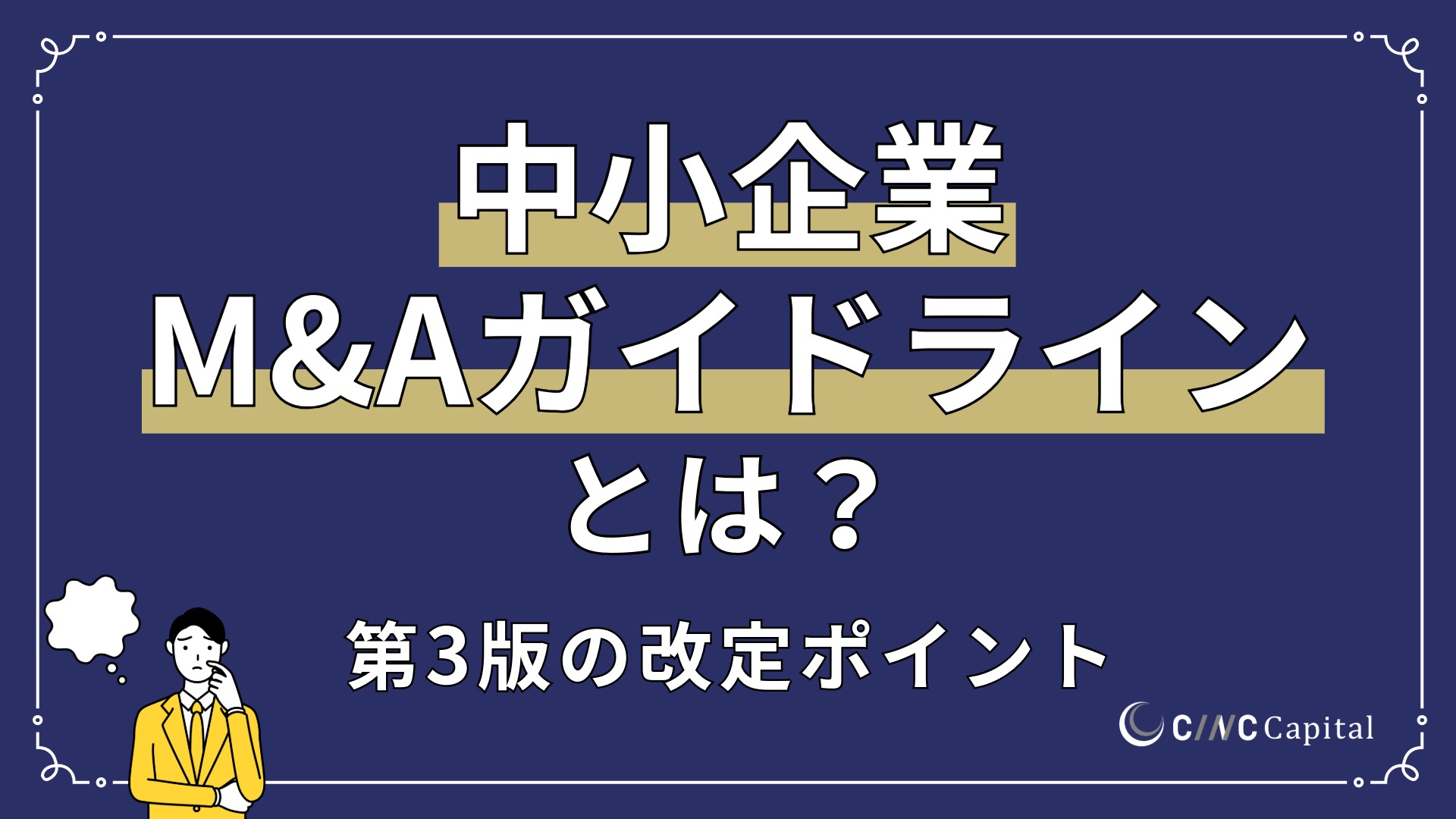
M&A / 基礎知識
- 公開日2025.09.29
中小企業M&Aガイドラインとは?概要や第3版の改訂のポイントを解説
事業承継やM&Aに関して、どのように進めればよいかお悩みではありませんか?
特に、信頼できる支援機関の選定や手数料の透明性、契約内容の理解など、不安を感じるポイントは多岐にわたります。
本記事では、2024年8月に改訂された「中小企業M&Aガイドライン(第3版)」の要点をわかりやすく解説します。
目次
中小企業M&Aガイドライン(第3版)とは?
中小企業M&Aガイドライン(第3版)は、後継者不在などの課題を抱える中小企業が、安心してM&Aを進められるように整備された指針です。
策定主体は経済産業省および中小企業庁であり、企業の円滑な事業承継を支援するために設けられています。
初版は2020年に公表され、その後、M&Aの実務における環境変化や具体的なトラブル事例の発生を踏まえて見直しが行われ、2024年8月に第3版が公表されました。
今回の改訂では、最新の課題に対応しつつ、取引の透明性と公正性を一層高めることが重視されています。
このガイドラインには法的拘束力はありませんが、中小企業庁が運営する「M&A支援機関登録制度」に登録している支援機関には遵守が求められています。
業界の自主規制としての役割を果たしており、違反が確認された場合には、登録の取り消しなどの措置が取られる可能性があります。
また、M&Aに関する補助金の受給要件として、登録支援機関の利用が必要となる場合もあります。
中小企業M&Aガイドラインの改訂の趣旨
中小企業M&Aガイドライン(第3版)の改訂は、近年顕在化した複数の課題に対応するために行われました。
具体的には、不適切な譲り受け側の存在、経営者保証に関するトラブル、M&A専門業者の過剰な営業・広告などの問題が挙げられます。
本章では、4つのポイントについて解説していきます。
不適切な譲り受け側の存在
中小企業のM&Aにおいて、譲り受け側が最終契約を履行しない、または意図的に不履行を生じさせるケースが報告されています。
例えば、譲り渡し側の経営者保証を譲り受け側に移行させる想定であったにもかかわらず、移行しないといった行為です。
これに対処するため、仲介者・FA(売り手または買い手の片方のみを支援する専門家)には、譲り受け側の財務状況や事業実態、コンプライアンス面の調査を実施し、譲り渡し側に対して調査結果を説明することが求められています。
このような取り組みにより、不適切な譲り受け側を市場から排除し、M&Aの健全性を確保することが期待されています。
経営者保証に関するトラブル
M&A後も譲り渡し側の経営者保証が解除されず、元経営者に負担が残るトラブルが発生しています。
この問題への対応として、ガイドラインでは、仲介者やFAが譲り渡し側の経営者と話し合い、経営者保証を解除するか、譲り受け側に引き継ぐかをあらかじめ決めておくよう求めています。
また、必要に応じて、士業等専門家や金融機関等への相談も推奨されています。
M&A専門業者に関する課題
M&A専門業者の中には、過剰な営業・広告を行い、依頼者に対して不適切な勧誘を行うケースが少なくありません。
これに対応するため、ガイドラインでは、仲介者・FAに対して、広告・営業先が希望しない場合の広告・営業の停止等を求めています。
また、手数料や業務内容、担当者の資格や実績の説明が求められており、支援の質が保たれる仕組みになっています。
健全な環境整備と支援の質の向上
中小M&A市場をより健全なものにし、支援機関のサポートの質を高めるために、ガイドラインでは中小企業向けの説明や、仲介者・FAが注意すべきポイントを充実させています。
これにより、中小企業が安心してM&Aを進めやすくなり、スムーズな取引が進むことが期待されているのです。
中小企業M&Aガイドラインの改訂の主なポイント
中小企業M&Aガイドライン(第3版)では、M&A支援の質と透明性を高めるため、7つの主要項目が改訂されました。
これらの改訂は、仲介者・FA(フィナンシャル・アドバイザー)およびM&Aプラットフォーマーが遵守すべき具体的な行動規範として明示されています。
本章では各項目の要点を説明します。
仲介・FAの手数料・提供業務に関する事項
M&Aを進めるにあたり、仲介者やFAが提供する業務や報酬が不明確な場合、依頼者は不安を感じます。
ガイドライン第3版では、契約前に手数料の内訳や支援内容を具体的に説明することが求められています。
特に、M&Aの各ステップでどのような業務が行われるのか、担当者の資格や経験、過去の成約件数まで含めて説明する必要があります。
また、売り手と買い手の双方から報酬を受け取る「両手仲介」は、利害の調整を一社が担えるため交渉が進みやすく、双方の立場を理解したうえで中立的な支援を行える点がメリットです。ただし、双方から報酬を得る関係上、利益相反の可能性については注意が必要です。
これに対し、「片手仲介(FA)」は一方の依頼者にのみアドバイスするため、利害調整には時間がかかるものの、依頼者の利益に沿った支援が期待できます。
こうした仲介形式の違いとそれぞれの特徴を依頼者が理解し、手数料や業務内容とあわせて事前に確認できることが、納得のいく契約や支援の信頼性向上につながります。
広告・営業の禁止事項の明記
M&Aを検討していない企業に対しても、過剰な広告や執拗な営業を仕掛ける業者が一部存在します。
こうした迷惑行為を防ぐため、ガイドラインでは営業先が望まない旨を示した場合、即座に営業活動を中止し、社内で共有・記録することが定められました。
営業再開には慎重な検討と組織的な判断が必要とされています。
利益相反に係る禁止事項の具体化
仲介者が売り手と買い手の双方から依頼を受ける「両手仲介」の場合、特定の依頼者に肩入れすることで取引の公正さが損なわれるリスクがあります。
第3版では、そうした利益相反行為に対し、具体的な禁止事項が設けられました。
例えば、買い手から追加報酬を受け取って優遇する行為や、取引実績の多い顧客を優先する行為などが明確に否定されています。
このようなルールの明文化によって、中立・公平な立場での支援が強化されました。
ネームクリア・テール条項に関する規律
M&Aの初期段階では、売り手企業の社名を買い手候補に開示する「ネームクリア」が行われますが、これには慎重な対応が求められます。
ガイドラインでは、売り手の同意なしに情報を開示することを禁止し、秘密保持契約の締結も推奨しています。
また、テール条項(仲介契約終了後一定期間内に成約した場合の報酬請求権)については、報酬請求の対象を限定する方針が示され、仲介者が契約終了後も広範に成功報酬を請求するような不当な取引を防ぐ仕組みとなっています。
最終契約後の当事者間のリスク事項について
M&Aは契約書に署名した瞬間がゴールではなく、むしろその後に発生するリスクの管理が重要です。
ガイドライン第3版では、最終契約前の段階で、クロージング(M&A取引の最終的な実行・完了のこと)後に起こり得るトラブルについて丁寧に説明することが義務づけられました。
代表的な例としては、隠れた負債の発覚や引継ぎミス、未解決の債権債務などがあります。
これらを契約前に整理し、リスクとして共有しておくことで、M&A後のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
譲り渡し側の経営者保証の扱いについて
中小企業では、経営者個人が会社の借入金に保証をつけていることが珍しくありません。
そのため、M&A後も経営者保証が残り続けることが大きな問題になります。
第3版ではこのリスクに対応し、M&A支援者が事前に売り手と協議し、保証の解除または買い手への引継ぎを明確に取り決めるよう求めています。
さらに、必要に応じて専門家や金融機関と連携し、契約書にも保証の取り扱いを明記することが推奨されています。
不適切な事業者の排除について
中小企業のM&A市場では、買収後に企業資産を不正に流用したり、経営放棄により会社を破綻させたりするような不適切な買い手が問題になっています。
ガイドラインでは、このような事業者の排除を目的に、仲介者やFAに対して買い手の信用調査を行い、その結果を売り手に説明する義務を定めました。
また、不適切と判断した場合はマッチング自体を控えることや、業界内での情報共有体制の整備も推奨されています。
こうした取り組みによって、安心してM&Aを進められる市場環境が育まれます。
まとめ|中小企業M&Aガイドライン第3版の意義と活用
中小企業M&Aガイドライン第3版は、信頼できるM&Aの実現に不可欠なルールを具体化した指針です。
手数料体系や契約内容の明示、支援機関の行動規範の徹底により、これまで不透明だった部分が大きく改善されました。
加えて、不適切な事業者への対応や経営者保証の取り扱いも明確化され、中小企業がより安心してM&Aに臨める環境が整いつつあります。
ガイドラインを正しく理解し活用することで、公正かつ持続的な事業承継が社会全体に広がっていくことが期待されています。