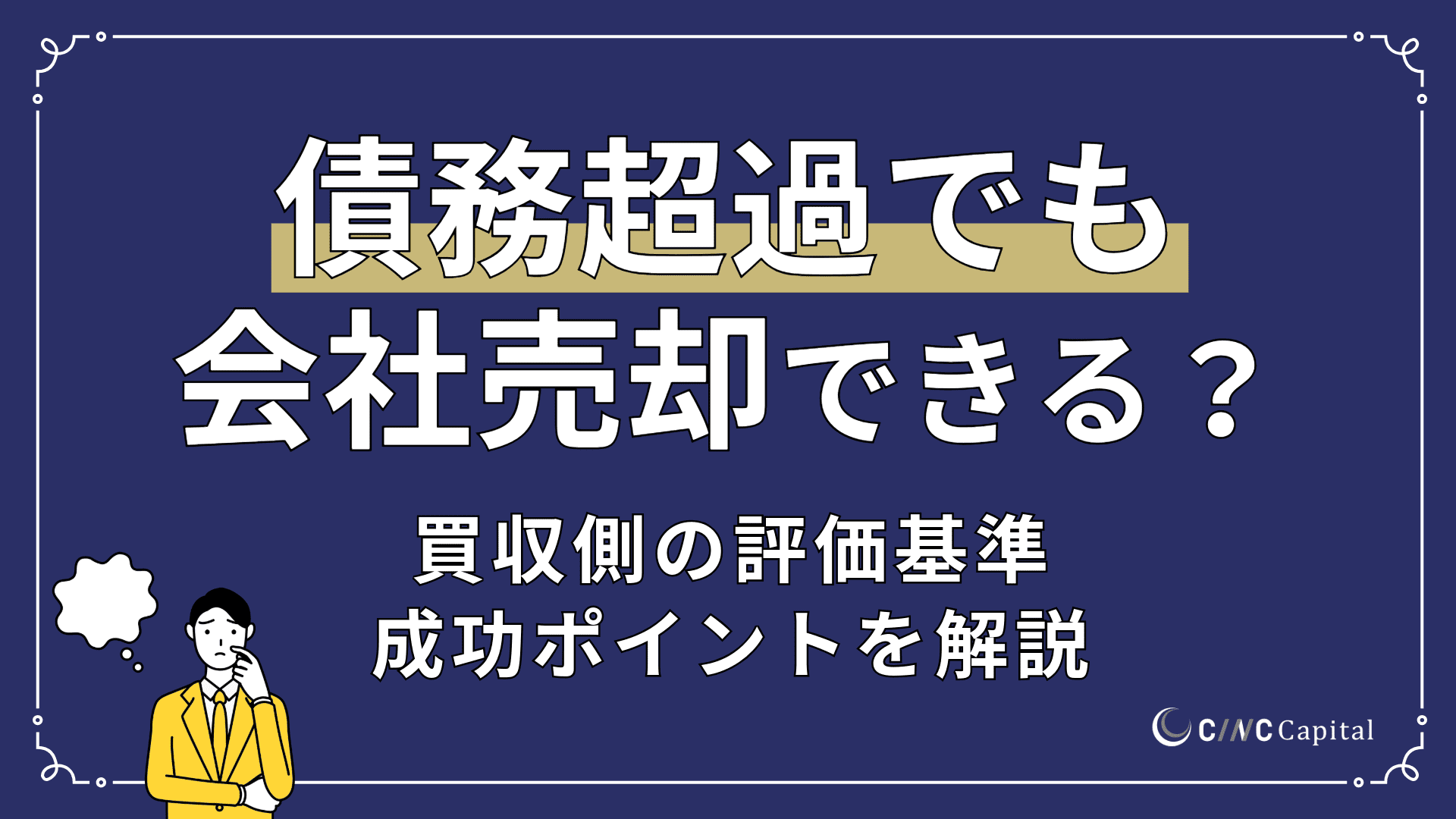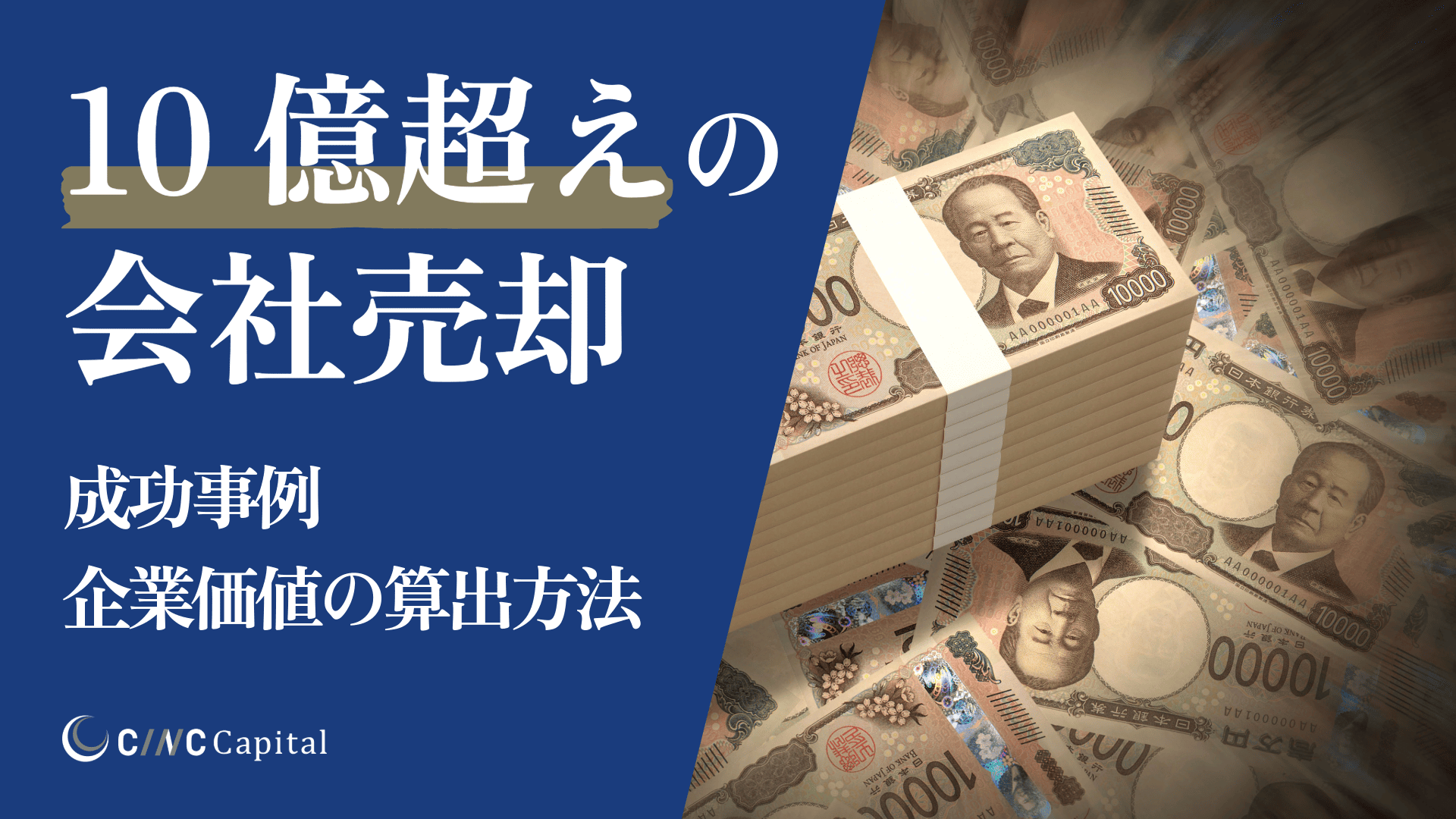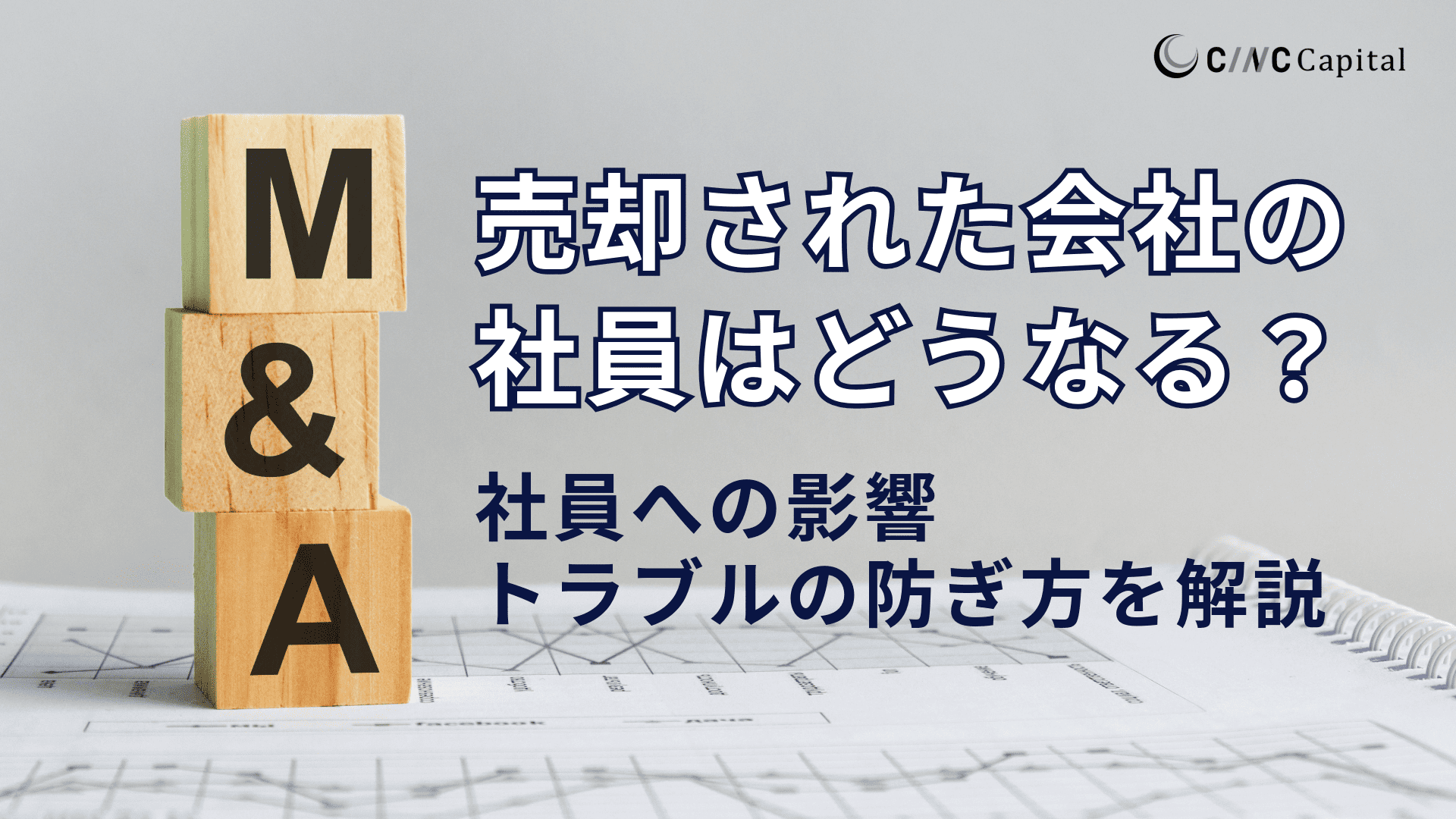CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
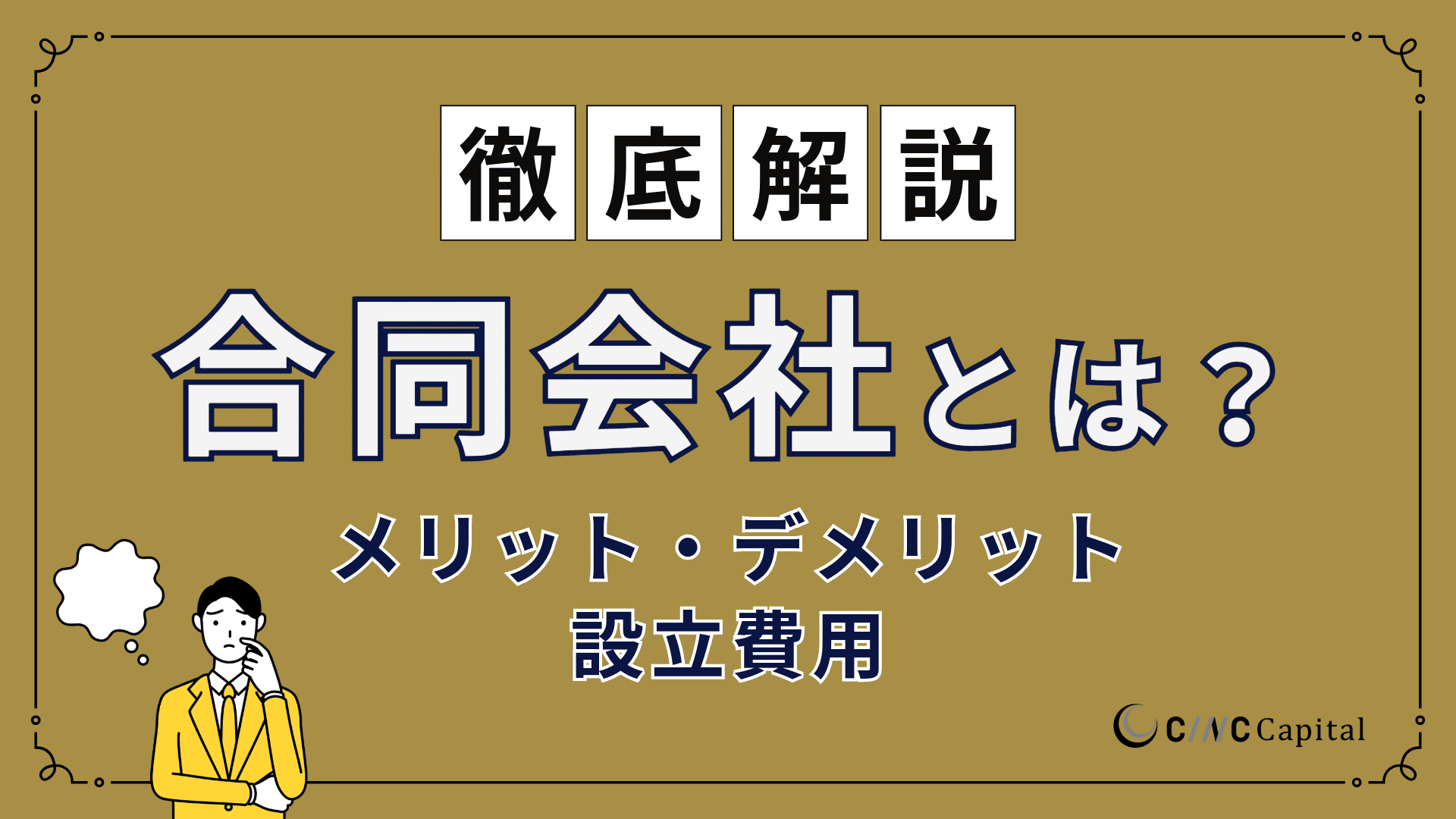
売却 / 会社売却
- 最終更新日2025.06.26
合同会社とは?設立のメリットデメリット、設立費用、株式会社との違いをわかりやすく解説
「設立費用を抑えたいけど、信用されないって本当?」「将来後悔しないためにはどうしたらいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。株式会社との違いや、設立費用のこと、評判が良くない理由など、気になる点がたくさんあると思います。
本記事では、株式会社や個人事業主との違い、メリット・デメリット、設立費用や手続きの流れまでを解説します。
目次
合同会社とは?
合同会社は、2006年の会社法改正により創設された法人形態で、出資者が経営に関与できる仕組みを採用しています。定款で業務執行権限を限定することも可能です。株式会社と異なり、会社の意思決定をスピーディーに行える点から、近年多くの起業家に選ばれています。略称は「合同」または「LLC(Limited Liability Company)」です。
本章では、合同会社と他の会社形態との違いについて詳しく説明します。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の最大の違いは、出資者と経営者の関係にあります。合同会社では出資者がそのまま経営者となるため、意思決定が早く、運営がシンプルです。一方、株式会社は株主と経営者が分離されており、経営の透明性は高いものの、意思決定には株主総会などの手続きが必要です。
M&Aの観点からも両者には大きな違いがあります。株式会社は株式の譲渡が容易であり、将来的な会社売却や事業承継の選択肢が広がります。また、株式を細分化して移転することも可能です。一方、合同会社は持分の譲渡に社員全員の同意が必要であり、M&Aの際に手続きが複雑になる傾向があります。
そのため、将来的な企業売却や事業拡大を視野に入れている場合は株式会社、小規模ビジネスの維持や運営コストの削減を重視する場合は合同会社が向いているでしょう。
合同会社と個人事業主との違い
合同会社と個人事業主の違いは、責任の範囲と信用力にあります。個人事業主は事業に関する全責任を無限に負いますが、合同会社の出資者は有限責任のため、出資額を超えるリスクを負いません。
加えて、法人格を持つことで取引先や金融機関からの信頼も得やすくなります。節税面でも、法人ならではの経費計上や欠損金繰越が可能となり、税負担の最適化が図れます。
合同会社のメリット
合同会社には、他の法人形態にはない多くのメリットがあります。特に、設立費用の安さや経営の柔軟性、利益配分の自由度などは、スモールスタートの起業や少人数でのビジネスにおいて大きな強みとなります。
本章では、合同会社が選ばれる理由を代表的な6つのポイントに分けて解説します。
設立費用が安い
合同会社は、株式会社と比べて設立時の費用が圧倒的に安く済みます。株式会社を設立する際には定款認証に約5万円、登録免許税に15万円かかりますが、合同会社なら定款認証が不要で、登録免許税も6万円で済みます。初期コストを抑えて起業したい方にとって、大きなメリットとなります。
経営の自由度が高い
合同会社は、出資者自身が経営に携わる仕組みのため、意思決定が非常にスピーディーに行えます。株式会社では取締役会や株主総会などの手続きが必要ですが、合同会社では出資者間の合意だけで重要な方針を決められます。外部の意見に左右されずに経営したい人に適してるでしょう。
利益配分の柔軟性がある
合同会社では、定款の定めにより、出資比率にかかわらず利益配分のルールを自由に設定することができます。株式会社では出資額に応じた配当が基本ですが、合同会社は定款で貢献度などを反映した分配比率を定められます。これにより、人的貢献の大きなメンバーにも正当な報酬を配分できる仕組みが整うのです。
決算公告の義務がない
合同会社は、法律上の決算公告義務が課されていません。ただし、金融機関などから決算書の提出を求められるケースはあります。株式会社は毎期、官報などで財務情報を公開する必要がありますが、合同会社はその手間も費用も不要です。これにより、運営コストが下がり、プライバシーを保った経営が実現します。
代表の肩書を自由に決められる
合同会社では、法律上「代表社員」として登記されますが、社外に向けた肩書は一定の範囲で柔軟に設定できます。たとえば、「CEO」や「代表」など、株式会社でよく使われる呼称を名乗ることも可能です。この柔軟性により、取引先や顧客に対して信頼感や安心感を与える表現を選べます。
しかし、「代表取締役」は株式会社のみに認められる法的役職であり、使用は誤認を避けるため慎重に判断しなければなりません。いずれにしろ、登記と異なる肩書を使用する場合には、誤解を生まないよう社内外での説明を工夫する必要があります。適切な肩書を活用することで、ブランドイメージの向上にもつながるでしょう。
税制上のメリットがある
合同会社は法人として課税されるため、個人事業主よりも節税の選択肢が豊富にあります。たとえば、赤字の繰越期間が最長10年となり、役員報酬を経費にできる点も大きな利点です。
一定の利益が出ている事業なら、法人化することで税負担を軽減できる可能性があります。
合同会社のデメリット
合同会社は柔軟な運営が可能で、設立コストも低いことから注目されていますが、メリットだけではありません。実際に設立・運営していく中で、不都合やリスクにつながるデメリットもいくつか存在します。
本章では、合同会社にありがちな6つの注意点を解説します。
社会的信用が低い
合同会社は、株式会社に比べて社会的信用が劣ると言われています。これは、株式会社という会社形態が一般的であり、合同会社の認知度がまだ十分に浸透していないことが理由です。
たとえば、取引先との初対面時や、融資を検討する銀行などから「合同会社って大丈夫なのか」と懸念されるケースも見受けられます。特に対外的な信用を重視する業種では、会社形態が与える印象は大きな影響を及ぼすでしょう。
社会的な安心感を得にくいという側面がある以上、事前に合同会社の制度について丁寧に説明できる準備をしておくことが求められます。
資金調達が難しい
合同会社は株式を発行できないため、出資による資金調達手段が限られています。
株式会社であれば、新株発行によるエクイティファイナンスやベンチャーキャピタルによる出資が可能ですが、合同会社ではそのような方法が取れません。特にスタートアップ企業において重要となるのが、将来的な資金調達の選択肢の広さです。株式会社では第三者割当増資やストックオプションなど多様な手段が活用できますが、合同会社ではこれらの手段が制限されます。
また、M&Aによる出口戦略(Exit)の観点からも、合同会社は不利な面があります。ベンチャーキャピタルや投資ファンドは通常、将来的な株式上場(IPO)やM&Aによる売却を想定して投資を行いますが、合同会社はこうした投資家の要望に応えにくい形態です。
事業拡大や企業価値向上を目指す企業にとっては、資金調達の制約は大きな障壁となる可能性があります。
代表者の個人保証を求められることが多い
合同会社は有限責任制を採用しており、会社が負う債務について出資者個人の財産が責任を負うことは原則ありません。実務上、金融機関から融資を受ける際に代表者個人の連帯保証が求められることがあります。保証の有無は金融機関や融資条件によって異なります。
つまり、会社が返済できなくなった場合、個人資産で返済を求められる可能性があります。これにより、せっかくの有限責任の仕組みが実質的に機能しなくなる恐れがあります。特に創業期は信用実績が乏しいため、保証を免れるのは難しいのが現状です。融資を検討している場合は、個人の信用や資産状況も考慮に入れる必要があります。
株式発行ができない
合同会社では株式の発行ができないため、株主を募る形での出資やストックオプションによる人材確保といった資本政策の選択肢に制約があります。M&Aや事業承継の観点からも、この点は大きなハンディキャップとなります。
株式会社では株式の部分的な譲渡により段階的な事業承継が可能ですが、合同会社の持分は原則として社員全員の同意がなければ譲渡できません。そのため、例えば後継者に少しずつ経営権を移していくといった柔軟な承継プランを立てにくくなります。
また、会社を売却する際にも、買い手はより手続きが簡便で制度として確立された株式会社を好む傾向があります。実際のM&A市場では、合同会社より株式会社の方が売却しやすく、場合によってはより高い評価を受けることもあります。
特に上場やファンドからの投資を視野に入れるなら、最初から株式会社として設立するか、早い段階で組織変更することを検討すべきでしょう。
企業イメージが弱い
合同会社という社名は、株式会社と比べて一般的な認知度が低いため、企業規模や信頼性に対して誤った印象を与えてしまう可能性があります。特に消費者を相手にするBtoCビジネスでは、会社の名称がブランドイメージに直結する場面も少なくありません。
「○○株式会社」という名称のほうが信頼感があるという意見も根強く、合同会社というだけで不安に思われることもあるのが実情です。もちろん、会社の実態や提供価値が優れていれば形態にかかわらず評価されますが、第一印象を左右する以上、見せ方には工夫が求められます。
ロゴデザインや事業紹介の伝え方など、外部との接点で不利にならないよう補完策を講じることが重要です。
解散時の手続きが複雑になる
合同会社は設立しやすい反面、解散や出資者の脱退といった局面では煩雑な手続きが発生します。
たとえば、持分の譲渡には原則として社員全員の同意が必要であり、1人でも反対すれば手続きが進まなくなります。M&Aの観点からこれは非常に重要な問題です。
企業買収や事業譲渡の際、合同会社では出資者間での意見の不一致が取引自体を頓挫させるリスクがあります。特に複数の出資者がいる場合、全員の同意を得ることは時として困難を極めます。
また、持分の評価方法も株式会社に比べて確立されておらず、適正な譲渡価格の算定が難しいという課題もあります。M&Aにおける企業評価は通常、マルチプル法やDCF法などによって行われますが、合同会社の持分に対してはこれらの手法が適用しにくく、買い手側が評価に慎重になる傾向があります。
このような理由から、将来的なM&Aや事業承継を視野に入れている場合は、定款で持分譲渡に関する独自のルールを設けるか、株式会社への組織変更を検討すべきでしょう。
合同会社の設立費用
合同会社は、低コストで設立できる法人形態として知られています。株式会社の設立費用と比較しても半額以下で済むケースが多く、起業初期の資金負担を抑えられるのが大きなメリットです。
登録免許税は最低6万円で、定款の認証も不要なため、公証役場にかかる費用も発生しません。また、電子定款を使えば印紙代の4万円を節約できます。そのため、合同会社の設立に必要な法定費用は実質6万円〜10万円程度に収まります。
ただし、会社実印の作成費や登記事項証明書の取得など、数千円程度の周辺費用も見込んでおく必要があります。
合同会社を設立する手順
合同会社の設立は、比較的シンプルな流れで完了します。それぞれの工程には必要な書類や期限があるため、事前に把握しておくことでスムーズに進行できます。
本章では、合同会社の設立に必要な6つのステップを紹介します。
会社の基本事項を決める
会社設立の最初のステップは、基本事項の決定です。社名や事業目的、本店所在地、資本金、出資者の構成などを明確にします。たとえば、商号は「○○合同会社」といった形式で、既存の会社と重複しないか確認が必要です。また、事業目的は融資や税務にも影響するため、将来的に行う予定の事業も含めて広めに設定することが推奨されます。
さらに、誰が代表者となり、どのような体制で運営するかも決めておく必要があるのです。これらの情報は後の定款作成や登記申請にそのまま使用されるため、曖昧なまま進めると後で修正手続きが発生します。
定款を作成する
会社の基本方針を定める定款は、合同会社設立において必須の書類です。定款には、商号、目的、本店所在地、出資額、社員構成、利益配分の方法などを記載します。
合同会社の場合、公証役場での認証は不要ですが、紙定款の場合は収入印紙代として4万円が必要になります。コストを抑えたい場合は、電子定款で作成すればこの印紙代を節約できます。
定款に記載する内容は会社のルールそのものとなるため、将来的なトラブルを避けるためにも、慎重に記載内容を検討することが重要です。たとえば、利益配分や代表社員の権限範囲などは、出資者間の役割や責任に直結します。
資本金を振り込む
定款の作成が完了したら、定めた資本金を代表社員の個人口座に振り込む必要があります。これは会社がまだ設立されていない段階のため、法人名義の口座が存在しないためです。
資本金の入金は、設立時に必要な「払込証明」としての役割を果たします。振り込んだ日付や金額が分かる通帳のコピーや明細を取得し、登記申請時に添付します。出資者が複数いる場合は、それぞれが決められた金額を振り込んだ証拠を残すようにしましょう。
なお、資本金は1円からでも設立可能ですが、実際には当面の運転資金を見越して金額を設定するのが一般的です。資本金が少なすぎると、信用や融資面でマイナスに働くこともあるため注意が必要です。
法務局に設立登記を申請する
資本金の払込が完了したら、次は法務局に会社の設立登記を申請します。提出する書類は、登記申請書、定款、払込証明書、代表社員の就任承諾書、印鑑届出書など多岐にわたります。
書類がすべて揃い、問題なく受理されれば、数日〜1週間ほどで会社の登記が完了します。登記が完了すると、法人格が付与され、正式に事業を開始できる状態になります。
登記後には、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や法人印鑑証明書などが取得可能となります。これらの書類は、口座開設や契約締結、行政手続きに必須となるため、必ず早めに準備しておくべきです。なお、登記の申請は郵送・窓口・オンラインから選択可能です。
税務署や自治体へ必要な届出を行う
会社設立後は、税務署や都道府県・市区町村などへの各種届出を速やかに行う必要があります。
まず税務署には、「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出します。これらは、設立後原則として1〜2ヶ月以内に提出が義務付けられており、遅れると青色申告ができなくなるなどの不利益があります。
また、地方自治体に対しても、法人住民税や事業税に関する届出が必要です。提出先や提出物は地域によって異なるため、あらかじめ自治体のホームページなどで確認しておくと安心です。
銀行口座を開設し、事業を開始する
登記が完了した後は、法人名義で銀行口座を開設する必要があります。口座開設にあたっては、登記事項証明書、印鑑証明書、会社実印、代表社員の本人確認書類などが求められます。金融機関によって審査の基準が異なるため、事業計画書やホームページの提出を求められる場合もあるので注意が必要です。
また、近年はマネーロンダリング対策の強化により、審査が厳しくなっている傾向があります。口座開設までに数日~数週間を要するケースもあるため、早めに準備を進めることが大切です。
合同会社が「やめとけ」「やばい」と言われる理由は?
インターネット上では「合同会社はやめとけ」や「やばい」という否定的な意見を目にすることがあります。その背景には、合同会社の制度上の特徴や、運営の実態に関する誤解・リスクが存在します。
合同会社が「やめとけ」と言われる最大の理由は、社会的信用の低さや資金調達の難しさです。たとえば、「取引先から信用されなかった」「銀行融資を断られた」といった体験談が見受けられます。
また、複数人で設立した場合に、利益配分や意思決定を巡ってトラブルが発生し、運営に支障をきたすケースもあります。特に定款で明確なルールを決めていないと、代表者の暴走や責任の所在不明といった事態に発展する可能性があるのです。さらに、将来的に株式会社へ移行したくなっても、組織変更には時間とコストがかかるため、初めから合同会社にしたことを後悔する例もあります。
一方で、合同会社に関するネガティブな意見の多くは、制度の仕組みを理解した上で適切な準備をすることである程度防ぐことが可能です。ただし、社会的信用や資金調達など外部要因については完全に回避できるとは限らないため、設立前に十分な検討が求められます。
合同会社の運営で注意すべきポイント
合同会社は柔軟な運営が可能な反面、制度上の特性からトラブルが起こりやすい側面もあります。ここでは、合同会社の運営を安定させるために重要な3つの注意点について解説します。
出資者間のルールづくりや信用力の向上に関する対策を知ることで、長期的に安定した経営が実現できるでしょう。
業務執行社員の権限と意思決定のルールを明確にする
合同会社では、出資者全員が原則として業務執行権限を持ちます。そのため、意思決定のルールが曖昧だと、経営方針が定まらず内部対立に発展する恐れがあります。
たとえば、「誰が代表権を持つか」「重要な契約を誰が判断するか」といった点を定めていないと、現場での判断に時間がかかり、ビジネスの機会を逃すことになります。そこで、定款や契約書において、業務執行社員と代表社員の権限範囲を具体的に明記しておくことが重要です。
また、複数人で意思決定を行う際の議決方法(多数決か全会一致かなど)もあらかじめ決めておくことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
出資者の脱退や持分譲渡のルールを決めておく
合同会社では、社員の脱退や持分譲渡に関して特別なルールがない場合、社員全員の同意が必要となります。これが原因で、出資者の一人が辞めたいと言っても他の社員が同意せず、身動きが取れなくなる事態が起こりえます。M&Aや事業承継の観点からは、この制約は非常に重要です。
たとえば、将来的に事業を第三者に売却したい場合、持分の譲渡に社員全員の同意が必要となるため、一人でも反対すれば取引が成立しません。このリスクを軽減するために、以下のような対策を定款に明記しておくことが有効です。
- 「持分譲渡は社員の過半数の同意で可能とする」という条項
- 「特定の条件(例:会社創業から5年経過後)を満たした場合は、社員は他の社員に持分を買い取らせることができる」という条項
- 「持分の評価方法」を明確に定める条項
また、共同創業者や複数の出資者がいる場合は、持分を売却する際の優先順位や相互に買い取る権利(先買権)についても定めておくと、将来のトラブルを防止できます。M&A実務の観点からは、このような詳細なルールを設立時に定めておくことが、後の円滑な事業承継や会社売却には不可欠です。
資金調達や信用力向上の対策を行う
合同会社は株式発行ができず、金融機関の融資にも慎重な審査がされるため、資金調達に苦戦する傾向があります。これを補うためには、創業初期から信用力を高める努力が不可欠です。
たとえば、事業計画書を整備し、過去の取引実績や顧客からの評価などを積極的に開示することで、金融機関からの信頼を得やすくなります。また、日本政策金融公庫や信用保証協会などの創業支援制度を活用するのも効果的です。さらに、WebサイトやSNSを通じて実績や社会的貢献を可視化すれば、取引先や顧客からの信用力も自然と向上します。
形態上のハンディを補うには、地道な信頼構築の積み重ねが何より重要です。
まとめ|合同会社のメリット・デメリットを理解し、最適な選択を
合同会社は、設立費用の安さや経営の柔軟性といった多くの利点を持つ一方で、信用力や資金調達面では注意が必要な会社形態です。小規模での起業や少人数での経営には非常に適していますが、将来的な成長戦略やリスク管理も踏まえて設立を検討することが重要です。
メリットとデメリットを正しく理解したうえで、自社の目的に合った最適な選択をしましょう。