CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
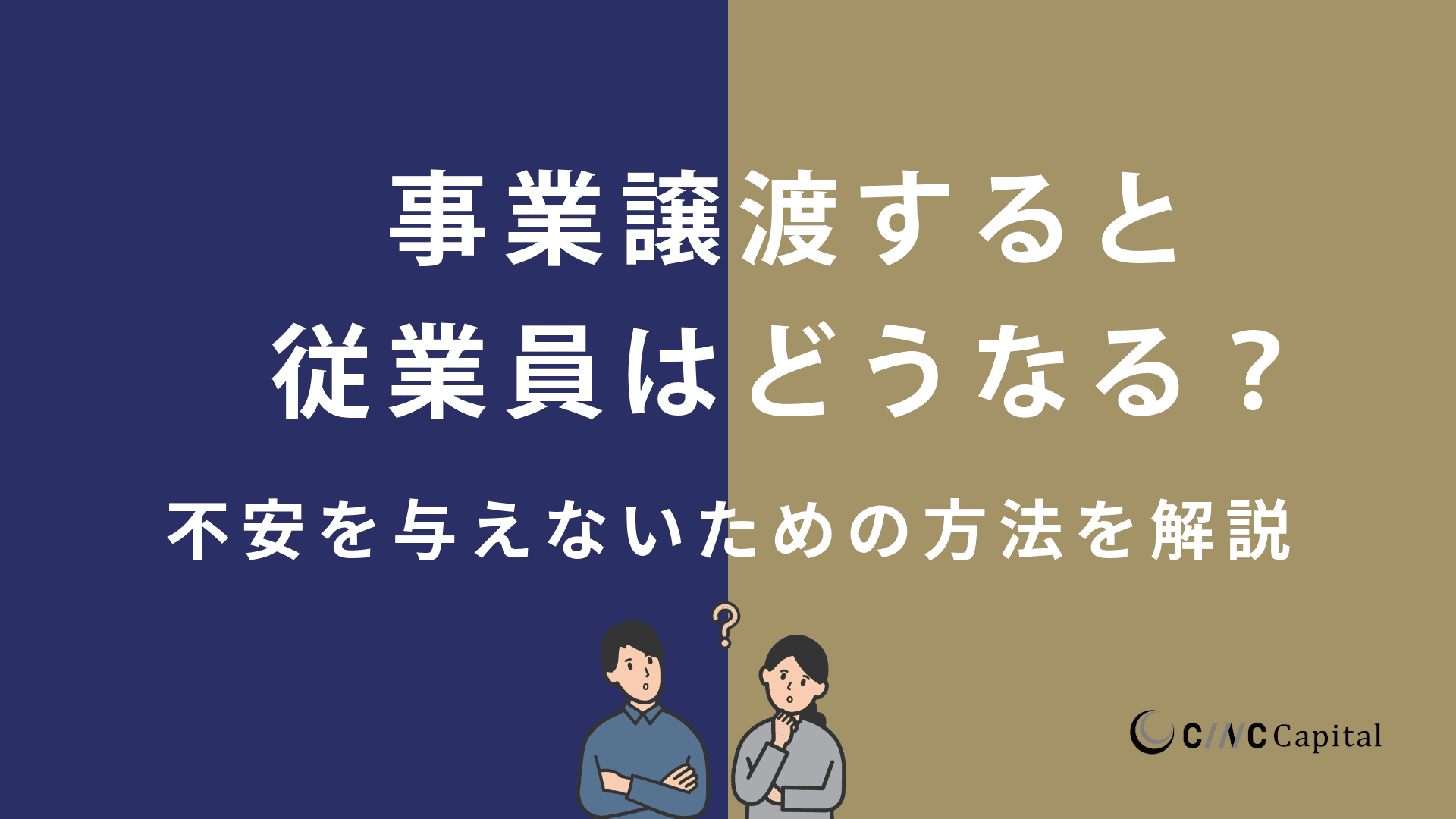
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
事業譲渡によって従業員が受ける影響とは?不安を与えないための対処
事業譲渡の際は、従業員も譲受側の企業へ引き継ぐケースが多くなります。従業員は転籍・配置転換・退職・出向などを選択することになりますが、いずれにせよ大きな環境の変化が訪れることに変わりはありません。
事業譲渡に際して、従業員が不安を抱くのは当然といえるでしょう。
この記事では、事業譲渡で従業員が受ける影響や、従業員へ不安を与えないための対策のコツなどを徹底解説します。
目次
事業譲渡とは
事業譲渡とは、事業の全てもしくは一部を売却するM&A手法です。基本的には契約や許認可などが包括的に受け継がれるのが特徴となっています。
譲渡企業に勤める従業員の中には、事業譲渡によって職場環境の変化を余儀なくされるケースがあります。企業側は、そういった従業員一人ひとりの意向を伺い、選択に応じた対応を行う必要があります。
事業譲渡を行う際の従業員の主な選択肢
事業譲渡を実施する際は、従業員の今後について具体的に提示する必要があります。以下では、主な選択肢をご紹介します。
譲受企業への転籍
事業を引き継いだ譲受企業へ転籍する方法です。従業員が譲渡企業を離れ、譲受企業と雇用契約を結び直します。
譲受側としては、これまで事業に携わってきた社員は確実に獲得しておきたいものです。ただし、転籍は強要できるものではなく、従業員の合意を得る必要があります。同意があれば「転籍承諾書」や「転籍同意書」といった書面に残すことが基本です。
譲渡企業での継続勤務
譲渡企業に別の事業が残っている場合、そのまま譲渡企業で勤務を続けられるケースがあります。従業員に対しては、配置転換を打診することになります。労働条件や勤務地など、これまでと変更になる点を適切に伝えた上で同意を得ることが重要です。
退職
転籍や継続勤務などの条件がのめず、退職を選ぶケースも見られます。ただし、「合理的な理由なく労働条件が不利益変更される場合」「事業譲渡を理由とした退職勧奨がある場合」などの条件下では、整理解雇と判断される可能性がある点に留意しましょう。その場合は、解雇予告手当の支払いが必要です。
※解雇予告手当:解雇予告手当とは、企業が従業員を突然解雇する場合に、30日以上前に通知しない場合に支払う手当のこと
出向
譲渡側の企業に雇用されたまま譲受側企業へ出向し、これまで通りの業務に従事する方法です。従業員側が転籍を拒否して出向扱いになった場合も、譲受企業に慣れた頃に再度転籍を打診すると、同意をもらえるパターンがあります。
事業譲渡によって従業員が受ける影響とは?主なメリット・デメリット
事業譲渡に際して、従業員の環境が改善することもあれば、条件が悪化してしまうこともあります。具体的なメリットや注意点などを見ていきましょう。
従業員にとってのメリット
新たな雇用機会
事業譲渡は新たな雇用機会のタイミングとなり得ます。高いスキルを持つ従業員は、現状よりも良い待遇や職務などを目指すことも可能です。上司や同僚などが変わり、より働きやすい職場環境になることもあるでしょう。
キャリアアップの可能性
事業譲渡が行われる場合、譲受側の企業が大企業であるケースも珍しくありません。従業員の労働環境も大きく変化し、これまでとは違ったチャンスに巡り合う可能性もあるでしょう。
業務内容は変わらなくても、キャリア形成の意識に変化がもたらされるケースもあります。譲渡企業に残留して配置換えした場合も同様で、新たなキャリアパスを描くことが期待できます。
スキルアップのチャンス
成長の機会が多い譲受企業への転籍が実現すると、スキルアップにつながる可能性もあります。例えば、譲渡企業では存在しなかった教育・研修制度の恩恵を受けられる場合もあるでしょう。
また配置換えを選択した場合も、これまでと異なるスキルを身につけられるかもしれません。
従業員にとってのデメリット
雇用契約の変更
新たな会社へ移る際、雇用契約が変更され、給与や勤務場所、福利厚生などの内容が変わってしまう場合があります。従業員にとってマイナスとなる変化であれば、モチベーションの低下に繋がるケースもあるでしょう。
慣れ親しんだ環境からの変化
職場環境の変化はメリットばかりとはいえず、人によってはうまくなじめずストレスを抱えてしまうことがあります。移籍したものの環境が合わないと感じた社員は、転職を選ぶことも考えられるでしょう。
転籍を拒否した場合のリスク
譲渡企業に配置換え可能な事業がない場合、転籍を拒否した従業員は退職せざるを得ないことがあります。失業によるデメリットは大きく、従業員の人生にも影響を与えてしまいます。可能な限り雇用を継続できるような工夫を行うことが大切です。
事業譲渡で従業員に不安を与えないためには
従業員の不安を払拭するためには、どのような対策を行えば良いのでしょうか。以下では、事業譲渡時に従業員へ不安を与えないためのポイントを解説します。
十分な説明とコミュニケーション
事業譲渡に際しては、従業員にしっかりと説明を行うことが重要です。フォローが不十分だと退職者が大量に出てしまい、事業譲渡そのものが失敗になる可能性があります。
事業譲渡における従業員側のメリットを伝えることで、転籍にも納得してもらいやすくなります。従業員の目線に立ち、丁寧にフォローすることを心がけましょう。
全体の説明に加えて個別面談を実施し、労働契約や待遇面などの変化について伝え、不安点や疑問点についての相談を受け付けることが大切です。
労働条件の維持
従業員に不利のないよう、譲渡企業の労働条件を維持、もしくは向上できる内容を契約に組み込むことが望ましいでしょう。譲渡企業・譲受企業・従業員の三者ですり合わせることが大切です。
全従業員の雇用の継続性の確保
譲受企業によっては、一部従業員のみの転籍を希望し、その他の従業員は受け入れを拒否するケースがあります。配置換えが難しい場合、その他の従業員の受け入れ先がなく、雇用継続が困難になってしまうでしょう。
事業譲渡において全従業員の雇用を継続できるかどうか、事前に条件をしっかりと確認しておくことが求められます。
有給休暇や勤続年数の継続
有給休暇は勤続年数に応じて加算されていくことが基本です。転籍によって譲受企業に入社した場合、勤続年数が0からのスタートとなり、有給休暇日数もリセットされてしまう場合があります。
従業員の不利益となるため、有給休暇・勤続年数が引き継げるような契約を結ぶのが望ましいでしょう。
譲渡企業での継続勤務
譲渡企業の状況によっては、転籍を拒否した従業員も異動して勤務を続けることが可能です。希望する従業員には、配置の変更が可能である旨を伝えておきましょう。
退職金の扱いの明確化
勤続年数に応じて退職金がアップする企業の場合、転籍による影響が気になる従業員も少なくないでしょう。退職金の扱いは、主に2種類あります。一つが、譲渡企業を離れる際に退職金を支払う方法です。譲渡企業側の規定に応じた金額を清算します。
もう一つが、譲受企業が退職金を引き継ぐ方法です。転籍の段階で清算される予定だった退職金の額を引き継ぎ、転籍後は譲受側企業の規定に応じた退職金が加算されます。勤続年数を通算できるか否かについても企業間で話し合い、契約に盛り込みましょう。
キャリアアップの機会提示
事業譲渡後、労働条件の改善が期待できることや、キャリアアップの可能性があることなど、従業員にとってのメリットを伝えることも重要です。転籍がキャリアアップにつながると理解してもらえれば、同意を得やすくなるでしょう。
まとめ|事業継承における従業員への対応は慎重に進めよう
事業譲渡における従業員への影響や、不安を与えないためのポイントなどを解説しました。
事業譲渡に際し、自身の不利益を懸念する従業員も少なくありません。わだかまりなく転籍に臨んでもらえるよう、企業側が責任を持って対応することが大切です。
個別面談を実施するほか、その後も密にコミュニケーションの機会を設けることで、従業員の不安を取り除くよう心がけましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、事業譲渡のご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















