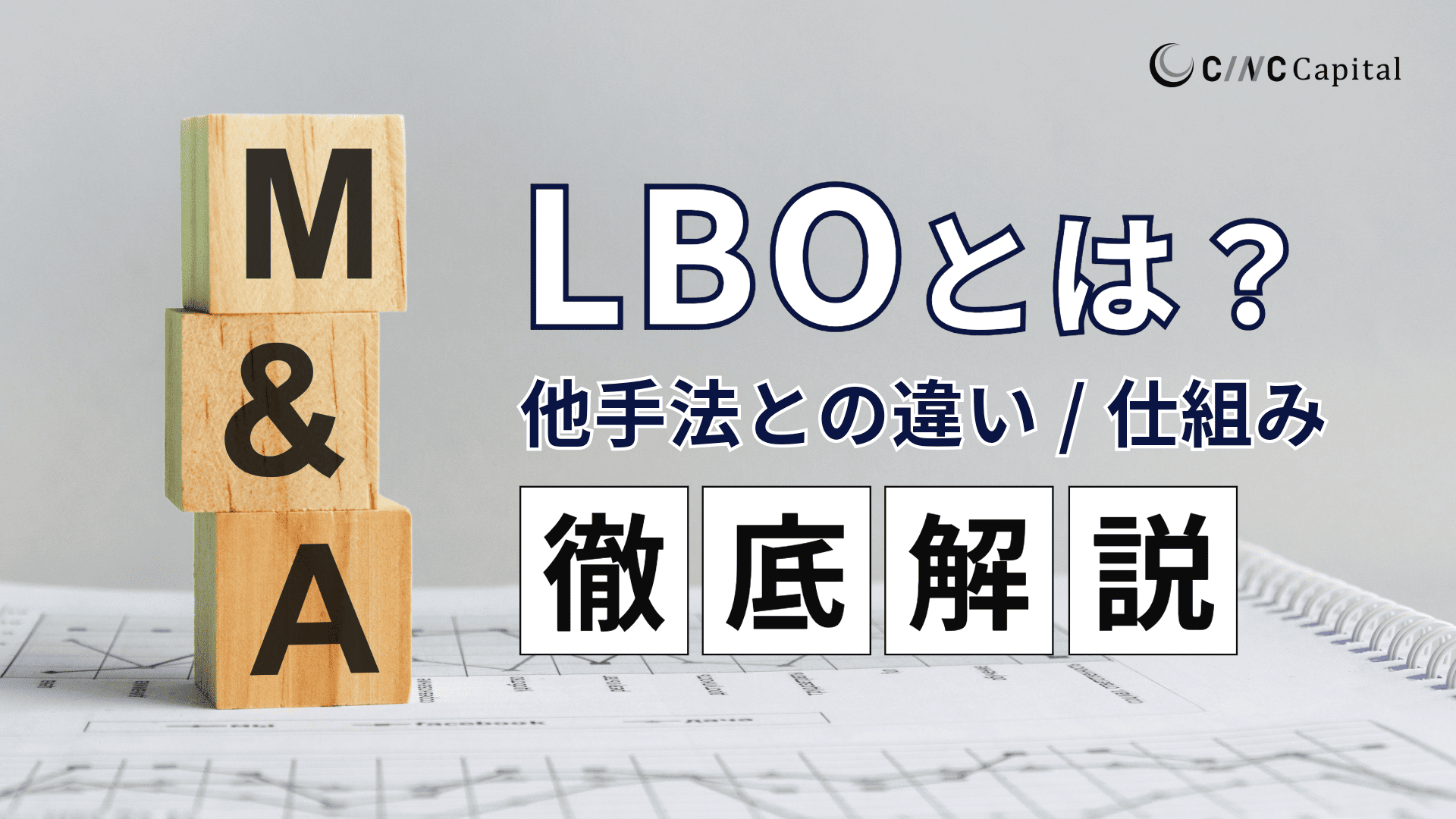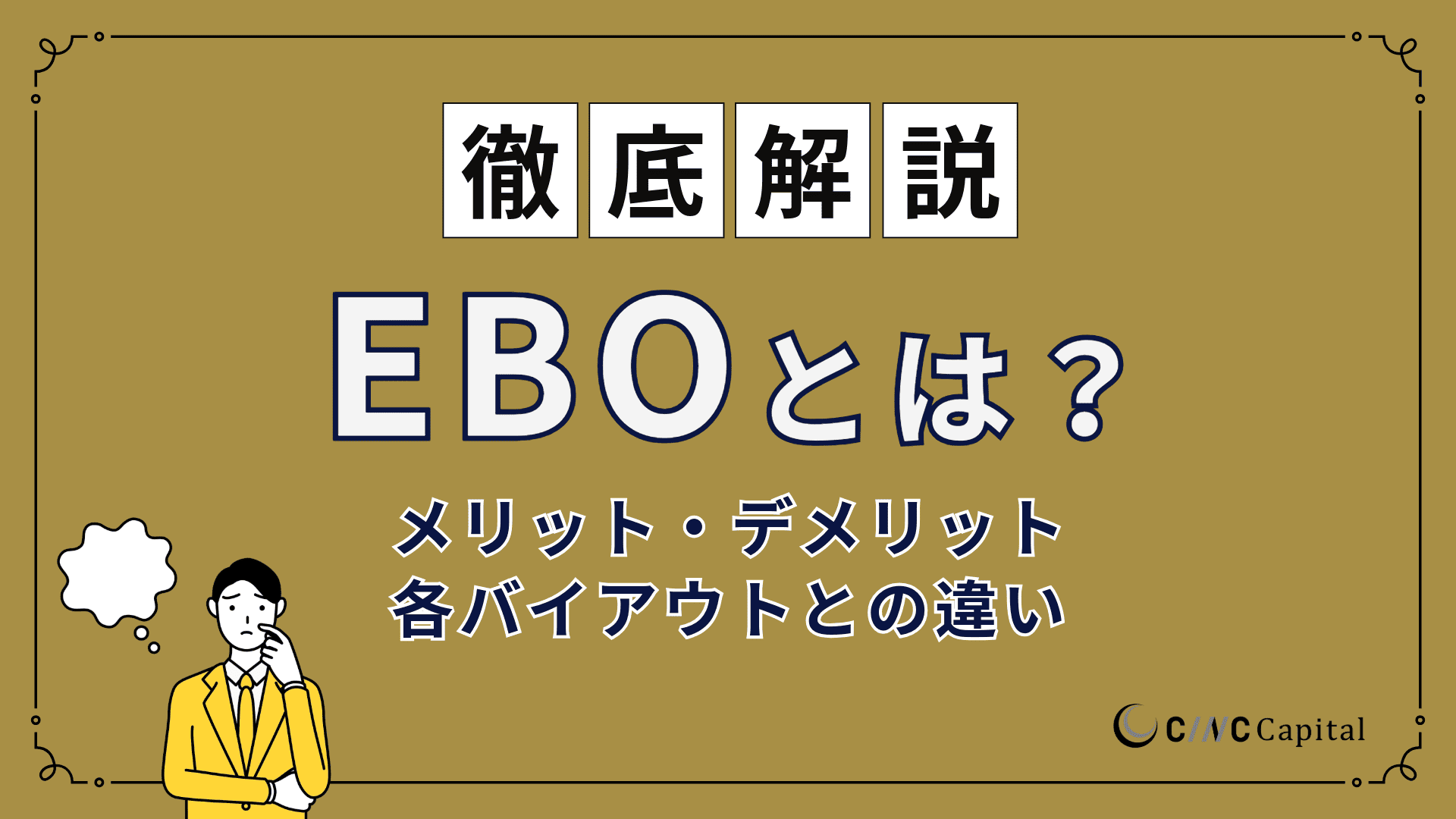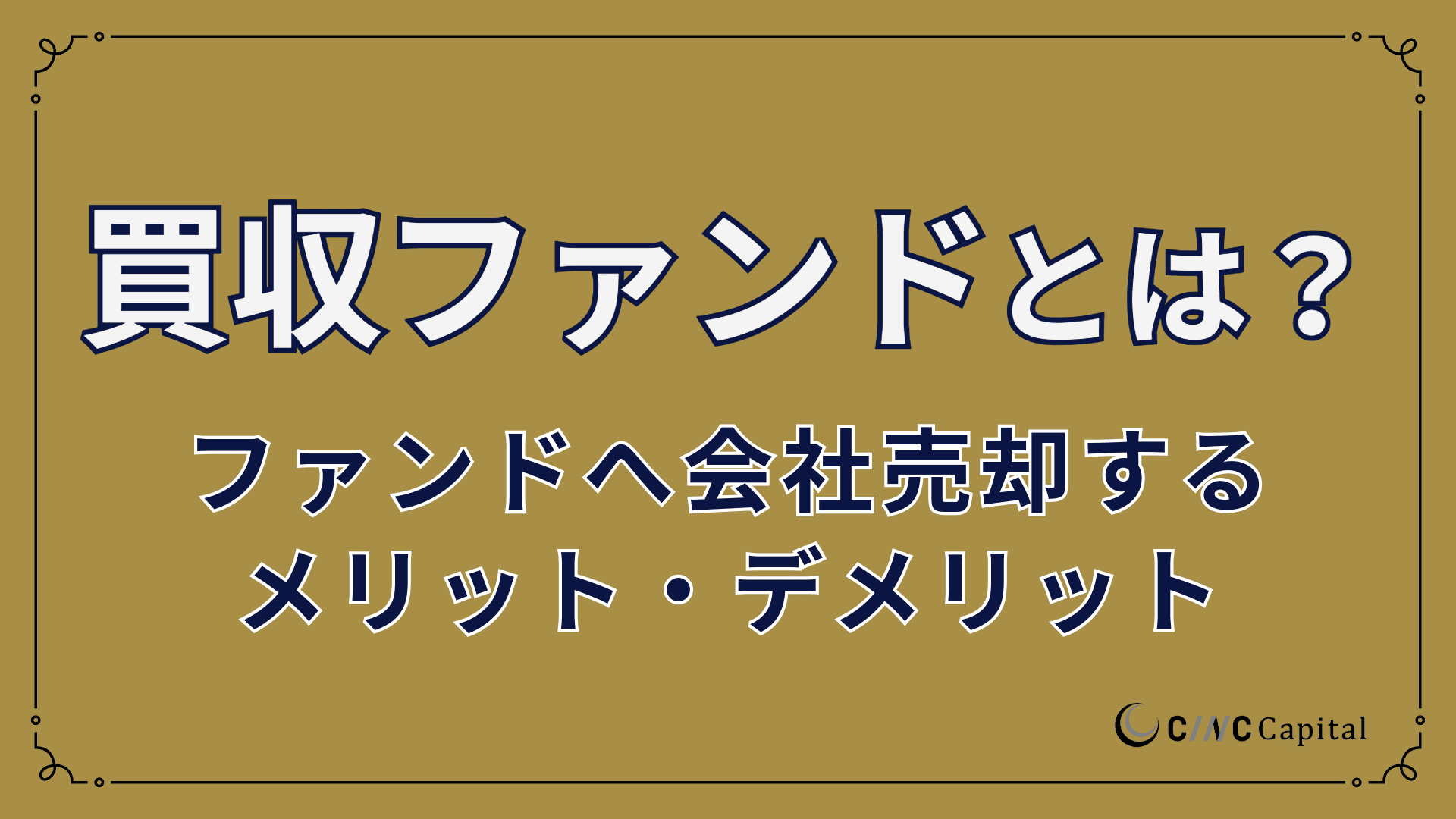CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / スキーム
- 公開日2025.09.30
M&AにおけるMBOの事例7選!増加している背景や進めるうえの注意点を解説
経営の自由度を高めたい、短期的な株主の意向に縛られずに長期戦略を描きたい、そんな悩みを抱えていませんか?
近年、上場企業を中心に「MBO(マネジメント・バイアウト)」という選択肢を取る企業が増えていますが、仕組みや背景を正しく理解している方は多くありません。
本記事では、MBOとは何かという基本から、実際に行われた事例、増加している理由、メリット・デメリット、進める際の注意点までを総合的に解説します。
目次
MBOとは?
MBO(マネジメント・バイアウト)とは、企業の経営陣が外部株主から自社株式を買い取り、経営権を社内に移す手法です。
これにより経営陣は意思決定の自由度を高められ、外部株主や短期的利益に左右されずに中長期的な戦略を推進できるようになります。
特に上場企業では、TOBを通じた非公開化により、機動的な経営改革が可能になるのです。
MBOは、経営陣が自社の株式または事業部門を取得して経営権を掌握するM&Aの一手法になります。
企業の所有者が経営陣へ移ることで、経営の自由度とスピードが向上するのが利点です。
例えば、経営陣は将来性ある新規事業への投資やリストラクチャリングを迅速に進めることが可能になります。
この手法の資金調達では、経営陣自身の資金だけでなく、金融機関からの借入や投資ファンドからの出資を組み合わせることが一般的です。
特にLBOスキームが活用され、買収後の将来キャッシュフローや企業資産を担保にして資金を借り入れるケースが多く見られます。
また、上場企業のMBOではTOB(株式公開買付)を通じて特定価格以上で株式を取得し、完全非公開化を目指します。
これによりオーナーシップを社内に集約し、企業文化や経営の継続性を維持しつつ、新体制で次のステージに進むことができるようになるのです。
MBOの事例
こちらでは、日本企業の代表的なMBO事例を取り上げます。
それぞれの目的、スキーム、背景、そしてその後の展開を詳述し、MBOが経営戦略としていかに活用されているかを見ていきましょう。
永谷園ホールディングス
永谷園ホールディングスは、2024年6月に丸の内キャピタルと連携してTOB方式のMBOを実施し、2024年7月に成立。
その後9月末に東証プライム市場から上場廃止しました。
当初企業が直面していた国内市場の成熟化を背景に、海外展開や大規模な設備投資、新規M&Aを加速させるため、経営の自由度を高める狙いでした。
買付価格は1株3,100円、TOB成立後の自己株式取得も含め約485億円の大型案件でした。
経営陣と創業家は廃止後も経営に継続して携わる計画を明かしており、外部ファンドのノウハウ活用も視野に入れた長期戦略が注目されます。
【出典】株式会社永谷園ホールディングス「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」
すかいらーく
すかいらーくは2006年に国内過去最大級となる約2,700億円規模のMBOを実施し、株式を非公開化しました。
当時の外食産業の低迷や短期的株主プレッシャーを避けるため、TOB+SPCスキームを採用しています。
結果として経営改革が進み、2008年以降の追加資本投入と再構築を経て、2014年に再上場を果たしました。
この一連の流れはMBOによる経営再建のモデルケースとされています。
【出典】Bloomberg「株式非公開へ、最大2720億円でMBO-M&A積極的(9)」
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)
CCCは2011年に経営陣によるMBOを通じて上場を廃止し、非上場企業へ転換しました。
目的は外部株主の短期的視線を排し、新規事業やTSUTAYA改革を社内主導で進めるためです。
非上場化後は店舗改革に加え、蔦屋家電など新ブランドへ挑戦しやすくなり、経営の自由度が飛躍的に高まりました。
公開ソースとして、CCCの非上場化に関する報道記事やビジネスメディアの分析が確認可能です。
【出典】日本経済新聞「『TSUTAYA』のCCCがMBO 買い付け総額700億円 4日からTOB」
インフラトップ
インフラトップは2024年4月、DMMグループ傘下の一事業を独立させる形で、経営陣が「BUBU株式会社」を設立するMBOを実行しました。
狙いは、意思決定スピードの向上とプログラミング教育サービスの質的伸長を図るためです。
外部ではなく内部主体のMBOにより、経営資源の集中と迅速な市場対応を実現しています。
公式発表に基づいたプレスリリースやM&A専門メディアから内容を確認できます。
【出典】BUBU株式会社「DMM.comグループ会社である株式会社インフラトップの経営陣による、一部事業MBOの実施のお知らせ」
スノーピーク
アウトドア用品大手スノーピークは2024年2月、ベインキャピタル傘下のBACJ‐80社によるTOB方式のMBOを発表し、株価は1250円に設定されました。
同社はコロナ後の市場変化や海外展開強化に対応するため、非上場化によって中長期的な企業価値向上を目指す構造改革を進めています。
TOBには特別委員会設置など公正性確保措置が講じられました。
【出典】日本経済新聞「スノーピーク、MBOが成立 株主総会後に上場廃止へ」
幻冬舎
幻冬舎は2010年に創業者である見城徹社長率いるTKホールディングスがTOBを通じてMBOを実行し、上場廃止。
この非上場化により、経営の自由度を高め、コンテンツ開発など市場変化に柔軟に対応する経営体制を整えました。
具体的には、当時の日経新聞やマールレポートなどにその背景と目的、実施スキームが報じられています。
【出典】日本経済新聞「幻冬舎が60億円でMBO 経営と資本一体化で出版不況生き残り」
ダイオーズ
オフィス向けコーヒーサービス提供企業ダイオーズは2022年、コロナ禍による業績悪化を背景に、経営陣と国内投資ファンド(インテグラル)が連携してMBOを実施。
株式公開市場から離れた後、迅速な事業再構築と収益基盤強化を進めました。
このMBOは外部環境変化への対応策として注目されており、経済紙や企業IRにもその内容が記載されています。
【出典】日本経済新聞「ダイオーズが株式非公開化へ、MBOを発表 200億円規模 投資ファンドのインテグラルが支援
近年MBOが増加している背景
ここでは近年MBOの件数が増加している理由を、市場再編、株価状況、投資家圧力、経営環境、資金条件の5つのポイントから整理します。
各要因がどのようにMBOを後押ししているかを見ていきましょう。
東京証券取引所の市場再編と資本効率改善の要請
2022年4月に東京証券取引所(東証)がプライム・スタンダード・グロース市場への再編を行い、上場維持基準を厳格化しました。
それに加え、2023年3月からは資本コストや株価を意識した経営に取り組むことが企業に強く求められ、2024年からはその対応状況も開示対象となっています。
この環境変化により、上場企業はIRや決算報告などのコスト負担が増したうえ、短期の株主対応が圧迫要因となり、非公開化の選択肢としてMBOを検討するケースが増えてきました。
2025年上期には59社が上場廃止に踏み切るなど、非公開化の動きが加速しています。
株価の低迷
多くの上場企業は株価純資産倍率(PBR)が1倍未満にとどまり、株価が帳簿価値を下回る割安水準が続いています。
こうした状況は、経営陣にとって「自分たちの会社を市場より安く買い戻すチャンス」であり、MBOを通じた経営権の内製化を後押しする要因です。
※ただし、株価が低いという理由だけでMBOを行う場合、少数株主の利益を損なわないよう公正な価格評価や独立委員会の設置が求められます。
日本企業のMBOは2023年に17件以上、買付総額は1.4兆円を超えるなど、PBR割れと連動した動きが明らかになっています。
【出典】日本経済新聞「MBO過去最高の1.4兆円 市場の規律が新陳代謝促す」
投資家の影響と株主からの圧力
近年、アクティビストなど「物言う株主」の存在が増し、企業に対して配当の拡充や株主還元の強化が激しく求められるようになっています。
この圧力は中長期的な成長施策に取り組む経営陣にとっては制約となり、短期的利益を優先しなければならない状況に陥りやすくなるのです。
その結果、経営の選択肢を広げる手段として、株式市場から離れるMBOが魅力的に映る状況が生まれています。
経営の自由度向上と中長期的な視点の確保
MBOにより株式公開をやめることで、経営陣は四半期ごとの業績報告やIR活動、株主対応といった短期対応義務から解放されます。
その結果、構造改革、新規事業への投資、経営戦略の大胆な転換などを中長期視点で自由に実行できるようになるのです。
事実、MBO後に非上場化した企業は、経営の自由度を最大限に活かして再構築を行う例が多数見られ、MBOの魅力として広く認知されつつあります。
金利上昇を前にした低コストでの買収資金調達
長期的な低金利環境は金融機関やファンドからの資金調達を容易にし、MBOに適した資金調達が可能な状況をもたらしました。
一方で日銀による金融政策の正常化(利上げ)も示唆されており、金利が上昇する前にMBOを実行しようとする動きが顕著です。
このようにコストが安いタイミングに資金調達する戦略的動きは、MBO件数の増加につながっています。
MBOを行うメリット
このセクションでは、MBOを実施することで生まれる主要な5つのメリットを取り上げます。
「長期視点の経営」「意思決定の迅速化」「従業員の理解」「敵対的買収の防御」「事業承継の円滑化」について、それぞれの効果と事例を見ていきましょう。
長期的なビジョンに基づいた経営が可能になる
MBOでは株式を内部に集約することで、株主の短期利益志向から解放され、中長期的な戦略を描きやすくなります。
多くの上場企業が、頻繁な四半期決算に追われて中長期的な視点を置きづらいなか、MBOはそれを改善する手段として有効です。
例えばすかいらーくはMBO後に店舗展開やメニュー刷新といった長期的戦略を加速させ、成功を収めています。
意思決定の自由度とスピードが向上する
株主総会の承認を得る必要がなくなり、経営陣による判断が迅速になります。
急激な市場変化や技術革新時代においては、意思決定のスピードが大切です。
MBOはこの点において、従来の株主構造に比べて圧倒的に有利であり、変革を志向する経営には不可欠な要素となっています。
従業員の理解と協力を得やすい
MBOでは経営陣がそのまま経営を続けるため、従業員には安心感が生まれ、抵抗も少なくなります。
第三者による買収とは異なり、組織の雰囲気や文化を維持しながら変革を推進できる点が強みです。
特にリストラクチャリングや組織再編時に、従業員の支持を得るために有効です。
敵対的買収やTOBから企業を守れる
MBOでは経営陣が株式の多くを保有するため、他社によるTOB(株式公開買付)や敵対的買収に対して防御力を高められます。
公開市場から株を引き上げ非上場化することで、第三者の介入を防ぐことが可能です。
日本企業では、MBOが買収防衛策として活用されるケースも増えています。
事業承継の課題をスムーズに解決できる
親族に後継者がいない中小企業や創業者引退時において、MBOは現経営陣による円滑かつ継続的な事業承継を可能にします。
株式を第三者に売却するよりも、従来メンバーによる経営継承により、信頼関係や企業文化を維持したまま承継を進めやすくなるのです。
この手法は事業承継問題のソリューションとして注目されています。
MBOを行うデメリット
このセクションでは、MBOが抱える典型的なリスクを整理します。
「既存株主との対立」「財務リスク」「経営改革の停滞」「資金調達制約」という4つの視点から、背景や具体例を見ていきましょう。
既存株主との対立が生じる場合がある
MBOでは経営陣が株式を購入する価格を市場や既存株主とすり合わせる必要がありますが、経営陣は可能な限り低価格で買いたいと考えるのに対し、株主はより高い価格を求めます。
その結果、交渉が難航したり、最悪の場合は株主の売却に合意が得られずMBO自体が不成立になる可能性があるのです。(利益相反による法的問題が生じたケースも存在します。)
このリスクを軽減するために、独立委員会の設置や第三者評価を組み込むことが重要となります。
財務リスクや資金繰りへの慎重な対応が求められる
MBOを実行するには通常、金融機関やファンドからの借入による資金調達が必要です。
大きな負債が会社に残ることで、金利負担や返済の重圧が経営を圧迫し、資金繰りが悪化する可能性があります。
特に金利が上昇傾向にある状況では、返済計画に綿密な見通しを立て、シナリオ分析を用いた資金戦略が不可欠です。
経営改革が進みにくくなるリスクがある
MBOにより現経営陣が主体となることで、安定した経営基盤が維持される一方、既存の体制や判断スタイルが温存され、変化が遅れる可能性があります。
革新的な視点や新陣営との交替を伴わないため、経営刷新が進まないリスクが存在するのです。
変革を目的とするMBOでは、導入初期に外部アドバイザーや取締役の起用によって、改革の起点を明確にする工夫が求められます。
上場廃止により資金調達の手段が限られるおそれがある
MBO後に上場廃止となると、公開市場での株式発行はできなくなり、社債発行も含めた資金調達手段の選択肢が狭まるおそれがあります。
このため、資金調達は主に借入に依存する構図となり、柔軟性が縮小されるおそれがあるのです。
企業によっては事業拡大や設備投資に必要な資金確保が難しくなるケースもあり、事前に資金計画を精査し、将来の資金源を明確に設計しておく必要があります。
MBOと似ている手法
本節では、MBOと類似性や差異のある3つのバイアウト手法を紹介します。
それぞれ「LBO」「EBO」「MBI」の定義と特徴を解説し、MBOとの関係性を見ていきましょう。
LBO
LBO(レバレッジド・バイアウト)は、買収対象企業の資産やキャッシュフローを担保にして借入を行い、企業買収を実行する手法です。
MBOと異なり、経営者自身でなく、投資ファンドや第三者が買い手になるのが一般的ですが、MBOでも資金調達手段としてLBO構造が組み込まれます。
買い手は主にSPC(特別目的会社)を設立し、借入を活用して買収を実行することが多いです。
買収後にSPCが経営することで、レバレッジ効果による資本効率改善を図りつつ、最終的に統合や再売却を目指します。
MBOにおいては、経営陣が主体としてこのLBOスキームを使うため、本質的には「自社買収型LBO」と言えるのです。
EBO
EBO(Employee Buyout)は、従業員が主体となって、自社または一部門を買収する手法です。
MBOとは異なり経営者ではなく従業員が主体になる点が特徴で、日本ではユニゾHDが2019年に従業員によるEBOを実施し、上場廃止を通じて株式公開市場から離脱しました。
この手法では、従業員が主体として事業承継や企業防衛を行いつつ、買収資金はローン・スターなど外部ファンドからの融資などに頼るケースが多く、従業員の経営参画意識が高まる一方で、財務負担への慎重な計画が求められます。
MBI
MBI(Management Buy-In)は、経営陣ではない外部のマネジメント層が会社を買収し、経営権を取得する手法になります。
MBOとは主体が異なり、新たに外部経営者が参画する点が特徴です。
しばしばMBOと組み合わせて「BIMBO」(Buy-In/Buy-Out)と呼ばれる混合型スキームも用いられ、既存経営陣に新陣営が加わることで、経営刷新のパワーを導入しやすくなる仕組みとして活かされます。
MBOを進めるうえでの注意点
このセクションでは、MBOを円滑に進行させるために必要な3つの重要なポイントを説明します。
既存株主との合意形成、資金計画の策定、そして上場廃止によるリスクとメリットのバランスについて見ていきましょう。
既存株主との合意形成を慎重に行う
MBOでは経営陣が株式を取得する際、既存株主との合意が不可欠です。
そこでまず、株式価格をめぐる利害の相違が生じることがあります。
経営陣はできる限り安い価格で取得したい一方、株主はできる限り高値を求めるでしょう。
こうした利益相反が交渉を難航させ、最悪の場合MBOの不成立につながる可能性があります。
そのため、第三者評価や独立委員会の設置、公正価値の提示を行うことで、利害調整を図る必要があるのです。
適切な資金計画を立てる
MBOには高額の買収資金が必要ですが、ほとんどのケースでは金融機関から融資を受ける形が多いです。
借入額が多くなるほど、金利負担や返済圧力が企業に重くのしかかります。
それゆえ、資金調達にあたっては将来のキャッシュフローを見据えた保守的な予測と複数のシナリオ分析が不可欠です。
専門家の意見も踏まえ、返済計画に柔軟性を持たせた計画を策定する必要があります。
上場廃止によるリスクとメリットのバランスを検討する
MBOによる非公開化は、IRコストの削減や経営の自由度向上など多くのメリットをもたらしますが、一方で株式市場を通じた資金調達ができなくなるリスクが発生します。
信用力低下による取引先や金融機関からの評価変化や、上場廃止に伴う透明性の低下も考慮すべき点です。
そのため、非公開化後の補填策として、銀行融資以外の資金調達方法(社債発行や特定株主からの追加出資など)を準備したうえで判断を行うべきです。
まとめ|MBOは中長期的成長を実現する有効な選択肢
MBO(マネジメント・バイアウト)は、経営陣が自社の株式を取得し、企業の支配権を社内に集約することで、中長期的な成長戦略を実現できる強力な手段です。
市場再編やPBRの低迷、外部株主の圧力など、近年の環境変化はMBOを後押ししています。
一方で、買収価格をめぐる株主との対立や資金調達による財務負担、非上場化による制約などのデメリットも存在します。
MBOを成功に導くには、事前の合意形成、慎重な資金計画、リスクとメリットのバランスを冷静に見極めることが欠かせません。
企業の将来にとって最善の選択となるよう、適切な判断と準備が求められます。
CINC CapitalはM&A仲介協会会員・中小企業庁の登録支援機関です。
業界歴10年以上の専門家が、譲渡や買収の目的に応じて適切な手法をご提案します。
秘密厳守でスムーズな取引を支援します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。