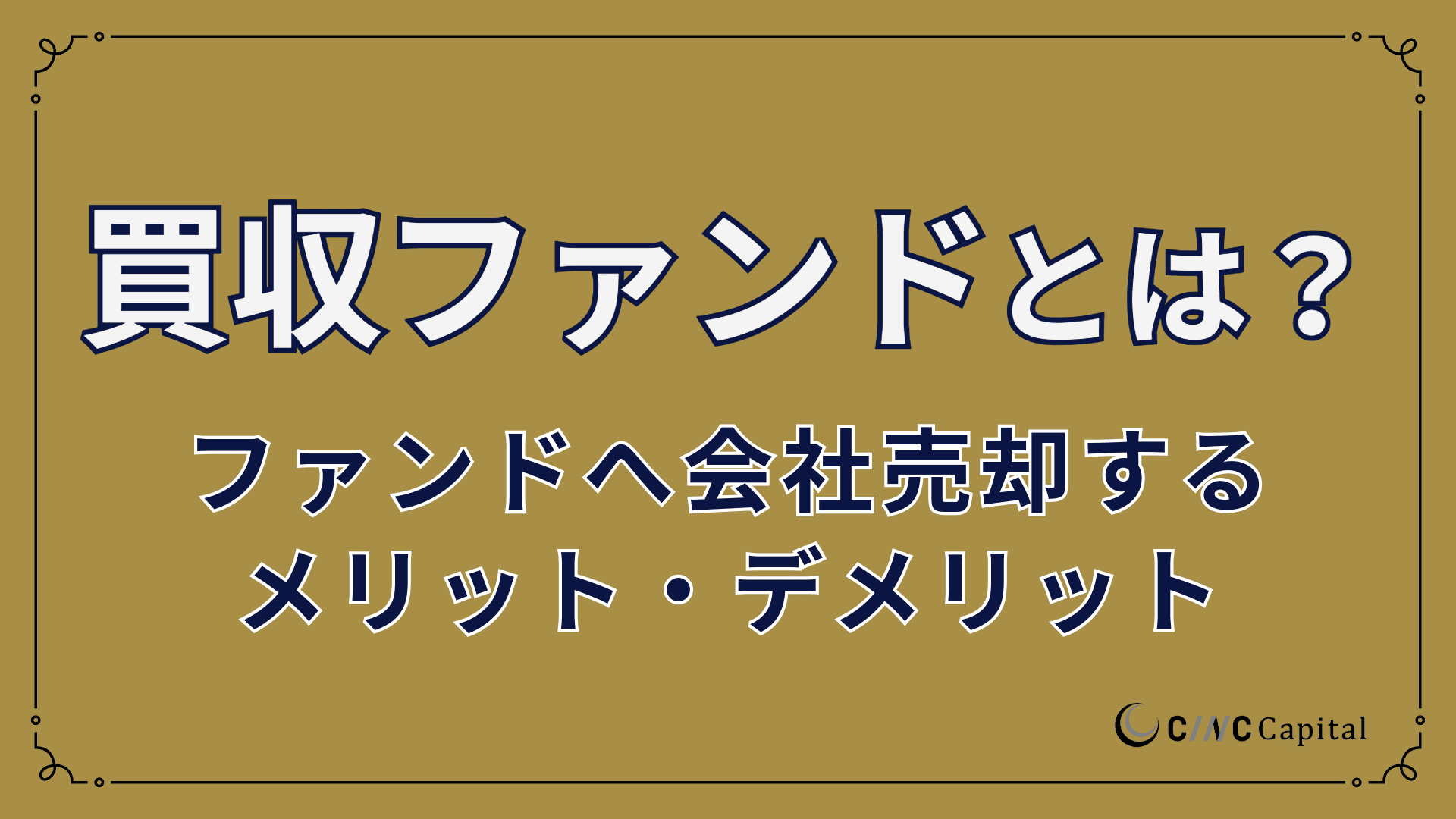CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / スキーム
- 公開日2025.09.30
吸収合併では契約は承継される?例外や覚書が必要なケース、労働契約を承継する際の注意点を解説
吸収合併を行うにあたり、「契約は引き継がれるのか?」「従業員の雇用条件はどうなるのか?」といった不安を抱えていませんか。
法務や人事の担当者であれば、合併後のトラブルを未然に防ぐためにも、契約承継のルールや労務対応について正確に理解しておきましょう。
本記事では、吸収合併における契約の承継可否や例外事項、雇用契約の取り扱い、従業員対応のポイントなどを詳しく解説します。
目次
吸収合併とは?
吸収合併とは、存続会社が消滅会社を取り込み、法人格を維持しつつ相手のすべての権利義務を一括で引き継ぐ合併形態です。
吸収合併では、消滅会社の事業資産や債務、契約関係、従業員の雇用契約に至るまで全てを存続会社が包括的に承継する仕組みを用います。
会社法第750条により合併効果の効力発生日に権利義務が移転すると定められており、この法的枠組みにより契約承継がスムーズに行われるのです。
吸収合併が選ばれる主な理由は、許認可や取引契約を再取得する必要なく事業を継続できる点であり、特にグループ再編や事業拡大のM&Aで頻繁に活用されます。
また新たに会社を設立する必要がない点から、手続きやコスト面でもメリットが大きく、実務上優先されることが多い手法です。
吸収合併では契約は承継される?
吸収合併では、消滅会社が締結していた契約関係を含む、すべての権利義務が法的に存続会社へ一括して承継されます。
これは会社法第750条に基づき、合併の効力発生日に自動的に行われる制度です。
例えば、賃貸借契約や業務委託契約など、消滅会社が当事者となっていた契約も、存続会社が当然のように引き継ぎます。
そのため、取引先から個別に同意を得る必要はなく、契約の再締結も原則不要です。
この包括承継の仕組みにより、契約関係は合併後も継続され、業務の中断や契約更新の手間を回避できます。
ただし、すべての契約が無条件で承継されるわけではありません。
契約内容や法的制限によっては例外が生じることもあるため、実務では注意が必要です。
包括承継とは
包括承継とは、吸収合併などの組織再編において、消滅会社が有するすべての権利義務を一括して存続会社または新設会社に移転させる法的仕組みです。
個別の契約ごとに手続きを行う必要がなく、会社法の規定により一括して権利義務が承継されます。
なお、包括承継は相続(民法上の包括承継)においても使われる概念ですが、法人の合併と個人の相続では法的な手続きや根拠法令が異なる点に注意が必要です。
会社法第750条に定める吸収合併では、この包括承継によって、消滅会社が締結していた契約類、所有資産、債務、従業員との労働契約などを、すべて存続会社側が引き受けます。
これにより、例えば消滅会社が保有していた許認可や契約関係、従業員に関する労働条件が、合併後も途切れることなく維持されるのです。
取引先や行政側に改めて確認を取る必要がないため、手続きの簡便化と組織統合の円滑化が実現します。
これは事業譲渡のように契約をひとつずつ引き継ぐ「特定承継」と対照的であり、特定承継では許認可や契約ごとに交渉や再契約が必要になるのに対し、包括承継にはその手間がありません。
吸収合併で契約が承継できない例外はある?
吸収合併では、消滅会社のすべての契約が包括承継されるのが原則ですが、実務上は例外が存在します。
この章では、COC条項が含まれる契約により承継に制約が生じるケースと、吸収合併後の覚書作成が法的に必要かどうかについて見ていきましょう。
チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは?
チェンジオブコントロール条項(COC条項)は、M&Aや合併などで企業の支配権が移動した際に、取引先が契約に影響を受けることがないように、契約書に特別な対応を設ける条項です。
この条項があることで、支配権の移転を機に契約の継続、解除、内容変更、通知義務などが定められます。
COC条項は主に、通知義務があり、合併・買収などで経営権が変更されるタイミングで取引先に告知が求められる場合と、契約解除権の規定で、相手企業の支配権が変わることを理由に契約を打ち切れるケースに分けられるのが一般的です。
実務では、ライセンス契約や賃貸借契約、金融機関との融資契約によく盛り込まれており、支配権が他社に移る際に契約相手の立場を守る役割があります。
例えば、合併によって筆頭株主が変わり、信用や事業方針に大きな影響が生じることが想定される場合、取引先はCOC条項を根拠に、契約を解除したり、新たな同意を求められる可能性があるのです。
こうしたリスクを放置してM&Aを進めると、合併後に主要取引が失われ、事業の根幹が揺らいでしまう恐れもあります。
しかし、COC条項はM&Aを阻止する仕組みではなく、むしろ透明性の高い交渉環境を構築する契約的セーフティーネットともいえるでしょう。
吸収合併では改めて覚書の締結が必要?
吸収合併では、消滅会社が締結していた契約は会社法に基づく包括承継により、存続会社にそのまま引き継がれます。
そのため、契約書の名義変更や覚書の締結は、法的には原則不要です。
具体的には、合併前に旧社名で締結された契約書が存在しても、合併発効の瞬間にその法的効力は存続会社に移り、賃貸借契約や業務委託契約に対して個別に相手方の承認を取る必要はありません。
しかし実務上、取引先が「社名が変わったことで相手が違う会社になった」と認識し、不安を抱くケースは少なくありません。
その際、信頼関係の維持や混乱防止を目的に任意で覚書や確認書を締結することがあります。
これは安心感の醸成および対外的な説明のための実務措置であり、法的義務ではないものの、取引上は効果的な対応手段として有効です。
そのため、合併を進める際は法律論と実務対応の両面で判断が求められます。
COC条項など契約内容によっては別途対策が必要なケースも存在しますが、覚書については「不要」と断言できるわけではなく、「状況次第で任意に活用すればいい実務ツール」として捉えることが適切です。
【労働契約承継法】雇用契約や労働条件を承継する際の注意点
吸収合併においては会社法に基づく包括承継により従業員の労働契約が自動的に承継されるため、労働契約承継法(会社分割や事業譲渡に伴う労働契約の承継等に関する法律)は適用されません。
しかし複数の就業規則が併存すると運用上の混乱や不公平が起きやすく、合併の効力発生日に向けて雇用条件の統合が望まれます。
本章では、合併に伴う労働契約の承継における注意点を見ていきましょう。
労働契約を適正に承継するための手続きを確認する
吸収合併では、消滅会社の労働契約や就業規則、労働協約などは、会社法に基づく包括承継の仕組みにより存続会社に自動的に引き継がれます。
このため、労働契約の承継にあたって従業員の個別同意は不要とされており、民法第625条第1項の適用は問題とならないと解されています。
しかし実務では、旧会社ごとに異なる就業規則や賃金体系、福利厚生制度が混在し、そのまま統合すると運用に混乱が生じるリスクがあります。
そのため、合併の効力発生日に向けて、労働契約や就業規則を事前に整理しておく仕組みが必要です。
具体的には、合併契約と並行して「効力発生日に新規の労働契約を適用する」「従業員ごとに書面で同意を取得する」「労働組合との協定によって統一ルールを定める」などの手続きが一般的に行われます。
これにより、合併後の制度運用が一本化され、管理上の不整合や不公平が生じにくくなるのです。
例えば、A社・B社という異なる制度を持つ企業が合併するときは、合併前に人事部門と法務部門が連携して、どの制度をベースに統合するか、変更内容や猶予期間をどうするかといった方針を明確にしておく必要があるでしょう。
この準備により、合併後に「どのルールが適用されるのか」といった従業員の疑問も事前に解消できます。
また、このような取り組みは法律上だけでなく、従業員の安心感を高め、労務トラブルを回避する効果もあります。
労働条件の変更が必要な場合は慎重に対応する
吸収合併に伴い、異なる就業規則や賃金制度を持つ企業間で労働条件を統一する過程では、不利益変更が不可避となる場合があります。
労働契約法第8条および第9条の定めにより、労働条件の不利益変更は原則として労働者の合意が必要です。また、第10条に基づき、労働者の個別合意なしに就業規則を変更する場合には、「合理性」が厳格に判断されます。
合理性の判断には、①従業員が被る不利益の程度、②変更の必要性、③変更後の内容の相当性、④労働組合や従業員代表との交渉経過などが総合的に考慮されるのです。
さらに、不利益変更を行う場合は、当該就業規則の改定後に従業員への「周知」が法定で義務付けられており、例えば就業規則を配布する、電子媒体で閲覧可能にする、職場に掲示するなど、確実に従業員が変更内容を認識できる状態に置かなければなりません。
合理性の判断がクリアされない場合や、従業員の反対や懸念が強い場合には、合意に基づく変更となり、労働組合または従業員代表との十分な協議が必要です。
特に、賃金の削減や退職金の変更といった重大な見直しを行う際には、企業は十分な説明と代替措置(移行措置や補償)を用意して不公平感を解消し、不合理な不利益をできる限り抑える努力が求められます。
実務上は、合併の効力発生日に合わせてスケジュールを組み、就業規則や給与制度統合の方針説明を含む「移行計画書」を作成することが望ましいです。
また、文書で個別説明内容や協議履歴を記録し、不服申し立てなど将来のトラブルに備えておくことが重要です。
従業員に対して誠実な情報提供と説明を行う
吸収合併において、従業員は最も大きな影響を受ける立場にいるため、法的義務はないものの丁寧な情報提供が統合において重要になります。
従業員の不安や関心事は、「雇用はどうなるのか」「給与・待遇に変化はあるか」といった点に集中するため、合併実行段階では、これら基本情報を確実に伝えることが大切です。
実務経験によれば、従業員に通知しないまま合併を進めると、情報不足による憶測や不満が抑えきれず、モチベーション低下や離職のリスクが急増します。
まず、合併の基本的な内容(目的、スケジュール、従業員の雇用保証、配置や業務内容の変更有無)を明示が必要です。
特に、「雇用は継続される」「現在の雇用条件は合併後も維持される」ことを明確にすることで、安心感を醸成できます。
その後、部署統合や人事異動、研修体制など具体的な展望についても説明し、従業員にとっての影響を可視化しましょう。
また、説明のタイミングも重要であり、基本合意前は企業情報が最も機密であるため、経営幹部・キーマンへの先行説明が適切です。
その後、最終契約直後やクロージング後に一般従業員に対する説明会を開催し、質問や懸念に直接応えることが望ましいです。
こうしたフローを設けることで、企業全体の信頼関係が維持されやすくなります。
さらに、説明会だけでなく社内報・イントラネットによる情報開示や、個別面談を通じて個々の不安や条件変更に対応するプロセスも有効です。
内容が重く複雑な場合は、資料と併せてFAQ形式で展開することで理解の促進につながります。
まとめ
吸収合併では、消滅会社の契約や労働条件が存続会社に包括承継され、基本的に再契約は不要です。
ただし、支配権移転時に契約解除権が発生するチェンジオブコントロール条項(COC条項)の有無は必ず確認しなければなりません。
また、企業が複数の就業規則や制度を統合する際は、労働条件の合理性や補償措置を整えたうえで、従業員への丁寧な説明と合意形成を行うことで、合併後のトラブルを回避できます。
CINC Capitalは中小企業庁登録支援機関およびM&A仲介協会会員で、業界歴10年以上の専門家が目的に応じた最適手法を提案します。
秘密厳守のもと、スムーズな取引を実現します。まずは無料相談をご利用ください。