CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
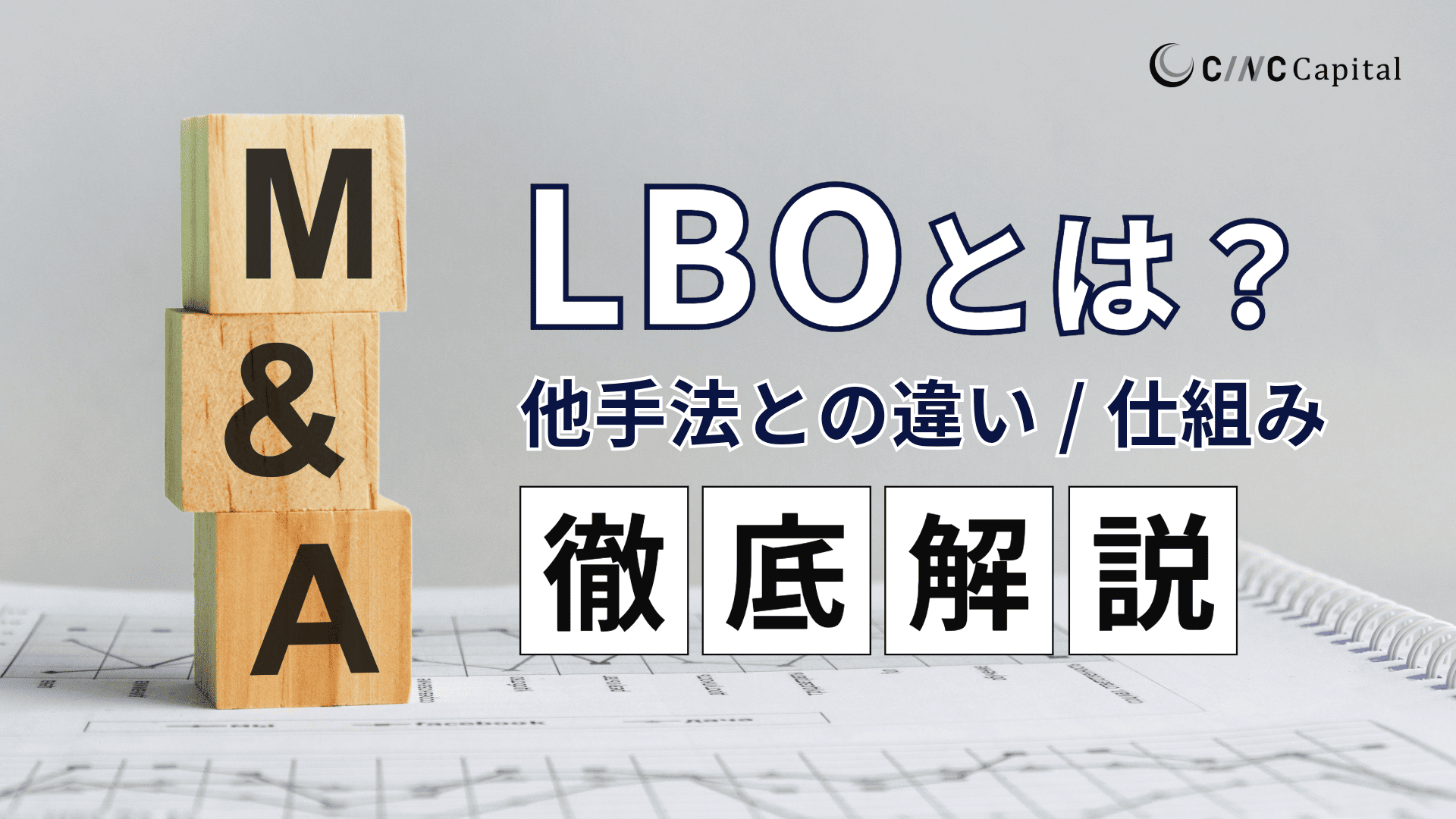
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
LBOとは?他手法との違いや仕組み、メリット・デメリットについて
事業承継や経営資源の再編を目的として企業売却を検討する経営者の方にとって、どのような手法で売却を進めるかは極めて重要な判断となります。中でもLBOは、買い手が借り入れを活用して企業を取得するスキームとして注目されています。
LBOは、短期間での資金化や企業価値の適正な評価を実現できる可能性があり、売り手にとっても有力な選択肢の一つです。
本記事では、LBOの仕組みやMBO・EBOとの違い、LBOの流れ、売り手・買い手それぞれのメリット・デメリットを解説します。
目次
LBOとは?
LBOは、企業買収の手法の一つで、買収資金の大部分を借入金で賄うことが特徴です。ここでは、LBOの概要や他の手法との違いについて解説します。
LBOの概要と仕組み
LBOとは「Leveraged Buyout(レバレッジド・バイアウト)」の略で、企業買収の際に自社の資金だけでなく借入金も活用して事業を買収する手法です。
LBOでは、買収完了後に取得した企業の資産やキャッシュフローを担保として金融機関から資金を調達することが特徴であり、買い手は少ない自己資金で大規模な買収を実現できます。買収時には特別目的会社(SPC)を設立し、そのSPCが融資を受けて買収を実行した後、買収した企業と合併するという流れが一般的です。
例えば、2020年に行われた昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)による日立化成のLBOでは、総額約9600億円の資金が投じられました。資金のほぼ全額は、みずほ銀行や日本政策投資銀行からの借り入れや優先株発行による出資で調達しました。LBOは特にPEファンドによって積極的に活用されています。
PEファンドとは「Private Equity Fund(プライベート・エクイティファンド)」の略です。PEファンドは未上場企業への投資を専門とする投資ファンドで、投資家から集めた資金をもとに企業や事業を買収し、経営改善によって企業価値を高めたうえで売却し、利益を得るというビジネスモデルを採用しています。
ただし、LBOによる企業買収には、一定のリスクが伴います。PEファンドは、買収後の経営改善によって、借入金の返済に十分なキャッシュフローを生み出す必要があるためです。そのため、LBOを実施する際には、対象企業が安定したキャッシュフローを有しているかどうか、将来的な成長が見込めるか、経営改善の余地があるかといった点を綿密に分析します。分析の内容を踏まえたうえで、買収後の経営戦略を慎重に立案していくのです。
【出典】昭和電工株式会社「資金調達、連結子会社の減資及び特定子会社の異動に関するお知らせ」
【出典】昭和電工株式会社「日立化成株式会社株式(証券コード 4217)に対する公開買付けの結果及び子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ」
日本におけるLBOの活用状況
日本では、主にPEファンドや投資会社がLBOを活用して企業買収を行うケースが多く見られます。特に事業承継問題を抱える中小企業において、後継者不在の場合にPEファンドがLBOを活用して買収し、経営改善後に次の買い手に譲渡するというスキームが注目されています。
また、日本の金融機関も中小企業のM&Aへの融資に積極的になっており、適切な事業計画とキャッシュフロー見通しがあれば、LBOに必要な資金調達の環境は整いつつあります。
LBOの流れ
SPCの設立から借入金の返済までがLBOを行う一連の流れです。一見複雑に見えるかもしれませんが、主に5つのステップに分かれています。
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
特別目的会社(SPC)の設立
LBOの初めのステップとして、特別目的会社(SPC)の設立が行われます。SPCとは「Special Purpose Company(スペシャル・パーパス・カンパニー)」の略で、特定の目的のために設立される法人のことです。主に資産の流動化や特定事業の運営を目的として設立されます。
SPCは特定の目的のために設立されるため、金融機関はその目的に基づいて融資を行うことができます。SPCの設立により、買収対象企業の信用力に依存せず、より良い条件で資金を調達できる可能性があるのです。LBOでは、買収を行うためにまず買い手企業がSPCを株式会社の形態で設立します。
資金調達
次に、SPCが金融機関からLBOファイナンスを行います。LBOは買収資金の大部分を借り入れで賄うため、資金を調達しなければなりません。
金融機関から融資を受ける際には、売り手企業の資産やキャッシュフローを担保にすることが一般的です。また、新たな社債や株式を発行して必要な資金をSPCに集めます。
SPCが売り手を買収
資金調達が完了した後、SPCが用意した資金を使って売り手企業の株式を買い集めます。買収が完了した時点で、SPCが実質的な買収主体となります。
売り手側とSPCが合併
買収が完了した後に行われるのが、SPCと売り手企業の合併です。合併により、売り手企業の資産と負債はSPCに引き継がれ、買収の一環としての経営統合が進められます。
しかし場合によっては、SPCを特殊会社として維持し、ホールディングス体制を構築する目的や、売り手の許認可を継続させるためなどの理由から、SPCを解散せずに存続させるケースもあります。
借入の返済
合併後、LBOローンに基づく借入金の返済を行います。返済主体は売り手企業であり、融資の早期返済が求められます。なぜなら、返済期間中は投資家によって収益確保のために厳しい経営条件が課される可能性があるためです。
投資家の目的はあくまで投資に対するリターンの最大化にあるため、売り手企業は保有資産を最大限に活用し、短期間での返済完了を目指すのが一般的です。
そのため、企業側はLBOローンに伴う多数の特約条項に抵触しないよう、社内の管理体制を整備する必要があります。また、LBOローンの返済や金利負担は軽視できず、資金繰りのコントロールは従来以上に経営の重要な課題となります。
【売り手側】LBOのメリット・デメリット
LBOには、売り手側、買い手側の双方に特有のメリットとデメリットがあります。ここでは、売り手側の視点からLBOのメリットとデメリットについて解説します。
売り手側のメリット
売り手側にとってのLBOのメリットは、迅速な取引が可能であることです。LBOを活用することで、十分な自己資金を持たない買い手でも買収が可能になるため、より多くの買い手候補と交渉できる可能性があります。これにより、売却機会が増え、より良い条件での売却につながる場合があります。
また、LBOによる売却は、企業価値の適切な評価につながる可能性もあります。特にPEファンドなどの専門的な買い手は企業価値評価の経験が豊富であるため、企業のポテンシャルが適切に評価される契機となり得るでしょう。
さらに、売却する企業にとっては、新しい経営者や投資家のもとでの成長機会が生まれます。PEファンドなどの買い手は経営改善や事業拡大のノウハウを持っていることが多く、対象企業の従業員や事業にとっては新たな成長の機会となる可能性があります。
売り手側のデメリット
LBOの売り手側のデメリットは、経営権の移転が前提となることです。
LBOは通常、買収側が経営権を確保するために十分な株式取得を目指します。多くの場合、売り手企業の経営陣は一定の役割変更や退任を求められます。買い手である投資ファンドが新たな経営陣を導入することが多いため、企業の文化や経営方針が大きく変わることがあります。
また、LBOは借入金返済のプレッシャーから短期的な収益改善を強く求められるため、長期的な視点での経営判断が制限される可能性があります。これにより、従業員や取引先との関係性、事業の持続可能性などに影響を与えることもあるでしょう。
さらに、LBOでは買い手が投資リターンを最大化するために、一定期間後に企業を再売却することも多く、短期間で複数回の所有者変更が起こるおそれがあります。これにより、企業の長期的な安定性や戦略に影響を与える場合があります。
【買い手側】LBOのメリット・デメリット
買い手側から見たLBOは、適切に利用されれば大きな利益をもたらす可能性を持っていますが、同時にリスクも存在します。
ここでは、買い手側から見たLBOのメリットとデメリットについて解説します。
買い手側のメリット
買い手側にとってLBOの魅力の一つは、少ない自己資金で大きな買収が可能になることです。
LBOでは主に借入金を利用して企業を買収するため、自己資金の投入を最小限に抑えながらも大規模な買収ができます。これにより、投資家の自己資本利益率(ROE)を高める可能性があります。自己資金が少なくて済むため、成功時のリターン率が高くなる「レバレッジ効果」が期待できるのです。
さらに、LBOによる企業買収は、買収後の企業価値向上戦略を駆使して高いリターンを見込めます。買収後に経営効率を改善し、企業価値を高めて、企業の将来的なパフォーマンスを向上させることができるからです。また、買収後の経営改善によって生み出された余剰キャッシュフローを借入金の返済に充てることで、財務体質を改善しながら企業価値を高めていくことが可能です。
買い手側のデメリット
LBOを活用する買い手側には、いくつかの特有のデメリットがあります。その一つが、財務上の制約が生じる点です。
LBOを行う際には、通常、金融機関から多額の借り入れを行います。このとき、金融機関はリスク管理のためにコベナンツと呼ばれる財務制限条項を設けることがあります。例えば、一定の財務比率の維持や追加借入の制限などが設定されることがあります。これらの財務制限があることで、買収後に予期せぬ事業環境の変化があった場合、追加の設備投資や事業投資が制限される可能性があります。
また、定期的な借入金の返済が必要となるため、短期的なキャッシュフロー改善を優先せざるを得ない場合もあるでしょう。さらに、LBOの大きなリスクは、高いレバレッジ(借入比率)による「両刃の剣」効果です。
業績が好調な場合は自己資本に対するリターンが増幅されますが、逆に業績が当初の計画を下回った場合は、固定的な借入金返済の負担が重くのしかかり、経営危機に陥るリスクが高まります。金利上昇リスクや景気変動リスクにも注意が必要です。
まとめ|LBOを検討する際はメリットとデメリットをしっかり把握しよう
LBOは、買い手が借り入れを活用して企業を取得する手法として、近年の日本企業のM&A市場でも活用事例が増えています。例えば、経済産業省/中小企業庁の「中小M&A推進計画」によると、中小企業のM&A件数は年々増加傾向にあり、その中でLBOを活用した案件も増えています。
ただし、LBOは借り入れによる資金調達が基本となるため、財務上のリスクが増大し、経営に重圧がかかる可能性も高まります。特に返済が滞ると、企業経営自体が危機に陥る可能性もあるため、慎重なプランニングと、専門的な知見に基づいた戦略的判断が不可欠です。
【出典】中小企業庁『「中小M&A推進計画」の主な取組状況~補足資料~』
企業売却をご検討中の経営者の方は、LBOを含めた最適なスキームの選定に向けて、ぜひ一度、弊社までご相談ください。弊社はM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。

















