CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
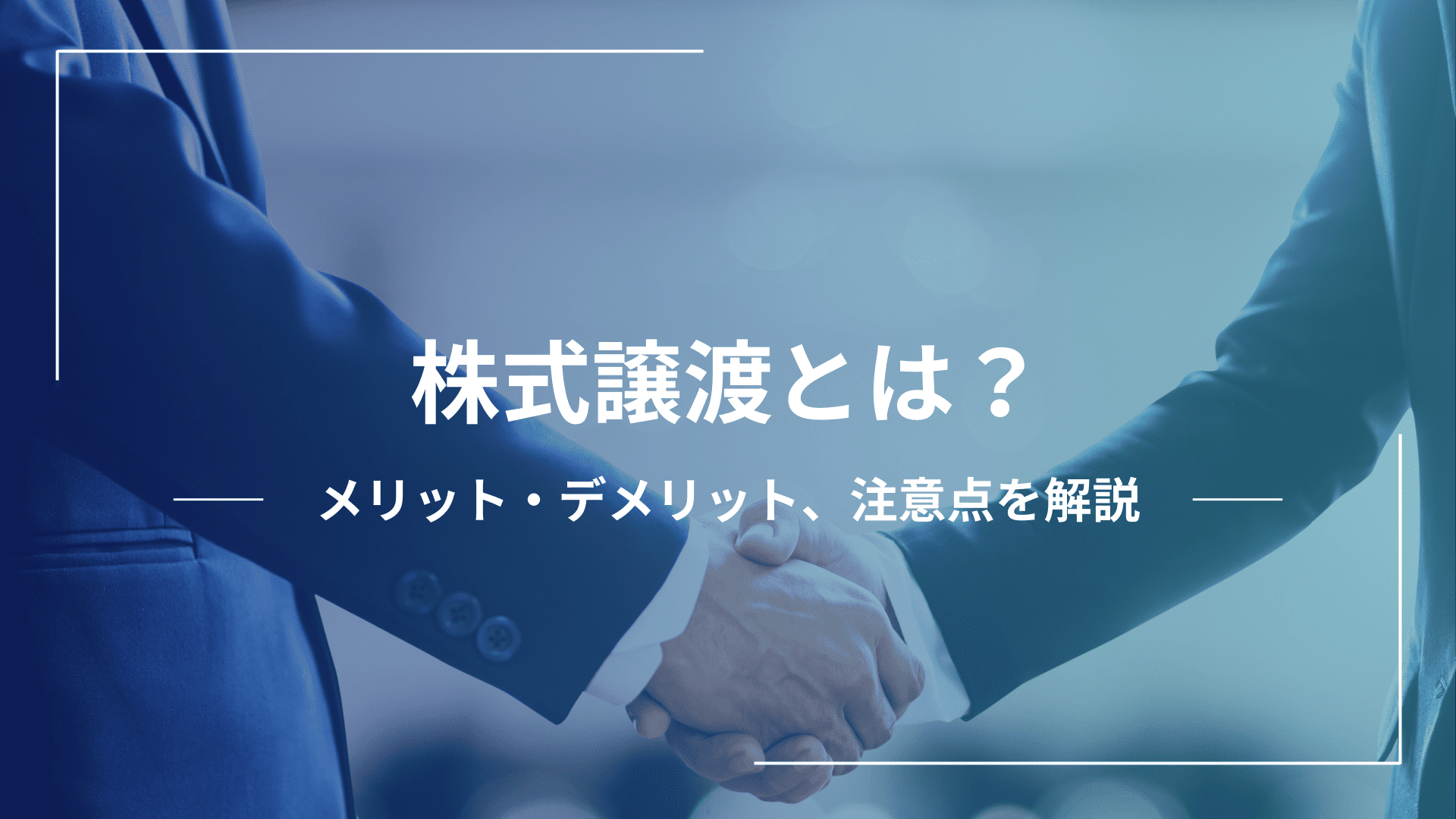
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.07.15
株式譲渡とは?メリットやデメリット、方法、手続きの流れ、税金をわかりやすく解説
株式譲渡は、企業の経営権を移転する方法として幅広く利用されています。
この記事では、株式譲渡の基本から事業譲渡や吸収合併との違い、メリット・デメリット、手続きの流れまで初心者にもわかりやすく解説します。
目次
株式譲渡とは?
株式譲渡は、会社の所有権を構成する株式を株主から第三者へ譲り渡すことで、経営権を移転する方法です。
会社自体が契約主体になるわけではなく、株主個人と譲受人との間で取引が完結します。
このため、会社の法人格や事業はそのまま維持され、従業員や取引先との契約も基本的には継続します。
中小企業の事業承継や、大企業のM&Aでも利用される手法で、経営権を迅速かつ比較的簡単に移転できる点が特徴です。
ただし、株式の譲渡には会社法上の制限が設けられている場合があり、譲渡制限株式を扱う際には会社の承認が必要になります。
譲渡の適正性を確保するために、株価の算定や税務処理の確認も重要です。
株式譲渡と事業譲渡との違い
株式譲渡と事業譲渡は、いずれも会社の経営資源を移転する手段ですが、仕組みが根本的に異なります。
株式譲渡では株主が株式を手放すだけで、会社の権利義務や契約はそのまま維持されます。
一方、事業譲渡では会社が事業単位で資産や負債、契約を第三者へ直接移転するため、取引先や従業員の同意が必要になることが多いです。
例えば、事業譲渡では許認可や契約が移転のたびに承認を受ける必要がありますが、株式譲渡であれば法人の主体は変わらないため、こうした手続きが不要になる場合がほとんどです。
このため、スムーズに経営権を移転したい場合は株式譲渡が選ばれることが多いです。
株式譲渡と吸収合併との違い
株式譲渡と吸収合併も混同されやすい手法ですが、法的な位置づけが異なります。
吸収合併では、存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に引き継ぎ、消滅会社は法人格が消滅します。
一方、株式譲渡はあくまで株主の交代にとどまり、会社自体は存続します。
例えば、吸収合併では組織統合に伴い会社の名称や内部制度が大きく変わるケースがありますが、株式譲渡では法人や契約関係は原則として変わらずに引き継がれます。
事業の連続性を維持しながら経営権のみを移す場合、株式譲渡は比較的手間の少ない手段といえるでしょう。
株式譲渡の方法
株式譲渡には、相手と直接交渉する方法から市場を通じた買付けまで、いくつかの手段があります。
それぞれの特徴を理解し、状況に合った方法を選ぶことが大切です。
- 相対取引
- 市場買付け
- 公開買付け(TOB)
相対取引
株式譲渡の中でも最も一般的なのが相対取引です。
これは売り手と買い手が当事者間で直接交渉を行い、条件を決定する方法です。
柔軟に条件を調整できるため、中小企業の事業承継や非上場株式の売買で多く利用されます。
例えば、譲渡価格や支払い方法、表明保証の内容などを当事者同士で自由に取り決めることが可能です。
ただし、買い手候補の選定から条件交渉までを自力で行う必要があるため、手続きが煩雑になりやすく、専門家の支援を受けながら進めるのが一般的です。
取引の透明性を確保し、将来の紛争を防ぐためにも、契約内容は詳細に定めておくことが重要です。
市場買付け
市場買付けは、上場企業の株式譲渡で活用される方法で、証券取引所を通じて株式を購入します。
取引所の仕組みを利用するため、相手方との個別交渉は不要です。
例えば、株式を取得したい買い手が市場に注文を出し、希望価格に応じて自動的に売買が成立します。
取引の透明性が高く、流動性のある株式であれば比較的迅速に多くの株式を取得できます。
一方で、市場価格の変動に影響されやすく、思うように取得できない場合もあります。
短期間に一定以上の株式をまとめて取得したいときは、後述する公開買付けの方が適しています。
公開買付け(TOB)
公開買付け(TOB)は、上場企業の株式を一定数以上取得する場合に使われる手法です。
証券取引所外で、あらかじめ買付価格・期間・株数などを公告し、株主に広く買付けを呼びかけます。
例えば、企業買収や経営権の取得を目的に、買い手が市場より高い価格を提示して応募を募るケースも珍しくありません。
公開買付けは法的な手続きや公告義務が厳格に定められており、透明性が高い反面、届出や開示が必要で準備に時間とコストがかかります。
特に上場企業の経営権を取得する場合、一定以上の株式取得は原則としてTOBを通じて行う必要があるため、計画的な進行が求められます。
TOB(株式公開買い付け)の事例はこちらをご覧ください。
【売り手側】株式譲渡のメリットとデメリット
株式譲渡を選ぶことで、売り手には資金確保や事業承継の面で多くの利点があります。
しかし同時に注意すべきリスクやデメリットも存在します。
ここでは主なポイントを整理します。
メリット
- 譲渡対価を受け取り資金を確保できる
- 許認可や契約関係をそのまま引き継げる
- 経営リスクや責任を軽減できる
- 後継者問題を解消できる
- 事業の継続性を維持しやすい
譲渡対価を受け取り資金を確保できる
株式譲渡の大きな魅力は、株式の売却によってまとまった資金を手に入れられる点です。
特に経営者が引退を考えている場合、譲渡対価を老後資金や新たな投資資金に充てられます。
例えば、業績が安定している企業の株式は高い評価を受けやすく、大きな譲渡益を期待できます。
早期に資金を確保したい場合に有効な選択肢です。
許認可や契約関係をそのまま引き継げる
株式譲渡は会社の法人格が変わらないため、許認可や取引契約、従業員との雇用契約が自動的に維持されます。
事業譲渡のように契約先の同意を取り直す必要がないのは大きな利点です。
例えば、許認可の再取得が難しい業種でもスムーズに経営権を移行できます。
経営リスクや責任を軽減できる
株式を手放すことで、経営判断や業績の責任から解放されます。
特に長期的な資金繰りや競争環境に悩んでいる経営者にとって、大きな心理的負担の軽減につながります。
譲渡後は新オーナーに経営権が移行するため、責任の範囲が明確に区切られます。
後継者問題を解消できる
親族や社内に適任者がいない場合でも、第三者へ株式を譲渡すれば経営のバトンを渡せます。
後継者不在に悩む中小企業では、株式譲渡が事業承継の有力な手段となります。
これにより、会社の存続と従業員の雇用維持を両立できます。
【関連記事】【中小企業】後継者不足の現状は?
事業の継続性を維持しやすい
株式譲渡では法人格がそのまま残るため、顧客や取引先との関係性を継続しやすい点もメリットです。
例えば、ブランドやサービスを変えずに経営権だけを移行できるため、事業の安定性を保てます。
デメリット
- 全株式の譲渡が難航する場合がある
- 不採算事業の影響で価格が下がる
- 情報が漏洩するリスクがある
- 譲渡後に経営方針が変更される可能性がある
- 表明保証責任を負う可能性がある
全株式の譲渡が難航する場合がある
株式をすべて譲渡するには、他の株主や関係者の調整が必要です。
特に株主が複数いる場合、交渉が長期化しやすく、全株取得の条件整備が難航するリスクがあります。
不採算事業の影響で価格が下がる
会社全体を譲渡するため、不採算事業や負債も譲受人が引き継ぎます。
その影響で企業価値が低く評価され、譲渡価格が下がることがあります。
資産の整理や業績改善が求められるケースもあります。
情報が漏洩するリスクがある
譲渡交渉の過程で財務情報や契約内容を開示する必要があり、機密情報が漏れる可能性があります。
秘密保持契約を締結するなど、情報管理の徹底が欠かせません。
譲渡後に経営方針が変更される可能性がある
新しい経営者が方針を変え、従来の経営理念や社風が維持されないケースもあります。
例えば、従業員の処遇や事業戦略が一変する場合があるため、事前に方針を確認することが大切です。
表明保証責任を負う可能性がある
株式譲渡契約では、売り手が会社の財務や法的状況について一定の表明保証を行います。
後から問題が発覚した場合、損害賠償を請求される可能性があるため、リスクを十分理解したうえで契約を締結する必要があります。
【買い手側】株式譲渡のメリットとデメリット
買い手側にとって株式譲渡は、経営権の早期取得や事業拡大を実現できる有効な手段です。
一方で、負債承継や文化の統合など注意が必要な点も多く存在します。
メリット
- 経営権を迅速に取得できる
- 既存の従業員や業務を引き継げる
- ブランドやノウハウを承継できる
- 新規市場に参入しやすい
- 比較的手続きが簡単である
経営権を迅速に取得できる
株式譲渡は株式を取得するだけで経営権を一括して手に入れられます。
ほかの手法に比べ、会社の承継に時間がかからないのが特徴です。
例えば、事業譲渡や合併では契約や許認可の移転に手間がかかりますが、株式譲渡なら法人格が変わらず、スムーズにオーナーシップが移ります。
既存の従業員や業務を引き継げる
株式譲渡では、会社が保有する雇用契約や取引契約が原則そのまま残ります。
そのため、従業員をはじめ、取引先や契約先との関係を維持しながら経営を引き継ぐことができるのが利点です。
事業の連続性を重視する場合に特に有効です。
ブランドやノウハウを承継できる
会社のブランドや営業基盤、業務ノウハウを丸ごと引き継げる点も大きな魅力です。
買い手側はゼロから事業を立ち上げる手間を省き、既に確立された信用や仕組みを活用できます。
例えば、老舗企業を取得することでブランド価値を即座に自社の資産にできます。
新規市場に参入しやすい
買い手企業が未開拓の業界や地域に進出する際、株式譲渡はスピーディーな市場参入手段になります。
既存の事業基盤や販路を活用しやすく、新規開拓に伴うリスクを抑えられるのが強みです。
戦略的拡大を目指す場合に選ばれます。
比較的手続きが簡単である
事業譲渡や合併と比べ、株式譲渡は必要な手続きや許認可の変更が少ないのが特徴です。
契約のスキームもシンプルで、短期間で完了できるため、M&Aの実務負担を軽減できます。
デメリット
- 譲渡側の負債を引き継ぐリスクがある
- 多額の資金を調達する必要がある
- 企業文化の統合が難航するおそれがある
- 収益性が期待通りにならないリスクがある
- 既存株主との調整が必要になる
譲渡側の負債を引き継ぐリスクがある
株式を取得することで、会社が抱える負債や訴訟リスクも引き継ぐことになります。
例えば、簿外債務が後から発覚する可能性もあるため、デューデリジェンスを徹底する必要があります。
多額の資金を調達する必要がある
会社全体を取得するためには、相応の買収資金を準備しなければなりません。
特に株価評価が高い場合、自己資金だけでは賄えず、借入や出資を調達する負担が大きくなることもあります。
企業文化の統合が難航するおそれがある
異なる企業文化を持つ組織同士が一つになるため、価値観や業務慣行の統合に時間がかかる場合があります。
特に中小企業の買収では、従業員のモチベーション低下や離職リスクが高まることもあります。
収益性が期待通りにならないリスクがある
買収時の業績が将来的に維持できる保証はなく、想定していた収益が確保できないリスクがあります。
例えば、主要取引先が離れたり、市場環境が悪化するケースもあります。十分な事前調査が重要です。
既存株主との調整が必要になる
一部株主が株式を手放さず残る場合、経営権や議決権の調整が必要です。
少数株主との意見の不一致が、経営の意思決定を複雑にする場合もあります。
譲渡契約の段階で調整策を検討しておくことが欠かせません。
株式譲渡で発生する税金
株式譲渡で得た利益は譲渡所得として課税対象になります。
上場株式と非上場株式の税務上の扱い
上場株式と非上場株式では税務上の扱いが若干異なるため、以下の表を参考にしてください。
|
区分 |
税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
課税方法 |
主な注意点 |
|---|---|---|---|
|
上場株式 |
20.315% |
申告分離課税 |
特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要も可 |
|
非上場株式 |
20.315% |
申告分離課税 |
時価評価の算定が必要 |
譲渡益は「譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算します。
特に非上場株式は客観的な時価評価が重要で、親族間の取引では税務署から確認を受けることもあります。
適切な評価や手続きを怠ると後日修正申告や追徴課税が発生するため、譲渡を検討する際は税理士に相談し、事前に納税額をシミュレーションしておくことが安心です。
売り手と買い手の税務上の扱い
株式譲渡に係る税務処理は、売り手と買い手で大きく異なります。
売り手の税務処理
売り手(譲渡側)が株式を売却する際には、譲渡所得税が課税されます。
これは、株式譲渡によって得られる利益は譲渡所得として計算されるためです。
譲渡の手法が株式譲渡の場合、以下の計算式で譲渡所得を導き出すことができます。
株式譲渡所得=譲渡収入-取得費※1-譲渡費用※2
株式譲渡の税負担=株式譲渡所得×20.315%
譲渡収入に取得費と譲渡費用を引いたものが株式譲渡所得です。
この株式譲渡所得に「20.315%」をかけたものが、株式譲渡の税負担となります。
売り手(譲渡側)は税負担があるので、この点は念頭に置いておきましょう。
※1 取得費:取得費か、譲渡収入5%いずれか大きい方を選択します。
※2 譲渡費用 : 仲介会社等へ支払う成功報酬など(譲渡に直接要した費用)が該当します。
※令和7年の1月から課税強化にあたり、追加納税が発生します。株式譲渡所得が10億円を超えると、株式譲渡所得×20.315%の税額に加え、追加納税(所得税、復興税)が生じます
買い手の税務処理
買い手が株式を取得する際には、贈与税や譲渡所得税は基本的に課税されません。
株式の取得そのものが資産の移転であり、即座に所得が発生するわけではありません。
取得した株式を売却するときに生じる利益は、譲渡所得として認識する必要があります。
株式を購入した時は、将来の売却時に発生する税務に注意を払いましょう。
株式譲渡の手続きの流れと進め方(株式譲渡制限会社の場合)
株式譲渡制限会社では、会社の承認手続きが必須となります。
ここでは、譲渡の準備から契約、名義変更までの具体的な流れを解説します。
- 譲渡先の選定や条件調整を行う
- 会社へ譲渡承認を請求する
- 承認決議を経て手続きを進める株式譲渡契約を締結する
- 株券を交付し代金を受け取る
- 株主名簿の名義書換を行う
- 税務申告など必要な届出を行う
1. 譲渡先の選定や条件調整を行う
まずは株式を譲渡する相手を選定し、価格や支払い方法など条件を決めます。
条件調整は譲渡交渉の中心であり、譲受人の信用や資金調達力を確認することが重要です。
例えば、後継者候補や取引先企業など複数の候補から最適な相手を選ぶケースもあります。
2. 会社へ譲渡承認を請求する
譲渡制限会社では、株式を移転する際に会社の承認が必要です。
譲渡承認請求書を会社へ提出し、取締役会や株主総会で審議を受けます。
承認請求を怠ると手続きが無効になるため、必ず正式な書式で提出しましょう。
3. 承認決議を経て手続きを進める
会社は譲渡を承認するか否かを決議します。
承認が得られた場合は手続きを進められますが、拒否された場合は会社が買い取りなど代替措置を講じる義務を負います。
この承認決議の有無が大きな分岐点になります。
4. 株式譲渡契約を締結する
承認後、売り手と買い手で株式譲渡契約を結びます。
契約書には譲渡株数、対価、支払い期日、表明保証などを明記し、後のトラブル防止のため詳細に取り決めます。
専門家に契約内容を確認してもらうのが安全です。
5. 株券を交付し代金を受け取る
契約締結後、売り手は株券を買い手へ交付し、買い手は代金を支払います。
株券が発行されていない場合は、株主名簿の名義書換が効力発生日になります。
譲渡対価の支払い方法や期日は契約書で合意した内容に沿って実行します。
6. 株主名簿の名義書換を行う
株券交付後、会社に名義書換請求を行い、株主名簿を書き換えてもらいます。
これにより、買い手が正式な株主となります。
手続き完了日は株主権行使の基準となるため、速やかに対応しましょう。
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名(名称)および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗できません
【引用】会社法130条1項
この手続きを怠ると、譲渡の効力が正式に認められず、会社法上の株主としても認定されません。
株主名簿名義書換請求を提出し、正式に株主を変更しましょう。
7. 税務申告など必要な届出を行う
最後に、譲渡益が発生した場合は確定申告を行い、譲渡所得税の納付が必要です。
株式譲渡に関する届出や証憑の整理も早めに済ませます。
税務処理を怠るとペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。
株式譲渡を進めるうえでの注意点
株式譲渡を安全かつ円滑に進めるためには、法務・税務の確認や利害関係者との調整が欠かせません。
ここでは特に重要なポイントを解説します。
- 譲渡制限の有無を事前に確認する
- 適正な株価を設定する
- 契約内容を明確にしておく
- 税務上の取り扱いを理解する
- 関係者への周知や同意を得る
譲渡制限の有無を事前に確認する
株式譲渡制限会社では、株式の移転に会社の承認が必要です。譲渡制限の有無を確認せずに進めると、手続きが無効になるおそれがあります。
例えば、定款に「取締役会の承認が必要」と定めている場合は、正式な承認決議が必須です。
事前に定款や株主名簿を確認し、必要書類や承認フローを把握しておきましょう。
適正な株価を設定する
譲渡価格が不当に高い・低いと、後のトラブルや税務リスクを招きます。
適正な株価を設定するため、第三者機関の評価や直近の決算書を活用することが大切です。
例えば、純資産価額方式や類似業種比準方式を用いると、公正性を担保しやすいです。
評価根拠を明文化しておくと、株主や税務署への説明もスムーズになります。
契約内容を明確にしておく
株式譲渡契約には、譲渡株数や価格、支払い方法、表明保証などを詳細に記載する必要があります。
内容があいまいだと、支払い遅延や責任範囲のトラブルが発生しやすくなります。
例えば、簿外債務の取扱いや競業避止義務の有無なども明記し、リスクを軽減しましょう。
弁護士など専門家の確認を受けるのが安心です。
税務上の取り扱いを理解する
株式譲渡には譲渡益課税がかかる場合があります。課税対象や申告方法を正しく理解しないと、追徴課税などのリスクを負う可能性があります。
例えば、上場株と非上場株では税率や課税方法が異なるため注意が必要です。
事前に税理士へ相談し、シミュレーションを行っておくと安心です。
関係者への周知や同意を得る
株式譲渡は経営体制に大きな影響を与えるため、従業員や主要取引先、株主に丁寧に説明することが大切です。
情報共有が不足すると不信感や契約解消につながるおそれがあります。
例えば、従業員には雇用条件の変更がないことを説明し、安心感を持ってもらう配慮が重要です。
円滑な事業承継には関係者との信頼関係が不可欠です。
まとめ|株式譲渡の仕組みと進め方を正しく理解しよう
株式譲渡は、株主が株式を譲渡するだけで会社の法人格や契約関係をそのまま維持できるため、比較的手続きが簡単で事業の継続性を保ちやすい方法です。
相対取引や市場買付け、公開買付け(TOB)など複数の手段があり、目的や規模に応じて選択できます。
一方で、負債の承継や企業文化の統合、譲渡後の経営方針変更などのリスクも伴います。
円滑に株式譲渡を進めるには、譲渡制限の確認や適正な株価設定、契約内容の明確化、税務面の整理が不可欠です。
また、従業員や取引先への十分な説明を行い、信頼関係を築くことも重要です。
株式譲渡を検討する際は、専門家の助言を受けながら計画的に進めることで、将来のトラブルを防ぎ、安心して経営権の移行を実現できます。
CINC Capitalでは、M&A仲介会社としてM&Aや株式譲渡の相談を受け付けております。
業界歴10年以上、実績多数のプロアドバイザーがお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。

















