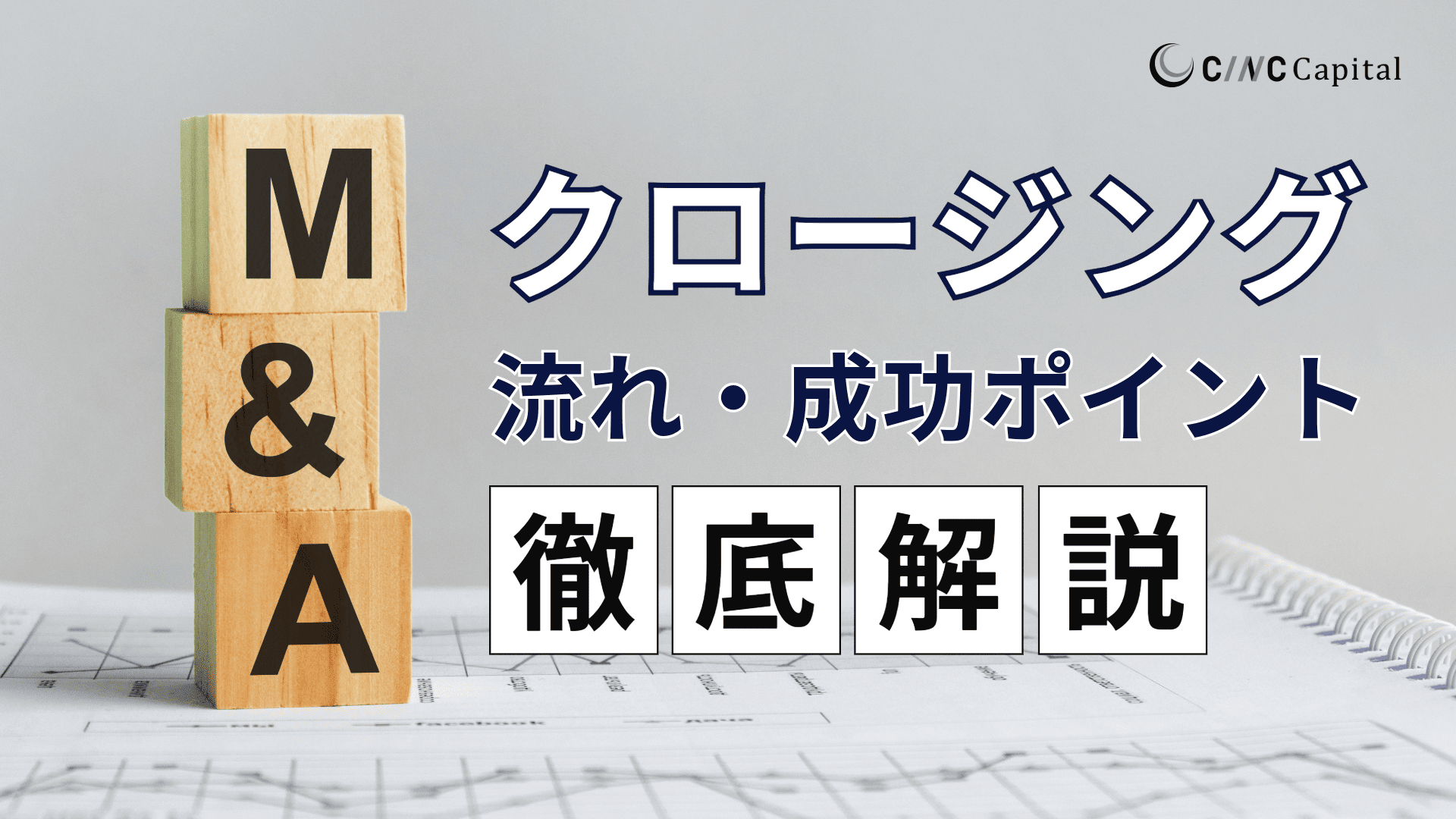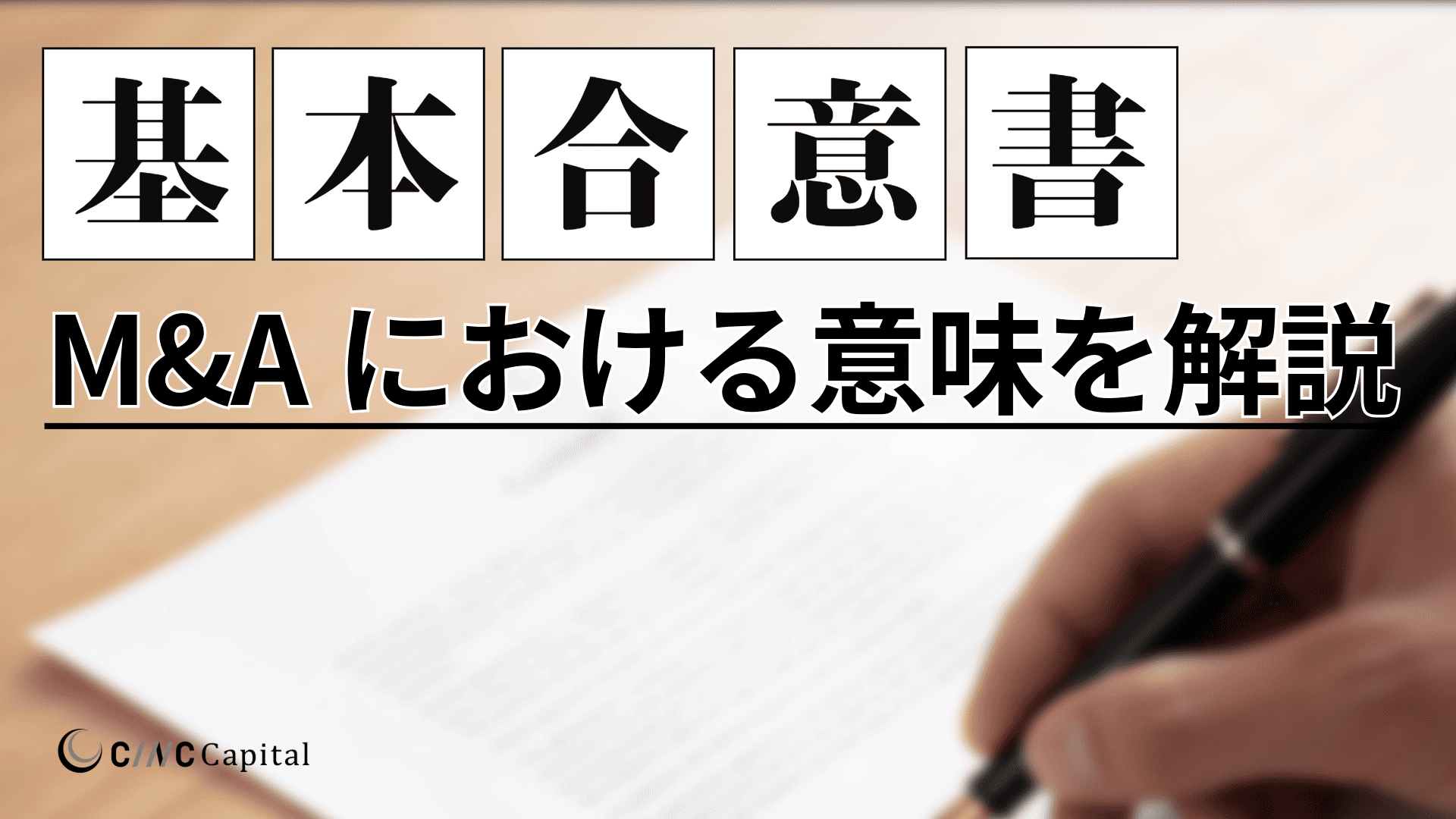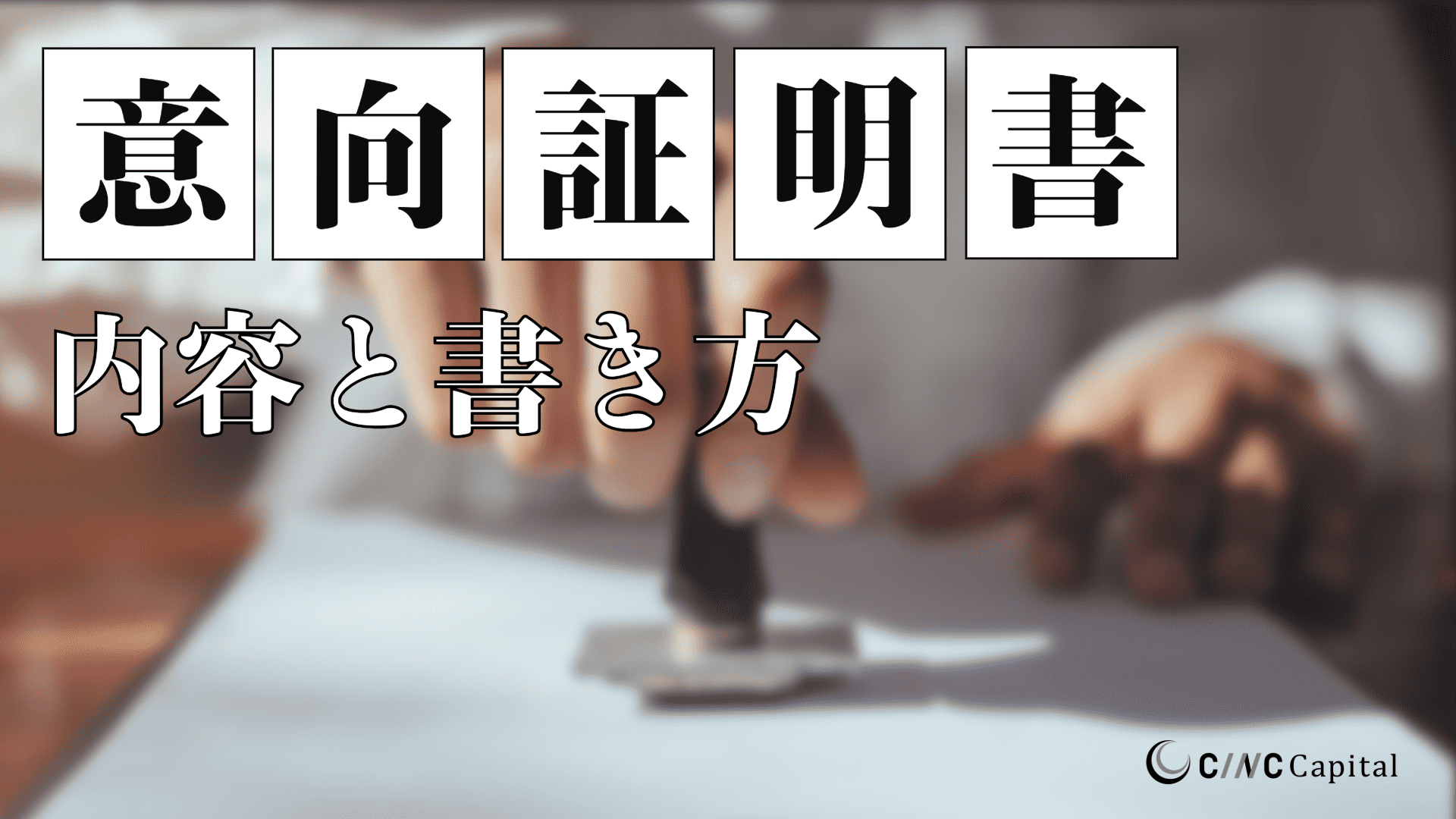CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
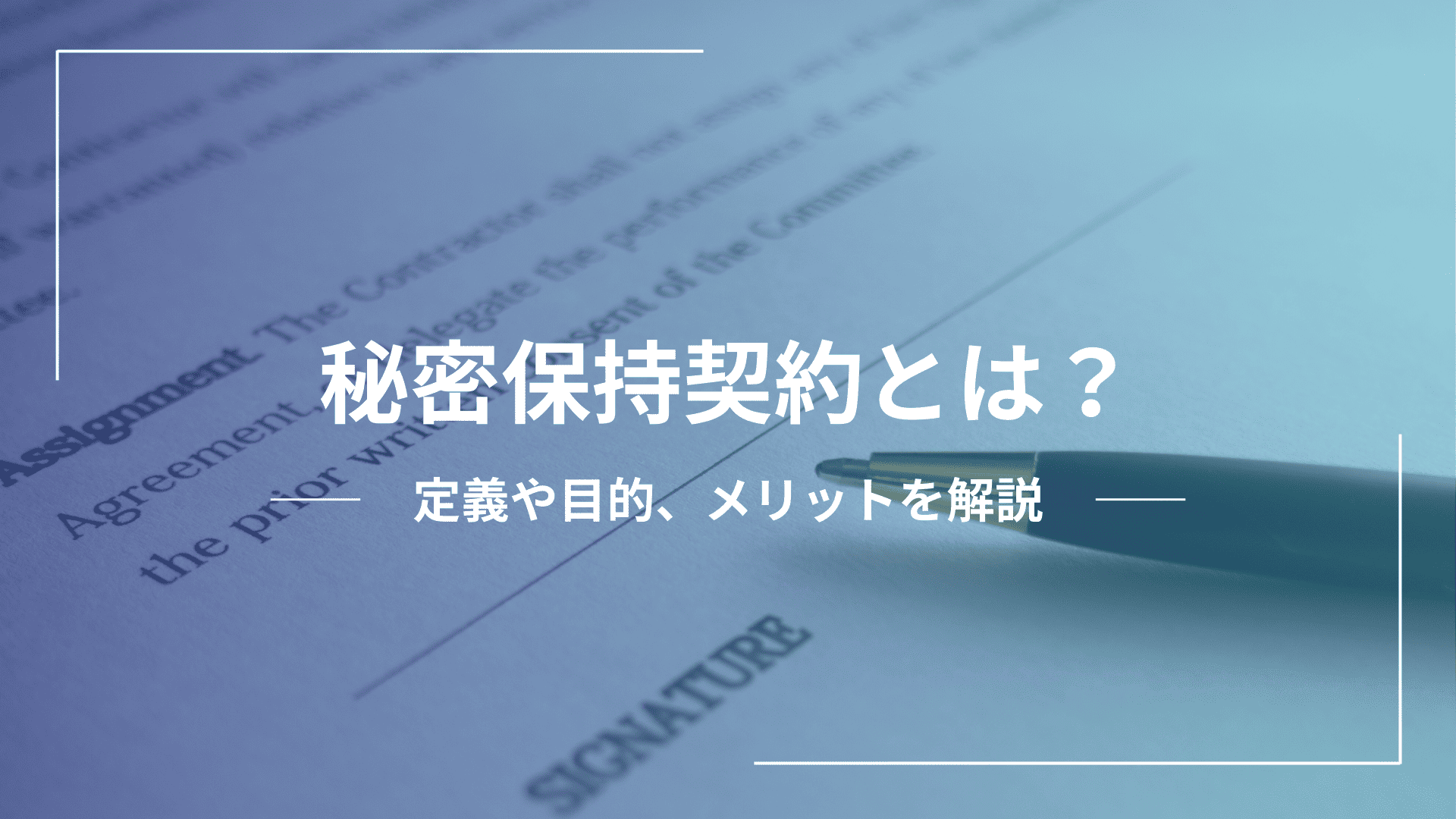
手続き・契約
- 最終更新日2025.06.26
M&Aの秘密保持契約(NDA)とは?目的や締結するメリットデメリット、契約条項、雛形、作成時のポイントを解説
M&Aを進めるうえで欠かせないのが「秘密保持契約(NDA)」です。
企業同士の機密情報のやり取りにおいて、信頼関係を築きつつ情報漏洩を防ぐために不可欠な契約です。
本記事では、NDAの基礎知識から目的、メリット・デメリット、契約書の条項や雛形、作成時の注意点まで実務に即した形で解説します。
目次
秘密保持契約(NDA)とは?
秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)とは、当事者間で開示された秘密情報を第三者に漏らさないことを約束する契約です。
M&Aなどの取引過程で、相手企業に財務状況や事業内容などの機密情報を開示する際に、情報漏洩を防ぐ目的で締結されます。
対象となる情報範囲や保持義務の期間、例外事項などを明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
機密保持契約との違い
秘密保持契約と機密保持契約は、法律的には基本的に同じ意味で、法的効力や内容には違いはありません。
どちらも業務上知り得た秘密情報を第三者に開示しないことを目的とした契約です。
秘密保持契約を締結する目的
秘密保持契約の主な目的は、機密情報の漏洩防止です。
M&Aにおいては、相手企業の経営状況や技術情報など、外部に漏れると企業価値や競争優位性に悪影響を与える情報が多く含まれます。
そのため、契約によって情報の範囲や取り扱い方法、責任の所在を明確にし、双方が安心して情報を開示できる環境を整えます。
また、情報漏洩リスクを最小化することで、円滑な交渉や意思決定が可能となります。
結果的に、信頼関係の構築や取引の円滑化にもつながるという重要な役割を担っています。
秘密保持契約を締結するメリット
秘密保持契約を結ぶ最大のメリットは、企業間で安心して情報を共有できることです。
交渉段階での情報開示がスムーズに行えるため、意思決定のスピードが向上します。
また、契約によって情報管理のルールが明文化されることで、万が一情報漏洩が発生した場合も、法的責任の所在を明確にできます。
例えば、M&A交渉で買収先企業が独自技術の詳細を開示する場合、秘密保持契約があればその技術の外部流出を防止できます。
さらに、秘密保持契約は情報漏洩が発生した場合の損害賠償条項を設定することができます。
この条項により、万が一情報が漏洩した場合に、相手方に補償を求めることができます。
競合企業等に機密情報が漏洩し、損害が発生した時は、その損失をカバーするための損害賠償を請求することも期待できます。
損害賠償条項の設定により、潜在的なリスクを事前に軽減することができるでしょう。
秘密保持契約を締結するデリット
一方で、秘密保持契約には注意すべきデメリットも存在します。
契約条項が厳しすぎると、必要な情報共有が制限され、交渉が停滞するリスクがあります。
また、秘密情報の定義が曖昧だった場合、後にトラブルに発展する可能性も否定できません。
例えば、「すべての業務情報」と広く定義した場合、どこまでが秘密に該当するのか判断が難しくなります。
その結果、意図せず契約違反を犯してしまうリスクもあります。
さらに、契約内容の交渉や見直しに時間とコストがかかる点もデメリットとして挙げられます。
こうした点を事前に把握し、バランスのとれた契約内容を目指すことが重要です。
秘密保持契約の契約条項と雛形
秘密保持契約には、売り手企業と買い手企業の情報を保護するために様々な契約条項が含まれます。
- 目的
- 秘密情報
- 秘密保持義務
- 秘密情報の破棄・返還
- 反社会勢力の排除
- 秘密情報の漏洩に関する義務
- 損害賠償
- 直接交渉の禁止
- 有効期間
- 協議事項
- 準拠法・管轄裁判所
- 署名捺印欄
ここでは、秘密保持契約の各契約条項の詳細を解説します。
目的
秘密保持契約の第1条では契約の「目的」が明記されることが多いです。
目的を明確にすることで、契約範囲外の情報が含まれないようにする役割があります。
「目的」の明確化は、契約範囲の限定と関係性の明確化に役立ちます。
秘密情報
秘密情報の対象となる情報を具体的に定める項目です。
CINC Capitalでは、秘密情報を「開示または提供された一切の情報」と定めております。
この秘密情報の範囲は各M&A仲介会社(M&Aアドバイザー)で内容が異なります。
ただし、この秘密情報は保護対象外となる内容についても併せて記載する必要があります。
既に公知の情報や、買い手企業から開示を受けた情報とは無関係に売り手企業が独自に開発した情報は、対象外となることが多いです。
秘密保持義務
秘密保持契約を締結した当事者は、「秘密保持義務」が課せられます。
ここでは具体的にどのように秘密を保持するのか、保持の範囲について記載があります。
ちなみにこの条項では「開示者」と「被開示者」について説明があります。
秘密情報を開示した当事者を「開示者」、秘密情報の開示を受けた当事者を「被開示者」とし、開示者と被開示者という言葉が各条項で用いられます。
秘密情報の破棄・返還
契約終了時の対応について記したものが「秘密情報の破棄・返還」です。
速やかに秘密情報を返還するか、適切な方法で破棄することが記載されます。
契約が終了する前に売り手企業から秘密情報の破棄や返還の要求があった場合の対応方法も記載されます。
秘密情報の返還が難しい場合の取り扱いについてもこの条項で記載するのが望ましいです。
反社会勢力の排除
秘密保持契約には「反社会勢力の排除」に関する条項 が含まれることが多いです。
経済活動の健全性を保つため、反社会勢力と関わりを持つ企業との取引の回避を目的に設定されます。
契約相手が反社会勢力と関りがあることが判明した場合に、契約を解除するための条文を盛り込みます。
「反社会勢力の排除」は社会からの信 頼関係の確保とリスク管理に寄与します。
秘密情報の漏洩に関する義務
秘密保持契約では「秘密情報の漏洩に関する義務」が規定されます。
この条項では実際に情報漏洩が起こった場合の対応方法について記載されます。
情報漏洩の発生時にはすぐに売り手企業へ報告する義務を設けることが多いです。
これにより、トラブル発生時に迅速な対応が可能になります。
損害賠償
秘密保持契約には「損害賠償」条項が含まれることが一般的です。
情報漏洩によって被った実際の損害額を請求できるように規定します。
「損害賠償」条項は契約違反時の法的手続きを円滑にする役割があります。
直接交渉の禁止
「直接交渉の禁止」は名前にある通り、今後M&Aを実施することが考えられる売り手企業と買い手企業がお互い直接交渉を禁止する条項です 。
ポイントは「事前の承諾なし」で直接交渉を行うことです。
売り手企業と買い手企業が交渉や取引 をしたい場合は、秘密保持契約を締結する前に相手方に相談しましょう。
有効期間
秘密保持契約の「有効期間」を明記します。
「契約日から〇年間有効」といった具体的な期間設定が行われることが一般的です。
ちなみにCINC Capitalがお客様と締結する秘密保持契約は、有効期間を1年間と定めていますが、「秘密保持義務」については3年間存続する ような取り決めになっています。
協議事項
秘密保持契約には「協議事項」の条項が設けられることがあります。
秘密保持契約の事項や内容に関わらず、売り手企業と買い手企業の間で疑問に思えることがあれば、誠実に協議をすることを目的に設定されます。
「契約にない事項、契約に関する疑義が生じた事項は、両当事者間で誠実に協議をする」のような記載をされることが多いです。
準拠法・管轄裁判所
秘密保持契約の準拠法は何か、紛争などが生じた場合の管轄裁判所が記載されます。
売り手企業と買い手企業で言い分が食い違ったときや契約の内容が契約書だけでは解釈できない時に準拠法は活用されます。
署名捺印欄
契約が双方によって正式に承認されたことを証明するために署名捺印欄が設けられます。
契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有します。印鑑は社印を使用します。
認印ではなく、実印を使用することが一般的です。
秘密保持契約の電子契約について
近年、秘密保持契約を電子契約で締結する事業者が増えています。
電子契約を利用することで、契約手続きを迅速に行える上、ペーパーレス化によるコスト削減が期待できるためです。
従来の紙ベースの契約では郵送や対面でのやり取りが必要でしたが、電子契約であればインターネット上で迅速に契約締結が完了します。
アクセス権限を設けたり、パスワードを適切に設定したりすれば、強固なセキュリティも確保できるでしょう。
なお、 CINC Capitalにおいても秘密保持契約の電子契約に対応しています。
電子契約について不明点がある方はお気軽にご相談ください。
秘密保持契約に違反するとどうなる?
秘密保持契約に違反した場合、損害賠償請求や契約解除といった重大な法的責任が発生します。
具体的には、漏洩した情報によって相手企業が損害を被った場合、その損害額の賠償を請求される可能性があります。
例えば、M&A交渉で開示された事業戦略が外部に漏れた結果、競合他社に先手を打たれてしまった場合などです。
また、故意または重過失による違反であれば、民事責任に加え刑事罰が科されることもあります。
こうしたリスクを防ぐには、契約内容を正しく理解し、情報管理体制を徹底することが求められます。
秘密保持義務違反が起こった場合の対処法
秘密保持契約を締結したあとに、万が一情報漏洩による損害や秘密保持義務への違反が発生した場合には、適切かつ厳格な対処が必要です。
秘密保持契約はビジネス上のリスクを最小限に抑えるために締結されますが、損害や違反が生じた場合の対処方法を明確にすることで、迅速かつ効果的に問題解決を図れます。
損害賠償請求など違反者に対する適切な制裁を実行することで、 従業員や取引先への影響を抑えられます。
対処法については必ず条項に記載しておきましょう。
秘密保持契約の注意点
秘密保持契約を結ぶ際は、条文の内容だけでなく、その運用面や実務上の落とし穴にも注意が必要です。
見落としがちなポイントを理解し、リスクを回避しましょう。
情報の定義を明確にする
秘密情報の範囲を明確に定めることは、契約を有効に機能させるうえで不可欠です。
情報の定義が曖昧なままだと、どこまでが秘密として保護されるべきか判断が難しくなり、契約違反のリスクが高まります。
例えば、「業務上知り得た情報すべて」といった抽象的な記載では、当事者間での解釈にずれが生じやすくなります。
契約書には、「書面で“秘密”と明記されたものに限る」など、秘密情報の形式や範囲を具体的に定義する記述を設けましょう。
こうした明文化によって、トラブル防止と実効性の確保につながります。
契約形態を適切に選択する
秘密保持契約は、「片務契約」と「双務契約」の2種類が存在し、どちらを選ぶかによって義務の範囲が変わってきます。
不適切な契約形態を選んでしまうと、想定外のリスクや義務を背負う可能性があります。
例えば、自社のみが情報を開示する場合に双務契約を結んでしまうと、不必要な義務を負うことになります。
情報のやり取りの実態に即して、契約形態を選ぶことが重要です。
事前に情報提供の有無や方向性を整理し、片務か双務かを明確に判断することが、トラブル回避の鍵となります。
社内外への周知を徹底する
秘密保持契約は、締結した本人同士だけが理解していれば良いというものではありません。
契約の内容を知らない従業員や委託先が情報漏洩を引き起こす可能性があるため、関係者への周知が不可欠です。
例えば、M&Aの過程で一部社員が相手企業の情報を誤って外部に話してしまうケースは少なくありません。
契約内容を社内マニュアルや研修などで共有し、関係者全体のリスク意識を高めることが必要です。
周知徹底を図ることで、契約違反の予防と情報管理体制の強化につながります。
秘密保持契約書を作成するときのポイント
秘密保持契約書の内容は、実務での運用に耐えうる設計である必要があります。
曖昧な条文や抜け漏れを防ぎ、実効性を持たせるための要点を確認しましょう。
情報共有の形式を明文化する
秘密情報とみなす条件を明文化することで、契約の解釈違いによるトラブルを防ぐことができます。
形式を定めないままだと、口頭で伝えた情報が秘密情報に該当するか否かが不明確になり、後の紛争につながるおそれがあります。
例えば、「秘密であると書面により明示された情報を対象とする」と明記すれば、証拠の有無や範囲が明確になります。
共有手段が多様化する現代において、電子メールやクラウド上のデータも含め、具体的に記述しておくことが実務的にも有効です。
これにより、情報保護の基準が明確になり、契約の実効性が高まります。
目的外使用を防止する
秘密情報の第三者への漏洩だけでなく、相手企業による目的外使用も防止しなければなりません。
契約に使用目的の限定がなければ、合法的に情報を流用されるリスクが残ります。
例えば、買収候補企業が開示した技術情報を、交渉を打ち切った後に他社事業に活用されるようなケースです。
このような事態を避けるには、「本契約の目的以外には使用してはならない」と明記し、違反時の責任についても規定しておく必要があります。
使用目的の明確化は、機密情報の保護における基本です。
義務期間を具体的に設定する
契約終了と同時に秘密保持義務が終了すると思い込むのは危険です。
情報の性質によっては、終了後も長期にわたり保護すべきケースが多くあります。
例えば、「契約終了後5年間は秘密保持義務を継続する」といった条文を設けることが一般的です。
これにより、交渉中止や契約終了後に発生する情報漏洩リスクを軽減できます。
また、保管義務の期間を明確にすることで、契約者間の認識齟齬を防ぎ、継続的な安全管理が可能になります。
実効性の高い契約にするためには、義務の終了条件を明記することが不可欠です。
秘密保持契約に関するよくある質問
秘密保持契約が意味ないと言われる理由は?
秘密保持契約が意味をなさないと言われる背景には、実際に契約違反が起きた際に、違反者が特定できず実効性に欠けるケースがあるためです。
契約で禁止されていても、情報漏洩の証拠を集めることが難しい場合、損害賠償請求などが困難になることがあります。
また、契約自体が形骸化していたり、曖昧な条文が含まれていたりすると、法的拘束力が弱まります。
しかしこれは契約の設計や運用の問題であり、適切に作成・運用されればNDAは非常に有効です。
秘密保持契約の期間終了後はどうなる?
契約期間が終了したからといって、すぐに秘密保持義務が解除されるとは限りません。
多くの契約では、契約終了後も一定期間、情報を保持し続ける義務が記載されています。
例えば「契約終了後5年間は秘密保持義務が継続する」などの条項が一般的です。
このため、契約終了後も引き続き注意を払う必要があります。
仮にその後、情報漏洩が発覚すれば、契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。
終了条件を明確にし、関係者に徹底しておくことが重要です。
秘密保持契約は複数社で締結されることはある?
秘密保持契約は2社間で締結されることが多いですが、複数社と同時に締結することも可能です。
特にM&Aプロセスにおいては、複数の買い手候補が存在するケースが多いため、それぞれと個別にNDAを結ぶことが一般的です。
この際は、すべての契約内容に一貫性があるかを確認し、内容の齟齬によるリスクを最小限に抑える必要があります。
また、情報提供の順序や範囲をコントロールする工夫も重要です。全社に同一条件で情報を提供することが、公平性の確保と法的リスクの回避につながります。
秘密保持契約書に収入印紙(印紙)は必要?
秘密保持契約書には、原則として収入印紙は必要ありません。
印紙税法では、金銭のやり取りを伴う契約が課税対象となるため、情報のやり取りのみを目的とした秘密保持契約は非課税とされています。
ただし、秘密保持契約と同時に業務委託契約や売買契約など金銭の支払いを伴う契約が一体となっている場合は、印紙の貼付が必要となるケースがあります。
そのため、契約書の内容や構成によって判断が分かれるため、法務部門や専門家への確認が望ましいです。
まとめ丨安全なM&Aを実現するために秘密保持契約の締結は不可欠
秘密保持契約(NDA)は、M&Aの初期段階から最後までを通じて、重要な役割を果たす契約です。
情報漏洩を防ぎ、信頼関係を築くうえで欠かせない一方で、条項内容の設計や運用には注意が必要です。
メリットだけでなくデメリットや注意点も踏まえ、自社の目的に合った契約を構築することが、円滑で安全なM&Aを実現する鍵となるでしょう。
必要に応じて、専門家の助言を受けながら契約内容を吟味することが成功のポイントです。
条項をはじめ、秘密保持契約の締結に関して 不明点などがあれば、お気軽にCINC Capitalにご相談ください。