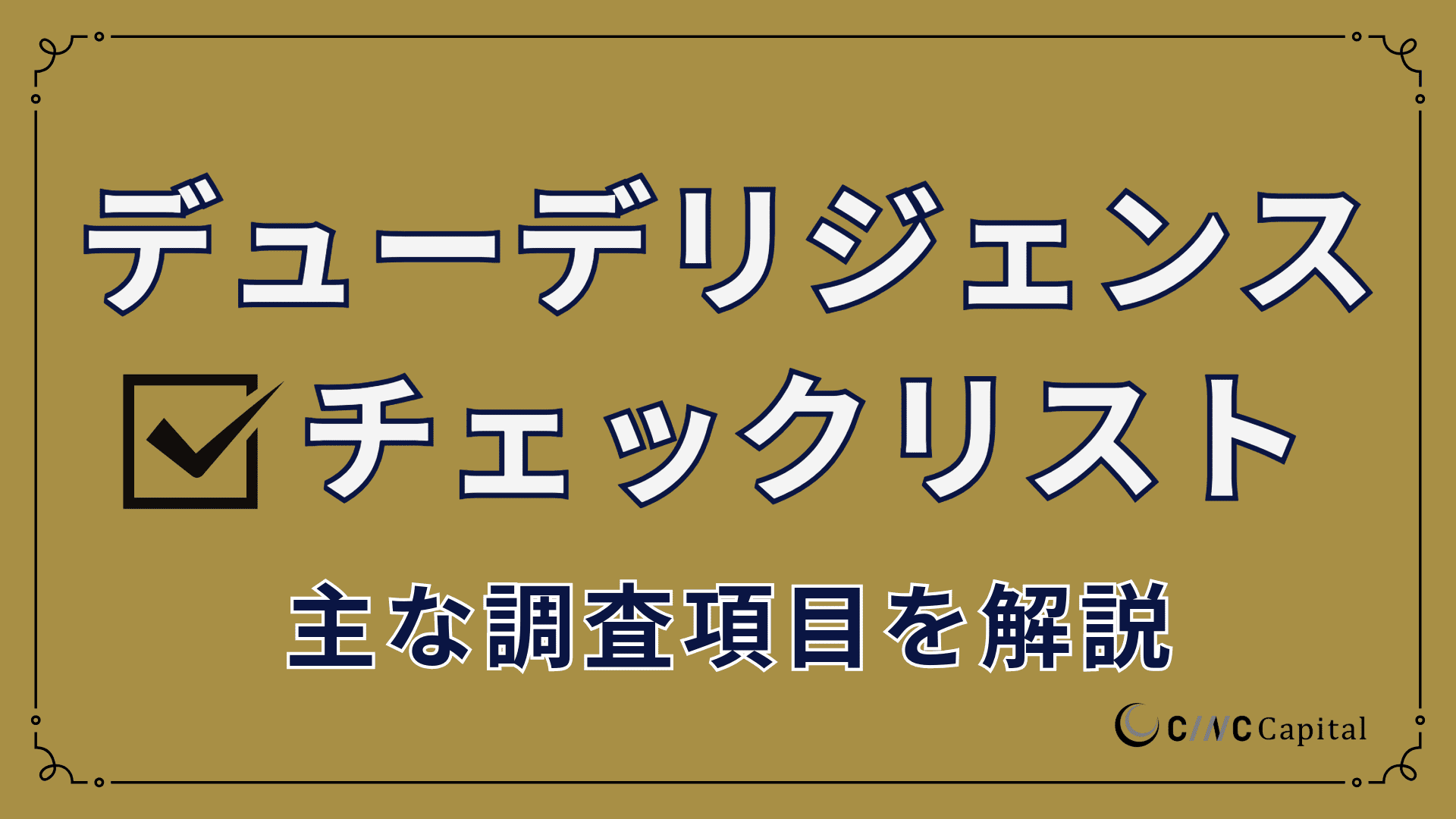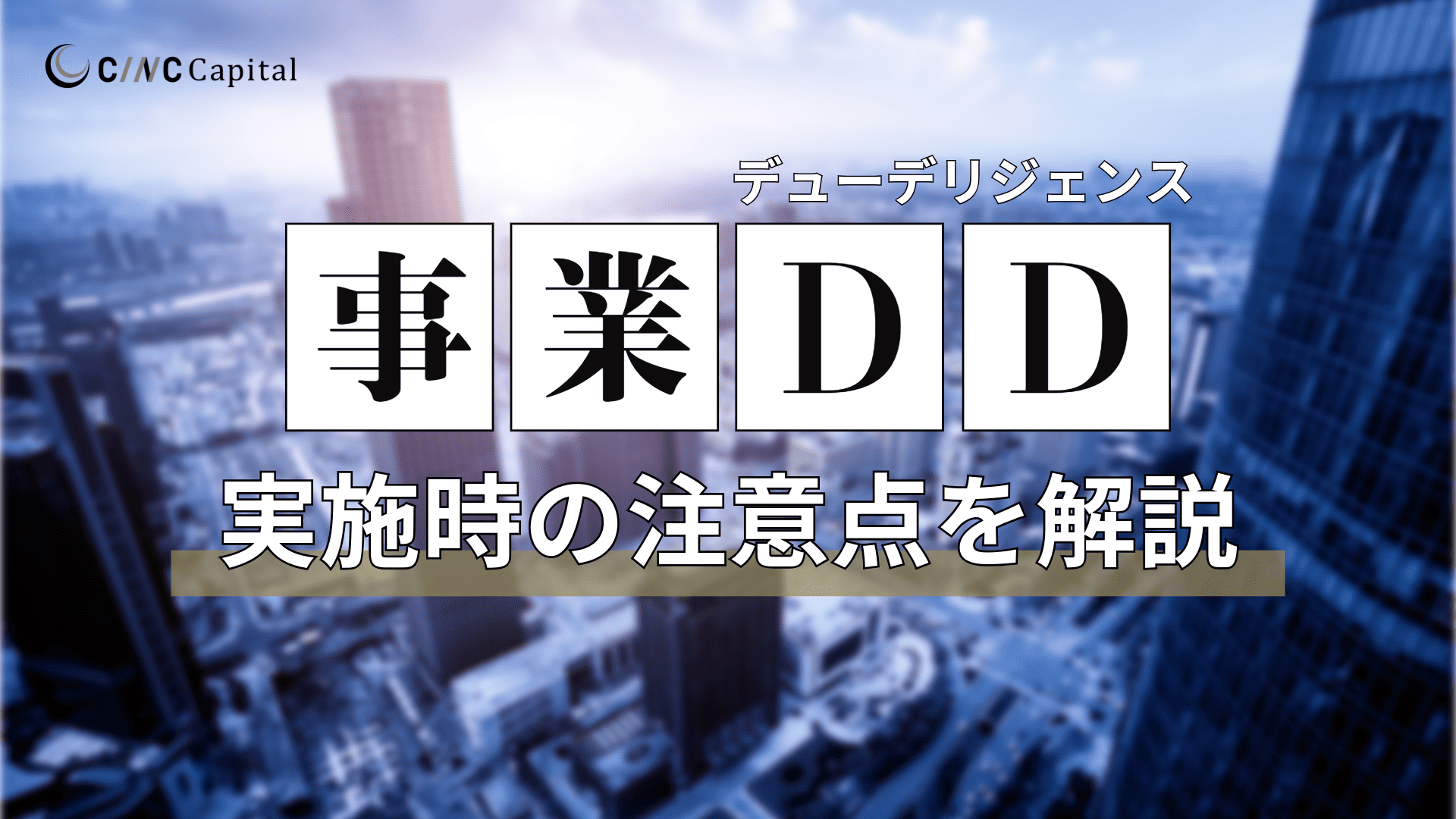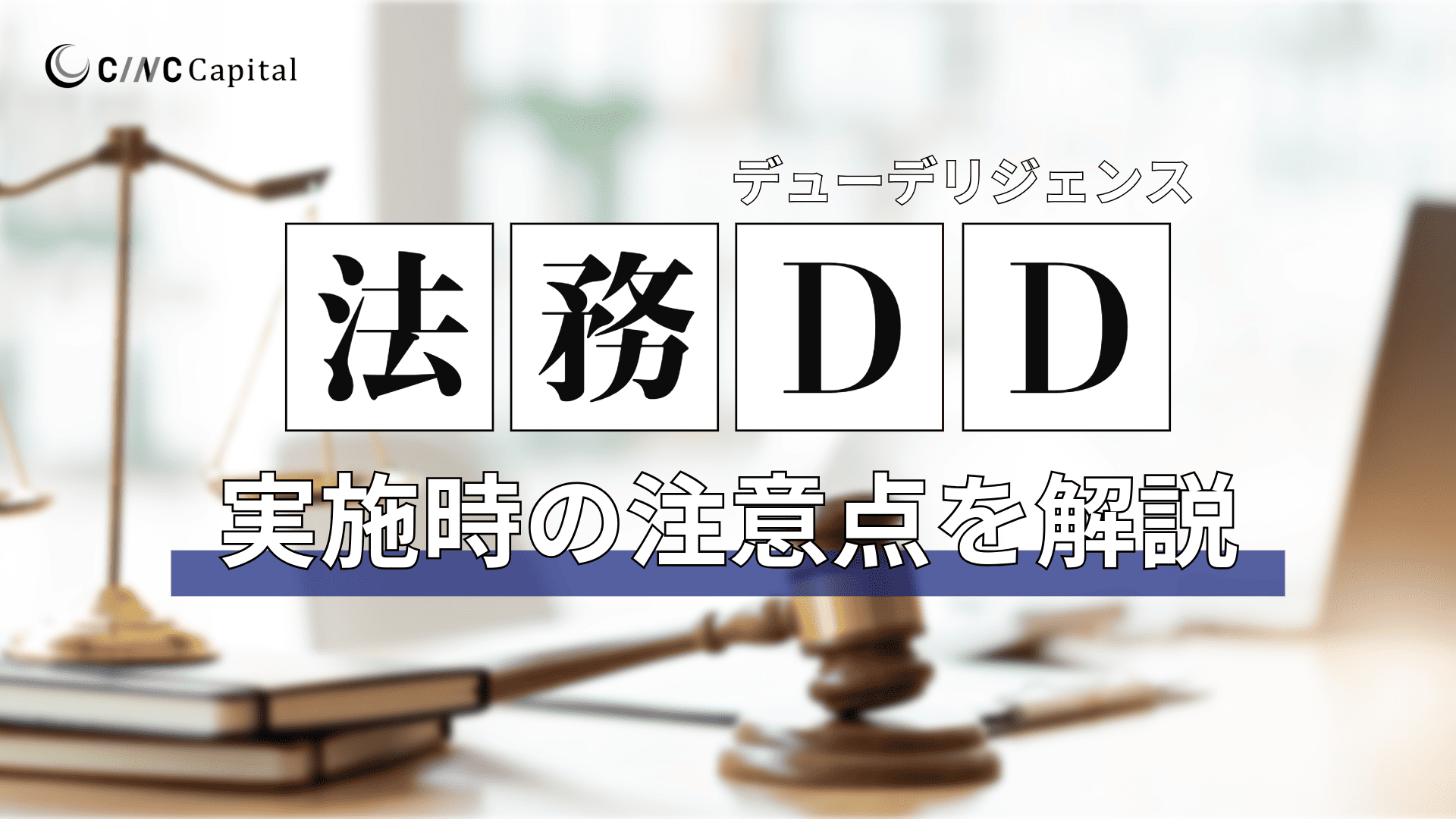CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
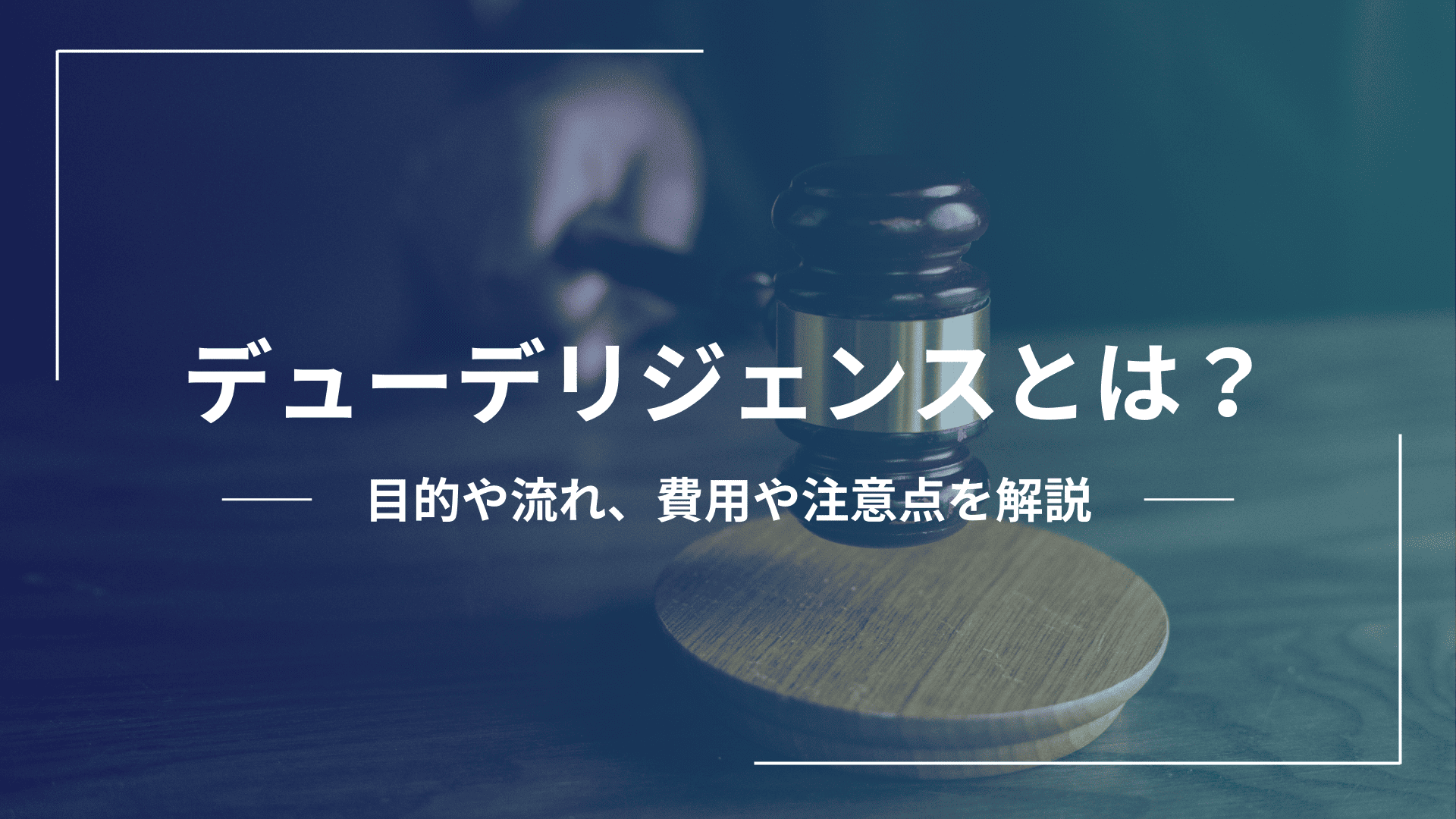
法務 / デューデリジェンス
- 最終更新日2025.07.09
デューデリジェンスとは?M&Aにおける意味や種類、進め方をわかりやすく解説
デューデリジェンス(DD)はM&Aで最終的な意思決定をするために重要なものとなります。ただ、初めてM&Aをする企業にとって、デューデリジェンスはわからないことのほうが多いはずです。
そこで、本記事ではデューデリジェンスに関する基本的な知識、流れや注意点を詳しく解説します。
目次
M&Aにおけるデューデリジェンスとは?
M&Aにおけるデューデリジェンス(Due Diligence)は、買収や合併を行う前に対象企業の実態を詳しく調査するプロセスです。
財務や法務、税務、人事など多方面からリスクや問題点を確認し、正確な企業価値を把握することが目的です。
例えば、簿外債務や契約上の制約、訴訟リスクなど、買収後にトラブルとなる要素を洗い出します。
これにより、適正な買収価格を決め、将来的な損失を防げます。
デューデリジェンスは投資判断の重要な材料になるため、専門家の力を借りて慎重に進めることが必要です。
デューデリジェンスを実施する目的
デューデリジェンスの目的は、主に3つあります。
- M&A実施の有無を決めること
- 適正な価格を決めること
- 買収後のリスクを最小限に抑えること
買い手企業が売り手企業の正確な価値を把握することで、M&A実施の有無の判断をしやすくなったり、適正な価格を提案できたり、メリットがもたらされるでしょう。
また、買収後に発生する可能性のあるリスクを事前に特定し、対策を講じることも期待できます。
デューデリジェンスを実施するタイミング
デューデリジェンスは、M&Aにおいて基本合意書を締結した後、最終契約の締結前に実施されます。
この段階では、買い手企業が対象企業の財務状況や法的リスク、事業の実態を詳細に調査し、買収の最終判断を行います。
このタイミングで実施される理由として、交渉の初期段階では売り手企業が詳細な情報を開示しないことが一般的であるため、基本合意後に本格的な調査が進められます。
デューデリジェンスを通じて潜在的なリスクを把握し、適正な価格や契約条件を確定することが重要です。
デューデリジェンスの主な種類
M&Aにおけるデューデリジェンスには多くの種類があり、それぞれ異なる角度から対象企業の実態やリスクを明らかにします。
ここでは代表的なデューデリジェンスの種類と調査内容を解説します。
- 財務デューデリジェンス
- 法務デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- ビジネスデューデリジェンス
- 労務デューデリジェンス
- 人事デューデリジェンス
- ITデューデリジェンス
- 事業デューデリジェンス
- 環境デューデリジェンス
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスは、対象企業の財務状態や収益性を多面的に評価するために行います。
これにより、資産や負債の全容だけでなく、決算書に表れない隠れた債務や取引リスクも確認できます。
例えば、売掛金の回収状況や在庫評価の妥当性、資金繰りの安定性を精査することで、将来的にキャッシュフローを圧迫するリスクを把握します。
調査結果は適正な買収価格を算定するための根拠になるため、プロの会計士による厳密な分析が不可欠です。
法務デューデリジェンス
法務デューデリジェンスは、対象企業が抱える法的リスクの全体像を明らかにするために実施されます。
契約書、定款、許認可、知的財産権、訴訟履歴などを確認し、法令違反や潜在的な紛争を特定します。
もし不備が見つかれば、将来の損害賠償や取引停止のリスクが高まるため、事前に対応策を検討する必要があります。
特に独占禁止法や業法上の規制が関係する取引では、法務調査の結果がM&Aの成否を大きく左右します。
税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスは、過去の税務申告や納税状況を精査し、税務リスクを明らかにする調査です。
誤った申告や税務調査の指摘を受けていないか、税務上の繰延資産や損失の適切性を確認します。
例えば、過年度に過少申告がある場合は追徴課税が発生する可能性があります。
買収後に思わぬ負担を背負わないためにも、財務調査と並行して税務面の問題を整理することが大切です。
ビジネスデューデリジェンス
ビジネスデューデリジェンスは、対象企業のビジネスモデルや競争力、将来性を把握する調査です。
収益構造や市場でのポジション、主要取引先との関係性、成長戦略を確認します。
例えば、特定の取引先に依存している場合、リスクが集中している可能性があります。
また、買収後に生まれるシナジー効果や事業統合の可能性も評価し、投資価値を多角的に判断します。
労務デューデリジェンス
労務デューデリジェンスでは、人事制度や雇用契約、労使関係の問題を調査します。
労働条件や未払い残業代の有無、就業規則の整備状況、労働組合との関係を確認し、潜在的なリスクを特定します。
例えば、過酷な労働環境やハラスメント問題が潜んでいる場合、買収後の訴訟リスクに直結します。
発見された課題については是正策を検討し、スムーズな組織統合を実現する準備が求められます。
人事デューデリジェンス
人事デューデリジェンスは、組織体制や人材面のリスクを評価し、買収後の組織統合をスムーズに進めるための調査です。
役員や幹部層の適性、報酬制度、退職金やストックオプションなどの人事関連契約を確認します。
例えば、経営層に依存度が高い場合、退職による事業の停滞リスクが考えられます。
組織文化の違いやモチベーション低下を防ぐために、適切な引き継ぎ計画の策定も重要です。
ITデューデリジェンス
ITデューデリジェンスは、対象企業の情報システムやインフラの状況を評価し、リスクや改善点を明確にする調査です。
具体的には基幹システムやクラウド環境の運用状況、セキュリティ体制、ライセンス管理を確認します。
特に情報漏洩やサイバー攻撃への脆弱性は大きな経営リスクになるため、詳細な分析が必要です。
また、買収後にITシステムを統合する場合は、運用コストや移行に伴う課題も同時に評価します。
事業デューデリジェンス
事業デューデリジェンスは、対象事業の市場性や競争優位性、成長可能性を深く分析するプロセスです。
主力商品やサービスの収益性、顧客基盤、業界動向を多角的に検証します。
例えば、業界全体の縮小傾向や規制強化が影響するリスクを把握し、将来的な事業継続性を判断します。
調査結果は買収判断だけでなく、事業戦略の見直しにも活かされます。
環境デューデリジェンス
環境デューデリジェンスは、対象企業や事業拠点における環境リスクを確認する調査です。
土壌汚染や有害物質の使用、廃棄物管理の不備などがある場合、買収後に多額の対応費用が発生します。
環境法令への適合状況を精査し、潜在的なリスクの有無や必要な是正措置を洗い出します。
特に製造業や不動産関連のM&Aでは、環境デューデリジェンスが重要な調査領域となります。
デューデリジェンスにかかる費用
デューデリジェンスの実施には費用がかかります。
デューデリジェンスは専門性の高い業務であるため、専門家に協力を依頼することが多いです。
財務、法務、税務、ITなど各分野のデューデリジェンスを実施するためには、それぞれの専門家のコンサルティング料金が発生します。
専門家に依頼する場合は、企業全体で数十万から数百万円程度かかります。当然規模が大きくなればかかる費用も高額になります。
デューデリジェンスの進め方・実施の流れ
デューデリジェンスは、M&Aを進めるうえで避けて通れない重要な工程です。
企業の全体像を多角的に把握し、潜在的なリスクを明らかにするため、計画から最終判断まで段階的に進めます。
ここでは、7つのステップに分けて流れとポイントを解説します。
- 準備(目的定義・チーム組成)
- 資料リスト提示・NDA締結
- 資料開示・データルーム設定
- 分析・現地調査
- QAセッション
- ドラフト報告書
- クロージング判断
1. 準備(目的定義・チーム組成)
調査の目的をはっきりさせることは、全プロセスの方向性を定める重要な作業です。
買収の目的が市場拡大や技術獲得などで異なる場合、調査範囲や重点ポイントも変わってきます。
例えば、技術獲得を目的とする場合は知的財産の調査が主軸になります。
さらに、調査を担う専門家チームの組成が必要です。
弁護士や会計士、税理士、人事・ITの専門家を確保し、それぞれの役割や責任を明確にします。
スケジュールの設定とコミュニケーションルールの確認も重要です。
準備が不十分だと、調査が長引いたり資料が揃わなかったりするリスクがあります。
だからこそ、段取りと体制の整備を最初に徹底することが、成功するデューデリジェンスの出発点です。
2. 資料リスト提示・NDA締結
このステップでは、守秘義務契約を交わし、必要な資料をリスト化して共有することで、スムーズな情報収集体制を整えます。
デューデリジェンスを始めるにあたっては、秘密保持契約(NDA)の締結が欠かせません。
機密情報の流出を防ぎ、双方が安心して資料をやり取りする環境を作ります。
そのうえで、調査に必要な資料のリストを対象企業に提示します。
例えば、直近3期分の財務諸表、税務申告書、契約書、知的財産関連書類、従業員の雇用契約書などが必要です。
これらを網羅することで、調査の精度が格段に高まります。
資料の範囲は、M&Aの目的に応じて調整します。
財務の健全性を重視する場合は決算書やキャッシュフロー、知的財産を重視する場合は権利証明書などが中心となります。
資料リストを明確にすることで、調査の手戻りを防ぎ、円滑に進行できます。
十分な準備と守秘体制が、次のステップへの土台となります。
3. 資料開示・データルーム設定
必要資料を効率的に確認できるように、データルームを活用して共有体制を構築します。
これにより調査の透明性とスピードを高めます。
NDAが締結された後、対象企業はリストに沿って資料を開示します。
多くの場合、仮想データルームを設置し、オンラインで資料を確認できるようにします。
クラウド型データルームなら、複数の専門家が同時にアクセスできるため、確認の進捗が速まります。
資料開示の際には、最新情報であるか、不備や矛盾がないかを入念に確認します。
例えば、税務申告の内容と財務諸表に整合性が取れているか、契約書に未公開の条件がないかなど、細かな照合作業が求められます。
不明点があれば、即座に追加資料を依頼することが大切です。
迅速な対応ができる体制があれば、調査に遅れが生じにくくなります。
データルームを整備することで、調査メンバーが必要情報にタイムリーにアクセスし、精度の高い調査を行える環境が整います。
4. 分析・現地調査
ここでは、書類分析に加えて現地調査を実施し、企業の実態を多面的に評価します。
これにより、潜在的なリスクの把握が可能となります。
資料が揃ったら、各専門分野ごとに詳細分析を行います。
財務調査では収益力や負債の有無、キャッシュフローの安定性などを精査します。
過去の決算書だけでなく、将来の収益予測も確認し、成長性を見極めることが重要です。
法務調査では、訴訟リスクや契約条件、知的財産の保護状況を徹底的に確認します。
人事調査では、給与体系、離職率、労務リスクが主な検証対象です。IT調査では、システムの耐障害性やセキュリティが焦点になります。
現地調査では、工場や事業所を訪問し、設備の老朽化や生産体制をチェックします。
例えば、製造業では実際に生産ラインを確認することで、稼働状況や改善点を把握できます。
書類と現場を組み合わせた調査が、実態に即した判断材料をもたらします。
5. QAセッション
分析の結果見つかった疑問や追加確認事項は、QAシートを用いて対象企業に質問し、回答を得ていきます。
調査の過程で必ず生じるのが、資料だけでは解決できない疑問点です。
これを整理し、QAシートにまとめて提出するのがこの段階です。
例えば、収益構造に影響する特定契約の条件や、予備資料に含まれないデータの有無などが代表的な質問事項です。
また、在庫評価の算定方法や資産計上基準についても確認する必要があります。
対象企業はこれらの質問に対し、根拠資料や説明を添えて回答します。
この回答が遅れたり不明確だったりすると、調査全体の進行が停滞するため、早期のやり取りが求められます。
QAセッションを適切に行うことで、調査の曖昧な部分を解消し、リスクを最小化することができます。
最終判断に直結する大切な工程です。
6. ドラフト報告書
すべての調査結果を統合し、リスクや懸念事項をまとめたドラフト報告書を作成します。これは意思決定の基礎資料です。
ドラフト報告書では、財務、法務、人事、ITといった各分野の調査結果を網羅的に整理します。
どの分野にどのようなリスクがあるか、影響度はどれくらいかを具体的に示すことが大切です。
例えば、潜在的な訴訟リスクや財務上の不整合、ITシステムの更新コストなどを詳細に記載します。
併せて、買収後に取るべき対応策や統合プランも提案し、リスク軽減の道筋を示します。
ドラフトは関係者に共有され、疑問点や追加調査の要望を反映して修正されます。
このプロセスを重ねることで、最終的に信頼性の高い最終報告書が完成します。
精度の高い報告書が意思決定を支える最も重要な成果物です。
7. クロージング判断
最後に、報告書の内容を踏まえて買収の最終判断を行い、条件調整やクロージングに進みます。
最終判断では、報告書をもとに経営陣が意思決定を行います。
リスクが大きければ、取引条件の再交渉や中止も選択肢に含まれます。
例えば、調査で予想外の債務が発覚した場合、価格調整を求める交渉が必要です。
また、重大な法務問題があれば契約条件に特約を盛り込み、リスクを限定する方法もあります。
逆に、問題が軽微であれば予定通り買収を進め、クロージングの手続きに入ります。
クロージング判断は、調査を通じて集めた情報の総合的な評価です。
慎重に検討を重ねることで、買収後の不確実性を最小限に抑え、成功確率を高めることが可能です。
【買い手】デューデリジェンス実施時の注意点
デューデリジェンスは、M&Aの成功において欠かせないプロセスです。
しかし、このプロセスを適切に行うためにはいくつかの注意点があります。
調査範囲を明確にする
デューデリジェンスは財務・法務・税務・ビジネスなど多岐にわたるため、事前に調査範囲を明確に定めることが重要です。
対象企業の規模や業種に応じて重点を置くべき項目が異なるため、適切な範囲設定を行わないと、調査の抜け漏れが発生する可能性があります。
信頼できる専門家を起用する
デューデリジェンスには高度な専門知識が求められるため、財務・法務・税務の各分野で専門家を起用することが望ましいです。
特に法務や税務に関するリスクは見落としやすく、後に大きな損害を招く可能性があるため、経験豊富な専門家の協力が不可欠です。
早い段階で潜在的リスクを把握する
M&Aの交渉が進んでから重大なリスクが発覚すると、取引の中止や条件変更を余儀なくされることがあります。
そのため、デューデリジェンスの初期段階で潜在的な問題を洗い出し、リスクの有無や対策の検討を行うことが重要です。
特に、過去の訴訟履歴や未払い債務、労働問題などは早めに確認すべきポイントです。
売り手との適切な情報開示を確保する
売り手企業がすべての情報を積極的に開示するとは限らないため、買い手側は適切な開示を求める姿勢が求められます。
特に、財務諸表や契約書、資産状況などの重要な情報は、詳細な確認を怠ると後に問題が発生する可能性があります。
秘密保持契約(NDA)を締結したうえで、十分な情報開示を得ることが不可欠です。
調査結果を基に適正な条件交渉を行う
デューデリジェンスの結果をもとに、買収価格や契約条件を見直すことが一般的です。
問題が見つかった場合には、適切な価格調整やリスク回避のための条項を契約に盛り込む必要があります。
調査結果を踏まえて売り手と適切な交渉を行うことで、リスクを最小限に抑えながらM&Aを進めることができます。
【売り手】デューデリジェンス実施時の注意点
M&Aにおいて売り手側がデューデリジェンスを受ける際には、適切な準備と対応が求められます。
買い手からの詳細な調査に対して、正確な情報を提供しつつ、自社の価値を適正に評価してもらうことが重要です。
情報の整理と開示を徹底する
デューデリジェンスでは、財務諸表や契約書、従業員の雇用条件など、幅広い情報を求められます。
情報が整理されておらず、不備が多いと、買い手の信頼を損ない、取引条件が不利になる可能性があります。
事前に必要な資料を揃え、正確なデータを提供できるよう準備しましょう。
重要事項の開示は慎重に行う
デューデリジェンスの過程で、買い手に対して企業の内部情報を開示する必要があります。
しかし、すべての情報を無条件に提供するのはリスクが伴います。
秘密保持契約(NDA)を締結したうえで、慎重に情報を共有し、機密情報の漏洩を防ぐことが重要です。
法務・税務リスクの洗い出し
買い手は、売り手企業の法務・税務面のリスクを特に重視します。
未払いの税金、訴訟リスク、契約上の問題などが見つかると、取引が破談になったり、買収価格の引き下げ要因になったりする可能性があります。
事前に専門家と相談し、問題点を洗い出しておくことが重要です。
従業員や取引先への影響を考慮する
M&Aの交渉が進む中で、従業員や取引先に不安が広がることがあります。
特にデューデリジェンスの段階では、買い手が社内情報を確認するため、社内に噂が広まりやすくなります。
情報管理を徹底しつつ、適切なタイミングで従業員や取引先に説明を行う準備を進めましょう。
交渉過程での条件変更に備える
デューデリジェンスの結果によっては、買い手が価格の引き下げや条件の見直しを求めてくることがあります。
売り手としては、事前に交渉戦略を練り、譲歩できる点と譲れない点を明確にしておくことが重要です。
また、複数の買い手候補を検討し、適切な条件を引き出せるように交渉を進めることも有効です。
まとめ|適切なデューデリジェンスでリスクを低減し成功確率を高めましょう
デューデリジェンスは、M&Aの成功または失敗に大きく影響する重要なプロセスです。
事前に企業の財務状況、法務リスク、税務問題などを詳細に調査することで、リスクを最小限に抑え、取引の安全性を高めます。
デューデリジェンスを適切に行うことで、M&Aの成功確率が大幅に向上します。
M&Aを成功させるためにもデューデリジェンスの実施は専門家の助言を求めることをおすすめします。
専門家の力を借りながら、慎重に進めることを心がけましょう。