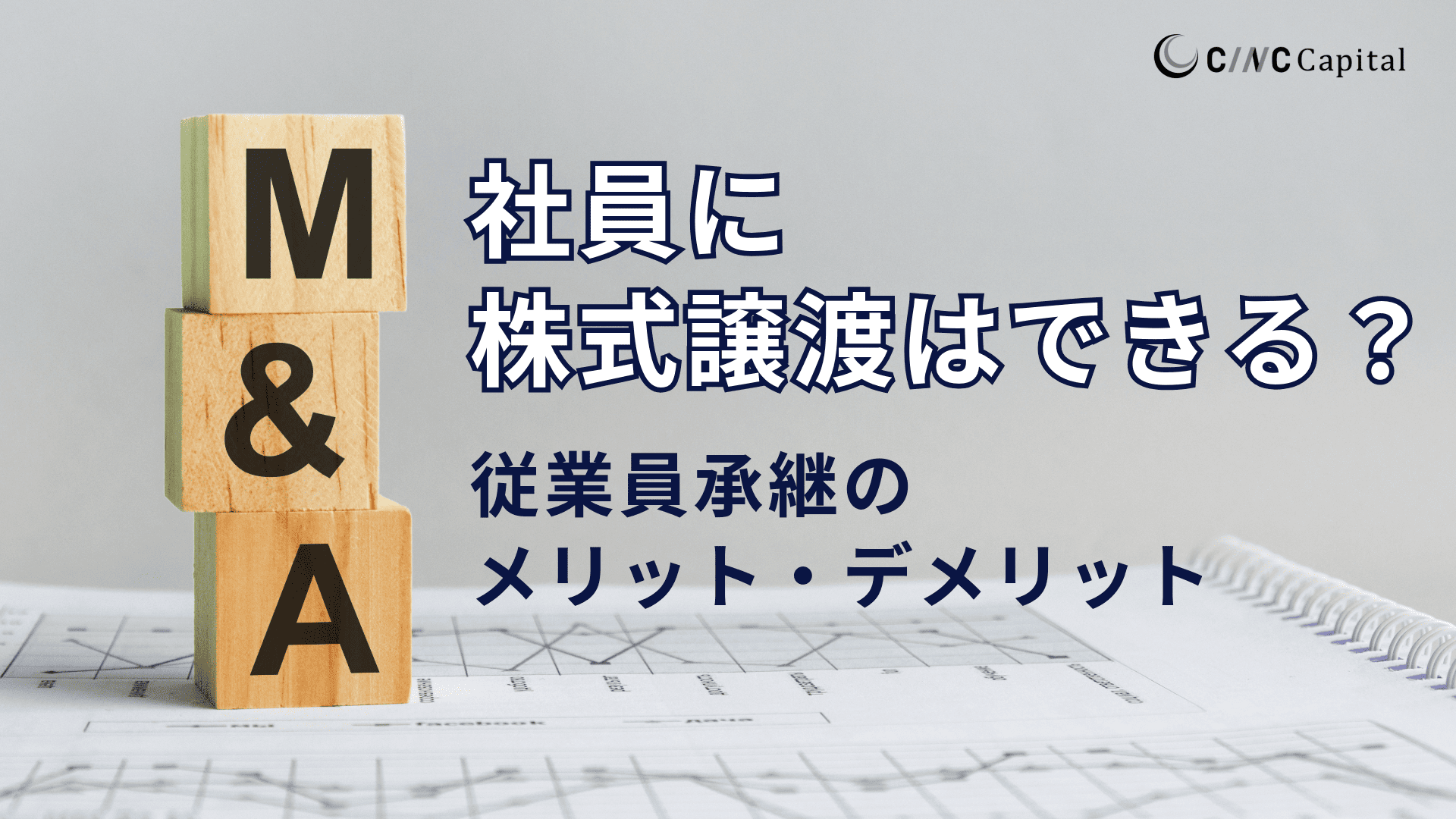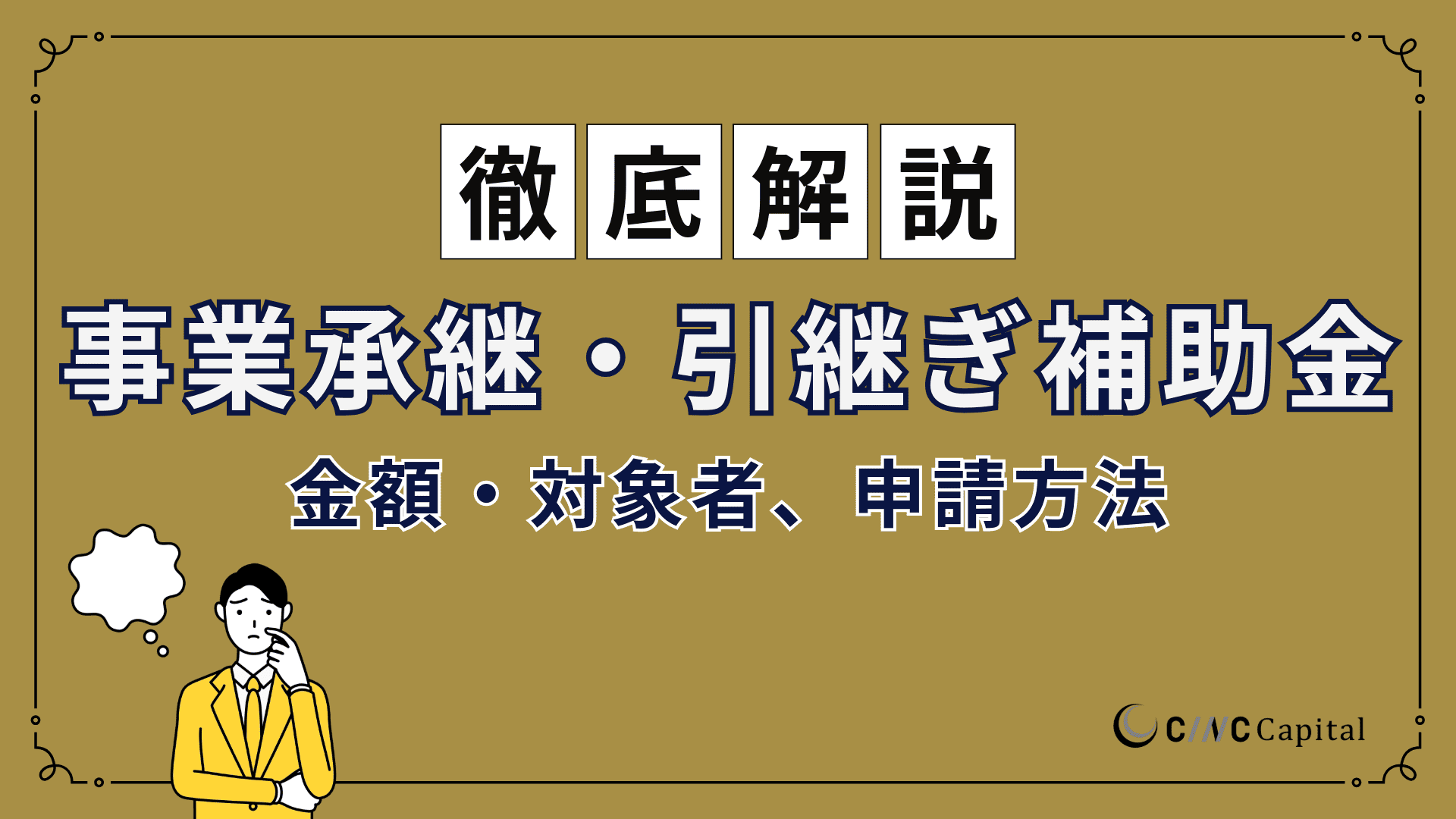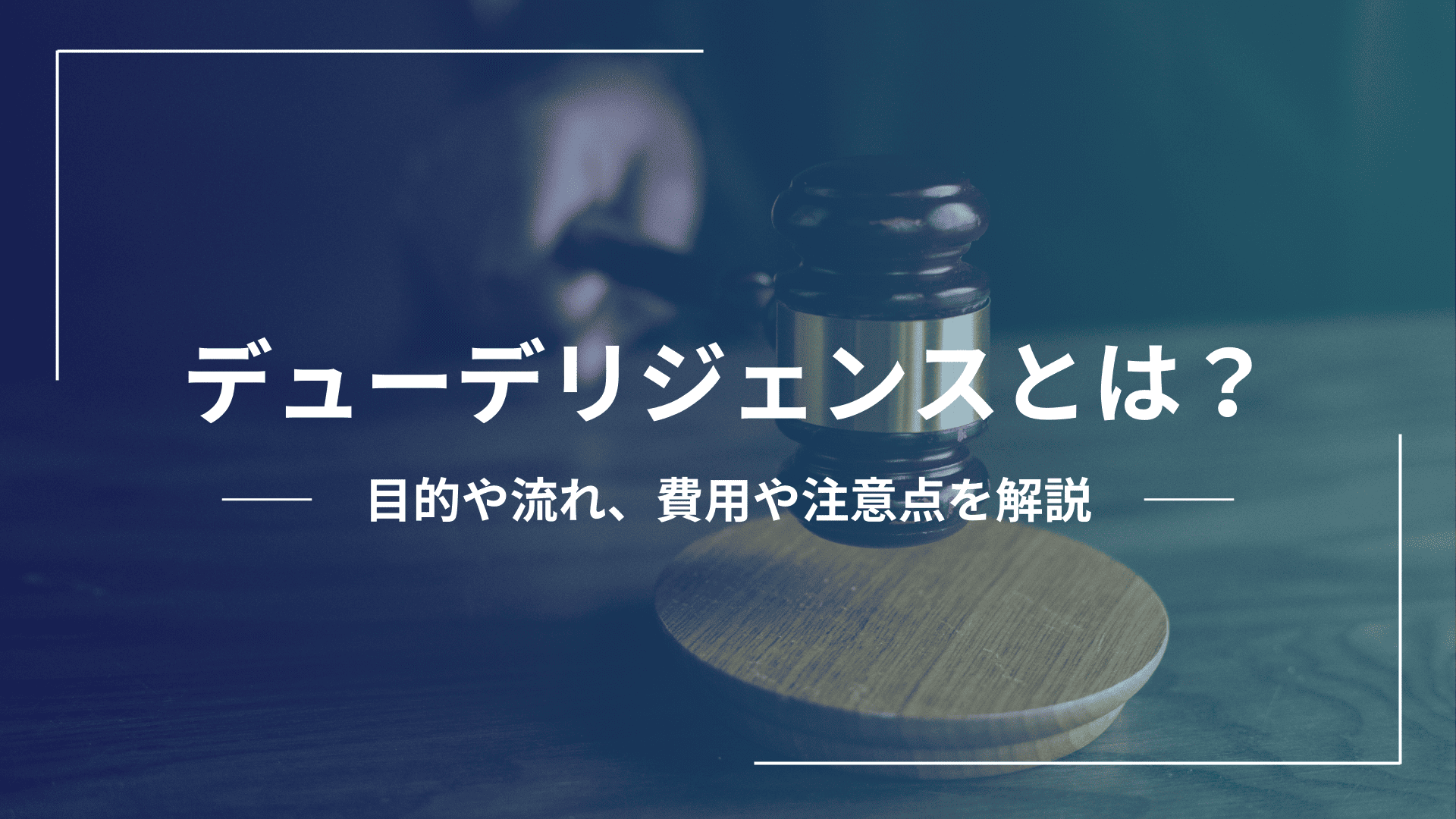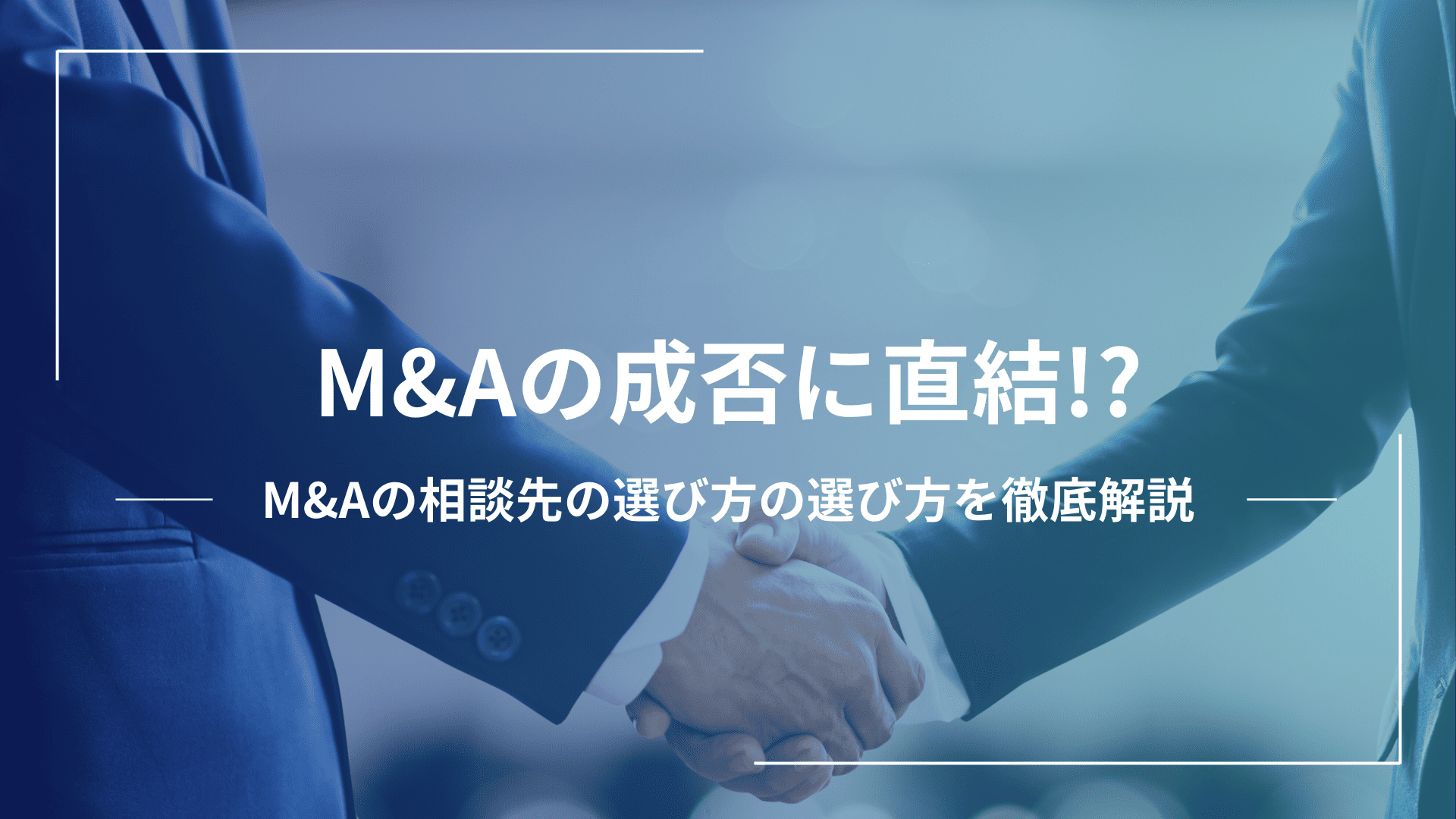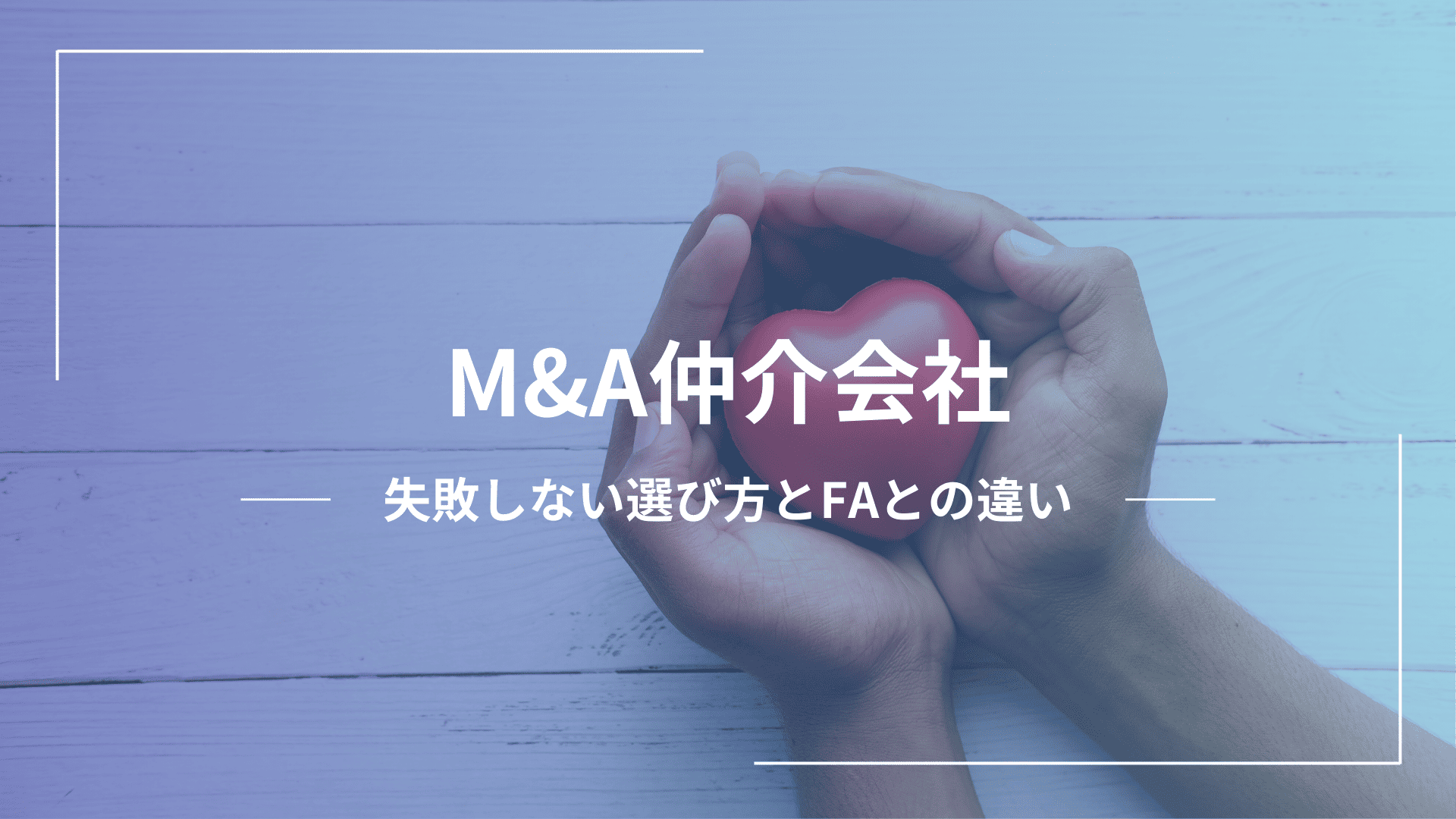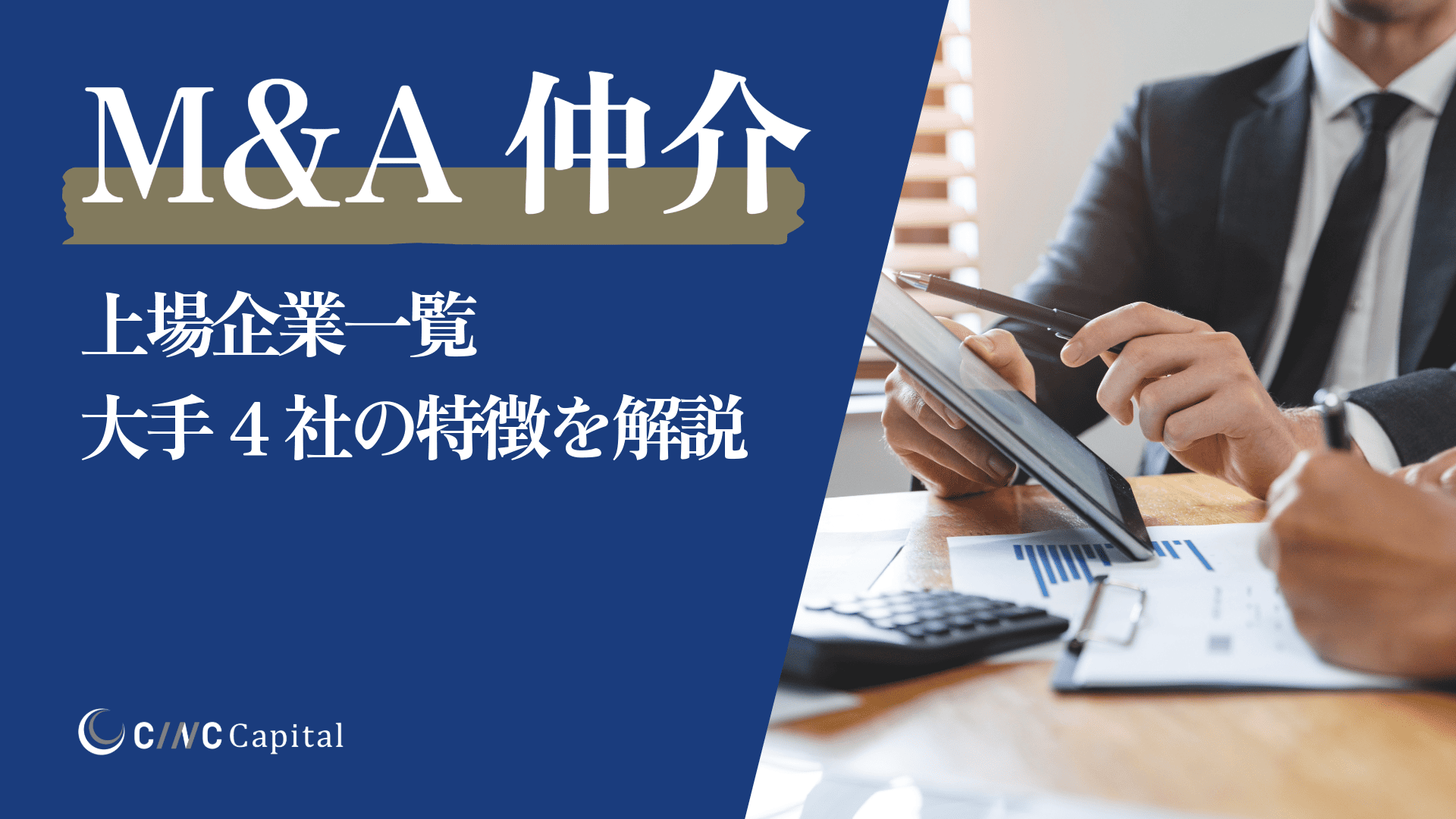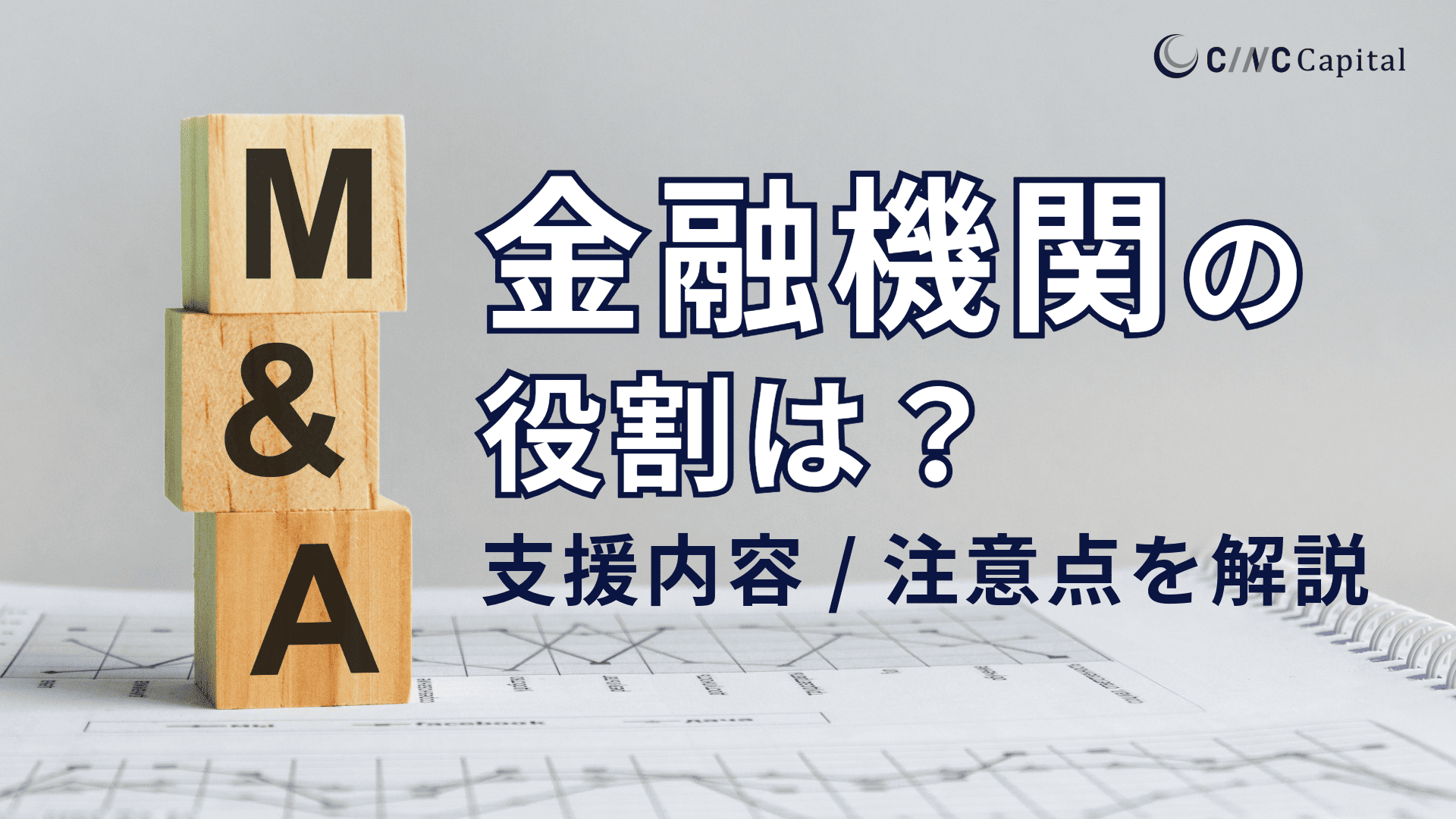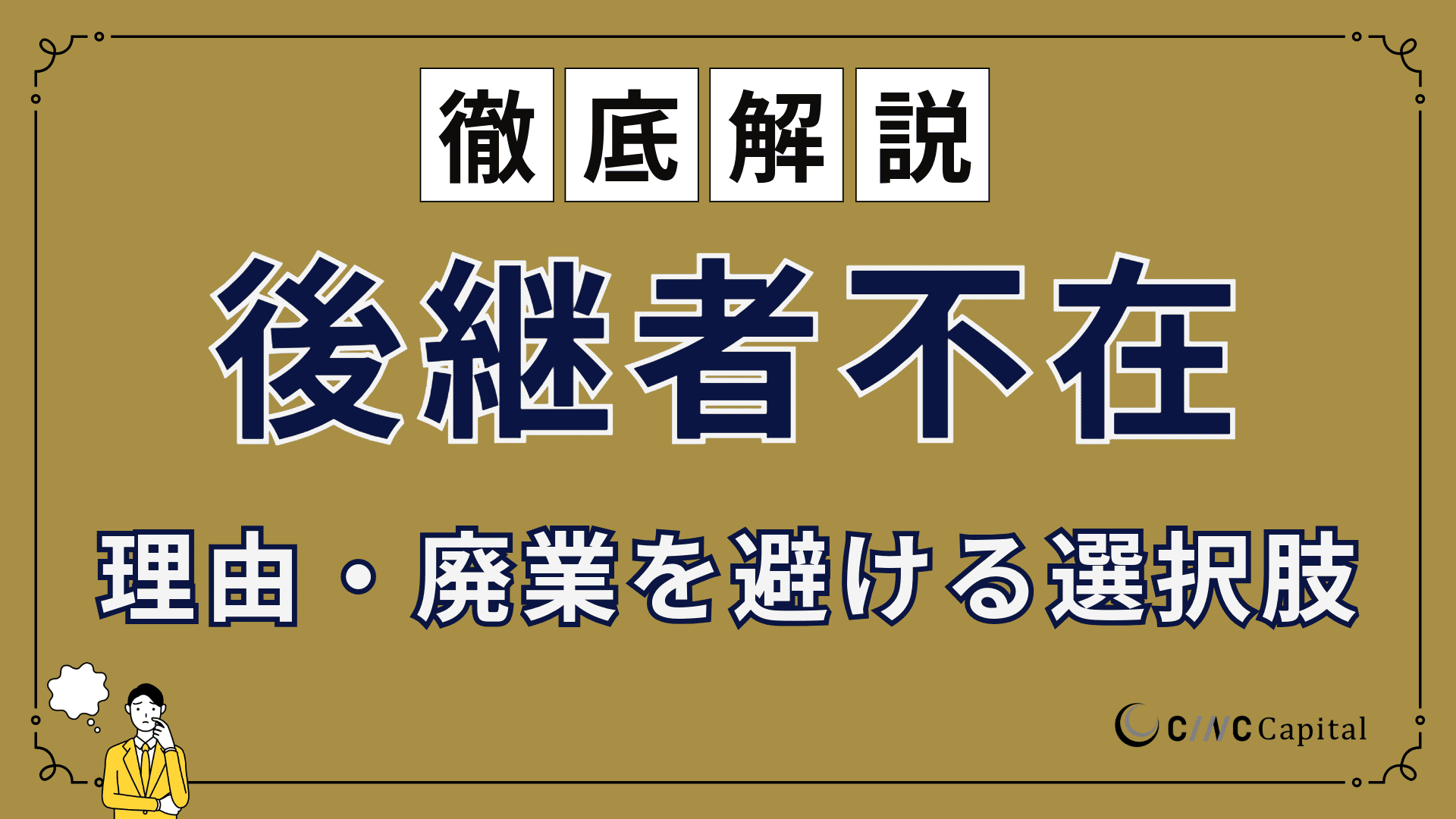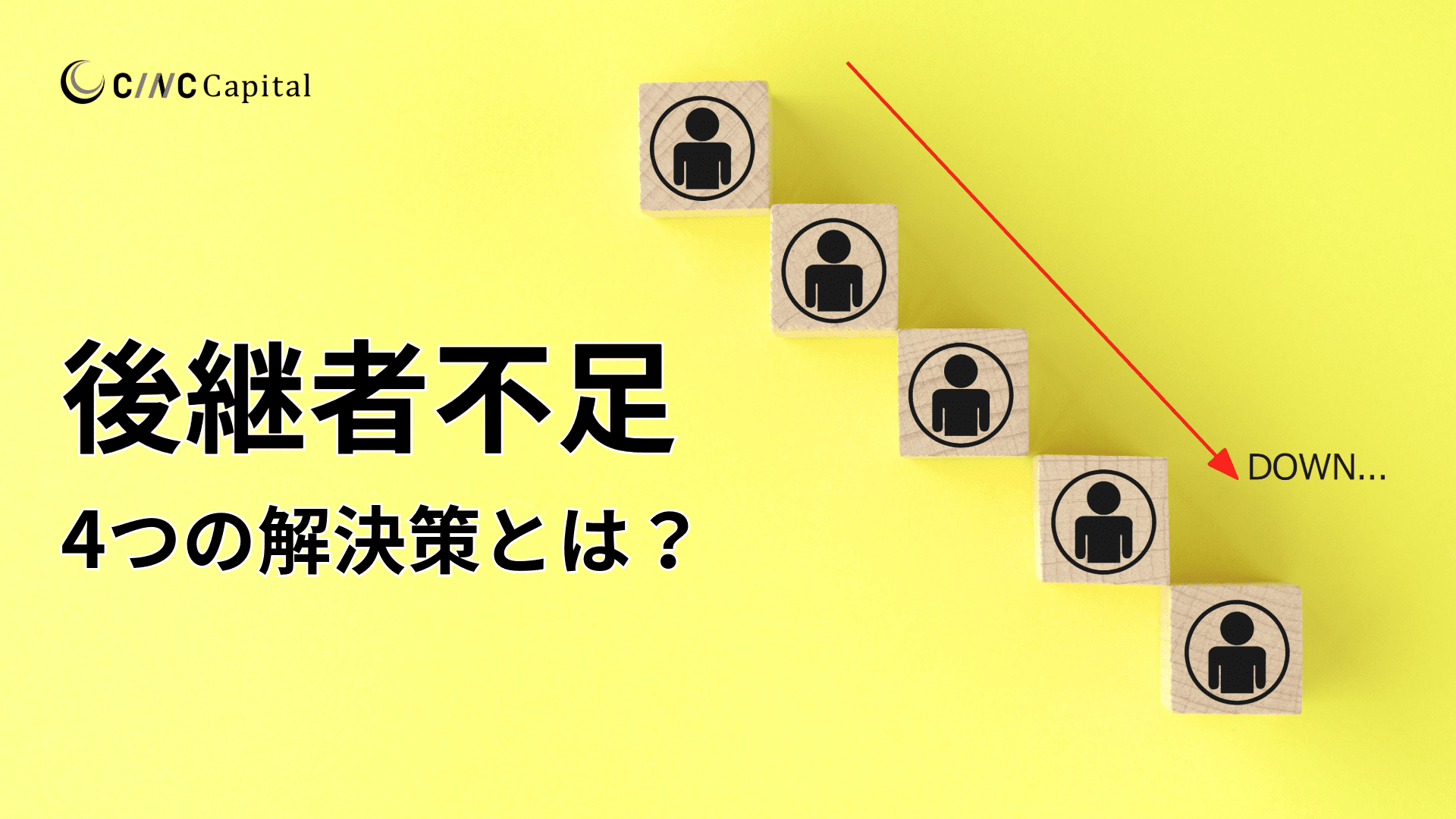CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
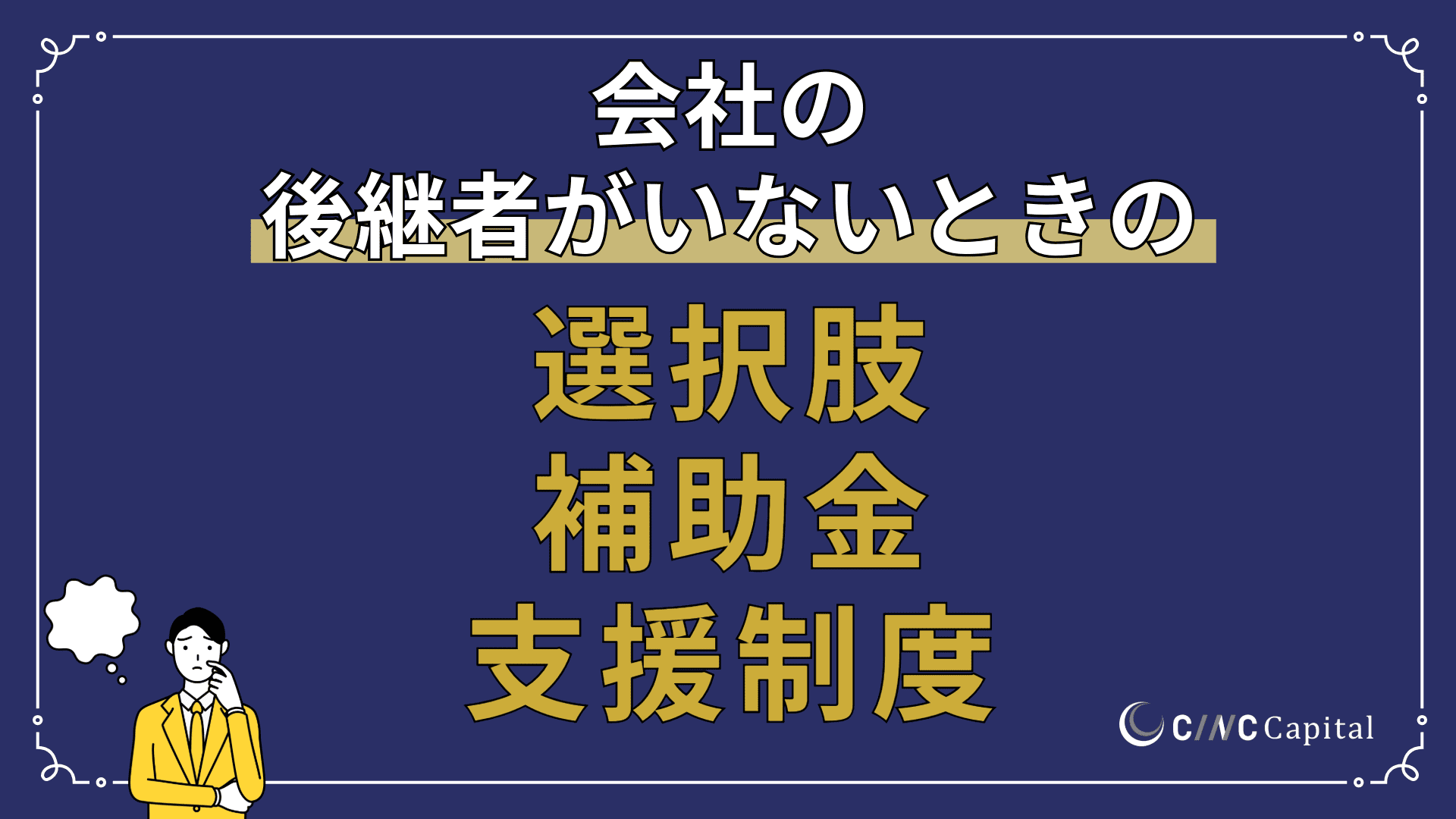
後継者問題・跡取り問題
- 公開日2025.09.30
後継者がいない会社はどうする?選択肢や活用できる支援制度や補助金を解説
「後継者がいない会社をどうすれば良いか」と悩んでいませんか?
本記事では、後継者不在企業の定義から選択肢、支援制度などを詳しく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
後継者がいない会社の定義
後継者がいない会社とは、現在の経営者が引退または退任を予定しているが、事業を引き継ぐ後継者が親族・従業員・第三者いずれの中にも決まっていない企業です。
この状態では、企業が長年培ってきた事業のノウハウや顧客基盤、従業員の雇用などが引き継がれず、廃業という最終手段を選ばざるを得ない可能性が高くなるでしょう。
中小企業庁の調査では、2025年時点で70歳以上の中小企業経営者245万人中127万人が後継者未定と推計されています(70歳以上の経営者層に限る報告)。
さらに帝国データバンクの2024年の調査では、全国企業のうち約52.1%が後継者不在という深刻な実態が明らかになっています。
【出典】中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」
【出典】帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」
後継者のいない会社が増えている理由
後継者がいない会社が増えている背景には、いくつかの要因が重なっているのです。
まず、少子高齢化により親族内の後継候補が減少しています。
さらに、子どもが家業を継がず自分の道を選ぶケースが増えたことで、親族内承継は減少傾向です。
加えて、経営環境の悪化により「継がせたくない」と考える経営者も少なくありません。
また、多くの経営者が承継準備を先送りしており、気づいたときには後継候補も育っておらず、引継ぎの選択肢がなくなっている企業も少なくありません。
後継者がいない会社の選択肢は?
後継者がいない企業も、事業を継続または円満に終了させるために選べる選択肢があります。
本章では4つの選択肢について、メリットや注意点を詳しく見ていきましょう。
M&Aによる第三者承継
後継者がいない場合、近年注目されている選択肢としてM&Aによる第三者承継があります。
これは親族や従業員ではなく、外部の個人や法人に会社を譲渡する方法です。
M&Aによる第三者承継には、株式譲渡と事業譲渡の方法が一般的であり、株式譲渡の場合は売却益が経営者個人や株主に帰属し、事業譲渡の場合は売却益が企業(法人)に帰属します。
そのため、経営者個人が対価を得て引退を希望する場合は、株式譲渡が適しています。
また、中小企業でもM&Aの事例は増加しており、専門家のサポートを受けながら進めるケースが一般的と言えます。
社内人材への承継
社内の従業員や役員に事業を承継する方法も現実的な選択肢のひとつです。
会社の実情を理解した人物に引き継ぐため、業務や人間関係の引継ぎがスムーズに進みやすくなります。
しかし、株式取得のための資金面や、経営能力の有無が課題になることもあるでしょう。
そのため、後継者教育や外部支援の活用を含めた事前準備が重要です。
事業の廃業・清算
承継が難しい場合、廃業や会社清算という選択もあります。
経営者が高齢で体力的に厳しい、業績が振るわないなど、やむを得ない事情がある場合に選ばれることが多いです。
ただし、廃業は従業員の雇用や地域の取引先に影響を与えるため慎重に判断しましょう。
事業の一部譲渡・分割
会社全体を承継するのではなく、一部の事業や部門を譲渡・分割する方法もあります。
例えば、主力事業のみを残し、非中核部門を他社に譲渡することで、経営資源を集中できるのです。
買い手にとっても必要な事業だけを取得できるため、マッチングが成立しやすくなります。
後継者募集を成功させるためのポイント
後継者募集を成功させるには、まずどのような人材が自社に適しているかを明確にし、企業の魅力を正しく伝え、引継ぎの体制を整えなければなりません。
本章では、後継者募集について3つのポイントに分けて解説していきます。
後継者候補とマッチする人材像を明確にする
後継者募集では、まず「どんな人材が自社に合うのか」を定義しましょう。
最初に現在の経営戦略や会社文化を踏まえ、必要な資質や経験・年齢層を設定します。
次に、複数候補から理想像に近い人物を比較しながらピックアップしていきましょう。
さらに、現経営者との価値観の擦り合わせや育成プランも整えることで、募集活動に一貫性が生まれます。
企業の魅力を正しく伝える情報開示を行う
後継者に興味を持ってもらうには、数字や無形価値を丁寧に伝えましょう。
まず財務・顧客・技術の現状を整理し、成長可能性などを数値で示します。
そして社風・理念や経営者の想いなど、候補者が共感するストーリーも明確にしてください。
これにより、候補者は経営参画へのリアリティを持ちやすくなります。
スムーズな引継ぎを可能にする体制を整える
後継者が正式に決まった後は、引継ぎを円滑に進めるための体制構築が必要です。
まずは、引継ぎスケジュールと内容を明文化し、関係者に周知しましょう。
次に、経営判断や人事体制などに関わるメンバーを再編し、後継者を支える組織を整えます。
さらに、必要に応じて専門家を投入し後継者育成やPMI支援も行いましょう。
後継者のいない会社が活用できる支援制度や補助金
後継者不在の企業が事業を継続・再構築するには、経済的・制度的支援が欠かせません。
本章では、4つの制度についてそれぞれ紹介します。
事業承継・引継ぎ補助金(中小企業庁)
事業承継やM&A、廃業準備に伴う経費を支援する制度が「事業承継・引継ぎ補助金」です。
補助対象はM&A支援費用、新技術の導入、設備廃棄費などに広がり、補助率は原則2/3、最大800万円ほどが支給されます。
この補助金を活用すれば、後継者候補の育成や専門家導入などに必要な資金を公的に補うことが可能になるのです。
事業承継・M&A補助金(中小企業庁)
M&Aに伴う専門家費用に特化した補助金が「事業承継・M&A補助金」です。
専門家のアドバイザリーやデューデリジェンス費用の2/3が補助され、最大800万円まで支給されます。
燃費のかかるM&A手続きを専門家に任せられる点が大きなメリットです。
とくに初めてM&Aに取り組む企業にも敷居が低くなり、より安心して第三者承継に臨める仕組みとなっています。
個人版事業承継税制(国税庁)
個人事業主が事業用資産を後継者に相続・贈与する際、税負担を猶予または免除する制度です。
青色申告事業者が2028年12月31日までに承継を行った場合、贈与税・相続税の100%が納税猶予されます。
一定期間、事業を継続するなど条件を満たした場合に猶予された税額が免除されるのです。
これによって、税負担の重さがネックとなっていた個人事業の承継が容易になります。
事業承継マッチング支援(日本政策金融公庫)
売り手と買い手を無料でつなぐマッチング支援を提供しており、2024年度の申込数は4,786件、成約103件に達しています。
この支援により、中小企業でも安心感を持って第三者承継の第一歩を踏み出せるようになりました。
さらに専門家派遣や融資相談も一体で受けられるため、資金と人材の両面からバックアップを受けられます。
【承継者向け】後継者がいない会社を買うには?
後継者がいない会社を引き継ぐには、明確な目的を持って計画的に行動することが重要です。
本章では3つのポイントについて解説していきます。
買収対象企業の選定方法を理解する
買収を成功させるには、最初に買収目的と自社戦略との整合性を明確に定義する必要があります。
例えば「既存業務を強化する」「新市場へ進出する」など明確な目的がないと企業選定がぶれてしまうためです。
その後、市場調査と競合分析を通じて、自社との相性が良い企業を抽出し、リスト化して比較検討しましょう。
デューデリジェンスでリスクを把握する
買収前には、リスクを把握するためのデューデリジェンスが欠かせません。
財務・法務・労務などを多角的に調査することで、簿外債務やトラブルを事前に防げます。
中小企業ではITの老朽化や未払い残業代が見落とされやすいため、専門家の協力が必要です。
M&A仲介会社や支援機関を活用する
最後に、M&Aを円滑に進めるためには専門支援の利用が不可欠です。
M&A仲介会社やFA(フィナンシャルアドバイザー)を通じて、買い手は非公開情報の収集・交渉支援・契約締結・PMI設計まで統合的なサポートを受けられます。
これにより、経験が浅い方でも安心してプロセスを進められ、成功率を大きく高めることが可能です。
【承継者向け】後継者がいない会社を買うメリット
後継者不在の会社を買収する際には、既存基盤の引き継ぎ、迅速なスタート、コスト・リスク低減という三つのメリットがあります。
本章では、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
既存の事業基盤や顧客を引き継げる
後継者不在企業を買う最大の利点は、事業基盤や顧客をそのまま引き継ぐことができる点です。
既存顧客による安定収益が見込め、営業の停滞を防げます。
従業員や取引先との関係も維持できるため、立ち上げよりスムーズに事業を始められるのです。
短期間で事業をスタートできる
稼働中の事業を買えば、設備や人材が整っているため、すぐに事業を始められます。
新規起業に比べて準備期間を大幅に短縮でき、早期の収益化が可能です。
このスピード感は起業家にとって大きな魅力になります。
新規参入よりもコストやリスクを抑えられる
既存の売上実績や財務履歴がある企業は、銀行融資が受けやすく、初期投資を抑えられるのです。
信頼性が高いため、資金調達条件も好転しやすくなります。
また、新規で起業する際のマーケットテストやブランド構築といったリスクも軽減されるため、安全性の高い事業買収となる可能性が高くなるでしょう。
【承継者向け】後継者がいない会社を買うデメリット
後継者がいない企業を買うことには大きなメリットがありますが、注意すべきリスクもあります。
本章では、3つのデメリットについて見ていきましょう。
簿外債務や労務問題などのリスクを引き継ぐ可能性がある
後継者不在企業の買収では、簿外債務や労務トラブルなど予期せぬリスクを引き継ぐ可能性があります。
中小企業では未払い残業代や保証債務が多く、財務を圧迫することもあるでしょう。
事前のデューデリジェンスと契約での補償対応が重要です。
企業文化や従業員の適応に時間がかかる
企業文化が異なる会社を買収すると、従業員が新しい方針や組織構造に順応できず、一時的に離職や業務効率低下が起きることがあります。
特にキーパーソンや幹部社員が退職すると、事業の信頼性やノウハウにも深刻な影響が出ることも考えられるでしょう。
企業文化の相違により人事制度や社風が混乱し、生産性の低下といった負の連鎖が発生することも珍しくありません。
引継ぎが不十分だと事業継続に支障をきたすことがある
引継ぎが不十分なまま承継を進めると、ノウハウや顧客情報、業務の流れなどが正しく伝わらず、事業に支障が出ることがあります。
重要な情報が抜けると判断ミスや信頼低下につながり、従業員の退職や顧客離れ、資金繰りの悪化を招くおそれもあるでしょう。
【承継者向け】後継者がいない会社を買う際のポイント
後継者不在企業を買収する際は、慎重な準備と的確な判断が欠かせません。
特に重要なのが、買収目的の明確化、リスクの事前把握、そして買収後の統合計画です。
本章では3つのポイントについて解説していきます。
買収目的を明確にし、戦略と合致させる
買収を成功させるには、目的を明確にすることが大切です。
事業の補強や新市場への進出など、意図をはっきりさせれば選定や交渉がしやすくなります。
戦略と目的を一致させることで、買収後のミスマッチも防げるのです。
綿密なデューデリジェンスによりリスクを事前に把握する
買収前には、リスクを見極めるデューデリジェンスが欠かせません。
財務や法務だけでなく、労務やITなども調査し、簿外債務や未払い問題を事前に把握します。
中小企業では見えにくいリスクが多いため、専門家と連携して確認することが重要です。
譲渡後の統合プロセス(PMI)を計画的に進める
買収後に価値を発揮するには、統合(PMI)を計画的に進めましょう。
組織や業務の統合には専任体制が必要で、買収前から準備を始めることが理想です。
明確なスケジュールと目標を設定すれば、従業員や顧客の離脱を防ぎ、早期に成果を得られます。
【承継者向け】後継者がいない会社を探す方法
後継者不在企業の買収を検討する際、まず信頼できる案件を見つけることが大切です。
安易に探すと情報が偏ったり、希望条件に合わない企業を選ぶリスクがあります。
本章では、買い手が活用すべき4つの方法について見ていきましょう。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、全国47都道府県に設置された公的相談窓口です。
相談を通じて承継・M&Aの課題抽出から、譲渡候補の紹介、専門家派遣までを無料で受けられます。
とくに支援センターは秘密保持に配慮しながら、マッチングから譲渡契約成立まで一貫支援してくれるのが強みです。
M&A仲介会社
M&A仲介会社とは、買い手と売り手の間に立って交渉から契約、専門的な助言までをサポートする専門家です。
彼らは案件紹介だけでなく、企業価値評価や契約書作成、DD支援など幅広い業務を担い、中小企業のM&Aでも不可欠な存在です。
多様な案件を保有しているため、自社に合った企業を効率よく紹介してもらえます。
金融機関
銀行や信用金庫などの金融機関も事業承継の仲介を行っています。
取引先企業の状況を把握しており、後継者不在企業の情報提供やマッチング支援を受けることが可能です。
公庫の事業承継マッチング支援と連携して、譲渡・譲受両方の相談に応じてくれるケースもあります。
M&Aマッチングサイト
インターネット上で匿名掲載や条件検索を通じたマッチングが可能なM&Aマッチングサイトも有力な手段です。
BATONZやTRANBI、スピードM&Aなどは毎月多数の案件が登録されており、手軽に情報収集ができます。
利用者側の審査やサポート体制が整っているサイトも増えており、初心者でも安心して利用できる環境が整っていると言えるでしょう。
【参考】BATONZ
まとめ
後継者がいない会社は、放置すれば廃業や技術・雇用の断絶といった損失が避けられません。
一方で、M&Aや内部承継、親族継承、廃業・分割など多様な選択肢が存在し、それぞれに適した環境や準備が必要です。
経営者は早期に後継者対策を始め、採用活動や承継計画に着手し選択肢を広げましょう。
CINC Capitalは後継者不在に悩む経営者様を支援しています。
事業の価値を正当に評価し、譲渡先の選定から契約手続きまで一貫して対応し、会社の未来を守る具体的な方法をご提案します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。