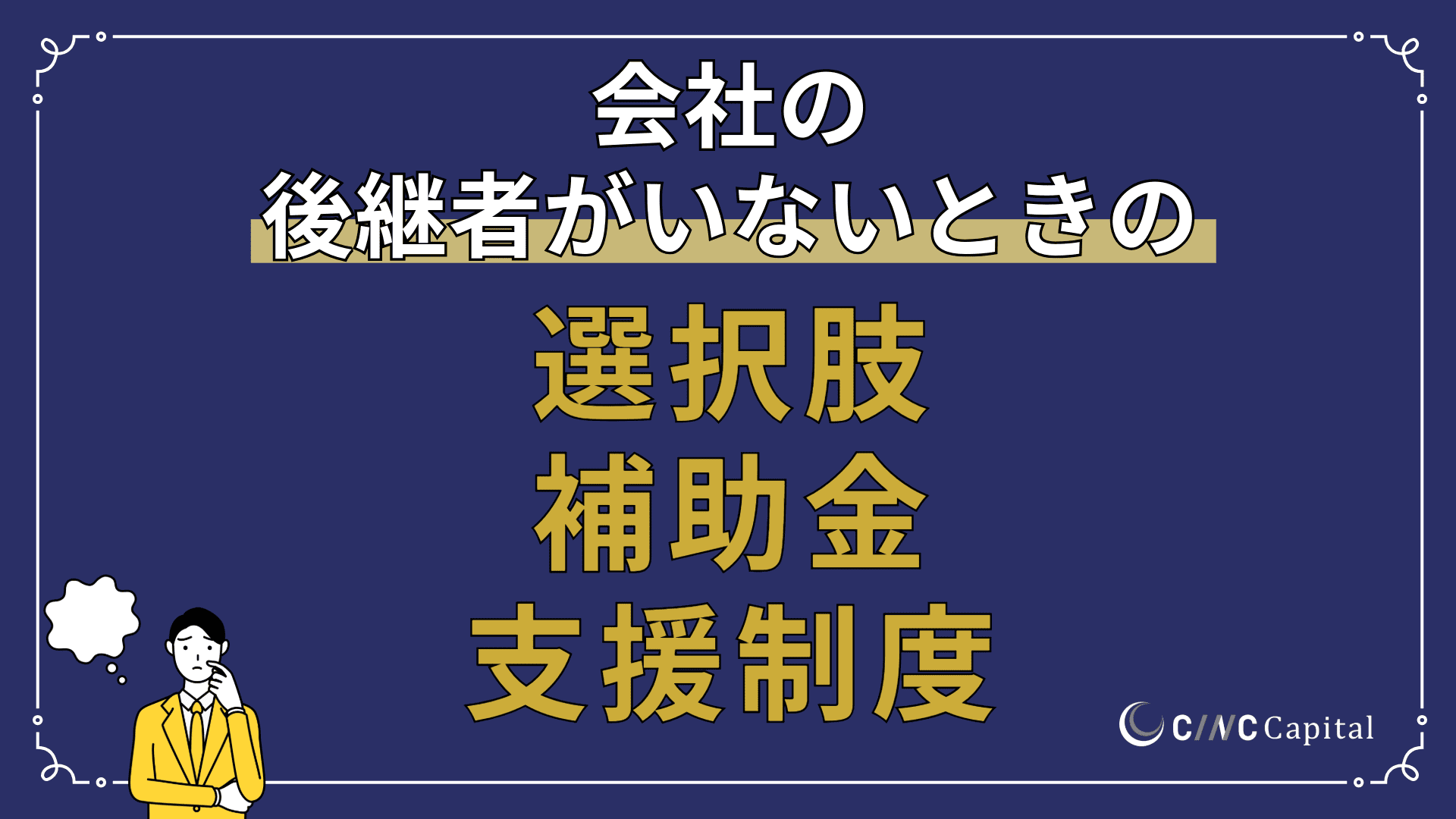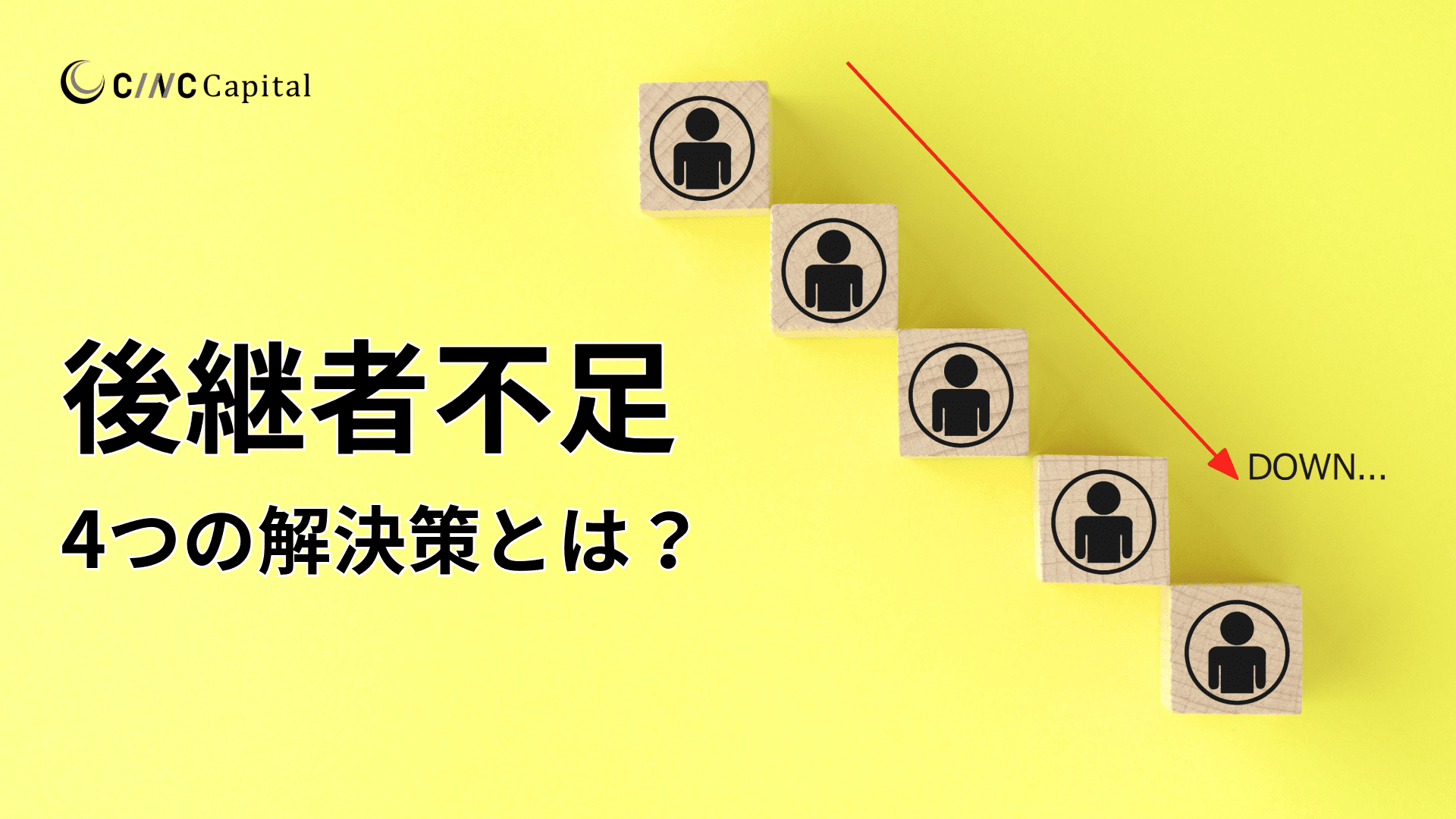CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
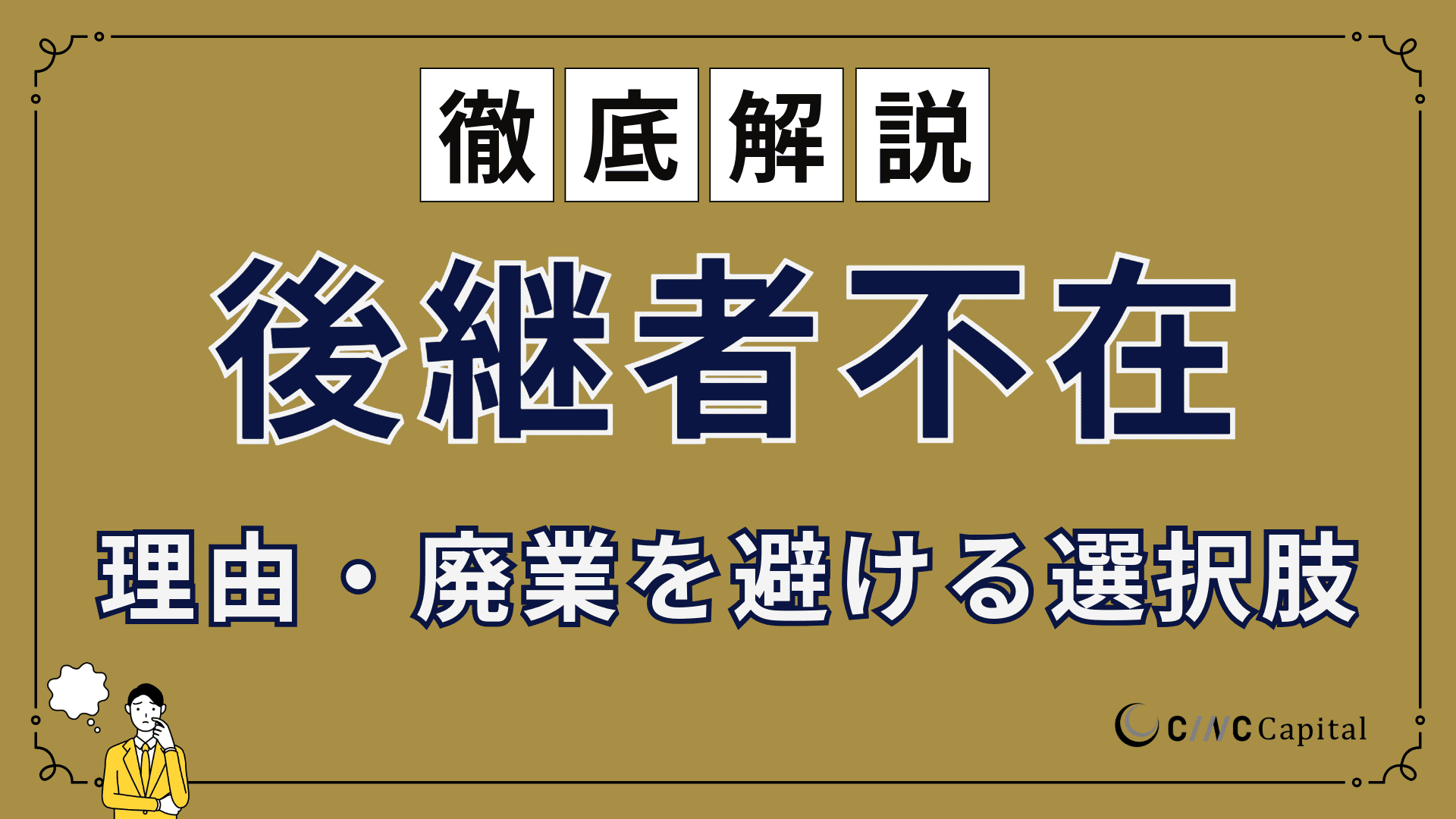
後継者問題・跡取り問題
- 公開日2025.09.30
後継者不在とは?理由や廃業を避けるための選択肢、ポイントを解説
後継者が見つからず、このまま会社をどうすべきか悩んでいませんか?
「子どもが継がない」「従業員に任せられない」と感じている経営者の方は少なくありません。
本記事では、中小企業における後継者不在の現状などを詳しく解説します。
目次
中小企業の後継者不在の問題の現状は?
中小企業の経営者の高齢化が進む中で、後継者が決まらない企業が多数存在しています。
2023年時点では、全国の中小企業経営者のうち70歳以上が約245万人に達し、その約半数が後継者未定とされています。
これは、黒字経営にも関わらず廃業せざるを得ない企業が増えている要因です。
事実、2022年の休廃業・解散件数は約5万件にのぼり、そのうち54.9%が黒字企業でした。
このように、後継者不在が原因で収益性のある企業すら市場から消えているのが現状です。
また、一時は66.5%まで上昇した後継者不在率は、近年やや改善傾向にあり、帝国データバンクの2023年調査では53.9%と報告されています。
それでもなお中小企業の約2社に1社は後継者が不在という深刻な状態です。
このまま対策を講じなければ、地域経済や雇用、産業インフラへの悪影響は避けられません。
後継者不在の原因
中小企業における後継者不在の背景には、複数の要因が複雑に絡んでいます。
特に、経営者の高齢化や親族内承継の減少、将来性に対する不安、後継者育成の遅れ、といった要素が、承継の障壁です。
本章では、それぞれの要因について詳しく解説します。
経営者の高齢化
中小企業の後継者不在が深刻化している最大の要因は、経営者の高齢化です。
2024年時点で中小企業の経営者の平均年齢は60.7歳に達しており、過去最高を更新しています。
特に60歳以上の経営者が全体の51.7%を占めており、引退時期を迎えてもなお事業承継が進んでいない企業が多数存在します。
このような状況では、急病や事故によって突然の経営断絶に陥るリスクが高くなります。
高齢化により残された時間が限られるなか、早急な承継準備が必要不可欠です。
【出典】帝国データバンク「全国「社長年齢」分析調査(2024年)」
親族内承継の減少
親族内で事業を引き継ぐケースが年々減少していることも、後継者不足の一因です。
近年では、親族内承継の割合が全体の3割程度まで減っており、代わって従業員や第三者への承継が増えています。
これは、後継候補となる子どもが家業を継がない選択をするケースが増えているためです。
また、経営者本人が「子に継がせたくない」と感じている場合もあり、親族内承継に対する価値観そのものが変化しています。
このように、親族内に適任者がいても承継されない現象が後継者不在を助長しています。
経営の将来性に対する不安
事業そのものの将来性に対する不安が、後継者確保を困難にしています。
実際に、日本政策金融公庫の調査では、今後5年以内の事業見通しを「良くない」とする経営者が7割を超えています。
このような悲観的な見方を持つ経営者は、そもそも事業を継がせる意欲が低く、後継者を育成する意識も薄くなりがちです。
また、承継される側からしても、先行き不透明な企業を継ぐリスクは大きいため、継承を避ける傾向があります。
こうした将来性への懸念が、後継者の不在を招く大きな要因となっています。
【出典】日本政策金融金庫「中小企業のうち後継者が決定している企業は10.5%、廃業を予定している企業は57.4%」
後継者育成の遅れ
後継者の育成が後回しにされることで、承継が間に合わないケースも多く見られます。
中小企業庁の調査によると、第三者承継では7割近くが準備期間1年未満で承継に踏み切っており、育成が不十分なまま承継が行われています。
特に親族外承継では、日常業務で手いっぱいの中小企業において、育成の時間や体制が確保できないまま事業を引き継ぐ事例が少なくありません。
このように、計画的な人材育成を怠ると、承継後の経営がうまくいかず、結果的に事業の継続が困難になるリスクが高まります。
負債や保証の問題
経営者の個人保証や企業の債務は、後継者の承継意欲を低下させる要因です。
実際に、帝国データバンクの調査では、新経営者の約6割が前経営者の個人保証を引き継いでいると報告されています。
経営に失敗したときに借金の返済を個人で負うので、家族や従業員が後継者になるのをためらうことがあります。
また、金融機関によっては個人保証を求め続ける姿勢もあり、後継者探しにおいてハードルを一層高めています。
財務上のリスクが承継の障害となっている企業は少なくありません。
後継者不在の企業の選択肢は?
後継者が見つからない場合でも、企業が取り得る選択肢は複数あります。
親族への承継が難しくても、従業員承継や第三者承継、公的機関の活用などによって事業を次世代につなぐことが可能です。
本章では代表的な6つの選択肢について、それぞれの特徴を紹介します。
親族内承継
親族内承継は、経営理念や価値観を継承しやすい方法です。
実際に家族であれば信頼関係も深く、取引先や社員に対しても安心感を与えることができます。
また、事業承継税制などの優遇制度を活用すれば、相続税や贈与税の負担も抑えられます。
しかし、継ぐ意思や適性のある子どもがいない場合は実現が難しくなります。
後継者候補がいる場合は、早期に育成を始めることが重要です。
従業員承継
従業員承継は、社内の信頼できる人材に経営を引き継ぐ方法です。
現場を理解している社員や役員が後継者となるため、業務の引継ぎがスムーズに進む利点があります。
特に近年は、親族内承継に代わる手段として実施する企業が増加傾向にあります。
ただし、株式の買い取り資金や経営知識の習得など準備すべき課題もあります。
承継対象者と十分な対話を重ね、段階的に経営権を委譲することが大切です。
事業引継ぎ支援センターの利用
事業引継ぎ支援センターは、後継者不在の中小企業を対象に、国が設置した公的相談窓口です。
後継者の紹介やM&Aマッチング支援、専門家によるアドバイスなどを無料で提供しています。
令和6年度には全国で23,000件以上の相談が寄せられ、2,000件超の第三者承継が実現しています。
創業希望者とのマッチングも行っており、事業承継の幅を広げる支援体制が整っているためです。
公的支援を活用することで、自力での後継者探しが難しい企業も道が開けるでしょう。
【出典】独立行政法人中小企業基盤整備機構「令和6年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について『第三者承継(M&A)の成約件数が過去最高を更新』」
M&Aによる第三者承継
M&Aは親族や従業員に代わり、外部の企業や個人に事業を譲渡する方法です。
後継者が見つからない企業でも、買収先が見つかれば事業の継続と発展が可能になります。
近年はM&Aを活用した事業承継が一般化し、民間仲介会社や支援機関のサポートを受ける企業も増えています。
自社の価値を見極め、専門家の支援を得ながら進めることが重要です。
IPO(株式公開)
一定の規模や成長性を持つ企業であれば、将来的なIPO(株式公開)を見据えて組織体制を整備するという選択肢もあります。
IPOによって資金調達の幅が広がり、外部からの人材登用や経営体制の強化を進めることができます。
ただし、上場には厳格な審査があり、ガバナンス・財務の透明性、そして経営の継続性が求められます。
特に、IPO直後にオーナー経営者が退任することは、投資家の信頼を損なうリスクが高く、実現可能性は極めて限定的です。
また、上場準備には通常2〜3年の時間と多額のコストがかかるため、後継者不在に悩む中小企業にとっては現実的な選択肢とは言えません。
したがって、IPOは「限られた企業のみが長期的視野で検討できる承継手段」であることを理解した上で、慎重に判断する必要があります。
廃業
後継者が見つからず、他の選択肢も選べない場合には、廃業も現実的な判断のひとつです。
2022年には全国で5万件以上の企業が休廃業や解散を選択しており、そのうち半数以上が黒字企業でした。
事業継続が困難な状況で無理に引き継がせるより、関係者への影響を最小限にした円満な廃業が望まれます。
法務や税務の整理には専門家の助言が必要なため、計画的に進めることが大切です。
後継者不在を解消するためのポイント
後継者不在の問題に直面した企業でも、早期に行動を起こせば事業の存続は十分可能です。
本章では、実際に効果的とされる4つの解決策を紹介します。
早めに承継の準備に取りかかる
後継者問題を解決するには、早期に準備を始めることが最も効果的です。
中小企業庁の調査でも、親族内承継で5年以上前から準備をしていた企業の多くがスムーズな移行に成功しています。
反対に、第三者承継では準備期間が短い傾向があり、混乱が生じやすいことが明らかになっています。
承継に必要な時間は年単位となるため、50代のうちから動き出すのが理想的です。
後継者の育成に注力する
後継者が決まっていても、育成が不十分であれば承継後の経営が不安定になります。
実際に、長期的な育成期間を確保した企業ほど、承継後の事業継続率が高い傾向にあります。
育成では、現場経験だけでなく、財務や人事、取引先対応といった総合的なマネジメントスキルが求められるのです。
経営者の意識として「育てて引き継ぐ姿勢」を持つことが、承継成功の基盤になります。
外部人材を活用する
親族や従業員に後継者が見つからない場合は、外部から人材を招く選択肢も有効です。
事業引継ぎ支援センターが運営する「後継者人材バンク」では、創業意欲のある人材と企業のマッチング支援が行われています。
2024年度には新規登録者が1,500人を超え、全国で100件以上のマッチングが成立しました。
経営経験や専門性を持つ外部人材の参画により、事業の再成長を狙うことも可能です。
【出典】独立行政法人中小企業基盤整備機構「令和6年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について『第三者承継(M&A)の成約件数が過去最高を更新』」
M&A仲介サービスに相談する
第三者承継を検討するなら、M&A仲介会社に相談することがおすすめです。
自社に適した買い手を見つけるには、相手企業の選定から条件交渉、契約締結まで複雑な手続きが必要となります。
こうした過程を専門家がサポートすることで、承継成功の可能性が大幅に高まるのです。
実際に、CINC Capitalなどの仲介を通じて、毎年数千件の中小企業が譲渡を実現しています。
まとめ
中小企業の後継者不在は、企業の存続だけでなく地域経済全体に影響を及ぼす深刻な課題です。
高齢化や親族承継の減少など原因は多岐にわたりますが、早期の準備と柔軟な選択があれば、事業を次世代につなぐことは可能です。
親族や従業員にこだわらず、第三者や公的支援を活用することで、承継の道は広がります。
後継者がいないからと諦めるのではなく、今できる行動を一つずつ積み重ねていきましょう。
CINC Capitalは中小企業の事業承継を専門に支援しています。
豊富な実績を持つアドバイザーが、会社と社員の将来を見据えながら最適な進め方をご提案し、円滑な承継を実現できるようお手伝いします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。