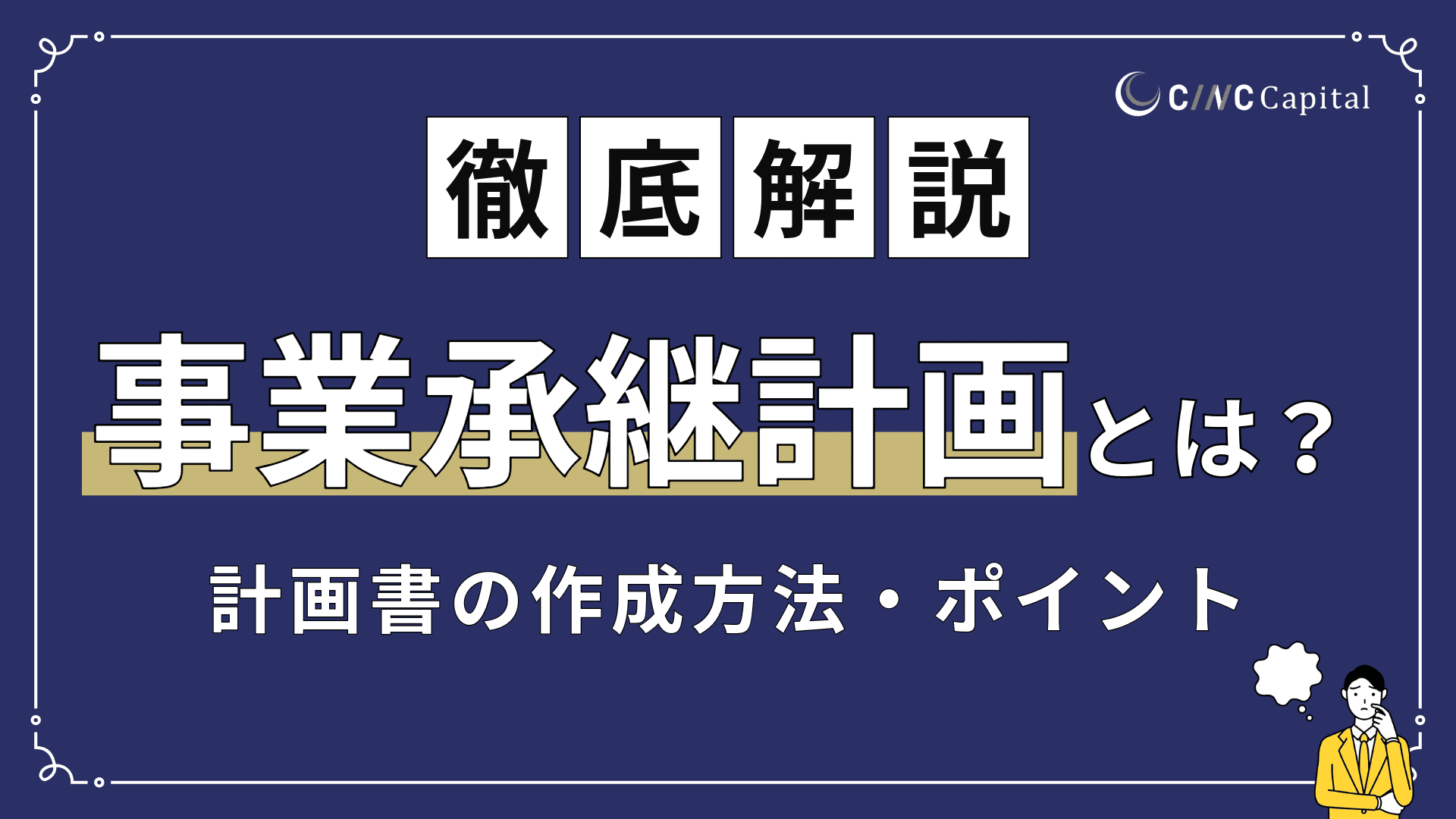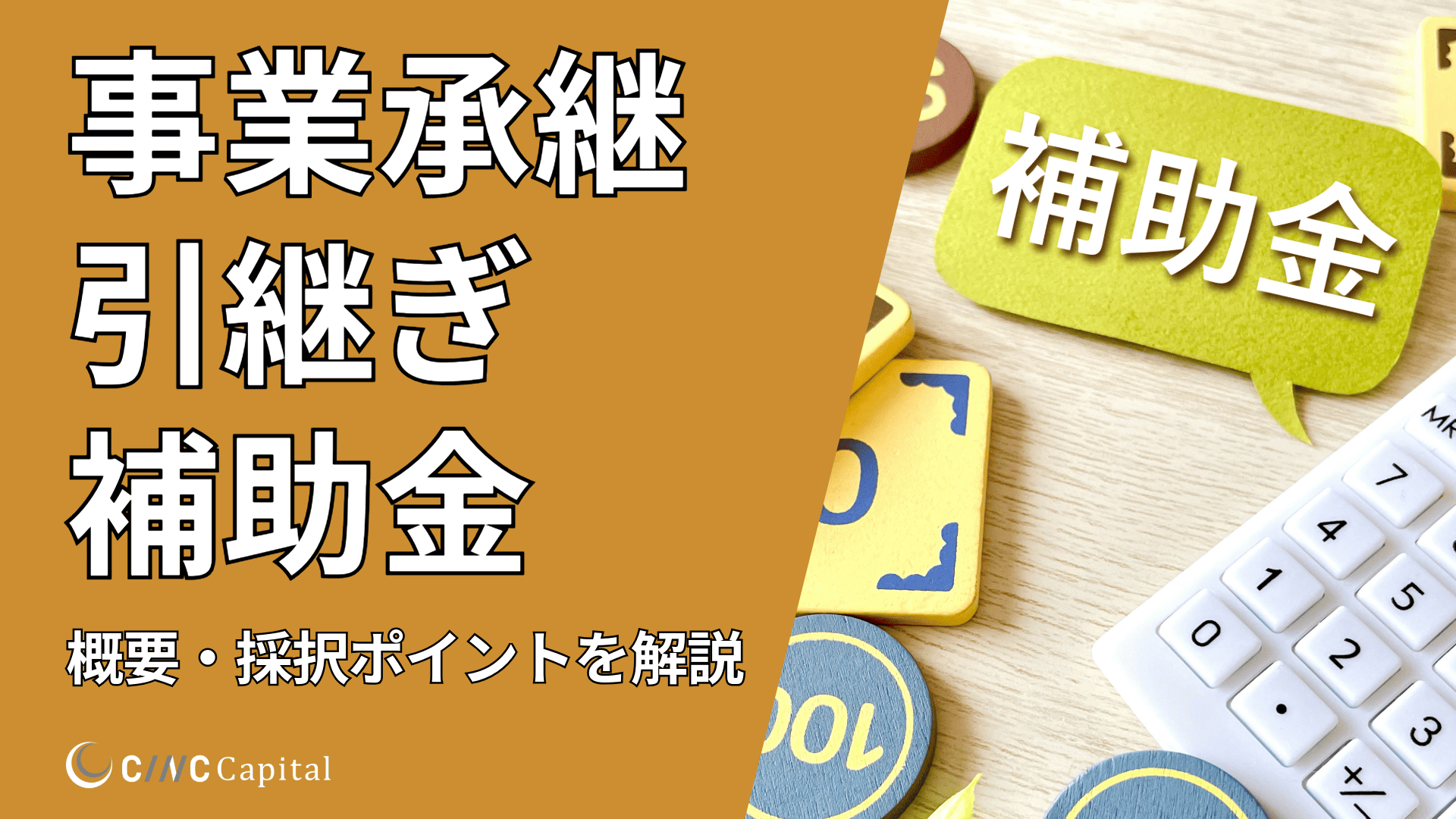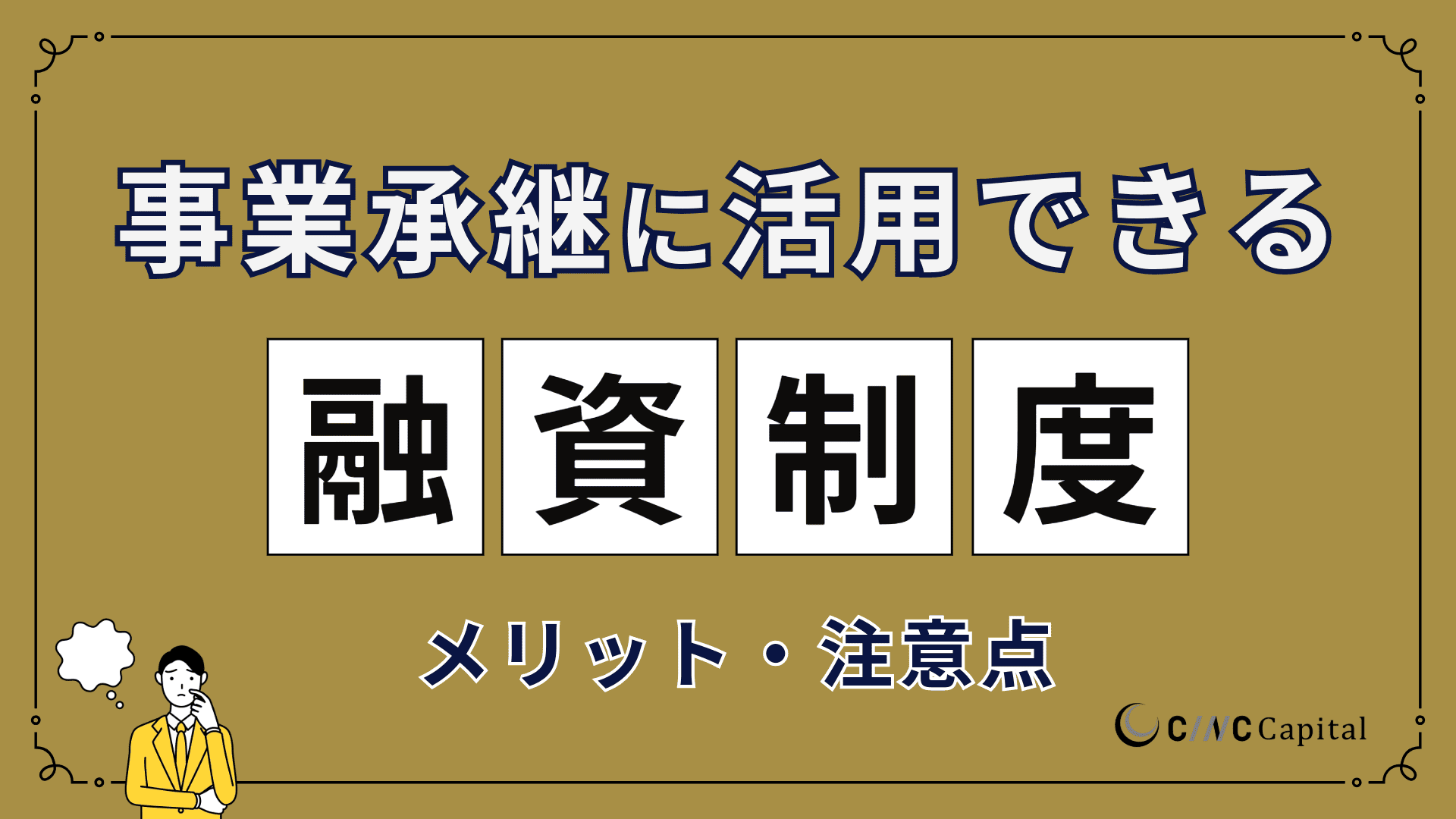CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

事業承継
- 最終更新日2025.07.08
親族内承継とは?メリットデメリットや税金、方法、成功させるためのポイントを解説
「会社を後継者に引き継ぎたいが、親族内承継が本当に最適なのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。親族内承継は、信頼関係が築かれた身内に事業を譲れる点が魅力です。しかし、後継者の適性や税負担など、考慮すべき課題も多く見られます。
本記事では、親族内承継のメリットとデメリット、具体的な手続き、税金対策、成功のポイントなどを解説します。スムーズな事業承継のために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
親族内承継とは
M&Aや事業承継の一形態として位置づけられる「親族内承継」とは、経営者の子どもや兄弟、孫などの親族に会社の経営を引き継ぐ事業承継の方法です。日本でも親族内での承継が多く、中小企業を中心に広く採用されています。親族内承継にはさまざまなメリットがありますが、後継者の選定や育成、税負担の対策など、多くの課題も伴います。まずは、親族内承継についての基礎知識を確認してみましょう。
親族外承継との違い
親族外承継とは、会社の役員や従業員、または第三者に事業を引き継ぐ方法です。親族以外の社内人材に承継する場合、企業文化の継承がしやすい一方で、株式の取得資金の問題が生じることが課題となります。
一方、親族内承継では、経営者自身が後継者を指名しやすく、従業員や取引先にとっても安心感があるのが特徴です。どちらの方法を選ぶにせよ、後継者の適性や会社の将来像を見据えた慎重な判断が求められます。
親族内承継の割合
親族内承継の割合は年々減少傾向にあります。2020年以降の過去5年間で代表者が交代した企業において、2024年(速報値)では、役員や社員を後継者とする「内部昇格」が36.4%を占めています。これまでもっとも多かった「同族承継」(32.2%)を上回りました。2023年(実績値)では「同族承継」が36.0%と最多でしたが、「内部昇格」との差はわずか1.6ポイントにまで縮小しています。
親族外承継の増加傾向の背景には、価値観の多様化により、後継者候補となる親族が事業を継ぎたがらないケースが増えていることがあります。少子化により、経営者の親族に後継者が存在しないパターンも珍しくありません。しかし、現在でも約3社に1社は親族内承継を選択しており、適切な準備と計画次第では成功させることが可能です。承継を円滑に進めるためには、早めの準備と後継者育成が鍵となるでしょう。
【出典】帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査」(2024年)
親族内承継のメリット
親族内承継には、長期的な視点で事業を引き継げる点や、従業員や関係者の理解を得やすい点など、多くの利点があります。ここでは、親族内承継の具体的なメリットについて解説します。
後継者の教育や引き継ぎの準備の時間を確保しやすい
親族内承継では、後継者を早い段階から育成し、十分な引き継ぎ期間を確保できるのが大きなメリットです。中小企業庁の調査によると、後継者を意識的に教育した場合、事業承継の満足度が高いことが分かっています。具体的には、現経営者との対話や各部門のローテーション、責任ある役職への登用などを通じて、後継者に必要なスキルや知識を身につけさせることができます。
従業員などの理解や協力を得やすい
親族内承継は、日本の中小企業において広く採用されている事業承継の方法です。そのため、従業員や取引先にとっても馴染みがあり、比較的スムーズに受け入れられるケースが多いでしょう。特に、創業者一族が経営を担う企業では、親族が後継者になることが自然な流れとみなされることが多く、社内外の理解を得やすいといえます。
さらに、後継者がすでに社内での経験を積んでいる場合、従業員との信頼関係が構築されているため、より円滑な事業承継が期待できます。
相続や贈与による事業承継ができる
親族内承継のもう一つの大きなメリットは、相続や贈与を活用して事業承継ができる点です。会社の株式や経営権をスムーズに引き継ぐことが可能になります。特に、中小企業では経営者が大半の株式を保有しているケースが多いため、親族内承継を選択することで、所有と経営の分離を回避しやすくなります。
ただし、相続税や贈与税の負担が発生するため、事前に適切な税務対策を講じることが重要です。
親族内承継のデメリット
親族内承継はメリットが多い一方で、いくつかのデメリットも伴います。事前にリスクを把握し、適切な準備を進めましょう。
親族間とトラブルが生じる可能性がある
親族内承継では、後継者の選定をめぐり親族間で意見が対立するケースがあります。社内に後継者以外の親族がいない場合でも、相続や贈与の際に株式の評価額が問題となり、親族間で争いが生じることがあります。
さらに、民法上の「遺留分」の問題にも注意が必要です。遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続財産の取り分のことで、原則として遺産の半分が該当します。遺留分を侵害された相続人は、遺贈や生前贈与を受けた後継者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるため、相続対策を慎重に進めることが重要です。
個人保証に関する問題が発生するおそれがある
中小企業の経営者は、金融機関からの融資に際して個人保証を求められるケースがあります。親族内承継を行う際には、後継者がこの個人保証をどのように引き継ぐのかが大きな課題となります。
後継者の経営実績がない場合、金融機関が個人保証の変更を認めないこともあるため注意が必要です。後継者の資力が十分でない場合、個人保証の引き継ぎが困難になり、結果として経営の安定性が損なわれる可能性もあります。
親族内承継の方法
親族内承継を円滑に進めるためには、計画的な準備が必要です。ここでは、親族内承継の具体的な方法について解説します。
- 親族内から後継者を選ぶ
親族内承継を進めるにあたり、まず後継者を選定することが必要です。後継者の適性や意欲を確認し、経営者としての資質を育成することが求められます。単に血縁関係があるだけでなく、会社の経営方針を理解し、従業員や取引先との信頼関係を築ける人物を選ぶことが望ましいでしょう。 - 会社資産の承継準備をする
後継者がスムーズに経営を引き継ぐためには、会社の資産承継の準備が不可欠です。特に、自社株や事業用資産の移転は慎重に行う必要があります。株式の割合によっては、ほかの親族との調整が求められるケースもあるため、専門家の助言を受けながら適切に進めましょう。 - 従業員や取引先へ周知する
後継者が決まった後は、従業員や取引先に対して事業承継の計画を周知することが重要です。早めに情報を共有することで社内外の混乱を防ぎ、取引の継続性を確保できます。また、後継者の紹介を行い、信頼関係を構築することも大切です。 - 承継手続き(相続・生前贈与・遺言など)を行う
会社の経営権を正式に引き継ぐためには、相続や生前贈与、遺言などの法的手続きを適切に行う必要があります。相続税や贈与税の負担を考慮し、計画的に資産移転を進めることが求められます。遺留分の問題が発生しないよう、専門家と相談しながら進めるのが賢明です。 - 個人保証を後継者に変更する
中小企業では、現経営者が会社の借入に対して個人保証をしているケースが多く、事業承継時には後継者への保証変更が必要になります。しかし、後継者の経営実績がない場合、金融機関が保証変更を認めない可能性もあります。そのため、事前に金融機関と交渉し、適切な対応を取ることが大切です。
親族内承継にかかる税金
親族内承継を行う際には、相続税や贈与税、株式譲渡にかかる所得税など、さまざまな税金が発生します。どの方法で承継するかによって課税額が変わるため、それぞれの仕組みを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
相続税・贈与税
相続税は、事業承継の際に後継者が相続した財産に課される税金です。課税額を算出するためには、まず課税遺産総額を求め、法定相続分で按分した後、税率と控除額を適用して計算します。
一方、贈与税は生前贈与によって事業承継を行う場合に発生する税金です。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、それを超える部分に税率が適用されます。相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円までの贈与が非課税になりますが、贈与者が亡くなった際には相続税の計算に含めることが必要です。
なお、2024年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度を選択した場合でも、贈与額の合計に対して年間110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
所得税・復興特別所得税・住民税
株式を後継者に譲渡(売買)する場合、現経営者には所得税や住民税が課されます。譲渡益に対する税率は、所得税が15%、住民税が5%です。また、2037年までは所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税も加算されます。株式の評価額や譲渡のタイミングによって税負担が変わるため、慎重に計画することが大切です。
事業承継税制の活用
親族内承継における大きな負担となる税金対策として、「事業承継税制」の活用が効果的です。事業承継税制とは、後継者が経営者から自社株式等を相続・贈与により取得した場合に、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。
2018年の税制改正により、2027年までの特例措置として、「納税猶予対象株式の拡大(発行済株式総数の最大100%)」「雇用確保要件の実質的な撤廃」「後継者以外の株主からの買取りに係る相続税の納税猶予」などの優遇が受けられるようになりました。
適用条件としては、「中小企業であること」「5年間の事業継続」「雇用の8割維持」などがあります。特に、事前の経済産業大臣の認定を受けることが必須となるため、計画的な申請が重要です。税負担の軽減により事業の継続性が高まるだけでなく、後継者の経済的負担が大幅に軽減されるため、積極的に検討しましょう。
親族内承継の成功事例と失敗事例
ここでは、親族内承継でよく見られるパターンとして、成功事例と失敗事例をご紹介します。
【成功事例】老舗和菓子店の親族内承継
創業100年を超える老舗和菓子店A社では、先代社長が60歳を迎えた時点で、当時30歳だった長男への事業承継計画を立てました。10年かけて段階的に権限を委譲し、株式も相続時精算課税制度を活用して計画的に贈与。
また、他の子どもたちには事前に十分な説明を行い、不動産などの資産で相続のバランスをとることで遺留分の問題を回避しました。現在は3代目となる長男が事業を成長させ、新たな商品開発も成功させています。
【失敗事例】製造業の親族内承継
従業員50名の製造業B社では、創業者が突然の病で倒れ、準備が不十分なまま長男が事業を承継しました。ところが、事前の取り決めがなかったため、他の兄弟から「遺留分」を理由に株式の分配要求が出され、家族間で対立が発生。
さらに、後継者の長男は経営経験が乏しいため、金融機関からの信頼を得られず、運転資金の確保に苦労することになります。結果的にB社は業績が悪化し、第三者への事業売却を余儀なくされました。
親族内承継を成功させるためのポイント
親族内承継を円滑に進めるためには、事前の準備と関係者の理解が不可欠です。具体的なポイントを確認していきましょう。
後継者は早めに決めて準備を進める
親族内承継を成功させるには、後継者の早期決定と育成が重要です。後継者の意向を確認し、必要な知識や経営スキルを身につけるための育成期間を確保することが求められます。特に、後継者が他社での経験を積んでいる場合や、経営に関する十分な知識を持っていない場合には、計画的な育成が欠かせません。
また、事業承継には時間がかかるため、できるだけ早い段階から準備を始めることが望ましいでしょう。事業承継計画を策定し、経営の引き継ぎを段階的に進めることで、後継者がスムーズに経営を担えるようになります。
後継者以外の親族や取引先へ周知し理解を得る
事業承継を行う際には、後継者本人だけでなく、後継者以外の親族や取引先にも周知し、理解を得ることが大切です。特に親族内での承継では、後継者以外の親族が経営に関わるかどうか、株式をどのように分配するかといった点でトラブルが生じる可能性があります。
事前に話し合いの場を設け、親族間で承継の方針を共有することで、相続トラブルの回避につながります。また、取引先や金融機関にも後継者の決定を伝えることで、経営の安定性に対する不安を解消し、承継後のスムーズな取引継続が期待できるでしょう。
個人保証や税金の対策を行う
事業承継に伴う個人保証や税金の問題は、後継者にとって大きな負担となる可能性があります。現経営者が個人保証をしている場合、後継者がそのまま引き継ぐことになれば、将来的に大きな返済負担が発生するリスクがあります。これを避けるために、「事業承継特別保証」などの制度を利用することが有効です。
また、相続税や贈与税の負担を軽減するために、事業承継税制の活用を検討しましょう。事業承継税制を利用すれば、相続税や贈与税の納税猶予を受けられるため、後継者の負担を軽減できます。適用要件や手続きについては、専門家に相談しながら進めるのが望ましいでしょう。
公正証書を作成する
事業承継に関する取り決めを明確にし、親族間のトラブルを防ぐためには、公正証書の作成が有効です。公正証書にすることで、後継者の決定や事業資産の分配に関する合意内容が法的に証明され、万が一の際にも円滑な承継が可能になります。
遺言書の作成を公正証書として行うことで、後継者への自社株や事業資産の集中承継を確実にし、相続トラブルのリスクを低減できます。公証役場での手続きが必要となるため、事前に準備を進めることが重要です。
事業承継の専門家などに相談する
親族内承継は、経営や法律、税務などの幅広い知識が求められるため、専門家の支援を受けながら進めることが成功の鍵となります。税理士や公認会計士、弁護士、事業承継コンサルタントなどの専門家に相談することで、最適な承継プランの策定や手続きの適正な進行が可能になります。
例えば、税務面での対策を講じるためには、税理士のアドバイスが欠かせません。また、親族間での意見調整や株式承継のスキーム設計には、弁護士やM&Aアドバイザーの支援が有効です。事業承継に関する制度や補助金の活用についても、専門家に相談することで適切な選択ができます。
まとめ|親族内承継を円滑に進めるためには早めの準備が重要
親族内承継を成功させるためには、後継者を早めに決定し、十分な準備期間を確保することが不可欠です。後継者の育成や親族・取引先への周知、自社株の承継計画、個人保証や税金対策など、事前に対策を講じることでスムーズな事業承継が可能となります。
また、公正証書の作成や専門家への相談を通じて、法的・税務的なリスクを最小限に抑えることも重要です。親族内承継は感情的な問題も絡むため、中立的な立場からアドバイスできる専門家のサポートが特に有効です。
弊社CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、親族内承継を含む様々な事業承継のサポートを提供しています。親族内承継の各プロセスにおける専門的なサポートを、透明性の高い料金設定でご提供します。
業界歴10年以上または特定業界に精通したアドバイザーのみがお客様をサポート。親族内承継特有の課題や感情的な側面にも配慮しながら、最適な解決策をご提案します。
親族内承継においても、資産の評価や譲渡条件の設定など、データに基づいた客観的な判断をサポートします。親族内承継に関するご相談は、ぜひCINC Capitalにお問い合わせください。