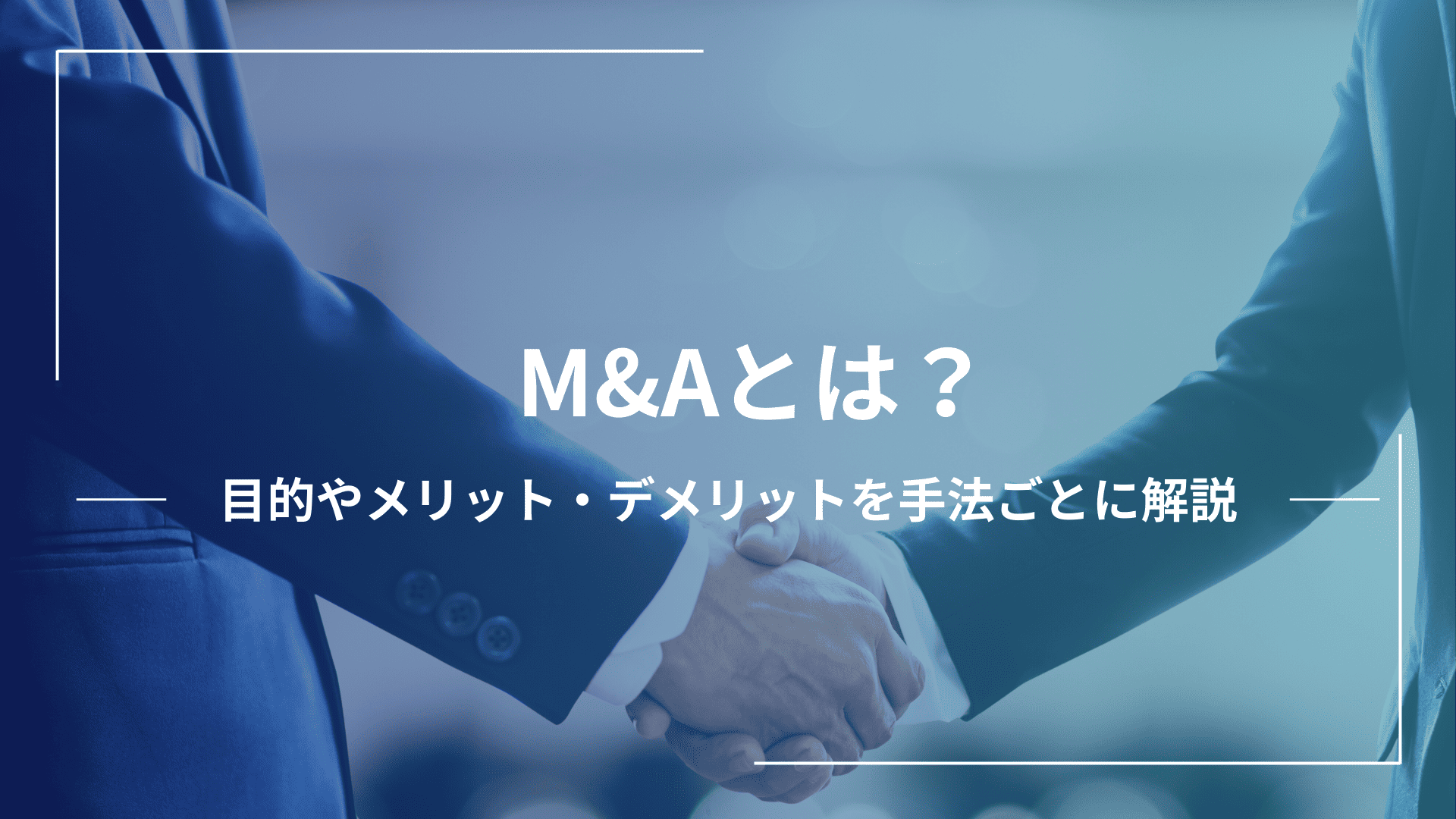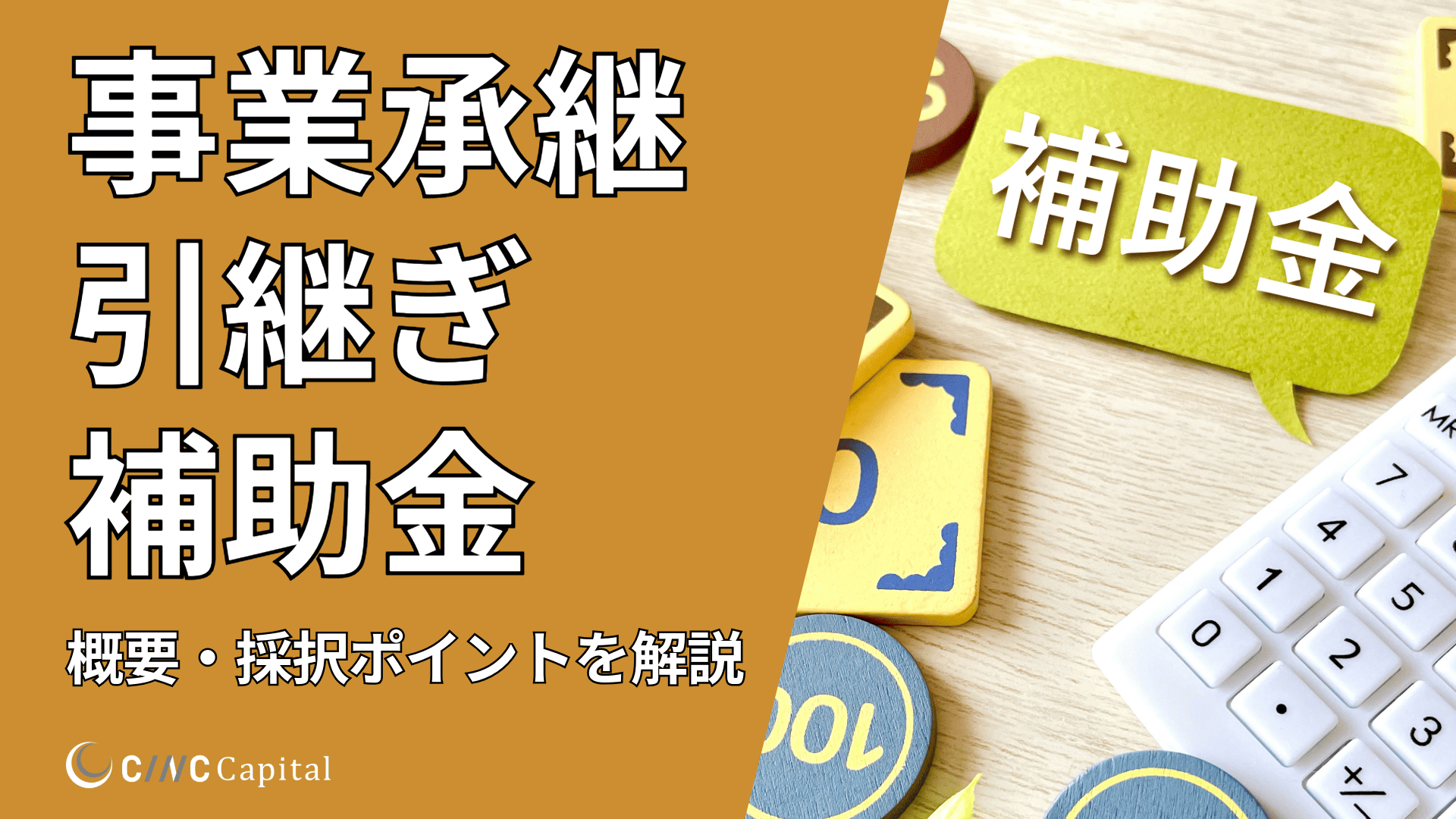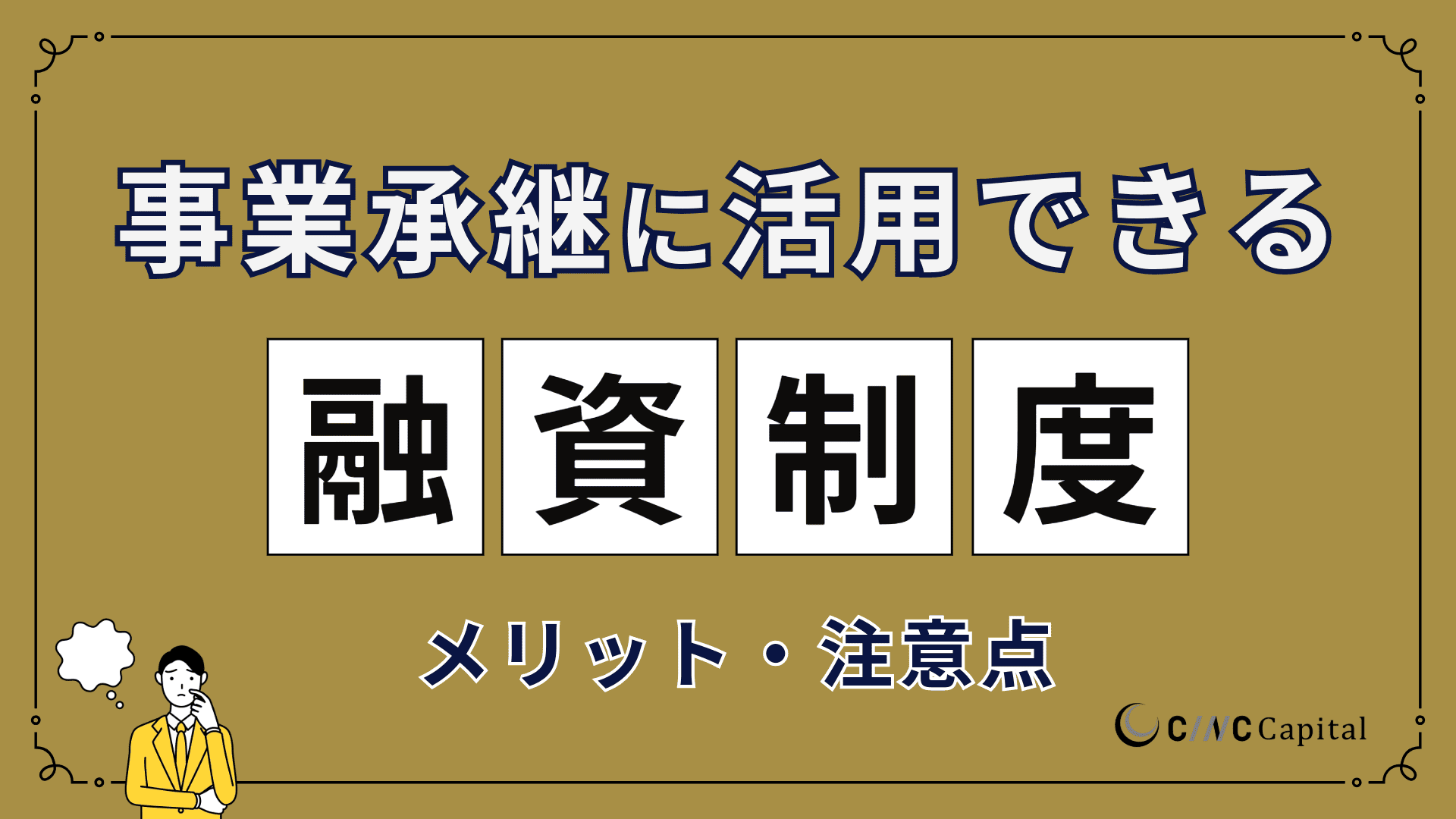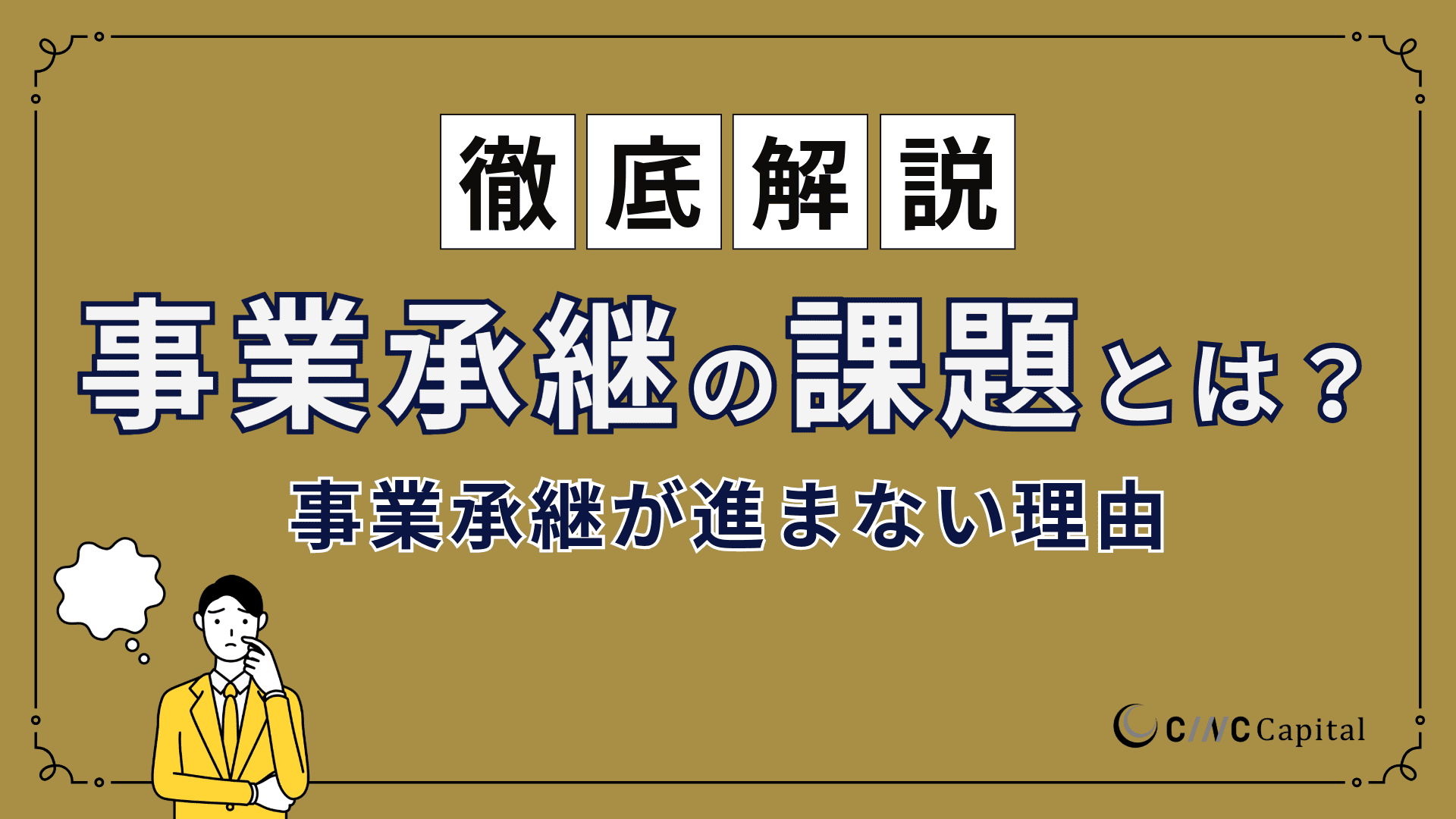CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
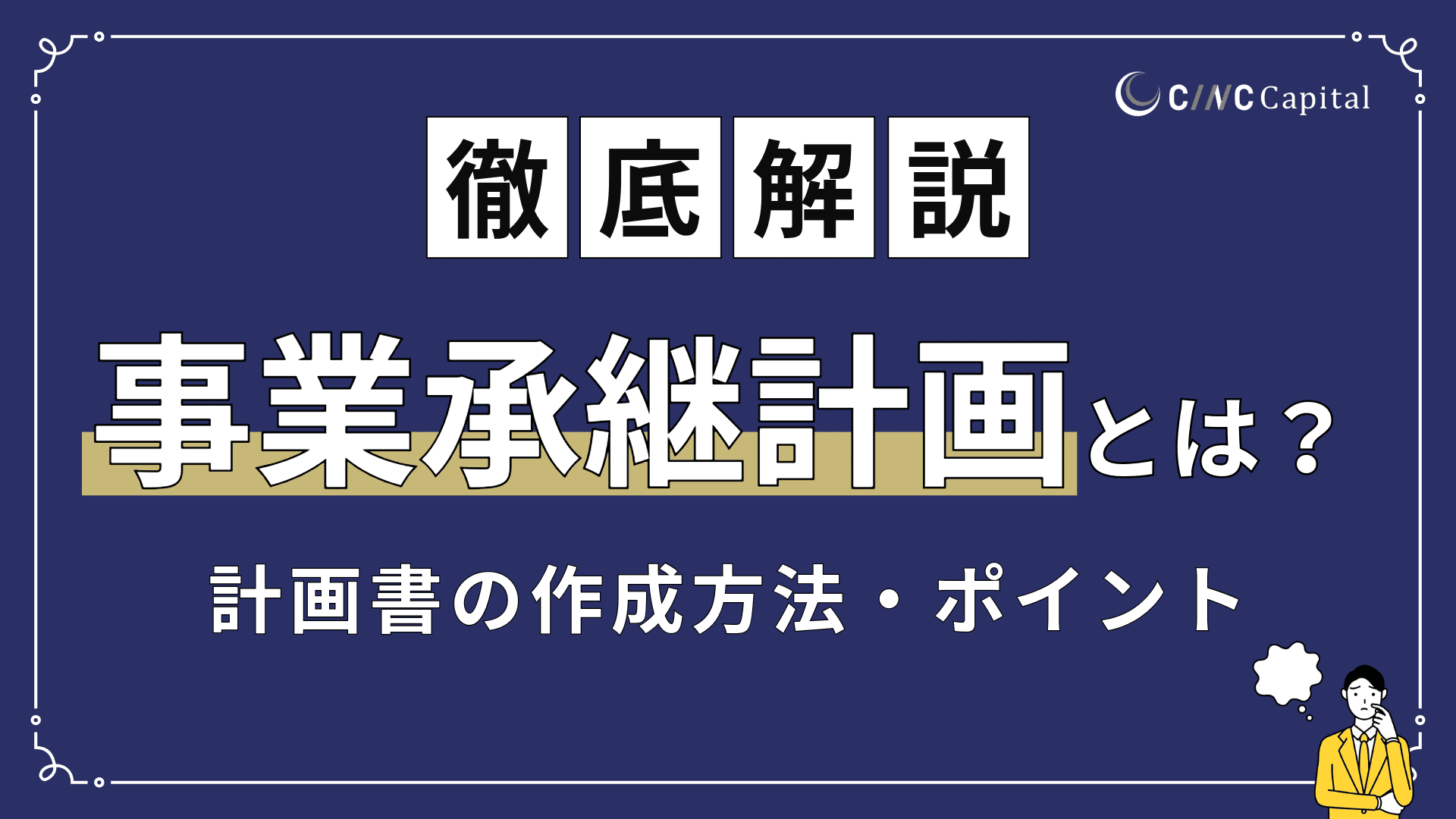
事業承継
- 公開日2025.09.30
事業承継計画とは?事業承継計画書の作成方法や策定のポイントを解説
事業承継を考える経営者の中には、「後継者は決まっているものの、何から始めればよいか分からない」と悩んでいる方も少なくありません。
本記事では、事業承継計画書の作成方法や、承継の種類、特例承継税制の活用条件など、事業承継を円滑に進めるためのポイントを詳しく解説します。
目次
事業承継計画とは?
事業承継計画とは、経営者が将来の引退を見据えて、誰に・いつ・どのように会社を引き継ぐかを明確にする中長期的な計画です。
事前に計画を立てることで、経営の空白や混乱を防ぎ、関係者との信頼関係を保ちながら円滑な承継が可能です。
この計画には、株式や資産の引き継ぎだけでなく、経営ノウハウや従業員・取引先との関係といった無形の経営資源の承継も含まれます。
現経営者と後継者が協力しながら進めることで、将来に向けた企業の方向性や課題を共有しやすくなります。
実際には「誰に承継するか」「いつ引き継ぐか」「どのような課題があるか」といった項目を整理し、文書化するのが一般的です。
この計画を通じて、税務や法務、資金の準備といった実務的な対応も早めに進めることができ、事業継続に必要な体制を整えやすくなります。
事業承継の種類
事業承継には複数の方法があり、後継者の立場によって大きく3つに分類されます。
本章では「親族内承継」「従業員承継」「第三者M&A」それぞれの特徴やメリット・課題について解説します。
親族内承継
親族内承継は、経営者の子どもや配偶者などの親族に事業を引き継ぐ方法です。
もっとも伝統的で、経営理念や価値観の共有がしやすいことが利点です。
加えて、周囲からの理解も得やすく、従業員や取引先との信頼関係を維持しやすい傾向があります。
しかし、親族間で後継者をめぐる対立が起きるリスクや、経営能力や意欲に不安がある場合の懸念も見過ごせません。
また、相続税や贈与税など資産移転にかかる税金が発生するため、事前の対策も必要になります。
そのため、早期に候補者を育成し、税務面や株式の集中管理にも配慮した計画を立てることが重要です。
従業員承継
従業員承継は、役員や社員など社内の人材に経営を引き継ぐ方法です。
親族に後継者がいない場合の選択肢として有効であり、会社を熟知している人材が承継することで、社内外からの信頼を維持しやすくなります。
加えて、業務の引継ぎがスムーズで、経営方針を大きく変えずに事業を継続できる点も大きなメリットです。
ただし、株式取得に必要な資金が課題となるほか、経営能力やリーダーシップの育成も必要となります。
この承継方法では、経営者としての適性を見極めたうえで、資金面・スキル面の支援を整えることが成功の条件となります。
第三者M&A
第三者M&Aは、親族や社内に後継者がいない場合に、外部の企業や個人に事業を譲渡する方法です。
M&Aを活用することで、事業の継続性を確保しつつ、経営者は株式の売却益を得て引退することができます。
また、買い手が新たな資本やノウハウを持ち込むことで、事業拡大のチャンスも生まれます。
一方で、買い手の選定や条件交渉に時間を要することがあり、従業員や顧客への影響も慎重に考慮しなければなりません。
第三者承継は、専門家の支援を受けながら計画的に進めることで、会社の価値を守りながら未来へとつなげる選択肢となります。
事業承継計画書の作成方法
事業承継計画書の作成は、円滑な事業承継を実現するための重要なステップです。
本章では、現状の把握から関係者の意思確認、承継方法や時期の検討、そして計画書・計画表の作成まで、具体的な手順を解説します。
現状を把握する
事業承継計画を立てる第一歩は、会社の現状を正確に把握することです。
これには、財務状況、経営資源、組織体制、株主構成、経営者個人の資産や保証状況などの確認が含まれます。
会社の情報を整理しておくと、事業承継で起こりうる課題やリスクが見えてきます。
現状把握を怠ると、後継者が思わぬ問題に直面し、事業の継続に支障をきたす可能性があります。
したがって、現状の詳細な分析は、事業承継計画の成功に不可欠です。
関係者への意思を確認する
事業承継を円滑に進めるためには、関係者の意思確認が重要です。
後継者候補の意欲や適性を確認し、親族、役員、従業員、取引先などの関係者と十分なコミュニケーションを図ることで、承継に対する理解と協力を得ることができます。
関係者の意向を無視した承継は、後継者への反発や信頼の失墜を招くおそれがあります。
関係者の意思を尊重し、合意形成を図ることで、事業承継が円滑に進むでしょう。
承継方法や承継時期を検討する
承継方法や時期の検討は、事業承継計画の核心部分です。
親族内承継、従業員承継、第三者へのM&Aなど、会社の状況や後継者の有無に応じて最適な方法を選択します。
承継時期については、後継者の準備状況や経営環境に加え、現経営者の年齢や健康状態、経営計画との整合性、主要取引先や金融機関の意向なども考慮します。
例えば、「現経営者が65歳になる年度末までに社長職を引き継ぐ」といった時期の目安を設定し、その前後に段階的な引継ぎを行うスケジュールを設計すると効果的です。
承継方法や時期を曖昧にすると、計画の実行に支障をきたす場合があるので注意が必要です。
事業承継計画書・事業承継計画表を作成する
現状分析と関係者の意思確認、承継方法や時期の検討を踏まえ、具体的な事業承継計画書と計画表を作成します。
計画書には、以下のような項目を盛り込むことが推奨されます。
- 承継の目的と背景
- 後継者の氏名と選定理由
- 承継予定日およびスケジュール
- 組織体制や役員構成の変更案
- 株式や資産の承継方法と分配計画
- 財務状況と資金調達計画
- 課題と対応策
- ステークホルダー(従業員、取引先、金融機関)への対応方針
計画表は、承継までの具体的な行動計画を時系列で整理し、進捗管理を容易にします。
また、事業承継税制の特例措置を利用する際にも、計画書の提出が求められるため、早期の作成が重要です。
株式の承継にあたっては、承継方法に応じた評価が必要です。
親族内承継の場合には、国税庁が定める評価方法(類似業種比準価額方式・純資産価額方式など)による株価評価が重要になります。
類似業種比準価額方式では、利益・配当・純資産などの水準を基準に評価額が算定されます。そのため、利益水準が高い企業では評価額が高くなりやすく、結果的に贈与税・相続税の負担も増える可能性があります。
事前に自社株の評価額を確認し、必要に応じて株式の分散や評価引下げ策(持株会社設立、役員退職金の計上など)を検討することが重要です。
一方、第三者M&Aの場合には、将来の収益力や市場環境を反映した企業価値評価(DCF法、マルチプル法など)が用いられます。
会社の状況や評価方法の選択によって結果は異なるため、専門家に試算を依頼することが望ましいです。
特例承継税制を活用する際の条件と提出期限
特例承継税制は、後継者が非上場株式を贈与または相続により取得した際、贈与税や相続税の納税が猶予・免除される制度です。
2018年から2027年までの10年間限定の措置であり、一定の条件を満たすことで税負担を大幅に軽減できます。
活用には、まず「特例承継計画」を2026年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
計画書には、後継者の情報や承継時期、経営見通しなどを記載し、さらに認定支援機関の指導を受けることが必要です。
認定支援機関とは、中小企業庁から認定を受けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関など)で、事業承継や資金調達、経営改善などに関する支援を行う機関です。
計画の妥当性や実行可能性の観点から、第三者の助言を受けることで、より実効性のある承継計画に仕上がります。
また、承継後は後継者が代表者に就任し、株式を継続保有するなどの要件もあります。
なお、贈与や相続の実行は2027年12月31日までが期限です。
この制度を活用するために、早期の準備を行いましょう。
事業承継計画策定のポイント
事業承継計画を策定する際には、会社の経営資源や資産状況の把握、後継者の選定と育成、そして予期せぬ問題への対応策の準備が重要です。
本章では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
会社の経営資源や資産状況を把握しておく
事業承継計画を立てる上で、会社の経営資源や資産状況を正確に把握することが不可欠です。
これには、財務状況、資産・負債、知的財産、従業員のスキルや経験などが含まれます。
これらの情報を整理することで、後継者が事業を円滑に引き継ぐための基盤を築くことができます。
また、経営資源の見える化により、事業の強みや課題を明確にし、承継後の成長戦略を立てる際の指針となるでしょう。
後継者について十分に検討する
後継者の選定は、事業承継の成否を左右する重要な要素です。
適切な後継者を選ぶためには、候補者の経営能力、リーダーシップ、企業文化への理解度などを総合的に評価する必要があります。
また、後継者の育成には時間がかかるため、早期に計画を立て、段階的に権限移譲や実務経験を積ませることが望ましいです。
これにより、後継者が自信を持って経営を担えるようになります。
問題が発生しても対応できるようにしておく
事業承継の過程では、想定外の問題が発生することがあります。
例えば、後継者が急に承継を辞退した場合には、サブ候補の育成や社外人材の確保といった代替プランを事前に準備しておく必要があります。
経営者に不測の事態が起こった際には、緊急承継マニュアルや遺言書、信託契約などを活用した緊急承継体制の整備が有効です。
また、株主間で意見の対立が生じた場合には、事前に株主間契約や議決権の取り決めを定めておくことで調整がしやすくなります。
これらのリスクに対しては、可能性と影響度を分類したチェックリストを用いて整理し、それぞれに対応する施策を明文化しておくことが望まれます。
加えて、税理士や弁護士など専門家のサポートを受けることで、法的・実務的なリスクにも柔軟に対応できます。
準備を怠らず、複数のシナリオを想定して備えることが、事業承継の成功を左右します。
まとめ
事業承継計画は、企業の未来を左右する重要な取り組みです。
計画的な承継を進めることで、経営の混乱を防ぎ、関係者との信頼関係を維持しながら円滑な承継を実現できます。
事業承継計画書の作成は、現状の把握、関係者の意思確認、承継方法や時期の検討、具体的な計画書・計画表の作成といったステップを踏むことで、スムーズな事業承継が可能となります。
また、特例承継税制の活用により、税負担の軽減も図ることが可能です。
事業承継計画を策定する際には、会社の経営資源や資産状況の把握、後継者の選定と育成、予期せぬ問題への対応策の準備が重要です。