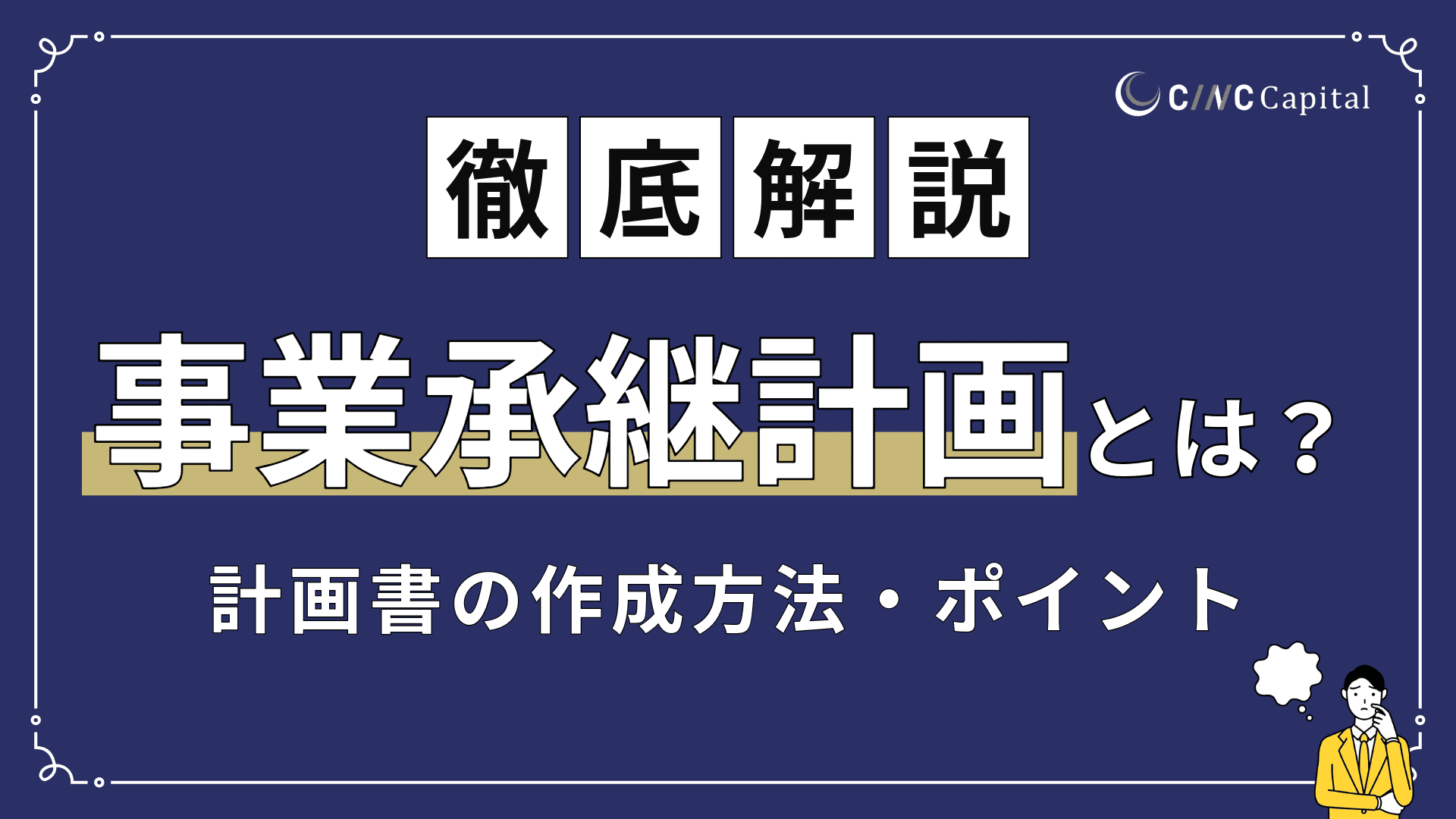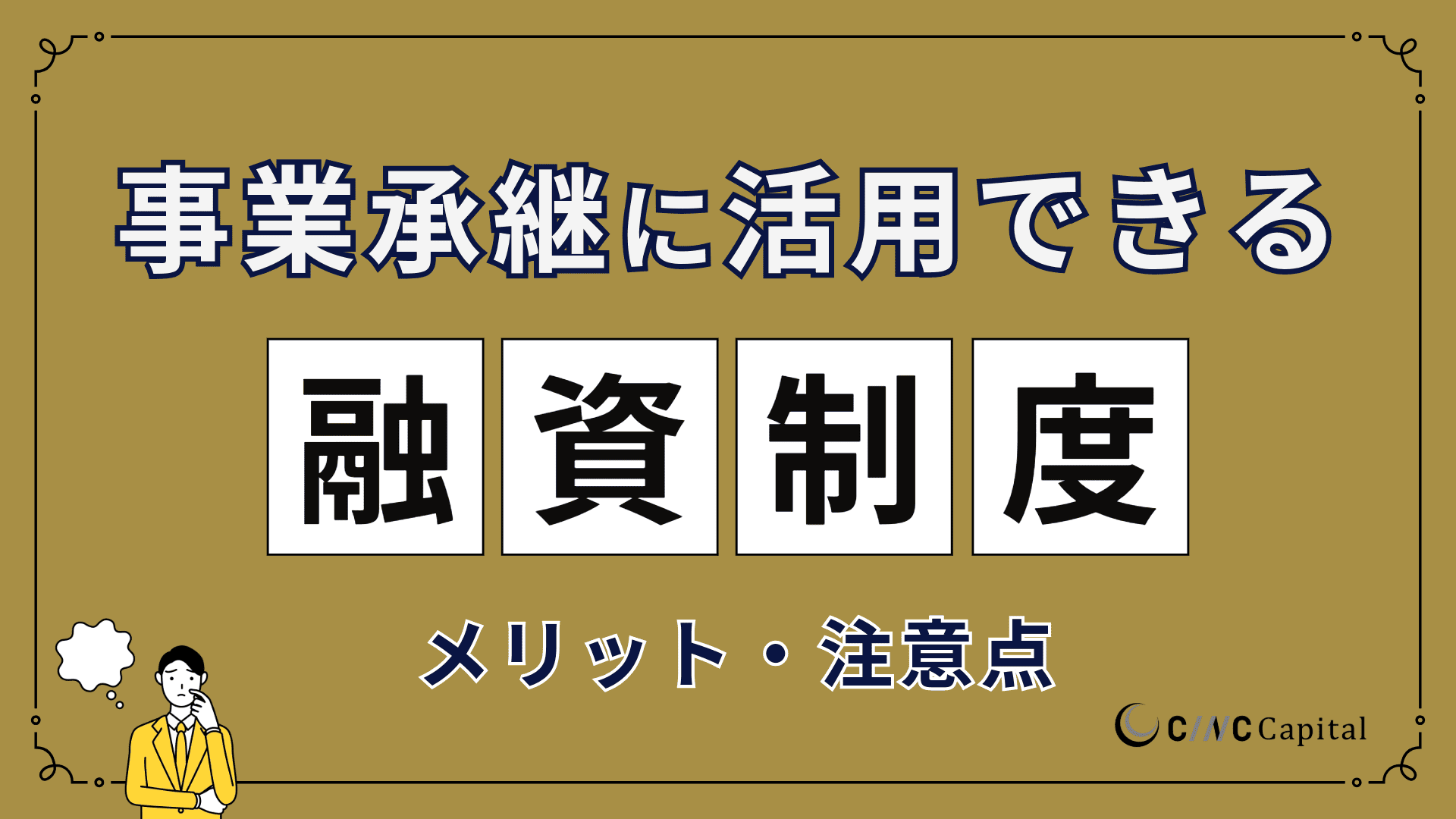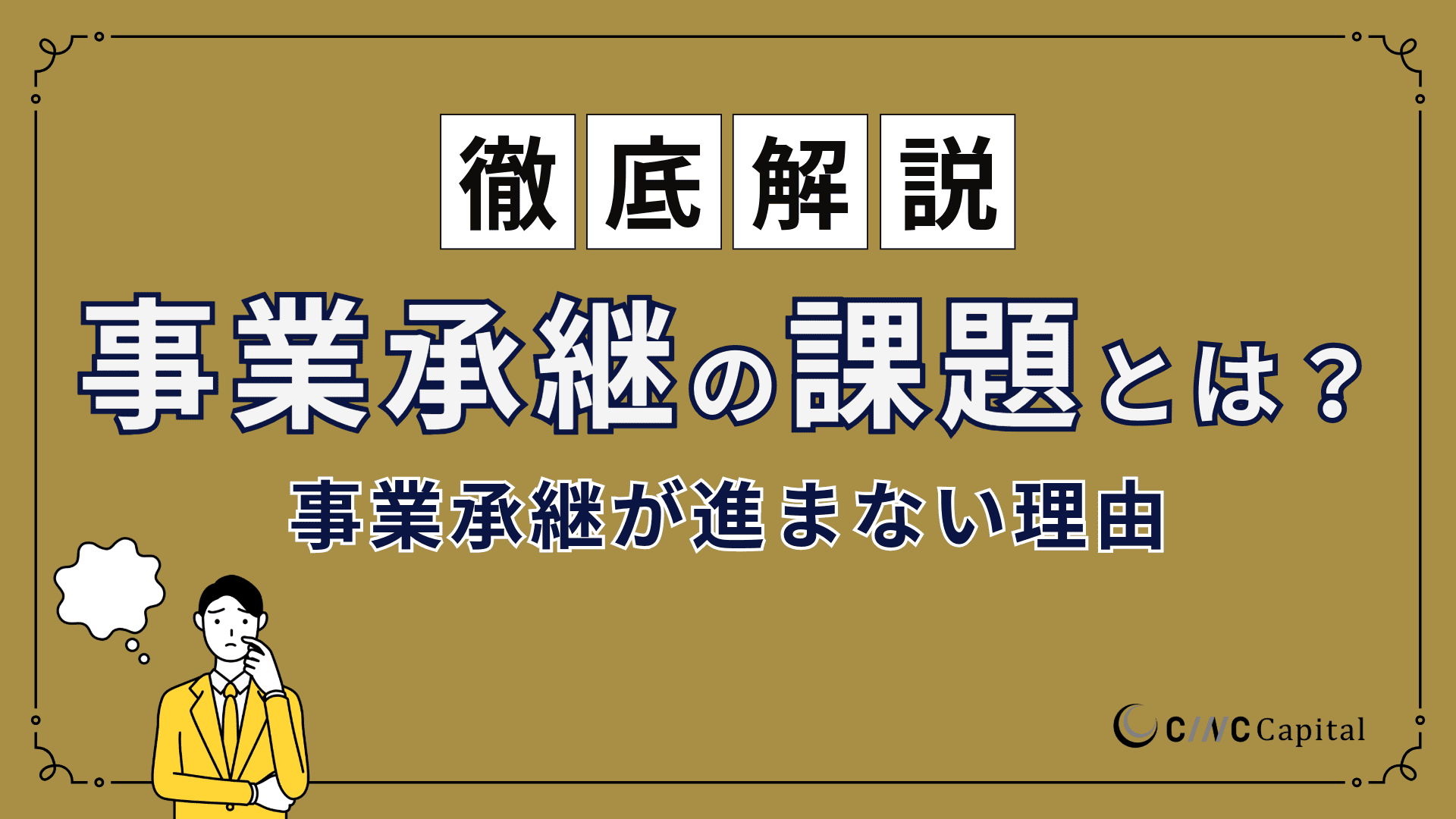CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
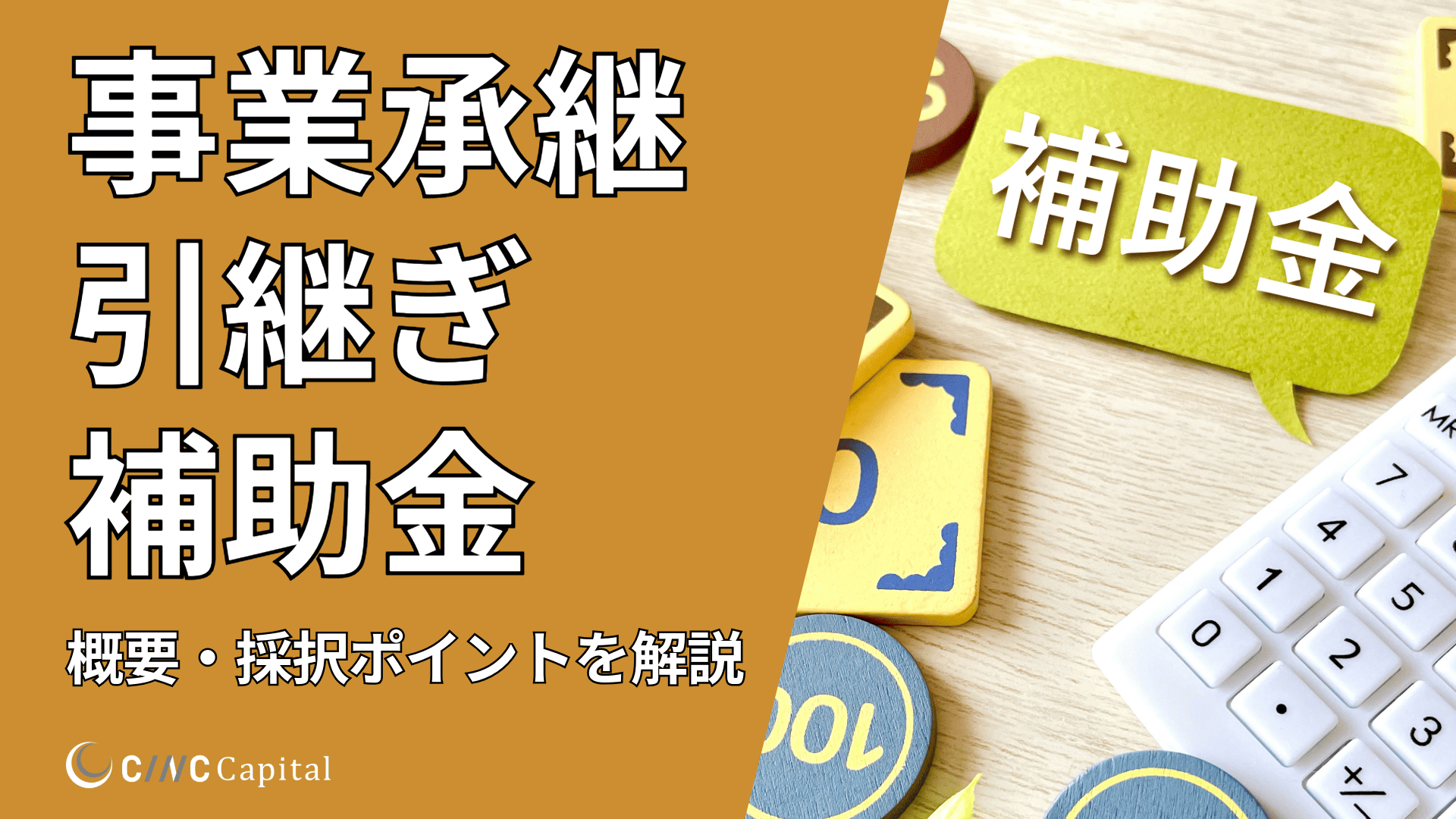
事業承継
- 公開日2025.09.30
事業承継・引継ぎ補助金とは?種類や対象者、2025年の公募概要、採択されるためのポイントを解説
事業承継やM&Aを検討しているけれど、どんな補助金が利用できるのかわからない…とお悩みではありませんか?
事業承継には多くの費用や準備が必要ですが、国の制度を上手に活用すれば、その負担を大きく減らせます。
本記事では「事業承継・引継ぎ補助金(2025年度版)」について、制度の概要から対象者、公募スケジュール、申請の流れなど詳しく解説します。
目次
事業承継・引継ぎ補助金とは?
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業や小規模事業者が親族内承継、従業員承継、あるいはM&Aを契機に行う事業活動に対して、国が費用の一部を支援する制度です。
対象となるのは、新たな事業展開、設備導入、専門家の活用、廃業整理などです。
目的は、事業承継や事業再編・統合に伴う経営資源の円滑な引継ぎと、事業の生産性向上を促すことで日本経済の活性化を図る点にあります。
【出典】事業承継・M&A補助金事務局「事業承継・引継ぎ補助金 7次公募~」
事業承継・M&A補助金との違い
2025年度から「事業承継・引継ぎ補助金」は「事業承継・M&A補助金」に改称され、新たにPMI推進枠(M&A後の経営統合支援)が加わりました。
この変更により、従来の経営革新枠(2025年以降は事業承継促進枠)、専門家活用枠、廃業・再チャレンジ枠に加えて統合後の支援が可能となり、支援の幅が大きく広がっています。
専門家活用枠の補助上限額は通常で600~800万円ですが、一定規模(100億企業要件)を満たす事業者は最大で2,000万円まで補助を受けられるようになり、支援の幅が大きく拡がっています。
これにより、M&Aや承継後の本格的な経営統合に必要な支援をより手厚く受けられるようになっています。
事業承継・引継ぎ補助金の種類
この補助金は、承継後の目的に応じて3つの枠に分かれています。
経営革新事業は新たな挑戦、専門家活用事業はM&A時の費用、廃業・再チャレンジ事業は廃業と再出発を支援するのが目的です。
本章では、それぞれの特徴と補助内容を詳しく見ていきましょう。
経営革新事業
経営革新事業は、事業承継やM&A後に設備投資や新商品開発、デジタル化などの経営革新を行う企業にとって有益な枠です。
補助率は2/3または1/2で、通常600万円まで、賃上げ要件などを満たせば800万円まで拡充されます。
さらに複数企業でグループ申請が可能となり、より広範な取り組みに対応できるようになりました。
なお、この枠では引継ぎ後に承継先企業の経営資源を活用する革新的な取り組みが要件とされています。
【出典】事業承継・M&A補助金事務局「中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 経営革新枠 8次公募のご案内」
専門家活用事業
専門家活用事業は、M&Aの際に発生するファイナンシャルアドバイザーや仲介業者、弁護士・会計士などの専門家に支払う費用を補助する枠となっています。
買手支援型・売手支援型の2種類があり、それぞれ補助率は2/3または1/2で、上限は600万円です。
しかし、一部条件を満たす場合には、補助額が最大2,000万円まで拡充されます。ただしこれは、買い手支援類型に該当し、かつ100億企業要件を満たす中小企業者等に限られるので注意してください。
また、補助対象となる専門家費用は、M&A支援機関登録制度に登録されたFAや仲介業者を利用した場合にのみ対象となります。
【出典】事業承継・M&A補助金事務局「事業承継・引継ぎ補助金 専門家活用」
廃業・再チャレンジ事業
廃業・再チャレンジ事業は、事業承継またはM&A後に旧事業の一部や全部を廃業し、廃業費用や原状回復、在庫廃棄、解体などに対する支援を行う枠です。
単独では補助率2/3・上限150万円、他枠(事業継承促進・専門家枠・PMI推進)と併用する場合には、それぞれの枠の補助上限に加算されます。
新たな取り組みに再挑戦したい事業者には、次のスタートを後押しする制度といえるでしょう。
【出典】事業承継・M&A補助金事務局「事業承継・引継ぎ補助金 廃業・再チャレンジ」
事業承継・引継ぎ補助金の対象となる事業者は?
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業基本法に該当する中小企業者や小規模事業者を対象とした制度です。
あわせて個人事業主や農業者にも申請が可能な枠が用意されています。
本章では、どのような事業者が補助金を申請できるのかについて見ていきましょう。
事業承継・引継ぎ補助金の対象者
事業承継・引継ぎ補助金は、資本金や従業員数が中小企業基本法の基準を満たす中小企業・小規模事業者が対象となります。
中には、直近が赤字である、コロナ禍で売上が減少したといった中小企業者も含まれるため、経営状況に応じて広く支援される制度として活用が可能です。
さらに、売り手・買い手いずれの立場でも、補助対象に該当する事業者であれば申請できます。
個人事業主や農業者は対象になる?
個人事業主は、青色申告を行っている中小企業者に該当すれば補助金の対象です。
特に経営革新枠(2025年以降の名称は事業承継促進枠)では、承継者・被承継者ともに青色申告者であることが要件として明記されています。
そのため、白色申告の個人事業主では申請が難しい一方、青色申告を実施していれば申請に踏み切ることが可能です。
農業者に関しては、農林水産省の「経営継承・発展等支援事業」があり、地域農業の担い手が後継者へ経営を承継する場合には最大100万円まで支援を受けられます。
【2025年度】事業承継・引継ぎ補助金の公募概要とスケジュール
2025年度は「事業承継・M&A補助金」という名称で公募が実施され、公募枠やスケジュールは変則的です。
2025年8月22日から12次公募の申請受付が開始され、同年9月19日に終了しました。
この枠ではFA費用や仲介手数料、デューデリジェンスといった専門家費用が対象で、申請後に約12か月の事業実施期間が設定されています。
公募は専門家活用枠のみとなっており、他の枠(PMI推進枠など)は今後の公募時期が未公表の状態です。
電子申請はGビズIDプライム及びjGrantsを通じてのみ受け付け可能です。
この12次公募のスケジュールと条件は公式サイトおよび公募要領に明記されています。
【出典】事業承継・M&A補助金事務局「事業承継M&A補助金11次公募〜」
事業承継・引継ぎ補助金の採択率や予算規模、申請数の動向
申請数は600〜900件、採択数は300〜500件程度で推移しており、枠別では経営革新・専門家活用枠がやや高く、廃業枠は変動が大きい傾向です。
2023年度は生産性革命推進事業の一環として約2,000億円が確保され、制度の継続性と予算の安定性が見込まれます。
予算規模自体は毎年政府予算案にて決定されるため、公募開始前の補正や改定情報は注意深く確認しなければなりません。
【出典】補助金ナビ「事業承継・引継ぎ補助金(9次公募) が採択されました。」
事業承継・引継ぎ補助金の申請の流れ
申請を行う上で準備不足や書類不備は不採択の原因となるため、スケジュールを逆算し、早めに対応を始めることが重要です。
本章では、4つのステップについて解説します。
電子申請のアカウント取得
補助金の申請には、まず「gBizIDプライム」という企業用の電子認証アカウントを取得して、電子申請システムjGrantsにログインする必要があります。
取得には印鑑証明書や申請書、メールアドレス、SMS対応の電話番号が必要で、完了まで2〜3週間程度かかる点に注意が必要です。
電子申請のみ受付可能で、締切間際では間に合わない危険性があるため、公募開始前に早めに準備しておきましょう。
確認書類の取得
経営革新や廃業・再チャレンジ枠では、認定支援機関(商工会、金融機関、税理士など)から「確認書」が発行されなければ申請できません。
支援機関は事業計画の内容をチェックし、問題がなければ所定の様式に記入・押印してくれます。
取得には相談期間が必要なため、公募開始直後に相談を始め、早めの依頼が成功の鍵になります。
必要書類の準備
確認書以外にも、申請書類として事業計画書、交付申請書、住民票や決算書、登記事項証明書、見積書など多数の資料を整える必要があります。
これらはすべてPDF等でjGrantsに添付するため、漏れやファイル形式に不備がないよう注意してください。
提出書類は公募ごとに異なる部分があるため、最新の公募要領に記載されたチェックリストをもとに準備を進めましょう。
書類の提出
必要書類が整ったら、jGrantsにログインして各フォームに必要事項を入力し、書類を添付して提出してください。
申請の締切は「○月○日 17:00まで」と厳密に定められており、当日ギリギリは回線混雑などのトラブルで遅延する可能性があります。
そのため余裕をもって提出し、”申請済み“ステータスを確認して完了としてください。
事業承継・引継ぎ補助金で採択されるためのポイント
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は50〜60%と比較的高い一方、審査に通るには戦略的な対応が必要になります。
本章では、採択に直結する3つのポイントを見ていきましょう。
自社の事業承継スタイルに適した補助金枠を正確に選ぶ
経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの3つから、自社の承継形態や取り組みに合致する枠を選ぶことで審査員に「要件適合」を納得してもらえます。
枠選択に迷う場合は、公募要領にある審査基準や制度の目的を読み込み、どの枠が自社の取り組みに最もふさわしいか判断してください。
審査落ちの多くは、要件の不一致や枠の選び間違いによるものです。
制度の趣旨と合っているかを最優先で確認しましょう。
後継者の経営ビジョンを明確に示す事業計画書を作成する
事業計画書では、後継者のビジョンと承継後に実現する内容を明確に示すことが重要です。
取り組み内容や数値目標を具体化すれば、説得力が高まります。
特に経営革新枠(2025年以降は事業承継促進枠)では審査視点に沿った構成と読みやすさが必要です。
専門家と連携しながら申請と報告の準備を効率的に進める
専門家と連携することで、申請書の精度が高まり、要件漏れや加点要素の見落としを防げます。
実績報告や会計処理も任せることで、本業に集中しながら制度を活用できるでしょう。
助言により申請内容の質も向上します。
事業承継・引継ぎ補助金の申請書の書き方と記入例
申請書は、①事業者情報、②事業内容と計画、③経費明細、④添付書類で構成されています。
最初に全体の構成を把握しておくと、記入がスムーズになり、提出ミスも防げるでしょう。
中でも「事業内容」の欄は重要で、現状の課題や補助事業の内容、新体制での効果などを具体的に書いてください。
「売上5%増」「新規市場3件」など数値目標を示すと、審査員にも伝わりやすくなります。
事業承継・引継ぎ補助金の公募で専門家のサポートを受けるメリット
補助金の申請には細かい要件や多くの書類が必要となるため、慣れていないとミスや抜け漏れが発生しやすくなります。
本章では、専門家のサポートを受ける3つのメリットについて見ていきましょう。
専門家の視点で応募要件や加点要素を漏れなく確認できる
専門家によるサポートを得ると、補助金公募で求められる要件や加点対象となる要素の漏れが防ぎやすいです。
制度の公募要領に記載された審査基準を熟知した専門家が確認することで、審査段階で読み落とされやすい政策連携(女性活躍推進、賃上げ等の加点要素)をきちんと盛り込めます。
結果として、申請漏れや読み間違いによる失点を回避し、採択率の向上につなげられるでしょう。
事業計画に専門的ノウハウを反映してブラッシュアップできる
専門家の助言によって、事業計画書に具体的なノウハウや業界知見を反映させられるでしょう。
審査で評価される革新性や実現可能性、継続性といった視点を踏まえた計画を組み立てられるため、説得力が格段に上がります。
専門家が書き方や構成まで精査してくれるため、自社だけでは気づきにくい内容の厚みを補強できるのです。
申請・報告業務を専門家に任せて経営に集中できる
補助金の申請やその後の実績報告には多くの書類作成や会計整理がともない、それが本業への負担になることが多いです。
専門家に引き継ぐことで、手続きのミスや遅延を回避しながら、経営者は経営活動に集中できます。
さらに、進捗管理や報告資料の整備も代行してもらえるため、補助金活用後の事業運営もスムーズに進行するという副次的なメリットも得られます。
事業承継・引継ぎ補助金で失敗しないための申請準備チェックリスト
本章では、公募要領の最新版チェックから必要書類の事前準備、スケジュール管理まで、申請成功に向けた重要なポイントを3ステップで説明します。
補助金の公募要領や通知事項を最新版で漏れなく確認する
補助金公募要領や更新通知は頻繁に改訂されるため、最新版を公式サイトから都度確認する必要があります。
申請枠ごとに要件やスケジュールが異なるため、公募ごとの変更点や加点要件に見落としがないようチェックしてください。
要領の細部まで読み込むことで、審査基準と制度目的に沿った申請が可能となります。
必要書類と証明資料を事前に準備して不備を防ぐ
申請には、事業計画書や決算資料、認定支援機関の確認書、住民票、登記事項証明書などが必須となります。
特に法人・個人事業主で必要書類に違いがあるため、公式のチェックリストを用いて公募ごとに整理してください。
準備に時間がかかる住民票取得などは余裕を持って進め、不備による却下リスクを事前に排除することが肝心となります。
申請から報告までのスケジュールを逆算して管理体制を整える
電子申請の締切や交付決定、事業実施期間、実績報告のタイミングなどは明確に定められており、直前の作業が業務負担になる可能性があります。
例えば、申請締切直前に確認書を依頼すると、承認が間に合わない場合も少なくありません。
公式資料には締切や報告期限も記載されており、公募前から逆算してスケジュールを設定しておけば、運営トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ|事業承継・引継ぎ補助金を正しく理解して活用しましょう
事業承継・引継ぎ補助金は、承継後の新たな挑戦やM&A、廃業・再チャレンジまで幅広く支援する制度です。
採択を目指すには、自社に適した枠を選び、後継者のビジョンを明確に示した事業計画書を作成し、専門家と連携しながら丁寧に準備を進めることが大切です。
最新の公募要領を確認し、書類やスケジュール管理も徹底することで、採択の可能性を高められます。
事業承継を成功させるために、早めの準備と戦略的な活用をしましょう。