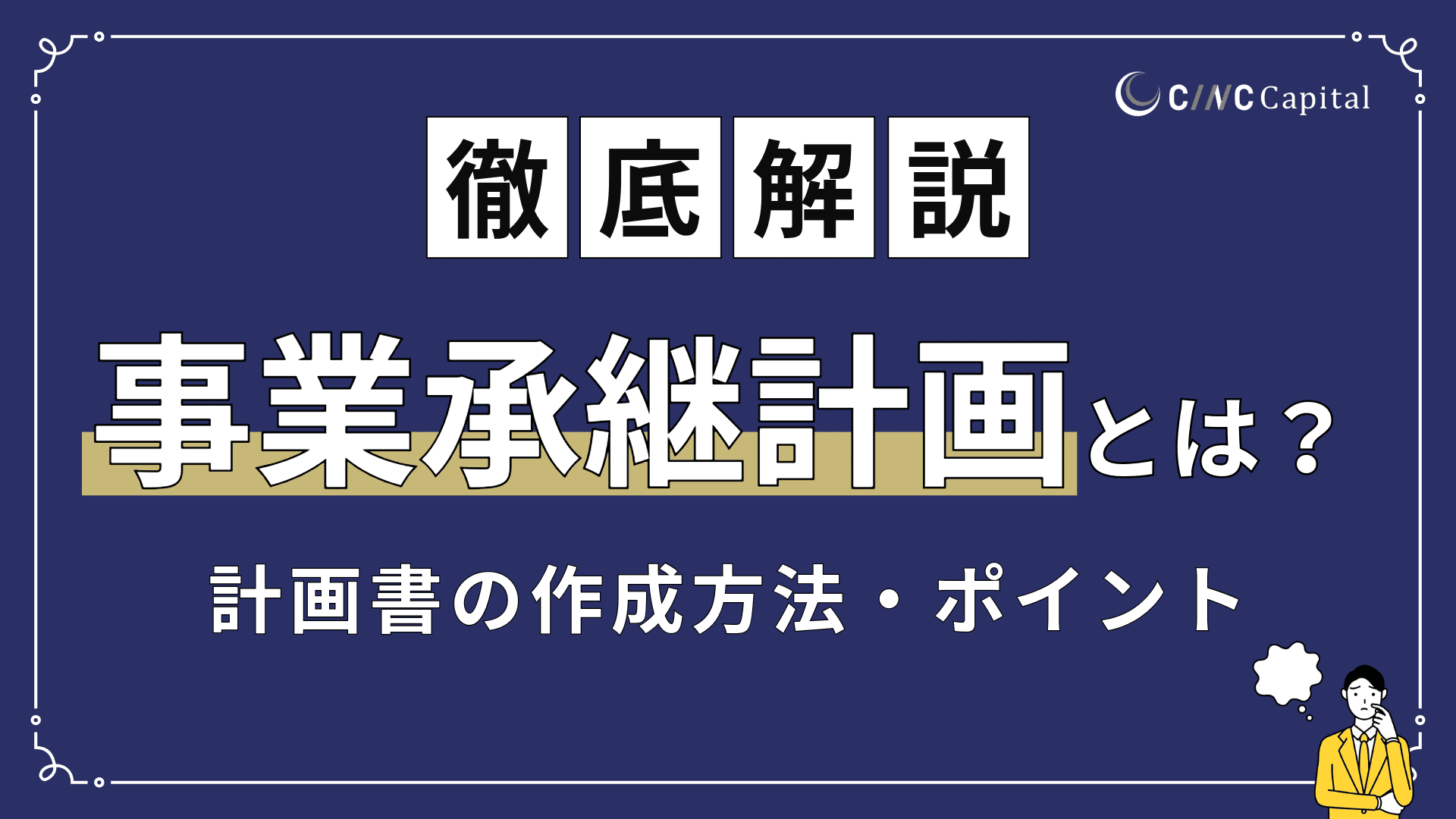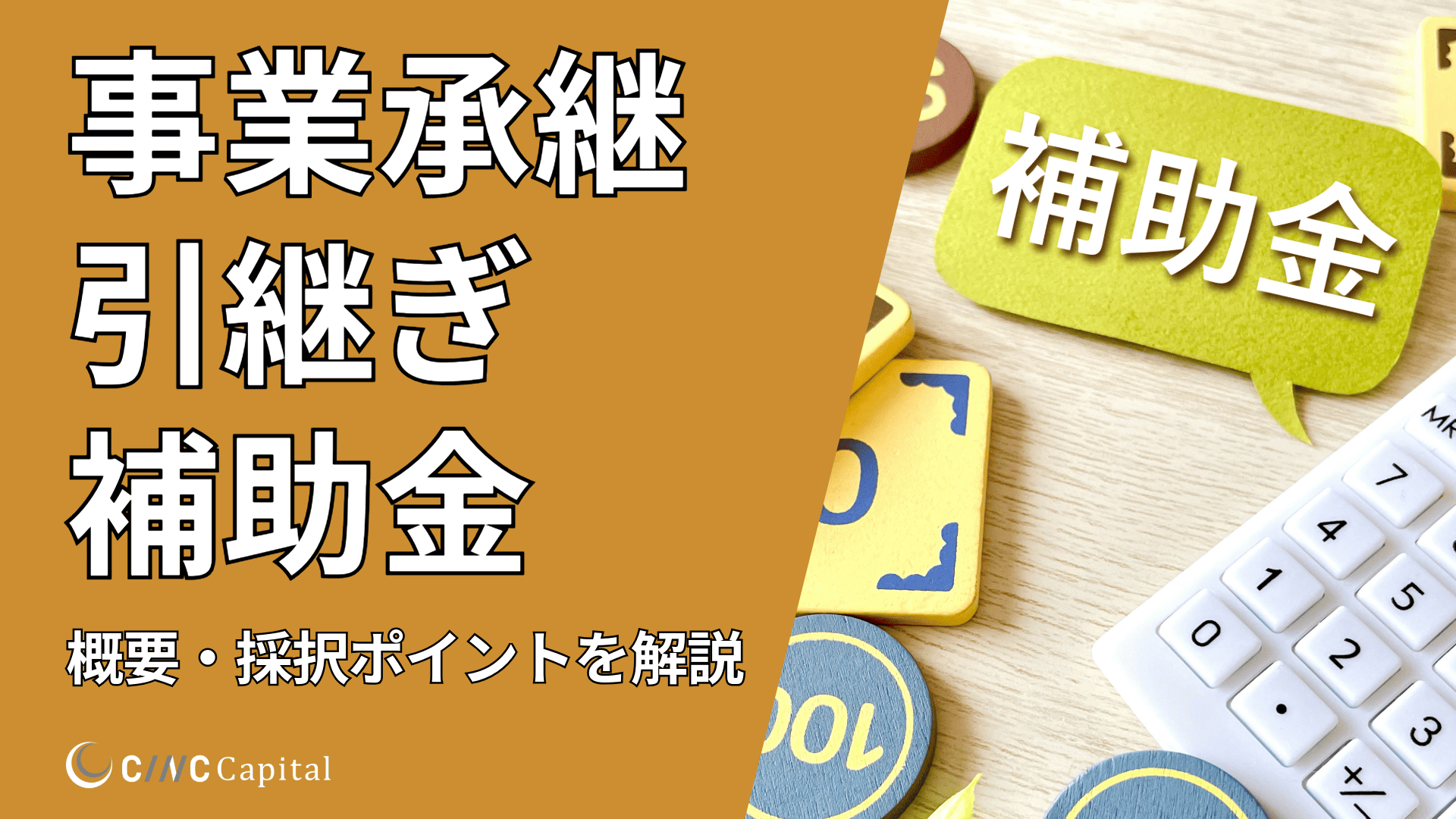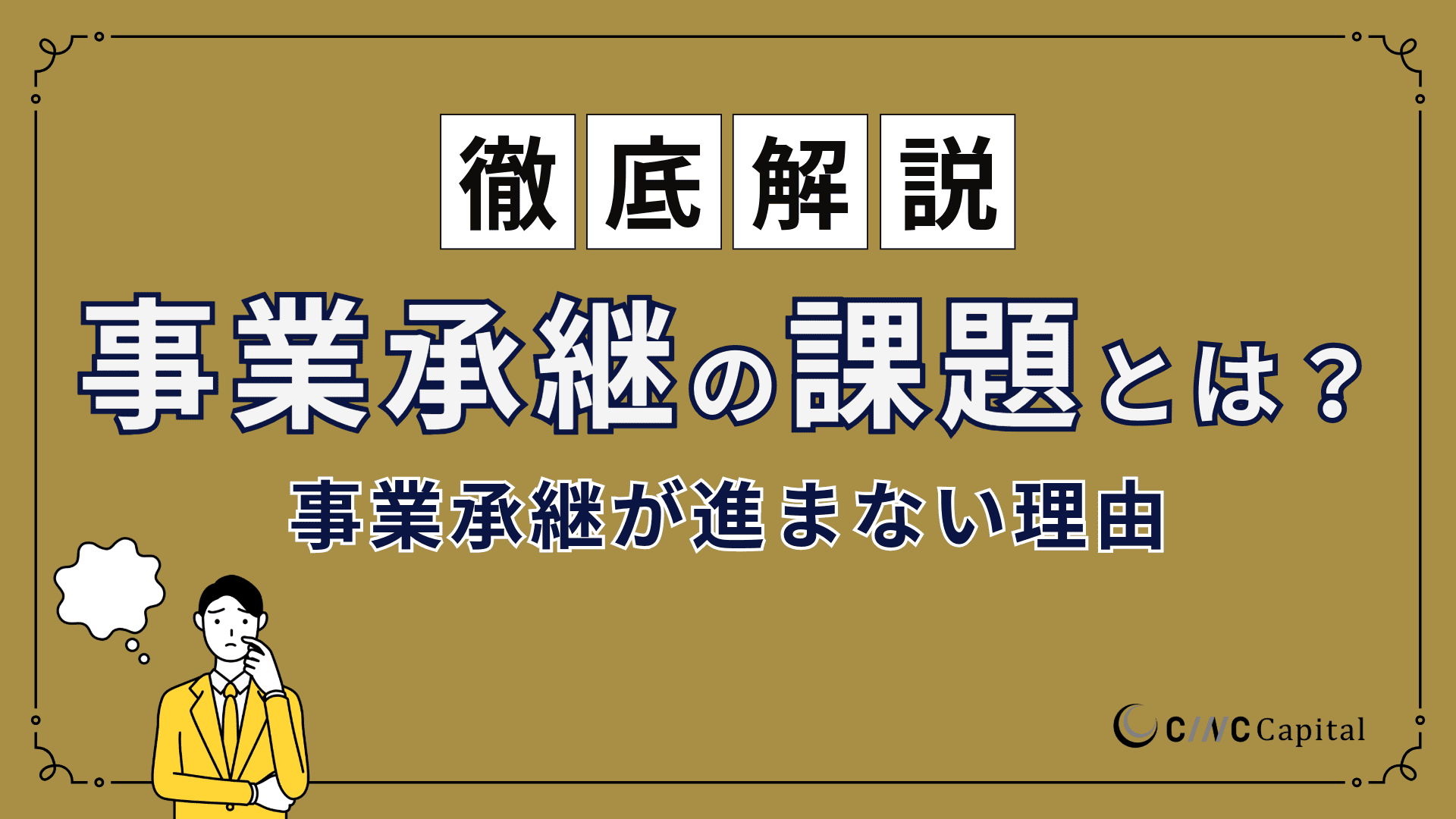CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
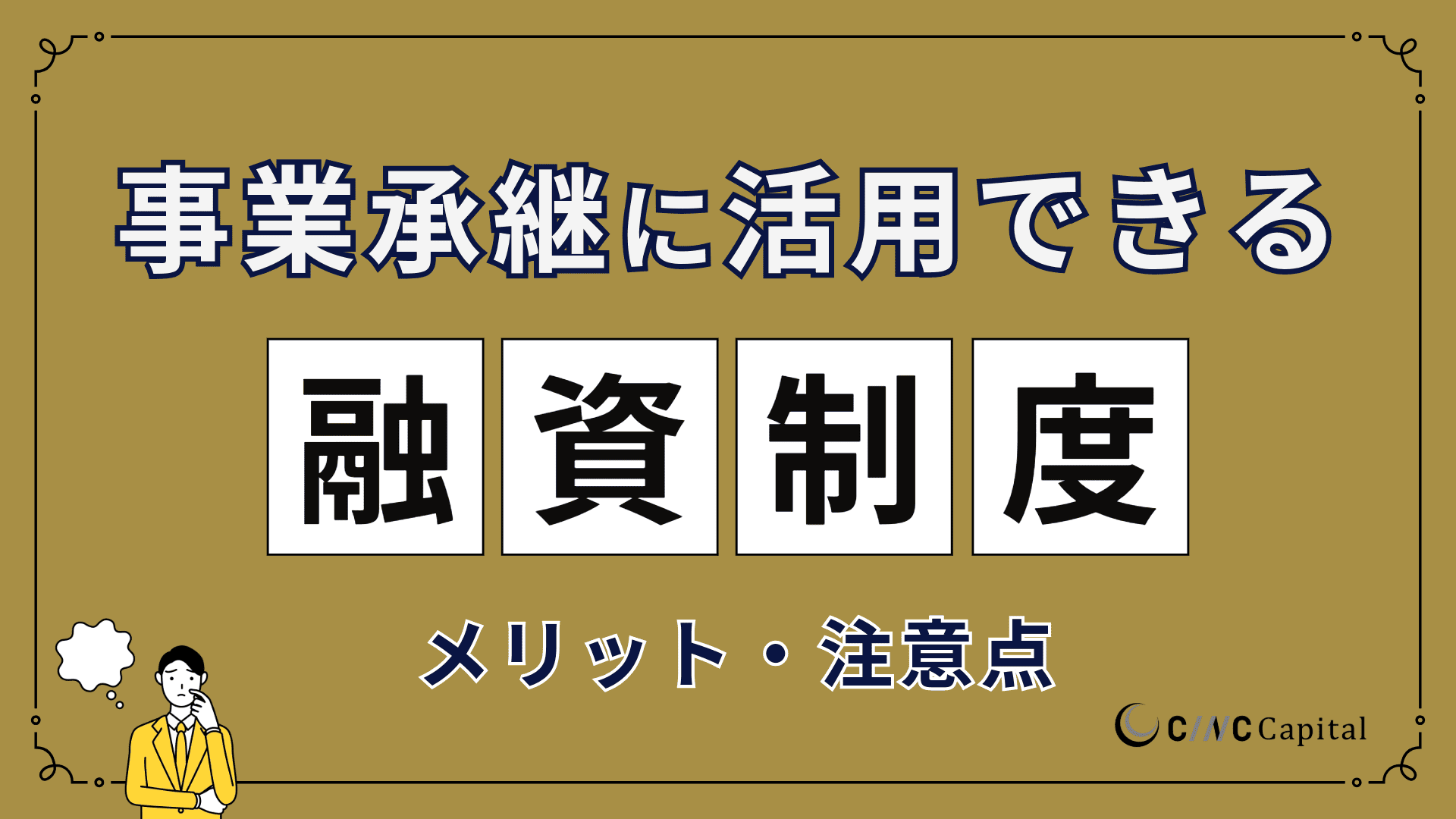
事業承継
- 公開日2025.09.29
事業承継で活用できる融資制度は?融資が必要な理由や活用するメリット、注意点を解説
事業承継には、株式の取得や相続税の支払い、設備投資など多額の資金が必要となります。
そのため、自己資金だけで賄うのが難しいと感じている経営者や後継者も少なくありません。
本記事では、事業承継における融資の必要性や活用できる融資制度、融資を活用するメリットなどを詳しく解説します。
目次
事業承継で融資が必要なのはなぜ
事業承継には多額の資金が必要となるため、融資の活用が重要です。
本章では、資産の買い取り資金と税金の負担という二つの主要な理由について説明します。
資産を買い取るための資金が必要になるため
事業承継では、後継者が会社の株式や事業用資産を取得する必要があります。
これには、多額の資金が必要となることが一般的です。
特に従業員承継や第三者へのM&Aの場合は、株式や設備、営業権などを適正な価格で買い取る形になるため、資金の準備が欠かせません。
自己資金だけでは足りないケースも多く、融資を活用することで、必要な資金を確保し、スムーズに事業を引き継ぐことが可能となります。
税金を負担する必要があるため
親族内承継では、経営権の移転に伴い、相続や贈与が発生し、相続税や贈与税の納付義務が生じます。
これらの税金は現金で支払う必要があり、後継者が不動産や非上場株式といった換金しにくい資産を多く相続する場合には、納税資金の確保が大きな課題となります。
こうした状況では、金融機関からの融資を活用することで、必要な納税資金を確保でき、資産を手放すことなく事業承継を円滑に進めることが可能となります。
事業承継で活用できる融資制度一覧
事業承継を円滑に進めるためには、適切な融資制度の活用が不可欠です。
本章では、代表的な融資制度を紹介し、それぞれの特徴と活用方法について説明します。
事業承継・集約・活性化支援資金
事業承継に伴う資金調達には、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」が有効です。
この制度は、後継者が株式や事業用資産を取得する際の資金や、事業承継後の第二創業に必要な資金を支援します。
日本政策金融公庫の事業承継支援資金では、国民生活事業で最大7,200万円、中小企業事業では最大14億4千万円まで融資が可能です(令和6年9月現在)。用途により返済期間や据置期間も柔軟に設定できます。
なお、融資条件は制度改正などにより変更される場合があるため、詳細は日本政策金融公庫にお問い合わせください。
事業承継計画を策定している中小企業者が対象です。
中小企業経営承継円滑化法に基づく融資
経営承継円滑化法に基づく融資は、事業承継時の資金調達を支援する制度です。
経営承継円滑化法には、①相続税・贈与税の納税猶予制度、②金融支援制度、③遺留分に関する民法の特例制度の3つの支援措置があります。
納税猶予については、認定中小企業者として認定を受けることで、相続税や贈与税の猶予を受けられます。
融資に関しては、②の金融支援制度により、信用保証協会の特別保証を活用することで、経営者保証の免除や保証料の軽減が可能となります。
後継者が安心して事業を引き継ぐための環境が整備されています。
事業承継支援資金
地方自治体では、地域の中小企業の事業承継を支援するために、独自の融資制度を設けています。
例えば、立川市の「事業承継支援資金」では、令和9年10月現在、融資限度額2,000万円、貸付期間7年以内(据置期間1年を含む)、利率年0.375%(市が1.625%を補助)といった条件で、事業承継に必要な運転資金や設備資金の融資を行っています。
ただし、制度の内容は変更される場合があるため、詳細は立川市の公式サイトなどで最新情報をご確認ください。
このような制度を活用することで、地域の中小企業は円滑な事業承継を実現できるでしょう。
【出典】立川市「事業承継支援資金」
地域金融機関による事業承継促進事業
東京都では、地域金融機関と連携し、事業承継に関する課題の洗い出しから資金調達までを一貫して支援する「地域金融機関による事業承継促進事業」を実施しています。
この事業では、専門家の派遣や事業承継計画の策定支援、融資相談などを通じて、中小企業の事業承継をサポートします。
地域密着型の金融機関が主体となることで、企業の実情に即した支援が可能となります。
事業承継に融資を活用するメリット
事業承継では多額の資金が必要となるため、融資の活用が重要です。
本章では、資金不足の解消、金融機関からのアドバイス、新規事業への資金確保という三つの主要なメリットについて説明します。
資金不足の際にも事業承継ができる
事業承継には、株式の取得や相続税の支払いなど、多額の資金が必要となります。
自己資金だけでこれらの費用を賄うことが難しい場合、融資を活用することで、必要な資金を確保し、円滑に事業承継を進めることができます。
例えば、日本政策金融公庫の『事業承継・集約・活性化支援資金』では、令和6年9月現在、国民生活事業で最大7,200万円、中小企業事業で最大14億4千万円の融資が可能です。
いずれも長期返済や据置期間の設定に対応しています。
ただし、制度の内容や融資条件は変更される場合があるため、詳細は日本政策金融公庫の公式サイトなどでご確認ください。
アドバイスを受けることができる
融資を申し込む際、金融機関から事業承継に関するアドバイスを受けることができます。
金融機関は、企業の資金繰りや経営状況を把握しており、適切なアドバイスを提供することが可能です。
これにより、事業承継の計画をより具体的かつ現実的なものにすることができます。
新規事業の際の融資も確保できる
事業承継を契機に、新たな設備投資や新規事業への進出を検討する企業も少なくありません。
融資を活用することで、これらの取り組みに必要な資金を確保することができます。
例えば、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」では、第二創業や新市場への進出に必要な資金も対象となっています。
事業承継で融資を活用する際の注意点
事業承継において融資を活用する際には、いくつかの注意点があります。
本章では、個人保証の必要性、利息による経営への影響、審査の通過難易度、融資実行までの期間について説明します。
個人保証が必要な場合がある
事業承継に伴う融資では、経営者個人の保証が求められることがあります。
特に、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」では、一定の要件に該当する場合に個人保証が必要となります。
個人保証があると、万が一返済が滞った際に、経営者個人の資産が差し押さえられるリスクがあります。
そのため、融資を検討する際には、個人保証の有無や条件を事前に確認し、リスクを理解した上で判断することが重要です。
利息が経営を圧迫するおそれがある
融資を受ける際には、利息の支払いが必要となります。
利息の負担が大きい場合、返済が経営を圧迫する可能性があります。
特に、事業承継後の収益が安定していない段階で高額な利息を支払うことは、資金繰りを困難にする要因となり得ます。
そのため、融資を検討する際には、利率や返済期間を含めた返済計画を慎重に立て、無理のない範囲での借入を心がけることが重要です。
審査に通らないこともある
融資を受けるためには、金融機関の審査を通過する必要があります。
審査では、事業の信用や返済能力などが評価されます。
場合によっては、現地調査や追加質問が行われることもあります。
審査に通らない場合、融資を受けることができません。
そのため、事業計画や財務状況を明確にし、審査に備えることが重要です。
融資を受けるまでには期間がかかる
融資を受けるまでには、事業計画書や財務資料などの書類を準備し、金融機関による審査や契約手続きといった複数のステップを踏む必要があります。
制度や金融機関により異なりますが、これらの手続きには一定の時間を要し、一般的には融資の申し込みから資金実行までに1〜2ヶ月程度かかるとされています。
スムーズに事業承継を進めるためには、承継のタイミングに間に合うよう、早期に金融機関と相談を始め、融資準備を進めておくことが重要です。
まとめ
事業承継には多額の資金が必要となり、融資の活用が重要です。
適切な融資制度を利用することで、資金不足の解消や専門的なアドバイスの取得、新規事業への資金確保といった多くのメリットが得られます。
一方で、個人保証の有無、利息の負担、審査の通過難易度、融資実行までの期間など、注意点も存在します。
これらを踏まえ、適切な融資制度を選択して、円滑な事業承継の実現に繋げましょう。