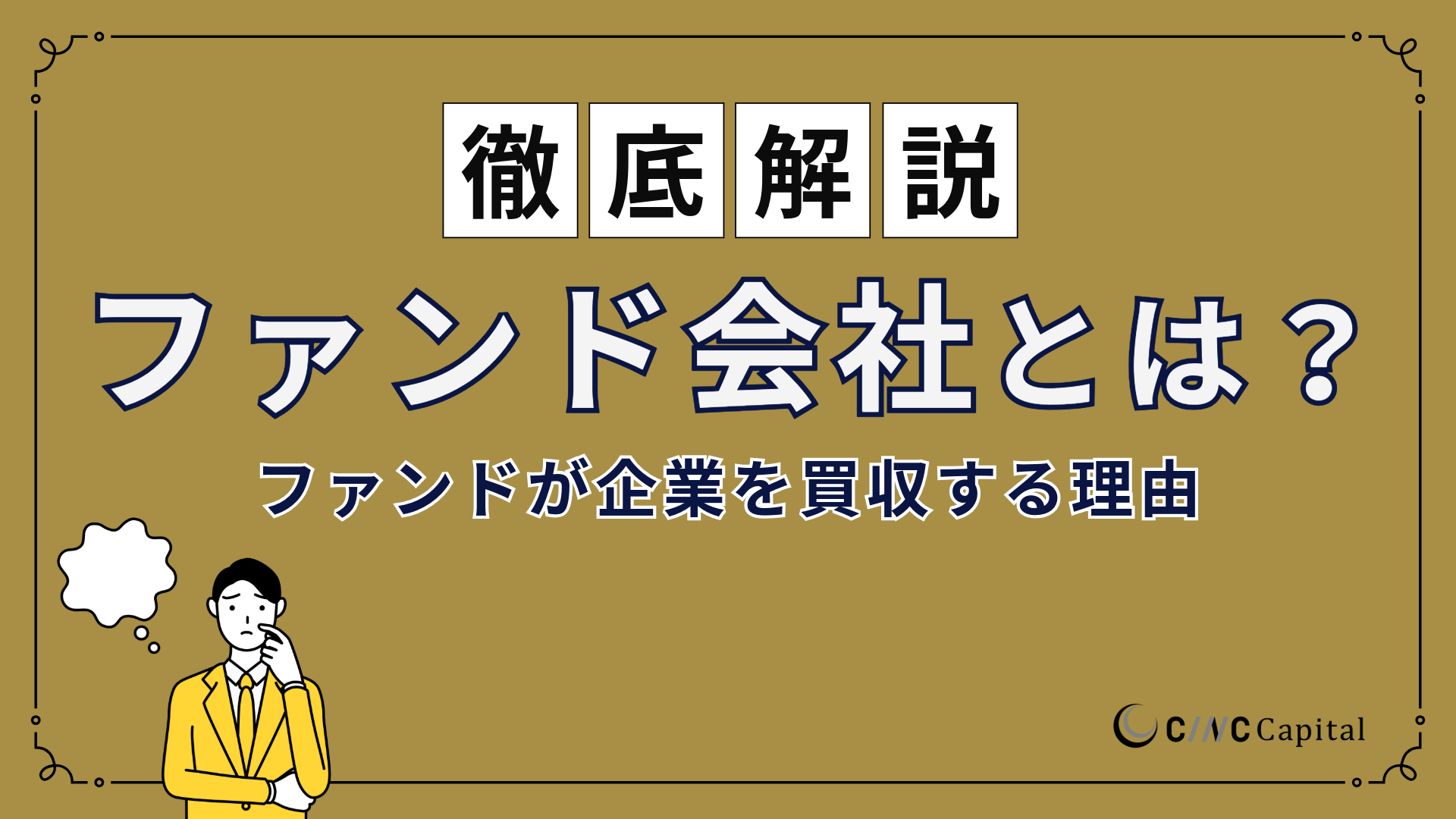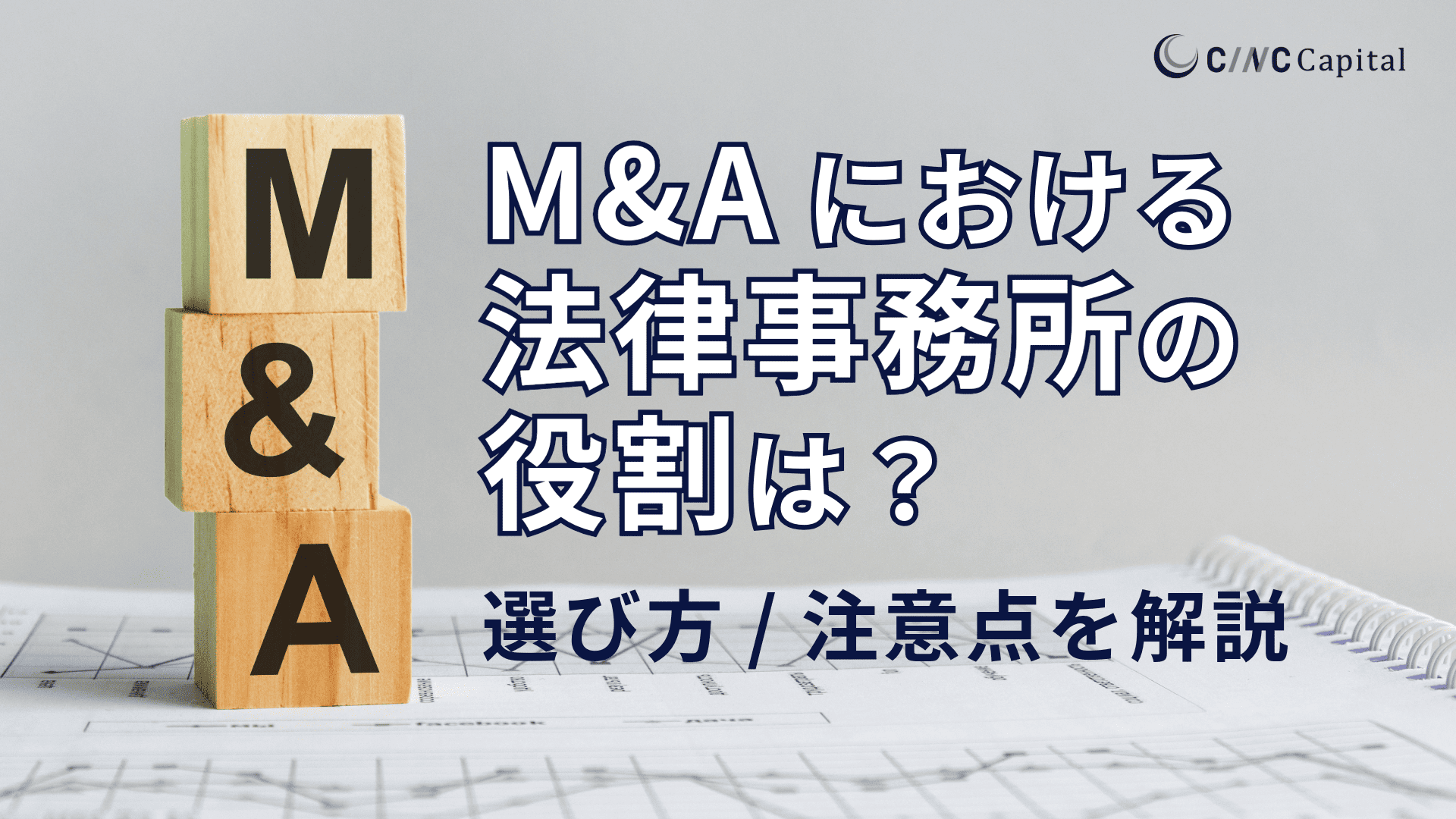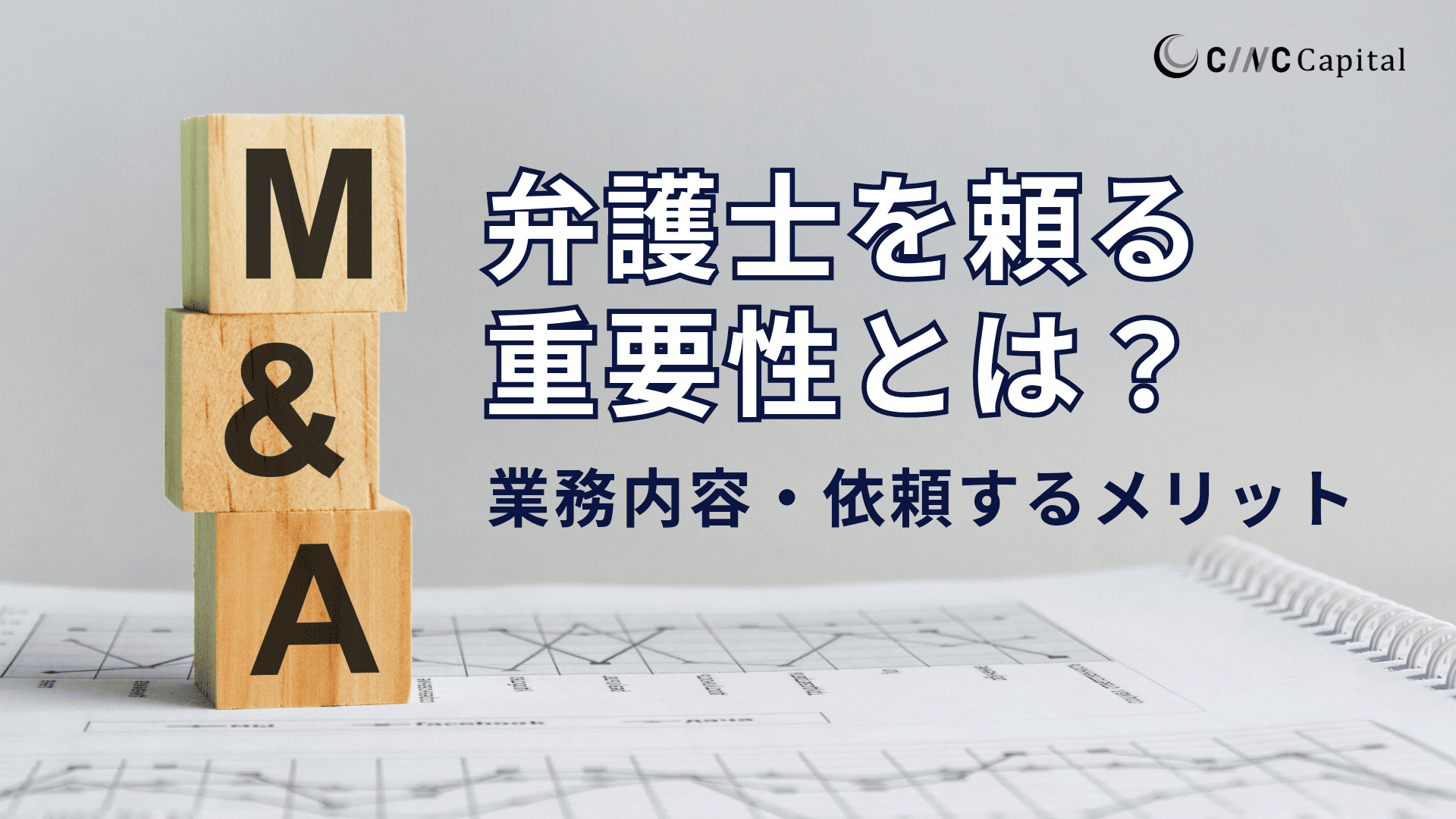CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
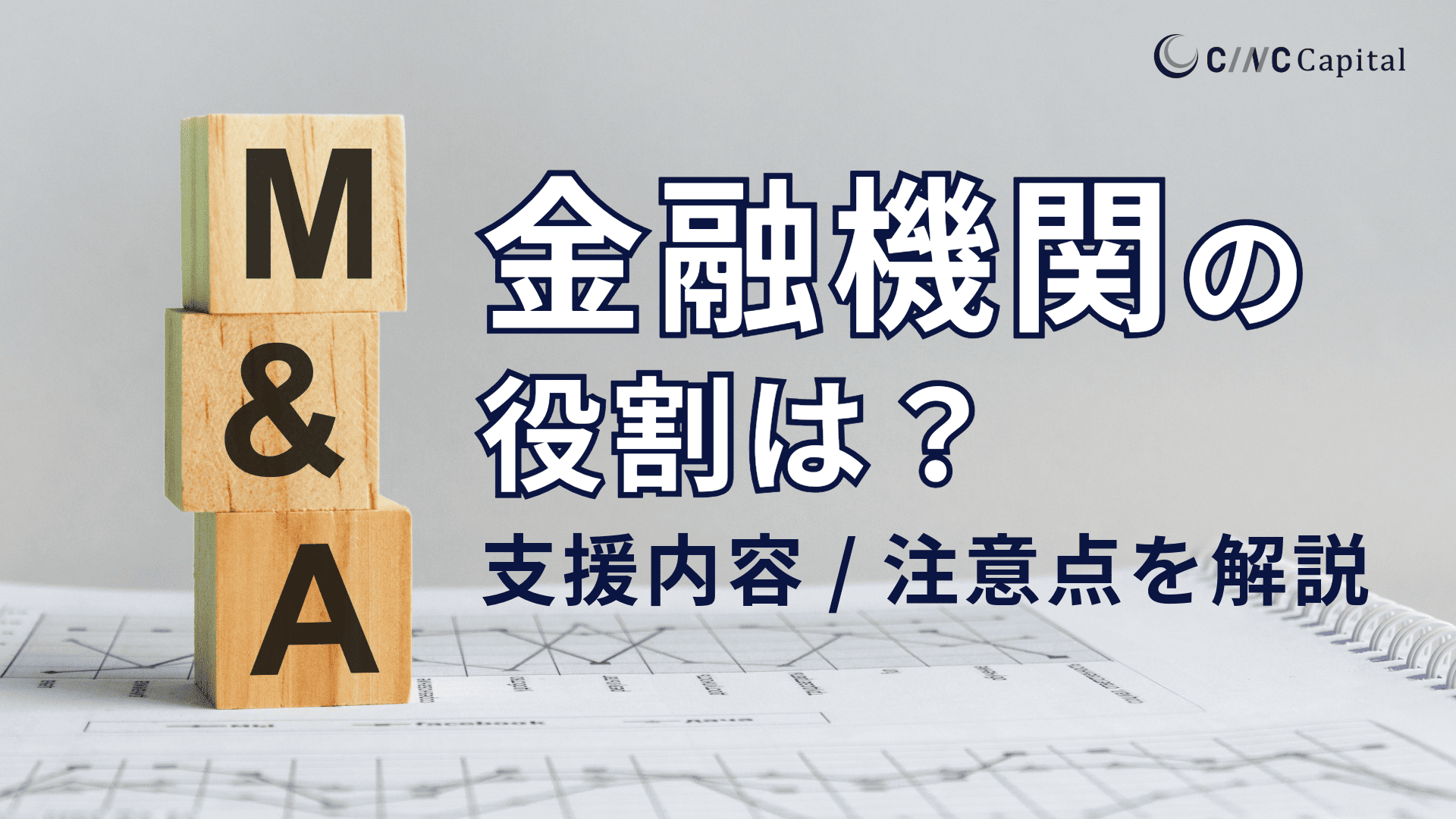
支援 / 金融機関
- 最終更新日2025.06.26
M&Aにおける金融機関の役割は?支援内容や関係する法律、金融機関経由のM&Aの注意点を解説
近年、中小企業の後継者不足や成長戦略の一環として注目されるM&A(企業の合併・買収)。そのプロセスにおいて重要なパートナーとなるのが「金融機関」です。しかし、銀行や信用金庫などの金融機関がどのように関与し、どういった役割を果たしているのか、具体的には知らないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、M&Aにおける金融機関の支援内容や関係する法律、金融機関経由でM&Aを行う際の注意点などを解説します。
目次
M&Aにおける金融機関の役割
M&A(企業の合併・買収)は、企業の成長戦略や事業承継の手段として広く活用されています。ここでは、M&Aにおいて金融機関が果たす代表的な役割を紹介します。
買収資金の融資を提供する
M&Aの実行には多額の資金が必要となるケースが一般的です。特に買い手企業にとっては買収資金の確保が最大の課題となります。金融機関は、コーポレート・ファイナンスやプロジェクト・ファイナンスなどの手法を通じて、買収資金の融資を提供可能です。
メインバンクであれば、企業の財務状況や将来性を踏まえた上で、柔軟な資金調達方法を提案してくれることもあります。また、買収後の資金返済可能性を判断材料にして融資の可否が決まるため、金融機関の評価がM&Aの成否に影響を与えることもあります。
M&Aアドバイザリー業務を提供する
金融機関の中には、M&Aに関する専門部署や担当者を設けており、アドバイザリー業務を提供しているところもあります。これは、買い手もしくは売り手のいずれか一方と契約を結び、適切な条件でM&Aを進められるようサポートする業務です。
取引先企業との関係を深く持つ銀行だからこそ、実情に即した現実的な提案が得られると期待できます。加えて、資金調達に関する専門的なアドバイスも受けられます。
実務においては、金融機関とM&A仲介会社が連携して支援することも少なくありません。金融機関が資金面のサポートを担い、M&A仲介会社が専門的なアドバイスや交渉サポートを提供するといった役割分担が効果的なケースもあります。
売り手企業の債権者として関与する
M&Aにおいて、売り手企業または買い手企業のいずれかが金融機関からの融資を受けている場合、金融機関は債権者として取引に関与することになります。この場合、M&Aによって返済能力や事業継続性が変化するため、金融機関はその影響を精査し、場合によっては条件変更や債権回収の手段を検討する必要があります。
また、金融機関が債権者として関わる場合、債権者としての立場からM&Aの実行に同意しないケースもあります。金融機関との事前調整は極めて重要です。
買収後の統合プロセス(PMI)を支援する
M&Aの成功は、買収後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)にかかっているといっても過言ではありません。金融機関は、PMIにおいても資金面や財務管理の支援を行うことがあります。
特に、財務状況の可視化や運転資金の確保、経営統合に伴う資本再構築などの面で、経験豊富な金融機関の支援は大きな力になるでしょう。また、M&Aによって変化する内部統制や決算処理などに対しても、銀行系のコンサルティング部門などがサポートを行うケースがあります。
ただし、金融機関からの支援はあくまでも財務や資金面にとどまるため、実際の経営統合に関する部分はM&Aの専門家にサポートを依頼することが求められます。
リスク管理とコンプライアンスのサポートを行う
M&Aには、法的リスクや財務リスクがつきものです。金融機関は、企業の信用調査やデューデリジェンスを通じて、リスクの洗い出しや分析を行えます。
また、金融機関は法令遵守(コンプライアンス)やマネーロンダリング防止などの観点からも、取引の適正性を確認する役割を担います。M&Aを安心して進める上で、こうしたリスク管理機能が役立つでしょう。
金融機関を通じたM&Aに関係に影響する法律
M&Aを進める際、金融機関を通じた取引では多くの法律が関係します。ここでは、M&Aに関わる主な法律とその概要について解説します。
銀行法
銀行法は、銀行業を営む企業の設立や業務運営、監督に関する基本的なルールを定めた法律です。M&Aにおいては、銀行が他社の株式を取得したり、合併・買収などを行ったりする場合、一定の届出や許可が必要になります。特に持株会社化や他業種との統合などでは、金融の健全性確保の観点から厳格な審査が行われます。
金融商品取引法
金融商品取引法は、有価証券の取引の公正性と透明性を確保するために設けられた法律です。M&Aでは、株式の市場買い付けや公開買い付け(TOB)に関する規制が重要となります。特に上場企業を対象としたM&Aでは、投資家保護の観点から情報開示や手続きの適正性が求められます。
独占禁止法
独占禁止法は、公正な市場競争を維持することを目的とする法律です。M&Aによって特定市場での競争が実質的に制限される場合、公正取引委員会への事前届出や審査が必要となり、場合によっては取引自体が認められないこともあります。こうした規制は市場の公正性を守る上で重要な役割を果たしています。
外為法(外国為替及び外国貿易法)
外為法は、日本と外国との間で行われる資本取引や貿易取引を規制する法律です。外国資本が日本企業を買収するようなクロスボーダーM&Aでは、事前の届出や審査が必要となる場合があります。国の安全保障や重要産業の保護を目的として、外資によるM&Aに対して厳しい規制が設けられることがあります。
会社法
会社法は、会社の設立から運営、統治、組織再編に至るまで、企業活動の基本ルールを定めた法律です。M&Aに関しては、合併や会社分割、株式交換などの手続きや株主の権利保護に関する規定が含まれており、法的手続きを適切に進める上で基礎となる法律です。
労働契約承継法
労働契約承継法は、会社分割や事業譲渡において、労働者の雇用関係を適切に引き継ぐための特例を定めた法律です。M&Aにより雇用先が変更される場合、労働者の雇用条件が不当に変更されたり不利益を受けたりすることがないよう、労働契約の承継方法にルールが設けられています。労働者の保護と、円滑な事業承継を両立させるための重要な制度です。
金融機関経由のM&Aが有利なケースと不利なケース
M&Aの実行にあたっては、どのようなルートで相手企業と出会い、交渉を進めていくかが成功の鍵を握ります。ここでは、金融機関経由でのM&Aが有利に働くケースと、不利になり得るケースを具体的に紹介します。
有利なケース
買収資金の融資が必要で、金融機関の審査や支援が前提となる場合、金融機関経由のM&Aは非常に有効です。資金調達と同時にM&A支援を受けられるため、資金面と実務面の両方でスムーズに取引を進められます。
また、地域密着型の金融機関なら、地元企業同士のマッチングに強みを持つ場合もあります。地元の経済や企業事情に精通していることから、互いの企業文化や経営スタイルを理解した上で適切な相手を紹介してくれる点が魅力です。
さらに、金融機関が関係先企業の情報を豊富に持っており、相手選定や交渉が有利になる場合もあります。長年の取引を通じて蓄積された財務情報や経営者の人柄に関する知見など、表に出ない情報を活かしたアドバイスや支援が期待できます。
不利なケース
スピード感や柔軟性が求められるM&Aで、金融機関の意思決定が遅い場合、タイミングを逃してしまうリスクがあります。慎重な審査や社内手続きが多く、即断即決が必要な場面では不向きといえるでしょう。例えば、買収案件が急募されている場面において、金融機関の審査が長引いてしまうと、タイムリーな意思決定ができなくなる可能性があります。
また、金融機関に紹介された相手が自社の戦略と合致しない場合、無理に取引を進めることで期待したシナジーが得られず、M&A後の統合に課題を抱えることがあります。紹介先が限られている場合、候補の選択肢が狭まることもデメリットです。
加えて、独立性のあるアドバイザーや専門家による中立的な判断が求められる場合には、金融機関の立場が中立でないと判断されることがあります。取引先との関係性を重視するあまり、真に自社の利益にかなう提案が得られない可能性も考慮する必要があります。
金融機関を介したM&Aで注意すべき点
金融機関を通じたM&Aは、信頼性の高さや資金面での支援が期待できる反面、特有のリスクや注意点も存在します。ここでは、金融機関経由のM&Aを検討する際に押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。
金融機関が取引先両方に関与している場合の利益相反リスクに注意する
金融機関が譲渡側と譲受側の両方に関わっている場合、利益相反が生じるリスクがあります。例えば、融資先企業の経営が悪化した場合、金融機関としては回収の見込みを高めるために、信用力のある企業へ早期に売却を進めたいと考えることがあります。
このような場面では、売却側に対して買収側の条件を優先するよう圧力がかかる可能性があり、結果として譲渡側が不利な条件で合意するケースも考えられるでしょう。
M&Aアドバイザリー業務は、利益相反管理の対象となっています。しかし、トラブルを防ぐためには事前にどのような立場で支援しているのかを確認し、情報の偏りがないかを慎重に見定める必要あります。
紹介案件が金融機関の都合に偏っていないか見極める
金融機関から紹介されるM&A案件は、必ずしも自社の戦略や希望条件に適合するとは限りません。特に、金融機関が取引関係にある企業の救済や利益確保を目的としている場合、その紹介は金融機関自身の都合に基づくものになりがちです。
例えば、融資先の再建を目的とした案件や、営業エリア内のマッチングを優先した案件では、自社にとって真にメリットのある提携とはいえないこともあります。紹介案件については、内容や背景を丁寧に精査し、安易に受け入れない姿勢が重要です。
金融機関の支援範囲を事前に明確にしておく
M&Aにおいて、金融機関がどこまで支援してくれるのかを明確にしておくことも大切です。例えば、単なる資金面の支援だけでなく、相手先の紹介、交渉支援、契約書の作成支援まで対応してくれるのかどうかは、金融機関ごとに異なります。
金融機関の種類によってM&Aの関与の仕方も変わってくる可能性があります。例えば、地方銀行は地域企業とのつながりを活かした案件紹介に強みがある一方、メガバンクは大規模・複雑なM&Aに対応できる専門性やグローバルネットワークを持っているケースがあります。
また、アドバイザリー契約を結ぶ場合には、着手金や成功報酬、継続的な月額報酬などの費用が発生することもあります。そのため、契約内容を事前にしっかり確認しておくことがトラブル防止に有効です。費用対効果のバランスも検討しておきましょう。
まとめ|金融機関の強みとリスクを理解し、納得感のある意思決定を
金融機関を介したM&Aは、資金調達の面で有利に働く場合や、地域に根ざしたマッチングが期待できるなどのメリットがあります。しかし一方で、スピード感や柔軟性に欠ける、また利益相反のリスクが存在するなど、慎重に見極めるべきポイントも少なくありません。
金融機関の強みとリスクを正しく理解した上で、自社にとってもっとも望ましい形のM&Aを選択することが求められます。必要に応じて、金融機関とは別に独立した仲介会社に相談して、アドバイザーの意見も取り入れることで、より中立的で納得感のある意思決定につなげられるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。