CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
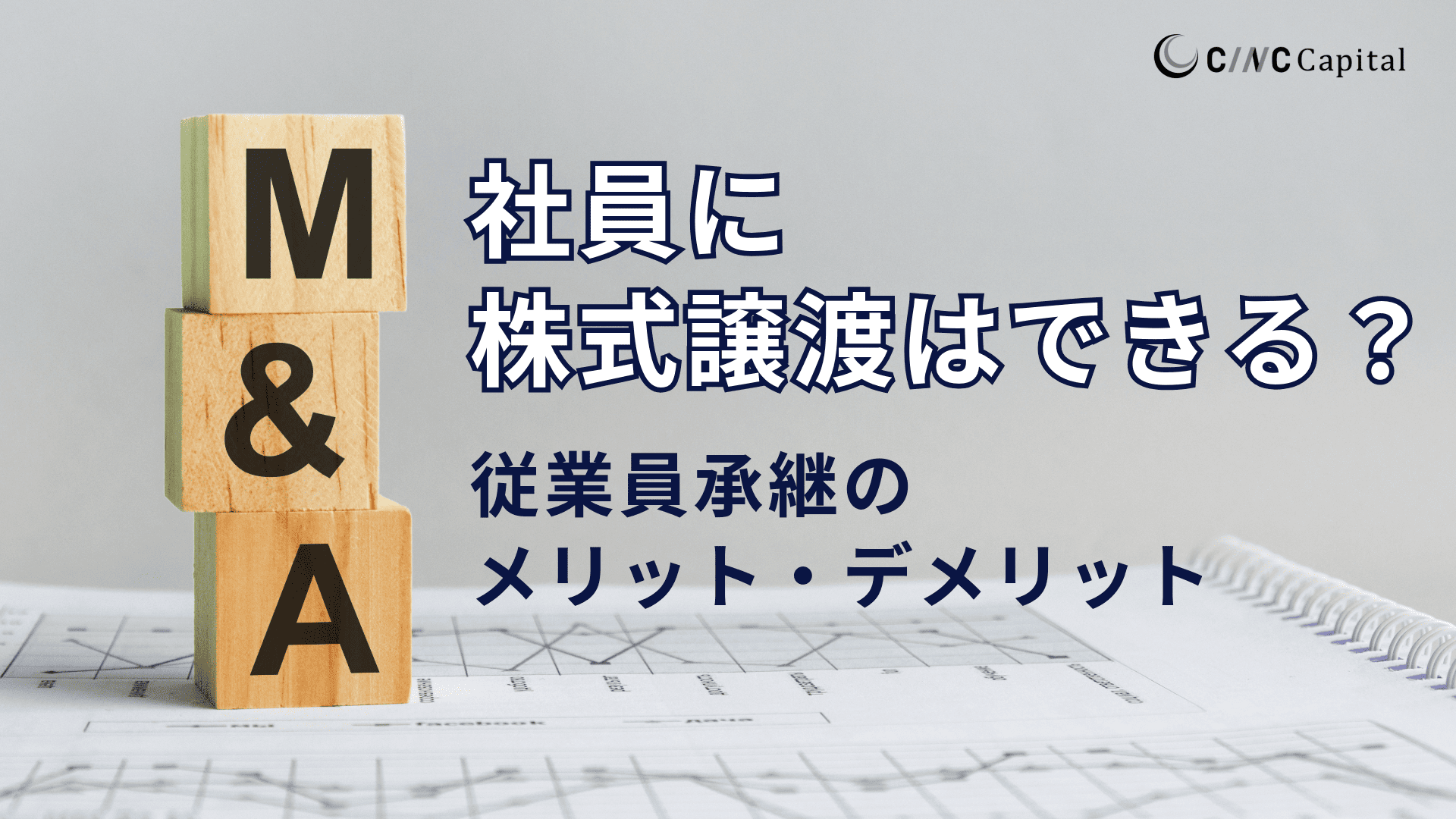
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
社員へ株式譲渡はできる?従業員承継のメリットやデメリットについて解説
会社の将来を考えるうえで、「信頼できる社員に株式を譲渡したい」と考える経営者は少なくありません。近年では、親族以外の承継方法として、社員への株式譲渡を選ぶケースも見られます。では、社員への株式譲渡は実際に可能なのでしょうか。
この記事では、社員への株式譲渡の可否や手続きの基本に加え、従業員承継のメリット・デメリット、実施時の注意点まで詳しく解説していきます。
目次
社員に株式譲渡することはできる?
株式譲渡は、現経営者や既存株主が保有している株式を他者に移転することで、会社の経営権を引き継ぐ手段の一つです。中小企業のM&Aにおいてもよく用いられる方法となります。特に株式を100%譲渡するケースでは、新たな株主に経営を一任し、事業を継続させることができます。
株式譲渡は親族や他企業だけでなく、社員(従業員)に対して行うことも可能です。信頼できる社員に事業を託したいという経営者の思いから、従業員承継の手段として株式を譲渡するケースが実際に行われています。
例えば、社員に全株式を譲渡すれば、その社員が経営権を全面的に引き継ぐことになります。一方、一部の株式を譲渡した場合には、社員も経営に関与する立場にはなるものの、意思決定の主導権は譲渡者側に残る可能性が高いでしょう。社員が会社に対してどの程度の影響力を持つかは、譲渡される株式の割合に応じて決定されます。
社員への株式譲渡は法的にも可能であり、実際に活用されることもある方法です。ただし、譲渡後の関係性や責任の所在、社員側の経営意識の変化なども含め、事前に十分な検討と準備が求められます。また、非上場企業では譲渡制限が設けられていることも多く、そういったケースでは取締役会などの承認を要する点に注意が必要です。
社員への株式譲渡のメリット
社員に株式を譲渡することは、事業継続や社員の意識改革など、経営面で多くのメリットをもたらします。ここでは、社員への株式譲渡によって得られる主なメリットについて解説します。
事業承継を実現できる
近年、多くの中小企業が後継者問題に直面しています。親族に適任者がいない、外部からの経営者候補が見つからないといったケースも少なくありません。そんな中、長年会社に貢献してきた社員に株式を譲渡することで、信頼のおける人物に経営を引き継ぐことが可能となります。
社員への株式譲渡によって事業承継を実現すれば廃業を避けられるだけでなく、社内に蓄積されたノウハウや文化を維持しながら会社の存続が図れます。
社員の雇用を維持できる
社員に株式を譲渡して経営を任せる形での事業承継は、既存の従業員の雇用維持にもつながります。外部の企業への売却とは異なり、経営体制の変化によるリストラや労働環境の大幅な変更といったリスクが抑えられるためです。
会社に対する理解が深く、社員同士の関係性を把握している人物が後継者となることで、社内の安定が保たれやすくなります。結果として、社員の不安を最小限に抑え、円滑な事業継続を実現することが可能です。
株式譲渡した社員のモチベーション向上につながる
株式を保有することで、社員の会社に対する意識は大きく変わります。配当金を受け取れる立場になることで、自らの業績が会社の成長に直結するという実感が生まれ、日々の業務に対する責任感や熱意が向上するでしょう。
また、給与や賞与の増額が難しい状況でも、株式からの配当という形で社員へ還元できれば、報酬に対する満足度を維持する手段としても有効です。社員のエンゲージメント強化に役立つことが期待できます。
社員への株式譲渡のデメリット
社員への株式譲渡には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、社員へ株式譲渡するときに起こり得る代表的なデメリットについて解説します。
後継者選びが難しい
社員への株式譲渡は、対象の社員に経営を任せることを前提とした手法です。しかし、優秀な社員であっても経営者としての資質があるとは限りません。経営者には、事業全体を俯瞰する視点や、対外的な交渉力、人材マネジメント力、財務の知識など、広範なスキルや専門知識が求められます。こうしたスキルを備えた社員が社内に存在しない場合、後継者選びは難航するでしょう。
また、適切な後継者が見つからないまま譲渡を進めてしまうと、会社の将来に悪影響を与えるおそれもあります。そのため、社員への株式譲渡を検討する際には、経営能力を冷静に見極める必要があります。
シナジー効果が得られない
M&Aによって外部企業と提携する場合には、互いの事業資源や強みを生かした「シナジー効果」が期待できます。しかし、社員への株式譲渡では、対象が自社の内部にいるため、そうしたシナジー効果は基本的に生まれません。
例えば、技術力の補完や販売網の拡大といった、他社との連携によって得られる付加価値は見込めないため、企業の成長加速にはつながりにくい可能性があります。会社のさらなる飛躍を狙う場合には、他社とのM&Aも視野に入れる必要があるでしょう。
社員への株式譲渡の方法
ここでは、社員への株式譲渡の具体的な方法を3つ紹介します。それぞれの違いを確かめておきましょう。
有償譲渡
有償譲渡とは、社員が株式を購入することで経営権を取得する方法です。代表的な形式に、役員が取得する「MBO(マネジメント・バイアウト)」や、社員が取得する「EBO(エンプロイー・バイアウト)」があります。現経営者が保有する株式を、後継者として選んだ社員に対価を得て売却する形です。
メリットは、経営者が譲渡益を得られる点と、会社の支配権が確実に移転する点です。株式の売買契約を結ぶことで手続きも比較的簡便に進められます。また、譲渡益は老後の生活資金や新たな事業への資金として活用できます。
デメリットは、後継者となる社員に大きな経済的負担がかかることです。会社の株式価値が高ければ、数千万円単位の資金が必要になることもあり、資金調達のために外部の支援(ファンドやベンチャーキャピタルなど)を受けるケースもあります。
無償譲渡
無償譲渡は、現経営者が株式を社員に無償で譲る方法で、主に「贈与」や「遺贈」が該当します。贈与は生前に行う方法であり、遺贈は遺言によって死後に行われる方法です。いずれも、株式を金銭のやり取りなく移転するため、社員側の負担を抑えられます。
メリットは、社員の経済的負担を軽減できる点です。資金力に関係なく優秀な人材を後継者として選び、事業を託せるのは大きな魅力といえるでしょう。
デメリットは、贈与税や相続税の負担が発生することです。特に高額な株式の贈与では、数千万円単位の贈与税が発生する可能性があり、無償譲渡であっても受け取る社員には納税資金が求められます。また、遺贈の場合には相続人間で遺留分の争いが起きるリスクもあるため、生前に関係者の理解を得ておきましょう。
従業員持株会への譲渡
従業員持株会を活用する方法も、社員に対する株式譲渡の手段の一つです。従業員持株会とは、複数の社員が共同で会社の株式を保有する制度です。設立には一定の準備と社員の合意形成が必要ですが、制度を整えることで長期的なエンゲージメント向上につながる可能性があります。
メリットは、税務上の評価額(配当還元価格)で株式を譲渡できる可能性があるため、譲渡価格を抑えつつ、現経営者は現金を得られる点です。また、株式を持株会に譲渡することで、相続税対策として資産の圧縮効果が期待できます。譲渡する株式の種類や割合を調整することで、支配権を維持したまま社員に経営への参画意識を持たせることも可能です。
デメリットは、個々の社員に直接株式が渡るわけではないため、後継者として特定の人物に経営権を集中させたい場合には適さない可能性があります。支配権の明確化が必要な場合は、他の方法と併用するなどの工夫が求められます。
社員への株式譲渡の流れ
社員に株式を譲渡する際には、会社法に基づく正式な手続きを踏む必要があります。ここでは、株式譲渡の一連の流れを、順を追ってわかりやすく解説します。
株式譲渡の目的を決める
最初に、株式譲渡の目的を明確化しましょう。例えば、事業承継を見据えた後継者育成、社員のモチベーション向上、業績連動のインセンティブなど、目的によって譲渡する株式数やタイミングも変わってきます。目的があいまいなまま進めると、トラブルや後悔を招く可能性があるため、慎重な検討が必要です。
譲渡対象者を選定する
株式譲渡の対象となる社員を選定します。経営理念への共感度や、将来的に経営に参画する意思があるかといった視点が重要です。譲渡対象者が複数いる場合は、株式比率のバランスや社内の公平性にも配慮しましょう。場合によっては、弁護士や税理士など専門家に相談することも有効です。
取締役会や株主総会で承認を受ける
譲渡制限が付された株式であれば、譲渡前に取締役会または株主総会での承認が必要です。これは、会社の方針にそぐわない人物による株式取得を防ぐための制度です。承認が必要な場合、譲渡承認請求書を作成し、承認の可否を決議してもらう必要があります。定款に定めがある場合は規定に従いましょう。
株式譲渡契約を締結する
承認が下りたら、譲渡当事者間で正式に株式譲渡契約を締結します。契約書には、譲渡日・譲渡価格・・支払方法・株式の種類・株数などの詳細を明記しましょう。契約締結により、株式の売買が法的に成立し、当事者双方の責任が明確になります。必要に応じて、契約書には弁護士などのチェックを入れると安心です。
株主名簿の書き換えを行う
株式譲渡契約の締結と代金決済が済んでも、株主名簿が書き換えられない限り、譲渡は完了しません。現在は株券を発行していない企業が多く、株主の地位は株主名簿への記載によって証明されます。譲渡人・譲受人が共同で名義書換を請求し、会社側が株主名簿に記載を行うことで、譲渡手続きが正式に完了します。
税務申告を行う
株式を譲渡した社員側には、譲渡益が発生した場合に所得税(譲渡所得)などの納税義務が発生する可能性があります。一方、譲渡人側も譲渡損益がある場合は確定申告の対象になります。取引の内容によっては贈与とみなされるケースもあるため、譲渡前後には必ず税理士などの専門家と相談し、適切な税務申告を行いましょう。
まとめ|社員への株式譲渡を円滑に進めるために、専門家に相談を
社員への株式譲渡は、後継者不在の課題を解消する手段として注目されており、経営の継続性や従業員のモチベーション向上にもつながります。ただし、譲渡には目的や対象者の選定、社内での承認手続き、契約締結、名簿の書き換えや税務申告など、法的に求められるステップが複数存在します。
特に譲渡制限株式の場合は、取締役会や株主総会での承認が不可欠であり、適切な手続きを踏まないと株式の効力が発生しないリスクもあるため注意が必要です。
社員への株式譲渡を円滑に進めるためには、法的知識や契約実務に精通した専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。M&Aを通じて社員に株式を譲渡したいとお考えの場合は、まずは信頼できる専門家に相談し、自社に最適なスキームを検討するところから始めましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















