CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
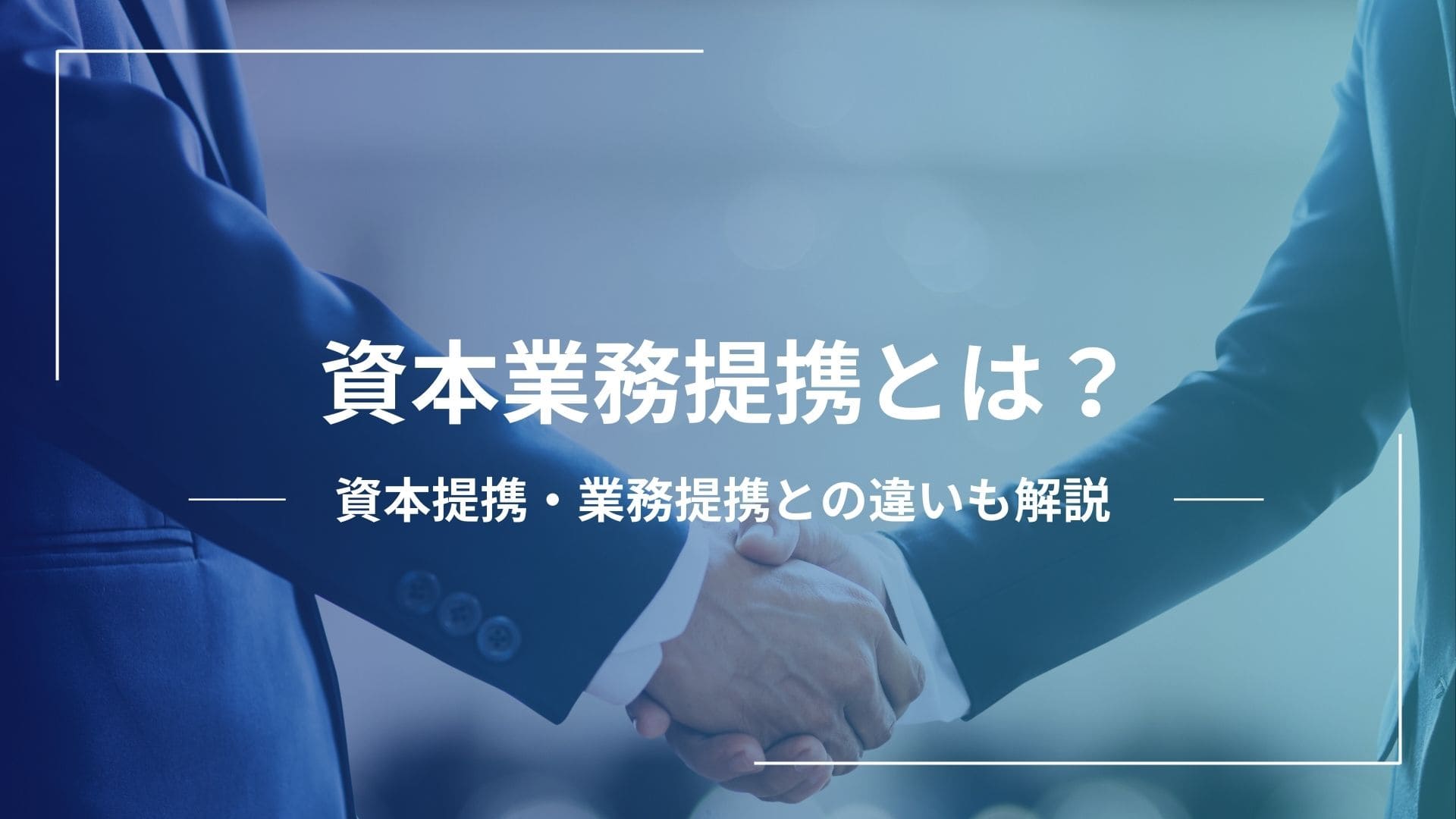
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
資本業務提携とは?子会社化やM&Aとの違い、メリットデメリットをわかりやすく解説
資本業務提携は事業拡大の有力な手段として、多くの企業が注目しています。
本記事では、これから事業をさらに拡大したい企業に向けて、資本業務提携とは何か、そしてよく比較される資本提携や業務提携との違い、さらにメリット・デメリットについて解説します。
目次
資本業務提携とは?
資本業務提携とは、複数の企業が相互の強みを活かし合い、事業活動を共同で行うために、資本(株式の持ち合いなど)と業務の両面で提携関係を構築することを指します。資本業務提携により、資金提供や経営資源の共有、技術開発、人材交流、販売網の統合などが可能になります。
資本提携では一方が他方の株式を取得するなどして信頼性を高め、業務提携では具体的なプロジェクトや事業活動を通じて相互協力を行います。
より緩やかな企業間連携をお考えの企業におすすめで、将来的なM&Aへの第一段階として実施されることもあります。完全な経営統合を行わずに、シナジー効果を得ることがで期待できます。
資本業務提携と「業務提携」「子会社化」「M&A」「買収」の違いは?
資本業務提携は、業務提携や子会社化、M&Aなどと混同されることが多いです。ここでは資本業務提携とそれぞれの違いについて解説します。
業務提携との違い
業務提携は業務やプロジェクトの共同実施を目的として行われます。販路を一気に拡大したい企業や研究開発を加速させたい企業にとっては、業務提携は有効な手段です。
ただ技術や業務を共有し合うのではなく、人材や顧客を共有し合うことも可能です。お互いの経営資産の共有でシナジー効果がもたらされる場合は、業務提携は大変おすすめできます。
子会社化との違い
子会社化は、親会社が相手企業の株式を過半数以上保有し、経営権を掌握することで支配関係を築くことを指します。親会社は子会社の重要な意思決定に直接関与し、経営方針や戦略も親会社主導で進められるのが特徴です。
一方、資本業務提携では株式の持ち合いや業務協力が行われますが、企業の独立性は保たれ、経営への直接的な支配は行いません。このため、両社が対等な立場で協力を進める点が、子会社化との大きな違いです。
【関連記事】M&Aによる子会社化とは?方法やメリットデメリット、事例を解説
M&Aとの違い
資本業務提携は、企業が独立性を保ちながら資本(株式の持ち合い)と業務(技術提携や共同開発)で協力し、相互の強みを活かして成長を目指すものです。
一方、M&A(合併・買収)は、企業を統合または支配することを目的としており、合併では複数の企業が統合して新しい組織を形成します。
資本業務提携は柔軟でリスクが分散しやすいのに対し、M&Aは統合後の大きな責任とリスクを伴います。
【関連記事】M&Aとは?意味や目的、手法など基本をわかりやすく解説
買収との違い
資本業務提携は、企業間で一定の株式を保有することで信頼関係を強化しつつ、業務面での協力を行いますが、各企業は経営の独立性を維持します。
これに対し、買収は一方の企業が他方の株式を過半数以上取得することで、経営権を掌握し支配することを目的とします。資本業務提携は対等な協力が前提ですが、買収は支配・被支配の関係が生じる点が異なります。
【関連記事】買収とは?意味やメリットデメリット、手続きの流れ、最新事例をわかりやすく解説
資本業務提携を行うメリット
資本業務提携は企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、資本業務提携のメリットについて解説します。
強固な協力関係が構築できる
業務だけでなく、資金面でも支援と共有があり、強い協力関係を築き上げることが可能です。お互いの資産を保有し合うことで長期的な関係性を作ることもできるでしょう。
また、財務面で苦労していた企業は、資産業務提携を行うことでパートナー企業からの資金の支援が期待でき、財務面の改善につながる場合もあります。
シナジー効果の期待できる
企業間の資本と業務の連携により、事業面で新たな機会を創出し、コスト削減や業務の効率化など、シナジー効果が期待できます。
「自社にはない強みを他社が持っている」または「自社が持っている強みを他社に共有することで事業が加速する」という場合は、資本業務提携を実施することで事業が大きく成長するかもしれません。
【関連記事】M&Aのシナジー効果とは?種類や分析フレームワーク、定量化する方法を解説
市場参入のハードルを下げられる
提携先企業の販売網や現地での知識、信頼関係を活用することで、新しい市場や地域へのスムーズな参入が可能となります。
特に海外市場への進出では、現地企業との資本業務提携により、言語や文化、規制などの障壁を乗り越えやすくなります。これにより、市場参入の成功確率が格段に向上します。
リスク分散が可能になる
大規模なプロジェクトや新規事業において、提携先企業とリソースやリスクを分け合うことで、単独での挑戦よりも安全性を高められます。
例えば、新技術の研究開発や市場投入の際、費用や失敗のリスクを双方で負担することで、事業展開をより柔軟に進めることができます。これは特に不確実性の高い事業環境において有効です。
技術革新や研究開発を促進できる
資本業務提携を通じて、相手企業の持つ先進的な技術や研究開発ノウハウを共有することで、自社だけでは達成できないイノベーションを実現できます。
例えば、特定の分野で強みを持つ企業との提携により、製品開発のスピードが向上し、競争力の強化につながります。また、研究費用やリソースの分担により、効率的な開発が可能となる点も見逃せません。
資本業務提携を行うデメリット
資本業務提携はメリットがある一方で、デメリットも存在します。ここでは、資本業務提携を行う際のデメリットについて解説します。
契約解除ができない
資本業務提携は一度締結すると、契約解除ができません。資本にあたる株式の売買が発生するため、提携を解消しようとすると、株式売買に伴う手続きが必要になります。この手続きにはコストや時間がかかる可能性があるためです。
資本業務提携を実施する際は、このデメリットを理解のうえ、契約解除をしない前提で提携する進めることが大切です。
意思決定が遅れるおそれがある
提携相手企業との調整が必要になることで、経営上の意思決定が複雑化し、スピードが低下する可能性があります。
特に、経営方針や事業戦略で意見が対立した場合、調整に時間がかかることがあり、市場環境の変化に迅速に対応できないリスクが高まります。このような意思決定のスピードが落ちるリスクは、競争の激しい業界では大きな課題となります。
提携による成果が確実ではない
資本業務提携に期待されるシナジー効果や事業の成長が、必ずしも計画通りに実現するとは限りません。
業界環境の変化や両社の企業文化や戦略の相性が原因で、提携が十分な成果をもたらさない場合もあります。この不確実性は、提携の目的や範囲を慎重に検討する必要性を示しています。
資本業務提携を行う方法
ここでは、資本業務提携を行う方法について解説します。
資本業務提携を行う方法は、主に以下の4つです。
- 株式譲渡
- 第三者割当増資
- 株式交換
- 株式移転
各方法の特徴に着目しながら、お伝えしていきます。
株式譲渡
株式譲渡とは、企業が保有する株式を他の企業に売却または譲渡し、資本関係を構築する方法です。この手法は、資本業務提携の中でも比較的シンプルなプロセスで実現できるため、多くの企業が採用しています。
株式譲渡を利用すると、譲渡元の企業は資金を調達することができ、譲渡先の企業は株式を取得することで経営への関与を深めることが可能になります。また、資本関係の構築を通じて、企業間の協力関係を強化しやすくなる点が魅力です。
例えば、新規事業の展開や既存事業の拡大を図る際に、株式譲渡を通じて提携先を募るケースがあります。しかし一方で、株式を譲渡することで経営権を一部失うリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
また、譲渡条件や価格設定についての交渉が重要であり、適切な評価を行わなければならない点も課題となります。
株式譲渡は手続き自体は比較的簡易ですが、事前にパートナー企業との関係性を十分に議論し、双方が納得したうえで進めることが成功の鍵となります。
株式譲渡については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】株式譲渡とは?メリットやデメリット、事業譲渡との違いも解説
第三者割当増資
第三者割当増資とは、新たに発行した株式を特定の第三者に割り当てることで資金調達を行う方法です。既存の株主に対する影響を最小限に抑えながら、資本業務提携を実現する手段として広く利用されています。
第三者割当増資の最大のメリットは、増資によって提携先企業に資本を提供しながらも、自社の経営権を大きく失わない点です。そのため、「経営権を保持したいが、資本提携を進めたい」というニーズを持つ企業にとって効果的な選択肢となります。
例えば、スタートアップ企業が大手企業と提携する場合、第三者割当増資を通じて資金を確保しながら、提携先から経営支援やノウハウを受けるケースが多く見られます。一方で、株式を割り当てる際には、公正な株価評価を行い、提携先と条件を慎重に協議する必要があります。
また、既存株主との関係性にも注意を払う必要があります。株式の希薄化による反発を防ぐため、透明性の高い説明が欠かせません。これらをしっかりと準備することで、第三者割当増資は企業の成長を後押しする効果的な手段となります。
株式交換
株式交換は、ある企業が他の企業の株式を取得し、完全子会社または親会社の関係を築く方法です。この手法は、企業間の経営統合やグループ化を進める際に広く活用されます。株式交換による資本業務提携は、企業間のシナジーを発揮することが目的です。
例えば、親会社となる企業が子会社となる企業の株式をすべて取得することで、グループ全体の事業を効率化しやすくなります。また、株式交換を通じて資本関係を明確化することで、長期的な協力体制を築くことができます。ただし、株式交換を実施する場合、株式の価値を適切に評価し、双方の合意を得ることが重要です。
さらに、税制面でのメリットが得られる場合もあり、企業の再編や規模拡大を図る上で有効な手段となります。しかし、株主に対する説明責任や合併後の運営体制の統一といった課題もあります。これらの点を事前に整理することが、成功につながる鍵となるでしょう。
【関連記事】株式交換とは?メリットとデメリット、手続き方法を解説
株式移転
株式移転とは、新たに設立する親会社が既存の複数の企業の株式を取得し、それらの企業を完全子会社化する手法です。この方法は、持株会社を設立してグループ経営を強化したい場合に多く利用されます。
株式移転の主な特徴は、株式交換と同様に、企業グループ全体の効率的な経営を実現できる点にあります。特に、各企業の独立性を尊重しながらも、親会社として一元管理を行うことで、リソースの最適配分や事業の統合がスムーズに進みます。
実際の事例として、異業種間の提携を行う場合や、海外進出の足がかりをつくるために株式移転を活用するケースが挙げられます。一方で、手続きの複雑さや、株主間での同意形成の難しさが課題となる場合もあります。したがって、法的な専門家の支援を受けながら慎重に進める必要があります。
株式移転は、戦略的な目的に応じて活用することで、大きな成長機会をもたらす可能性がありますが、リスクも伴うため、計画段階での詳細な検討が不可欠です。
【関連記事】株式移転とは?メリットやデメリット、手続きの流れなど基礎知識を解説
資本業務提携の進め方・手続きの流れ
資本業務提携をスムーズに進めるためには、計画的に各ステップを進めることが重要です。ここでは、資本業務提携の一般的な進め方と手続きの流れを詳しく解説します。
資本業務提携の目的を明確にする
資本業務提携を進める最初のステップは、その目的を明確にすることです。資本業務提携には、事業の成長を目指した「新規市場への参入」、リソースを活用した「技術開発の強化」、競争優位性を高める「シナジー効果の創出」など、さまざまな目的があります。
しかし、目的が明確でなければ、提携後の成果が不明瞭になり、効果的な提携が実現できない可能性があります。
目的を定める際には、社内で「どのような課題を解決したいのか」「どの分野で協力が必要か」などを明確に議論しましょう。
例えば、自社で不足している技術力を補うために提携先を探す場合、技術提供だけでなく、研究開発体制の強化や市場シェアの拡大も目的に含めるべきです。
目的が定まると、提携先を探す基準が明確になり、交渉もスムーズに進められるようになります。提携の方向性が一致していないと、後々の統合作業や意思決定で問題が生じるリスクがあるため、この段階をしっかりと進めることが成功の鍵となります。
資本業務提携先を探す
資本業務提携を進める上で重要なのが、適切な提携先を見つけることです。提携先を選ぶ際には、自社の目的やビジョンに合致しているかを慎重に見極める必要があります。
例えば、事業規模や市場でのシェア、技術力、ブランド力、財務状況など、さまざまな観点から候補を評価することが重要です。
提携先を探す方法としては、業界内のネットワークを活用する、専門家やコンサルタントの力を借りる、またはM&Aプラットフォームを利用するなどがあります。
また、候補企業の文化や経営方針が自社とどれほど一致しているかも重要な要素です。経営の方向性や価値観が異なりすぎる場合、提携後にスムーズな統合が難しくなることがあります。
例えば、自社が技術提供を求めている場合、技術力が強みの企業を選ぶだけでなく、その企業が市場で信頼されているか、財務的に安定しているかを確認する必要があります。
この段階では、複数の候補を比較検討し、最終的に適切なパートナーを選定することが、提携の成功につながります。
提携の詳細を決める
提携先が決まったら、次に提携の具体的な条件や詳細を詰めていきます。このステップでは、出資比率や提携範囲、経営への関与の程度などを明確に決定します。これにより、双方の役割分担や責任が明確になり、提携後の運営をスムーズに進めることができます。
例えば、出資比率を決める際には、自社がどの程度の経営権を保持したいのか、また相手企業にどの程度の関与を求めるのかを検討する必要があります。
さらに、提携範囲についても、資本だけでなく技術提供や販売協力など、どの分野で具体的に協力するのかを決めることが大切です。この段階では、事業計画や収益予測を共有し、提携の効果を具体的にイメージすることが重要です。
また、万が一提携が解消される場合に備え、解消条件やリスク対応策についても話し合いましょう。これらの詳細を明確にすることで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
提携条件を交渉する
提携の詳細がある程度固まったら、相手企業との具体的な交渉に入ります。提携条件を話し合いながら、双方が納得のいく形で合意を形成することが重要です。この交渉では、提携内容に関する細部まで詰めることが求められます。
例えば、出資比率に関する交渉では、相手企業がどの程度の出資を希望しているのか、自社の経営方針との整合性が取れるのかを検討します。また、利益配分や経営への関与度合いについても、双方が納得する条件を設定する必要があります。
交渉の際には、提携の目的や期待される成果を再確認しながら進めると良いでしょう。専門家や弁護士を交えて話し合うことで、法的リスクやトラブルを回避することが可能です。交渉が成立すれば、最終的な契約内容を確定し、次のステップに進むことができます。
契約を締結する
交渉がまとまったら、最終的に契約を締結します。契約書は、提携内容や条件を法的に拘束力のある形で明記した文書であり、双方の合意が明文化されたものです。
契約を締結する段階では、契約内容に不備がないかを慎重に確認し、必要に応じて法務専門家のサポートを受けることが推奨されます。
契約書には、提携の目的や範囲、出資比率、利益配分、役割分担、提携期間、さらには提携解消時の条件などが含まれます。また、守秘義務や紛争解決の手段についても盛り込むことが一般的です。
契約締結後は、提携の具体的な実行段階に移行します。このタイミングで社内外に適切な情報を公開し、ステークホルダーに対して説明責任を果たすことも大切です。適切な契約の締結は、提携成功の重要なステップとなります。
資本業務提携の株式保有率の詳細
資本業務提携を行う際、出資比率は目的や案件によって大きく異なります。ここでは、各出資比率の経営の内容・閾値について解説します。
各出資比率の閾値(いきち)は以下のとおりです。
- 3%程度:会計帳簿閲覧権の閾値
- 15%程度:重要提案権の閾値
- 20%程度:持分法適用の閾値
- 33.4%未満:拒否権の閾値未満
※それ以上の出資比率のケースもあります。
出資比率を決める時は以下の要因を参考にします。
- 提携の目的
- 両社の意向
- 経営の独立性の希望度合い
- 事業上のシナジー
- 資金需要
- 将来的なM&Aの可能性
経営権獲得が目的で資本業務提携が行われる場合もありますが、ほとんどが戦略的な協力関係の構築のために行われることが多いです。
出資比率は提携の目的に応じて柔軟に設定されます。
まとめ|強固な協力関係を作りたい企業に資本業務提携はおすすめ
資本業務提携は、企業が互いの強みを活かしながら、独立性も維持できる有効な手段です。事業成長をより早く実現させたい企業は、資本業務提携を検討しましょう。
提携を実施する際はパートナー候補の企業と具体的な提携の内容、そして、株式の売買に伴う取り決めを話し合うことが大切です。
さらに、資本業務提携に詳しい専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な提携が実現できるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、資本業務提携のご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。資本業務提携の相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















