CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
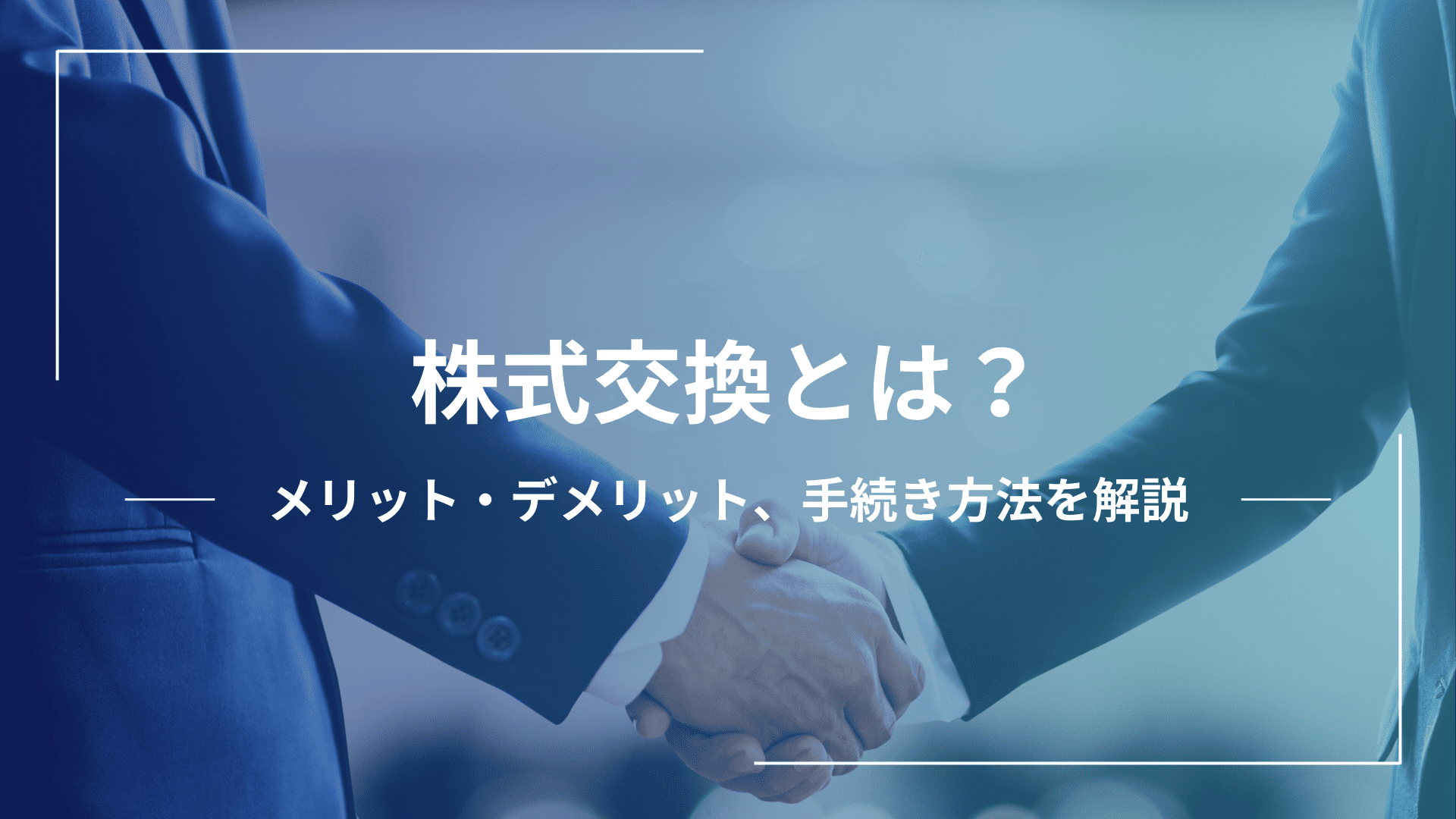
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.07.15
株式交換とは?株式移転との違いやメリットデメリット、手続きの流れをわかりやすく解説
株式交換は、企業買収や組織再編の場面で活用される重要な手法の一つです。
本記事では株式交換の基本から、株式移転との違い、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れまでを初心者にもわかりやすく解説します。
目次
株式交換とは?
株式交換は、会社法に基づく組織再編手法の一つで、買い手企業(完全親会社)が売り手企業企業(完全子会社)を完全子会社化する際に用いられます。
この手続きでは、現金などの対価を支払うのではなく、親会社の株式を対価として交付することが特徴です。
そのため、買収に必要な資金調達を行わずに済む点がメリットとされます。
例えば、A社がB社を子会社化する場合、A社はB社の株主にA社の株式を交付し、B社株式を取得します。
これにより、B社はA社の100%子会社となります。
株式交換は主に上場企業による非上場企業の買収や、企業グループ内での組織再編など、利用は限定されています。
株式交換と株式移転との違い
株式交換と混同されやすいのが株式移転です。両者は似た仕組みですが、組織再編の目的や手続きには明確な違いがあります。
株式移転は、既存の複数の会社が共同で新たに持株会社を設立し、その持株会社の株式を既存株主に交付する手法です。
一方で、株式交換は既存の会社同士で親子関係を構築するため、すでに存在する会社が買収主体となります。
例えば、株式移転ではA社とB社が共同でC社という持株会社を新設し、A社・B社はC社の完全子会社になりますが、株式交換ではA社がB社を取り込み、A社がB社を単独で支配します。
また、株式移転は主にグループ経営の統合を目的とし、株式交換は経営権の取得や経営資源の集約を意図するケースが多いです。
制度上も手続きや税務処理が異なるため、どちらを選択するかは経営戦略や目的に応じて慎重に判断する必要があります。
また、株式譲渡と事業譲渡との違いは以下の通りです。
株式交換のメリット
株式交換を活用することで、買収に伴う資金負担を抑えつつ、柔軟に経営統合を実現できます。ここでは主な利点を解説します。
買収後も別法人として事業に関与できる
株式交換を行っても、売り手企業は法人格を維持したまま完全子会社となります。
そのため、既存の事業ブランドや取引先との関係を継続しながら、経営の独立性を一定程度保つことが可能です。
この仕組みは、急激な組織変更による従業員の混乱や顧客離れを避ける効果があります。
例えば、買収された会社が地域密着型の事業を展開している場合、既存の信用や人材を活かした運営を続けやすいです。
こうした柔軟性は株式交換の大きな強みといえるでしょう。
買収資金を用意する必要がない
株式交換では、親会社が対価として自社株を交付するため、現金で多額の買収資金を調達する必要がありません。
これは資金負担を大幅に軽減する上、借入金による財務リスクを抑えられる点で有効です。
実際、資金力に余裕のない中堅企業や成長企業でも、株式交換を活用して規模拡大を目指すケースが増えています。
例えば、上場企業が自社株を用いて非上場企業を子会社化する場合、現金買収に比べて資本効率を高めやすいです。
このように、株式交換は手元資金に制約がある場合でも戦略的M&Aを実現できます。
株主全員の同意がなくても実施可能
株式交換は、株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)で承認されれば実施できます。
つまり、全株主の同意が条件ではないため、実務上のハードルを下げやすい手法です。
特に上場企業や株主数の多い会社では、全員から合意を得るのは非常に困難です。
株式交換なら、一定の賛成を得ることで手続きを進められるため、スムーズな意思決定が可能になります。
こうした柔軟性はスピーディーな経営統合を進めたい場合に有効です。
株式交換のデメリット
一方で、株式交換には価格変動リスクや手続きの複雑さといった注意点もあります。
導入前にデメリットを理解しておくことが重要です。
受け取る株式の価格下落リスクがある
株式交換で取得する株式は、将来的に価格が下落する可能性があります。
株式市場の影響を直接受けるため、受け取った株式の価値が減少すれば株主に損失が生じます。
例えば、親会社の業績悪化や株価の急落が発生した場合、対価として交付された株式の評価額が著しく低下するおそれがあります。
このリスクを踏まえ、取引先企業の財務状況や市場動向を十分に分析しておくことが大切です。
手続きが複雑になりやすい
株式交換の実施には、株式交換契約の締結、株主総会の決議、開示書類の備置など多岐にわたる手続きが必要です。
これらを適正に進めるためには、法律・会計・税務の専門家の助言が欠かせません。
例えば、株式交換比率の算定や書類作成だけでも多くの準備が求められます。
準備不足のまま進めると手続きの不備が生じ、後のトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、事前の計画立案と専門家の協力が重要です。
既存の株主構成が変わる可能性がある
株式交換によって親会社の新株が発行されるため、既存株主の持株比率が低下する可能性があります。
これは希薄化と呼ばれ、既存株主の経営への影響力が弱まる要因となります。
例えば、買収規模が大きい場合や多くの株式を交付する場合、株主構成が大きく変化することも珍しくありません。
こうした変化は経営権や議決権に直結するため、株主との調整を慎重に進める必要があります。
株式交換の手続きの流れ
株式交換を円滑に進めるために、手続きや流れに沿った対応をしていくことが大切です。
ここでは、株式交換の手続きについて解説します。
株式交換は以下の流れで進んでいきます。
- 事前準備
- 株式交換契約の締結
- 事前開示書類の備置
- 株主総会での承認
- 反対株主の買取請求
- 効力発生と登記
- 事後開示書類の備置
それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
1. 事前準備
事前準備では、株式交換の目的や計画の詳細を明確にすることが重要です。
事前準備が不十分な場合、後の手続きで予期しない問題が発生する可能性があります。
専門家の助言を得ながら、事前にしっかりとした計画と準備を行うことで、手続き全体が円滑に進行します。
2. 株式交換契約の締結
会社法にのっとり、株式交換契約を締結します。
取締役会または株主総会にて以下の点を決議します。
- 株式交換の予定日
- 子会社化する予定の企業に提供する株式の交付割合
契約を適切に締結して、全ての当事者間で合意を確認することが大切です。
3. 事前開示書類の備置
会社法で定められた日 または株主総会の2週間前の日に事前開示書類に備置が必要です。
書類には株式交換締結 などの法定開示事項が記載されています。
4. 株主総会の承認
株主の承認を得ることで、株式交換が法的に適用されます。
株式総会では株主より原則3分の2の賛成または議決権の承認が必要となります。(全ての承認を得る必要はありません。)
5. 反対株主の買取請求
会社法に乗っ取り株式総会で承認に反対した株主に 株式を適正価格で買取するように請求をすることができます。
株式交換の効力発生日の20日前までに、株式交換について株主に通知します。
買取価格については株主と会社の間で協議して決めます。
6. 効力発生と登記
株式交換契約書に記載された効力発生日に株式交換契約が成立します。
登記事項に変更が生じた場合は、効力発生日から2週間以内に登記変更をします。
7. 事後開示書類の備置
買い手企業と売り手企業は、それぞれ事後開示書類の作成にあたります。
効力発生日から6カ月間が備置期間となります。
事後開示書類には、株式交換の手続きの結果や差止請求、反対請求の状況などが記載されます。
株式交換で株式総会の決議を省略できるケース
株式交換では条件を満たすと、子会社側(売り手企業)が株式総会決議を省略できます。
簡易な手続きが可能な「簡易株式交換」と「略式株式交換」を紹介します。
簡易株式交換
簡易株式交換は、株式交換の対価が子会社の純資産の一定割合を超えない場合に適用されます。
具体的には、対価が子会社の純資産の20%以下であれば、株主総会の特別決議を行わず取締役会の決議だけで手続きが進められます。
この仕組みによって、迅速に親会社への株式交換を実現できるのが特徴です。
例えば、比較的小規模な子会社をグループ内再編の一環として完全子会社化する際、簡易株式交換を利用すると大幅に事務負担を軽減できます。
ただし、少数株主の利益保護の観点から、重要な影響を及ぼす取引には適用できないため、条件を満たしているか慎重に確認する必要があります。
略式株式交換
略式株式交換は、親会社が既に子会社株式の90%以上を保有している場合に利用できます。
この場合、子会社の残りの株式を取得する際に株主総会の決議を省略できます。
親会社が圧倒的な議決権を有しているため、手続きの合理化が認められているのが特徴です。
例えば、持株比率を100%にするために残余株式をまとめて取得する場合、略式株式交換を活用すればスムーズに完全子会社化を完了できます。
ただし、少数株主の権利保護のため、反対株主には買取請求権が認められる点に注意が必要です。
手続きの正当性を担保するため、必要書類の作成や開示は慎重に行いましょう。
株式交換における税務処理
株式交換では、親会社・子会社それぞれの立場で税務処理が大きく異なります。
適格・非適格の区分や資産の評価方法を正しく理解し、課税リスクを回避することが重要です。
株式交換後の完全子会社の処理
株式交換後、完全子会社となる売り手企業は、基本的に新たな課税が生じません。
これは、対価として現金ではなく親会社の株式を受け取るだけであり、資産の譲渡益が発生しない扱いとなるためです。
ただし、既存の資産や負債に関連する税務処理は引き続き通常通り行う必要があります。
例えば、子会社が保有する土地や有価証券に含み益があっても、株式交換そのものによって時価評価課税が行われることはありません。
こうした取引の税務負担が比較的小さい点は、株式交換が組織再編で多用される理由の一つです。
株式交換後の完全親会社の処理
一方、株式交換後に完全親会社となる買い手企業では、取引が「適格株式交換」に当たるかどうかで税務処理が大きく変わります。
適格株式交換とは、経営再編や企業グループの強化を目的とする取引であり、この場合は課税が繰延べとなりません。
反対に、単なる株式の売買を目的とする「非適格株式交換」と判断されると、課税対象となります。
具体的には固定資産や土地、有価証券、繰延資産などの資産を時価評価し、その差額に応じて課税が発生します。
ただし、税務上の帳簿価額が1,000万円未満であれば時価評価は不要です。
適格・非適格の判定は専門的で判断が難しいため、税理士や再編に詳しい専門家に必ず相談し、事前にシミュレーションを行いましょう。
株式交換を実施する際の注意点
株式交換を円滑に進めるためには、法務や税務だけでなく、株主や利害関係者への対応にも細心の注意が必要です。
ここでは実務で特に重要なポイントを解説します。
適正な株価評価を行う
株式交換を行う際、適正な株価評価は最も重要なプロセスの一つです。評価が不適正だと株主間の不公平が生じ、反発や訴訟リスクが高まります。
特に上場企業の場合は市場価格を基準としつつ、非上場株式の場合は純資産法や収益還元法などを用いて公正な算定が求められます。
例えば、売り手企業の事業価値を過大評価すれば、親会社株主の持分が不当に薄まるおそれがあります。
適正な評価を確保するには、公認会計士や第三者評価機関に依頼することが有効です。
取引スキームの税務影響を確認する
株式交換は税務面でもさまざまな影響が発生します。
適格株式交換として認められる場合、課税繰延の扱いを受けられますが、要件を満たさないと譲渡所得が発生し、想定外の納税負担が生じることがあります。
例えば、株式交換比率や保有期間、組織再編の目的が適格要件に該当しない場合、株主に課税が発生する可能性が高いです。
取引の前に税理士や税務専門家と詳細に協議し、税務リスクを正確に把握することが欠かせません。
既存株主や利害関係者への説明を徹底する
株式交換は既存の株主構成や経営体制に影響を及ぼすため、透明性の高い説明が不可欠です。
説明不足のまま進めると、株主総会での承認が得られないだけでなく、後から不信感や訴訟リスクが生じます。
例えば、取引の目的や期待するシナジー、株式交換比率の合理性などを丁寧に説明することで、理解と納得を得やすくなります。
利害関係者に対する誠実な対応は円滑な実施を支える重要な基盤です。
必要な契約書や書類を漏れなく準備する
株式交換には契約書の締結、株主総会議事録、開示書類の備置など多くの書類が必要です。
手続きを進める中で書類に不備や漏れがあると、効力発生日が遅れたり、法的に無効とされるおそれもあります。
例えば、株式交換契約の記載内容が不明確だと、後のトラブルが生じる可能性が高いです。
実務では専門家の支援を受けながら、手続きのスケジュールと必要書類を事前にリスト化しておくことが重要です。
将来の経営権やガバナンスに配慮する
株式交換によって経営権やガバナンスの枠組みが大きく変わります。
例えば、親会社株主の持分が希薄化することで経営への影響力が弱まり、意図しない支配構造が生まれる場合もあります。
また、子会社側の経営陣との役割分担を明確化しないと、組織の混乱を招くおそれがあります。
将来の経営権や意思決定プロセスを整理し、ガバナンス体制をあらかじめ設計することが円滑な経営統合の鍵です。
まとめ|株式交換の仕組みと注意点を理解しよう
株式交換は、親会社が自社株を交付して他社を完全子会社化する仕組みです。
買収資金を用意する必要がなく、既存の法人格を残せる点が大きな特徴です。
一方で、株価の変動リスクや株主構成の変化など注意すべき課題もあります。
適正な株価評価や税務面の確認、関係者への説明を徹底することがスムーズな手続きにつながります。
専門家の助言を受けながら、目的に応じた適切なスキームを検討しましょう。
CINC Capitalでは、M&A仲介会社として、株式交換のご相談を受け付けております。
業界歴10年以上のプロアドバイザーも在籍しております。
M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















