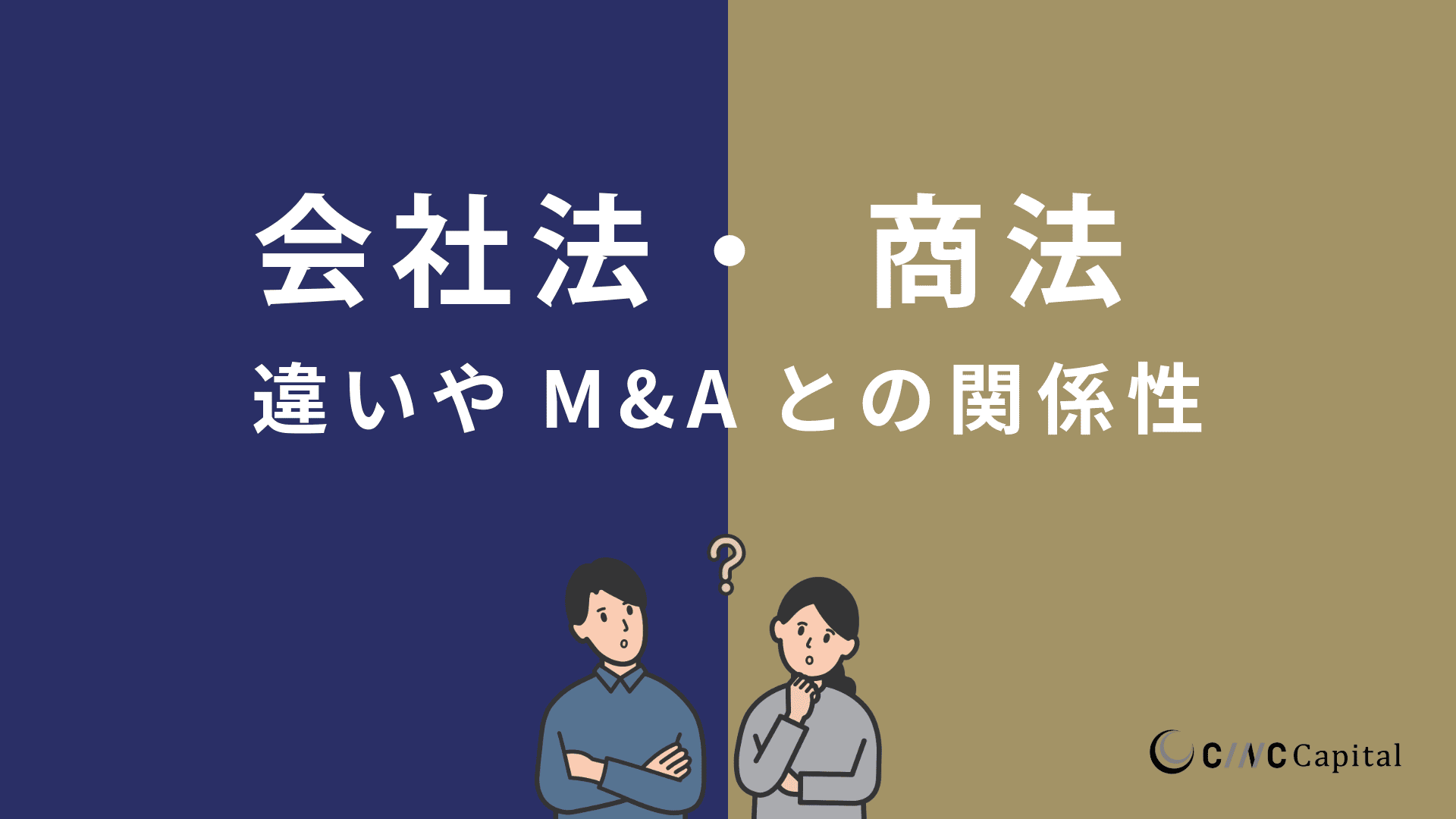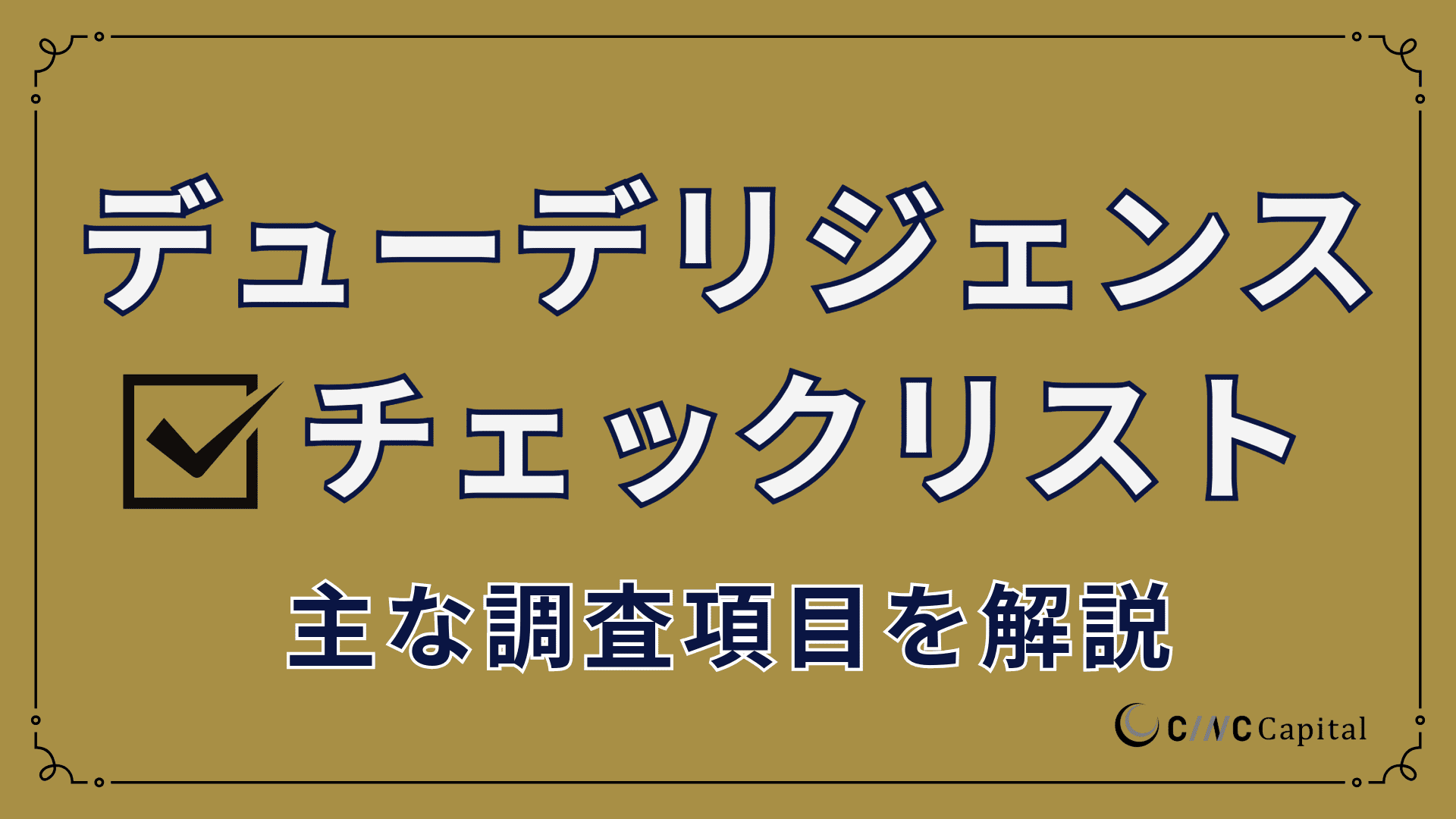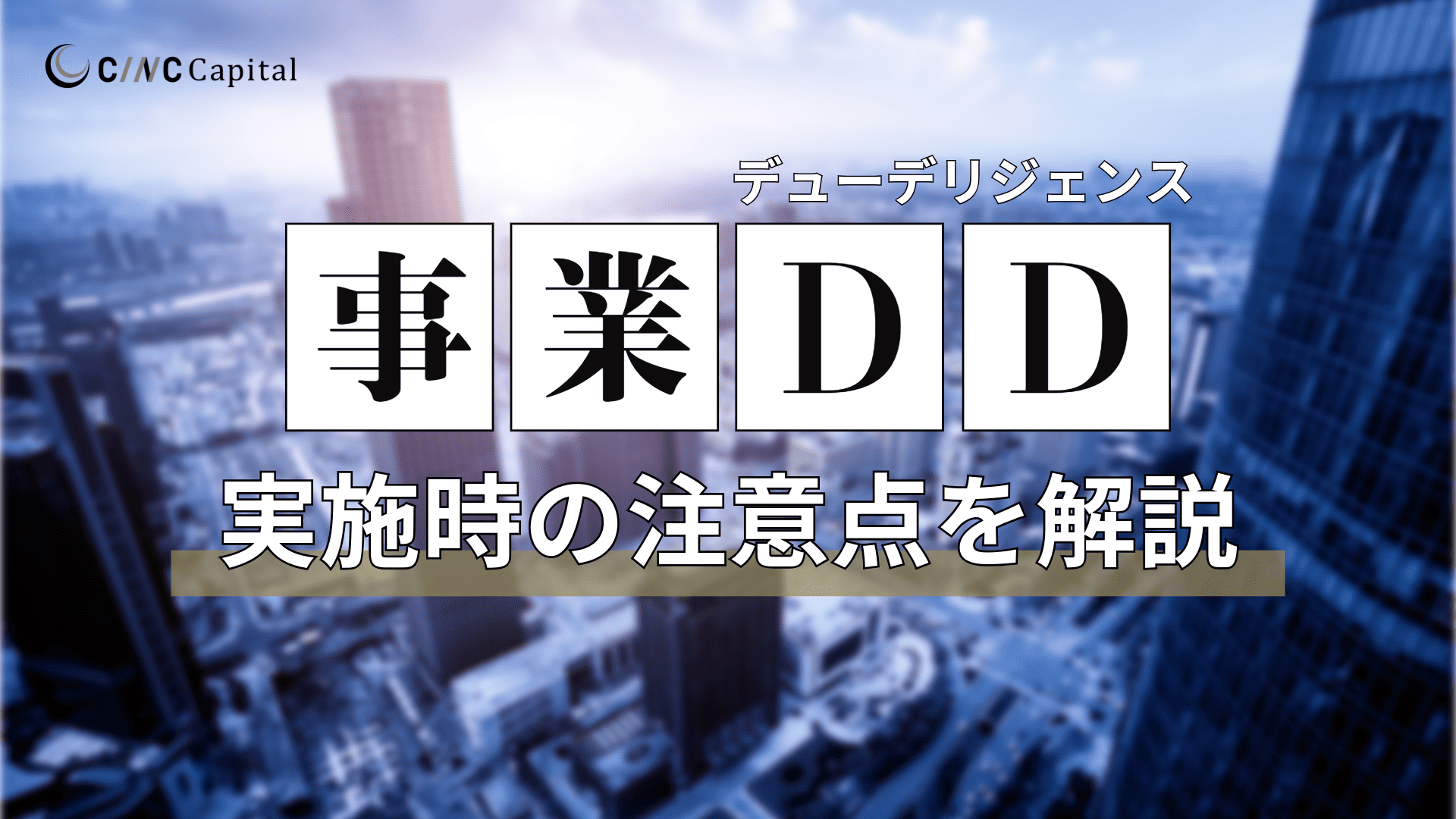CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
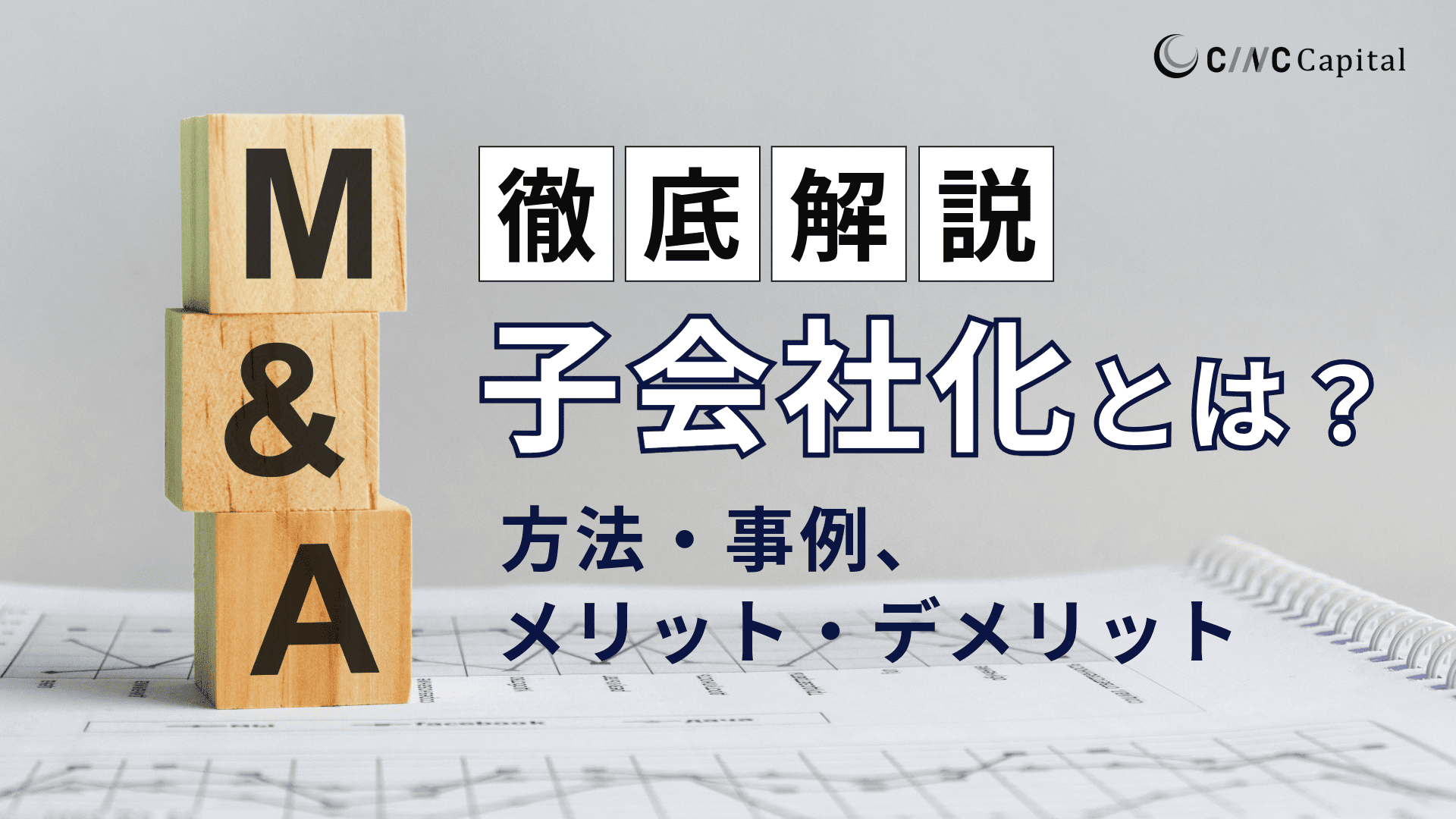
法務 / 法律
- 最終更新日2025.06.26
M&Aによる子会社化とは?方法やメリットデメリット、事例を解説
M&Aによる子会社化は、企業成長や事業再編の戦略として注目される手法のひとつです。この記事では、子会社化の仕組みや方法、そのメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
具体的な事例や企業に与える影響も紹介しながら、買い手・売り手双方にとってのポイントを明らかにします。
目次
M&Aにおける「子会社化」とは?
M&Aにおける子会社化とは、ある企業が他社の支配権を取得し、自社グループに取り込むことを指します。まずは、子会社化の概要と種類について整理します。
子会社化の種類ごとの違い
子会社化にはいくつかの形態があり、それぞれ支配の度合いや法的な関係に違いがあります。主に「完全子会社」「連結子会社」「孫会社」の3つに分類されます。
|
種類 |
概要 |
支配構造 |
|
完全子会社化 |
親会社が100%出資している会社 |
親会社が全株式保有 |
|
連結子会社 |
親会社が実質的に支配権を持つ会社(50%超の株式所有など) |
親会社が過半数出資 |
|
孫会社 |
子会社がさらに保有する子会社(親会社から見て2階層下) |
親会社 → 子会社 → 孫会社 |
これらの違いを理解しておくことは、企業統治や会計処理を適切に行ううえで重要です。
子会社化の主な手法
子会社化を実現するためには、さまざまなM&A手法が活用されます。以下に主要な3つの方法を紹介します。
株式取得
子会社化の基本的な手法として最も一般的なのが株式取得です。これは対象企業の株式を買収し、一定以上の議決権を得て支配権を獲得する方法です。
株式取得の魅力は、柔軟性が高く交渉次第で段階的な子会社化も可能な点にあります。例えば上場企業では市場での株式取得も視野に入るため、戦略に応じたスピード感のある対応が可能です。
一方で、買収価格の適正評価や既存株主との合意が必要なため、実行には事前の慎重な準備が求められます。
第三者割当増資
第三者割当増資は、対象企業が新たに株式を発行し、それを買い手企業が引き受けることで子会社化を進める方法です。
第三者割当増資は、既存株主の持株比率を薄めることで支配権を獲得することが可能であり、特に成長資金を必要とする企業との利害が一致しやすいのが特徴です。
また、新たな資本注入により対象企業の財務基盤も強化されるため、双方にとってメリットがあります。ただし、発行側には既存株主の理解を得るための調整も必要になります。
株式交換・株式移転
株式交換・株式移転は、企業再編の際によく利用される手法です。株式交換では、親会社が対象企業の株主に自社株を交付して支配権を得ます。株式移転は、複数の企業が共同で新設会社を設立し、その傘下に入る形をとります。
株式交換・株式移転は、現金を使わずに持株比率の調整ができることが特徴です。特に同業種間での再編やホールディングス化に有効とされます。一方で、株価評価や株主への説得など手続きが複雑になりやすく、法務・税務面での慎重な設計が必要となります。
M&Aで子会社化される側の変化とは?
子会社化される企業にとっては、経営や組織面で大きな変化が生じます。ここではその代表的な変化を紹介します。
経営権の移行により意思決定のプロセスが変化する
子会社化により親会社が経営権を掌握すると、重要な意思決定は親会社の方針に基づいて進められるようになります。これにより、従来は独自に行っていた事業判断が、親会社の承認や連携を必要とするようになります。
特に予算編成や投資判断などの場面でこの影響が顕著です。従業員や経営陣にとっては、意思決定のスピードや裁量が制限されると感じることもあります。
従業員の待遇や人事制度が親会社基準に統一される
M&A後は、人事制度や福利厚生の見直しが検討されることがありますが、すべての場合で親会社基準に統一されるわけではありません。実務上は既存制度を尊重しつつ段階的に調整していくケースや、各社の特性に応じて異なる制度を維持するケースも少なくありません。
給与体系や評価制度の統一によりグループ全体の人材マネジメント効率が高まる効果も期待できますが、急激な変更は避け、従業員に配慮した移行計画が重要です。従来の社内文化や習慣が変わることに対して従業員の不満が生まれることもあり、丁寧な説明と移行期間の確保が重要です。
企業文化や社風が親会社の影響を受けて変化する
M&Aにより企業文化の融合が避けられないため、子会社の社風も徐々に親会社の影響を受けるようになります。スピード重視のベンチャー文化が、大企業的なプロセス重視型に変化するケースもあります。
このような文化的ギャップは、従業員のモチベーションや生産性にも影響を及ぼすため、双方の文化を尊重しつつ、段階的な融合を図る必要があります。
買い手企業にとっての子会社化のメリット
子会社化は、買い手企業にとって経営戦略上の多くの利点をもたらします。ここでは、代表的なメリットを解説します。
事業の多角化や新規市場への迅速な参入が実現できる
子会社化により、買い手企業は対象企業の持つ市場や商圏、商品・サービスに即時にアクセスできるようになります。新規市場への進出を自社単独で行うには時間とコストがかかりますが、既存の事業基盤を持つ企業を傘下に収めることで、その負担を大きく軽減できます。
例えば、地方に強い販売網を持つ企業を子会社化すれば、そのエリアへの拡大を迅速に進めることが可能です。このように、M&Aは時間とリソースを節約しながら多角的な展開を目指せる有効な手段です。
必要な技術・ノウハウ・人材を効率的に取り込める
M&Aによる子会社化では、買い手企業が自社で持っていない独自の技術や専門性を持つ人材をスムーズに獲得できます。例えば、IT系ベンチャー企業を買収することで、最新のソフトウェア開発技術やアジャイル開発のノウハウを取り入れることが可能です。
このようなケースでは、自社で一から人材を育成するよりも、即戦力を確保できる点が大きなメリットになります。結果として、新規プロジェクトの立ち上げや競争力強化につながることが期待されます。
税務面や会計処理でグループ経営上のメリットを得られる
買い手企業は子会社化によって、グループ全体での税務戦略や会計処理を最適化することができます。連結決算制度による会計上の効率化に加え、グループ通算制度(旧連結納税制度)の活用により、黒字会社と赤字会社の所得を通算することで、グループ全体での税負担の最適化が図れます。
また、内部取引の把握や資金繰りの一元化によって、グループ全体の経営管理が効率化されます。このような財務上のメリットも、子会社化を進めるうえで見逃せない要素です。
競合を取り込むことで市場シェアを拡大できる
競合企業を子会社化することで、直接的に市場シェアの拡大を実現できます。同一業種のM&Aでは、販路の重複解消やスケールメリットを得ることが可能で、競争力の強化につながります。
例えば、同じ製品を扱う企業同士の統合により、価格交渉力の向上や仕入コストの削減といったシナジーが期待されます。こうした戦略的な子会社化は、業界内での地位を高める有効な手段となります。
買い手企業にとっての子会社化のデメリット
子会社化には多くの利点がありますが、一方で慎重に検討すべきリスクも存在します。ここでは代表的なデメリットについて紹介します。
買収後の統合作業(PMI)で予想外のコストや摩擦が発生するリスクがある
PMI(Post Merger Integration)とは、買収後の統合作業を指します。このプロセスは想定以上に時間とコストがかかる場合があります。業務プロセスやITシステムの統合、人事制度の見直しなど、多くの領域で調整が必要になり、現場に混乱を招くこともあります。
特に文化的な違いやコミュニケーションのズレは摩擦を生む原因となり、従業員の離職にもつながりかねません。子会社化後の安定運営のためには、PMIに対する十分な計画と人的リソースの投入が不可欠です。
買収対象のリスク(簿外債務・風土の違い)を十分に見抜けない可能性がある
子会社化では、事前にデューデリジェンス(企業調査)を行いますが、すべてのリスクを事前に把握するのは困難です。
特に簿外債務や訴訟リスク、企業風土のミスマッチといった「見えないリスク」は、買収後に問題として顕在化することがあります。このようなリスクを低減するためには、専門家による多角的な調査と、買収後のリスク対応策の準備が不可欠です。
買い手企業は、経済的コストだけでなく、目に見えにくい「組織的リスク」にも注目する必要があります。
子会社に対する統制やモニタリング体制の構築が必要になる
子会社化した企業に対しては、親会社としての統制責任が生じます。経営の透明性確保やガバナンス強化のため、定期的なモニタリングが求められます。
例えば、月次レポートの提出義務化や役員の派遣など、ガバナンス体制の整備が必要です。これにはコストと時間がかかるだけでなく、親子会社間の信頼関係構築も大きな課題となります。
ガバナンス体制を軽視すると、グループ全体の信用リスクにも波及するため、慎重な対応が必要です。
売り手企業にとっての子会社化のメリット
売り手企業にとっての子会社化は、単なる経営権の譲渡ではなく、将来的な成長や安定につながる選択でもあります。
後継者問題を解決し企業の存続を図ることができる
中小企業における深刻な課題の一つが「後継者不在」です。M&Aによる子会社化は、これを解決する有効な手段です。
親会社に経営を引き継ぐことで、事業継続の道筋をつけることが可能になります。実際、経営者が高齢化しているものの後継者がいないケースでは、M&Aを通じた第三者への承継が企業の命運を左右する選択肢となっています。
企業としてのブランドや従業員の雇用を守りながら次のステージへ進むことができるため、売り手側にとっても前向きな解決策です。
親会社の資本力を活用して安定経営や成長戦略が描きやすくなる
子会社化により、大手企業のグループに入ることで資金調達の幅が広がり、経営基盤が安定します。これにより、これまで踏み出せなかった新規事業や設備投資にチャレンジしやすくなります。
例えば、ベンチャー企業が大手企業の傘下に入ることで、販路の拡大や信用力向上が実現するケースもあります。親会社の支援を受けながら、自社のビジョンを追求することが可能となるのは、大きな魅力の一つです。
従業員の雇用や取引先との関係を維持しやすくなる
子会社化は、事業の継続性を保つという点で、従業員や取引先に対しても安心感を与える手段となります。特に中小企業では、経営者の交代が企業の存続に直結するため、外部資本の導入による安定経営は大きなメリットです。
また、親会社の信頼性が加わることで、既存の取引関係を維持しやすくなるとともに、新規取引の機会も広がります。M&Aは企業の存続だけでなく、関係者の安心を支える手段でもあるのです。
売り手企業にとっての子会社化のデメリット
一方で、子会社化は売り手企業にとっても一定の制約や課題をもたらします。ここではその代表的なデメリットを見ていきましょう。
経営判断の自由度が大きく制限されるようになる
子会社となることで、親会社の経営方針に従う必要が出てきます。これにより、従来のような独立した意思決定が難しくなるケースがあります。
例えば、新規事業の立ち上げや予算の使い道などにおいて、親会社の承認を得なければならない状況が増えます。その結果、スピード感のある経営や、柔軟な現場対応が難しくなる可能性があります。これを回避するには、子会社化の前に意思決定ルールを明確にすることが重要です。
親会社との意思疎通に時間や調整が必要になる
M&A後は親会社と綿密な連携が求められますが、その分だけ調整に時間がかかることもあります。特に組織の規模や文化が異なる場合、意思疎通における認識のズレが発生しやすくなります。
例えば、報告様式や会議体制の違いによって、業務効率が下がるケースも少なくありません。このような問題を防ぐためには、統合後のコミュニケーション体制を丁寧に整備しておく必要があります。
M&Aによる子会社化の事例
企業成長や事業承継、シナジー創出を目的に実施されるM&Aによる子会社化の動きが各業界で活発化しています。ここでは子会社化の事例を紹介します。
日本精工硝子による三洋化学工業の完全子会社化
2025年2月、日本精工硝子株式会社は、会社分割(吸収分割)の手法により、三洋化学工業株式会社を完全子会社化しました。
日本精工硝子は130年にわたりガラス瓶の製造・販売を手がける老舗企業であり、今回傘下に加わった三洋化学工業は、樹脂容器やキャップ、中栓の製造に加え、化粧品の製造・充填までを行う独自性の高い企業です。
この子会社により、両社の製品を融合させたワンストップ提供体制が整い、顧客対応力の強化やコスト最適化が期待されます。機能性とデザイン性を兼ね備えた容器の供給体制を強化することで、容器・化粧品業界における競争力向上が見込まれる動きです。
【出典】三洋化学工業株式会社「三洋化学工業株式会社グループの完全子会社化について」
三菱地所による日本リージャスホールディングスの子会社化
三菱地所株式会社は2023年2月、株式会社ティーケーピー(TKP)傘下のTKPSPV-9号より、日本リージャスホールディングス株式会社(日本RegusHD)の全株式を取得し、子会社化しました。
日本RegusHDは、世界最大のワークスペースプロバイダーIWGの日本国内パートナーであり、「Regus」「SPACES」などのブランドで全国172拠点を展開しています。
この子会社により三菱地所は、IWGのグローバルネットワークやITインフラを活用し、フレキシブル・ワークスペース領域の事業拡大を図っています。オフィス事業との相乗効果により、ハイブリッドワーク時代の多様なニーズに対応し、新たな働き方の実現を加速する動きといえます。
オリックスによるディーエイチシーの子会社化
オリックス株式会社は2023年1月、化粧品・健康食品メーカーである株式会社ディーエイチシー(DHC)の発行済株式の91.1%を取得し、子会社化しました。
DHCは国内において高い知名度を持ち、化粧品・健康食品市場で広範な顧客基盤と販売チャネルを有する企業です。
この動きは、オリックスが注力するヘルスケア分野におけるネットワーク拡大と、同社の成長戦略の一環として実施されました。創業オーナーの退任に伴う事業承継も目的の一つであり、今後はオリックスの企業価値向上ノウハウを活かし、DHCの持続的成長とガバナンス体制の強化が期待されます。
【出典】オリックス株式会社「株式会社ディーエイチシーの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
博報堂DYホールディングスによるソウルドアウトの子会社化
2022年4月、博報堂DYホールディングスは、デジタルマーケティング支援を行うソウルドアウト株式会社の親会社となり、同社をグループ傘下に迎えました。
ソウルドアウトは中小・ベンチャー企業向けにデジタル広告やマーケティング支援を行い、全国20拠点・社員数400名超と成長を遂げてきた企業です。
今回のM&Aにより、同社は博報堂DYグループの持つ大規模なメディア資源やプロモーション力と融合し、より多角的なマーケティングソリューションの提供が可能になります。地方発の成長支援を掲げるソウルドアウトにとって、全国展開や新たな価値創出を加速させる動きとなりました。
【出典】ソウルドアウト株式会社「拝啓、ソウルドアウトグループを応援してくださる皆さまへ」
まとめ|子会社化のメリット・デメリットを把握し、有効的な活用を
M&Aによる子会社化は、企業の成長戦略や事業承継の選択肢として非常に有効です。株式取得や株式交換などの多様な手法を通じて、買い手企業は新たな資産や市場を獲得でき、売り手企業も経営の安定や継続が可能になります。
ただし、PMIや統制体制の構築、文化の融合といった課題も伴うため、十分な準備と理解が必要です。双方にとって成功となるM&Aを実現するには、メリットとデメリットの両面をしっかりと把握し、長期的な視点で戦略を描くことが重要です。