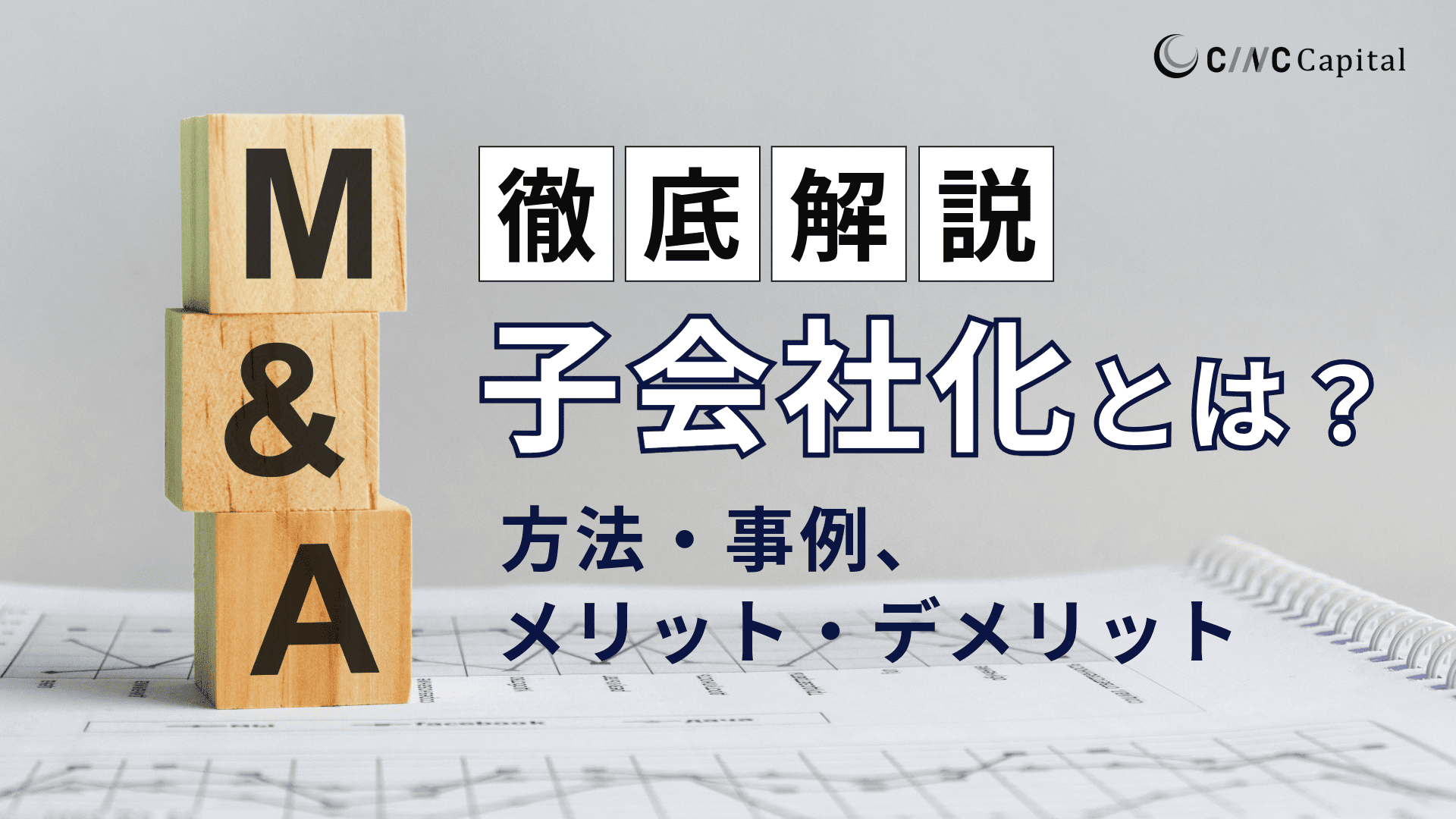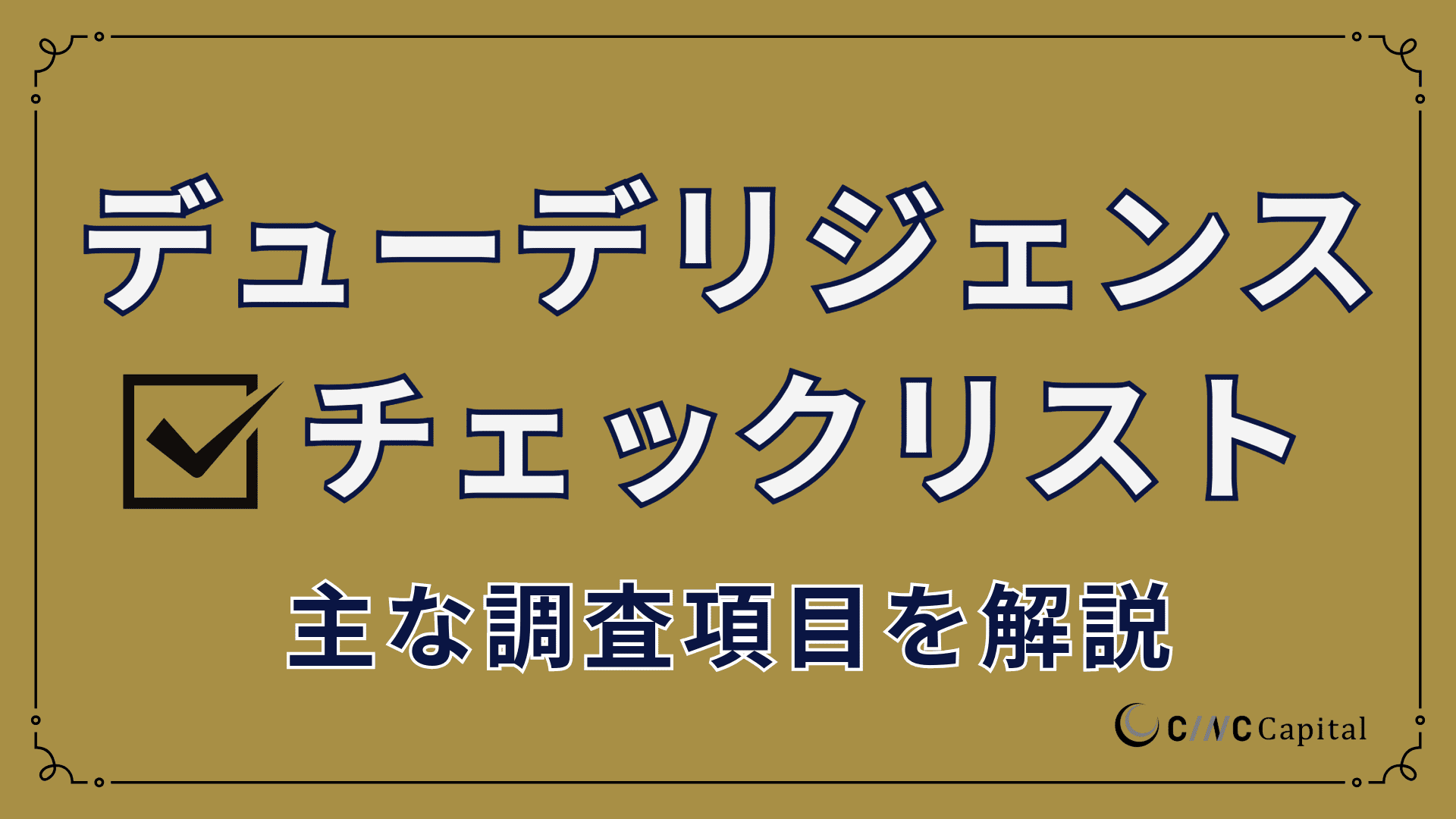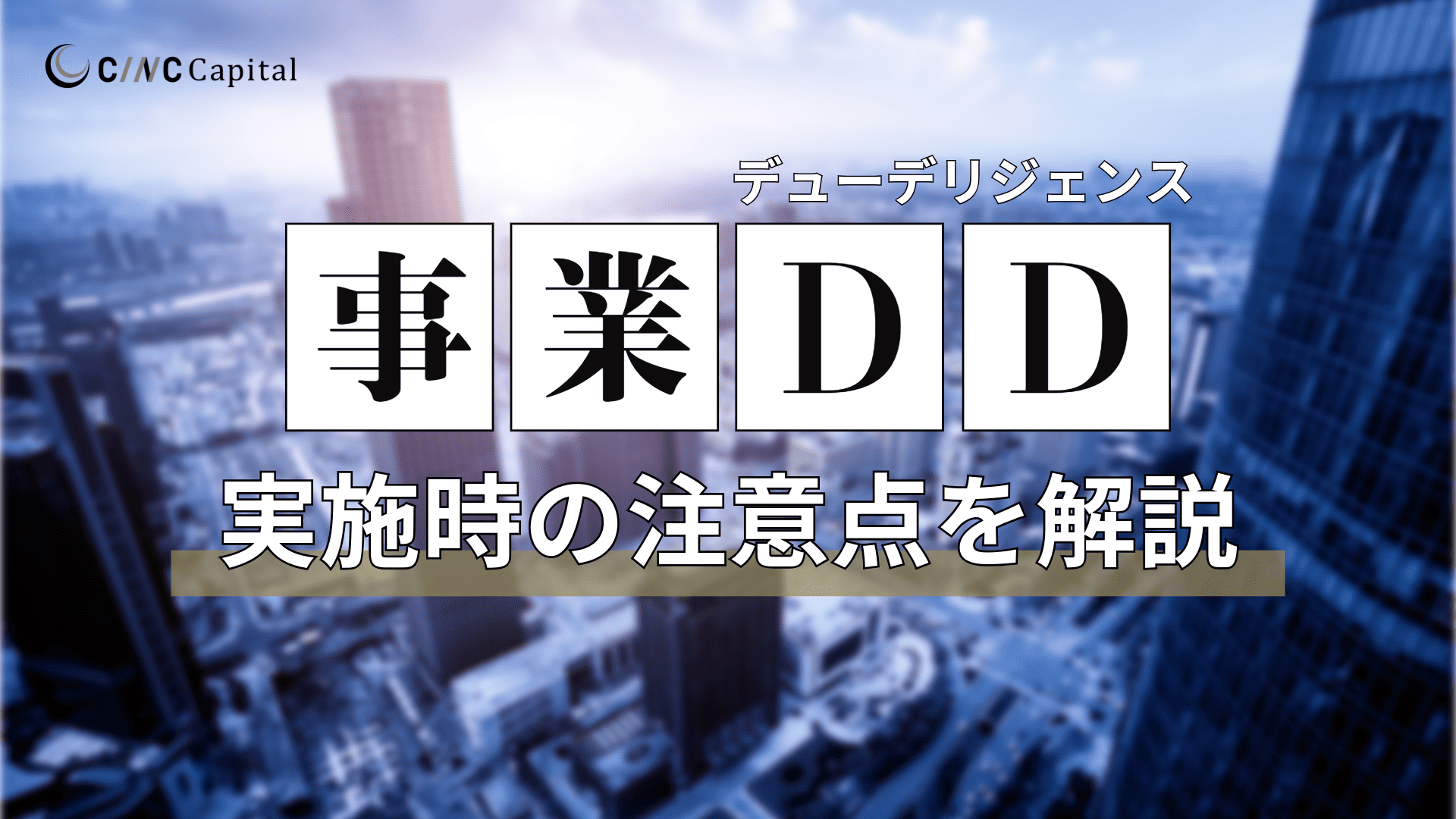CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
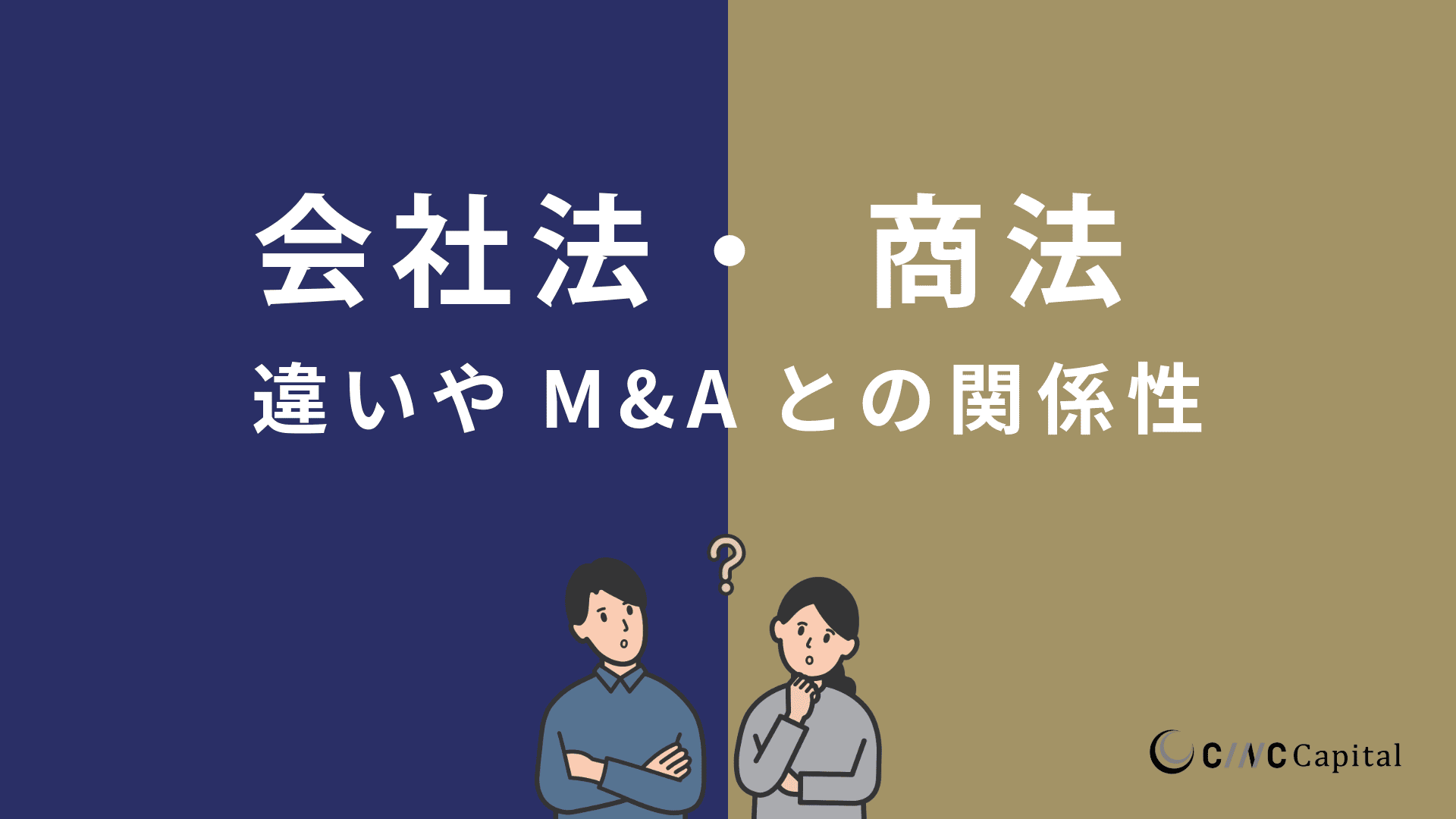
法務 / 法律
- 最終更新日2025.06.26
会社法と商法の違いは?法改正のポイントやM&Aとの関係性を解説
会社法と商法は企業活動に深く関わる基本的な法律であり、会社の運営や商取引を支える大切なルールを定めています。しかし、それぞれの目的や適用範囲がわかりづらく、混同してしまうことも少なくありません。
まずは会社法と商法の概要を理解することで、事業や取引をスムーズに進める基礎を築きましょう。
本記事では、両法の特徴や直近大きな改正となった2019年の会社法改正、同年の商法改正について、それぞれの内容や影響を解説します。さらに会社法と商法がM&Aにどのように関わるか、押さえておくべき要点もわかりやすく紹介します。
目次
会社法とは
会社法は会社の設立や機関設計、運営などを定める法律であり、株式会社をはじめとする会社全般を対象とします。2006年に商法から分離して施行されました。
会社法は、旧商法の中に含まれていた会社に関する部分が独立し、より企業実務に即した形で整備された法律です。例えば株式会社の設立要件や機関設計のあり方などが、時代のニーズに合わせて柔軟に改正されるようになりました。その背景には、現代のビジネス環境がグローバル化やIT化の進展によって大きく変化しており、適切な会社運営のルールを明確に定める必要が高まっていたという事情があります。
会社法では、取締役や監査役、株主総会などの組織体制を定めるだけでなく、意思決定プロセスの透明性や株主の権利保護にも重点が置かれています。これはコーポレート・ガバナンスを強化し、不祥事の予防や企業価値の向上を図る狙いがあります。また、設立資本金の要件を緩和するなど、起業のハードルを下げる規定も盛り込まれており、新たな企業が誕生しやすい環境づくりに寄与しています。
商法とは
商人や商行為に関する総合的な法律で、個人事業主や企業の商業活動全般を規律します。会社法の施行後も、商行為の基本的ルールとして機能し続けています。
商法は、明治時代に制定された旧商法をベースに、長い歴史を経て必要な改正を重ねてきた包括的な法律です。会社法が独立する以前は、商法の一部として会社の設立や管理に関する規定が設けられていました。2006年以降、会社に関する部分は会社法に移管されましたが、商法は依然として商人や商取引に関わる基本的な原則を定めています。
商法の特徴としては、企業だけでなく個人で商業活動を行う場合も対象となる点が挙げられます。例えば商号登記や代理権の範囲など、日常的な取引慣行を支える多くのルールが含まれています。さらに運送や海商といった特殊な取引の規定も含むため、ビジネスや物流を行う上で欠かせない法律となっています。
会社法と商法の違いは?
一見すると似ている両法ですが、目的や対象、具体的に扱う内容が大きく異なります。ここでは、それぞれの法律の違いについて解説します。
目的
会社法は、会社制度を整備して企業活動を円滑化するとともに、取締役会や監査役制度などを通じて適切なコーポレート・ガバナンスを実現することを主な目的としています。
一方、商法は商人や商行為の原則を定めることで、取引全般を支える法的基盤を提供することを目的としています。両者は最終的には健全な商業活動を促進するという共通のゴールを持ちますが、アプローチの切り口が異なるのが特徴です。
対象
会社法は、その名の通り会社組織を対象とし、株式会社をはじめ合名会社・合資会社・合同会社など、さまざまな会社形態に対応しています。商法は個人も含むあらゆる商人を対象としており、商行為を行う者すべてに適用されます。
つまり、企業運営には会社法が密接に関わり、個人事業主も含めた商取引全般には商法が広く関与するという位置付けになっています。
扱う内容
会社法では、会社の設立方法や資本構成、株主総会・取締役会の運営など、会社を運営する上での詳細な規定が整備されています。
商法は売買や運送、保険などの商行為全体に関する基本ルールを定め、個人事業から国際的な商取引に至るまで幅広く適用されるのが特徴です。両方の法律を組み合わせることで、企業の内部統制から外部取引まで網羅的に法整備が行われています。
【2019年】会社法改正による変更点
2019年の会社法改正では、コーポレート・ガバナンス強化や新制度の導入など、企業の実務に直結する内容が盛り込まれました。ここでは、改正による主な変更点について説明します。
株主総会の見直し
2019年改正では、従来よりも迅速かつ透明性の高い株主総会運営を目指すための施策が導入されました。具体的には招集通知の電子提供や議決権行使の電子化など、IT技術を活用した効率化が図られています。株主とのコミュニケーションコストを低減し、多様な株主の意見を吸い上げやすくすることが狙いです。
取締役会の見直し
社外取締役の選任拡大や取締役会の権限規定の明確化を通じて、責任所在をはっきりさせる方向へと変化しました。これにより、経営判断の実効性や客観性が高まり、企業価値の増大を目指す取り組みが一層促進されています。外部からの監督機能を強化することで、不祥事の未然防止にもつながると期待されています。
株式交付制度の導入
会社の組織再編やM&Aの場面で活用できる新たな手法として、株式交付制度が導入されました。株式交付制度は、買収対象会社の株式を取得する際に、買収会社が自社の株式を対価として交付できる制度です。この制度により、現金を用意せずに買収を実行できるため、特に成長中の企業にとって資金調達の負担を軽減できるメリットがあります。
株式交付制度は、株式会社同士の株式移転を柔軟に行えるようにすることで、企業グループの再編や買収時のスキームを多様化させる狙いがあります。市場の変化に合わせた形態の再編が可能になったことで、経営戦略の幅が広がりました。しかし、実務ではまだ活用事例が少なく、今後の普及が期待される段階です。
【2019年】商法改正による変更点
商法は運送や海商なども規定する包括的な法律であり、2019年の改正では運送に関する規定が大きく見直されました。ここでは、主な改正内容を取り上げます。
複合運送の規定新設
海運・陸運・空運など異なる輸送手段を組み合わせる複合運送契約に関する新たな規定が設けられました。これまで曖昧だった契約スキームが法的に整理され、当事者間の責任や費用負担の基準が明確化されたのが特徴です。国際的な物流が増加する現代の実態に即し、リスク軽減を図る意義が大きい改正と言えます。
運送人の責任範囲の見直し
運送過程での事故や損害が発生した場合の運送人の責任がより具体的に示されるようになりました。契約当事者が事前に責任分担を確認できるため、不測の事態に備えやすくなった点が大きなメリットです。企業間取引でのトラブルを減らし、スムーズな荷受け・荷渡しにつなげる狙いがあります。
運送人の責任に関する期間制限
運送終了後に一定の期間を経過すると運送人の責任が制限される規定が導入され、責任期間が明確化されました。これにより、荷主は早期に請求の意思表示を行う必要がある一方、運送人としてもリスク管理を行いやすくなります。迅速なクレーム対応を促進することで、紛争解決もスムーズに進むことが期待されています。
危険物通知義務の明文化
危険物を運送する際には、荷主が運送人にその内容や取り扱い注意点を事前に通知する義務が明文化されました。安全対策や事故防止を徹底するために、責任や連携の明確化を図る狙いがあります。これにより、安全管理意識が高まり、運送事業全体の信頼性向上につながると期待されています。
会社法・商法とM&Aとの関係は?
企業の合併や買収(M&A)においては、会社法や商法の規定が大きく関わります。特に株式の売買契約や組織再編の手続きなどで両法に基づく手続きを踏む必要があります。
M&Aを進める際には、会社法が定める組織再編や株主総会決議の方法をしっかりと理解することが重要です。例えば会社分割や合併スキームを採用する場合、手続きが複雑化しやすいため、取締役会や監査役の承認手続きの流れを把握しておくとスムーズに進行できます。企業買収を含む大規模な再編では、ミスを防ぐために専門家のサポートを受けることも多いです。
一方、商法の視点からは、売買契約や業務提携契約などの基本的なルールを押さえる必要があります。対象となる事業や資産が個人商人に関係する場合や、複数の商行為が絡むケースでも商法の規定が指針を示します。これらの法律を相互にチェックしながら、合併後の運送契約や販売契約などの整合性を取ることが、スムーズな事業統合の鍵となります。
自社がどのような手法でM&Aを進めるのかによって、会社法と商法のどちらが深く関わるのかが変わります。M&Aの手法としては、株式譲渡と事業譲渡が主な選択肢となります。株式譲渡は会社法に基づく手続きが中心となり、事業譲渡は商法および会社法の両方が関係します。特に中小企業のM&Aでは、資産・負債の評価や契約の承継など、商法の観点からの確認が重要になります。
会社法や商法について正しく内容を理解し、法務面でのリスクを回避することで、企業価値向上やシナジーの最大化に直結する戦略的なM&Aが実現しやすくなるでしょう。
会社法や商法に関する専門用語
会社法・商法を正しく理解するためには、それぞれの法律で用いられる専門用語を知っておくことが大切です。基礎知識をしっかりと固めることで、契約書や定款の内容もより的確に把握できるようになるでしょう。
会社法の専門用語
会社法では、会社の組織設計に深くかかわる用語が数多く存在します。特に持分会社の概念や複数の機関設計モデルについては、初心者が混乱しやすいポイントです。代表的な用語を押さえることで、実務対応や専門家とのコミュニケーションを充実させることができます。
社員
会社法における『社員』は一般的な従業員を指す用語ではありません。合名会社や合資会社、合同会社などにおける出資者のことを指し、経営に直接関与する立場として位置づけられます。株式会社の場合は株主がそれに相当しますが、両者の権利義務や責任の範囲には違いがあります。
株式会社
会社法で定める代表的な会社形態であり、株式を発行して資金調達を行う仕組みが特徴です。株主は出資額に応じた権利を持ちながら、通常は経営意思決定には直接携わりません。取締役や監査役などの機関を整備することで、コーポレート・ガバナンスを高める仕組みが整っています。
商法の専門用語
商法では、基本的に商人や商行為に関する用語が数多く登場します。日常の取引から国際的な輸送まで幅広く適用されるため、それぞれの概念を理解しておくとビジネス全体の把握に役立ちます。特に商行為の範囲に含まれる契約や取引形態は多岐にわたるため、自社の業務に当てはまる内容を整理することが重要です。
商人
商人とは、自己の名を用いて営利目的の営業を継続的に行う者を指します。会社だけでなく、個人事業主も含まれるため、商法が広い範囲で適用される背景となっています。名目ではなく実態として営業活動を行っているかどうかが基準として重視されます。
商行為
営利を目的として行われる行為で、売買や運送、保険などが典型的な例です。商法はこれらの行為が公正かつ安全に行われるように規制を設ける役割を担っています。企業活動はもちろん、個人事業主の取引にも適用されるため、幅広いビジネスシーンで重要となる用語です。
まとめ|会社法・商法の違いについて理解し、M&Aの成功に役立てよう
会社法と商法はそれぞれ異なる目的・対象を持ち、企業運営やM&Aに重要な影響を与えます。両方の法律を正しく理解することで、円滑なビジネス展開とリスク回避に役立てましょう。
ビジネス環境が変化し続ける現代において、法理解は企業の持続的成長に直結します。会社法・商法の双方を正しく使いこなすことで、堅実かつ柔軟な企業組織を築き、競争力のあるビジネスを展開していきましょう。