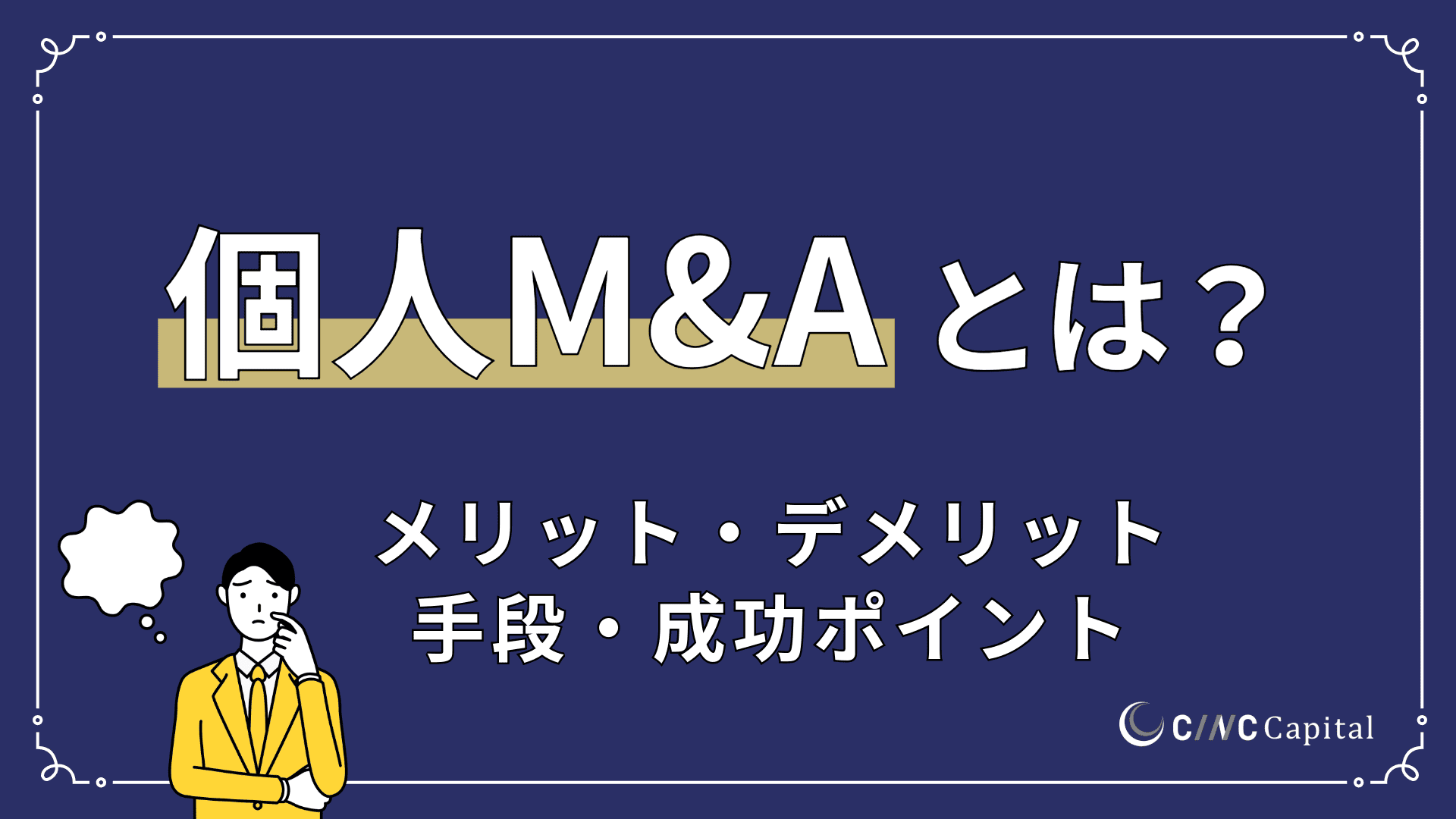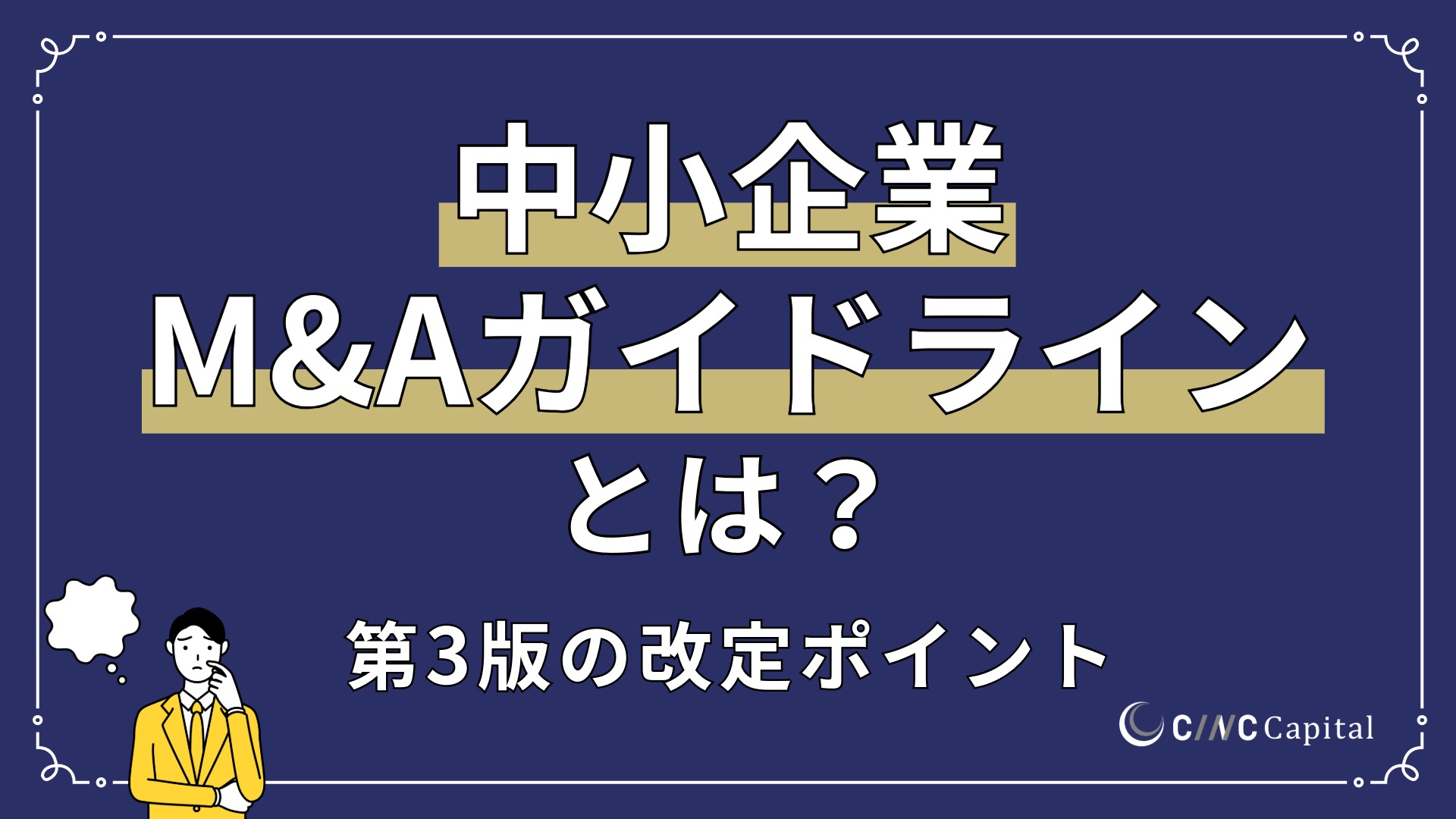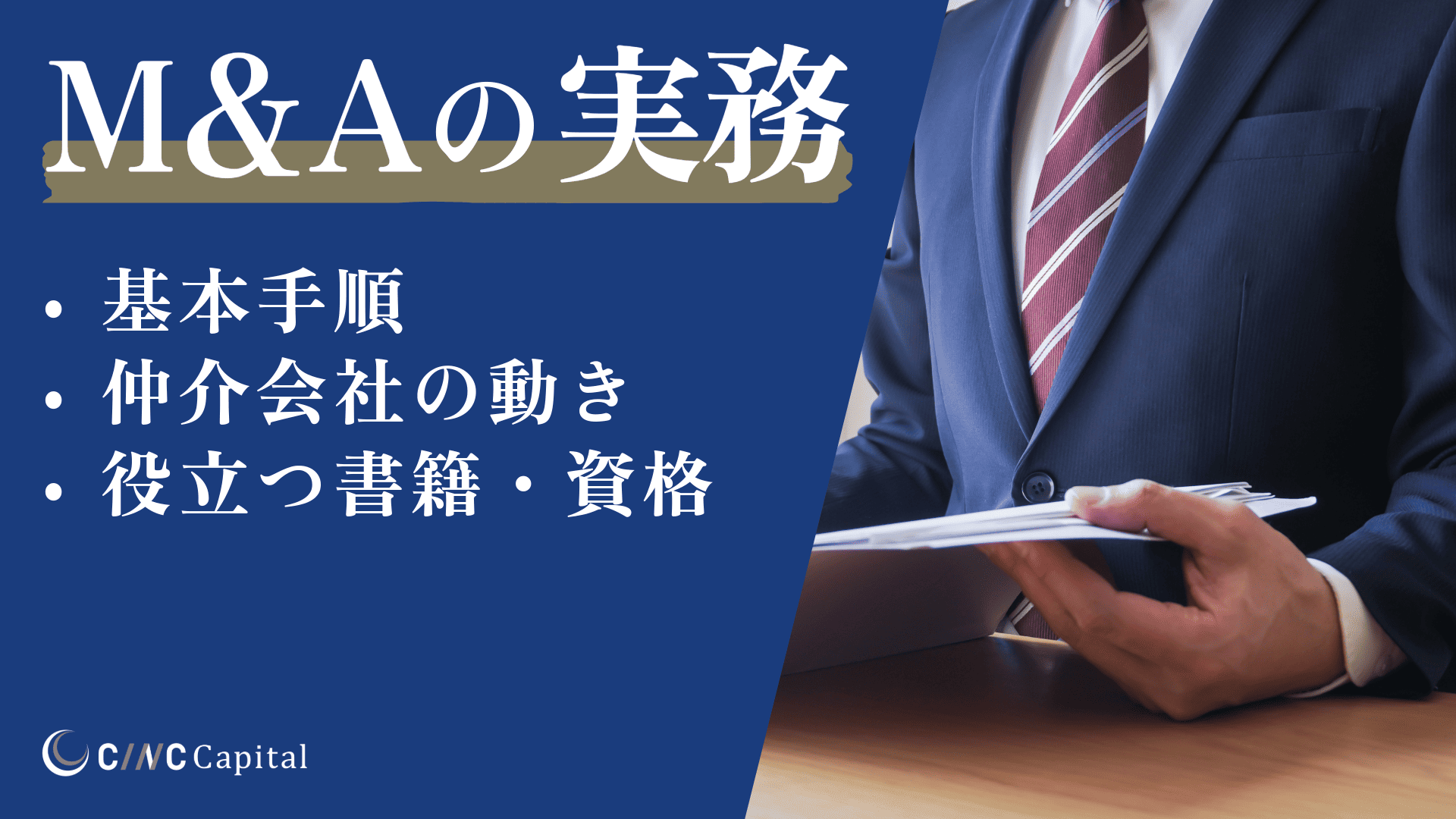CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
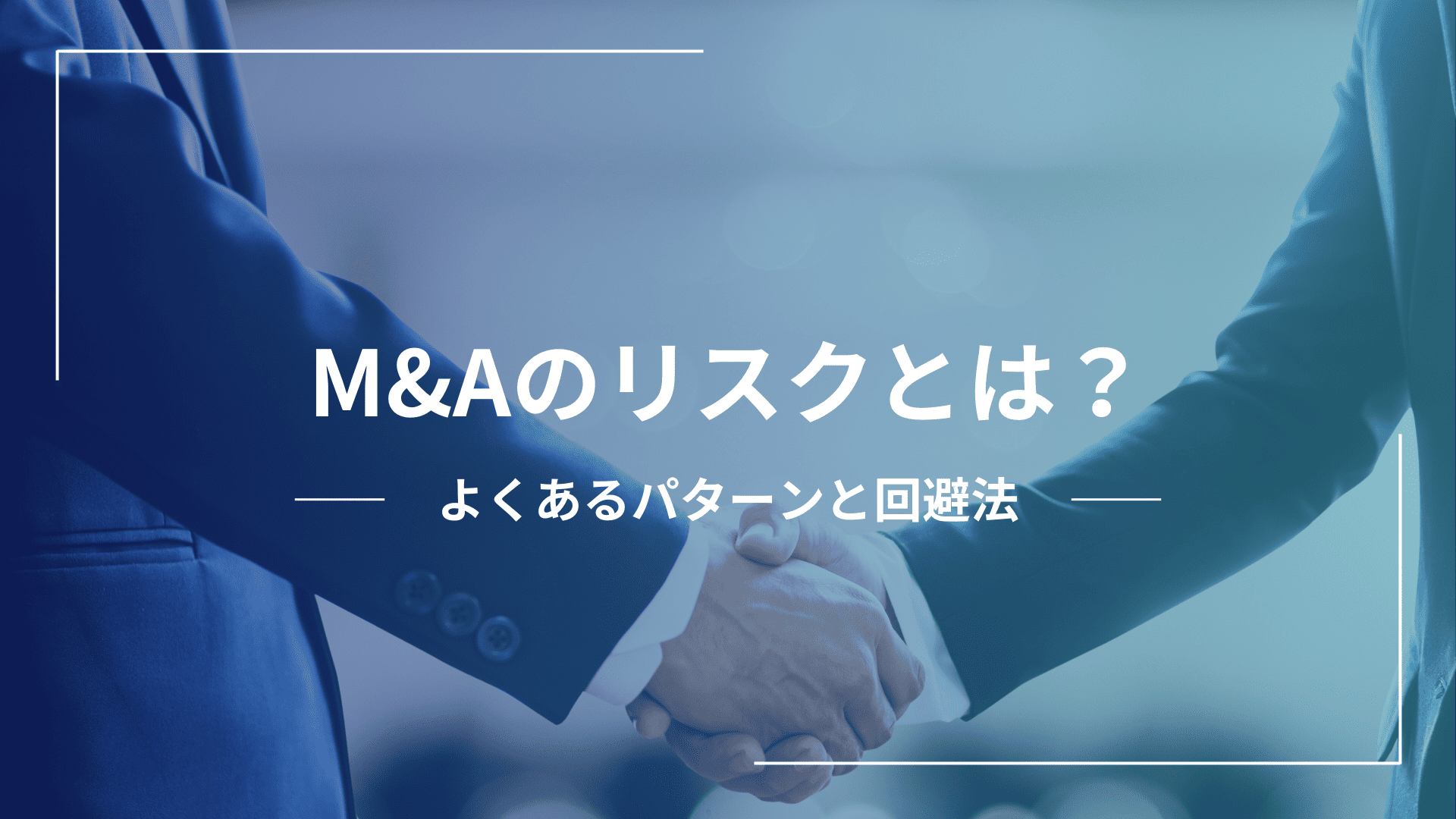
M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.06.26
M&Aのリスクとは?売り手と買い手によくあるリスクと回避する方法を解説
M&Aは、事業の成長や再編、後継者問題の解決といった多くのメリットをもたらす一方で、さまざまなリスクも伴う繊細なプロセスです。財務や法務、人材、経営など、売り手・買い手それぞれが直面する可能性のあるリスクを正しく把握し、適切な対策を講じることが、M&Aの成功を左右するといっても過言ではありません。
本記事では、M&Aにおける代表的なリスクの種類とその具体例をはじめ、トラブル回避のためのマネジメント方法や対策、実際に起きやすい失敗事例までを解説します。
目次
M&Aで起きうる主なリスク
M&Aにはさまざまなリスクが存在します。まずはより理解しやすいようにリスクの種類を4つに分けました。それぞれのリスクが一体どのようなものなのか、説明していきます。
財務リスク
売却される企業が所有する資産の財務面から起こるリスクのこと全般を、財務リスクと言います。
買収した企業に予測していなかった債務があった場合、買収した企業はそれらの債務もそのまま引き継ぎます。つまり、多くの債務があった際は買収後の経営に大きな影響を与えることがあるのです。
具体的な財務リスクの例として、貸借対照表に計上されていない「簿外債務」があります。簿外債務は表面的には見えないため、事前の調査が不十分であった場合には、買収後に突然明らかになることがあります。また、将来的に債務となる可能性がある「偶発債務」の存在も、財務リスクの1つです。
法務リスク
買収される企業が抱えるリスクのうち、法に関係するもの全般を法務リスクと言います。法務リスクの具体例として、契約に関するリスクがあります。これは、売却される側の企業が、経営権が移動した際の対応について契約を結んでいるときに起こり得るリスクです。
もう1つの例として、許認可に関するリスクが挙げられます。許認可や免許などが必要な業務を行う企業を買収する際に起こり得る問題です。もし必要な許認可などが引き継げなかった場合、事業運営に支障が出ることになります。
法務リスクが高い場合、M&Aの実施自体が頓挫してしまう可能性もあります。
経営リスク
買収後の企業経営に関するリスクが、経営リスクです。経営リスクが原因で問題が発生すると、企業の収益だけでなく、社会的イメージを損なうおそれがあり、顧客や取引先の信頼を失う要因にもなりえます。
具体的なリスクの例は、売り手側の企業で残業代の未払いがあったり、ずさんな労働管理が行われていたりするケースなどです。
こうした実態のある企業を買収するのはコンプライアンスの観点からもリスクが高く、敬遠される傾向にあります。
人材リスク
人材リスクとは、従業員や役員が関係するさまざまなリスクのことを指します。異なる組織文化や風土を持つ企業同士が統合する場合、働く従業員に与える影響は大きいです。
例えばM&Aによって労働環境が大きく変わり、従業員によっては将来に対する不安を感じるかもしれません。こうした状態が続くと従業員のモチベーションは低下します。モチベーションの低下を放置していると、最終的には優秀な人材の流出を招くことになるかもしれません。
【売り手側】M&Aのリスク
まずは、売り手側に着目してリスクを分析していきます。M&Aにおいては、売り手側にも複数のリスクが存在します。
こうしたリスクを無視してM&Aを進めようとすると、企業が不利益を被る事態になりかねません。
情報漏洩のおそれ
特にM&Aが成立する前に情報が漏れてしまうと、計画に重大な支障をきたすことになります。
もし社内でM&Aを行うことが広まると、優秀な社員によっては将来の不安から退職を決意してしまう可能性があります。M&A成立後であればフォローが可能ですが、成立前に情報が漏れて退職しまった場合は適切なフォローが難しいです。
また、情報漏洩は単に社内だけの問題にとどまらず、信用問題にも関わってくるため、取引先や買い手企業からの信用を失う可能性があります。最悪の場合、M&Aそのものが中止となってしまうことも考えられます。
買い手がつかず売却できない可能性
どれだけ売却したくても、買い手が見つからないことにはM&Aは成立しません。特に市場のニーズや買い手が求める要件に合致しない場合、なかなか買い手が見つからない可能性があります。
そのため、売り手としては自社の強みを明確に示し、魅力的な提案を行うことが重要です。
また、買い手側が見つかったとしても、条件の面で折り合いがつかず、交渉が破綻するケースもあります。
想定や相場よりも安値での買収
売却のタイミングや業界全体の市場動向によっては、希望額よりも低い額での買収が行われることがあります。条件交渉の余地はあるものの、最終的には買い手側が合意しない限りM&Aは成立しません。
さらに、譲渡価格の相場や適切な売却時期を売り手側が正しく理解していない場合にも、希望額を下回る買収が起こる可能性があります。M&Aについて正しく理解していない状態はリスクが高いといえるでしょう。
買収前に発生した損害賠償責任の負担
売り手側の企業に労務や法務に関するリスクを抱えている場合、M&Aの際にリスクになります。そして、こうしたリスクを解決しないままM&Aが進んで、もしM&A成立後になってリスクが発覚した場合、買い手側から売り手側に対して損害賠償を求められることがあるのです。
損害賠償の額によっては売却額を上回ることも珍しくありません。もしそうなった場合は、売り手側にとって大きな経済的損失をもたらします。
敵対的買収のおそれ
買い手側が売り手側企業の株式の過半数を取得し、経営権を獲得しようとする行為が「敵対的買収」です。買い手側企業は企業を買収する際に、敵対的買収を選択することがあります。
敵対的買収が成立すると、売り手側の従業員や設備などの経営資源すべてが買収側に移ってしまいます。
敵対的買収では売り手側企業の意向は反映されづらく、企業文化や経営方針の変化が生じがちです。その結果、従業員や顧客だけでなく、取引先が離れてしまう事態が起こる可能性もあります。
【買い手側】M&Aのリスク
買い手側にとってM&Aは企業成長や事業拡大の手段として有効ですが、買い手側にはさまざまなリスクが伴います。
特に、適切な調査や準備が不足していると、大きな損失や混乱を招く可能性があります。
財務状況や債務の見落とし
M&Aにおいては、買収先の財務状況を正確に把握することが極めて重要です。なぜなら、帳簿上では健全に見える企業であっても、実際には隠れた債務や偶発債務が存在する可能性があるからです。
例えば、未払いの税金や訴訟リスク、オフバランスのリース債務などが見落とされると、買収後に多額の損失を被るおそれがあります。
このようなリスクを防ぐには、財務デューデリジェンスを専門家に依頼し、キャッシュフローや資産の実在性、債務の全容を徹底的に検証することが求められます。M&Aの初期段階から財務リスクに目を向けることが、長期的な安定経営の鍵となります。
シナジー効果が得られない
M&Aの目的の一つであるシナジー効果が期待どおりに得られないケースは少なくありません。そもそもシナジーとは、単独では得られない経済的価値を、統合によって実現することを意味します。
しかし、実際には経営統合後に部門間の連携が進まず、販路の重複や人材リソースの非効率化が起きることがあります。例えば、販売チャネルが異なり連携が難しい場合、売上拡大のシナリオが崩れてしまいます。
こうしたリスクを回避するには、M&A前に統合後の具体的な事業計画を策定し、実行可能性を多角的に検証することが必要です。シナジーの実現には、期待値ではなく、現実的なシミュレーションが不可欠です。
組織文化の不一致による混乱
企業ごとに異なる組織文化の違いは、M&A後の大きな障害となり得ます。文化的な不一致は、社員のモチベーション低下や離職を招き、組織運営に混乱をもたらすことがあるからです。
特に、トップダウン型の企業とボトムアップ型の企業が統合されると、意思決定のスピードや価値観のギャップが衝突しやすくなります。
買収先の社員が新体制に不満を持ち、キーパーソンの退職につながった事例もあります。このような事態を避けるには、買収前から組織文化の調査を行い、M&A後には双方の文化を尊重する柔軟な統合戦略を実施することが重要です。人材の定着と企業価値の向上には、文化面の調整が不可欠です。
過大な買収価格による経営圧迫
過大な買収価格を支払った結果、企業全体の財務体質が悪化するケースもあります。M&Aでは将来の成長性を見込んで高値で買収することがありますが、過度な楽観的評価が経営を圧迫する要因となり得ます。
収益性の低い事業を高値で買収した結果、のれんの減損処理により多額の損失を計上した企業もあります。こうしたリスクを回避するには、買収価額の妥当性を冷静に評価し、DCF法やマルチプル法など複数の評価手法で検証することが不可欠です。理想的なM&Aは、「高く買わない」ことも重要な戦略の一つといえるでしょう。
知的財産や契約関係の不備
知的財産や契約関係の不備は、買収後に重大な法的トラブルを引き起こす可能性があります。特に、特許や商標の権利が不明確だったり、ライセンス契約に問題がある場合は、買収企業が損害を被ることもあります。
買収後に競合企業とライセンス契約が重複していたことが判明し、損害賠償を請求された事例もあります。このような事態を避けるためには、法務デューデリジェンスを徹底し、知的財産の権利関係や契約内容を詳細に精査することが重要です。法的リスクへの対応は、M&Aの成否を左右する重要な要素です。
M&Aでのリスクマネジメントの基本
M&Aにおけるリスクマネジメントとは、取引に伴う不確実性や損失の可能性を予測・評価し、それを最小限に抑えるための戦略的な管理手法を指します。
リスクを適切に管理することは、取引の成功可否を左右する重要な要素です。特に中小企業においては、人的・資金的リソースに限りがあるため、事前のリスク評価と対応策の策定が欠かせません。
① リスクの洗い出し
M&Aにおけるリスクマネジメントの第一歩は、「リスクの洗い出し」です。例えば、財務リスク、法務リスク、人事リスク、オペレーションリスク、レピュテーション(評判)リスクなど、多岐にわたる要素を網羅的にリストアップすることが重要です。この作業は、売り手と買い手双方が自社の状況を正確に把握するうえでも欠かせません。
② リスクの評価と優先順位づけ
次に行うべきは、「リスクの評価と優先順位づけ」です。すべてのリスクが同じ重みを持つわけではありません。発生確率と影響度の2軸で評価を行い、特に重大な影響を及ぼすリスクから優先的に対策を検討します。
例えば、買収後に簿外債務が発覚した場合、財務的な損失だけでなく経営全体への打撃も想定されます。このようなリスクは特に注意を要します。
③ リスクへの対策の設計と実行
リスクの把握と評価が済んだら、具体的な「対策の設計と実行」に移ります。財務面のリスクにはデューデリジェンスの徹底、法務リスクには契約書の精査や弁護士によるチェック、人事リスクには従業員への十分な説明や条件交渉が必要です。
さらに、想定外の事態に備え、リスク移転(例:保険加入)、リスク回避(契約範囲の制限)などの手段も検討されます。
④ M&A完了後の対応
また、リスクマネジメントは「M&A完了後」にも続きます。統合フェーズ(PMI:ポスト・マージャー・インテグレーション)においては、新体制へのスムーズな移行、人材の流出防止、顧客との関係維持などの課題が浮上します。
この段階でも、発生し得るリスクを事前に予測し、移行計画に盛り込むことが重要です。たとえば、従業員の不安を和らげるために、説明会やFAQの整備、評価制度の明示など、コミュニケーション施策を充実させることが効果的です。
さらに近年では、ESG(環境・社会・ガバナンス)リスクやITセキュリティに関するリスクも重要視されています。M&Aによって新たに加わる事業の社会的責任や、サイバー攻撃の対象となりうる情報資産などに対しても、事前にリスクアセスメントを行い、対策を講じる必要があります。
リスクマネジメントは一度きりの作業ではなく、「継続的に見直し・改善していくプロセス」です。外部環境や事業状況の変化に応じて、柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えておくことで、M&Aの成功確率を高めることができます。
経営陣だけでなく、実務を担う担当者や外部専門家(弁護士、公認会計士、FAなど)との連携を密にしながら、組織全体でリスクマネジメントに取り組む姿勢が求められます。
M&Aのリスクを回避する方法
M&Aのリスクを回避するための方法がいくつかあります。以下、表明保証条項の設定、財務状況の明確化、信頼関係の構築、法令の遵守、買収防衛策の活用、M&Aの専門家への相談について解説します。
財務状況の明確に把握する
財務状況が不透明なままM&Aが進んでしまうと、後々になって思わぬ損害賠償に発展するおそれがあります。こうした事態を防ぐために行うべきなのが財務状況の明確化です。
売り手側の企業が自社の財務状況を調査し、M&Aの際は買い手側企業に対して情報を開示します。特に、簿外債務や偶発債務が存在しないかどうかを調査することが重要です。財務状況が明確されれば、買い手側企業から見た不安点も少なくなり、M&Aもスムーズに進みやすくなります。
相手企業との信頼関係を構築する
M&Aは、売り手側と買い手側の双方にとって大きな取引であるため、信頼関係の構築が不可欠です。互いの信頼がなければ、M&Aはスムーズに進みません。売り手側は、信頼を損なうリスクを避けるために、企業のマイナス面を隠したり、交渉中に不利益となる情報を後出ししたりしないよう努めましょう。
誠実に情報を開示すれば、買い手側との信頼関係を築くことができます。
関連する法令を正しく遵守する
M&Aを進行するにあたって、さまざまな法律を遵守することが重要です。具体的には、会社法や金融商品取引法、独占禁止法、労働契約法など、多岐にわたる法律が関与します。これらの法律は、取引の適法性や透明性を確保するために存在しており、法令を無視することは大きなリスクを伴います。
万が一、法律違反となる行為が明るみに出た場合、訴訟問題へと発展し、最悪の場合、M&Aそのものが取りやめになる可能性があります。
適切な買収防衛策を活用する
売り手側の企業が敵対的買収を防ぐためには、さまざまな買収防衛策を活用することが重要です。買収防衛策とは、敵対する第三者に経営権を取得されないように各種対策を講じることを指します。
買収が行われる前にできる対策として、ポイズンピルや黄金株、ゴールデンパラシュート、MBO(マネジメント・バイアウト)といった手法があります。
しかし、買収防衛策を講じる際には、既存株主が極端な不利益を被らないように注意しなければなりません。手法によっては、逆に既存株主に不利益を与える可能性があるため、慎重に計画を進める必要があります。
M&Aの専門家に相談する
M&Aにおけるリスクを適切に回避するためには、経験や実績、知識が豊富なM&Aの専門家の力を借りることが有効です。専門家のサポートがあれば、企業売却のプロセスをスムーズに進められます。
専門家の知見は、M&Aに関する複雑な法務や財務の問題を解決する手助けをしてくれます。法的な書類の準備や、財務状況の分析といった専門知識を必要とする分野でも、専門家がいれば心強い味方となるでしょう。
さらに、適切な戦略の策定から、買い手との交渉、取引の完了に至るまで、各ステージで的確なアドバイスを提供してくれるので、リスクを最小限に抑えることができます。
M&Aでよくあるトラブル例
M&Aは企業の成長や再編に役立つ手段ですが、適切に進めなければ重大なトラブルを招くことがあります。
最後に、実際に多く見られる代表的なトラブルの原因と対策を解説します。
財務内容の虚偽や誤認によるトラブル
M&Aで最も深刻なトラブルの一つが、財務情報の虚偽や誤認に基づく判断ミスです。買収後に簿外債務や粉飾決算が判明すると、買い手企業に大きな損失が発生し、信頼関係の崩壊や訴訟問題にも発展しかねません。
このようなトラブルは、主に財務デューデリジェンスの不足や表面的な数値だけに依存した判断が原因です。たとえば、売上や利益の水増し、不良在庫の未計上、リースや保証債務の隠蔽などが典型例です。特に中小企業では経理体制が整っていないことが多く、意図的でなくても誤認が発生するケースもあります。
ある中堅企業がM&Aで地方の同業者を買収した際、決算書上は黒字でしたが、実際には未収金の回収不能や架空売上が含まれており、買収後に多額の損失が発覚しました。このような事態を防ぐためには、外部の会計士や専門家による財務調査を徹底することが不可欠です。
M&Aにおいては、見かけ上の数値だけではなく、その裏にある取引の実態や継続可能性まで掘り下げて確認する姿勢が求められます。リスクを回避するためには、丁寧で網羅的なデューデリジェンスが最も効果的です。
従業員や取引先との関係悪化
M&Aによって経営体制が変わると、従業員や取引先との関係性に亀裂が生じるケースが少なくありません。買収に対する不安や不信感から、重要な人材が流出したり、主要な取引先との契約が打ち切られたりするリスクがあります。
関係性のトラブルの多くは、買収に関する情報の開示不足や、ステークホルダーへの説明が不十分であったことに起因します。特に従業員にとっては、雇用条件の変更や評価制度の不透明さが心理的ストレスとなり、離職に繋がることもあります。取引先においては、信用の根拠であった経営者が変わることで取引を見直すケースもあります。
あるIT企業が小規模な開発会社を買収した際、社員への十分な説明がなされず、多くのエンジニアが退職。さらに、既存の取引先が契約を解除し、買収後の事業継続に支障をきたしました。このような混乱を避けるには、事前の社内外への丁寧な説明と信頼構築が重要です。
M&Aは経営陣同士の合意だけで成立するものではなく、現場の理解と協力が不可欠です。情報の共有とコミュニケーションを通じて関係者の不安を払拭し、協力体制を構築することが成功の鍵となります。
契約条件の認識違いや解釈のズレ
M&Aにおける契約書は複雑で、専門用語や条件が多数含まれるため、売り手と買い手の間で契約内容の認識にズレが生じることがあります。このズレが原因で、買収後に「言った・言わない」のトラブルや追加請求、責任の押し付け合いなどが発生することがあります。
契約内容の不明確さや、重要条項の説明不足が背景にあります。表明保証(Warranties & Representations)や補償条項(Indemnification)など、実務上重要な条項を正しく理解しないまま契約締結してしまうと、後々の責任問題に発展する可能性があります。
実際に、買収後に旧経営者の責任範囲に関する解釈が食い違い、損害補填の範囲を巡って訴訟に至った事例もあります。このような問題は、事前に契約の内容を専門家とともに綿密に確認し、双方で文言の理解をすり合わせることで防止可能です。
M&A契約は専門性が高いため、経験豊富な弁護士やアドバイザーの関与が不可欠です。
すべての条項について合意形成を図り、後のトラブルを未然に防ぐためにも、契約内容の透明性と合意の明確化を徹底する必要があります。
まとめ丨リスクを正しく理解してM&Aを成功させよう
M&Aは決して「リスクのない取引」ではありませんが、適切なマネジメントを行えば、リスクをコントロールして成功へ導くことが可能です。
そのためには表面的な問題だけでなく、潜在的な課題にも目を向けることが重要です。実践的かつ総合的なリスク対策を講じ、財務・法務・人材・経営などの観点から継続的にリスクを見直すことで、M&Aの成果を最大化できるでしょう。
そして、M&Aは専門家への相談が非常に有効です。複雑な手続きや専門的な知識が必要になる場面では、専門家のアドバイスにより、リスクを軽減しスムーズな進行を図ることができます。
まず自社の状況や目的に適した相談先を見つけることが重要です。相談先にはさまざまな選択肢がありますが、適切なパートナーを選び出すことで、スムーズに、利益を最適化した売却を実現できます。