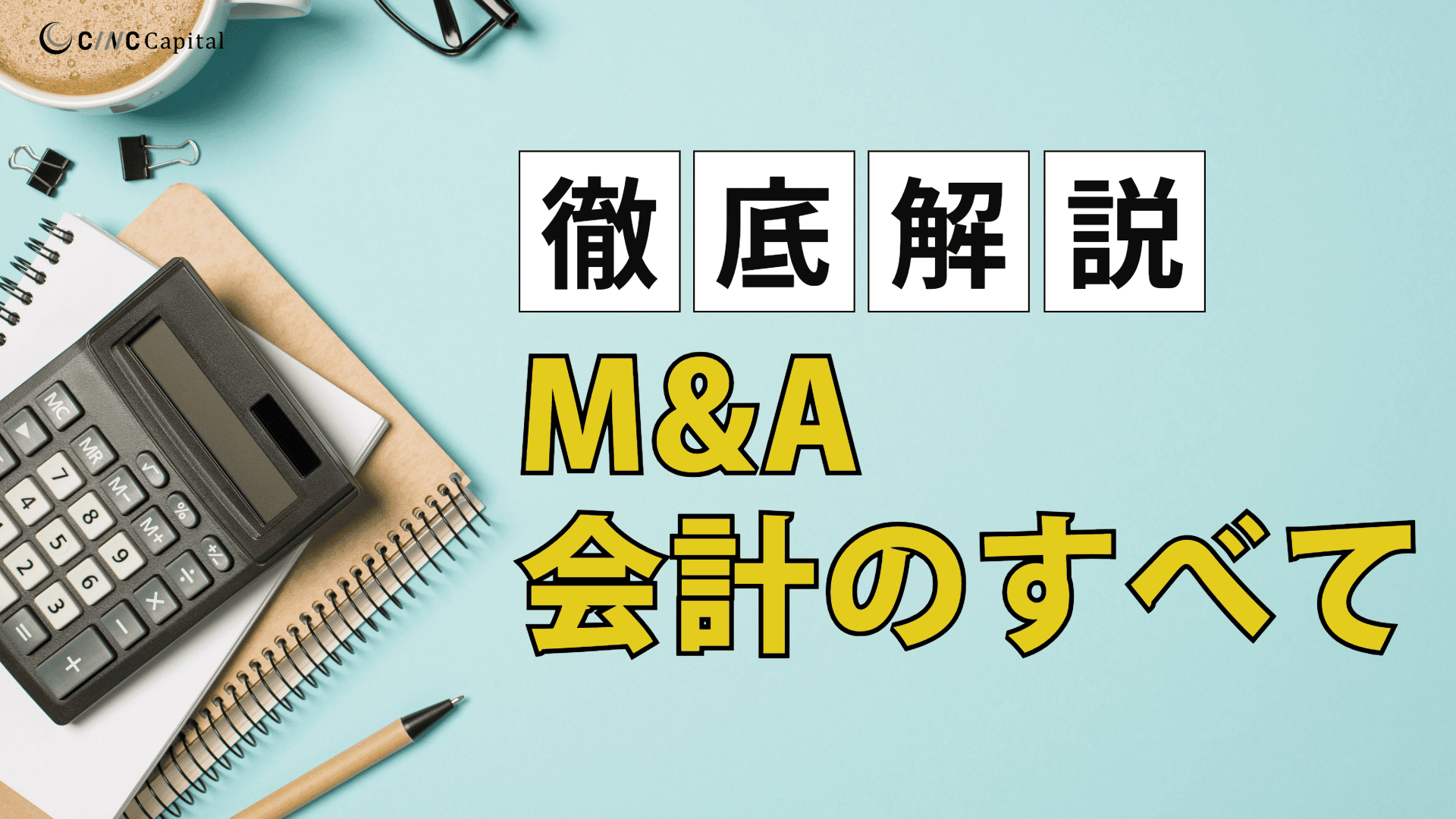CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
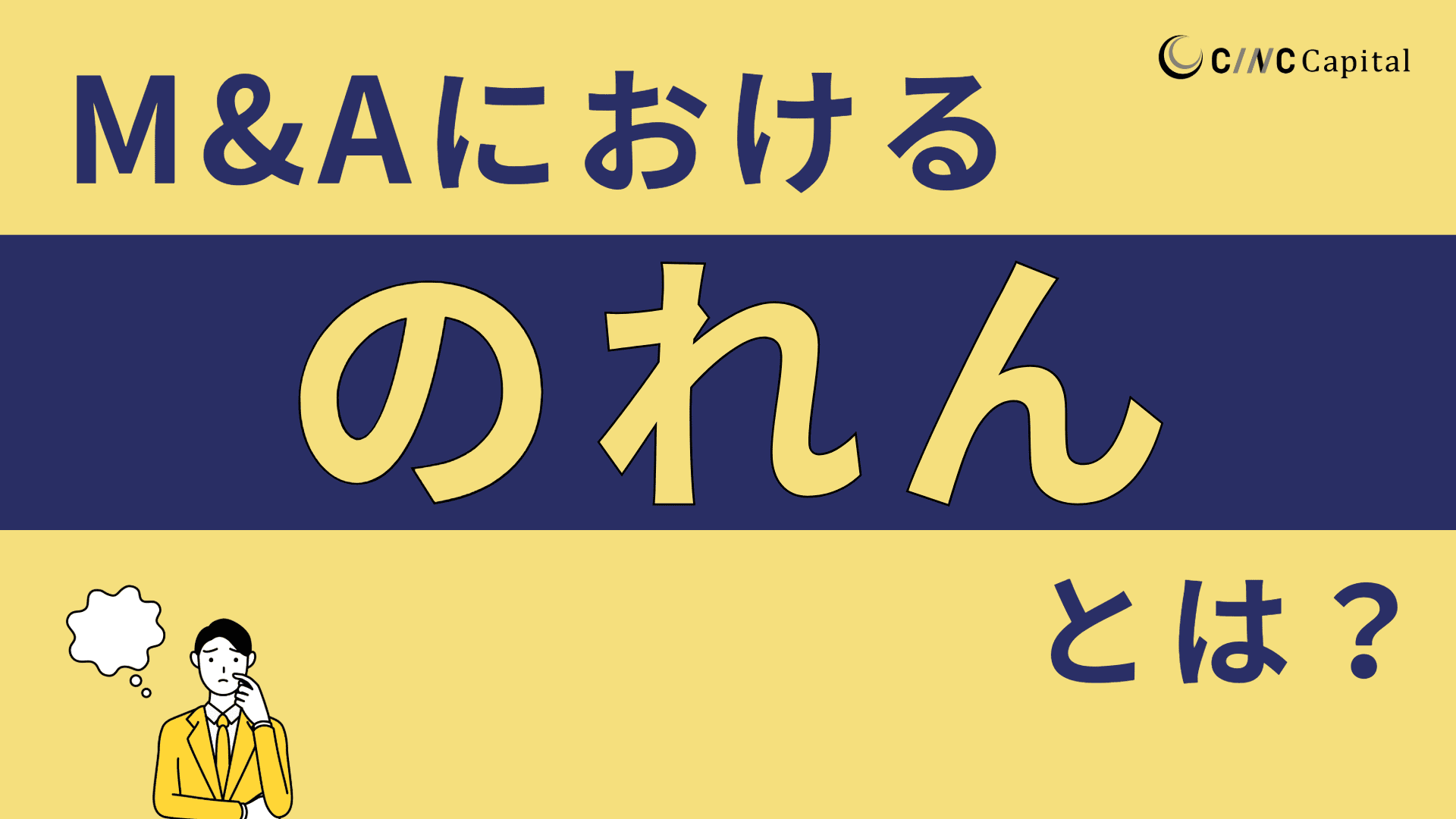
会計
- 最終更新日2025.06.26
M&Aにおける「のれん」とは?意味や計算方法、押さえておきたいポイントを解説
M&A(企業の買収・合併)を実施する際、売り手側・買い手側ともに知っておきたい用語の一つが「のれん」です。売り手側にとっては価格交渉の重要な要素となり、買い手側にとってはM&A後の会計処理などにも関わってきます。
M&Aの失敗を避けるためにも、のれんの基礎知識について確かめておきましょう。
この記事では、のれんの持つ意味や種類、計算方法などをご紹介します。
目次
M&Aにおける「のれん」とは?
M&Aにおける「のれん」とは、買収価格が被買収企業の純資産を上回る部分を指し、ブランド力や顧客基盤、技術力など目に見えない価値を表します。会計上は資産として計上されます。これは、企業の持つブランド力や将来的な収益力、顧客基盤といった目に見えない価値を反映するものです。
「のれん」という言葉は、飲食店や商店の入り口に下げられている「暖簾(のれん)」が元になっているといわれています。転じて、企業のブランド力や顧客基盤、独自の技術力など、帳簿には直接記載されない無形資産を指すようになりました。「のれん」と同じ意味で、「超過収益力」という言葉も使われます。
のれんが発生する理由
のれんが発生する主な理由は、企業の持つ「目に見えない価値」が買収価格に反映されるためです。例えば、以下のような要素がのれんの価値に影響を与えます。
- ブランド力
- 顧客基盤
- 技術力や特許
- 優秀な人材や組織文化 など
上記の要素が優れているほどのれん代の金額が大きくなり、収益力が高くなるといえます。ただ、すべての企業に「正ののれん」が発生するとは限りません。買収金額が純資産額を下回ってしまう場合、「負ののれん」が生じます。
負ののれんによって対価の金額が低くなる点に注意が必要です。売り手側は、企業価値が適正に評価されなかった可能性も考慮し、慎重に対応することが求められるでしょう。
のれんの種類
通常、のれんは「会計上ののれん」と「税務上ののれん」に大別され、それぞれ扱いが異なります。会計上ののれんは企業価値を表す無形資産として計上され、減損処理や償却が行われます。一方、税務上ののれんは「資産調整勘定」や「負債調整勘定」として処理され、会計上とは異なるルールが適用されます。
のれんには複数の種類があるため、混同しないように違いを把握しておくことが重要です。それぞれの詳しい内容については後述します。
のれんの計算方法
一般的に、のれんは以下の計算式によって算出されます。
買収価額-売り手企業の時価純資産額
買収価額を求める方法には「コスト・アプローチ」「マーケット・アプローチ」「インカム・アプローチ」などの種類があります。いずれの方法も専門的な知識をもとに企業価値を算出する点に留意が必要です。適切な数値を割り出すためには専門知識を持つ人材に依頼するのが望ましいでしょう。
【のれんの種類】会計上ののれん
ここからは、のれんの主な種類についてご紹介します。以下では、会計上ののれんについて詳しく解説します。
会計基準ののれん
のれんの扱いは、どの会計基準を採用しているかによって異なる場合があります。日本でM&Aを実施する場合、日本会計基準か国際会計基準かによる違いが見られるでしょう。
日本会計基準ののれん
「日本会計基準ののれん」と「国際会計基準ののれん」で会計処理が異なります。日本の会計基準をもとにのれんを処理する場合、毎期償却を実施することが特徴です。所定の期間中、のれん償却が規則的に行われるため、予算の見通しを立てやすいメリットがあります。
一方で、超過収益力が徐々に償却されることで、企業利益に負の影響を与える点はデメリットといえます。
国際会計基準ののれん
国際会計基準とは、国際会計基準審議会によって定められた、全世界共通で適用される会計基準のことです。「International Financial Reporting Standards」を略して「IFRS」とも呼ばれます。日本企業のなかにも、国際会計基準を採用しているところが見られます。
日本会計基準との大きな違いは、のれん償却に関する部分です。国際会計基準を採用している場合、毎期の償却は実施しません。減損処理は明らかにのれんの価値が低くなったときに行われます。
また、日本の基準では減損の兆候が見られたときに減損テストを行います。国際会計基準では、毎年減損テストを実施しなければいけません。利益にマイナスの影響が生じにくいものの、定期的に減損テストを実施する必要があり、負担が増えてしまう点に注意が必要です。
財務諸表ののれん
組織再編で選択されたスキームに応じて、財務諸表におけるのれんの扱いが変わることがあります。取り扱いの違いを確認しておきましょう。
個別財務諸表ののれん
会社単体での決算書を「個別財務諸表」と呼びます。M&Aの手法で株式譲渡を選択した場合、個別財務諸表上ではのれんが計上されないことが基本です。中小企業におけるM&Aは株式譲渡が実施されるケースも珍しくありません。その際、M&Aの対価は子会社株式の形で計上されます。
連結財務諸表ののれん
支配・従属関係にある複数企業の集団を一つの組織としてみなして作成する決算書を「連結財務諸表」と呼びます。グループ会社それぞれの個別財務諸表を集計し、調整した上で全体の財務情報を記載したものは連結財務諸表に該当します。
例えば、株式合併によって吸収された場合、買い手側の個別財務諸表にのれんとして計上されます。さらに、連結財務諸表が作られている場合は、同額が計上されます。
【のれんの種類】税務上ののれん
会計上でのれんとして計上した金額については、税務上では「資産調整勘定」や「負債調整勘定」として扱います。それぞれの違いを見ていきましょう。
資産調整勘定ののれん
対価が純資産額を上回る場合、「資産調整勘定」として計上されます。会計上ののれんから営業権を控除し、資産調整勘定を算定します。
税務上ののれんは、M&Aスキームによっては発生しないことがあります。株式譲渡や適格要件を満たした組織再編の場合、資産調整勘定は生じません。適格要件を満たさないケースでは資産調整勘定が発生します。
負債調整勘定ののれん
対価が純資産額を下回る場合は、税務上の負ののれんである「負債調整勘定」として扱われます。「退職給与負債調整勘定」「差額負債調整勘定」「短期重要負債調整勘定」の3種類に分けられます。
のれんの償却と減損
M&Aの結果に応じて、のれんの償却を行うか、減損を行うかの違いが出てきます。M&Aが失敗した場合は、のれんの減損処理を実施することになるでしょう。
のれんの償却
日本の会計基準に則って処理する場合、のれんを資産計上して償却を行います。償却期間は20年以内と定められていますが、実際の期間は投資した金額の回収期間に応じて変動します。また、期間中の償却金額は一定です。
のれんの減損
M&Aの実施後、のれんの価値が失われてしまい、投資した分を回収できないときは、償却ではなく減損処理を実施しなければいけません。帳簿上の価値を回収可能な範囲に下げる必要があります。
のれんの価値が下がる理由はさまざまです。例えば、経営統合が思うようにいかず業績が悪化した、対価を高く見積もりすぎたといった理由が考えられるでしょう。期待を下回る結果とならないよう、入念な計画と準備を行った上でM&Aを実施することが求められます。
まとめ|「のれん」を正しく理解し、M&Aを成功させましょう
のれん代はM&Aの買収価額に大きく関わります。適切な方法で価値を算定し、反映させることが大切です。のれんの計算方法や扱いなど、詳しいことを知りたいときは専門家の力を借りることが推奨されます。M&Aについて知見の深いアドバイザーへ相談し、のれんの価値を正しく見極めましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。