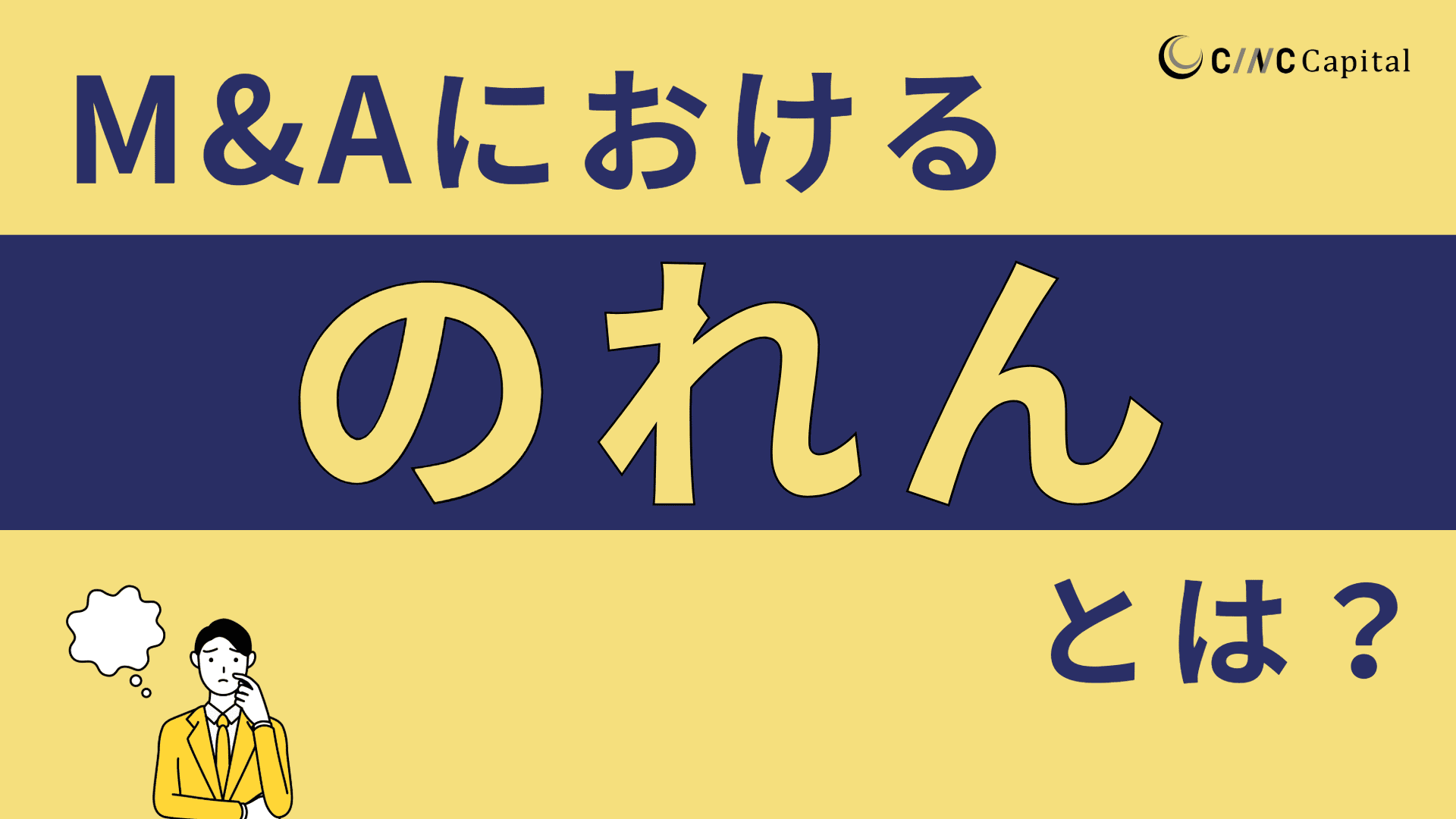CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
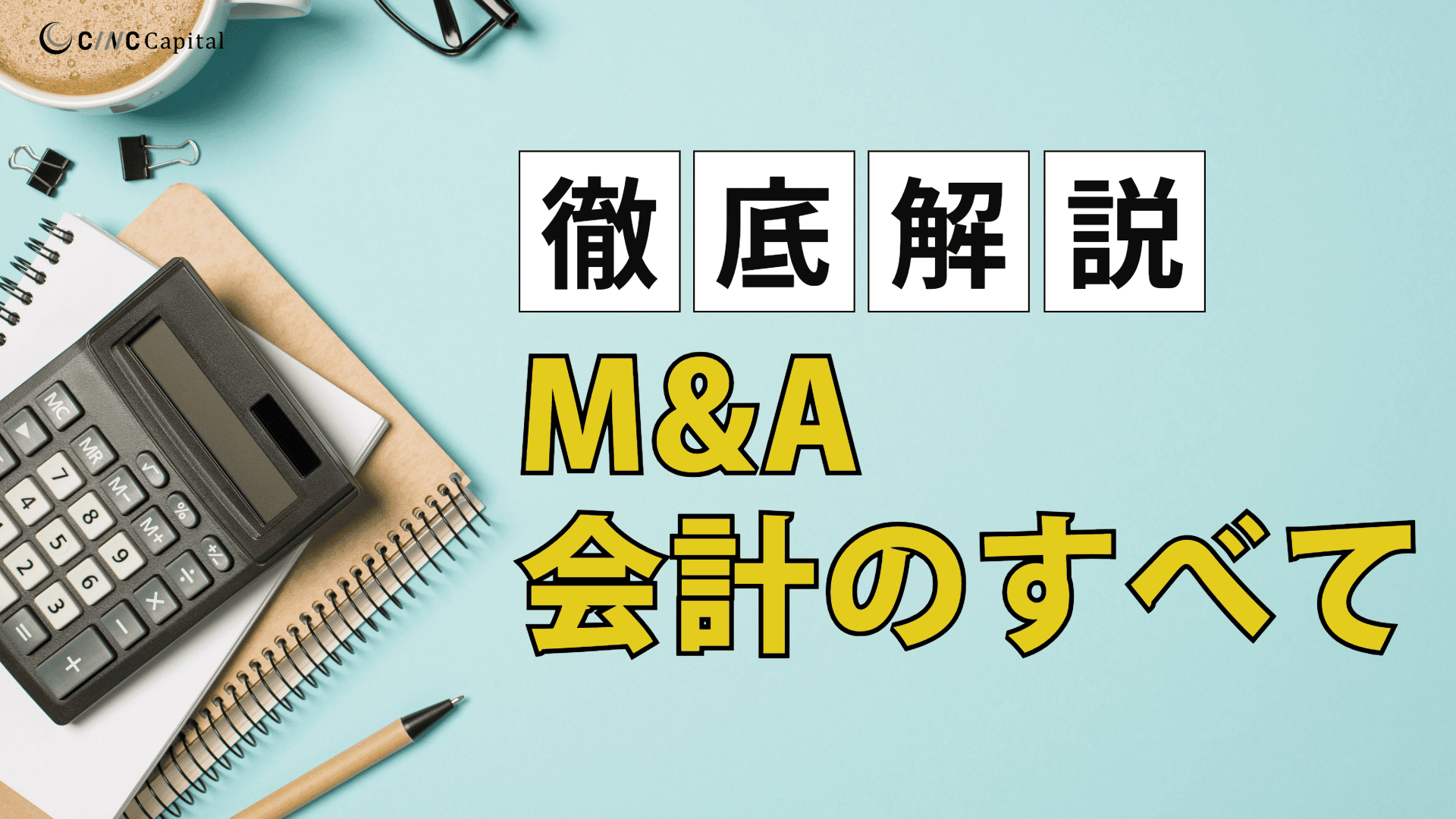
会計
- 最終更新日2025.06.26
M&Aにおける会計処理の概要|会計の種類や手法ごとの解説
M&Aを実施する際、売り手・買い手ともに特別な会計処理が必要になるケースがあります。選択したスキームに応じて処理方法が変わることもあるため、注意しておきましょう。
この記事では、M&Aにおける会計の種類や会計基準、手法別の会計処理などについてご紹介します。
目次
M&Aにおける会計
M&Aの会計処理を行う際は、「財務会計」と「税務会計」の2種類について把握しておく必要があります。それぞれの特徴を確かめてみましょう。
財務会計
財務会計とは、企業のステークホルダーに対する財務状況や経営状況などの報告を目的とした会計を指します。報告対象となる企業が単体の場合は個別会計、グループの場合は連結会計を行います。
個別会計
企業単体の財務状況については個別会計にて報告されます。M&Aの際に企業単体の価値を判断する場合も、個別財務諸表が判断材料となります。また、M&A後も個別会計の内容が指標となり、会計処理されるのが基本です。
連結会計
企業単体ではなく、関連会社や子会社も含めて一つのグループとみなし、連結財務諸表を作成して全体の財務状況を報告するのが連結会計です。グループに所属せず、単独で経営を行う企業は個別会計を実施することになります。
連結会計を行う企業の場合でも子会社ごとの会計は個別となり、単体での決算書が作成されます。ただし、個別会計上は認められるものの、連結会計上では消去される会計処理もあります。
税務会計
税務会計とは、税金の計算を適切に実施するのが目的の会計のことです。財務会計は後述する各種会計基準にて処理を行いますが、税務会計では法人税法などに基づいて課税所得額を割り出します。そのため、財務会計と金額や記載内容などが一致するとは限りません。
また、正しく税額を計算するためには税制改正に対応していく必要があります。会計ソフトのような自動化ツールや専門家の力を借りながら適切に対処することが求められます。
M&Aの会計基準
財務諸表は一定のルールに基づいて作成しなくてはいけません。M&Aに関連する会計処理は、主に「日本会計基準」「国際財務報告基準(IFRS)」「米国会計基準」のいずれかの基準が適用されます。それぞれの違いを見ていきましょう。
日本会計基準
日本独自の会計基準です。基本的には1949年に定められた「企業会計原則」に基づいた内容ですが、時代の流れに合わせて改正が行われてきました。企業会計原則は「一般原則」「損益計算書原則」「貸借対照表原則」などから構成されています。
国際財務報告基準(IFRS)
国際会計基準審議会によって定められた基準です。世界各国で採用されているため、海外展開している企業はこちらの基準に基づいて会計処理するケースが見られます。企業のグローバル化が進むと同時に、日本基準ではなく国際財務報告基準を採用するパターンも見られるようです。
米国会計基準
アメリカ国内の企業が採用している会計基準です。日本企業でも、アメリカに上場している場合はこちらの基準を適用できます。
上記の会計処理で、M&Aにおいてもっともわかりやすい違いが「のれん」に関する部分です。のれんとは、買収対象となる企業の純資産額と、買収価格の差額を表すものです。企業の持つブランドや顧客基盤、人材などの無形資産が持つ価値は、のれんとして計上されます。
日本基準の場合、20年以内にのれんを定期償却することになります。収益力が下がり、投資金額の回収不可と判断された場合は減損処理を行い、のれんの価値を下方修正します。
対して、国際財務報告基準や米国会計基準では減損テストを毎期行いますが、定期償却は実施しません。のれんの価値が著しく下がった際に減損処理を行います。企業の採用する会計基準によってのれんの扱いが変わる点に留意しておきましょう。
M&Aの手法ごとの会計処理
選択したM&Aスキームによって、会計処理の方法が異なる場合があります。手法別の基本的な会計処理のポイントを押さえておきましょう。
株式譲渡
株式譲渡はM&Aにおいてよく見られる手法の一つです。売り手側が保有する株式を買い手側へ譲渡し、経営権を受け渡します。
売り手側は、対価と株式の帳簿価額に差がある場合、売却損益として計上します。買い手側は、売り手企業へ支払った対価の金額を取得原価として計上します。連結財務諸表では、取得原価が純資産の時価を超える場合にのれんが生じる点を押さえておきましょう。
株式交換
株式交換は、買い手と売り手の間で株式を交換するM&A手法です。企業同士が完全親会社・完全子会社の関係になります。対価は株式が用いられるため、現金の授受は行われません。
通常、売り手側の株主と買い手企業が直接取引をすることになります。売り手企業は株式保有者が変わるだけなので、個別会計上では特別に処理されることがありません。
基本的に、会計処理を行うのは親会社となる買い手側で、取得した株式を計上します。また、自社株式の発行による増資が発生するため、資本金および資本剰余金の計上が必要です。
株式移転
株式移転とは、単独または複数の株式会社が持つ発行済株式を、新設する株式会社に取得させるM&A手法です。新設された企業が親会社となります。
株式移転の場合、基本的に子会社となる企業は会計処理を行う必要はありません。親会社の個別財務諸表では、実質的な取得企業の株式を簿価で、その他の被取得企業の株式を時価で計上します。
連結財務諸表では、被取得企業の資産や負債を時価で評価し、のれんが生じる場合は計上します。株式移転により取得した株式と被取得企業の純資産は相殺されます。
事業譲渡
事業譲渡とは、売り手側の事業の一部もしくは全部を、買い手側へ譲渡するM&Aのことです。売り手側に経営権を残すことができるため、企業を存続しながら不採算事業を手放したい場合などに向いています。
売り手側は、譲渡する事業の資産や負債を帳簿から消去します。対価と資産・負債の差額は移転損益として計上することになります。
買い手側では差額をのれんとして計上します。また、売り手・買い手間に資本関係が存在しない場合、通常は連結会計での処理は必要ありません。
合併
合併とは、複数の企業を一つに統合するM&A手法です。新しい会社を設立する「新設合併」や、一つの企業がその他の企業を統合する「吸収合併」などの方法があります。
売り手企業は法人格がなくなるため、特別に会計処理を行う必要はありません。合併の前に個別会計で財務諸表を作成しておきます。
買い手企業は、売り手企業の時価評価を行います。資産や負債の時価評価と対価に生じた差額はのれんとして計上します。
会社分割
会社分割は、事業の一部もしくは全部を承継するM&A手法です。事業譲渡と混同されることがありますが、会社分割は権利義務の包括承継が可能で、事業譲渡は個別承継となる点が異なります。
売り手企業は、事業を分割して受け渡した対価を株式として取得します。分割の対象となる資産や負債などは、帳簿価額で受け渡されます。
買い手側は、売り手企業の資産や負債を受け継ぐために自社株式を発行します。会計処理は、個別会計および連結会計の両方で考慮されます。
第三者割当増資
第三者割当増資は、第三者に特定の株式を割り当てて発行し、資金調達する手法です。買い手となる第三者企業が議決権の過半数を取得した場合、親会社となります。
売り手企業は、発行した株式の対価となる出資金を受け取り、資本金に組み入れることができます。買い手側については株式取得を仕訳に計上します。特別な会計処理は行いません。
まとめ|会計処理を正しく理解し、M&Aを成功させましょう
会計処理の方法は、採用している会計基準やM&A手法などに応じて変わってきます。自社のやり方に応じて適切な処理を実施することが重要です。M&Aを成功させるためには、検討段階から会計処理について理解しておくことが求められます。専門家のサポートを受けながら、M&Aの準備を進めていきましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。