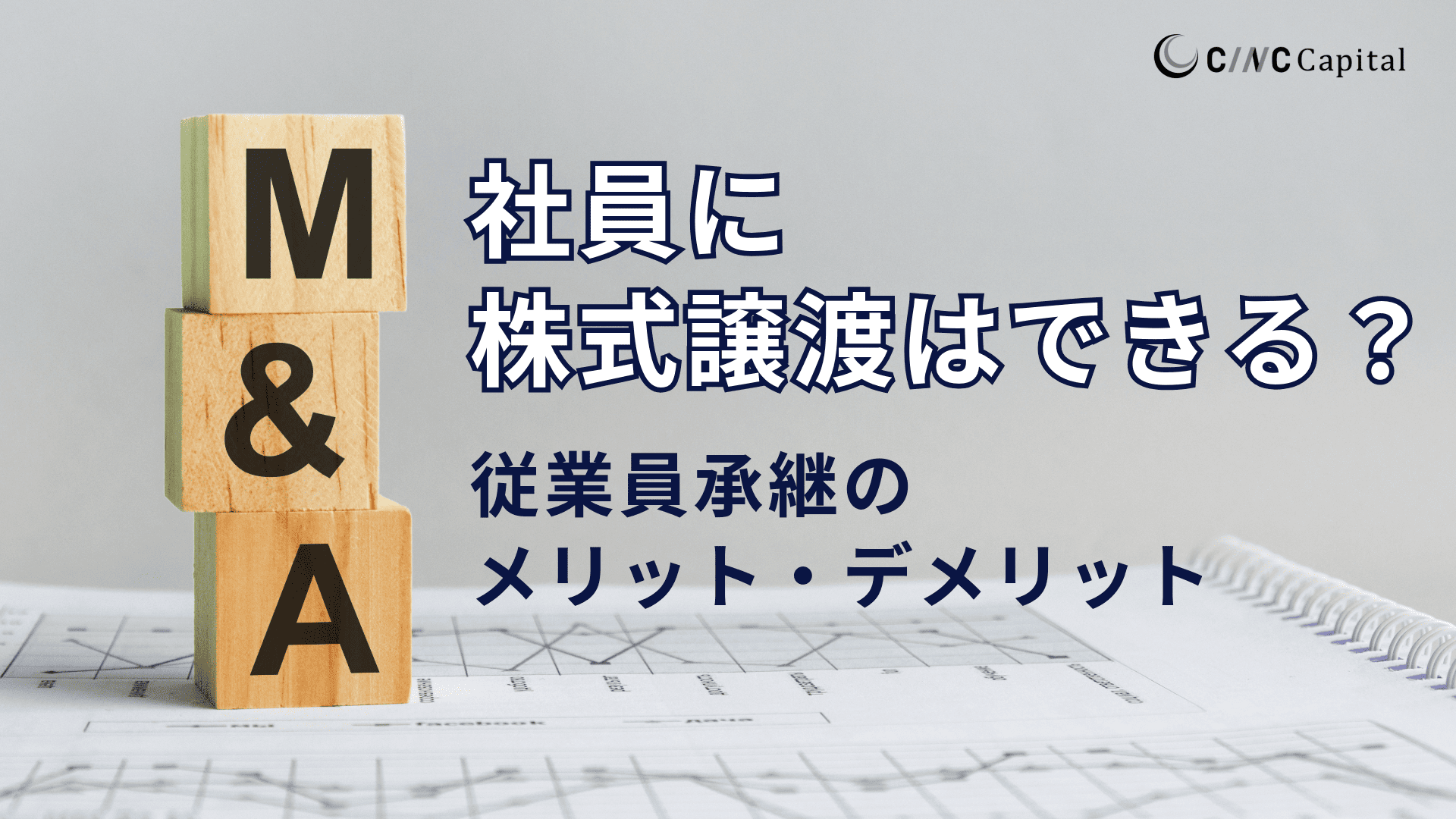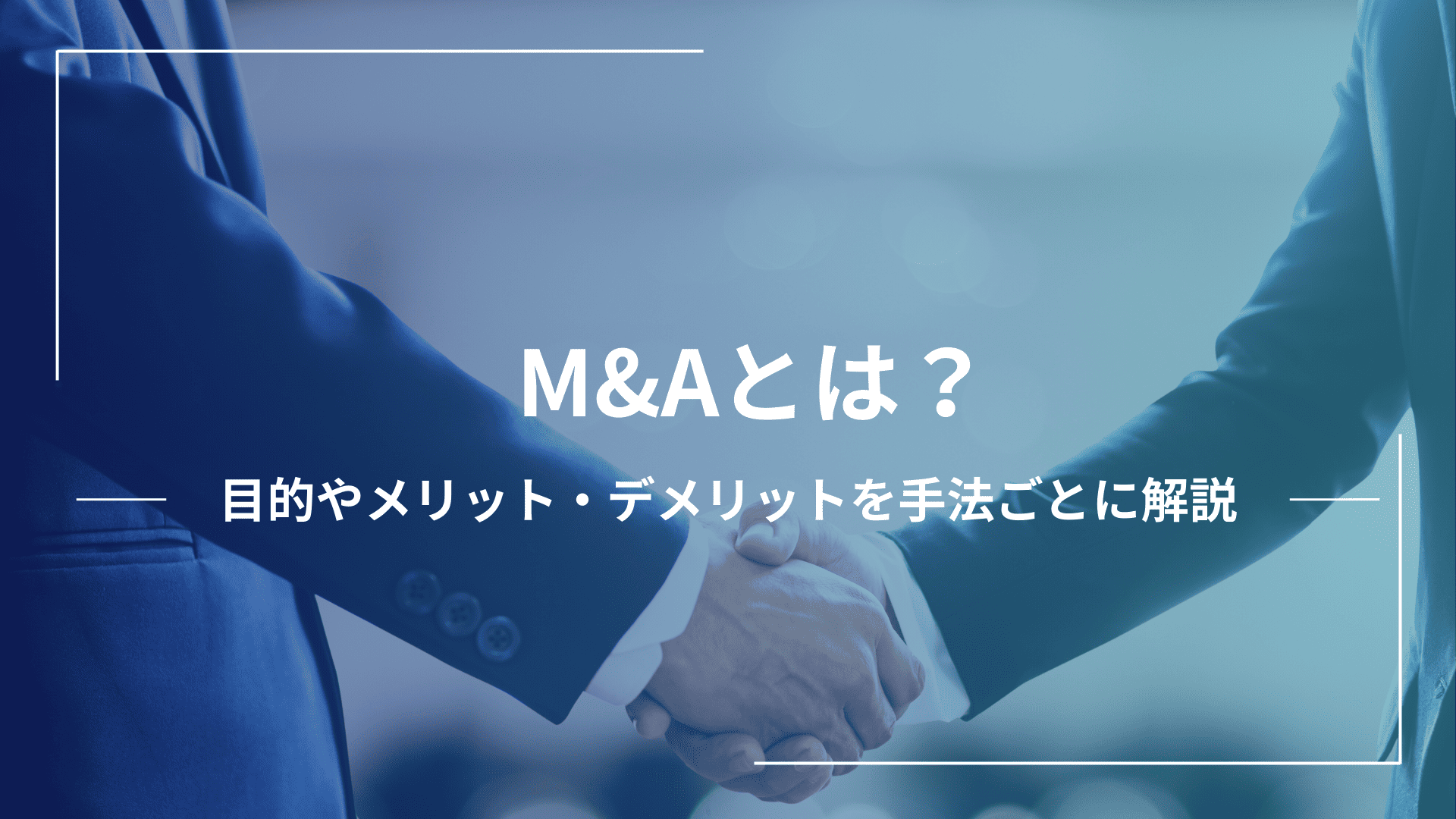CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
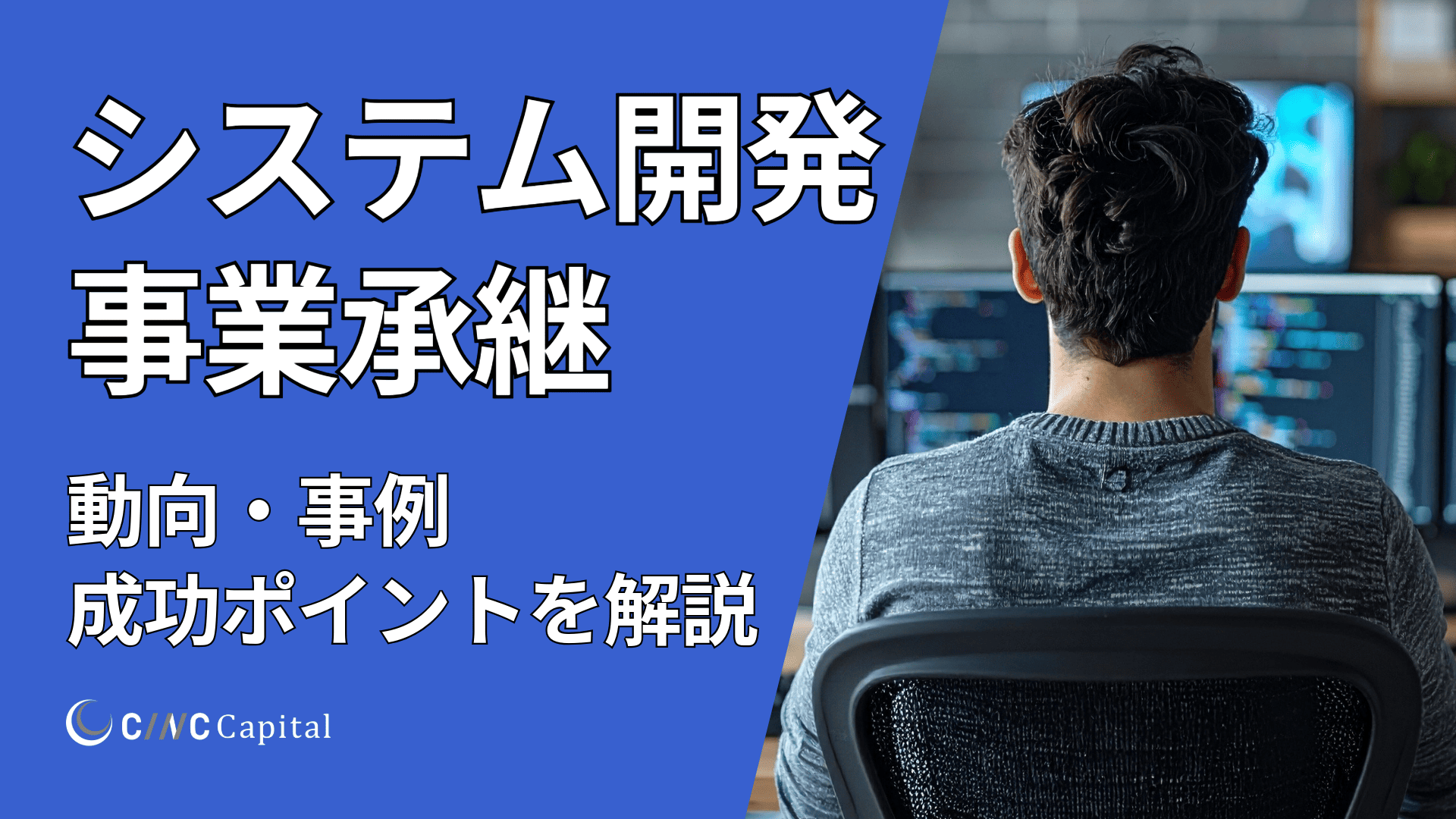
業種
- 公開日2025.09.29
【2025年】システム開発の事業承継とは?動向や手法、メリットデメリット、成功のためのポイントを解説
事業承継と聞くと、不安や悩みを感じる方も多いのではないでしょうか。
「後継者が見つからない」「技術や人材の引き継ぎがうまくいくのか心配」といった声は、経営者の間でよく聞かれます。
本記事では、2025年のシステム開発業界における事業承継の現状や、承継のメリット・リスクなどを詳しく解説していきます。
目次
システム開発業界の市場動向と課題
システム開発を含む国内IT・ソフトウェア市場は拡大基調にあり、特にDXやクラウド対応が成長を後押ししています。
本章では、システム開発業界の市場動向と課題について、3つの観点から解説していきます。
市場拡大が続くソフトウェア・IT市場
国内のソフトウェア・IT業界は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や生成AI、クラウド活用の高まりなどを背景に、市場全体が拡大を続けています。
業務システムの刷新・リプレース需要が強く、ソフトウェアの導入や更新が進んでいるのが現状です。
特にSaaS/PaaS形態のソフトウェアや、クラウド基盤・セキュリティ関連ソフトウェア、アプリケーションのAI統合、業務効率化を目的としたツールなどへの需要が増加傾向にあります。
また、法制度の改正(例:ペーパーレス化・電子契約など)や働き方改革関連の動きも、業務ソフトウェア・システムの導入を後押ししています。
こうした流れは、規模の大小を問わず中小企業にも影響を及ぼしており、最新技術への対応や業務改善を目的とした投資が続く見込みです。
人材不足と技術進化への対応負荷
日本では2030年までに最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。
さらに急速な技術進化に対応する負担が企業にのしかかっています。
人材育成や採用を強化しなければ、DXの流れから取り残される恐れがあるので注意が必要です。
【出典】経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」
レガシー刷新とクラウド化の遅れ
経済産業省は2018年に公表した「DXレポート」で、古いシステムへの依存が続けば、2025年前後に年間最大12兆円の経済損失が発生し得ると警鐘を鳴らしました。
さらに2022年時点でも、企業のデジタル投資の約8割が既存業務の維持・運用に偏っており、課題の深刻さは依然として解消されていません。
クラウド移行やシステム刷新は企業にとって重要な課題となっています。
【出典】経済産業省「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」
【出典】経済産業省「DXレポート2.2」
【2025年】システム開発業界の事業承継の最新動向
システム開発業界では、経営者の高齢化や後継者不足を背景に事業承継のニーズが高まっています。
本章では、システム開発業界における事業承継の最新動向について、見ていきましょう。
中小開発企業を中心にM&A活発化
中小規模のシステム開発会社では、後継者不足や人材確保の課題が深刻です。
レコフM&Aデータベースによれば、国内IT(情報通信業)企業におけるM&A件数は2024年に377件となり、前年の342件から増加しています。
DX需要の拡大も追い風となり、承継と成長を同時に実現する事例が増えているのです。
技術強化を目的としたAI・クラウド関連M&A増加
AIやクラウド分野に強みを持つ企業は、システム開発業界で高く評価されています。
競争力を高めるため、これらの技術を持つ企業を対象にしたM&Aが活発化しているのが現状です。
市場変化に素早く対応できる点から、成長戦略として注目を集めています。
システム開発業界で事業承継を実施する方法は?
事業承継とは、基本的に株式を後継者に引き継ぐことを指します。単に社長を交代するだけではなく、会社の所有権そのものを誰に承継するかが重要です。
承継の方法には大きく『親族内承継』と『第三者承継』があります。
第三者承継には、社内の役員・従業員に株を譲渡するケース(EBO)と、外部の企業や投資家に譲渡するケース(M&A)があり、近年は後者が中心です。
本章では、それぞれの方法について解説していきます。
親族内承継
親族に事業を引き継ぐ方法は、中小企業で長く選ばれてきた伝統的な手段です。
経営理念を守りやすい反面、ITスキルを持つ後継者が見つからないことも少なくありません。
技術習得や経営準備に時間と負担がかかる点が大きな課題です。
従業員承継
社内の幹部社員や外部の専門家に引き継ぐ方法は、業務や社風を理解している人材に任せられるため移行が比較的スムーズです。
ただし、経営能力やリーダーシップを発揮するまでには育成期間が必要になります。
承継を成功させるには、事前に計画的な準備を進めておくことが大切です。
M&A
M&Aは後継者が不在の企業にとって、事業を存続させる現実的な選択肢です。
買い手企業から資金や人材、技術といった経営資源を得られる点が大きな強みです。
近年では成長戦略を兼ねた承継手段として利用が増えています。
システム開発業界で事業承継するメリット
システム開発業界では、M&Aを活用した事業承継が増えており、会社や従業員に多くの利点をもたらします。
本章では、事業承継によって得られる主なメリットについて、5つの観点から解説していきます。
会社存続と雇用・取引の維持
M&Aを活用して事業を承継すれば、廃業を避けて会社を存続させられます。
従業員の雇用や取引先との関係を継続できる点は大きなメリットです。
事業や人員を買い手企業が引き継ぐことで、顧客や社員への影響を最小限に抑えられます。
資金・経営支援による拡大可能性
承継によって、単独では難しかった資金調達や事業拡大が可能です。
買い手企業の資本やノウハウを活用できるため、短期間での成長が期待できます。
設備投資や販路拡大、組織体制の強化を実現できる点も魅力です。
利益率・開発効率の改善
M&Aによって上流工程に参入するチャンスが広がるのもメリットです。
元請けに近い立場で案件を受注できれば、中間マージンを削減できるため利益率が改善します。
さらに、スキル向上や業務効率化によって開発効率も高まり、収益性が強化されるでしょう。
従業員待遇・育成の向上
M&Aによって買収先の教育制度や福利厚生を利用できるようになり、従業員はこれまで以上に安心して働ける環境を手に入れられるのもメリットと言えるでしょう。
こうした取り組みは待遇の改善だけでなく育成の仕組みを整える効果もあり、社員が長期的にスキルアップできる土台が築かれます。
その結果として、離職率の低下につながるだけでなく、社内全体のモチベーションが高まり、組織の安定性や活力を強めることが可能です。
技術・人材融合による競争力強化
M&Aを行うことで、買収企業と売却企業の双方が持つ技術や人材を組み合わせることが可能です。
単独では実現できなかった幅広い開発体制やノウハウの活用が期待できます。
こうした異なる強みが融合することで、新しい付加価値を生み出すシナジーが創出され、既存事業の質を高めるだけでなく将来に向けた基盤も強化されるのです。
システム開発業界で事業承継するデメリット
システム開発業界では、M&Aを活用した事業承継が広がる一方で、従業員の離職や情報漏洩、経営方針の不一致といった課題も懸念されています。
本章では、事業承継を進める際に注意すべき代表的なデメリットについて、3つの観点から解説していきます。
従業員の離職リスク
事業承継を進めると、従業員が離職しやすくなる点は大きな課題です。
M&Aにより職場環境が変わることで不安を抱く社員が出て、モチベーションの低下や転職につながる可能性があります。
特に情報サービス系の企業では、告知のタイミングや伝え方を工夫しなければ離職リスクが高まります。
機密情報の漏洩リスク
M&Aの交渉では財務データや顧客リスト、技術情報など重要な情報を扱うことが一般的です。
これらが漏洩すると取引の中止や企業の信用失墜に直結する危険があります。
そのため、秘密保持契約(NDA)の締結や仮想データルーム(VDR)の利用による厳格な情報管理が欠かせません。
経営方針や企業文化の不一致リスク
統合後に経営方針や企業文化が異なると、現場で混乱や摩擦が生じやすくなります。
システム開発業界では開発手法や意思決定の進め方が会社ごとに異なるため、特に注意が必要です。
事前にビジョンや文化をすり合わせておくことが、承継を成功させるための重要な対策になります。
システム開発業界で事業承継を成功させるためのポイント
システム開発業界では、承継を進める際に従業員の不安や技術資産の評価、経営文化の統合といった課題への対応が欠かせません。
本章では、事業承継を成功させるために押さえるべきポイントを5つ解説していきます。
従業員への情報開示と安心感確保
事業承継を進める際には、まず従業員に対して経営者自身の言葉で丁寧に説明することが欠かせません。
承継の目的や流れを合理的に伝えることで、従業員の不安を和らげることが可能です。
特にM&Aでは、告知のタイミングや説明の仕方を工夫することで、混乱を防ぎ円滑な移行につながります。
技術資産・財務状況の可視化準備
M&Aでは、財務データだけでなく技術資産や開発実績を明確に示すことが求められます。
保有する技術や開発チームの強みを整理し、数字や具体的な事例を提示することが重要です。
こうした可視化が進むと、企業価値を正しく評価してもらいやすくなり、交渉を有利に進められます。
IT業界に精通したM&Aアドバイザー活用
事業承継を成功させるには、業界特有の知識を持つM&Aアドバイザーの存在が大きいです。
経験豊富な専門家が関与することで、企業評価や交渉の質が大きく向上します。
さらに、適切な買い手候補を見つける選択肢が広がり、安心して承継を進められるようになるでしょう。
ビジョン・文化の事前すり合わせ
承継後の混乱を避けるためには、経営方針や企業文化を事前に共有し合意しておくことが重要です。
開発スタイルや意思決定の方法が異なると、統合後に摩擦や衝突が生じやすくなります。
トップ同士の合意形成に加えて、現場レベルでの共通理解を深める取り組みが欠かせません。
NDA・情報管理厳格化で機密保護徹底
M&Aの過程では、財務情報や顧客データ、技術情報といった機密情報を扱うことになります。
そのため、初期段階から秘密保持契約(NDA)を締結し、情報管理体制を徹底することが必要です。
情報の共有範囲や違反時の対応を明確にしておけば、漏洩リスクを最小限に抑えられるでしょう。
まとめ|事業承継に向けた「賢い一歩」を踏み出すために
システム開発業界はDXの進展で市場が拡大している一方、後継者不足や技術承継の課題が深刻です。
その解決策として事業承継の重要性が高まり、特にM&Aを活用した承継が中小企業を中心に増えています。
M&Aを行うことで会社の存続や雇用の維持、資金や技術の獲得、競争力の強化といった多くのメリットが得られるでしょう。
CINC Capitalは中小企業の事業承継を専門に支援しています。
豊富な実績を持つアドバイザーが、会社と社員の将来を見据えながら最適な進め方をご提案し、円滑な承継を実現できるようお手伝いします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。