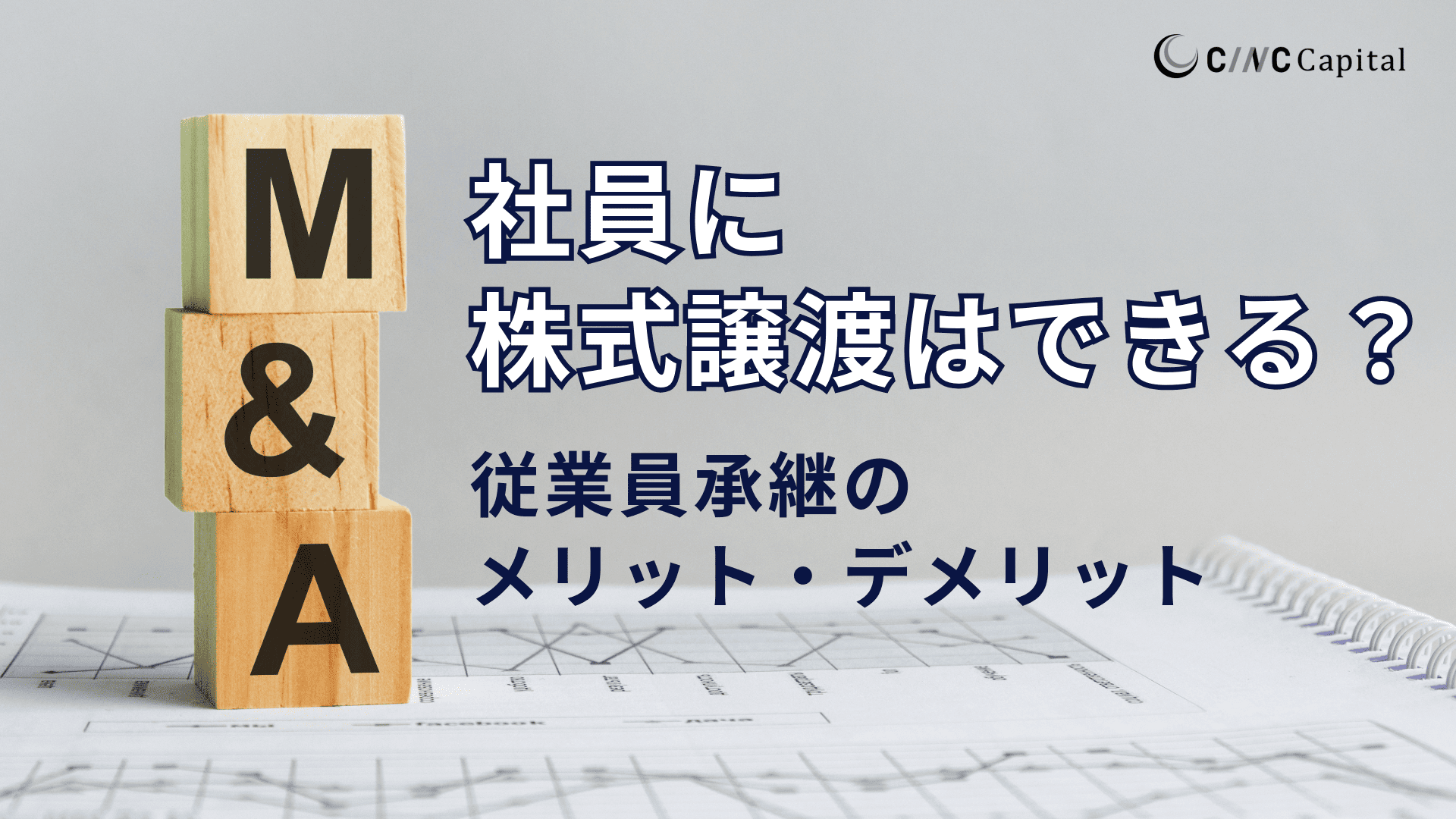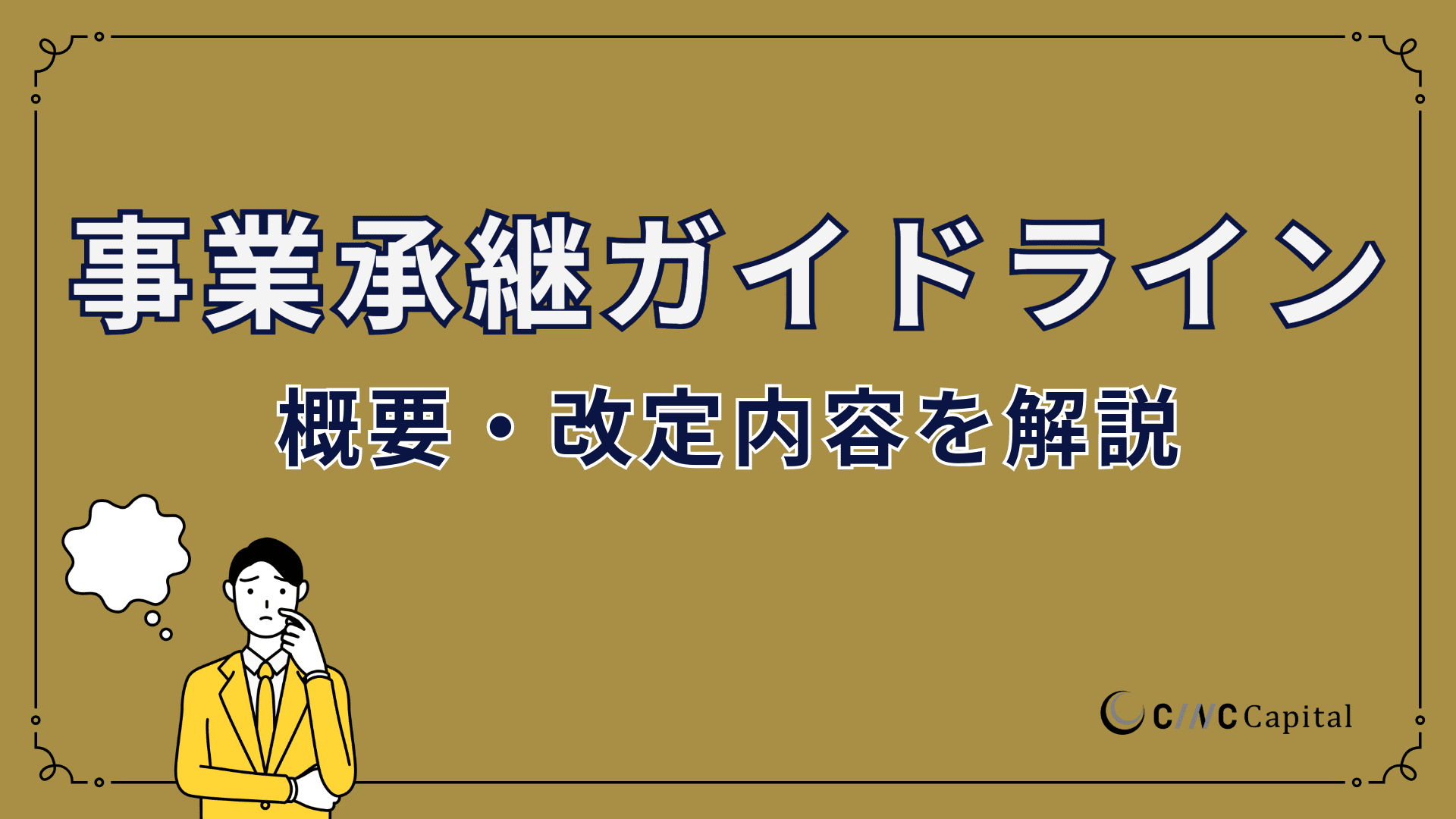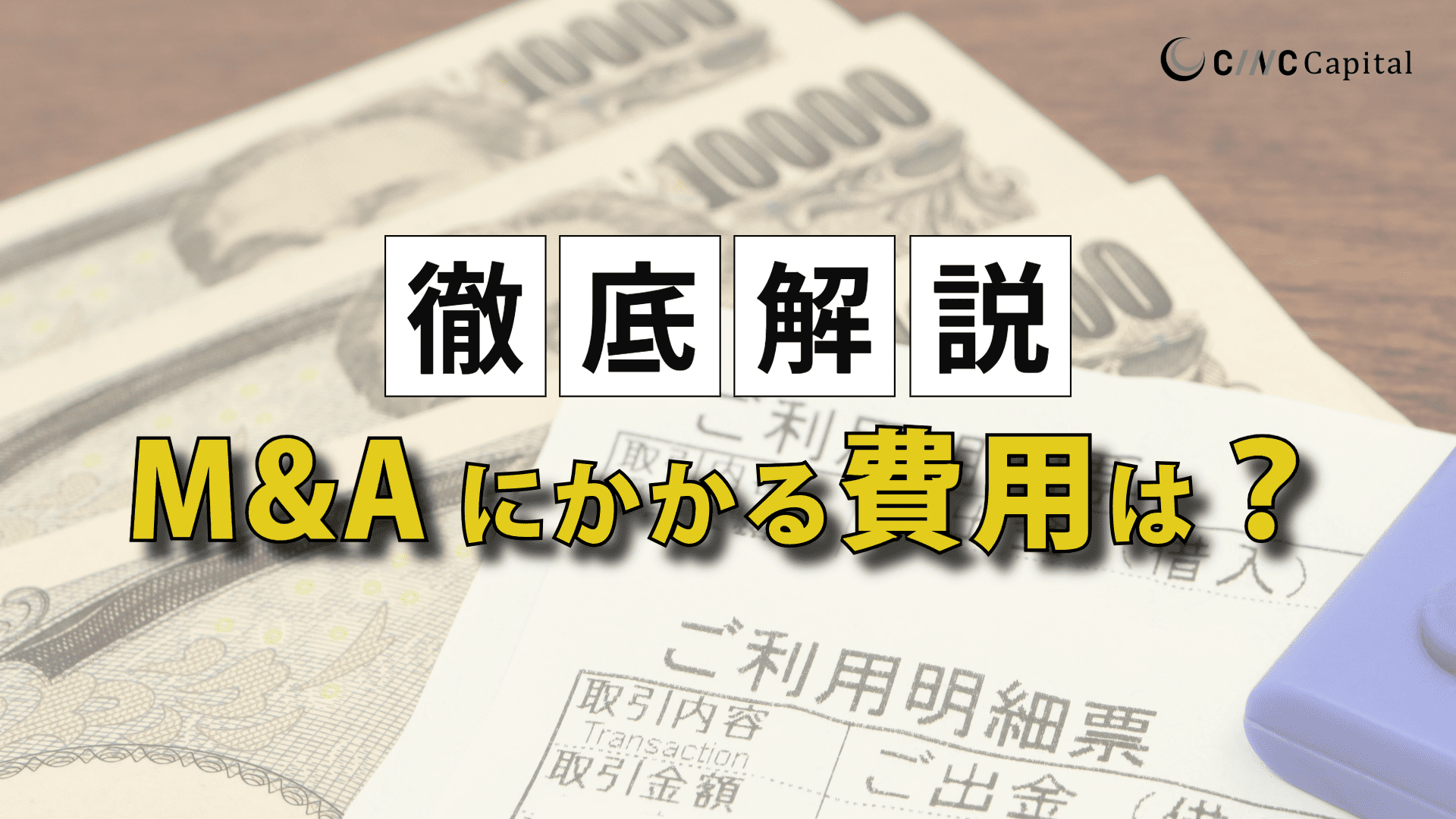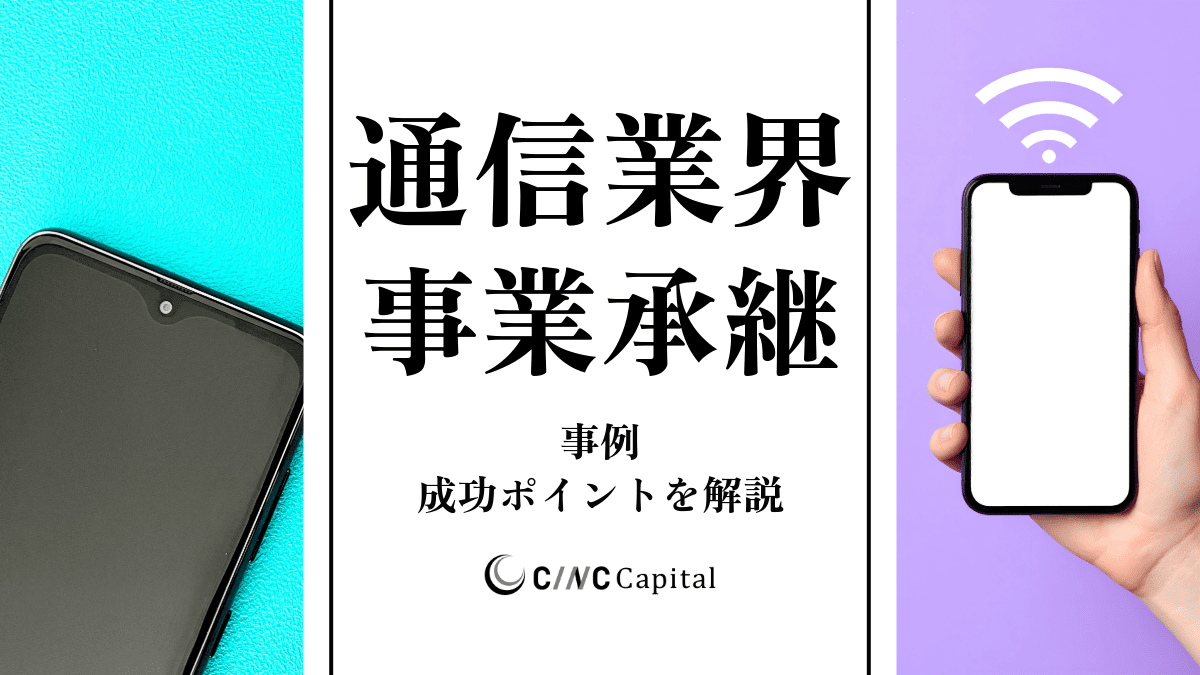CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種
- 公開日2025.09.30
【2025年】ショートステイの事業承継とは?動向や手法、メリットデメリット、成功のためのポイントを解説
ショートステイ事業の将来に不安を感じていませんか?
「後継者がいない」「今後の経営に自信が持てない」といった悩みを抱える事業者は少なくありません。
本記事では、ショートステイ業界における最新の市場動向や課題、事業承継に関する具体的な方法やメリット・デメリットなどを詳しく解説します。
目次
ショートステイ業界の市場動向と課題
ショートステイ業界は、高齢化の進行を背景に市場拡大が続いています。
しかし、成長の裏側では介護人材の不足や収益性の低さといった構造的な課題も浮き彫りになっているのです。
本章では、ショートステイ業界の成長性と課題について解説します。
今後も市場拡大が続く見通し
ショートステイは在宅介護の重要な受け皿として、今後も市場拡大が続く見通しです。
2022年度の介護保険給付費は約11.2兆円と過去最高を記録し、2023年には約11.5兆円と着実に増加し続けています。
高齢化の進行と要介護者増加が後押しする構図の中、2020年以降は一時的新型コロナウイルスによる利用控えが見られました。
しかし、2023年以降は回復の兆しを見せており、地域によっては供給が追い付かないほどの需要が続いています。
介護人材の不足と離職率の高さが課題
ショートステイ業界では、介護人材の不足と高い離職率が深刻な課題です。
介護労働安定センターの調査では、約6割の施設が人手不足を実感しており、「業務量の多さ」「低賃金」「人間関係」が主な要因とされています。
特に中小施設では業務負担が偏りやすく、離職の連鎖が施設運営への影響が大きいです。
収益性の低さとコスト増加が課題
ショートステイを含む介護業界は、制度による価格制限やコスト上昇の影響で収益構造が厳しいです。
最低賃金や人件費、光熱費の高騰が経営を圧迫し、特に小規模施設では深刻な打撃を受けています。
【2025年】ショートステイ業界の事業承継の最新動向
ショートステイ業界では、経営者の高齢化や人材不足を背景に、事業承継の動きが加速しています。
2025年現在、大手や異業種によるM&A、第三者承継の一般化など、多様な承継パターンが業界全体に広がりつつあるのです。
本章では、特に注目されている3つの最新動向についてご紹介します。
大手・異業種によるM&Aが加速
ショートステイ業界では、介護事業者や異業種によるM&A参入が活発化し、地域の介護基盤が再編されています。
大手金融機関や異業種による介護事業への参入が進み、スケールメリットを活かした経営が展開されています。
人材確保・ノウハウ継承を目的とした買収が増加
介護職員不足が業界共通の課題であることから、M&Aは人材の一括確保というニーズにも応えています。
買い手企業は、買収によって資格を持った職員やケアノウハウをそのまま引き継ぐことが可能になり、即戦力化が期待できるのです。
2024年の介護関連M&Aは143件にのぼり、その中で人材確保を主要目的とする案件が増加傾向となっています。
【出典】日本経済新聞「介護関連M&A3割増、24年 人手不足で経営悪化・撤退も」
第三者承継が一般化し、事業売却が身近に
ショートステイ業界では、後継者不在を背景に、M&Aによる第三者承継が選択肢として定着しつつあり、社外への事業売却を選ぶ経営者が増えています。
少子化や経営者の高齢化により、社外への事業売却を選ぶ事業者が増加しており、選択肢の幅も広がっているのです。
特に小規模施設にとっては、有効な出口戦略として地域の介護インフラ維持にも貢献しています。
ショートステイ業界が事業承継を実施する方法は?
本章では、ショートステイ業界における3つの代表的な事業承継の方法を紹介します。
それぞれの方法に特徴があるため、経営者の状況や目的に応じて適切な選択をすることが大切です。
親族内承継
親族内承継とは、経営者が子どもや兄弟など親族に事業を引き継ぐ方法です。
後継者を早期に育成できるため、長期的な視点で事業継続の準備を進めやすい特徴があります。
従業員や取引先からの心理的な受け入れも得やすく、混乱の少ない承継が可能です。
従業員承継
従業員承継は、経営者の子どもや親族ではなく、会社に長年勤めてきた役員や従業員に事業を引き継ぐ方法です。
社内の事情や業務内容を深く理解している従業員が後継者となるため、事業の継続性が高く、従業員や取引先からの信頼も得やすいというメリットがあります。
また、既に社内での実務経験や人間関係を築いているため、スムーズに経営を引き継ぎやすく、育成や教育の負担を軽減できる点も強みです。
M&A
M&Aは、外部企業へ株式や事業を譲渡して経営を引き継ぐ方法で、ショートステイ業界でも活用が広がっています。
施設や人材、許認可を一括で承継できるため、事業基盤をそのまま残しやすいです。
特に後継者不在や成長戦略の一環として、M&Aは現実的な選択肢のひとつとされています。
ショートステイ事業を事業承継するメリット
ショートステイ事業を承継することで、既存の利用者や職員の継続的なサービス提供が可能です。
加えて、地域インフラとしての信頼を維持しやすいメリットがあります。
雇用と利用者の継続維持
特に株式譲渡の場合、法人格がそのまま残るため従業員の雇用や利用者との契約が継続され、サービスを途切れさせずに提供可能です。
事業譲渡の場合は契約の再締結が必要になるため、丁寧な対応が求められます。
その結果、地域密着型の介護基盤を途切れさせずに保てるのです。
初期投資コストの低減
既存施設や設備、人材をそのまま活用できるため開業コストを大きく抑えられます。
新規開設に比べて収益化までの期間を短縮することが可能です。
介護ノウハウや経験を引き継げる
長年の運営で培われたケアのノウハウや経験をそのまま継承できます。
これによりサービス品質を維持しやすくなるのです。
許認可の引継ぎが可能
ショートステイ運営に必要な許認可の取扱いは、事業承継の形態によって異なります。
株式譲渡であれば法人格が存続するため、許認可はそのまま維持されます。
一方、事業譲渡の場合は『指定替え』や『新規申請』が必要となり、行政手続きや利用者契約の対応が求められます。
地域との信頼関係を継続できる
既存の地域連携や行政との関係を継続しやすいため、スムーズなコミュニケーションが続きます。
結果として、承継後も信頼を損なうことなく事業を展開できるのです。
ショートステイ事業を事業承継するデメリット
ショートステイ事業承継には潜在的なリスクや注意点も存在するため、実施前に適切な対策が重要になります。
本章では、事業承継するデメリットを3つ見ていきましょう。
後継者の能力不足リスク
親族や従業員が事業を承継しても、経営スキルやマネジメント能力が不足している場合が考えられるでしょう。
その結果、経営判断の誤りや組織運営の混乱が生じ、事業改善や成長が停滞する恐れがあります。
計画的な育成と外部専門家の支援が不可欠です。
親族間の意見対立リスク
親族間で資産配分や経営方針を巡る意見の食い違いが発生する可能性があります。
とくに複数の相続人が関与する場合、感情的な対立に発展しやすくなります。
このような対立が事業承継そのものを妨げる要因になることもあるのです。
許認可変更による手続き遅延リスク
ショートステイ事業を引き継ぐには、行政の許認可が必要になります。
事業を譲渡する際は、変更届や新しい申請など複雑な手続きが発生し、時間がかかることが多いです。
手続きが遅れると、最悪の場合、一時的に施設の運営が止まってしまうリスクもあるため注意が必要になります。
ショートステイ業界の事業承継を成功させるためのポイント
ショートステイ事業を円滑に引き継ぐには、業界特有の事情を踏まえた準備と戦略が欠かせません。
本章では、ショートステイ業界で事業承継を成功させるために重要な5つのポイントを解説します。
許認可手続きを前倒しで進める準備
ショートステイ事業の承継では、株式譲渡か事業譲渡かによって必要な許認可手続きが異なります。
株式譲渡の場合は法人格がそのまま存続するため、許認可は維持されます。
一方で事業譲渡の場合は『指定替え』や行政への新規申請が必要となり、時間を要するケースがあります。
そのため、承継前から自治体と調整を進めることで、稼働停止リスクを最小限に抑えられます。
現場経験を通じた後継者育成を徹底する準備
後継者が現場での実務経験を積むことは、職員からの信頼を得るうえで重要です。
業務を理解し、現場の感覚を身につけておくことで、承継後の混乱を防ぐことができます。
経営と現場の両面を理解した後継者は、円滑な移行と安定運営を実現しやすくなるでしょう。
人材データや職場環境を魅力として整備する準備
資格保有者数や離職率などの人材に関する数値は、買い手にとって大きな判断材料になります。
これらの情報を分かりやすく整理・可視化することで、事業の魅力を高められます。
職員の声や現場の雰囲気を資料に加えることで、さらに信頼性の高い訴求が可能です。
情報発信に配慮した広報体制を整備する準備
事業承継に関する情報は、伝える時期や内容を間違えると混乱を招く恐れがあります。
職員の離職や利用者の不安を避けるため、段階的かつ丁寧な情報共有が必要です。
併せて、社内外への説明タイミングを含むコミュニケーション計画も用意しておきましょう。
介護業界に精通した専門家を早期に活用する準備
ショートステイの事業承継には、法務・税務・許認可対応など多岐にわたる知識が求められます。
そのため、介護業界に詳しい専門家と早めに連携しておくことが重要です。
M&A仲介会社や士業と連携することで、手続きや交渉が円滑に進みやすくなります。
ショートステイ業界の事業承継に関するよくある質問
Q1.事業承継をする際のステップは?
事業承継は「5つのステップ」で進めることが推奨されています。
まず早期に準備を始め、後継者の選定や株式・資産の整理を行い、自社の経営状況や課題を「見える化」して共有します。
そのうえで経営改善や体質強化を進め、承継計画を策定し、親族・従業員・M&Aなど承継方法に応じた専門家や支援機関と連携して実行に移すのが基本の流れです。
Q2.事業承継にかかる費用は?
事業承継に伴う主な費用は、デューデリジェンス(買い手負担)、仲介手数料(着手金・中間金・成功報酬等)、登記関連費用、そしてスキームに応じた税金です。
介護のように許認可が絡む業界では法務等の専門家費用が増えやすい傾向にあります。また、株式譲渡・事業譲渡・合併など選ぶ手法によって必要費用と税負担の中身も変わります。
最終的な負担者や金額は当事者間の合意や案件の複雑性で左右されるため、事前に費用項目と負担範囲を明確化しておくのが安全です。
Q3.事業承継の費用は誰が負担するのですか?
費用の負担主体は事業承継の形態によって異なります。
親族内承継の場合、基本的な諸費用(専門家への依頼料など)は会社または現経営者が負担し、後継者個人には相続税・贈与税といった税負担が生じる程度です。
従業員承継では、後継者となる従業員が株式の買取資金を準備したり贈与税を支払ったりする必要があり、資金調達を含めて後継者側の負担が大きくなります。
一方、M&Aの場合、一般的に買い手企業が事業取得の対価やデューデリジェンス費用を負担し、売り手側(承継元の経営者や法人)は譲渡対価から仲介手数料や譲渡益にかかる税金を支払う形となります。
まとめ|ショートステイ業界の事業承継を成功に導くために
ショートステイ業界は成長を続ける一方で、人材不足や収益性の低さといった課題を抱えています。
こうした中で、後継者不在に悩む経営者にとって、事業承継の重要性はますます高まるでしょう。
本記事では、市場動向、承継手法、メリット・デメリット、成功のポイントをわかりやすく解説しました。
自社に合った方法を選び、早めに準備を進めることが、経営の安定と信頼の継続につながるでしょう。
CINC Capitalは様々な分野の事業承継を支援しています。
経験豊富なアドバイザーが、会社と社員の将来を見据えて最適な方法をご提案します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。