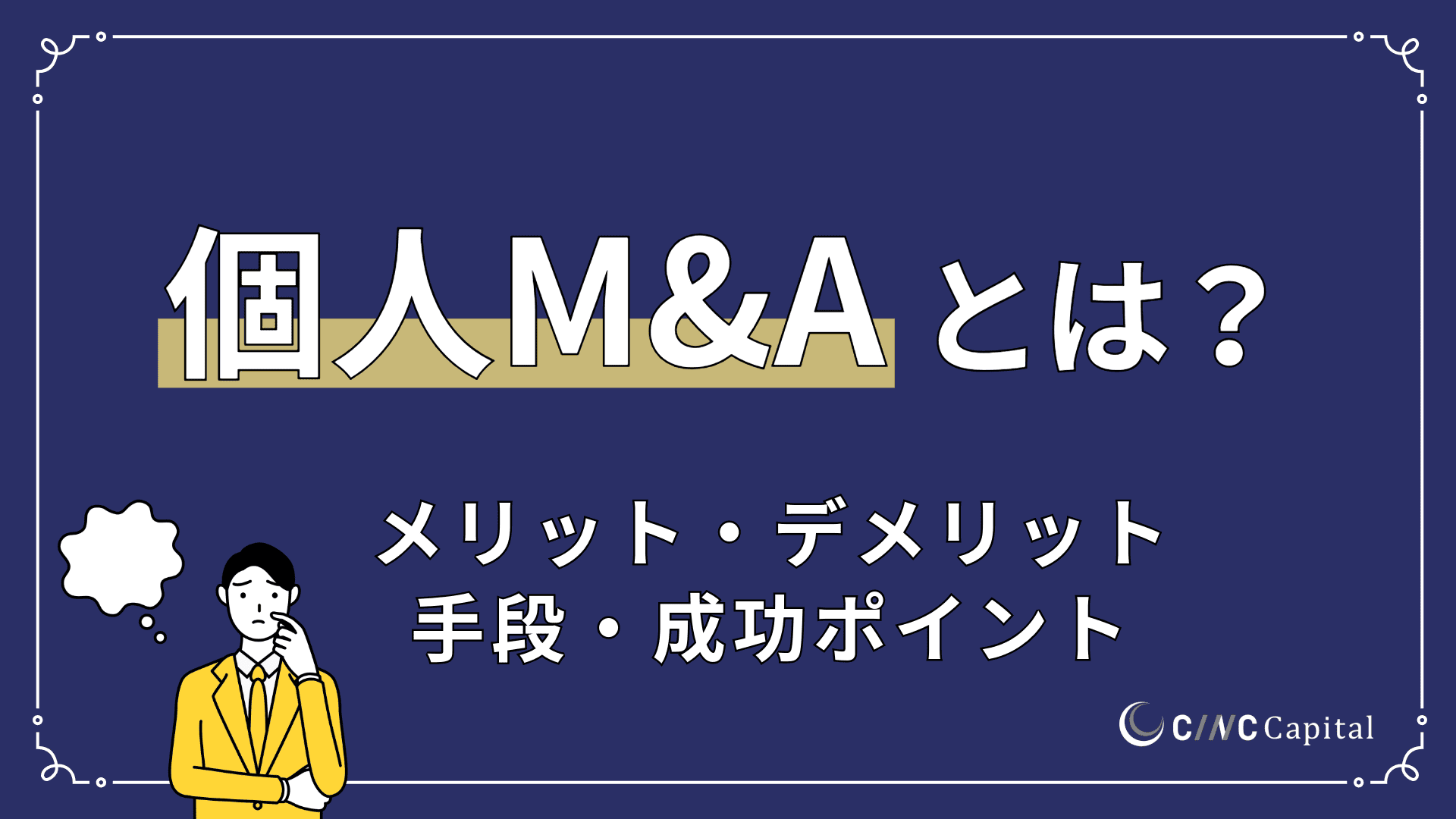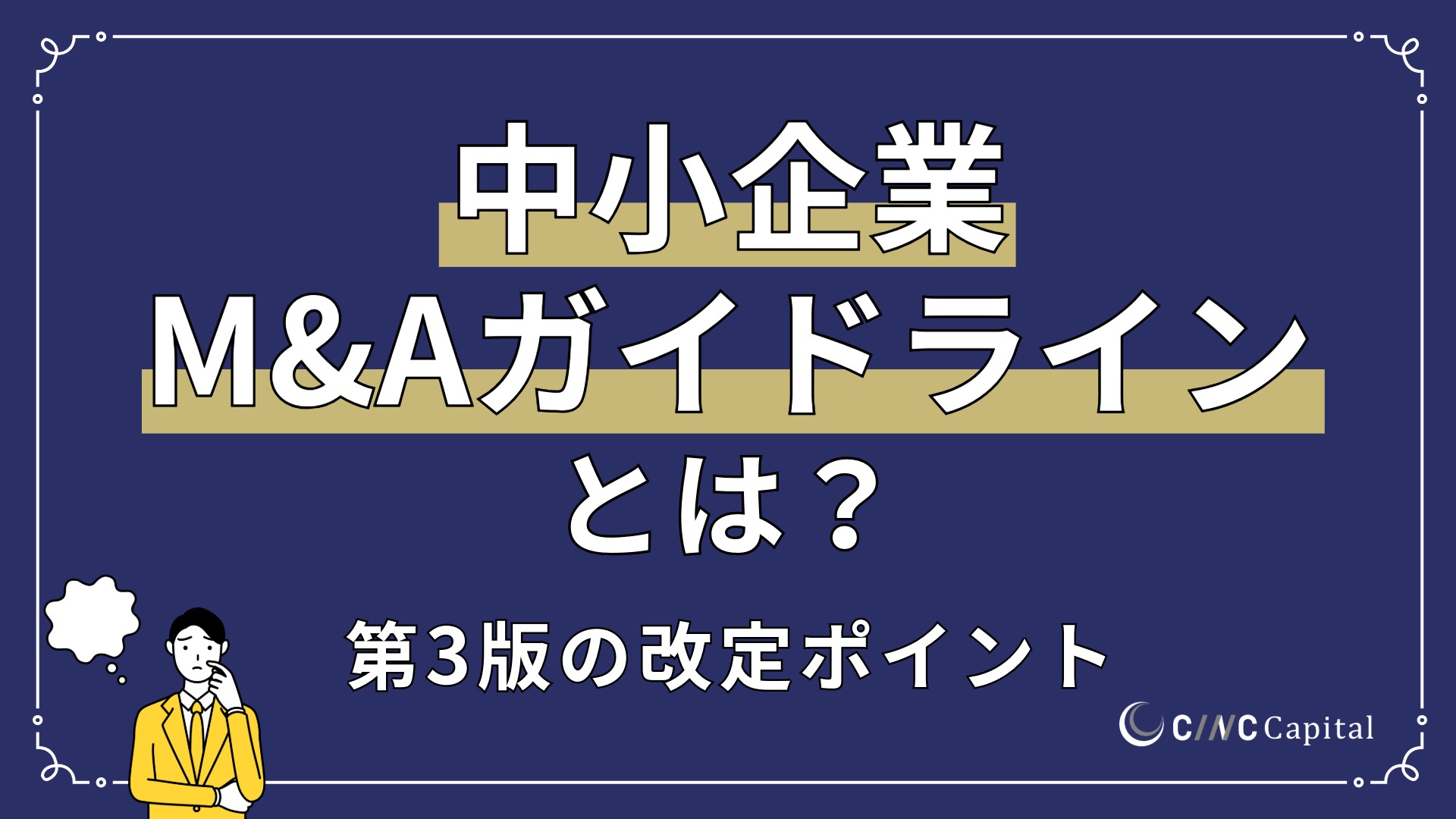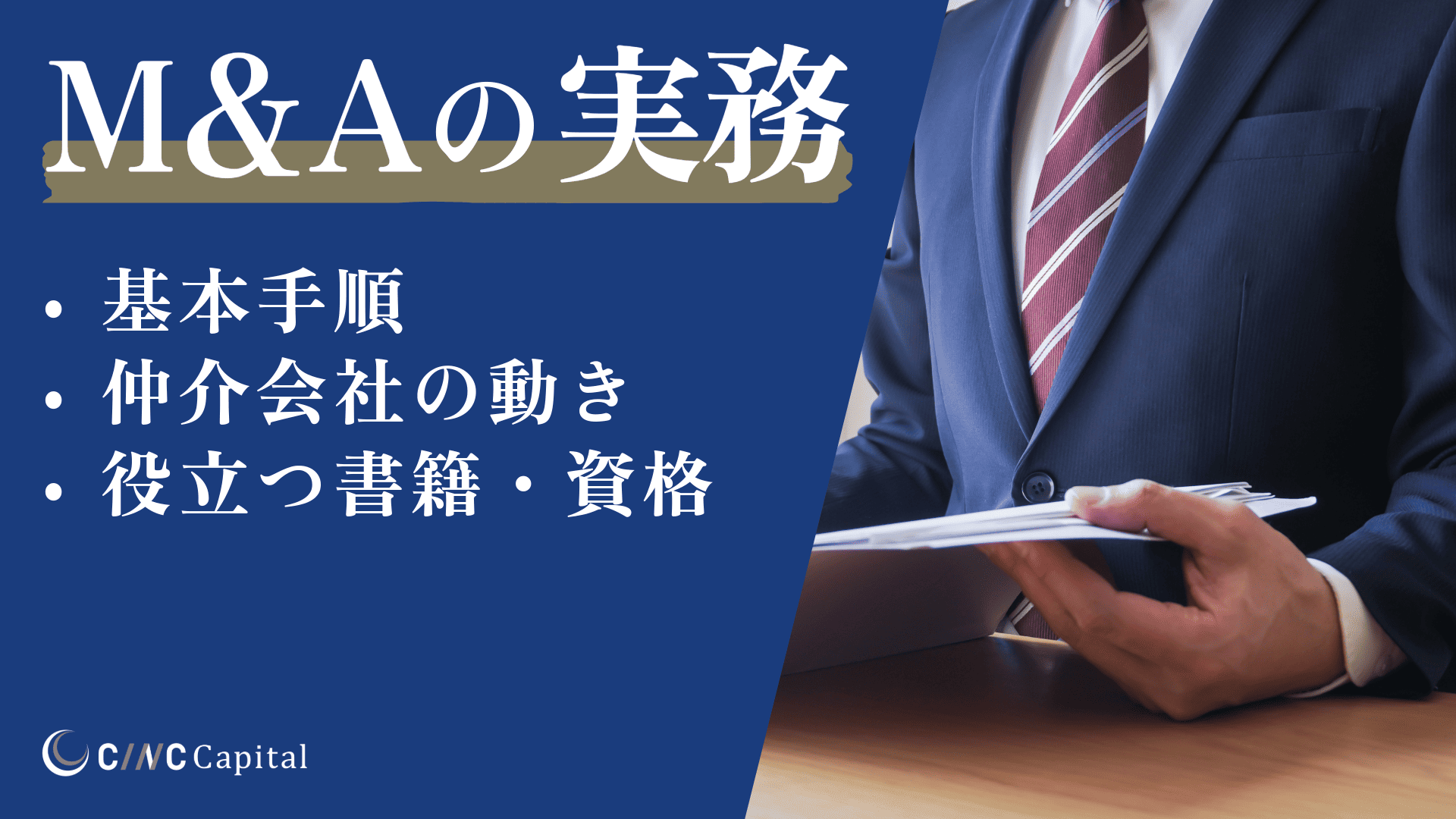CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
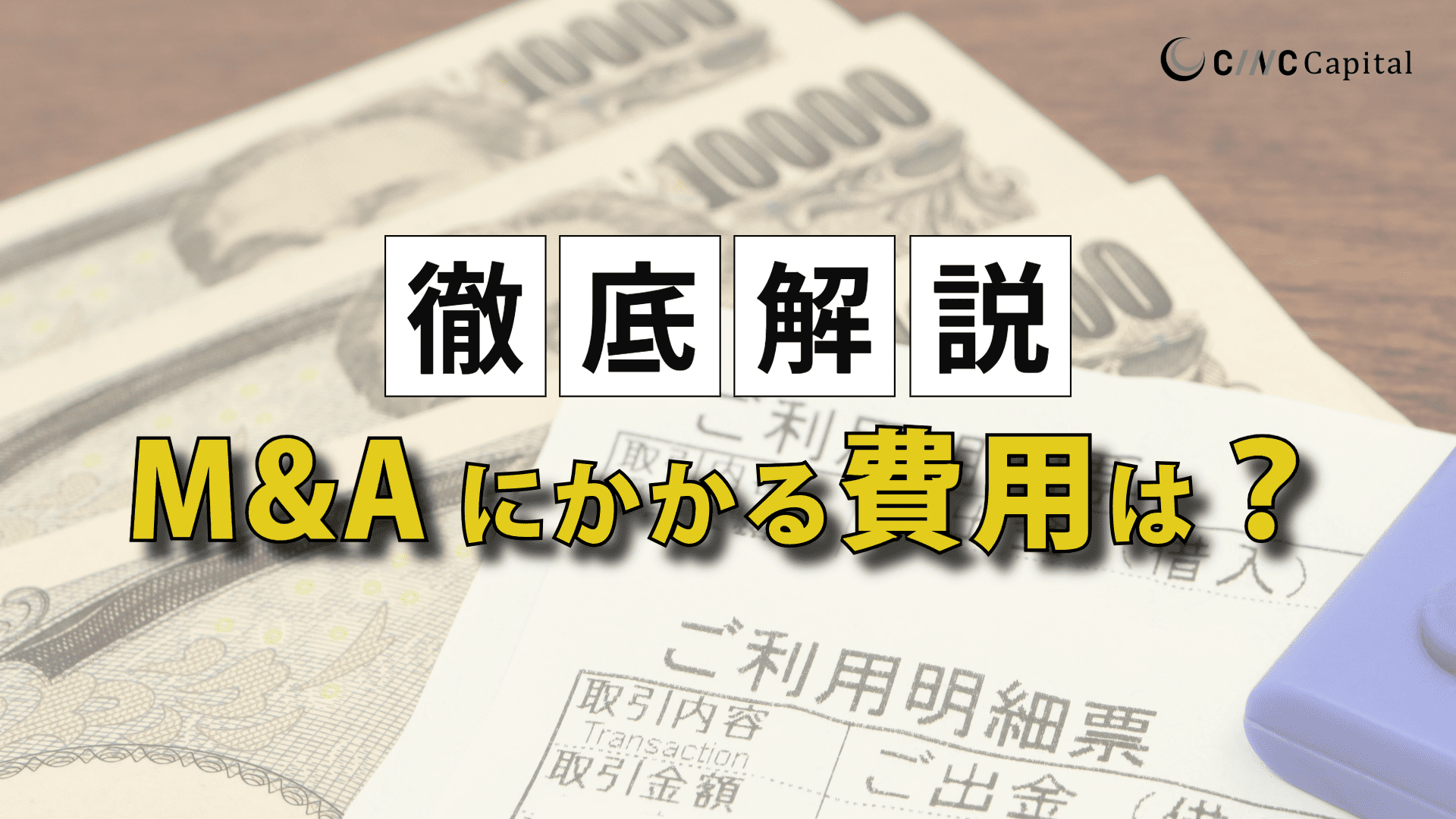
M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.06.26
M&Aにかかる費用にはどのようなものがある?内訳と影響を与える要素
M&Aで企業の合併・買収が行われる際は、かなりの金額が動くことが多いでしょう。買い手が売り手に支払う対価はもちろんのこと、税金やデューデリジェンス費用など、各種の費用が必要です。
一方で、なるべく費用を抑えたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、M&Aにかかるコストの具体的な内訳や、費用に影響を与える主な要素、費用を抑えるポイントなどを徹底解説します。
目次
M&Aにかかる費用の内訳
M&Aを実施する場合、買収する際の費用だけではなく、事前調査や登記、株券発行などのさまざまな費用が発生する場合があります。ここでは、M&A費用の主な内訳をご紹介します。
デューデリジェンス費用
デューデリジェンスとは、契約前に実施される調査のことです。基本的に買い手企業が支払うケースがほとんどですが、売り手企業の負担となるケースもあります。
徹底的にデューデリジェンスを行うことで、表面化していなかった負債が判明することもあります。デューデリジェンスは、M&Aの成約の成否に拘わる重要なフェーズのため、M&Aに欠かせない費用の一つです。
また、デューデリジェンスは弁護士や税理士、公認会計士といった専門家へ依頼します。依頼する人数や調査規模などにより、報酬の金額は変化します。
買収費用
買い手側が売り手側に対して支払う対価です。対価の種類は、M&Aスキームによって異なります。
【M&Aスキーム別の買収費用】
・株式譲渡の場合…現金、株式交換など
・事業譲渡の場合…現金、株式、社債など
・合併の場合…株式交換が一般的(※存続会社の株式を消滅会社の株主に交付する)
登記費用
M&Aの成立後に必要となる登記関連の費用です。M&Aスキームによって必要な登記手続きが異なります。登記費用には登録免許税や法務局への手数料などが含まれ、一般的に買い手側が負担します。ただし、当事者間の合意により負担者を決めることも可能です。
【M&Aスキーム別の登記費用】
・株式譲渡の場合…取締役変更などの役員変更登記が必要な場合のみ費用が発生する
・事業譲渡の場合…不動産の所有権移転登記が必要な場合のみ費用が発生する
・合併・会社分割の場合…新会社設立登記や変更登記などで費用が発生する
株券発行費用
株券を発行する際に発生する費用で、売り手側が支払います。2009年1月の株券電子化以降は、株券不発行が原則となっているため、通常この費用は発生しません。ただし、定款で株券を発行する旨を定めた非上場会社(株券発行会社)の場合は、株券の発行・交付が必要となり、費用が発生します。
税金
「M&Aの税負担はスキームによって異なり、成否に影響を与える重要な要素です。専門家に相談することをおすすめします。
【M&Aスキーム別の税金】
・株式譲渡の場合…売り手は譲渡損益に対する法人税または所得税(個人の場合)が課税されます。買い手側は印紙税が発生します。
・事業譲渡の場合…売り手は譲渡資産の譲渡損益に対する法人税、消費税が課税されます。買い手側は印紙税に加えて、不動産取得がある場合は登録免許税や不動産取得税が発生します。
・合併・会社分割の場合…適格要件を満たす場合は課税繰り延べとなりますが、非適格の場合は時価による譲渡損益課税が生じます。
仲介手数料
買い手側・売り手側ともに、M&A仲介会社に依頼した際、内容に応じて料金を支払うことになります。相談料や着手金、中間報酬、成功報酬など、どのような料金が必要になるかは企業やサービスによって異なります。相談料は無料の企業もあるため、まずは問い合わせをしてプロのアドバイスをもらうことがおすすめです。
M&Aにかかる費用に影響を与える要素
M&Aの費用は、多岐にわたる要素によって変わります。買い手・売り手それぞれの費用に影響を与える要素について解説します。
業界特性
業界の特徴により、必要となる専門家費用が異なります。例えば、許認可が必要な業界では法務費用が増加し、製造業では工場や設備の調査費用が必要となります。これらの専門家費用は、通常買い手側が負担します。
企業規模
企業規模に応じて、買い手・売り手双方のアドバイザリー費用が変動します。一般的に、M&A仲介会社への手数料は取引価額に応じた料率で計算されます。ただし、小規模案件では案件規模によらない最低報酬(フロア)が設定されることがあります。
案件の複雑性
企業グループの規模や取引スキームの複雑さにより、デューデリジェンス(財務・法務・税務)の費用が変動します。例えば、子会社が多い場合や、海外企業が関係する場合は、調査範囲が広がるため費用が増加します。これらの調査費用は、通常買い手側が負担します。
譲渡価格の計算法の選択
譲渡価格を決定する計算方法として、主に以下の種類があります。どの方法を選ぶかによって、最終的な金額が変化する可能性があります。
コストアプローチ
譲渡会社の純資産を基準に、買収金額を算定する方法です。「時価純資産法」や「簿価純資産法」などの手法が含まれます。市場価値の把握が難しい中小企業でも、この方法なら明確な金額を算出しやすい点が特徴です。
インカムアプローチ
将来予測される収益を基準に、買収金額を計算する方法です。「DCF法」や「配当還元法」などの手法が代表的です。将来性やシナジー効果などを評価できますが、計算に主観が入りやすい点に注意が必要です。
マーケットアプローチ
規模や業種が似た企業と比較し、市場価値を推定して買収金額を算定する方法です。「市場株価法」や「類似会社比準法」などの手法が用いられます。適切な比較対象を選ぶのが難しい点は考慮が必要です。
M&Aの費用を抑える方法
M&Aではさまざまな費用が発生します。買い手・売り手それぞれの立場から、費用を適切にコントロールするポイントを解説します。
M&Aスキームの選択による費用コントロール
取引スキームによって必要となる費用が異なります。たとえば、株式譲渡では株式価値算定費用が必要となり、事業譲渡では個別資産の評価費用が発生します。また、合併では組織再編に伴う費用が必要です。自社の目的に合わせて、最適なスキームを選択することが重要です。
デューデリジェンスの効率化
デューデリジェンス費用は、買い手側が負担する主要な費用の一つです。調査範囲を明確化し、重要度の高い項目から優先的に調査することで、費用を効率化できます。ただし、重要なリスクの見落としにつながる過度な範囲限定は避けるべきだといえます。
アドバイザリー費用の適正化
M&A仲介会社やアドバイザーの選択は、費用面で大きな影響を与えます。仲介手数料は、取引価額に応じた料率で算出され、会社によって料率や最低報酬額が異なります。ただし、単にアドバイザリー費用の低さだけでなく、実績や専門性も考慮して選定することが重要です。
専門家の効率的な活用
弁護士や会計士などの専門家費用は、通常買い手側が負担します。案件の初期段階から適切な専門家に相談することで、後々の出戻りや追加コストを防ぎやすくなります。必要な専門家を適切に配置し、費用対効果を高めましょう。
まとめ|M&Aにかかる費用を理解し、適切なスキーム・専門家の選択を
M&Aを行う際は、買い手側と売り手側どちらも相応の費用が生じます。できる限り費用負担を少なくしたい場合は、ご紹介したポイントも参考に工夫してみましょう。
ただし、費用を抑えることを重視しすぎてデューデリジェンスをおろそかにしたり、費用は安いが実績に不安がある仲介会社へ依頼したりするのは、避けることをおすすめします。M&A成功のために必須となる費用を確かめた上で、予算に応じた対応を行いましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。