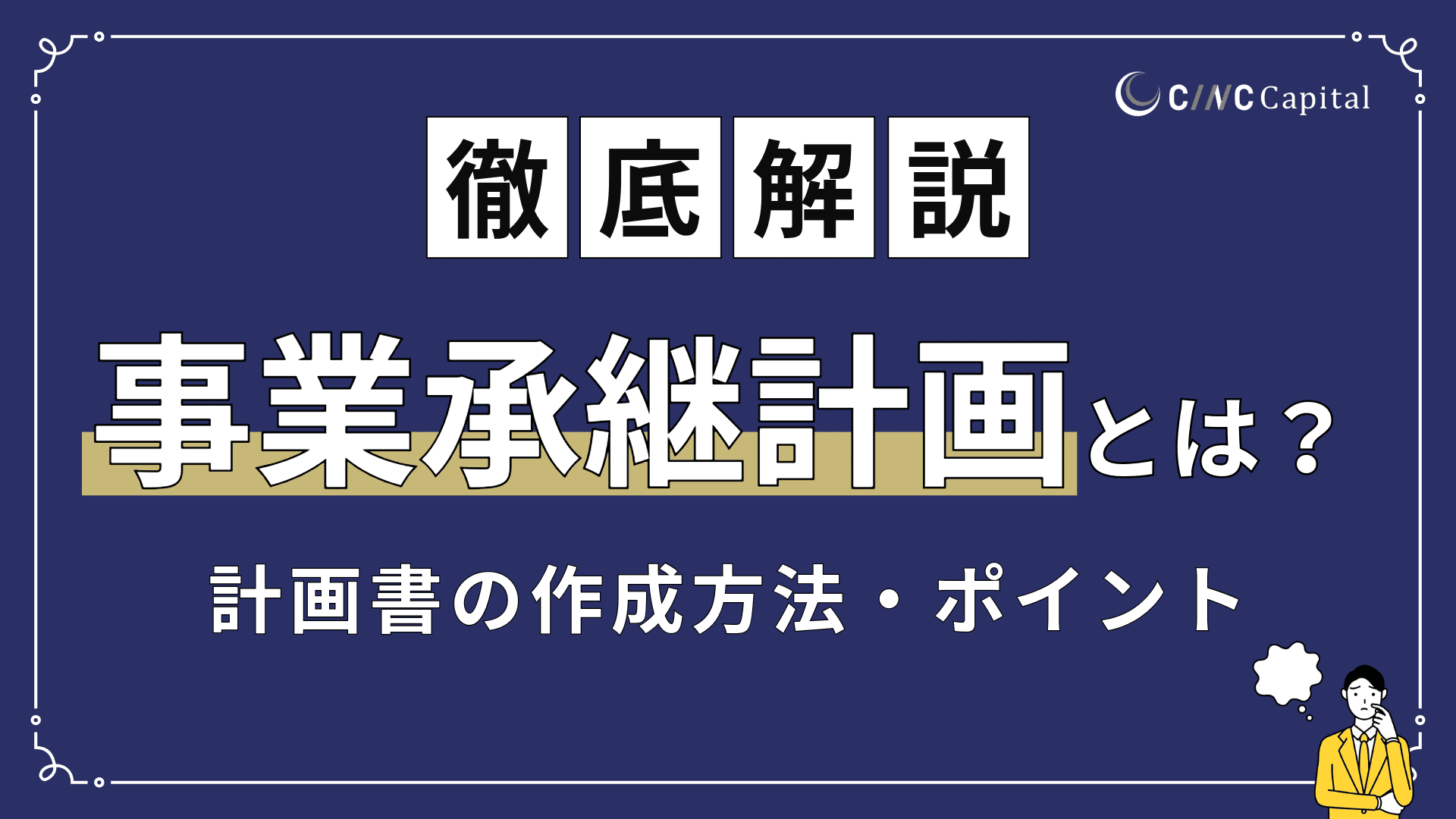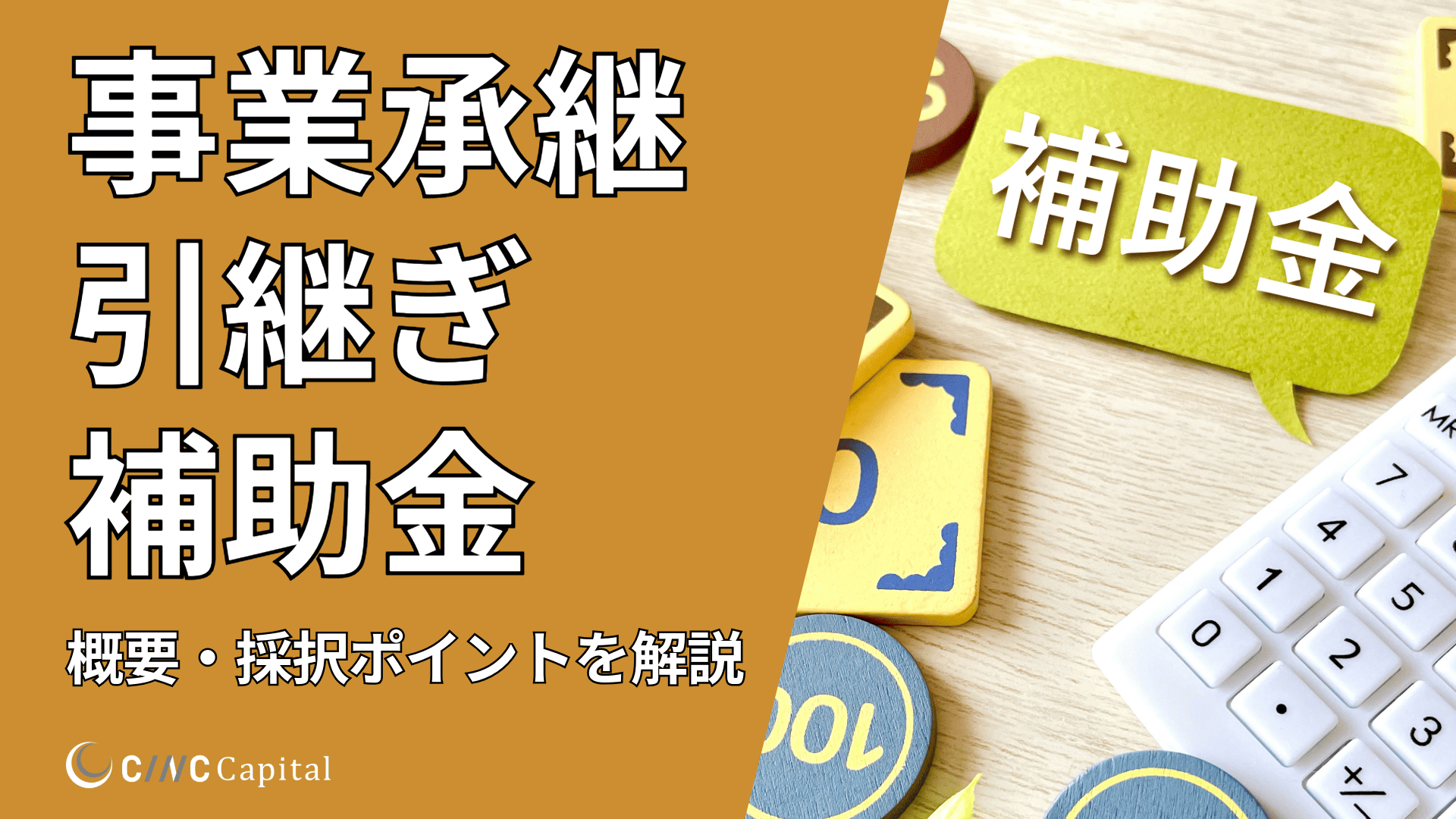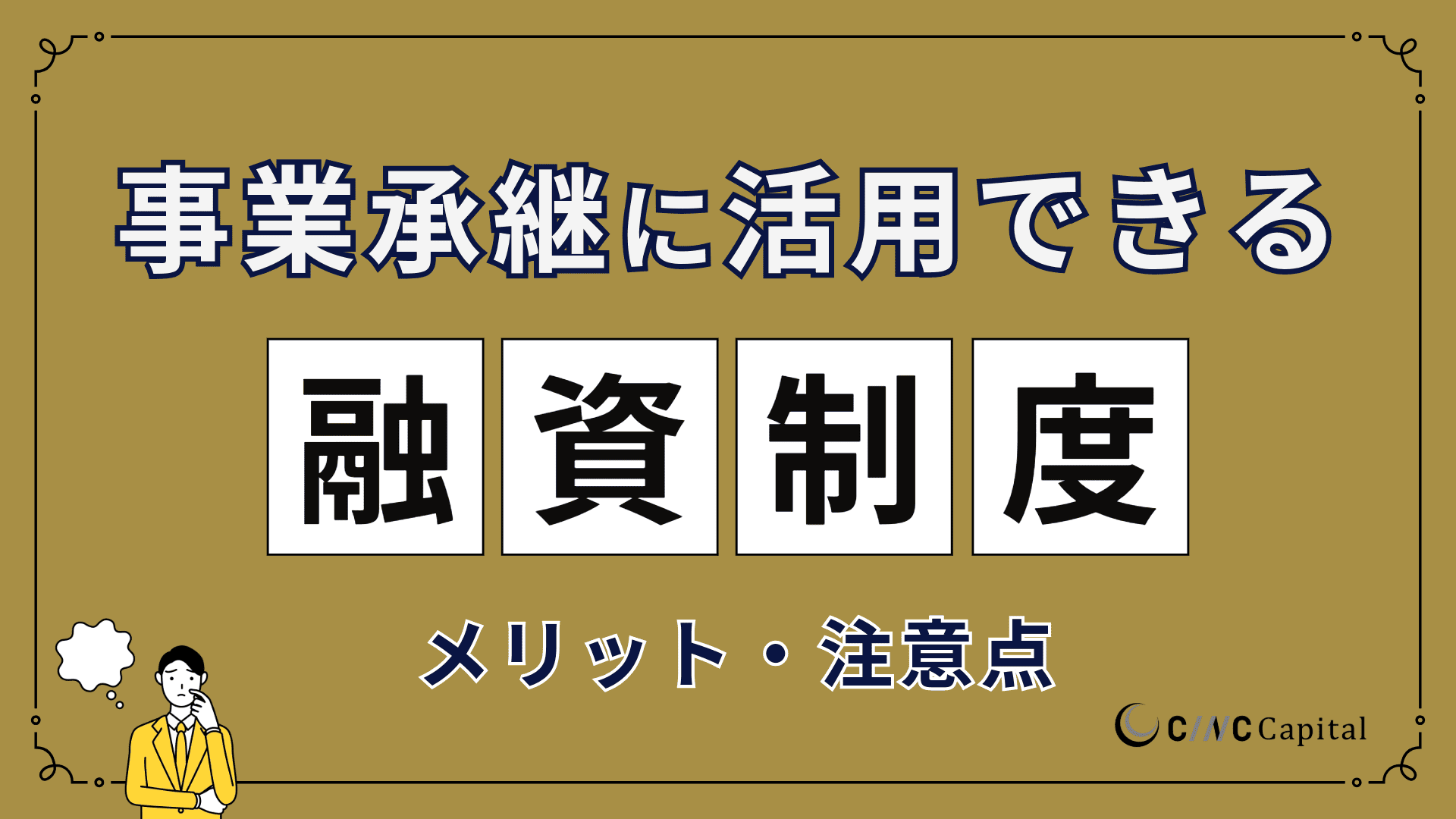CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
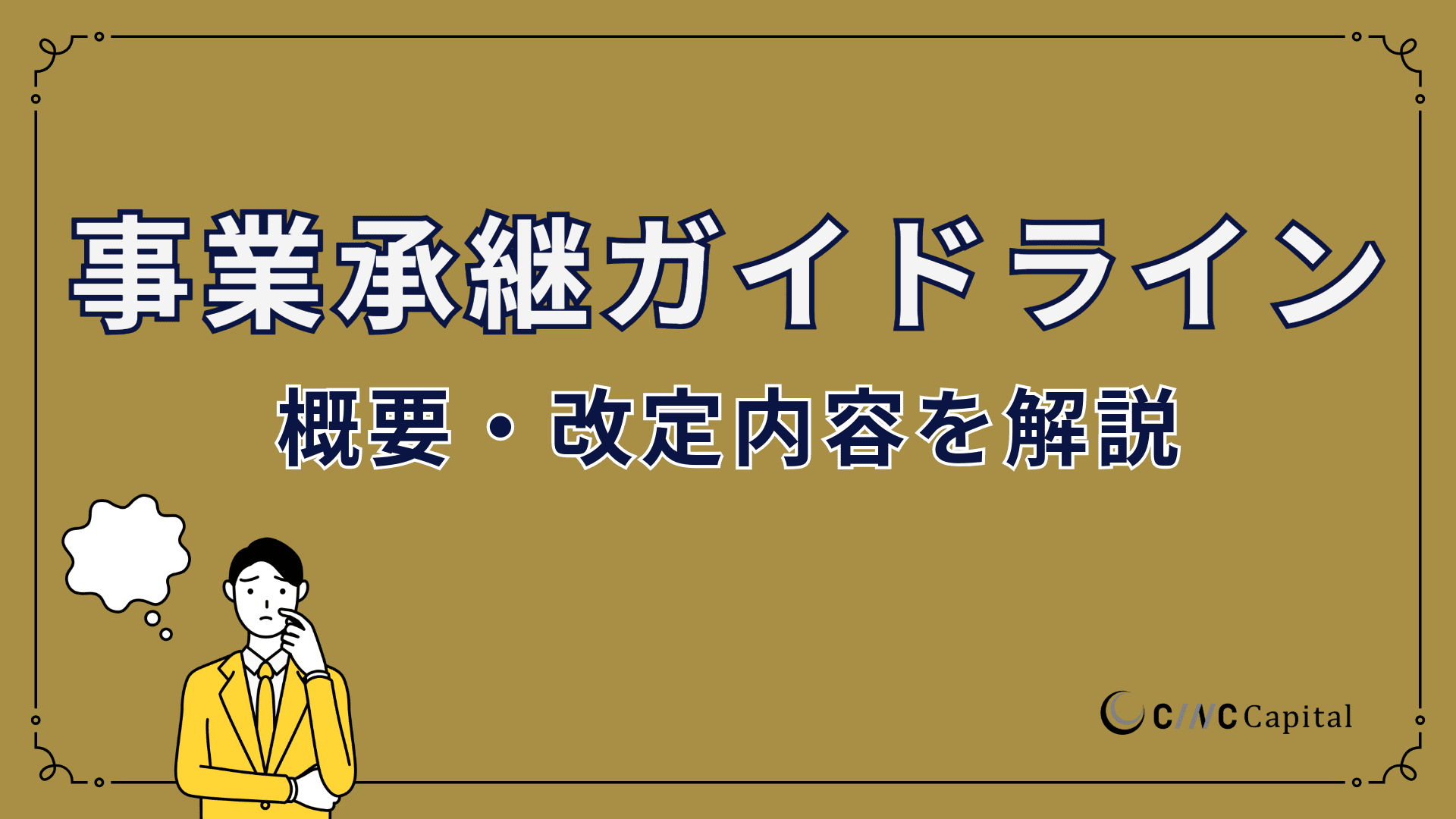
事業承継
- 最終更新日2025.06.26
事業承継ガイドラインの概要を解説!改訂内容や26問26答、事業承継の進め方とは?
事業承継について「何から始めれば良いのかわからない」と悩んでいませんか?特に中小企業の経営者の方にとって、後継者の選定や承継手続きは、経験のない複雑な問題です。
本記事では、「事業承継ガイドライン」の概要と活用法、2022年の改訂ポイント、実際に承継を進めるための5つのステップをわかりやすく解説します。
目次
事業承継ガイドラインとは?
事業承継ガイドラインとは、中小企業庁が策定した、事業承継の進め方を示した指針のことです。経営者が世代交代を進める際に直面する課題を整理し、親族内承継だけでなく従業員や第三者への承継、M&Aも含めて、円滑に進めるための流れを示しています。
事業承継ガイドラインの理解を深めるために、ここでは策定の背景と目的について詳しく解説します。
事業承継ガイドラインの背景
中小企業庁が事業承継ガイドラインを策定した背景には、日本経済の構造的な課題があります。一つは、経営者の高齢化と後継者不足の深刻化、もう一つは承継方法の多様化です。
「中小企業経営者の高齢化」と「後継者不在」の問題
中小企業の経営者の多くが高齢となりながらも、後継者が決まらないまま経営を続けるケースが増えています。中小企業庁では、2025年までに、70歳を超える中小企業の経営者が約245万人となると試算し、そのうち127万人は後継者未定となっています。
このままでは廃業や倒産が相次ぎ、雇用や地域経済への悪影響が避けられません。したがって、事業承継は企業を継続させるための最重要課題といえるでしょう。
【出典】中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」
事業承継の形態が多様化している
かつての事業承継は親族間で行うのが一般的でしたが、近年は承継の形が大きく変化しています。中小企業庁の調査によると、以前は事業承継の主流だった親族内承継の割合が急減し、近年では約3割程度まで減少しています。代わりに、従業員への承継やM&Aによる第三者承継が増加しています。
経営者にとっては選択肢が広がった一方で、それぞれの形態に応じた準備や判断が必要です。事業承継ガイドラインでは、こうした多様な承継スタイルに応じた支援も明記されています。
事業承継ガイドラインの目的
事業承継ガイドラインの目的は、経営者が早期から計画的に事業承継を進められるように支援することです。事業承継は会社の未来を左右する重大なテーマですが、対策が後回しにされることが多いのが実情です。そのため、ガイドラインでは準備の必要性を明示し、事業の見える化や承継計画の作成など、実行すべきステップを整理しています。
これにより、経営者が現実的な選択肢を持ち、着実に次世代に事業を継承できるようになります。
【2022年】事業承継ガイドラインの改訂内容
事業承継ガイドラインは、時代の変化に合わせて定期的に見直されています。特に2022年の改訂では、親族外承継の増加や支援制度の拡充といった背景に対応するため、内容が大幅にアップデートされました。ここでは、改訂の概要と改訂のポイントを紹介します。
改訂の概要
2022年の改訂では、2016年版からの社会環境の変化に対応するため、事業承継に関する支援や実務的なノウハウが大きく見直されました。これまでのガイドラインは主に親族内承継を想定していましたが、近年は親族以外への承継やM&Aの比率が増加しています。
そこで今回の改訂では、親族外承継を中心に、従業員への承継や第三者承継(M&A)についても詳しく解説されるようになりました。このように、多様な承継方法を選択できるよう情報が整理されたことで、どの企業にも実践的に活用できるガイドラインへと進化しています。
改訂のポイント
2022年の事業承継ガイドラインで特に注目すべき点は、従業員承継や第三者承継に関する記載が大幅に強化されたことです。これまでの版では親族承継が主流の想定でしたが、経営環境の変化により、親族以外に承継するケースが増えています。この実情に合わせて、今回の改訂では、従業員に継がせる際の教育や社内外の理解促進についての考え方や留意点が整理されています。
また、M&Aによる承継に関しては、「中小M&Aガイドライン」の内容も反映されており、後継者がいない企業でも活用できる実用性の高い内容です。
事業承継ガイドラインの「26問26答」とは?
事業承継ガイドラインには、「どこから手をつければ良いかわからない」という経営者の声に応えるため、補助資料として「26問26答」が用意されています。これは、事業承継に関する素朴な疑問や不安を26個のQ&A形式でまとめた小冊子で、ガイドラインのポイントを端的に理解できるよう工夫されています。
中小企業経営者の中には、「事業承継=難しいもの」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実際には計画的に進めれば確実に実現が可能です。その理解を促すため、「26問26答」では「なぜ承継対策が必要なのか」「誰に承継すべきか」「どう進めれば良いのか」など、実務で直面しやすいテーマが提示されています。
「26問26答」では、以下のような実務に即した質問が掲載されています。
- Q:事業承継対策で注意しなければならないことは何ですか?
- Q:後継者を決めるにあたっては、どのようなことを考慮すべきでしょうか?
- Q:適切な後継者がいないのですが、どのようにすればよいですか?
- Q:後継者教育は、どのように行えばよいですか?
このようなQ&A形式の資料を活用することで、経営者自身が自社にとって最適な承継方法を検討しやすくなり、ガイドライン全体への理解も深まるでしょう。
【出典】中小企業庁「中小企業事業承継ハンドブック 26問26答 平成21年度税制改正対応版」
事業承継を実現するための5つのステップ
事業承継ガイドラインでは、事業承継を円滑に進めるために「5つのステップ」が提示されています。これは、承継を計画段階から実行段階まで順序立てて進めるためのプロセスであり、親族内承継だけでなく、従業員承継やM&Aにも対応しています。
ここでは、それぞれのステップで何を実行すべきかを具体的に解説します。
事業承継に必要な準備を行う
事業承継を成功させるためには、早期の準備開始が重要です。経営者の中には「まだ先の話」と考える人もいるかもしれませんが、後継者の選定や育成、株式や資産の整理などには年単位の時間が必要になります。
特に後継者が決まっている場合でも、引き継ぎ体制や経営ノウハウの伝承には時間がかかります。そのため、60歳を目安に準備を始めることが望ましく、早めに着手することで企業の未来に安心をもたらすことができるでしょう。
経営状況や経営課題の「見える化」を行う
承継を円滑に進めるには、自社の経営状態を正しく把握することが不可欠です。経営者の頭の中にしかない情報を整理し、財務状況や資産構成、経営課題を明文化することで、関係者全員が状況を共有できるようになります。
特に、後継者や買い手となる相手が社外の人物である場合、第三者に伝わる情報として可視化されていることが重要です。この「見える化」を行うことで、承継後の混乱や誤解を防ぎ、スムーズな引き継ぎが実現します。
事業承継に向けた経営改善を行う
承継前の経営改善は、後継者の負担を減らし、企業価値を高めるために欠かせません。会社の将来性が不透明なままでは、後継者が継ぎたくないと感じてしまったり、M&Aにおける評価額が下がったりするリスクがあります。
M&Aによる第三者承継を考える場合、特に企業価値評価に直結する以下の点の改善が重要です。
- 収益性の改善:不採算事業の整理や利益率の向上は、マルチプル法(EBITDA倍率法)などによる企業価値評価を高める要素です
- 財務体質の強化:過剰な借入金の圧縮や資産の整理は、純資産価値を高め、買い手にとってのリスクを軽減します
- 事業基盤の強化:取引先の分散や安定した受注体制の構築は、将来のキャッシュフローの安定性を示し、評価額の向上につながります
これらの取り組みを行うことで、企業の魅力と信頼性を高め、より有利な条件での事業承継が可能になります。また、買い手側からのデューデリジェンス(買収監査)で問題が発見されるリスクも減らせます。
事業承継計画の策定や事業承継ファンドなどとのマッチングを行う
事業承継の方向性が固まったら、次に行うべきは承継計画の策定と支援機関との連携です。親族や社内に後継者がいる場合は、具体的なスケジュールや資産の移転手順、関係者との調整方法を盛り込んだ計画書を作成します。
一方、後継者がいない場合は、第三者承継(M&A)を視野に入れ、仲介会社や事業承継ファンドと連携して適切な買い手とのマッチングを進めます。こうした計画と連携により、承継が一過性のイベントではなく、企業成長の一環として確実に実行できるようになるでしょう。
事業承継計画やM&A手続きに沿って実施する
承継の準備と計画が整ったら、いよいよ実行段階に移ります。親族内承継の場合は、株式の譲渡や経営権の移転、代表者変更など、計画に沿って法的・実務的な手続きを進めます。
M&Aによる第三者承継の場合は、以下の流れで進めることが一般的です。
- 秘密保持契約の締結
- 買収監査(デューデリジェンス)の実施
- 基本合意書の締結
- 最終契約書の締結
- クロージング(決済)
この段階では、M&A仲介会社や弁護士、税理士、公認会計士などの専門家のサポートを受けながら、契約書の整備や税務対応、許認可の名義変更などを慎重に進めることが求められます。
特にM&Aでは、株式譲渡と事業譲渡の選択によって税務上の取り扱いも大きく異なるため、専門家の助言が不可欠です。実施が完了すれば、新体制のもとで企業は再出発でき、承継の目的が具体的に達成されます。
まとめ|事業承継ガイドラインを活用し、円滑に引き継ぎましょう
事業承継は中小企業の存続と発展に欠かせない重要な経営課題です。事業承継ガイドラインを活用することで、経営者は何をいつ実行すべきかが明確になり、親族内外を問わず円滑な引き継ぎが可能になります。
特に、5つのステップに沿って準備・改善・計画・実行を進めることで、企業価値を維持しながら次世代へとつなぐことができます。将来の不安を減らし、持続可能な経営を実現するためにも、早期の着手を行いましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。