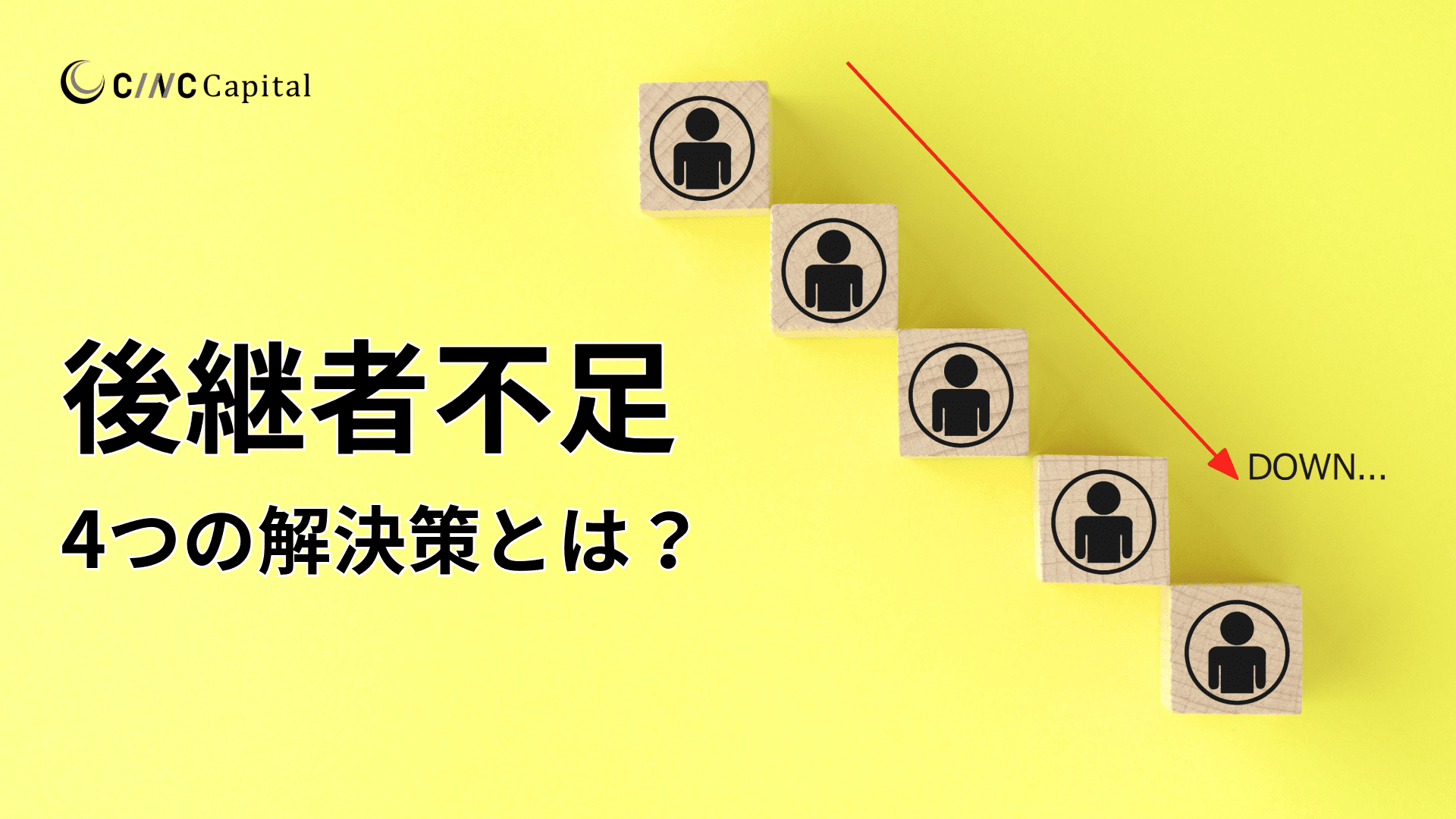CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / スキーム
- 最終更新日2025.10.16
【2025年】日本企業の買収動向は?今後の展望や買収額ランキング事例を解説
近年は市場の変化が激しく、多くの企業が成長戦略の一環としてM&Aを活用しています。
本記事では、日本の企業買収市場の現状や、過去に行われた大規模なM&A事例を紹介しながら、企業買収がもたらす影響やメリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次
日本の企業買収の動向は?【2025年】
2025年の日本における企業買収市場は、近年の流れを受け継ぎ、活発な動きを見せています。ここでは、日本の企業買収市場の現状を整理し、買収が増加している背景や今後の展望について解説します。
日本の企業買収市場の現状
日本の企業買収市場は拡大の傾向が続いており、2024年には国内外のM&A件数が4,700件を超え、前年より17.1%増加しました。この成長の要因には、企業の成長戦略としてM&Aが一般的になったことや、事業承継型の買収が増加したことが挙げられます。
また、M&Aの取引規模も拡大しており、2024年のM&A総額は約6兆円に達しました。特にデジタル技術の進化に伴い、IT分野やDX関連の企業買収が増えています。
日本企業の買収が増加している背景
日本企業による買収が増加している背景には、いくつかの要因があります。
理由の一つは、中小企業の後継者不足です。2025年までに70歳以上の経営者が約245万人に達すると予測されており、そのうち半数が後継者を確保できていません。
また、国内市場の成長が鈍化するなか、企業が持続的に成長するためには、新たな収益源の確保が不可欠です。特に、新規市場への参入や技術革新を目的として、異業種企業の買収が増えています。
さらに、デジタル技術の進化を背景に、AIやIoT関連の企業を買収するケースが増加しています。
日本の企業買収の今後の展望
今後も日本のM&A市場は成長を続けると予測されます。特にDX関連の企業買収が拡大し、IT・通信分野の企業が積極的にM&Aを進めると考えられます。
また、海外市場への進出を目的とした日本企業による海外企業の買収(海外M&AやクロスボーダーM&A)が増加する可能性も高いです。
加えて、M&Aの手法も多様化しており、従来の企業買収だけでなく、資本業務提携やジョイントベンチャーを活用した戦略が増えています。
これにより、より柔軟な事業統合が可能となり、M&Aの重要性は今後さらに高まるでしょう。
【事例】日本企業の歴代買収額ランキングTOP5社
日本企業が過去に行った企業買収の中で、特に大規模なものを5社、ランキング形式で紹介します。それぞれの買収の背景や影響についても解説します。
1位:武田薬品工業によるシャイアー社の買収(2018年)
武田薬品工業は、2018年にアイルランドの製薬企業シャイアーを約6.8兆円で買収しました。これは、日本企業による過去最大のM&Aであり、武田薬品のグローバル競争力を高める戦略的な決断でした。
買収の目的は、シャイアーが持つ希少疾患や血液疾患治療薬の強化と、国際市場での存在感を拡大することでした。シャイアーはバイオ医薬品分野で強みを持ち、買収によって武田薬品の事業ポートフォリオが多様化しました。
一方で、巨額の買収資金を調達するために多額の負債を抱えたことで、財務の健全性が懸念される状況になったのです。結果として、武田薬品はグローバル製薬市場での競争力を大きく向上させることに成功しましたが、財務の健全化に向けたコスト削減や資産売却が必要になりました。
今後の経営戦略が、このM&Aの成否を決める重要な要素となっています。
2位:ソフトバンクグループによるArmの買収(2016年)
ソフトバンクグループは、2016年にイギリスの半導体設計会社Armを約3.3兆円で買収しました。これは、ソフトバンクが次世代のIoT(モノのインターネット)分野で主導権を握るための戦略的な動きでした。
Armは、スマートフォンや組み込み機器向けの半導体設計技術を提供する企業であり、世界中の多くのメーカーがその技術を採用しています。ソフトバンクは、この買収によって半導体分野への影響力を強めることを目指しました。
しかし、半導体業界の競争激化や市場環境の変化により、Armの成長戦略を見直す必要が生じました。その結果、2023年にはArmを再上場させる方針を決定し、一部の株式を市場に売却する形で資金回収を進めています。
3位:ベインキャピタルによる東芝メモリの買収(2017年)
2017年、東芝は主力事業である半導体メモリ部門(東芝メモリ)を売却しました。買収額は約2.3兆円で、アメリカの投資ファンド「ベインキャピタル」を中心とする日米韓連合が買収を主導しました。
この買収の背景には、東芝の財務状況の悪化がありました。米国の原子力事業で多額の損失を出した東芝は、経営再建のために資産売却を進める必要がありました。東芝メモリはNAND型フラッシュメモリ市場で強い競争力を持つ企業だったため、買収をめぐって多くの企業が関心を示しました。
結果として、東芝メモリは「キオクシア」として再編され、成長を続けています。しかし、外資系ファンドによる買収であったため、今後の経営の独立性や長期的な戦略が課題として残っています。
4位:日本たばこ産業株式会社によるギャラハーの買収(2006年)
日本たばこ産業(JT)は、2006年にイギリスのたばこメーカー「ギャラハー」を約2.25兆円で買収しました。これは、国内市場が縮小する中で海外事業を拡大するための戦略的な決断でした。
ギャラハーは、欧州を中心に強いブランド力を持つ企業であり、JTはこの買収によって海外売上比率を大幅に向上させました。特に、イギリスやドイツなどの市場でのシェア拡大が進み、グローバルなたばこ市場での競争力が高まっています。
一方で、たばこ市場は規制の影響を強く受ける業界であり、買収後も市場環境の変化に対応する必要がありました。JTは、事業の多角化や製品開発を進めながら、持続的な成長を目指しています。
5位:セブン&アイHDによるスピードウェイの買収(2020年)
セブン&アイ・ホールディングスは、2020年にアメリカのガソリンスタンド併設型コンビニチェーン「スピードウェイ」を約2.2兆円で買収しました。この買収の目的は、北米市場での事業拡大です。
スピードウェイは、当時アメリカ36州で約3,900店舗を展開する業界第3位のコンビニチェーンであり、セブン&アイはこの買収によってアメリカでの市場シェアを大幅に拡大しました。結果として、アメリカ内の7-Elevenの店舗数は約14,000店に達し、競合他社との差を広げることができたのです。
しかし、大型買収による統合には時間を要し、買収後の経営効率の向上が課題となっています。競争が激化する米国市場において、セブン&アイがどのように成長戦略を進めるかが注目されています。
企業買収がもたらす影響とは?
企業買収は、買収を行う企業と買収される企業の双方にさまざまな影響をもたらします。特に、経営戦略の変化や株価の変動、ブランド価値への影響が大きく、買収の成功可否を左右する重要な要素です。
ここでは、企業買収がもたらす影響について解説します。
経営
企業買収は、買収を行う企業の成長戦略の一環として用いられることが多く、新たな市場への参入や事業の拡大を可能にします。
買収によって経営資源を獲得できる点は大きなメリットです。例えば、武田薬品工業がシャイアーを買収した際、希少疾患治療薬のポートフォリオが拡充され、グローバルな競争力が強化されました。しかし、巨額の買収による財務負担が重くのしかかり、コスト削減のためのリストラや資産売却が必要となりました。
一方で、企業文化や経営スタイルの違いから組織がまとまらず、業績低迷を招くこともあります。特に国際的な買収では、意思決定のスピードや事業の優先順位が異なるため、統合がうまくいかないケースが少なくありません。
したがって、買収の成功には事前の戦略設計と慎重な統合プロセスの実施が求められます。
株価
企業買収が発表されると、買収する側と買収される側の株価に大きな影響を及ぼします。市場は買収を評価し、成長が期待される場合には株価が上昇し、逆に財務負担の増加やシナジー効果が疑問視される場合には株価が下落することがあります。
例えば、ソフトバンクグループがArmを買収した際、市場は技術分野への進出を評価しましたが、一方で巨額の投資負担を懸念し、短期的には株価が低下しました。同様に、セブン&アイ・ホールディングスがスピードウェイを買収した際も、海外展開の加速が期待された一方で、高額な買収費用が経営リスクと見なされ、株価が一時的に下落しました。
買収が成功するかどうかは、企業が買収後に適切な統合を進め、期待された成長を実現できるかにかかっています。そのため、買収前には市場環境や財務リスクを十分に分析し、株主や投資家の理解を得ることが重要です。
ブランド
企業買収はブランド価値にも大きな影響を与えます。買収先企業のブランドを活用し、新たな市場を開拓することができる一方で、統合の仕方によってはブランド価値の低下や顧客の離反を招くリスクがあります。
日本たばこ産業(JT)がギャラハーを買収した際には、欧州市場でのブランド力を強化し、競争力を高めることができました。ギャラハーが持つブランドを維持しながら、JTの販売網を活用することで、相乗効果が生まれた好例です。しかし、企業買収後にブランドの統合がうまくいかなかった場合、市場での認知度が低下し、競争力を失うこともあります。
また、買収によって従来のブランドイメージが変化することもあります。例えば、セブン&アイ・ホールディングスによるスピードウェイの買収では、アメリカ市場でのブランド戦略が課題となりました。消費者に受け入れられる形でブランドを調整できなければ、買収のメリットを十分に発揮できない可能性があります。
このように、買収後のブランド管理が成功すれば、市場でのシェア拡大や収益向上につながりますが、ブランド価値を損なうリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
企業買収のメリットとデメリット
企業買収は、新たな市場への参入や事業拡大の手段として、多くの企業が積極的に活用しています。しかし、すべての買収が成功するわけではなく、経営上のリスクも伴います。
ここでは、企業買収のメリットとデメリットについて解説します。
企業買収のメリット
企業買収には、事業拡大や競争力強化などの大きな利点があります。特に、既存の市場や技術を短期間で獲得できる点が大きな魅力です。自社にない技術や資産を迅速に手に入れることで、競争力を高めることができます。
また、規模の経済を活用し、コスト削減を実現できることも大きな利点です。統合後に重複する業務を削減することで、効率的な経営が可能になります。さらに、新たな市場への参入がスムーズに行える点もメリットです。日本たばこ産業(JT)がギャラハーを買収したことで、欧州市場における販売網を強化できたように、海外進出の際に買収が効果的な手段となるケースが多く見られます。
このように、企業買収は適切に行えば、成長を加速し、競争力を向上させる有効な手段となります。
企業買収のデメリット
企業買収には多くのメリットがありますが、リスクも伴います。大きなデメリットの一つは、財務負担の増大です。
例えば、武田薬品工業がシャイアーを買収した際、6.8兆円という巨額の負債を抱えることになりました。このように、大型買収では資金調達の負担が増し、財務の健全性が低下するリスクがあります。
また、企業文化の違いによる統合の難しさも課題となります。異なる組織が一つにまとまるには時間がかかり、場合によっては優秀な人材が流出することもあります。特に海外企業を買収した場合、経営方針の違いが障害となることが多く、統合の失敗が買収そのものの価値を損なう要因になるのです。
さらに、ブランド価値の低下も懸念されます。消費者にとって馴染みのあるブランドを変更すると、顧客離れが発生する可能性があるため、慎重なブランド戦略が求められます。
まとめ
企業買収は、成長戦略の一環として多くの企業に活用されています。日本企業による過去の大型買収事例からも、競争力強化や市場拡大を目的としたM&Aが積極的に行われてきたことがわかります。
一方で、買収には財務負担の増大や統合の難しさといったリスクも伴います。成功のためには、買収後の統合戦略やブランド維持、経営の安定化が欠かせません。
今後もM&Aは企業の成長を左右する重要な手段となるため、戦略的な意思決定と慎重なリスク管理が求められます。適切な買収を行い、長期的な視点で経営を進めることが、企業価値の向上につながるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。