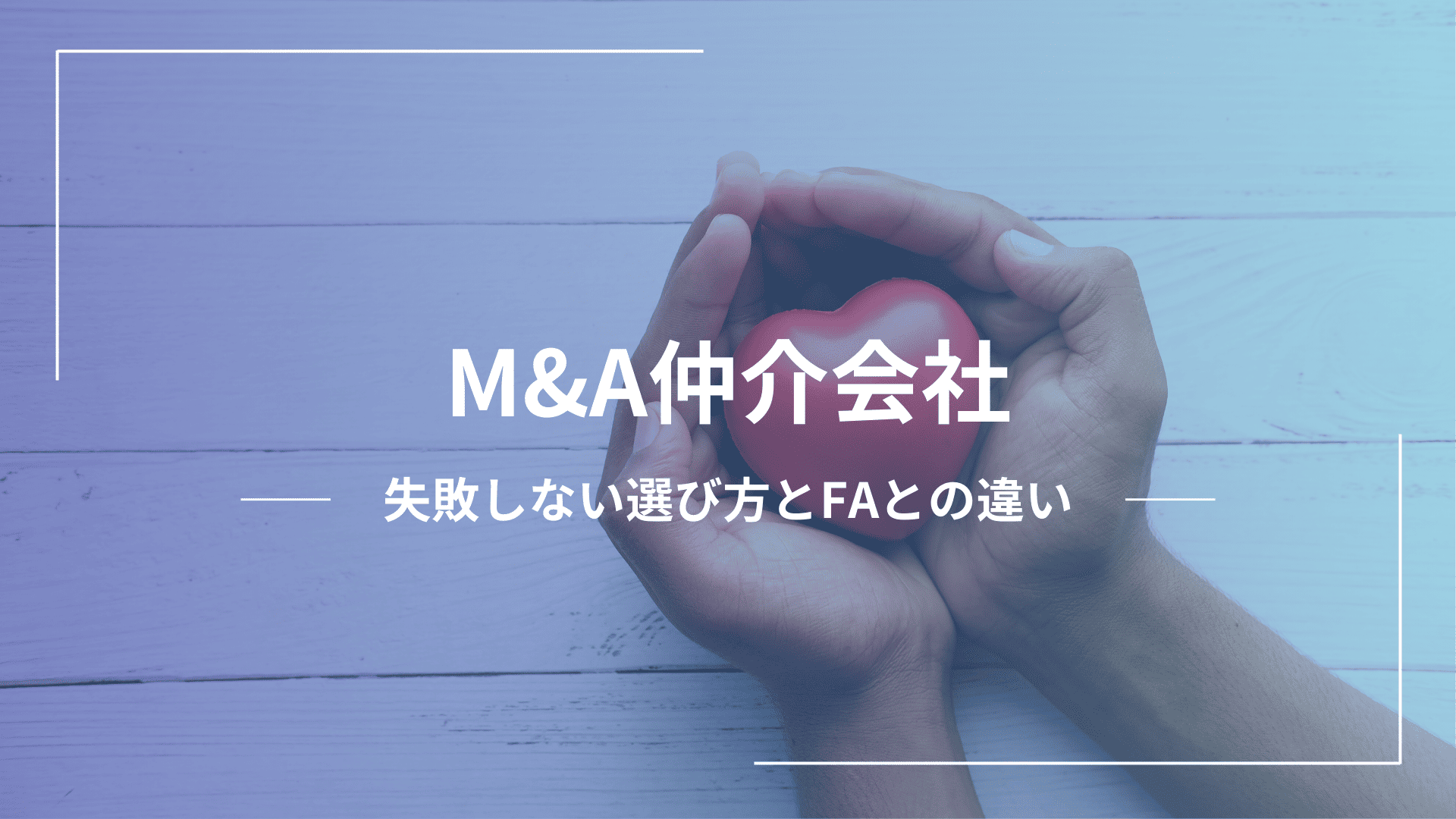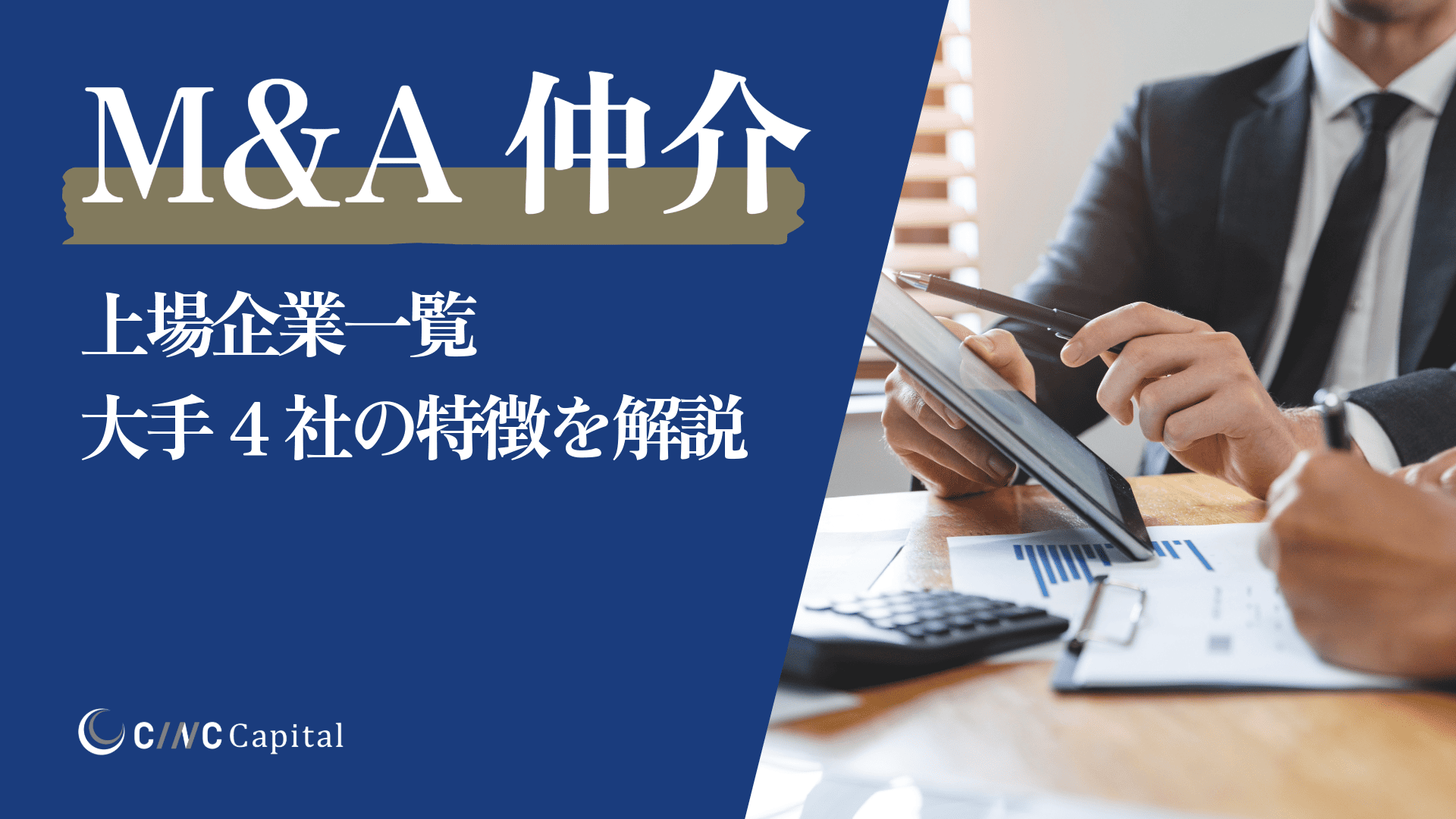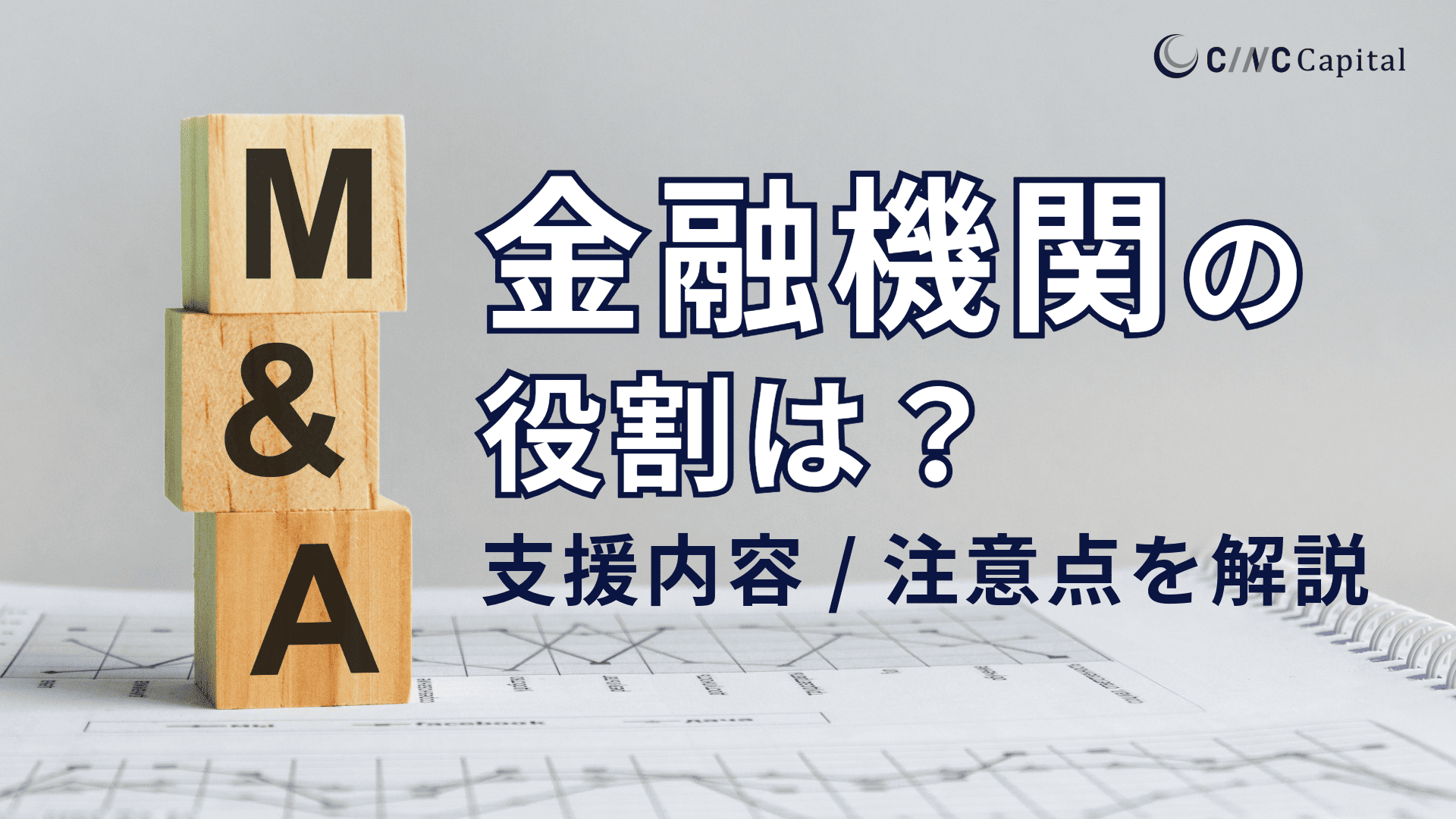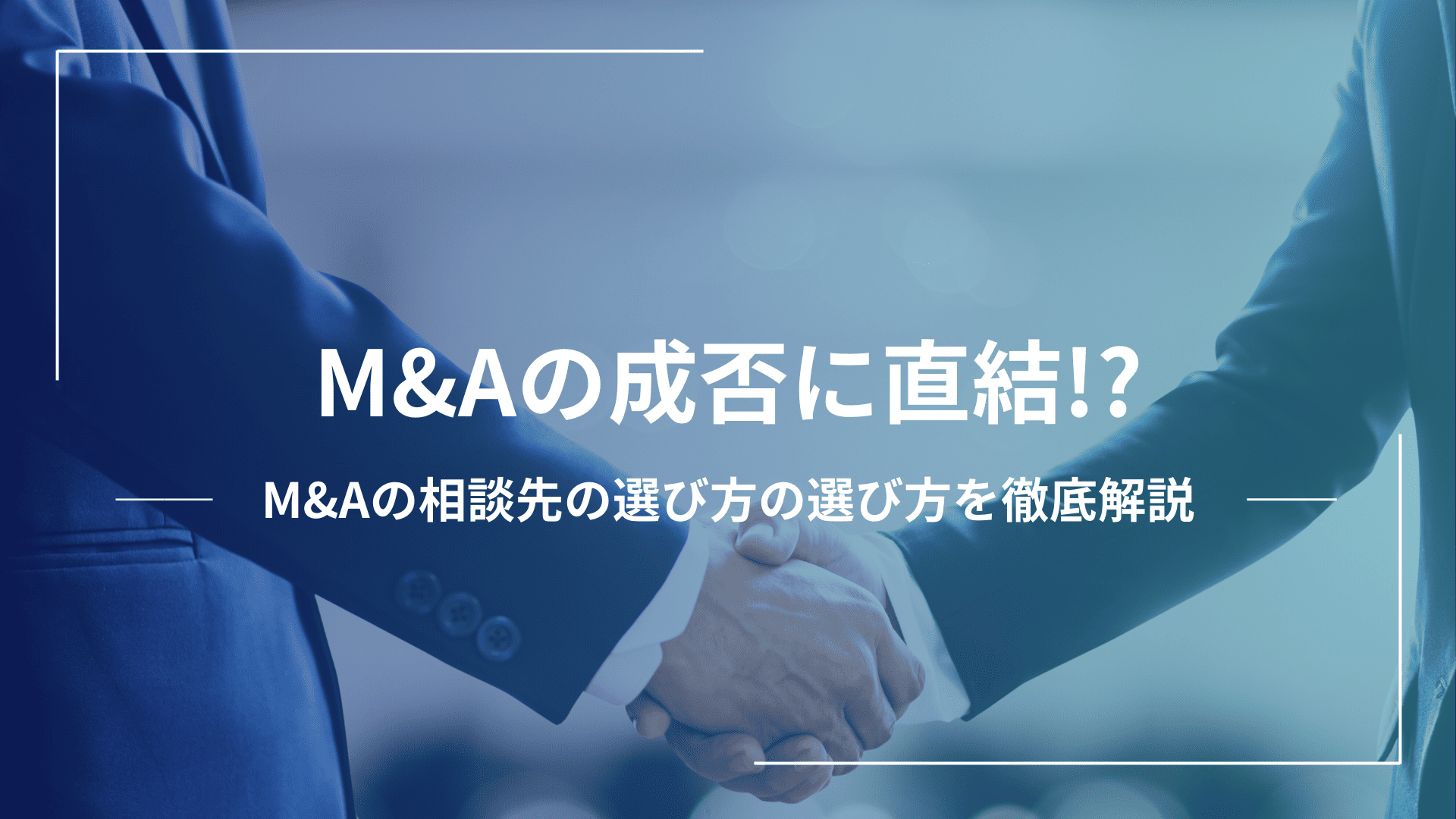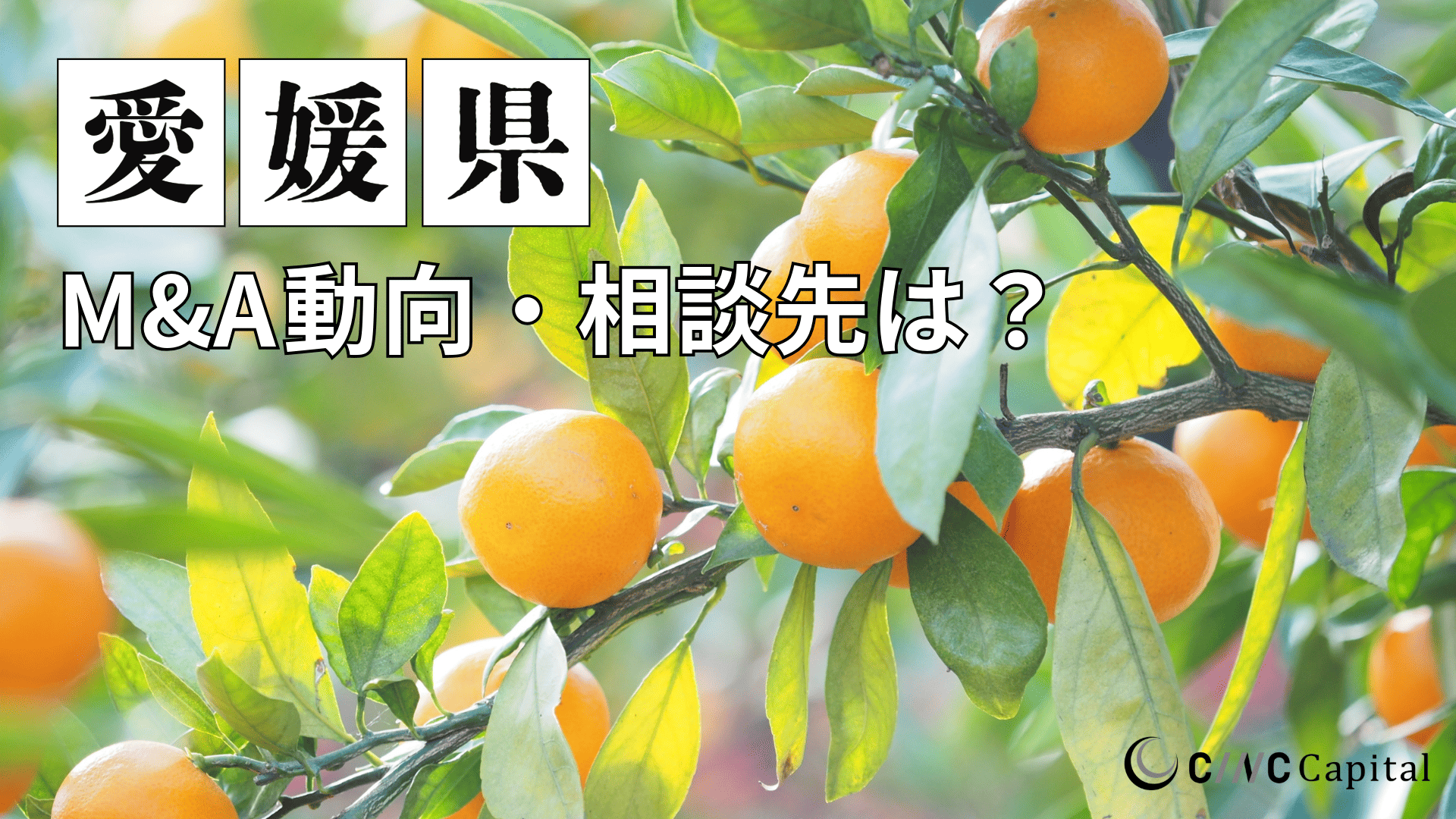CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

エリア
- 公開日2025.09.17
高知県のM&Aや事業承継の動向は?事例や信頼できる相談先/M&Aを進める時の注意点を解説
地域経済を支える多くの中小企業が、近年大きな岐路に立たされています。それは高知県も例外ではなく、経営者の高齢化や後継者不在といった課題が深刻化しているのが現状です。
そこで昨今は、自社存続と地域産業の維持を目的としたM&Aの活用が広がりつつあります。M&Aとは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略で、企業同士が統合したり、他社の経営権を引き継いだりする手法です。
この記事では、高知県におけるM&Aの実情や成功事例、信頼できる相談先、実際に進める際の注意点をわかりやすく解説します。
目次
高知県のM&Aや事業承継の最新動向【2025年】
高知県では近年、人口減少・経営者の高齢化による後継者不在という課題に対応するため、中小企業の事業承継が注目されています。
ここでは、高知県のM&A最新動向をご紹介します。
人口減少にともなう事業承継問題の深刻化
高知県の推計人口は68万4,049 人(令和3年10月1日時点)で、四国4県の中でもっとも人口が少ない県です。加えて、人口減少率が高く、地域全体で過疎化が急速に進行しています。
ビジネスシーンでは人材の確保がいっそう難しくなり、経営人材の不足や市場の縮小が企業活動に深刻な影響をおよぼしています。
また、「株式会社帝国データバンク」の調査によれば、2024年における高知県の後継者不在率は60.0%に達しており、全国平均の52.1%を大きく上回っています。人口減少や後継者の確保の問題が、地域の中小企業を存続させるうえで大きな壁となっているのが現状です。
【出典】株式会社帝国データバンク「四国地区『後継者不在率』動向調査(2024年)
【出典】高知県「高知県の推計人口年報(令和3年)」
一次産業を中心とした地域密着M&Aの広がり
高知県が公表した「令和5年版 高知県の農林水産業の概要」によると、県内総生産に占める一次産業の割合が3.6%、就業者のうち一次産業に従事する人の割合は10.2%と、全国第2位の水準です。
農業や漁業などの一次産業が地域経済の柱となっていることから、事業の後継者不足や高齢化への対応策として、M&Aの活用が広がりを見せています。
例えば、農業分野では、土佐文旦やゆずなど高知県の特産品を扱う生産・加工・販売事業者のあいだで、M&Aによる事業継承が注目されています。漁業分野も同様に、カツオの一本釣りなど伝統的な漁法を持つ事業者が、技術やノウハウを次世代につなぐ手段としてM&Aを活用する動きがあります。
高知県でM&Aや事業承継の相談どこにする?
自社のM&Aや事業承継について「どこに相談すればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、高知県でM&Aに関する相談ができる3つの窓口をご紹介します。
M&A仲介会社に相談する
まず挙げられるのが、事業承継などのスペシャリストであるM&A仲介会社です。
地域産業や経営環境に詳しい仲介会社を選ぶことで、農業や漁業、観光業といった高知県ならではの業種にも対応した、理想的な提案を受けやすくなります。
実績のある仲介会社であれば、譲渡先の選定から交渉、契約締結まで一貫したサポートを受けられる点も魅力です。
金融機関や公的機関を利用する
地方銀行や信用金庫のほか、各種公的機関も、M&Aや事業承継を支援しています。
これらの機関では、無料で相談を受け付けており、資金調達や補助金の活用についても具体的なアドバイスが得られます。
事業承継に関する幅広い支援を受けたい場合、公的なサポート機関を活用するといいでしょう。
M&Aマッチングサイトで探す
オンラインで売り手・買い手をつなぐM&Aマッチングサイトも、有効な選択肢のひとつです。
高知県では特に、一次産業や観光業に関心をもつ本土企業からの引き合いが多く、こうしたサイトを通じて県外とのマッチングが成立するケースも見られます。
匿名で情報を掲載できるサービスもあり、自社の状況に合わせて柔軟に活用できるのがポイントです。
高知県で信頼できるM&A・事業承継の相談先一覧
ここでは、高知県内でM&Aについて相談できる、信頼性の高い機関やサービスを紹介します。
高知県事業承継・引継ぎ支援センター
中小企業庁の支援のもと設置されている公的機関で、事業承継やM&Aに関する無料相談を受けつけています。
県内の中小企業の経営者、後継者不在で悩む企業に対し、専門家が親身に対応しています。
高知県よろず支援拠点
中小企業や小規模事業者の経営課題解決を総合的にサポートする公的機関であり、事業承継の相談にも対応しています。
創業予定者から既存事業者まで、さまざまな段階の企業に対して適切な解決策を提案しています。
【参考】高知県よろず支援拠点
高知県商工会議所(高知県事業承継ネットワーク)
商工会議所が事務局を務める「高知県事業承継ネットワーク」では、行政機関・商工団体・金融機関・士業などが連携し、中小企業の事業承継を支援する体制が整えられています。
地域経済を支える中核的な組織として、事業承継に加えて創業支援や融資相談、経営改善のアドバイスまで、幅広い課題まで対応してくれます。
高知県信用保証協会
中小企業の資金調達を支援するために、公的な保証人としての役割を担っている機関です。
M&Aや事業承継を進める際に融資が必要な場合でも、信用保証協会が保証を行うことで、金融機関からの融資をスムーズに受けやすくなります。
【参考】高知県信用保証協会
CINC Capital
「CINC Capital」は、マーケティングテクノロジーとデータ分析の専門知識を活かしたM&A仲介会社です。
独自のビッグデータとAI技術を活用したマッチングシステムにより、高知県内の企業に最適な譲渡先・譲受先を提案しています。
【参考】CINC Capital
高知県のM&Aや事業承継の事例
高知県のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
テクノホライゾン株式会社による株式会社アイネッツコムのM&A
テクノホライゾン株式会社は2024年11月、IT技術者派遣や運用サポートを手がける株式会社アイネッツコム(高知市)の全株式を取得しました。アイネッツコムは四国エリアを中心に活動しており、経験豊富なエンジニアを擁する地域密着型企業です。
一方、テクノホライゾンは「映像&IT」と「ロボティクス」を強みに、教育・安全・医療・FA分野へ幅広く展開しています。今回の買収により、同社の全国的な営業網や学校・自治体向けの実績と、アイネッツコムの技術者派遣力を掛け合わせることで、既存顧客の深耕や新規需要の開拓が期待されます。
外部成長の観点では、地方の専門人材を取り込みつつ、首都圏や全国へのサービス拡充を図る動きと位置付けられ、今後の地域IT人材不足への対応力強化につながる事例といえます。
【出典】テクノホライゾン株式会社「株式会社アイネッツコムの株式取得に関するお知らせ」
セーラー広告株式会社による株式会社メディア・エーシーのM&A
2024年10月、香川県高松市に本社を置くセーラー広告株式会社は、株式会社メディア・エーシーを株式譲渡により完全子会社化しました。メディア・エーシーは1996年創業以来、マス媒体の取り扱いに加え、販促ツールや印刷物、Web関連事業を幅広く展開し、安定した顧客基盤を築いてきました。
しかし、さらなる成長には営業力や企画提案力の強化が課題となっており、地域密着型で広告事業を展開するセーラー広告のグループ入りを選択しました。今後はセーラー広告の持つ提案力やノウハウを活用することで、事業基盤の強化と発展を目指す方針です。
外部成長戦略の一環として、地方広告代理店同士の連携によりサービスの質を高める動きは、地域市場における競争力確保の有効な手段といえます。
【出典】株式会社メディア・エーシー「セーラー広告株式会社への株式譲渡と完全子会社化のご報告」
小野建株式会社による株式会社ヤマサのM&A
2022年11月、小野建株式会社(東証プライム・福証上場)は、高知県高知市に本社を置く株式会社ヤマサの株式を取得し、議決権比率70.4%で連結子会社化しました。ヤマサは四国地方で鉄鋼や土木建築資材の販売、施工請負を展開し、地域に根ざした営業基盤と安定した業績を有する企業です。
小野建は「販売エリアの拡大」と「シェア向上」を成長戦略に掲げており、今回の子会社化により四国一円での営業体制を強化するとともに、高知県を物流拠点として顧客サービスの向上を図ります。
鉄鋼流通業界では、地域有力企業の取り込みを通じた商圏拡大の動きが加速しており、本件も同社の広域ネットワーク強化と企業価値向上に資する事例といえます。
【出典】小野建株式会社「株式会社ヤマサの株式取得(連結子会社化)に関するお知らせ 」
M&Aや事業承継を進めるときの注意点
ここでは、高知県で売却を検討している経営者が押さえておきたい注意点を紹介します。
地元ニーズや業種動向を見極める
農業・漁業・観光など地域に根ざした事業では、ブランド力や伝統技術などの無形資産が評価されることがあります。
自社の強みを客観的に整理し、どの資産が買い手にとって価値があるのかを明確にしておきましょう。
また、県内企業と県外企業では重視するポイントが異なる場合があります。
買い手が何を求めているかを想定し、財務情報や人材、地域とのつながりなど、適切な情報を丁寧に開示することが大切です。
公的支援や補助制度を活用する
高知県では、M&Aに関する県独自の補助制度が整備されています。
例えば、令和6年度から始まった「高知県事業承継奨励給付金」は、M&Aにかかる専門家費用の一部を行政が補助する制度で、資金面の負担を軽減できる点が魅力です。
こうした制度を活用すれば、コストを抑えながらM&Aを進めることが可能になります。
とはいえ、M&Aの実務は煩雑かつ専門性が高いものとなります。
補助制度の活用を考慮しつつも、やはり経験豊富なM&A仲介会社に相談するのが、もっとも確実な方法といえるでしょう。
適切な専門家に相談する
M&Aは会社の将来を左右する大きな決断であり、実施にあたっては、専門知識や交渉力が求められます。
特に売り手側にとっては、企業価値の算定や秘密情報の管理、買い手との条件交渉など、専門家のサポートが必要となる場面が多くあります。
こうした複雑なプロセスを、社内のリソースだけで乗り切るのは現実的ではありません。
M&Aの経験が豊富な専門家に、早い段階で相談することが、失敗を避ける最大のポイントといえるでしょう。
M&Aや事業承継を検討する際に知っておきたい基礎知識
M&Aは、中小企業にとっても事業継続や成長の有力な手段です。
とはいえ、「そもそもM&Aとは何か」「どんな方法があるのか」「費用はどのくらいかかるのか」など、基本的な疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、M&Aを初めて検討する方に向けて、よくある疑問に簡潔にお答えします。
M&Aと事業譲渡の違いはなんですか?
M&Aとは、「企業の合併や買収」の総称です。その中に含まれる手法の一つが「事業譲渡」となります。
2つの用語は混同されやすいものの、M&Aが包括的な枠組みであるのに対して、事業譲渡はその中の一つの手段であり、明確な違いがあります。
【関連記事】M&Aとは?意味や目的、手法ごとのメリットデメリットをわかりやすく解説
M&Aのメリットとデメリットはなんですか?
最大のメリットは、後継者問題の解消や経営資源の引き継ぎができる点です。
高知県のように少子高齢化が進んでいる地域では、後継者が見つからないケースも多く、M&Aが事業を次世代へつなぐ有効な手段となっています。
一方で、買い手との条件交渉や従業員・取引先への配慮が必要であり、進め方によっては混乱を招くおそれもあります。
こうした点も事前に理解しておくことが大切です。
【関連記事】M&Aのメリットとデメリットは?買い手と売り手の立場別にわかりやすく解説
M&Aの相場はどのくらいですか?
M&Aの価格は、企業の業種や規模、財務状況などによって大きく異なります。
代表的な算定方法には以下のようなものがあります。
- 時価純資産+営業権(のれん):中小企業でよく使われる方法
- マルチプル法:EBITDA(税引前利益+減価償却費)などに倍率をかける方法
- DCF法:将来キャッシュフローを現在価値に割り戻す方法
なお、DCF法は通常、上場企業やスタートアップ企業で使われる算定方法です。
M&Aへ向けて自社の企業価値を知りたい方は、以下のページから「企業価値算定シミュレーション」をご利用ください。
【参考】企業価値算定シミュレーション
M&Aでおすすめの相談先はどこですか?
M&Aを進める際は、実績のあるM&A仲介会社などの専門家に相談するのが一般的です。
高知県のように地域特性の強いエリアでは、第一次産業や観光業に理解のある専門家を選ぶことが、スムーズなマッチングのカギになります。
公的機関などは無料で相談できるため、情報収集の初期段階では有効でしょう。
ただし、実務的な支援や買い手候補の紹介まで含めて考えるなら、地域に精通したM&A仲介会社に相談するのが確実です。
【関連記事】M&Aはどこに相談する?相談先の選び方やメリットデメリットを解説
まとめ|高知県のM&Aのポイント
高知県では、後継者不足や人口減少を背景に、事業承継の動きが広がっています。
売却を検討する際は、地域特性や業種の状況を踏まえたうえで、最適なタイミングと手法を見極めることが大切です。
まずは、確かな実績を有するM&A仲介会社に相談してみましょう。
「CINC Capital」はM&A仲介協会会員・中小企業庁の登録支援機関です。
業界歴10年以上の専門家が、譲渡や買収の目的に応じて適切な手法をご提案します。
秘密厳守でスムーズな取引を支援します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。