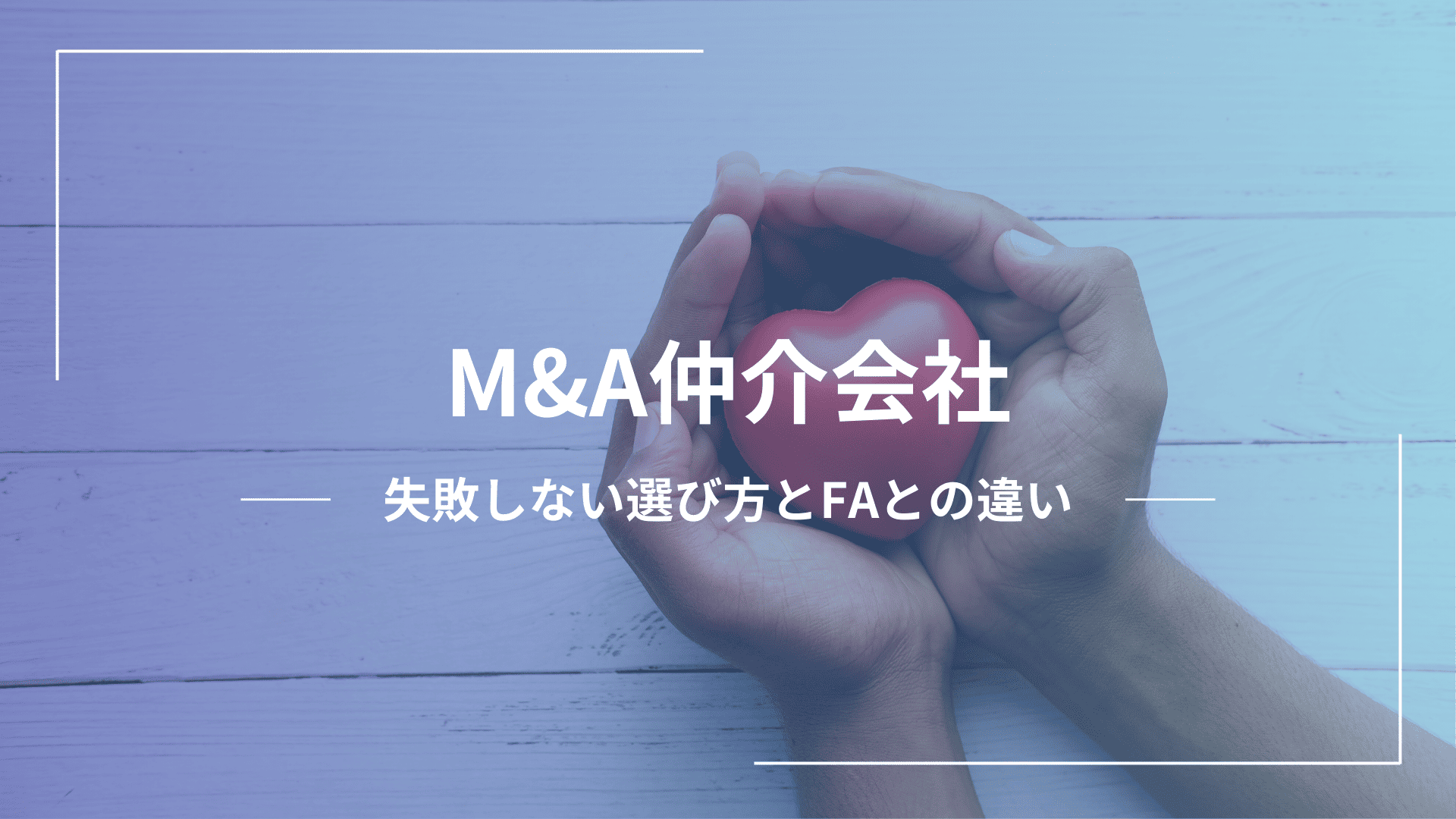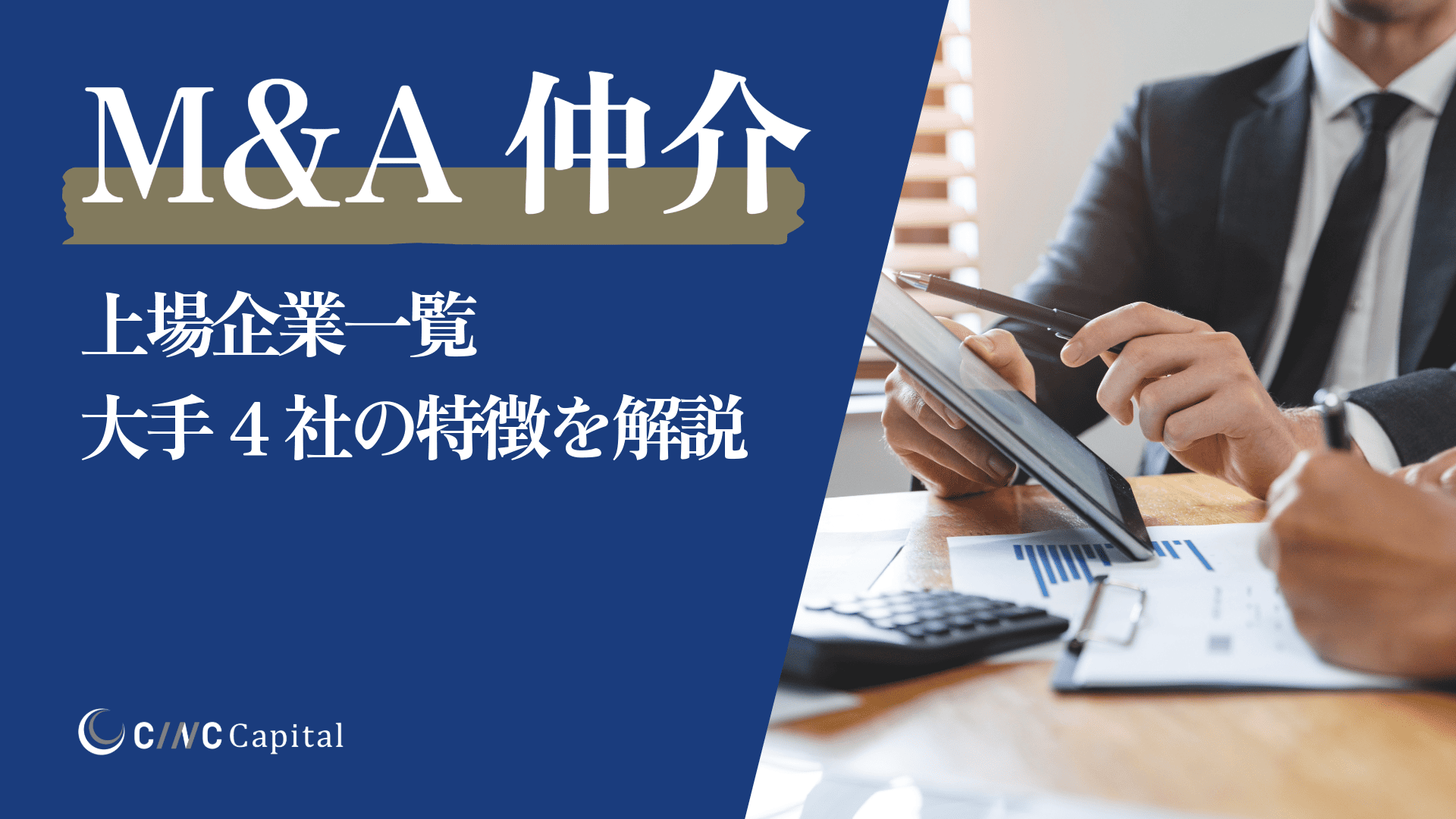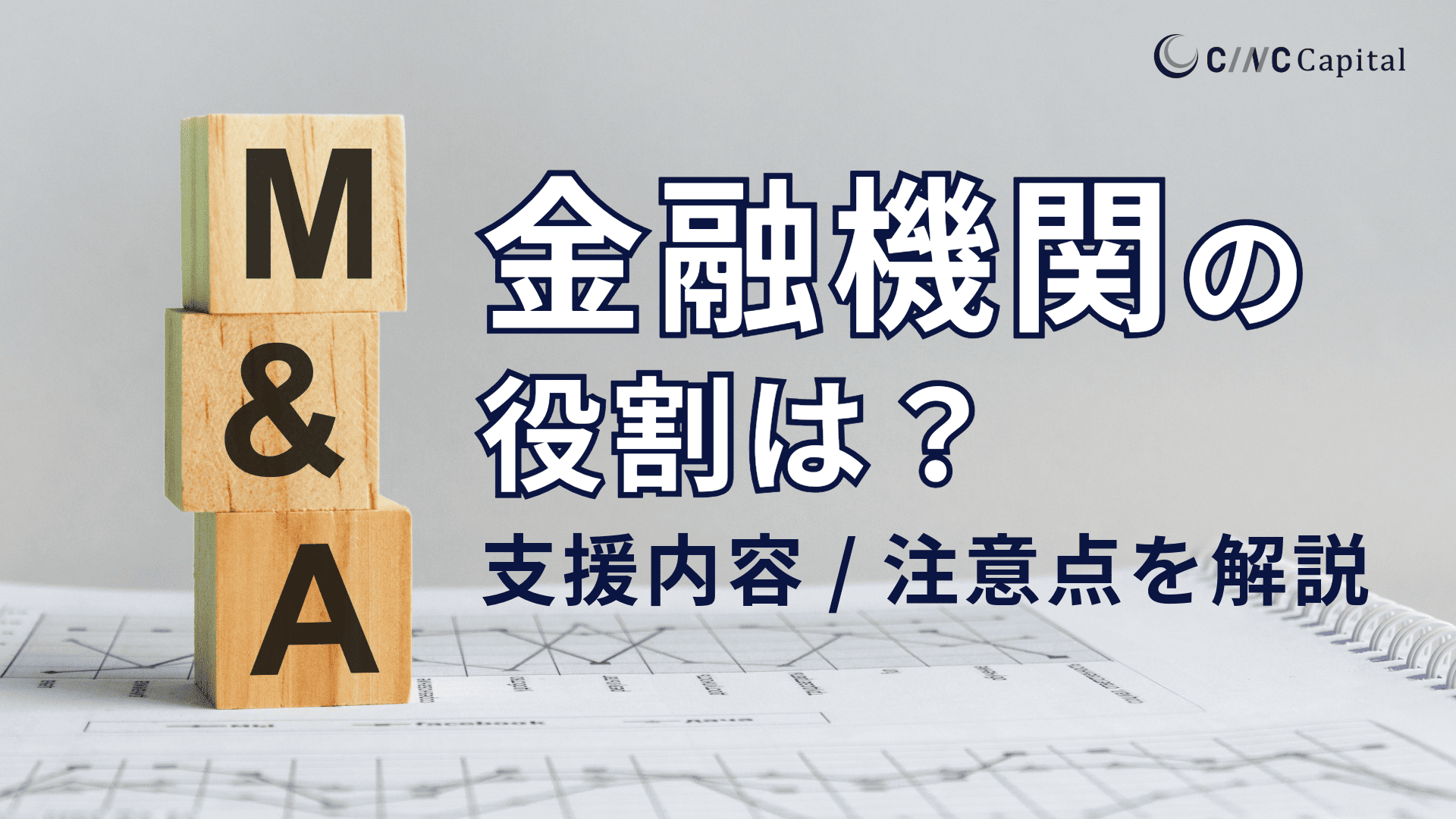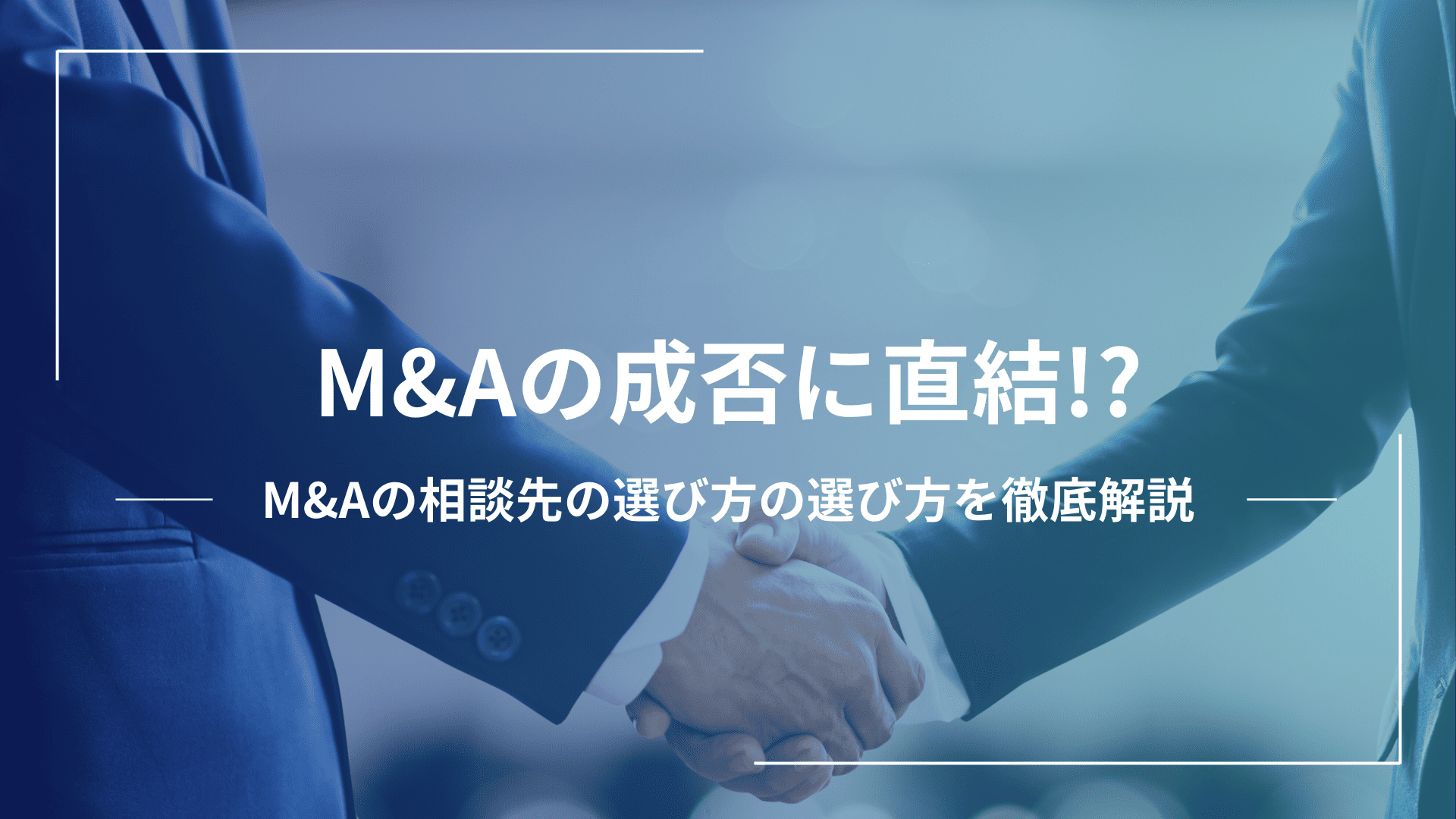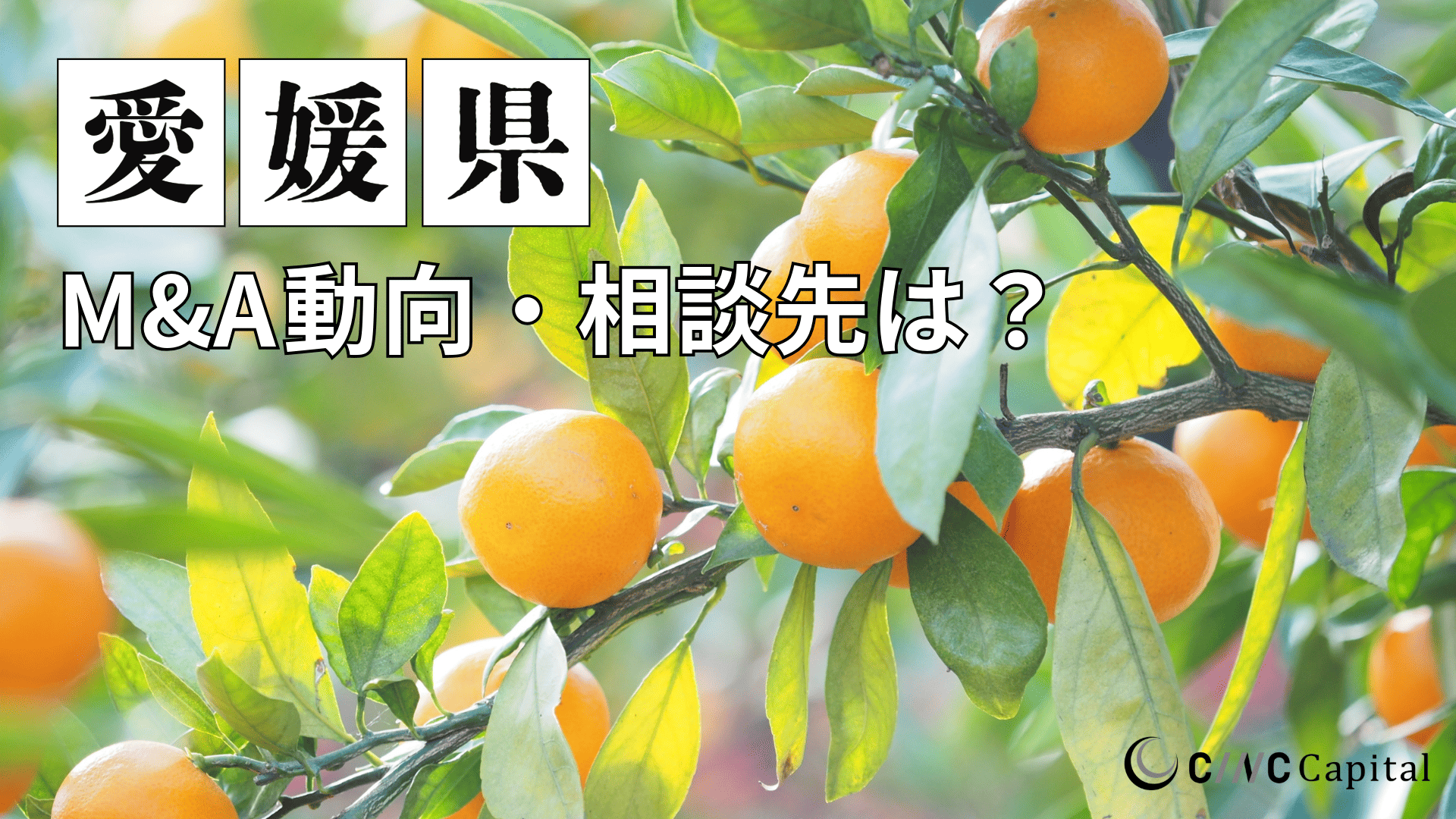CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

エリア
- 公開日2025.09.29
熊本県M&Aや事業承継の動向は?事例や信頼できる相談先/M&Aを進める時の注意点を解説
農業・畜産業や半導体関連産業に強みを持つ熊本県では近年、M&Aを活用した事業承継が広がりを見せています。
後継者不在という課題に加え、世界最大級の半導体受託製造企業の進出による経済構造の変化も、企業再編の動きを後押ししています。
ここでは、熊本県におけるM&Aの最新動向や信頼できる相談先の選び方、経営者が知っておきたい基礎知識などを徹底解説します。
目次
熊本県のM&Aや事業承継の最新動向【2025年】
2025年現在、熊本県内では事業承継支援の体制整備が進み、M&Aを活用しやすい環境が整いつつあります。
具体的にどのような動きがあるのか、最新動向を見ていきましょう。
後継者問題解消を目的としたM&A
「株式会社帝国データバンク」の調査によると、2024年における県内企業の後継者不在率は46.5%に達しており、また2024年の休廃業・解散件数は863件にのぼりました。
こうした状況のなか、事業の存続と発展を両立させる手段として、M&Aの有効性が周知され始めています。
【出典】株式会社帝国データバンク「熊本県内企業「後継者不在率」動向調査(2024年)」
【出典】株式会社帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」
農業・畜産業におけるM&Aニーズ拡大
近年は、農業・畜産業の分野でM&Aのニーズが高まっています。
なかでも、6次産業化を進める農業関連企業のあいだで、
熊本県を代表するスイカやトマト、また熊本が発祥の地である柑橘類のデコポンといった特産品を活用した「加工事業者による事業承継型の企業買収」が注目を集めています。
その背景には、高付加価値商品の開発や販路の拡大を見据えた事業統合の動きがあり、家族経営から法人経営への転換を図る事業者が少なくありません。
また、熊本県は畜産品およびその加工食品の分野で全国トップクラスの生産量を誇っており、規模拡大や効率化を目的とした企業統合も進行中です。
熊本が半導体産業の一大拠点に
2024年2月、台湾積体電路製造(TSMC)の熊本第1工場が開所し、同年末には量産がスタートしました。
これにより、県内の電子部品・デバイス・電子回路製造業に大きな影響がおよび、地域の産業構造にも変化が生まれつつあります。
半導体関連産業の成長が熊本経済を牽引する中で、周辺企業における事業承継やM&Aのニーズが今後さらに高まっていくと見込まれます。
熊本県でM&Aや事業承継の相談どこにする?
熊本県では、人口不足や後継者問題が一層深刻化しており、それを背景にしたM&Aや事業承継が注目を集めています。
ここでは、熊本県でM&Aの相談を行う際の主な手段を3つご紹介します。
M&A仲介会社に相談する
第一に挙げられるのがM&A仲介会社への相談です。
中堅・中小企業を対象とした仲介会社も多く、企業規模や目的に応じて柔軟な支援が受けられます。
特に、熊本の地域性や業界事情に精通した仲介会社を選ぶことで、交渉・手続きが円滑に進み、スムーズなM&Aの実現につながります。
金融機関や公的機関を利用する
熊本県では、地元の金融機関や公的支援機関がM&Aや事業承継のサポートを行っています。
例えば、県内の公的機関では無料相談の体制が整っており、資金調達や補助金に関するアドバイスが受けられます。
地域に根ざした「顔の見える支援」が受けられるのは、地元の金融機関や、公的支援機関ならではの強みといえるでしょう。
M&Aマッチングサイトで探す
近年、インターネットを活用してM&Aの相手先を探す「M&Aマッチングサイト」の普及が進んでいます。
特に、東京や大阪など都市圏の企業とのマッチングを希望する場合には、地理的な制約を超えて幅広い候補と出会える手段として有効です。
中小企業にとっては、まずは情報収集から気軽に始められるという点で、マッチングサイトはハードルの低い選択肢だといえます。
熊本県で信頼できるM&A・事業承継の相談先一覧
ここでは、熊本県内でM&Aを相談できる、信頼性の高い機関や企業をご紹介します。
事業承継を検討するうえでも、あらかじめ信頼できる相談窓口を把握しておきましょう。
熊本県事業承継・引継ぎ支援センター
中小企業庁の支援のもと設置されている公的機関です。
事業承継全般について無料で相談でき、初めてのM&Aでも安心して相談できる体制が整っています。
熊本県商工会連合会
熊本県内の各商工会と連携し、中小企業の経営支援を行っている団体です。
地域の事情に詳しいスタッフが在籍しており、地元企業同士のスムーズな事業承継をサポートしています。
【参考】熊本県商工会連合会
熊本県信用保証協会
中小企業の資金調達を支援するために、公的な保証人の役割を担う機関です。
M&Aや事業承継において、金融機関からの融資を円滑に受けられるよう包括的な支援を行っています。
【参考】熊本県信用保証協会
熊本商工会議所
熊本市を中心とした地域の商工業振興を目的とする経済団体です。
企業の経営相談や技術支援を通じて、事業承継に関するサポートを積極的に行っています。
地域に根ざした支援体制を強みとし、熊本市周辺の中小企業が抱える事業承継の課題にきめ細かな対応が期待できます。
【参考】熊本商工会議所
CINC Capital
「CINC Capital」は、中堅・中小企業を中心とした事業承継支援を全国で展開しているM&A仲介会社です。
マーケティングテクノロジーとデータ分析の専門知識を生かしたスペシャリストとして、熊本県の企業に最適な譲渡先・譲受先を提案しています。
【参考】CINC Capital
熊本県のM&Aや事業承継の事例
最後に熊本県のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社ヤマタネによる有限会社農産ベストパートナーのM&A
ヤマタネは2025年6月、熊本県山鹿市に本社を置く有限会社農産ベストパートナーの全株式を取得し子会社化するとともに、関連会社のしん力も孫会社化することを決定しました。
農産ベストパートナーは九州産米を中心に年間約4,000トンを取り扱う米卸・販売事業者で、ECブランド「こめたつ」を展開し、楽天市場「米部門大賞」を7度受賞するなど高い評価を得ています。
今回のM&Aにより、ヤマタネは同社のEC運営ノウハウを取り込み、自社の「米すたいる」や「フーデリッシュ」といったECブランドの強化を進める方針です。
また、西日本エリアを拠点とした販路拡大や商品ラインアップの充実も期待されます。
米卸の伝統的なビジネスモデルに加え、ECを通じた新たな販売チャネルを組み込むことで、バリューチェーンの拡大と持続可能な農業支援を進める戦略的M&Aといえます。
【出典】株式会社ヤマタネ「有限会社農産ベストパートナーの株式取得による子会社化に関するお知らせ」
日清製粉株式会社による熊本製粉株式会社のM&A
日清製粉は、熊本製粉株式会社の発行済株式の85%を永坂産業から取得し、連結子会社化することを発表しました。
熊本製粉は1947年創業の老舗製粉会社で、九州地方で高いブランド力を持ち、小麦粉だけでなく、そば粉や米粉など幅広い製品を展開しています。
両社は2011年から業務提携を結んでおり、製品供給や原料調達で協業してきたほか、2016年の熊本地震では日清製粉が復旧支援を行うなど、緊密な関係を築いてきました。
今回の子会社化によって、日清製粉は熊本製粉の技術力や販売基盤を取り込み、EC競争や人口減少に伴う需要縮小など国内市場の厳しい環境に対応。
コスト競争力や市場適応力を強化し、持続的成長と食のインフラとしての安定供給を目指すとしています。
このM&Aは、日清製粉にとって中核事業である製粉事業の国内基盤を強化するものであり、両社の補完関係を活かしたシナジー創出によって、競争力の一層の向上が期待されます。
【出典】日清製粉株式会社「日清製粉株式会社による熊本製粉株式会社の株式取得に関するお知らせ」
SFPホールディングス株式会社による株式会社ジョー・スマイルのM&A
2019年3月、熊本で居酒屋やカフェ、焼肉、バイキングレストランなど多業態を展開する株式会社ジョー・スマイルが、居酒屋チェーン「磯丸水産」や「鳥良商店」を200店舗以上展開するSFPホールディングス株式会社の連結子会社となりました。
本件はSFP社が推進する「SFPフードアライアンス構想」の一環で、SFP社の主力ブランドを熊本から九州全域へ広げる狙いがあります。
さらに、熊本発で地域の食材や食文化を全国へ発信することで、企業価値の向上と地域経済の活性化を図る方針が示されています。
外食業界では首都圏大手と地方有力企業の連携により、ブランド力強化と地域展開を同時に実現する動きが見られ、地方市場開拓や地域資源活用のモデルケースとなる事例といえます。
M&Aや事業承継を進めるときの注意点
熊本県でM&Aを進める場合、売り手側としては慎重な準備と情報収集が欠かせません。
ここでは、熊本県で売却を検討している経営者が押さえておきたい注意点をご紹介します。
地元ニーズや業種動向を見極める
熊本県は、農業・畜産業や半導体関連産業に強みを持つ地域です。
売却先が県内か県外かによって、求められるニーズや評価のポイントが異なるため、自社の業種がどのような需要を持つかを事前に把握しておきましょう。
公的支援や補助制度を活用する
熊本県内のM&Aは、条件次第で補助金制度を利用できる場合があります。
費用を抑えてM&Aを進めたい場合は、こうした制度をあらかじめ確認し、利用の可否を早い段階で検討しておくと安心です。
制度を知らないまま進めてしまうと、本来受けられた支援を逃してしまうおそれもあるため、事前の情報収集を徹底しましょう。
適切な専門家に相談する
M&Aは単なる売却ではなく、会社の未来を託す選択です。
経営人生において数少ない重大な意思決定だからこそ、M&A仲介会社をはじめとする専門家のサポートが欠かせません。
経営者が単独でM&Aを進めると「企業価値を正しく評価できない」「買い手候補と交渉がうまく進まない」「秘密保持に不安が残る」など、売り手側がつまずきやすいポイントがいくつもあります。
特に熊本県のように、農業・畜産業や半導体関連など地域特有の産業構造がある場合は、その実情を深く理解した専門家の存在が、成功と失敗を分ける決定的な要素となります。
M&Aや事業承継を検討する際に知っておきたい基礎知識
実際にM&Aを進めようとすると、「どのような手法があるのか」「どれくらい費用がかかるのか」など、疑問・不安を抱えるかもしれません。
ここでは、M&Aをはじめて検討する「売り手側」の経営者に向けて、最低限押さえておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。
M&Aと事業譲渡の違いはなんですか?
M&A(企業の合併・買収)は、経営権を他社に移す手法の総称であり、その中に「株式譲渡」や「事業譲渡」といった具体的な手段が含まれます。
つまり、事業譲渡はM&Aの一手法であり、包含関係にある用語だといえるでしょう。
【関連記事】M&Aとは?意味や目的、手法ごとのメリットデメリットをわかりやすく解説
M&Aのメリットとデメリットはなんですか?
後継者不在の解消」「従業員の雇用維持」「事業の成長加速」など、自力では難しかった経営課題の打開につながるメリットが多数あります。
一方で、買い手との条件交渉や従業員への説明、不安のケアなど、進め方を誤ると社内外に混乱を招くリスクは無視できません。
情報漏洩や売却価格とのミスマッチといったリスクもあるため、メリットだけでなくデメリットも踏まえたうえで検討することが大切です。
【関連記事】M&Aのメリットとデメリットは?買い手と売り手の立場別にわかりやすく解説
M&Aの相場はどのくらいですか?
M&Aの価格は、企業の規模や業種、財務状況、将来性などによって大きく異なります。
そのため、一律の相場を示すことは難しく、自社の状況に合わせた算定が必要です。
一般的な評価方法としては、「時価純資産に営業権(のれん)を加える方法」や、「EBITDAなどの利益指標に倍率をかけるマルチプル法」などが用いられています。
また、将来のキャッシュフローをもとに企業価値を算出するDCF法は、主に上場企業同士やスタートアップのM&Aに適した手法です。
M&Aへ向けて自社の企業価値を知りたい方は、以下のページから「企業価値算定シミュレーション」をご利用ください。
【参考】企業価値算定シミュレーション
M&Aでおすすめの相談先はどこですか?
M&Aの相談先としては、実績豊富なM&A仲介会社をはじめ、地域密着型の金融機関や公的支援機関などが挙げられます。
それぞれに強みがありますが、重要なのは自社の状況や目的に合ったパートナーを選ぶことです。
ただ、売り手の立場に寄り添った支援を重視したい方には、M&A仲介会社が最適な相談先といえるでしょう。
【関連記事】M&Aはどこに相談する?相談先の選び方やメリットデメリットを解説
まとめ|熊本県のM&Aのポイント
熊本県では、事業承継ニーズの高まりとともに、M&Aの活用が進んでいます。
特に後継者不在に悩む中小企業にとっては、M&Aが事業の存続と発展を両立できる有力な選択肢となるでしょう。
CINC Capitalは後継者不在に悩む経営者様を支援しています。
事業の価値を正当に評価し、譲渡先の選定から契約手続きまで一貫して対応し、会社の未来を守る具体的な方法をご提案します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。