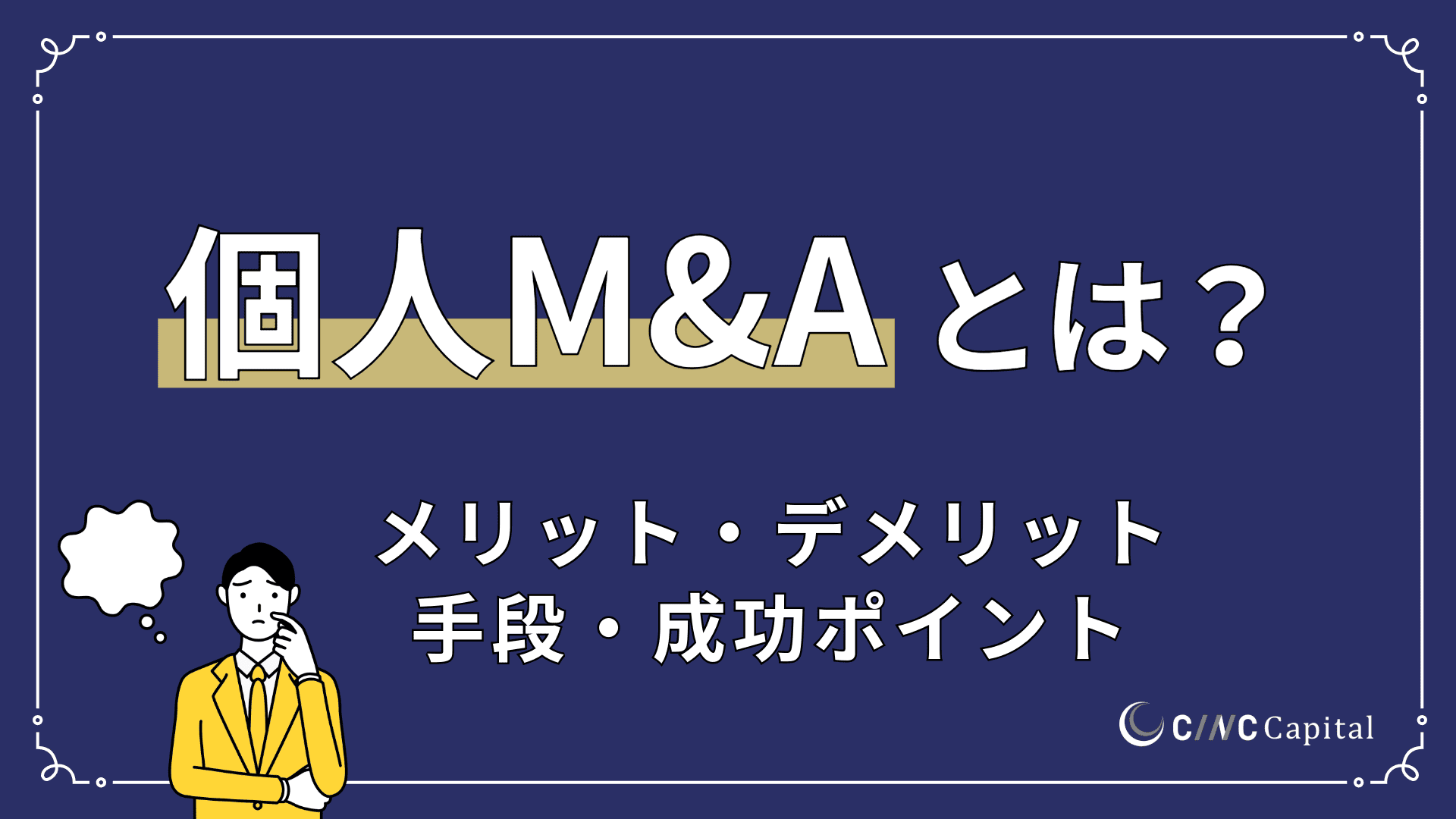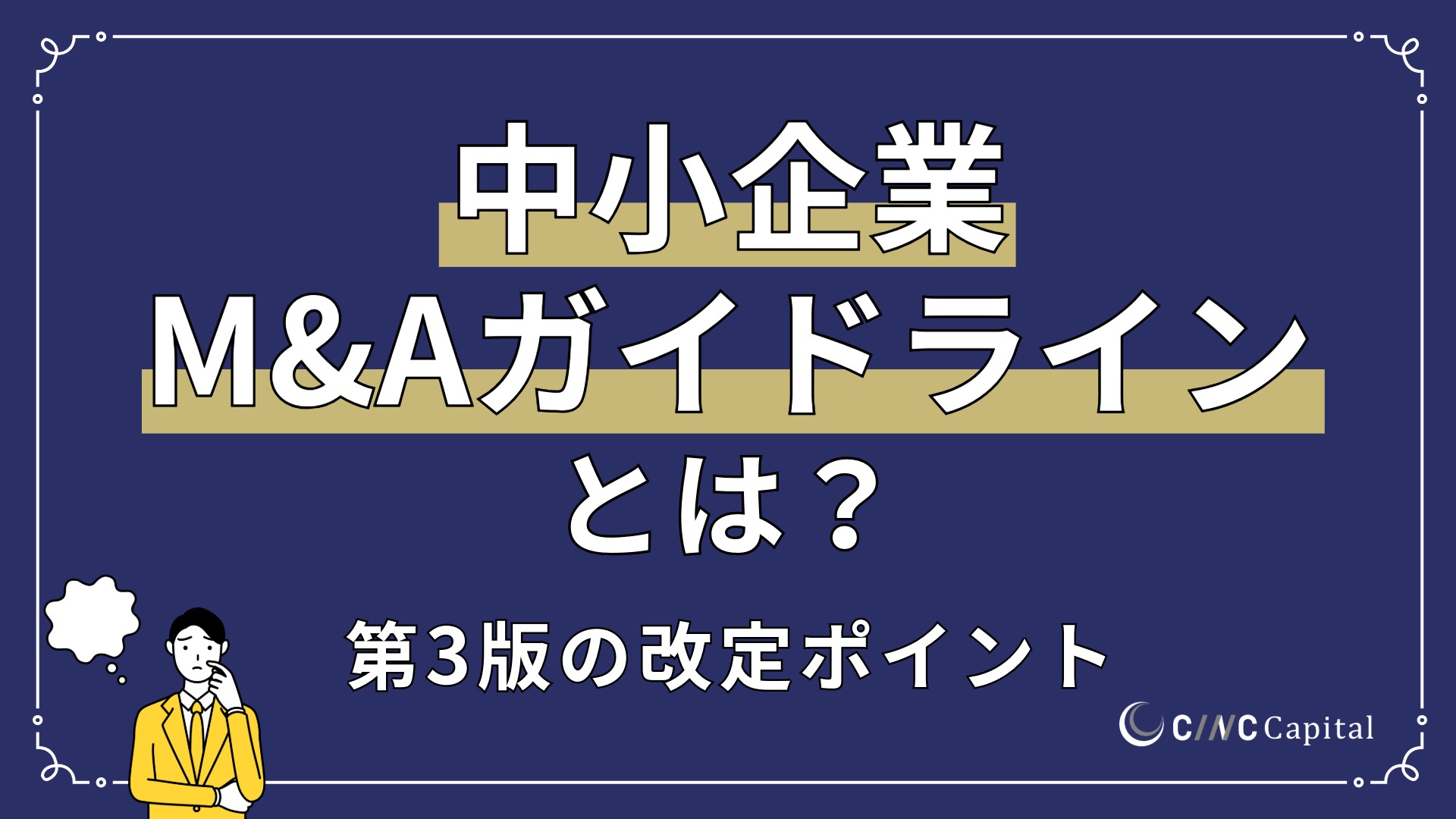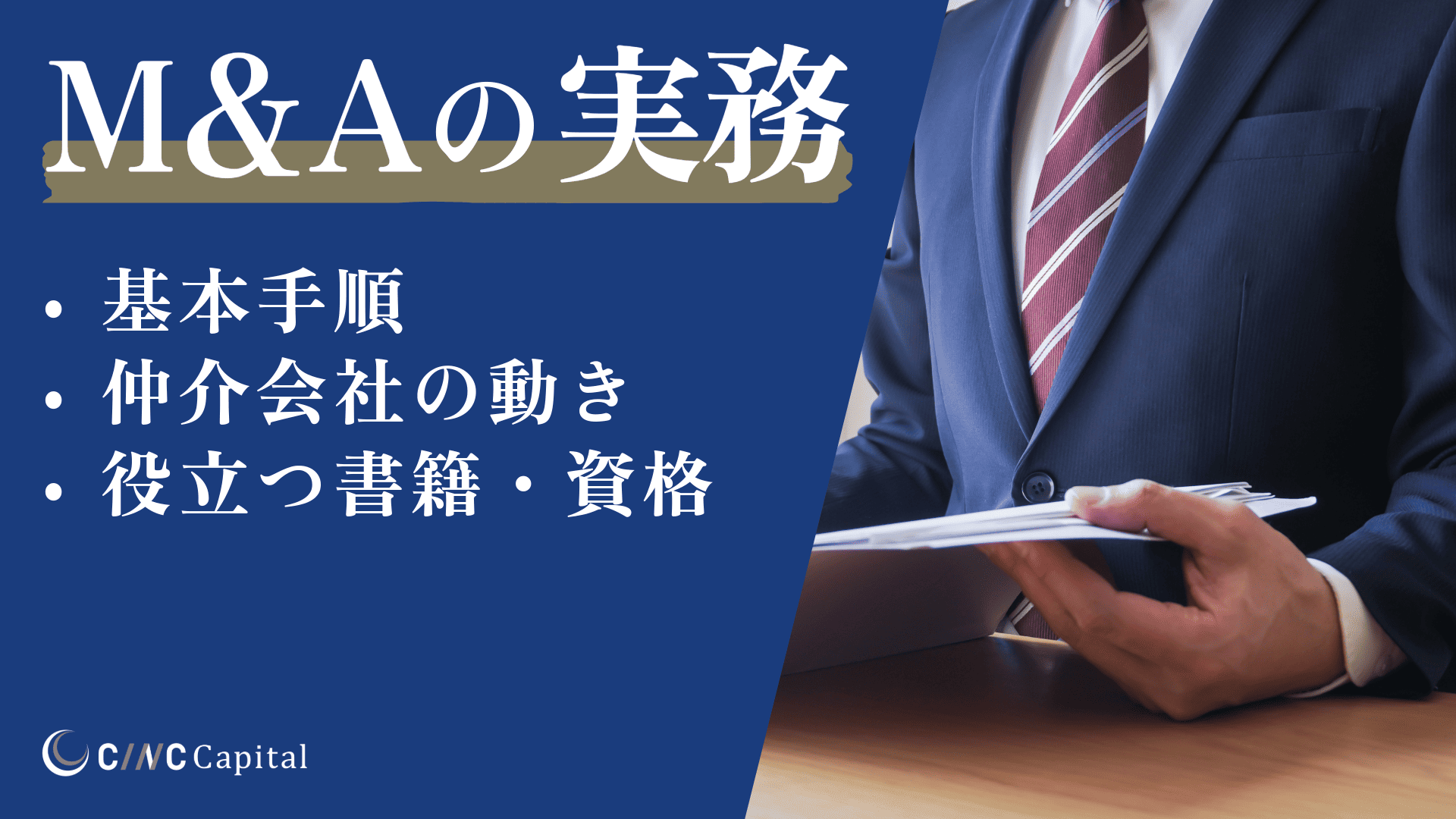CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
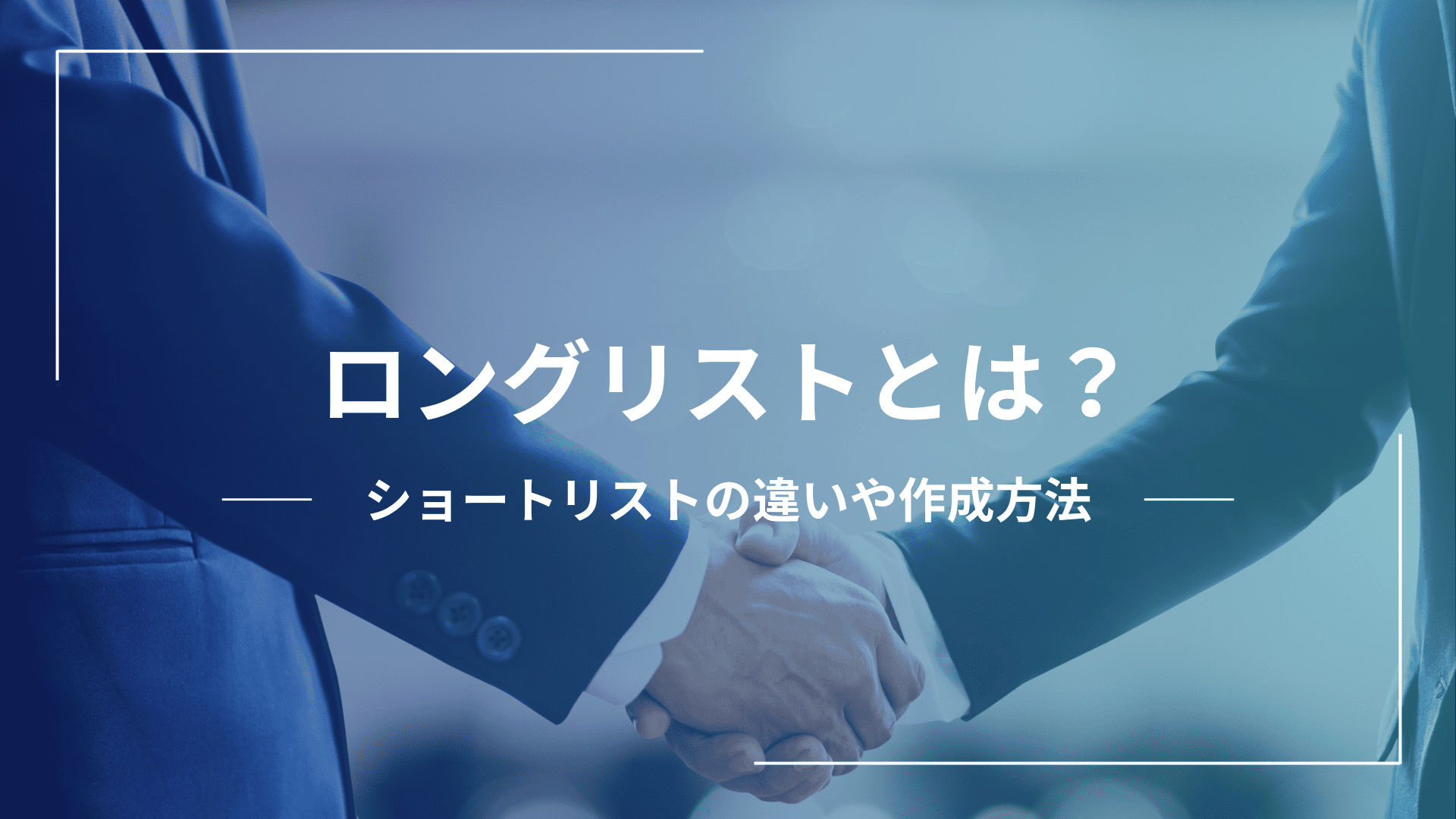
M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.06.26
M&Aのロングリストとは?記載項目や作り方、ショートリストの違い、作成のポイントも解説
M&Aの初期段階で重要となるのが「ロングリスト」です。適切な候補企業を抽出するためには、ロングリストの意味や作成方法を正しく理解しておくことが不可欠です。
本記事では、ロングリストとショートリストの違いや記載項目、作成時のポイントについて解説します。
目次
ロングリストとは?
M&Aにおける「ロングリスト」とは、買収や提携の対象となる企業を広く洗い出した初期候補リストのことを指します。
これは検討段階のリストであり、最終的な意思決定前に比較・分析を行うための土台となります。
ロングリストの目的は、候補の選定ミスを防ぎ、適切な相手を見つけるための情報収集の出発点を作ることにあります。
ロングリストは、買い手がアプローチ可能な企業を網羅的に抽出するのが一般的で、業種、地域、規模などの基本条件を満たす企業がリストアップされます。
その後、より詳細な分析を経て「ショートリスト」へと絞り込まれていきます。
ロングリストは、M&Aプロセスにおける戦略的な判断を左右する重要な資料と言えるでしょう。
ロングリストとショートリストの違い
ロングリストとショートリストは、M&Aプロセスにおけるフェーズの違いを表すリストです。役割や作成目的が異なるため、混同しないようにしましょう。
ロングリストは情報収集段階で幅広い候補をリストアップするもので、基本的には定量的な情報をもとに作成されます。
一方、ショートリストはロングリストから選抜された、実際に打診や交渉を行う対象として有望な企業群を指します。
こちらは定性的な要素、例えば企業文化の親和性やシナジーの可能性なども考慮して絞り込まれます。
ロングリストが「可能性のあるすべての企業」を含むのに対し、ショートリストは「交渉を進めたい企業」に限定されるため、情報の深度や重要度も異なります。
M&Aの成功には、ロングリストで網羅的に選定し、ショートリストで戦略的に絞るというプロセスの徹底が不可欠です。
【関連記事】M&Aのショートリストとは?
ロングリストの作り方
ロングリストの作成は、単なる候補の列挙ではなく、明確な戦略と手順に基づいた分析プロセスです。
以下に、実務で使える5つのステップに分けて解説します。
ステップ1
M&Aの目的を明確にする
ロングリスト作成の第一歩は、M&Aの目的を明確にすることです。目的が不明確だと、抽出する候補もバラバラになり、結果的にリストが機能しません。
目的には「販路拡大」「後継者問題の解決」「技術力の取得」などがあり、それぞれ必要とする相手企業の特徴が異なります。
例えば、新規市場への参入が目的なら、該当地域での実績がある企業を対象にする必要があります。
目的を最初に定義することで、その後のステップに一貫性を持たせることができ、最適な企業を効率よく選定できます。
ステップ2
選定基準を具体化する
次に行うのが、候補企業の「選定基準」を設定することです。
これには、業種、地域、売上高、従業員数、上場・非上場の別などの定量情報が含まれます。
基準を定めることで、網羅的かつブレのないリストを作成できます。
例えば、売上10億円以上の地方製造業を対象とする場合、全国を対象にするのか、特定エリアに限定するのかでもリストの性質は大きく異なります。
基準を曖昧にしてしまうと、後工程での絞り込みが非効率になり、再作成の手間も生じかねません。
ステップ3
企業情報を収集する
選定基準に基づいて、実際の候補企業を洗い出していく段階です。
この作業では、信頼性の高いデータソースの活用が欠かせません。代表的な情報源としては、帝国データバンク、東京商工リサーチ、業界団体の名簿、M&A仲介会社からの紹介などが挙げられます。
加えて、自社の取引先ネットワークや業界紙、SNSから得られる一次情報も有用です。
収集段階では網羅性を優先し、リスト対象を広く捉えるのがポイントです。
初期段階では“除外しない姿勢”が、意外な好条件の候補発見につながります。
ステップ4
リスト化して整理する
収集した情報を一覧表として整理し、比較可能な状態にまとめます。
Excelなどのスプレッドシートを活用し、「企業名」「売上高」「所在地」「主要事業」「設立年」などの項目を統一しましょう。
ここで大切なのは、情報のフォーマットを統一することと、定量・定性情報をバランスよく盛り込むことです。
例えば、「業績安定」「成長性あり」といった簡易評価項目を追加しておくと、後での比較が容易になります。
視覚的にわかりやすく整理されたリストは、関係者との情報共有やレビューの際にも大いに役立ちます。
ステップ5
社内でレビュー・ブラッシュアップする
リストが完成したら、社内関係者(経営陣、事業部門、M&A担当など)とのレビューを実施します。
異なる視点からの意見を取り入れることで、候補の妥当性や漏れのチェックが可能になります。
例えば、現場が抱える課題を考慮して、「システム統合がしやすい企業」「文化が近い企業」など、現実的な視点からフィルタリングすることが重要です。
また、リスト作成段階で定期的な更新を前提にし、候補企業の事業状況や業界動向を追跡できる体制を整えることも推奨されます。
このステップで、次のショートリスト作成にもスムーズに移行できます。
M&Aのロングリストに記載すべき項目
ロングリストの価値を最大化するには、候補企業に関する情報を適切に整理し、比較しやすい状態にすることが重要です。
以下に、記載すべき代表的な項目をまとめました。
実際にCINC Capitalで活用しているロングリストでは、以下の情報を記載しております 。
- 会社名
- 代表者名
- 大株主(買い手に対してのみ)
- 上場 or 未上場
- 業界・業種カテゴリ
- 事業概要
- 売上
- 利益
- 従業員数
- 会社URL
- 法人番号
①~⑪はCINC Capital(M&A仲介会社側)で管理するもので、売り手企業にお見せするときは以下の情報で共有します。
- 会社名
- URL
- 事業概要
- 売上
- 利益
- 法人番号
- 選定理由
- M&A実績(売り手に対してのみ)
M&Aのデータベースサイトや自社収集(CINCはCAMM DB※で独自データベース化)
このように、定量・定性の両面から情報を整理することで、M&A戦略における精緻な比較・検討が可能になります。
※CAMM DB(キャムディービー)…生成AIや自然言語処理を用いて、M&A仲介における迅速かつ最適なマッチングを行うための社内システムです。
【関連記事】子会社のCINC Capital、生成AIを活用したM&A仲介マッチングシステム「CAMM DB」に譲渡企業と譲受候補企業のマッチング度合い判定機能搭載のお知らせ
ロングリストを作成するときのポイント
ロングリストの質は作成時の視点と工夫によって大きく変わります。
ここでは、買い手と売り手それぞれの立場から意識すべきポイントを解説します。
買い手が意識すべきポイント
買い手側がロングリストを作成する際には、自社の成長戦略やシナジー効果を明確に意識することが重要です。
目的に合わない企業を選定すると、後の選別や交渉で無駄が生じます。
例えば、新規事業の立ち上げが目的であれば、技術力や既存顧客の有無、クロスセルの可能性などが重視されるべきです。
また、自社との文化や価値観の親和性も重要な評価ポイントです。
いくら業績が優れていても、経営スタイルがまったく合わなければ統合後にトラブルの原因となります。
ロングリストは「選定のためのリスト」ではなく、「選別のためのリスト」です。
そのため、あえて幅広く作成しつつ、自社の方向性に合致したフィルターをかけることが成功の鍵です。
買い手のロングリストを作成するタイミングは?
買い手は、買い手企業にM&Aの希望や要求についてヒアリングした後、プロアクティブサーチの依頼を受けた場合、その直後にロングリストを作成します。ロングリスト作成後、買い手企業にロングリストを共有し、すり合わせ、ショートリストの作成に移ります。
プロアクティブサーチとは、まだ譲渡の意思を示していない企業に対して、買い手企業の成長戦略に基づいて先回りでアプローチを行うM&A手法です。
売り手が意識すべきポイント
売り手がロングリストを扱う際には、どのような買い手と組むと自社の価値が最大化するかを見極めることが肝要です。
買収額だけでなく、事業の承継意向や従業員の雇用継続など、非財務的な条件も検討材料に含めるべきです。
例えば、地域密着型の企業であれば、同地域での展開実績がある買い手の方が、シナジー効果や従業員の安心感につながりやすくなります。
また、将来の経営方針に柔軟性があるか、事業継続のビジョンが一致するかなども、判断基準として欠かせません。
売り手にとってのロングリストは、「選ばれる」だけでなく「選ぶ」視点を持つことが大切です。
自社の事業の将来像に最適な相手を見定めるための戦略的な材料と位置づけましょう。
売り手のロングリストを作成するタイミングは?
売り手のロングリストの作成は、仲介契約やアドバイザリー契約締結後、IM(企業概要書)、NN(ノンネームシート)作成とほぼ同時並行で進めます。売り手オーナーと面談等で確認さえていただき、紹介を控えてほしい企業候補先についても伺います 。
M&Aのロングリストを取り扱うときの注意点
ロングリストの取り扱いには情報管理とコミュニケーションの観点で注意が必要です。
特に、情報の機密性が高いことから、社内外への漏洩リスクには細心の注意を払わなければなりません。
リストには未公開情報や企業の戦略的意図が含まれるため、閲覧権限の管理やアクセス履歴の記録を徹底することが求められます。
また、候補企業がリストに挙がっていること自体が交渉材料となる場合もあるため、意図しない情報流出が交渉失敗のリスクを高める可能性もあります。
加えて、リストの更新頻度にも注意を払いましょう。企業の状況は日々変化しており、情報が古いままだと正しい判断ができません。
最新情報を定期的に反映させることで、実効性のある分析と意思決定が可能になります。
【関連記事】秘密保持契約(NDA)とは?基本から締結のメリットまで解説
まとめ|希望や条件を含めたロングリストの作成がM&A成功の近道
ロングリストはM&Aの起点として、適切な候補企業の洗い出しに欠かせないツールです。
ロングリストとショートリストの違いを理解し、目的に沿った作成・運用を行うことで、M&Aの精度と成功率が高まります。
買い手・売り手それぞれの立場でポイントを押さえながら、戦略的かつ柔軟にリストを活用することが、望ましいM&Aの第一歩となるでしょう。
ロングリスト作成に関して不明点などがあれば、お気軽にCINC capitalにご相談ください。業界10年以上のプロアドバイザーが丁寧に貴社のM&Aや事業承継をサポートいたします。