CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
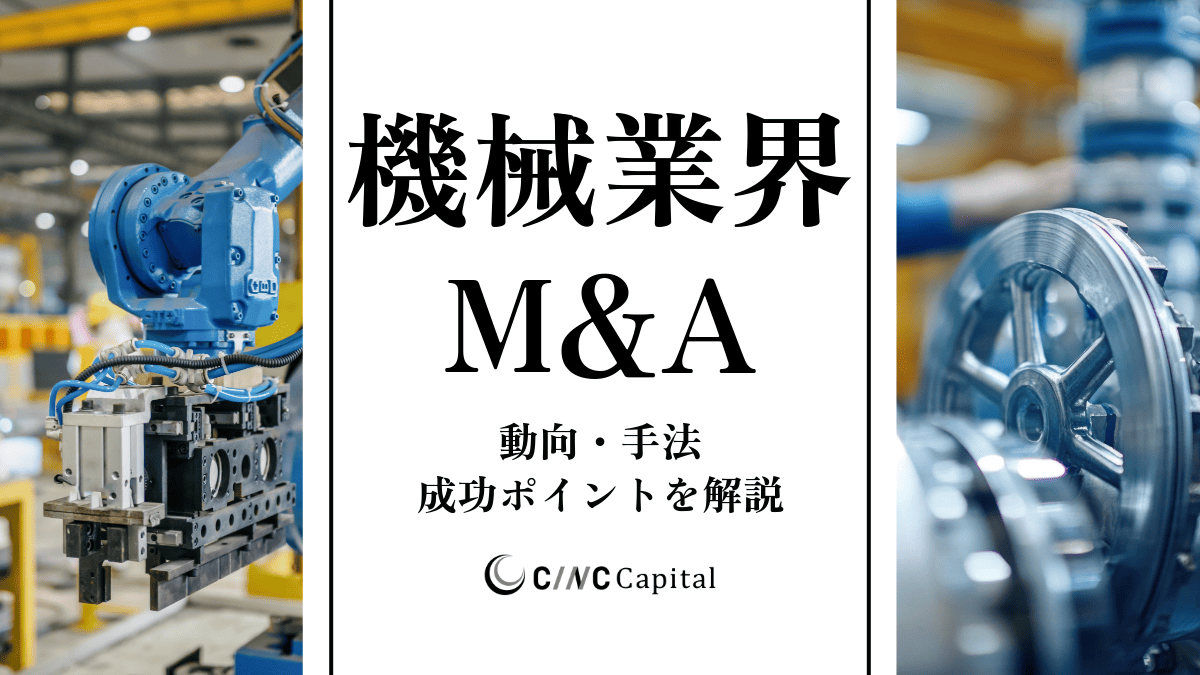
業種
- 公開日2025.09.29
機械業界のM&A動向は?事例や成功のポイントを解説【2025年】
「機械業界のM&Aに関心があるけれど、何から調べればいいのかわからない…」そう悩んでいませんか?
本記事では、機械業界におけるM&Aの市場動向から、実際に進行中のトレンド、成功させるためのポイントまでを詳しく解説します。
目次
機械業界の市場動向
日本の機械業界は製造業の中でも重要な位置を占めており、2023年時点で「機械器具製造業」(日本標準産業分類 中分類25~27:はん用・生産用・業務用機械)の出荷額は約45.3兆円に達し、非常に大きな市場を形成しています。
しかし一方で、国内では少子高齢化の影響により需要が徐々に減少しつつあります。
【出典】総務省・経済産業省「2023年 経済構造実態調査二次集計結果」
機械業界が抱えている課題
日本の機械業界は高い技術力を持っていますが、その技術をさらに発展させていくためには、いくつかの根本的な課題を乗り越える必要があります。
本章では、主に3つの課題について見ていきましょう。
人手不足と後継者不在
中小企業庁の調査によると、70歳以上の中小企業の経営者は約245万人おり、そのうち約半分が後継者を決めていません。
また、帝国データバンクの調査では、2024年の時点で中小企業全体の後継者がいない割合は52.1%にのぼり、特に製造業ではその傾向が強くなっています。
このまま後継者がいない状態が続くと、熟練した技術が受け継がれず、製品の品質や生産性が下がってしまうおそれがあるのです。
さらに、事業を続けられない会社が増えれば、機械業界全体が弱くなるリスクも高まります。
こうした事態を防ぐには、M&Aやマッチング支援を活用して、しっかりと事業を引き継ぐ仕組みをつくることが重要です。
【出典】中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」
【出典】帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」
DX・デジタル対応の遅れ
経済産業省の「ものづくり白書2023」によると、日本の中小製造業では、DX(デジタル化)に必要なIT投資が大企業と比べてかなり少なく、会社全体でのデジタル化があまり進んでいません。
さらに内閣府の調査では、製造業のうち全社的にDXをうまく進められている企業は27.6%しかないと報告されています。
その結果、IoTを使った設備の故障予測や、リアルタイムの在庫管理といった効率化の仕組みが導入されず、現場の作業が人に頼りきりの状態が続いているのです。
このような状況を放置すると、国際的な競争力を失うだけでなく、品質の安定や人手不足への対応も難しくなり、経営に大きな影響を与える可能性があります。
だからこそ、IT企業との連携やM&Aを活用して、外部からデジタルの力を取り入れることが急がれています。
【出典】経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2023年版 ものづくり白書」
グローバル競争とサプライチェーンの脆弱性
日本の機械メーカーは、製品の品質と信頼性の高さで世界から評価されています。
しかし最近では、コストの安い製品をつくる新興国企業との競争が激しいです。
さらに、コロナ禍や国際情勢の不安定さによって、海外からの部品供給や物流が止まるトラブルが相次ぎました。
内閣府の報告では、パンデミックによる物流の混乱が、部品の調達に大きな影響を与えたと指摘されています。
こうした問題が明らかになったことで、多くの企業が調達先を分散させたり、国内に供給体制をつくり直したりする動きを強めているのです。
機械業界のM&A最新動向(2025年)
2025年現在、機械業界におけるM&Aは、業界の構造変化や事業継承の課題を背景に、より多様な動きを見せています。
本章では主に3つの最新動向について詳しく見ていきましょう。
大手による中小企業買収の加速
2023年、日立機械大手の日本電産(Nidec)は、TAKISAWA機械を敵対的TOBで完全子会社化しました。
この買収は、中小の工作機械メーカーが持つ技術・特許・人材を取り込む狙いが明らかになっています。
日本電産は2030年までにM&Aで業績を補完するとしており、こうした波は他大手機械メーカーにも広がる見通しです。
【出典】ニデック株式会社「株式会社 TAKISAWA(証券コード:6121)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
異業種M&Aの増加(IT・商社・サービス)
製造業では、自社のIT力や流通の仕組みを強化するために、IT企業や商社、サービス業とのM&Aが増えています。
その目的は、工場のスマート化や受発注の自動化、物流の効率アップなど、新しい仕組みを取り入れることです。
2025年現在、日本国内のM&Aでは、IT分野の活発な動きが目立っており、製造業との連携も進展しています。
事業承継型・個人M&Aの一般化
後継者不在が深刻な中小企業を対象としたスモールM&Aが増加しています。
BATONZのようなマッチングプラットフォームでは、年商数千万〜数億円規模の企業が個人や小規模企業に譲渡される機会が増加中です。
加えて、中小企業庁も事業承継支援を拡充しており、制度面でも事業承継型M&Aへの後押しが進んでいます。
【参考】BATONZ
機械業界でM&Aを成功させるためのポイント
機械業界でM&Aを成功させるためには、一般的な手続きや交渉だけでなく、業界特有のリスクや課題に対応する視点が求められます。
本章では、成功させるために重要なポイントを5つ解説していきます。
環境リスクの精査
工場や土地を買収する際には、土壌の汚染やアスベストの有無、排水処理の不備など、見えにくい環境リスクが後から大きな負担になることがあります。
こうしたリスクを見逃さないために、PwCはM&Aを行う前に「環境デューデリジェンス(EDD)」を実施することを推奨しています。
リスクを事前に調べて契約条件に反映させることで、買収後の企業価値を守ることにつながるでしょう。
設備・在庫の適正評価
M&Aの対象となる企業では、工作機械や生産設備が資産の大きな部分を占めています。
しかし、帳簿に記載された金額と実際の状態が一致しないことは多いです。
そのため、Gordon Brothers Japanは、現地での確認と「Fair Value評価」を組み合わせて行うことで、正しい資産価値を把握できると説明しています。
こうした取り組みによって、買収後に不要な設備を廃棄したり、予想外の追加投資をしたりするリスクを防ぐことが可能です。
サプライチェーンの統合配慮
買収先が特定の取引先に依存する状況では、M&A後に契約解除や供給断絶が起きる可能性があります。
EYは、統合計画にキーパーソンや契約内容の把握、代替ルート設定を盛り込むことが、統合成功に不可欠だという見解を示しています。
【出典】EY Parthenon「Supply Chain in M&A Integration and Divestments」
許認可・法規制の確認
M&Aのやり方によっては、輸出管理や有害物質の取り扱いなどに関する許可がそのまま引き継げない場合があります。
その場合、あらためて許可を取り直さなければなりません。
ICLGの日本M&Aガイドでは、法務デューデリジェンスの段階で、こうした許認可や公正取引委員会への届出が必要かどうかを事前に確認することを勧めています。
それによって、手続きの抜け漏れが原因で事業が止まってしまうようなリスクを防ぐことが可能です。
【出典】ICLG「Mergers & Acquisitions Laws and Regulations Japan 2025」
従業員・ノウハウ継承の支援体制
製造現場で働く熟練の技術者と、その人たちが持つ経験や知識は、企業の強みとなる重要な資産です。
しかし、M&Aの後にその技術者たちが辞めてしまうと、統合による効果が大きく失われてしまいます。
これを防ぐためには、人事デューデリジェンスを行ったうえで、メンター制度や引き継ぎの仕組みを統合計画に取り入れることが大切です。
機械業界のM&A事例
最後に機械業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社ニッキによる大島機工株式会社のM&A
株式会社ニッキは2025年9月、大島機工株式会社の全株式を取得し子会社化することを決定しました。大島機工は神奈川県相模原市に拠点を置き、建設機械部品を中心とした切削加工・機械加工を手掛ける企業です。
1973年創業以来、安定した収益基盤を有しており、直近3期でも売上高は年間約5億円規模を維持しています。
今回のM&Aは、世界的に進む脱炭素・カーボンニュートラルの潮流を背景に、親会社が新規事業創出や事業構造転換を推進する一環として実施されたものです。
産業機械部品加工という製造領域をグループに取り込むことで、事業の多角化と安定収益源の確保を図る狙いがあると考えられます。
機械加工業はニッチながら高い技術力と継続的需要が見込まれる分野であり、既存事業とのシナジー創出や将来的な新市場開拓にもつながる可能性が高い事例といえます。
【出典】株式会社ニッキ「大島機工株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
パンチ工業株式会社による株式会社ASCeのM&A
金型部品製造大手のパンチ工業株式会社は、2022年10月、FA(ファクトリーオートメーション)機器の設計・製造を手掛ける株式会社ASCeの全株式を取得し、子会社化しました。
ASCeは食品加工・自動車部品・電子デバイス・医療分野など幅広い業種向けに、省力化・自動化を実現する特注機器をオーダーメイドで提供する企業で、高い設計力と短納期対応力を強みとしています。
パンチ工業は、中期経営計画「VC2024」でFA領域における特注品の販売拡大を成長戦略の柱に掲げており、本件M&Aはその実現を加速させる施策です。
グループが持つ世界1万5千社超の販売網や調達ネットワークと、ASCeの技術力を掛け合わせることで、より複雑かつ高度な自動化装置の提供が可能となります。
これにより、パンチ工業は3年後にFA事業を売上高50億円規模に育成することを目指しており、自動化需要の拡大を背景にグループ全体の収益基盤強化が期待される事例です。
【出典】パンチ工業株式会社「金型部品製造のパンチ工業が、FA機器設計・製造の株式会社ASCeの全株式を取得。株式会社ASCeがパンチグループへ加入しました」
ニデック株式会社による三菱重工工作機械株式会社のM&A
ニデック株式会社は、2021年2月に三菱重工業株式会社から三菱重工工作機械株式会社の株式および関連海外子会社3社の持分を取得する契約を締結し、同年8月に主要な手続きを完了しました。
これにより、三菱重工工作機械は「日本電産マシンツール株式会社」としてグループ入りし、中国・インドの拠点も順次「Nidec」ブランドへ移行しています。
三菱重工工作機械は1936年創業以来、歯車機械や門型マシニングセンタ、大型工作機械などで国内トップシェアを有し、レーザー・半導体製造装置など最先端分野にも展開してきました。
長年培った高精度加工技術と専門人材は、日本電産が成長戦略に掲げる工作機械事業拡大の中核を担います。
本件M&Aにより、日本電産は既存の機器装置事業や要素技術開発と相互補完関係を構築し、グローバル市場での競争力強化を狙います。
特に歯車加工分野での強みを活かしつつ、ブランド力や顧客基盤を融合することで、工作機械市場における世界的リーダーを目指す動きが鮮明となった事例です。
【出典】ニデック株式会社「三菱重工工作機械株式会社の株式取得等の完了と新子会社概要」
まとめ|機械業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
日本の機械業界では、後継者不足やDXの遅れ、国際競争の激化といった課題が深まっています。
その中で、M&Aは企業の成長や存続を支える重要な手段として注目されています。
実際に、大手による業界再編や事業承継型のスモールM&A、異業種との連携も広がっており、今後さらに活発化するでしょう。
ただし、M&Aを成功させるには、業界特有のリスクや事情を理解し、環境リスク・設備状況・取引先・許認可・人材継承などをしっかり確認する必要があります。
CINC Capitalは、様々な業界に精通したノウハウと実績をもとに、戦略設計から実行、統合支援まで一貫してサポートします。
M&Aを前向きに進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

















