CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
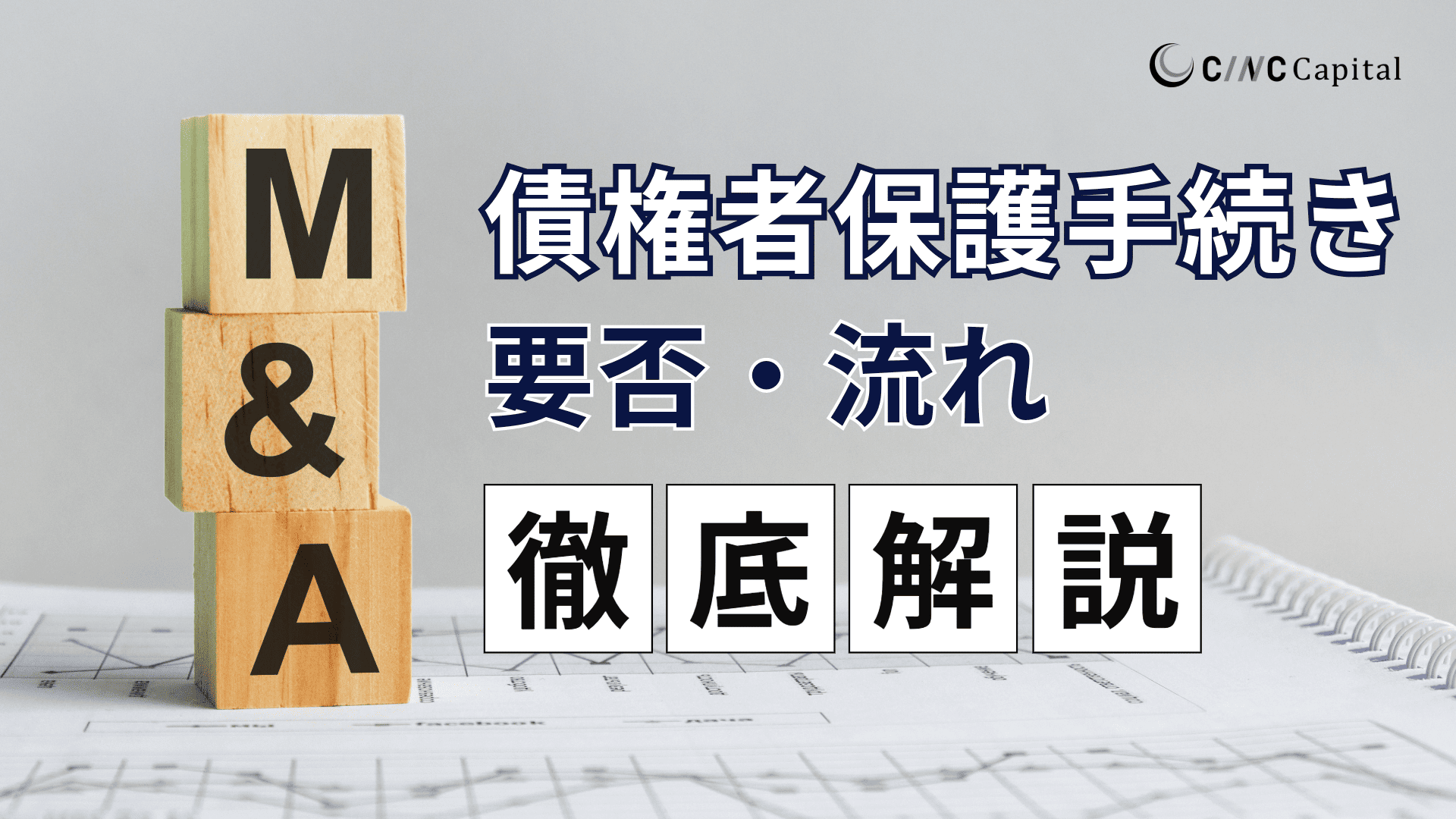
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
事業譲渡などのM&Aにおける債権者保護手続きの要否や流れを解説
M&Aを進める際、債権者保護手続きの要否を正しく理解することは、取引の円滑な実行とリスク回避に不可欠です。特に、事業譲渡や会社分割、合併などのスキームによっては、債権者に不利益が生じる可能性があるため、適切な対応が求められます。
本記事では、M&Aの各手法における債権者保護手続きの必要性や具体的な流れ、さらには事業譲渡における詐害行為取消権のリスクについて詳しく解説します。債権者対応のポイントを理解し、スムーズなM&Aを実現するために、ぜひ参考にしてください。
目次
事業譲渡における債権者保護手続きとは
債権者保護手続きとは、事業譲渡やM&Aの際に、債権者が不利益を被らないようにするための法的手続きです。会社法では、債権者の権利を守る規定が設けられており、特に合併や会社分割といった経営施策は、債権者に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この手続きでは、会社が経営施策を実施する前に、債権者に対して事前通知を行い、一定の期間内に異議を申し立てる機会を与えます。債権者から異議が出された場合、会社は弁済や担保の提供など、適切な措置を講じなければなりません。
なお、債権者とは、金融機関や仕入れ先など、企業に対して金銭的請求権を持つ者を指し、現金や手形などの債権の種類や、個人・法人といった区分に関わらず対象となります。
特にM&Aでは、買い手企業が売り手企業の負債を引き継ぐケースもあるので、買い手企業の債権者にとってリスクが生じる可能性があります。負債リスクを回避し、債権者の利益を保護するために、会社法によって債権者保護手続きが義務付けられているのです。
事業譲渡については以下の記事で解説しております。併せてご覧ください。
【関連記事】事業譲渡とは?メリットやデメリット、手続きをわかりやすく解説
事業譲渡では債権者保護手続きは必要?
事業譲渡において、債権者保護手続きが必要かどうかは、取引の性質や債権者の同意に大きく依存します。以下では、具体的なケースについて詳しく解説します。
事業譲渡では債権者保護手続きが不要
事業譲渡においては、会社法上の債権者保護手続きは規定されていません。これは、事業譲渡が個別継承の形式をとるためです。
事業譲渡では、会社が特定の事業を取引行為として第三者に譲渡するものであり、会社分割などとは異なり、譲渡対象となる債務や契約上の地位を移転するには、個別に契約相手方である債権者の同意が必要となります。
債権者が、債務の移転によって不利益を被らないと判断し、同意した場合にのみ、債務は第三者へ移転されます。したがって、事業譲渡においては、会社法上の債権者保護手続きが不要となるのです。
事業譲渡における詐害行為取消権について
譲渡企業が債務者である場合、優良な事業を譲受企業に不当に低い価格で譲渡するなど、債権者の権利を侵害する際は、民法第424条に基づく詐害行為取消権を行使できます。
詐害行為取消権とは、債務者が無資力の状態で財産を処分したときに、債権者がその処分を取り消せる権利です。
詐害行為取消権を行使することで、債権者に不利益をもたらす事業譲渡を防ぐ役割を果たします。
事業譲渡を行う際には、後に債権者から詐害行為取消権を主張されるリスクを避けるため、譲渡対価を合理的に設定することが重要です。
詐害行為取消権のリスクを回避するためには、事業価値評価を第三者の専門家に依頼し、適正な譲渡価格であることを客観的に証明できるようにしておくことが効果的です。CINC Capitalでは、M&A専門家による適正な事業価値評価と、取引スキームの設計によって、このようなリスクを最小化するサポートを提供しています。
事業譲渡以外のM&A手法での債権者保護手続きの要否
事業譲渡以外のM&A手法においても、債権者保護手続きの要否は重要なポイントです。以下では、具体的なケースを挙げて解説します。
債権者保護手続きが必要になるケース
会社分割
会社分割とは、売り手の事業部門を買い手企業に移転させるM&Aスキームの一つです。
会社分割は包括承継の形をとるため、事業譲渡のように個別の債権者同意を得る形では進められません。会社分割における包括承継とは、株式会社や合同会社がその事業に関連する権利義務を他の会社に承継させる法的手続きのことを指します。分割会社が持つ権利義務の全部または一部が承継会社または新設会社に移転されます。
会社法第789条および第810条では、分割会社および承継会社は債権者保護手続きを行うことが規定されており、これにより債権者が異議を申し立てる機会を確保しています。特に、不良資産を承継した場合など、買い手企業の債権者に不利益が生じる可能性があるので、債権者保護手続きが必要となるのです。会社分割については以下の記事で解説しております。併せてご覧ください。
【関連記事】事業譲渡と会社分割の違いは?それぞれのメリットやデメリット、流れ
合併
合併においては、相手方当事会社の経営状態が不安定な場合、合併後の財務状況の悪化により、債権回収が困難になるリスクが生じます。
これにより、他方当事会社の債権者が不利益を被る可能性が考えられるため、債権者保護手続きが必要です。
さらに、合併における資本金や準備金の設定次第では、債権者が引き当てとして把握する資本金・準備金の減少が発生し、財務的な安全性が低下する可能性があります。
財務的リスクを回避し、債権者の利益を守るため、債権者に異議を申し立てる機会を確保する債権者保護手続きが求められるのです。
債権者保護手続きが不要なケース
会社法において、株式譲渡に債権者保護手続きは義務付けられていません。株式譲渡は、対象企業の株式を売買することで経営権が移転するM&A手法の一つです。
株式の売買によって経営権は移転しますが、会社の財産状態には変化が生じません。そのため、債権者に不利益が及ぶ可能性は低く、特別な保護手続きは不要とされています。
債権者保護手続きが例外的に必要になるケース
株式交換
株式交換とは、完全親子会社関係を前提に買い手企業(親会社)が売り手企業(子会社)の全株式を取得するM&Aスキームです。会社法では株式交換を債権者保護手続きの対象としていませんが、場合によっては必要となります。
例えば、株式交換により親会社の資本剰余金が増加し、その資本剰余金を原資とした配当や自己株式取得による資金流出の可能性が高まった場合や、親会社が株式以外の対価を支払う場合など、親会社の財産状況が悪化する可能性があるため、債権者保護手続きが必要となることがあります。
株式交換については以下の記事で解説しております。併せてご覧ください。
【関連記事】株式交換とは?メリットとデメリット、手続き方法を解説
株式移転
株式移転とは、新設された企業が親会社となり、既存企業の全株式を取得して完全子会社とするM&Aスキームです。株式交換は株式交換と類似するスキームですが、会社法では債権者保護手続きの対象ではありません。
ただし、子会社が新株予約権付社債を発行しており、その債務を親会社が引き継ぐ場合は、債権者保護手続きが必要となることがあります。
債権者保護手続きの流れ
債権者保護手続きの流れを理解することは、M&Aを円滑に進めるために不可欠です。以下では、具体的な手続きの流れを解説します。
官報への公告
まずは、官報に公告を掲載しなければなりません。(会社法 第449条2項)官報とは、内閣府の管理のもと、独立行政法人国立印刷局が発行している国の機関紙です。
公告を掲載するには、各都道府県にある官報販売所への申し込みが必要となります。広告の掲載内容は、M&Aスキームの表明や、当事会社の会社名・住所などが含まれます。
債権者への個別催告
官報への公告と同時に、企業が把握している各債権者に対して個別催告を実施します。個別催告とは、官報公告の内容と同じ情報を、各債権者に直接通知する手続きです。一般的には、該当する書類を郵送することで行われます。
なお、定款において「債権者保護手続きの公告は、官報のほか電子公告または日刊新聞紙で行う」と定めている場合は、その規定に従い電子公告または日刊新聞紙へ掲載することで、個別催告に代えられます。
債権者からの異議への対応
官報公告および個別催告で示した異議の受付期間内に、債権者から異議が申し立てられた場合、会社側が債務の弁済・債務と同等の担保の提供・債務と同等の財産の信託のいずれかで対応する必要があります。
債権者からの異議に対し、債権者に不利益は生じないことを立証できれば、債務の弁済を行わずに済む場合もあります。
また、異議の受付期間内に債権者から何も連絡がなければ、異議はないとみなして事業譲渡などのM&Aの実行が可能です。
債権者からの異議申立期間は、会社法第449条6項において「1ヶ月を下ることができない」と規定されています。実務上は安全を見て1ヶ月と数日を設定することが一般的です。この期間はM&Aのスケジュールに大きく影響するため、プロジェクト計画の段階から考慮しておくことが重要です。
まとめ|事業譲渡における債権者対応のポイントを理解し成功に導くには
事業譲渡では会社法上の債権者保護手続きの義務はありません。しかし、債権者に不利益が生じる可能性がある場合には、事前に対応を検討し、ケースに合わせた措置を講じることが望ましいでしょう。
M&Aにおける債権者保護手続きは、法的要件を満たすだけでなく、債権者との良好な関係維持の観点からも慎重に進める必要があります。
CINC Capitalでは、業界10年以上の経験を持つM&A専門家が、効率的かつ確実な債権者対応をサポートします。マーケティングテクノロジーを活用した業務効率化と、業界最低水準の手数料体系で、オーナー経営者の円滑なM&A実現をバックアップしています。債権者保護手続きを含む、M&Aプロセス全般についてお気軽にご相談ください。

















