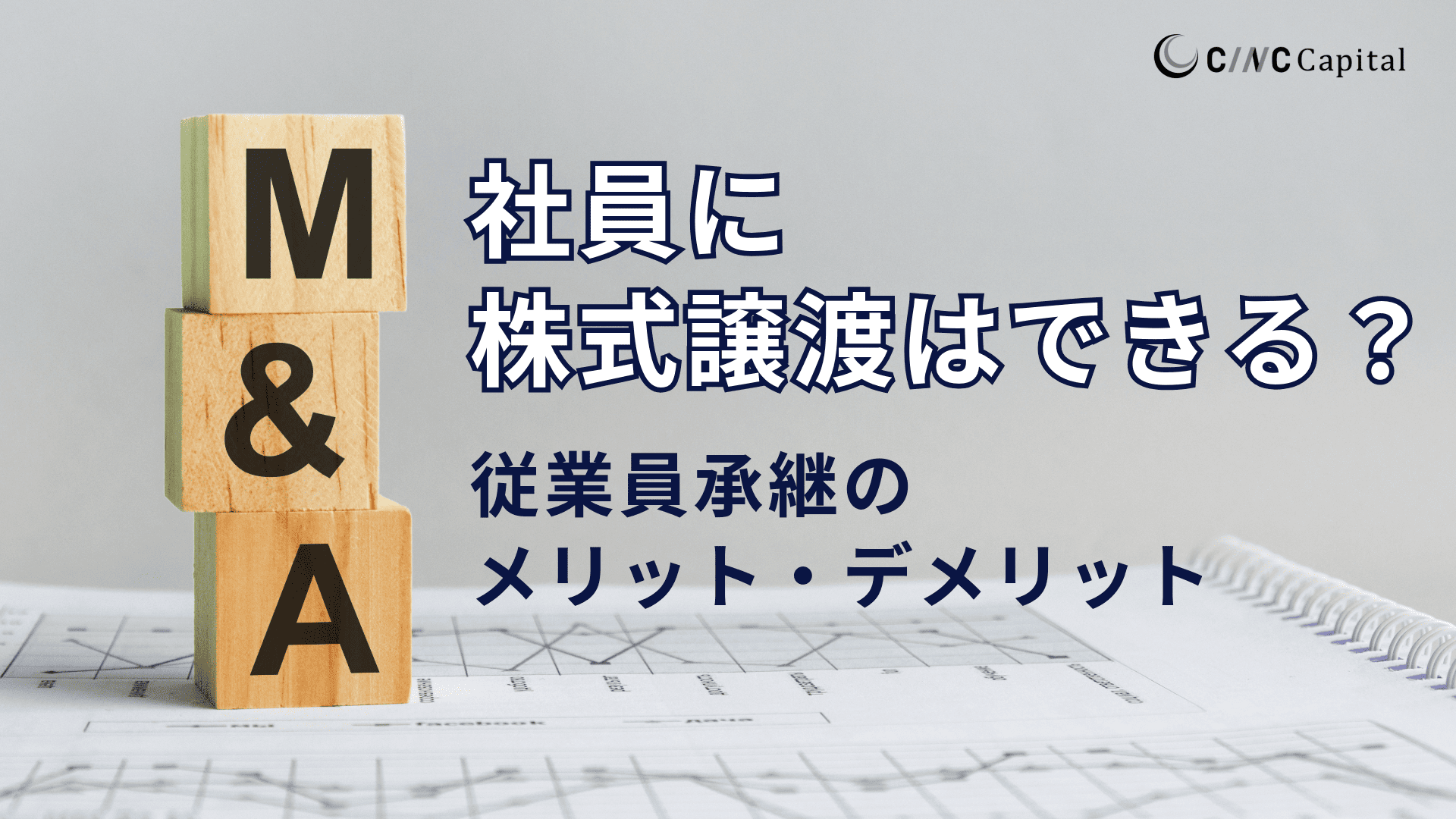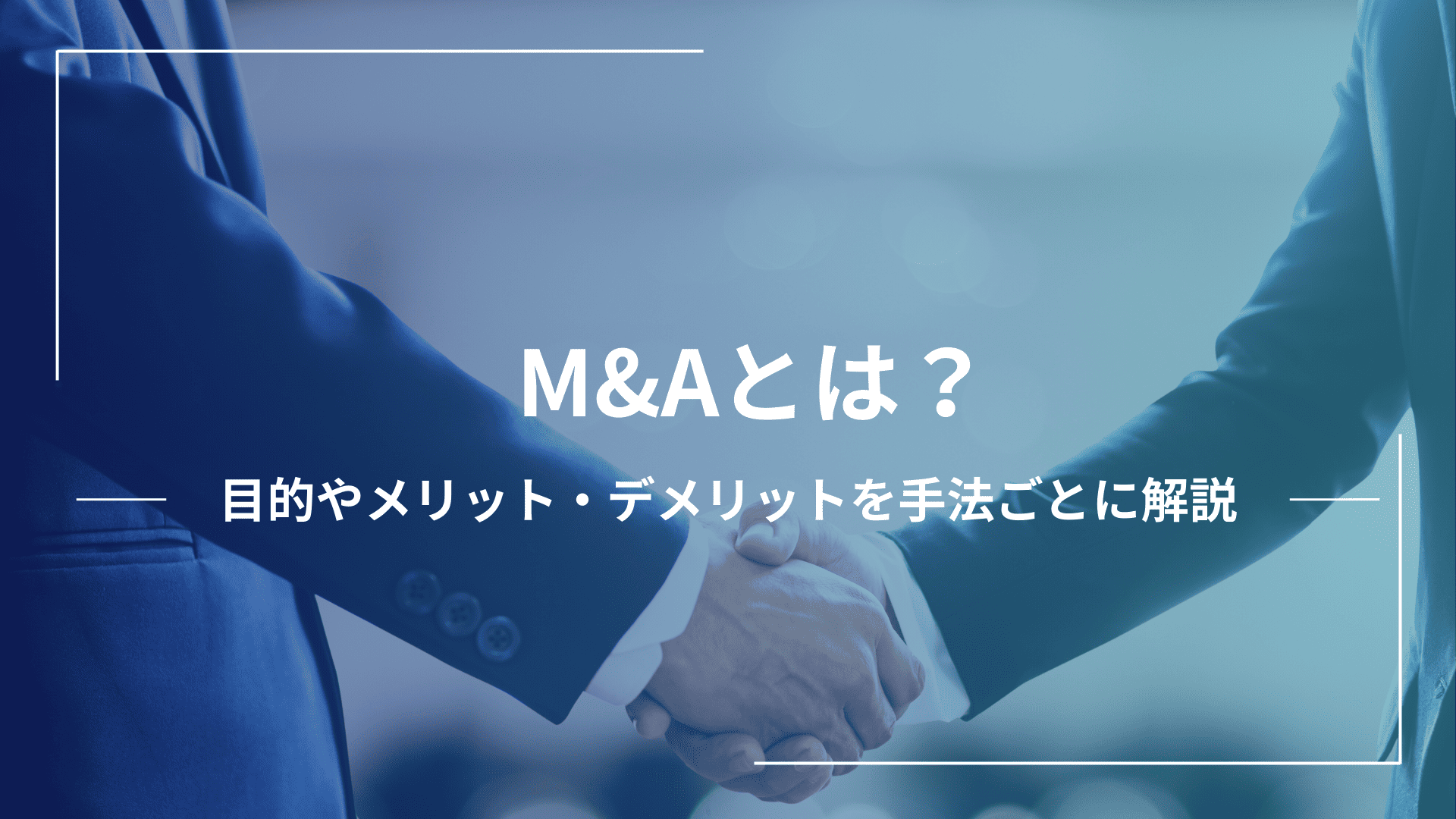CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
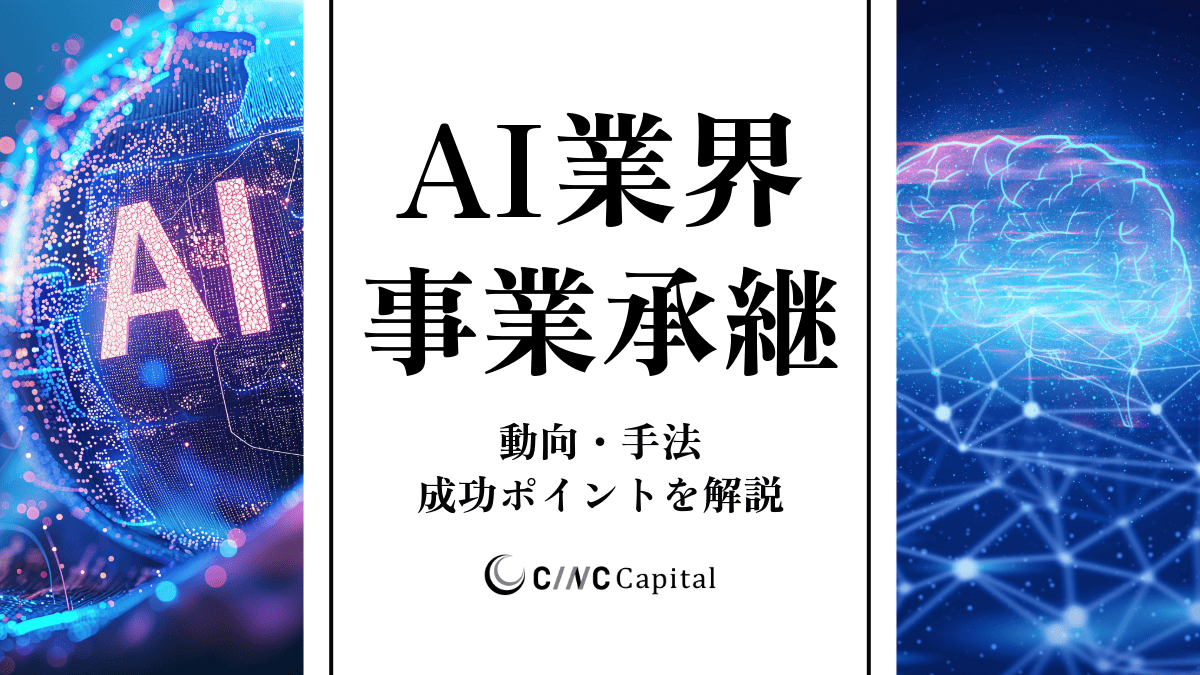
業種
- 最終更新日2025.09.30
【2025年】AI業界の事業承継とは?動向や手法、メリットデメリット、成功のためのポイントを解説
AI業界の事業承継について不安を感じていませんか?
「市場が急拡大している中で、自社をどう次世代に引き継げばいいのか」「技術や人材の継承はどうするべきか」と悩んでいる方も少なくありません。
本記事では、AI業界における最新の市場動向や、事業承継に伴う課題、承継手法の種類など、成功に導くための具体的なポイントを解説します。
目次
AI業界の市場動向と課題
国内のAI市場は年率30%を超える成長を続けており、2024年には約1兆円規模に拡大しています。
その一方で、専門人材の不足やノウハウの属人化といった業界特有の課題も顕在化している側面もあるのです。
本章では、市場動向と課題について3つのポイントに分けて解説していきます。
【出典】IDC「2024年 国内AIシステム市場予測を発表」
【出典】総務省「令和6年版 情報通信白書」
AI事業の市場規模は拡大傾向
2023年から2024年にかけて、日本のAIシステム市場は前年比で56.5%成長、市場規模は1兆3,412億円に達し、急速な拡大が続いています。
IDC Japanの予測によると、2025年以降には再び成長が加速し、2029年には4兆1,873億円まで伸びると見込まれているのです。
こうした成長の背景には、生成AIの普及によって企業が業務の自動化や効率化を目的にAI導入を加速させていることがあります。
さらに、生成AI単体の市場は2024年時点で1,016億円に達しました。
2028年には、年平均84.4%の成長率で、8,028億円規模まで拡大するとされています。
【出典】IDC Japan 株式会社「国内AIシステム市場予測を発表」
【出典】IDC Japan 株式会社「国内生成AI市場は今後5年で8,000億円規模への成長を予測」
専門人材の不足と育成の困難さ
日本のAI企業では高度な専門人材が依然として不足しており、中でも中小企業では採用・定着・育成のすべてが難航しています。
特にAIエンジニアに関しては求人倍率が極めて高く、人材獲得の競争が激化しています。
多くの中小企業で人手不足が起こっており、継続的な教育体制や経験を積ませる場の整備が追いついていない実情です。
そのため、事業承継の際に後継者となるべき人材が十分に育たず、企業の将来の安定に暗雲が垂れ込める状況にあります。
技術・ノウハウの属人化が課題
AI企業では創業者や主要エンジニアに業務の根幹が依存しやすく、ノウハウが暗黙知として埋もれてしまう傾向があります。
文書やマニュアルの整備が後回しになり、結果として限られた人しか内容を理解できず、他の人が再現できない状況がよく見られます。
このような属人化状態のまま事業承継を進めると、承継先が知識や技術を引き継げず、プロジェクトが停滞するリスクにつながるでしょう。
【2025年】AI業界の事業承継の最新動向
2025年現在、日本のAI業界では、特にM&Aを中心とした事業承継の事例が徐々に増加しつつあります。
本章では、AI事業の最新動向について詳しく見ていきましょう。
大手企業によるAIスタートアップの買収が活発化
近年、大手通信企業や総合商社などの非AI企業がAIスタートアップの買収に積極的に動いています。
これによりAI技術と人材の獲得が可能になり、競争優位を維持しやすくなっているのです。
たとえば、KDDIは2024年3月にELYZAへの出資・子会社化を発表し、自社グループでの生成AI活用に向けた連携を強めています。
この買収により日本語大規模言語モデル(LLM)を自社で扱えるようになった点が注目されています。
こうした動きは市場全体における即戦力型M&Aの流れを象徴しており、今後も大手によるAI技術獲得競争が一層激化する見込みです。
【出典】KDDI株式会社「ELYZAとKDDIグループ、生成AIの社会実装に向け資本業務提携を締結」
スタートアップ同士の統合・M&Aも進行
国内では、AIスタートアップ同士の統合やM&Aが活発になっています。
資金調達が難しい企業が他社と手を組むことで、技術やビジネスの基盤を補い合い、安定した事業承継が実現しやすくなるのです。
買収を目的とした一方的な承継ではなく、対等なパートナーとして協力し合う形が広がっているのが特徴です。
AI業界で事業承継を実施する方法は?
AI業界では、事業承継の手段として「親族内承継」「従業員承継」「M&A」の3つが主に用いられています。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、企業の状況や将来のビジョンに応じて、最適な方法を選ぶことが重要です。
以下では、それぞれの承継方法について詳しく解説します。
親族内承継
親族内承継は、経営者の子どもや兄弟姉妹など、家族に会社を引き継ぐ方法です。
身内での承継となるため、従業員や取引先からの信頼を維持しやすく、社内の混乱が起きにくいというメリットがあります。
また、後継者が早い段階から事業に関与できるため、時間をかけて教育・引き継ぎを行える点も強みです。
従業員承継
従業員承継は、経営者の子どもや親族ではなく、会社に長年勤めてきた役員や従業員に事業を引き継ぐ方法です。
社内の事情や業務内容を深く理解している従業員が後継者となるため、事業の継続性が高く、従業員や取引先からの信頼も得やすいというメリットがあります。
また、既に社内での実務経験や人間関係を築いているため、スムーズに経営を引き継ぎやすく、育成や教育の負担を軽減できる点も強みです。
M&A
M&A(合併・買収)は、株式や事業を他社に売却し、経営権を譲渡する形での承継方法です。
創業者にとっては事業の収益化が可能となり、長年築いてきた企業価値を資金として回収できます。
また、買い手企業が既存の体制や雇用を維持する方針を取れば、従業員や取引先にとっても安心できる承継手段です。
AI事業を事業承継するメリット
AI事業を承継することには、企業の価値を維持・向上させながら、組織の安定や成長を促すさまざまな利点があります。
ここでは代表的な5つのメリットについて、見ていきましょう。
雇用維持
事業承継によって従業員の雇用が守られることは、企業にとって大きな安心材料です。
特にAI事業のように専門人材に支えられている業界では、突然の廃業や経営交代による人員流出は大きな損失につながります。
承継によって経営体制が安定すれば、従業員は将来への不安を感じることなく、安心して働き続けられるでしょう。
資金流動性向上
AI事業を承継することで、創業者がこれまで保有していた株式などの資産を現金化が可能です。
M&Aのうち株式譲渡で得られる資金はオーナー個人の手元に残るため、新たなライフステージへの資金として活用できます。
一方、事業譲渡の場合は法人に資金が入り、新規事業への再投資などに使いやすくなります。
特にベンチャー型のAI企業では、株式の評価額が高くなるケースも多いため、経営者にとっては資産の出口戦略として有効です。
経営体制の刷新
事業承継を機に、外部の経営者やコンサルタントが加わることで、経営体制を見直すきっかけになります。
これにより、意思決定がより合理的・戦略的になり、成長戦略の再構築や業務の改善が進みやすくなります。
特に創業者が中心となっている企業では、第三者の視点が加わることで社内に新しい気づきが生まれ、組織の活性化にもつながるのです。
相続税・贈与税の対策
AI事業の承継に際しては、株式や事業資産にかかる相続税や贈与税への対策が欠かせません。
国や自治体では、一定条件を満たす場合に相続税・贈与税の納税を猶予・軽減する「事業承継税制」などの制度が用意されています。
これらを活用することで、後継者が過大な税負担を背負うことなく、スムーズに事業を引き継ぐことが可能です。
技術継承
AI事業の中核は、開発されたアルゴリズムや蓄積された学習データ、そしてそれを扱う人材の知見です。
これらの技術資産をしっかりと次の世代へ引き継ぐことにより、競合他社との差別化を図り、長期的な競争優位性を維持することが可能になります。
事業承継を通じて技術やノウハウが文書化・体系化されることで、属人化の解消にもつながり、より強固な組織運営が実現されるのです。
AI事業を事業承継するデメリット
AI事業の承継には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきリスクも存在します。
特に、経営体制の変化や企業文化の違い、後継者選定の失敗などは、事業の継続や成長に大きな影響を及ぼしかねません。
本章では代表的な3つのデメリットについて詳しく解説します。
経営主導権の喪失
M&Aや第三者承継によって事業を引き継ぐ場合、創業者が経営から完全に退くケースも少なくありません。
これにより、長年築いてきた経営方針や意思決定プロセスが一変し、会社の方向性に影響が出る可能性があります。
事前に「どこまで関与を続けるか」「新経営陣との意思疎通をどう取るか」についてすり合わせをしていきましょう。
文化・組織の混乱
AI企業では、独自の文化やチームの結束力が事業を支える大きな要素です。
ところが、事業承継によって新しい経営者や親会社が加わると、社風や働き方の違いから社内が混乱することがあります。
たとえば、意思決定のスピードや組織の仕組みが変わることで、従業員のやる気が下がり、退職者が増えてしまうケースもあります。
後継者とのミスマッチ
従業員承継やM&Aにおいて、後継者の選定は最も慎重に進めるべきポイントです。
仮に経営能力やビジョンが不一致な人物が後を継いだ場合、組織の求心力が低下し、事業の方向性がぶれてしまう恐れがあります。
特にAI分野では、専門的な理解やスピード感のある意思決定が求められるため、後継者に一定以上の技術知識や業界理解が必要です。
AI業界の事業承継を成功させるためのポイント
技術や人材が属人化しやすいAI業界では、事前準備の質が事業の存続を左右します。
本章では、承継を円滑かつ前向きに進めるための5つの具体的なポイントを見ていきましょう。
技術資産・知的財産の棚卸しと可視化
自社のAIモデルやソースコード、蓄積データなどの技術資産は、定量・定性的に整理し、明確に文書化することが重要です。
M&Aを含む事業承継では、知的財産の正確な評価と引き継ぎが企業の評価や将来性に大きな影響を与えます。
そのため、承継を円滑に進めるには、早期に資産の可視化が必要です。
主要エンジニア・研究者の継続関与の確保
承継後もキーパーソンが継続して活躍できるよう、技術継承の体制を整えておくことが重要です。
そのためには、報酬や役職の見直しに加え、ストックオプションや成果連動型の報奨制度など、適切なインセンティブを用意することが効果的です。
あらかじめこうした仕組みを整えておくことで、技術人材の離職によるノウハウやプロジェクトの喪失リスクを抑えることができます。
業務・ナレッジの形式知化
業務フローや顧客対応のノウハウなどをマニュアル化し、誰でも再現できる形で残すことが大切です。
AI領域では、コードだけでなく研究手法やアルゴリズムの選定理由も言語化する必要があります。
このように文書化されたノウハウを整備しておくことで、承継後もスムーズに事業を引き継ぎ、安定した運営が可能になるのです。
M&Aを前提とした戦略設計と専門家活用
AI企業が承継を前提とする際には、M&Aを意図した戦略構築が不可欠になります。
そのため、M&Aアドバイザーや知財評価の専門家、技術コンサルタントと早期に連携を取り、適切なバリュエーションや交渉体制を整えなければなりません。
仲介者との協働によって、企業価値の正当な評価・交渉が可能になり、第三者承継の成功率を高められます。
承継後の成長戦略を描く前向きな選択肢
事業承継は終わりではなく、成長の起点と捉えることが重要です。
統合計画や将来のビジョンを明確に示すことで、従業員や買収側の理解と信頼を得やすくなり、組織全体が前向きに取り組む雰囲気が生まれます。
AI業界の事業承継に関するよくある質問
Q1.承継をする際のステップは?
まずは 親族承継・社内承継・M&A など、どの方法で事業を引き継ぐのかを検討します。併せて、会社の価値や資産となる AIモデル、学習データ、特許、ソースコード などを整理しておきましょう。
次に、契約や利用規約、データの取り扱いについて 移転が可能かどうかを確認 し、必要に応じて 法務・許認可や情報セキュリティ体制 を整えていきます。
M&Aの場合は、この段階で 仲介会社に早めに相談 しておけば、自社に合った候補先を探す時間を十分に確保でき、承継方法の比較やスケジュール調整もスムーズに進められます。
その後は、譲渡契約の締結と同時に システムやレポジトリ、APIキーを引き渡し、さらに 社員や顧客への告知を計画的に実施 することで、経営やサービス提供を途切れさせることなく円滑な引き継ぎが可能になります。
Q2.AI業界の事業承継の際に使える補助金は?
中小企業庁による「事業承継・引継ぎ補助金」(現:事業承継・M&A補助金)が代表的な支援策で、事業承継やM&Aに伴う経営革新等の費用に対して、条件を満たす場合には最大で約800万円の補助を受けられる可能性があります。
また、国によるDX投資促進税制などの税制優遇措置がデジタル関連投資を後押ししてきた経緯もあり(同税制は2025年度末まで適用)、AI・DX分野の取り組みに対する支援策は補助金・税制の両方で整備されています。
Q3.ノウハウが属人化していても承継できますか?
属人化したノウハウがあっても事業承継は可能ですが、そのままでは特定の人材が抜けた際に知識や技能が失われ、業務が滞るリスクがあります。
円滑な承継のためには、個人に依存した業務や知見を見える化・標準化し、マニュアル整備やナレッジ共有によって「誰が担当しても同じ成果を出せる」体制を構築することが重要です。
まとめ|AI業界の事業承継を円滑に進めるために
AI業界は急成長を続ける一方で、人材不足や技術の属人化といった課題も抱えています。
事業承継を成功させるには、こうしたリスクを踏まえた上で、適切な承継方法と体制を整えることが重要です。
CINC Capitalは、AI企業を含む中小企業の事業承継を多数支援しています。
将来を見据えた承継計画の立案を通じて、経営者の理念や企業の持つ本質的価値を次世代へ円滑に継承する支援を行っております。
無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。