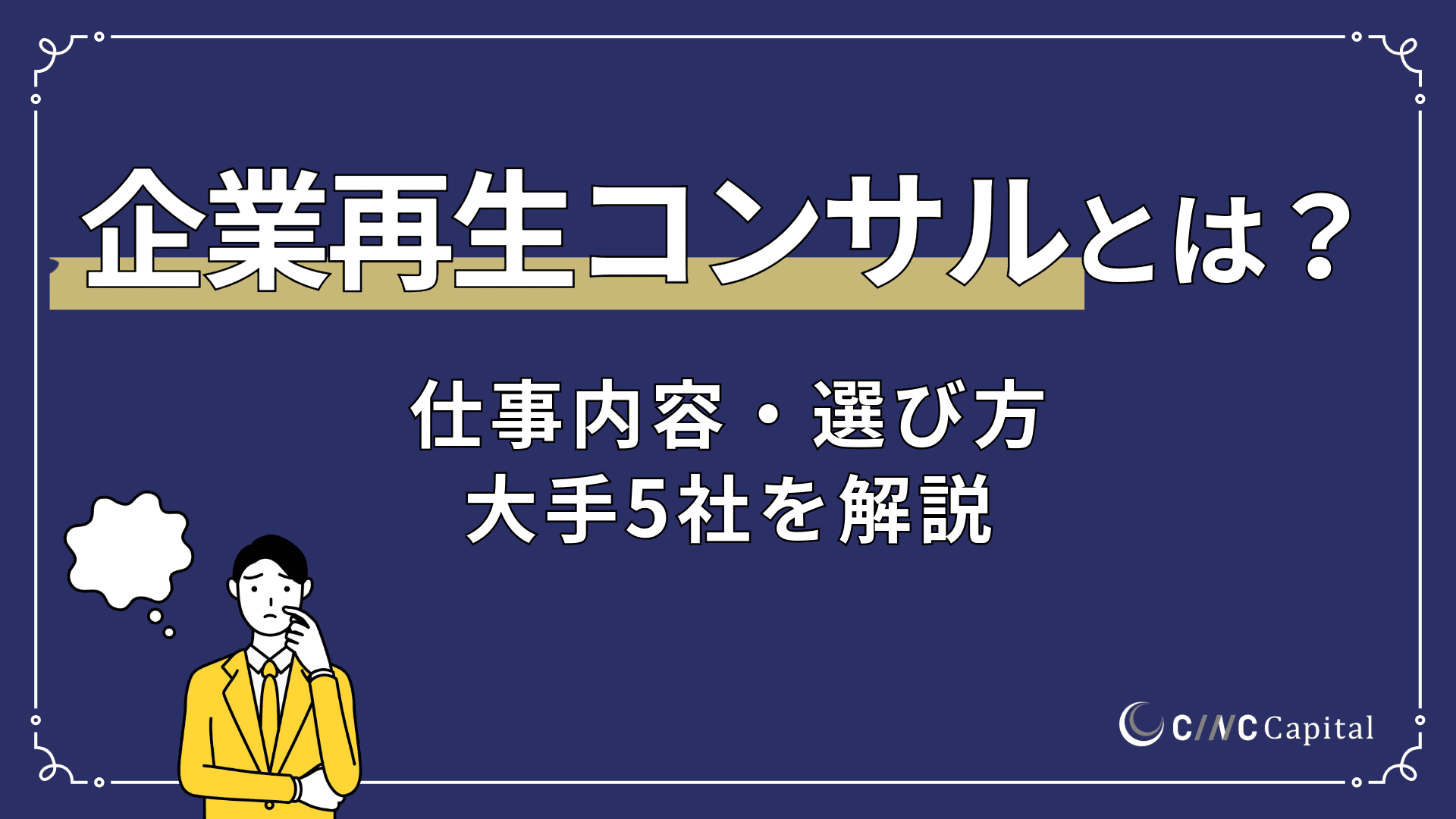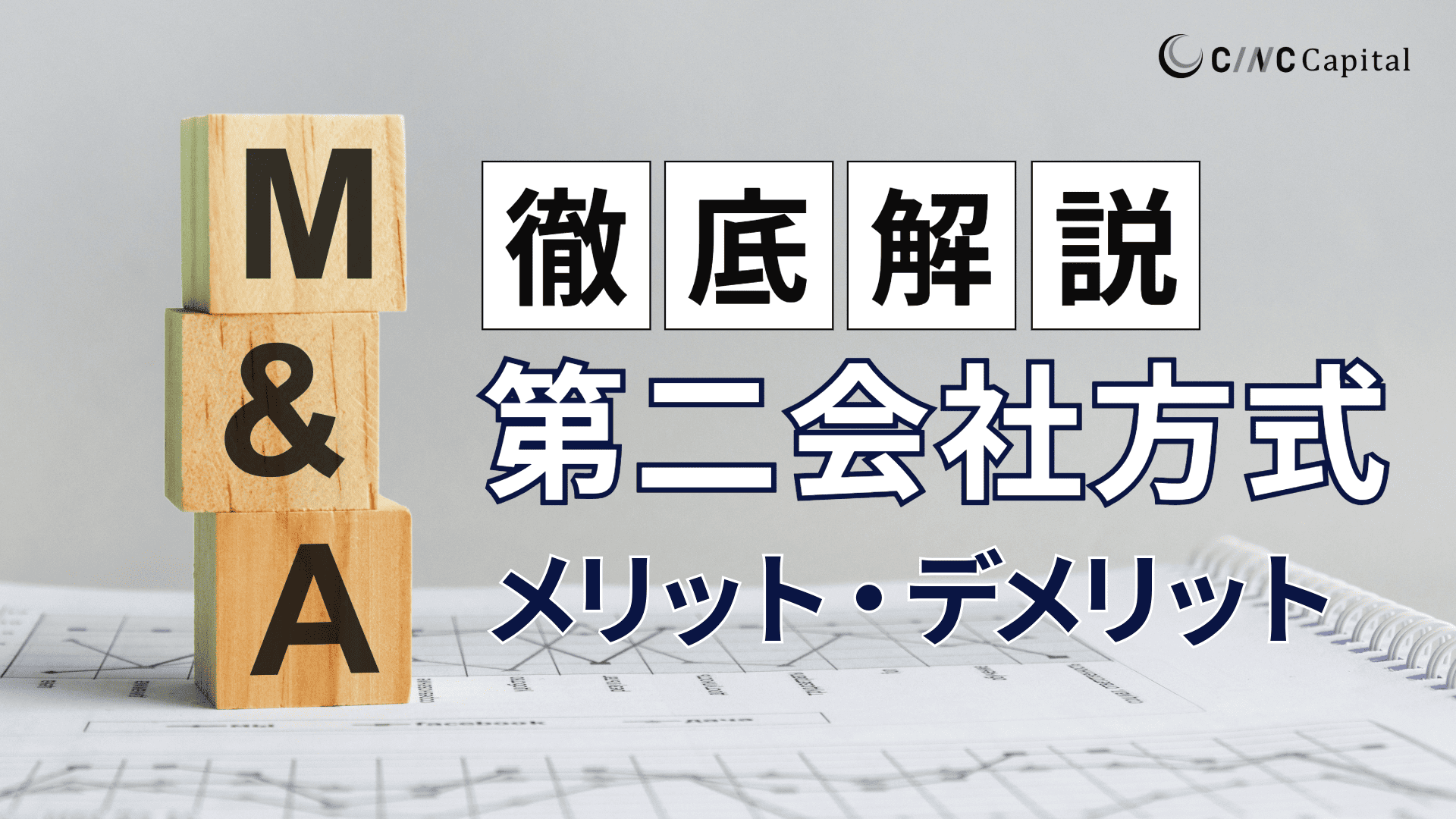CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
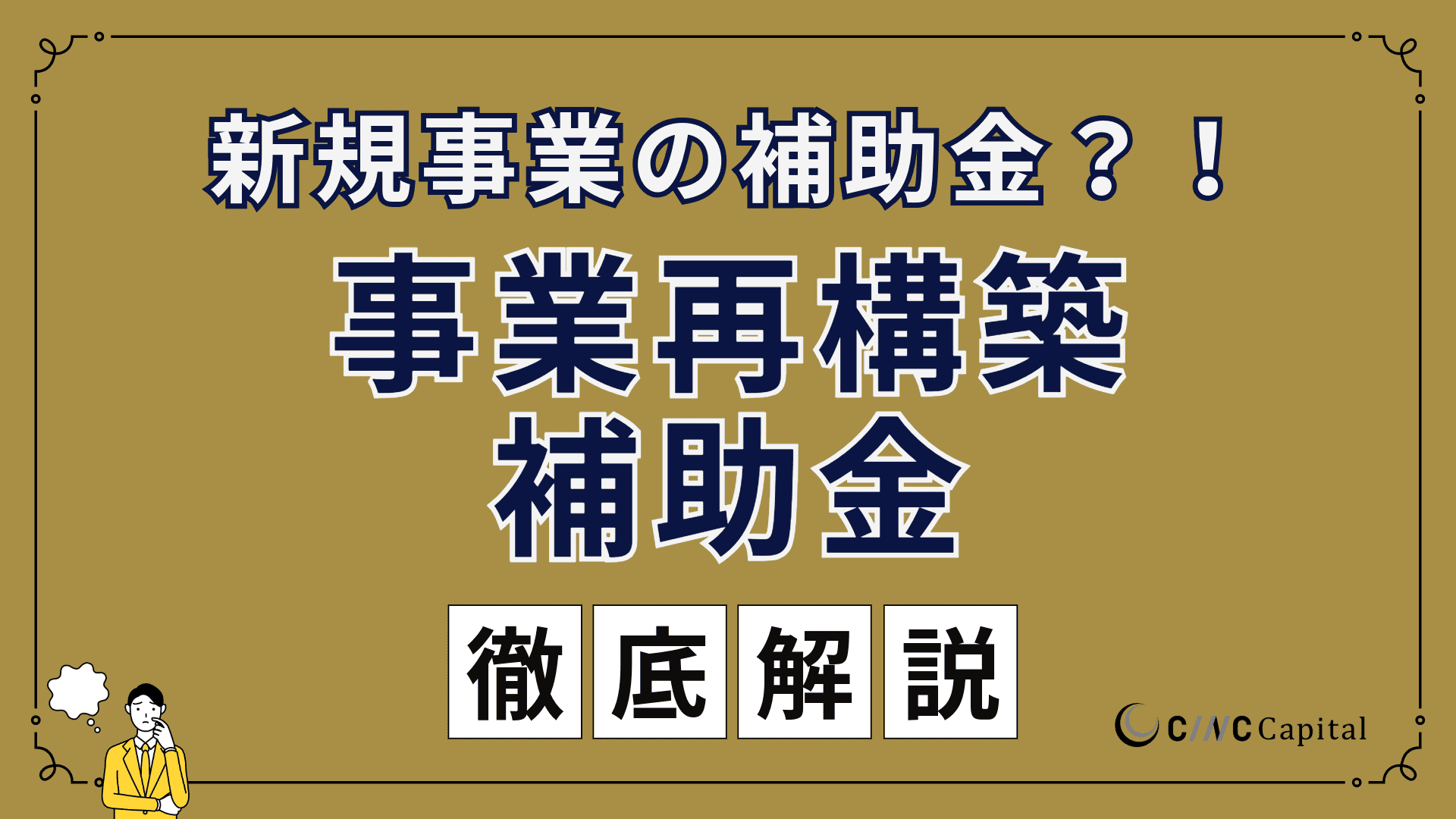
再生 / 事業再生
- 公開日2025.09.30
事業再生のための補助金とは?事業再構築補助金の概要と申請のポイントを解説
売上が伸び悩んでいる・既存事業だけでは将来に不安を感じていませんか?
新しい挑戦をしたいが、資金面の不安が大きく、どこから準備すればよいかわからないという方も多いでしょう。
本記事では、事業再構築補助金の概要から目的、補助対象、申請の流れや注意点などを詳しく解説します。
目次
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業がコロナ後の時代に対応するために、新しい事業に挑戦する際の費用を国が支援する制度です。
売上が減った企業が、新たな収益の柱をつくる取り組みを後押しし、日本全体の産業構造の転換を目指しています。
例えば、飲食店がテイクアウト専門の店舗を始める場合や、製造業がネット販売に切り替えるような事例が対象です。
事業転換を考える企業にとって、成長のきっかけとなる制度です。
【出典】経済産業省「事業再構築補助金」
事業再構築補助金の目的
事業再構築補助金の目的は、コロナ禍で既存事業の継続が困難になった企業が、新たな事業に挑戦し、経済構造の転換と成長を実現することにあります。
単なる一時的な資金援助ではなく、中長期的な企業成長と、日本経済全体の活性化を促す政策として設計されています。
具体的には、需要が縮小した事業から脱却し、成長分野へ移行することを支援します。
外食産業がオンライン販売に進出したり、製造業が脱炭素技術へ転換したりすることで、企業が変化に柔軟に対応し、収益性を回復させる道を広げます。
事業再構築補助金の補助対象者
事業再構築補助金の補助対象者は、主に日本国内に本社を置く中小企業や中堅企業、個人事業主です。
事業再構築に取り組む意思があり、一定の要件を満たす事業者が申請の対象となります。
具体的には、資本金や従業員数の基準を満たす中小企業・中堅企業のほか、企業組合、事業協同組合、特定非営利活動法人なども対象となります。
ただし、政治団体や宗教法人、補助金の趣旨に沿わない事業を営む法人は対象外です。
さらに、法人格の有無にかかわらず、継続的な事業活動を行っていない場合は申請できません。
事業再構築補助金の補助対象
事業再構築補助金では、どのような経費が補助の対象になるのかが明確に定められています。
補助対象経費に該当しないものを計上してしまうと、補助金を受け取れないリスクがあるため注意が必要です。
本章では、補助対象となる経費と、対象外となる経費の違いを詳しく解説します。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は、事業再構築の実施に直接必要な投資に限られます。
理由は、補助金の目的が新たな事業活動を支援することにあるからです。
例えば、建物の改修費や新設備の導入費、ITシステムの構築費などが対象になります。
さらに、広告宣伝費や外注費、専門家への報酬なども、計画の遂行に不可欠なものであれば補助対象として認められます。
補助対象とならない経費
補助対象とならない経費は、日常的な経費や私的利用が疑われる支出です。
補助金は新たな事業構築に限定して使うべきものと定義されています。
例として、パソコンやスマートフォンなどの汎用品、従業員の人件費や旅費、飲食や接待に関する費用、既存商品の仕入費などは対象外です。
また、賃料や光熱費などのランニングコストも補助の対象にはなりません。
不適切な経費計上により採択後に減額修正された例もあるので注意しましょう。
事業再構築補助金の対象になる取り組み
事業再構築補助金を申請するには、事業計画が「事業再構築」に該当する必要があります。
国が定める6つの類型のいずれかに該当する取り組みであることが必須です。
本章では、各類型がどういった取り組みを指すのか、それぞれの要件や目的について解説します。
新市場進出
新市場進出とは、これまで扱っていなかった商品やサービスを開発し、まだ販売したことのない新しい市場にチャレンジすることです。
このような取り組みが求められるのは、今の市場が縮小している中で、新たな収益源をつくる必要があるからです。
例えば、来店型の飲食店が冷凍弁当を作り、インターネットで販売を始めるケースがこれに当たります。
このように、これまでとは全く違う市場でビジネスを始めることが、新市場進出です。
事業転換
事業転換は、主たる業種は維持したまま、主力商品やサービスを別の内容に切り替える取り組みです。
この方法が有効な理由は、既存の業種内で強みを活かしながらも、売上の中心を変えることで収益の立て直しが可能になるためです。
例えば、宿泊業が宿泊サービスの提供をやめ、同施設をコワーキングスペースとして貸し出すようなケースが該当します。
事業転換はリスクを抑えつつ、事業構造を大胆に変革できる戦略として注目されています。
業種転換
業種転換とは、現在営んでいる主たる業種そのものを変更し、別業種で事業を開始する取り組みです。
根本的なビジネスモデルを見直すことが必要な場合、この手法は有効です。
アパレル製造業が事業をたたみ、新たに食品加工業へ参入するようなケースが該当します。
業種コードが変更されるほどの転換であることが要件となります。
事業再編
事業再編とは、合併、会社分割、事業譲渡などの企業再編行為を通じて、事業の構造を変える取り組みです。
この類型が設けられているのは、経営資源を再配置することで、新たな収益機会を生み出すためです。
例として、自社が他社を吸収合併し、統合した事業体で新しい製造ラインを構築するようなケースが挙げられます。
事業再編は複数企業の強みを活かし、競争力の高い新事業の立ち上げを実現する手法です。
国内回帰
国内回帰は、これまで海外にあった生産・調達拠点を日本国内に戻し、新たな国内体制を構築する取り組みです。
この取り組みが重視される理由は、海外依存リスクの低減と地域雇用の創出にあります。
例えば、中国で行っていた製品製造を打ち切り、国内に新工場を設立して内製化するケースが該当します。
導入する設備は先進的なものである必要があります。
地域サプライチェーン維持・強靱化
地域サプライチェーン維持・強靱化とは、ある地域で必要な製品が作れなくなったときに、その供給体制を立て直す取り組みです。
この取り組みが求められるのは、地域の経済を安定させ、必要な製品を途切れさせないようにするためです。
災害や事業撤退で供給が止まった部品を、地元の企業が代わりに作れるようにするケースが該当します。
こうした取り組みは、地域の産業を守り、サプライチェーンの穴を埋めるものとして高く評価されます。
事業再構築補助金の類型
事業再構築補助金には、申請者の状況や取り組みの内容に応じた複数の「申請類型」が用意されています。
本章では、企業がどの枠で申請すべきかを判断するために、4つの主要な類型について説明します。
なお、新回では異なる類型名や条件になっている場合があります。
各類型に関する補助金額や補助率などの数値情報も、公募回によって異なるため、参考値としてご理解ください。
成長分野進出枠(通常類型)
成長分野進出枠(通常類型)は、最も多くの企業が利用する基本的な枠で、新市場への参入や業態転換など幅広い事業再構築に対応しています。
例えば、飲食店が無人販売所を始める場合もこの枠に該当します。
中小企業では、従業員数に応じて1,500万~5,000万円が上限となっており、業種転換や新分野進出を目指す企業に最適な申請枠です。
成長分野進出枠(GX進出類型)
GX進出類型は、再生可能エネルギーやEV、水素などの脱炭素分野に進出する企業を対象とした特別枠です。
国のグリーン成長戦略に沿った事業を後押しする目的で設けられており、補助上限や加点措置が優遇されています。
例として、工場が太陽光+蓄電池設備に切り替える事業などが挙げられます。
GX重点14分野(経済産業省が定める脱炭素社会の実現に向けた成長分野のこと)に該当する取り組みは、特に高く評価されます。
【出典】経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
最低賃金類型は、最低賃金の上昇で人件費が増えた中小企業を支援する特別枠です。
最低賃金+50円以内で雇用する従業員が10%以上いる企業が対象で、補助率は最大3/4と高く、設備投資の負担を軽減できます。
賃上げの影響を受ける企業が再構築に取り組みやすい制度です。
【出典】経済産業省「事業再構築補助金 (D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」
規模拡大・大幅賃上げへの支援
この上乗せ枠は、通常の申請枠に加えて、将来的に規模拡大や大幅な賃上げを行う企業に補助上限の引き上げを認める制度です。
中小企業の「卒業」や継続的な賃上げ計画を持つ企業が対象で、補助金上限は最大で倍増し、採択優先度も高くなります。
社会的・経済的なインパクトを生む企業活動を後押しする制度です。
【出典】経済産業省「事業再構築補助金 (G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」
事業再構築補助金の申請の流れ
事業再構築補助金を受けるには、事前の準備から補助金の交付まで、複数のステップを正確に踏む必要があります。
本章では、最初の段階である「申請前の準備」について解説します。
申請前の準備
申請準備で最初にすべきことは、制度の内容と手続きの流れを正しく理解することです。
補助金の条件や申請方法は回ごとに異なるため、確認を怠ると不採択になったり、申請が無効になることがあります。
例えば、GビズIDを取得していないと申請自体ができず、公募要領を読まずに書類を作ると不備が出やすくなります。
公募要領の確認
事業再構築補助金を申請する際には、最新の公募要領を必ず確認する必要があります。
その理由は、公募回ごとに制度の条件や申請内容が変更されることがあるためです。
補助対象経費や加点要件、補助率、書類の提出形式などは年度や回次によって細かく異なります。
前回の情報をそのまま使うと要件を満たさない場合があるので注意しましょう。
GビズIDの取得
GビズIDプライムは、補助金の電子申請に必須の共通認証IDです。
なぜ取得が必要かというと、事業再構築補助金はオンラインでの申請が義務化されており、このIDがなければ申請画面にアクセスできないからです。
GビズIDの取得には、申請手続き完了まで通常でも1~2週間程度かかるとされていますが、申請が集中する時期にはさらに時間を要する場合があります。
申請を検討している方は、余裕をもって早めに取得手続きを進めることを強くおすすめします。
事業計画の作成
事業再構築補助金の申請において、最も重要となるのが事業計画の作成です。
審査では計画の実現性や収益性が厳しく評価されるからです。
例えば、新たな市場で何を提供し、どのように利益を確保するかといった説明が曖昧な場合、どれだけ経費が妥当でも不採択となる可能性があります。
事業の新規性や将来的な付加価値の向上、雇用への波及効果なども具体的に示す必要があります。
電子申請の実施
申請書類は、事業再構築補助金の専用電子申請システムからのみ提出できます。
紙やメールでの提出は不可で、GビズIDでログイン後、必要書類をすべてアップロードします。
入力ミスや不備があると申請が無効になるため、事前に操作方法を確認し、余裕を持って提出することが大切です。
採択審査委員会の審査
申請された事業計画は、外部専門家による審査委員会で評価されます。
新規性や実現性、収益性、社会的インパクトに基づき点数がつけられ、採択が判断されます。
見た目やスローガンではなく、成功の根拠が明確に示されているかが重視されます。
採択には、論理性と具体性のある計画を分かりやすく伝えることが重要です。
補助金交付候補者への採択後の手続き
事業再構築補助金は、採択されただけでは実際に補助金が支給されるわけではありません。
その後の「交付申請」「事業実施」「実績報告」などのステップを経て、初めて補助金の受領が可能になります。
以下では、採択後に必要な4つの実務的な手続きについて解説します。
交付申請
採択後にまず行うのが、正式な補助金交付申請です。
これは、採択された事業が補助要件を満たしているかを事務局が確認するための手続きです。
経費や契約見積、資金計画、誓約書などを提出し、内容に基づいて交付額が決まり、交付決定通知が発行されます。
この通知をもって補助金事業として正式に認められます。
事業計画の実施
交付決定後は、計画に沿って補助事業を実施する段階に入ります。
この期間は補助対象経費を実際に使う重要なフェーズです。
建物改修や設備導入、広告、研修などは申請内容通りに行う必要があり、軽微な変更でも事前の届出が求められることがあります。
交付内容を守って進めることで、補助金の適正な利用が保証されます。
実績報告と補助金の請求
補助事業が完了したら、速やかに実績報告を提出する必要があります。
これは補助金の最終額を確定するための手続きです。
事業の成果や支出内容、領収書、請求書、写真などを提出し、内容が確認されると補助金額が確定します。
その後、精算請求を行い補助金が支払われます。
事業の成果の報告
補助金を受け取った後も、一定期間は事業成果の報告が求められます。
国が補助金の効果を把握するために、売上や付加価値額(売上から外部支出を差し引いた企業の生産性を示す指標)、従業員数などの変化を定期的に報告しなければなりません。
こうしたフォローアップにより、補助金の成果確認と企業支援が続けられます。
事業再構築補助金を申請する際のポイント
事業再構築補助金を効果的に活用するには、申請前から採択後までの各段階で押さえるべきポイントがあります。
本章では、特に申請時に意識すべき4つの重要な観点について解説します。
公募スケジュールや応募要件を確認する
補助金申請では、最新の公募スケジュールと要件の確認が最優先です。
補助率や条件、対象経費は公募ごとに変わる可能性があり、古い情報で書類を準備すると不採択になるリスクがあります。
締切日や必要書類、支援機関の署名も早めに確認し、申請前に最新の公募要領を必ず確認することが重要です。
不備のないように申請書類を用意する
申請書類に不備がないことは、採択の前提条件です。
確認書の署名漏れや資料の未添付、記載漏れなどがあると、不受理や減点の対象になります。
見積書や添付ファイルの形式も要注意です。
提出前には第三者によるチェックを行い、形式ミスでの失格を防ぐことが重要です。
実現可能性の高い事業計画を立案する
事業計画は採択の決め手となる最重要書類であり、実現可能性の高さが評価されます。
しかし、市場調査不足や根拠のない収支計画では実行力に疑問を持たれ、不採択につながります。
自社の強みを活かした具体的な戦略を示すことで、審査員の評価を得やすくなるでしょう。
専門家への相談を活用する
申請成功率を高めるには、認定支援機関(中小企業の経営支援に関する専門的な知識や実績を持ち、国から認定を受けた機関のこと)など専門家への相談が有効です。
最新情報や審査傾向に基づくアドバイスにより、内容の整合性や説得力を高められます。
特に申請経験が少ない企業にとって、支援機関の協力は大きな力となり、成功に直結します。
まとめ
事業再構築補助金は、経営環境の変化に対応し、新たな成長を目指す企業を支援する制度です。
申請では、補助対象や事業類型を正しく理解し、実現可能な計画を立てることが重要です。
制度の流れをしっかり確認し、専門家のサポートも活用しながら、着実に準備を進めましょう。
CINC CapitalはM&A仲介協会会員・中小企業庁の登録支援機関です。
業界歴10年以上の専門家が、譲渡や買収の目的に応じて適切な手法をご提案します。
秘密厳守でスムーズな取引を支援します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。