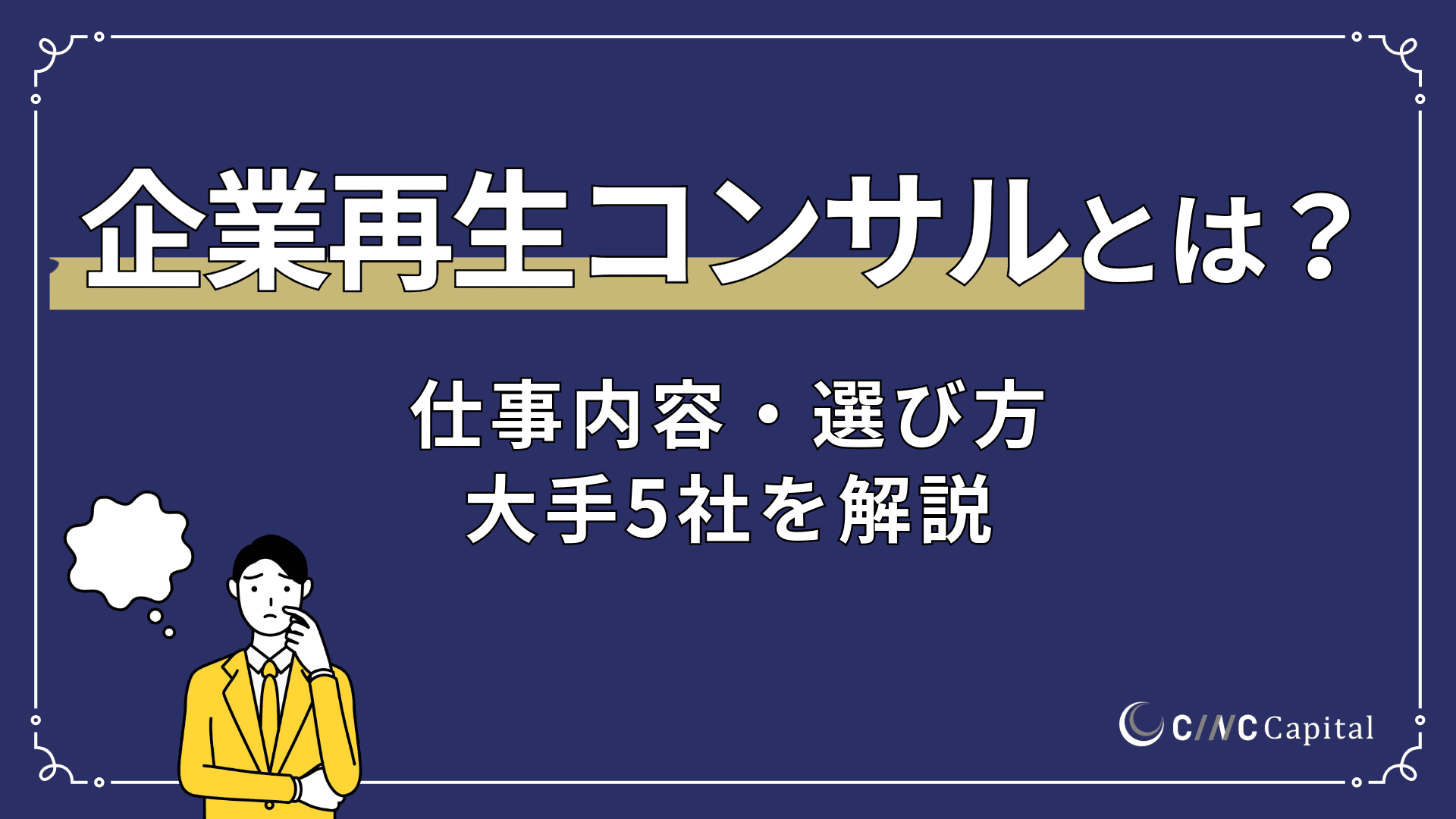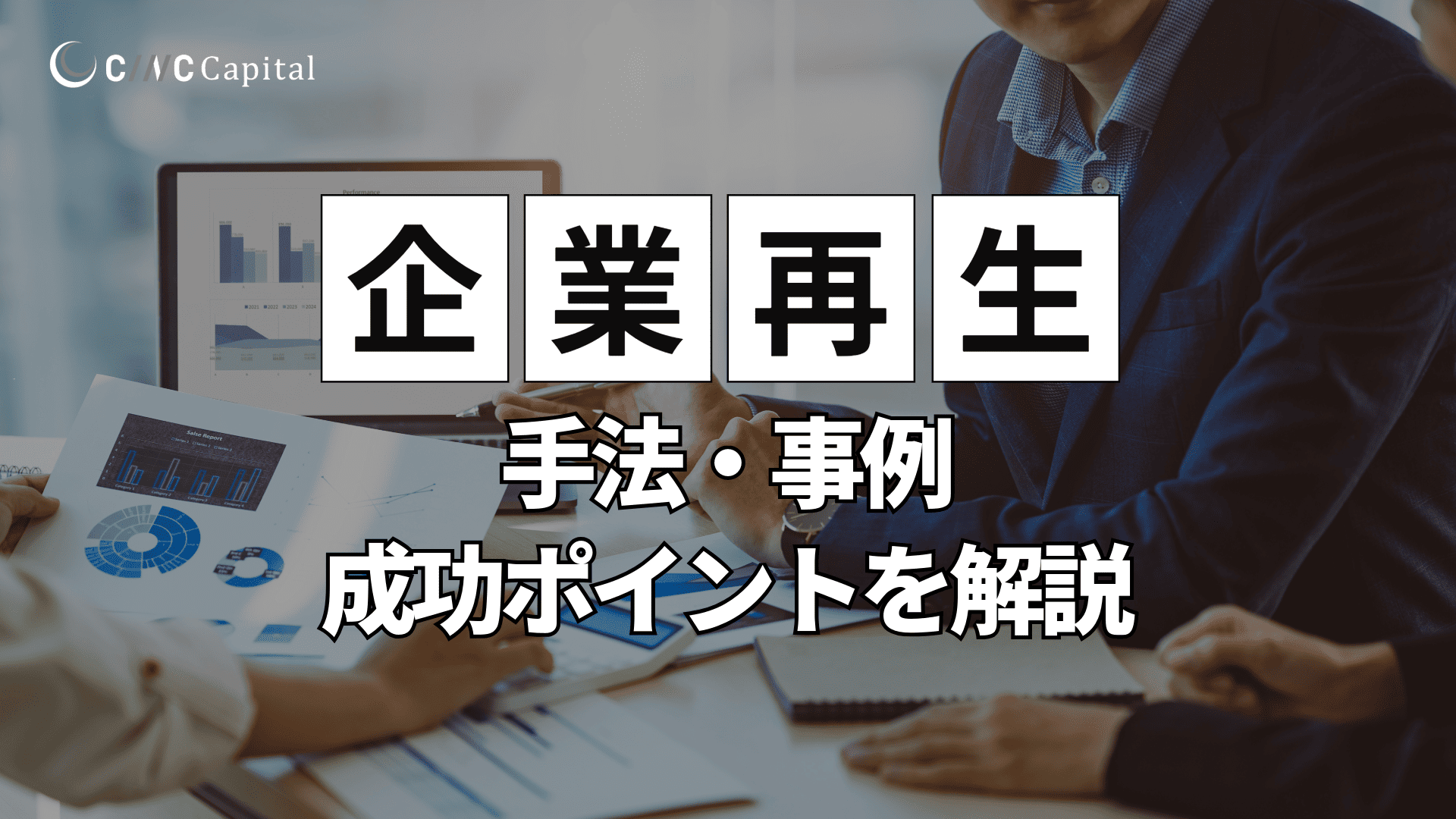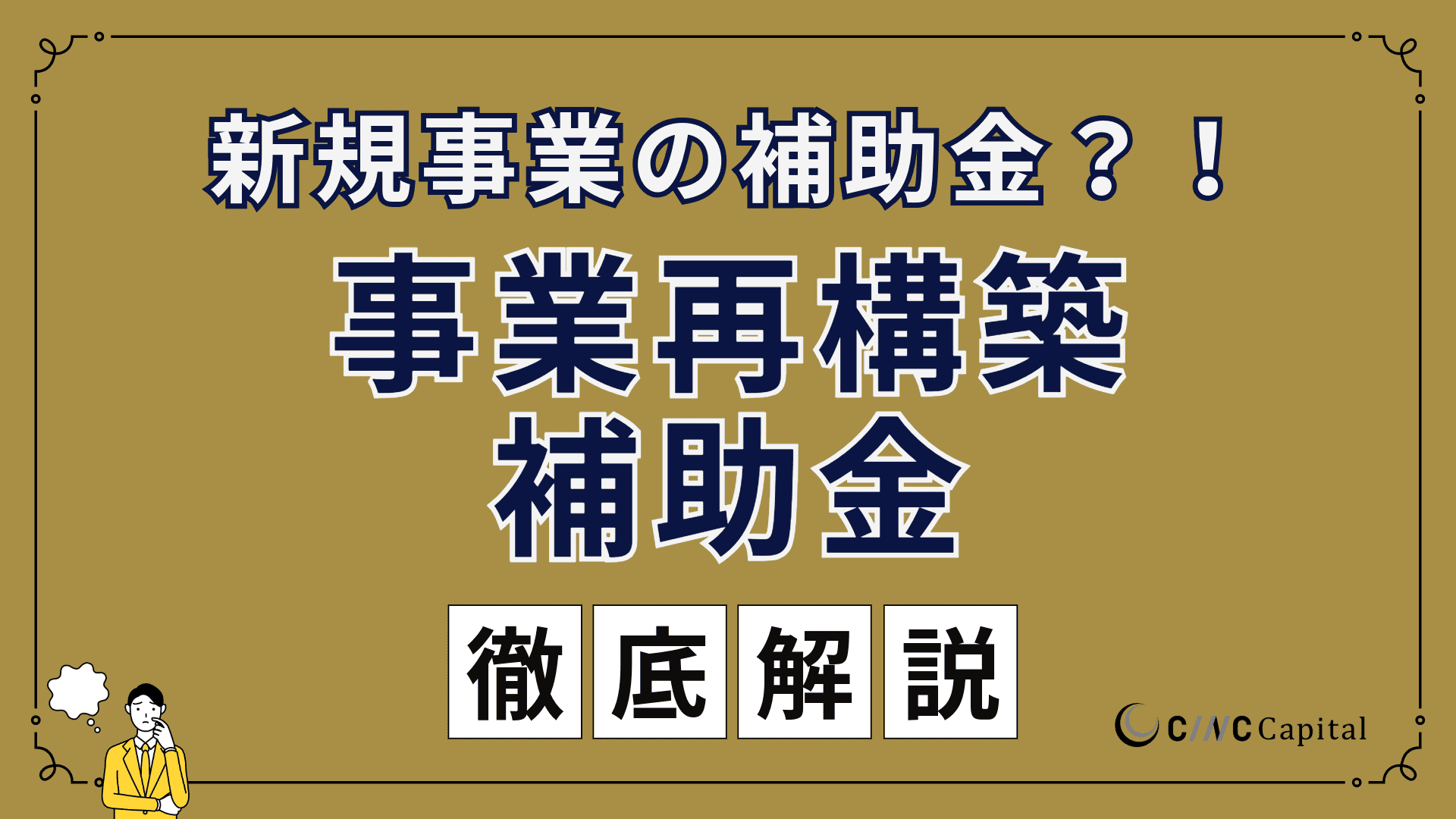CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
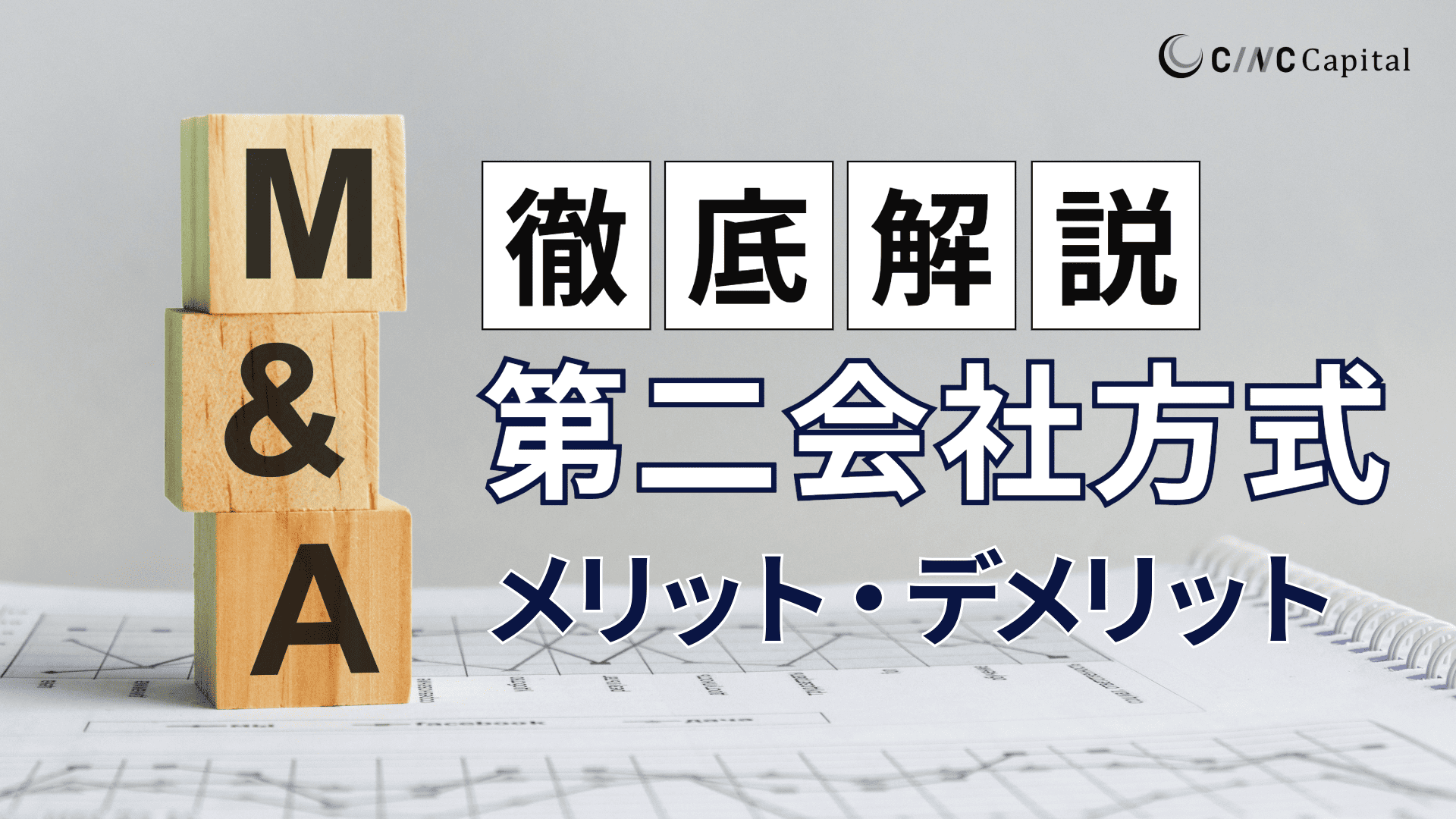
再生 / 企業再生
- 最終更新日2025.06.26
第二会社方式とは?メリットやデメリット、スキーム、債務免除益や税務処理のポイントを解説
経営が厳しくなり、債務の返済が難しいと感じていませんか?倒産を避けつつ事業を存続させる方法を探している経営者の方も多いでしょう。
そんな状況に適した手法が「第二会社方式」です。第二会社方式とは、不採算事業を切り離し、優良事業のみを新会社に移転することで、債務負担を軽減しながら経営を再建できる方法です。
本記事では、第二会社方式の仕組みやメリット・デメリット、実行時の注意点について解説します。
目次
第二会社方式とは?
第二会社方式とは、企業が本業とは別に新たな事業を展開する際、リスク分散や柔軟な経営を目的に別会社(第二会社)を設立する手法です。新規事業の失敗が本体に影響しにくく、独立性の高い運営が可能です。
第二会社方式は、事業を切り分けることで倒産を回避しながら、経営の再生を図れる点がメリットです。成長が見込める事業だけを新会社へ移し、経営資源を有効活用できるため、従業員の雇用維持や取引先との関係継続も可能です。
また、第二会社方式はM&Aの手法と組み合わせることで、外部資本を取り入れた柔軟な再建戦略としても活用されます。
第二会社方式と民事再生や特別清算との違い
第二会社方式は事業再生の一環として用いられる手法で、事業の一部を新設会社に移し再建を図る方法です。
一方、民事再生や特別清算は、主に債務整理を目的とした法的手続きです。民事再生は債務圧縮をしながら企業の存続を図り、特別清算は清算を前提にした整理手続きであり、いずれも裁判所の関与が必要です。対して第二会社方式は裁判所を通さず比較的柔軟に行えるのが特徴です。
民事再生は企業が法人格を維持したまま、裁判所の監督のもとで再建計画を立てる手続きであり、特別清算は会社を清算する際に、債権者との合意のもとで債務整理を進める方法です。
民事再生と比較すると、第二会社方式は手続きの柔軟性が高く、債権者との合意が得られれば迅速に実行できます。民事再生では、裁判所の関与があるため再生計画の認可に時間がかかり、債権者の過半数の同意が必要です。一方、第二会社方式では、主要な金融機関や取引先と調整できれば、より短期間で事業の再建が見込めます。
特別清算との違いは、会社の法人格が存続するかどうかにあります。特別清算は会社を清算し、法人格を消滅させるための手続きです。第二会社方式では、旧会社は清算されるものの、新会社で事業を継続できるため、企業価値を維持しながら経営の再建が可能になります。
第二会社方式が適用できる企業の条件や要件
第二会社方式はすべての企業に適用できるわけではなく、一定の条件や要件を満たす必要があります。特に、事業の存続が可能であること、債権者と合意形成できることが重要です。
主な適用条件としては、以下の3点が挙げられます。
- 企業に収益性の高い事業と不採算事業が混在しており、切り分けが可能であること
- 主要な債権者(金融機関など)が第二会社方式による再建に理解を示していること
- 新会社として事業を継続するための資金繰りの見通しが立っていること
この手法を成功させるためには、企業の財務状況や事業構造を慎重に分析し、適用の可否を判断する必要があります。
経営危機に陥っていても、上記の条件を満たし、収益性の回復が見込める企業であれば、第二会社方式による再建が有効な選択肢となるでしょう。なお、自社が条件を満たしているか確認したい場合は、専門家への相談をおすすめします。
第二会社方式の具体的なスキーム
第二会社方式では、事業を新会社へ移転する方法として、「会社分割」と「事業譲渡」の2つが一般的に採用されます。どちらの手法を選ぶかは、事業の規模や財務状況、債権者との交渉のしやすさなどによって異なります。ここでは、第二会社方式に用いられる会社分割の「新設分割」と「吸収分割」の違い、事業譲渡の特徴について解説します。
会社分割(新設分割・吸収分割)
会社分割は、旧会社から新会社へ特定の事業を包括的に移転する方法で、新設分割と吸収分割の2種類があります。新設分割では、新会社を設立し、そこに対象事業を移転します。吸収分割では、既存の別会社に事業を承継させる形をとります。
会社分割の利点は、契約関係や従業員の雇用を一括で引き継ぎやすい点です。事業の継続性を維持しやすく、取引先との関係もスムーズに移行できます。また、税務上のメリットとして、一定の要件を満たせば資産移転時の税負担が軽減される可能性があります。
一方で、会社分割は法的手続きが複雑であり、分割契約の内容を詳細に定める必要があります。さらに、分割後も一定期間、旧会社に責任が残る可能性があるため、慎重な設計が求められます。新設分割と吸収分割のどちらを選ぶかは、移転先の企業の有無や、事業の独立性の確保が重要な判断基準となります。
事業譲渡
事業譲渡は、旧会社が保有する事業の一部または全部を、新会社に売却する形で移転する方法です。この方法では、移転対象を自由に選定できるため、不採算事業や不要な資産を切り離しやすい特徴があります。ただし、債権者の同意が必要となるケースがあるため、慎重な交渉が求められます。
この手法の利点は、旧会社に残したい資産や負債を選別できる点です。例えば、不要な債務を旧会社に残し、収益性の高い資産や取引関係のみを新会社に移すことで、財務の健全化を図れます。さらに、税務上のメリットとして、資産の売却益を繰延処理することで税負担を分散できる可能性があります。
一方で、事業譲渡では契約ごとに個別の承諾が必要となるため、手続きの煩雑さが課題となります。特に、金融機関や主要取引先の契約変更手続きをスムーズに進めるためには、事前の調整が不可欠です。また、従業員の雇用契約も新会社との再締結が必要となるため、従業員の同意を得るプロセスも慎重に行う必要があります。
事業譲渡は自由度が高い一方、契約の整理に時間を要します。迅速な再建を目指す場合は、会社分割との比較検討が必要です。
第二会社方式のスポンサー型とスポンサーなし型の違い
第二会社方式には、スポンサー型とスポンサーなし型(自力再生型)の2つのパターンがあります。
【スポンサー型の特徴】
- 外部企業や投資家が新会社に資金を提供し、株主として参画
- 信用力や財務基盤が強化され、金融機関からの評価が高まる
- スポンサーの経営ノウハウや事業シナジーを活用できる
- 経営の主導権をスポンサーに譲る必要があるケースも見られる
【スポンサーなし型(自力再生型)の特徴】
- 現経営陣が主体となり新会社を設立して再建
- 意思決定の自由度が高く、これまでの経営方針を維持しやすい
- 資金調達力や信用力の面でスポンサー型より劣る場合がある
- 経営者自身が新会社の資金を拠出することも多い
金融機関からの支援を受けやすくするという観点ではスポンサー型が有利ですが、経営の自主性を重視する場合はスポンサーなし型が適しています。自社の状況と優先すべき目標に応じて判断すると良いでしょう。
第二会社方式のメリット
第二会社方式は、企業が債務超過に陥った場合でも、事業の存続を可能にする再生手法です。この手法を活用することで、倒産を回避しながら優良事業を残し、企業の再建を目指せます。ここでは、第二会社方式の主なメリットについて解説し、企業が活用する際のポイントを説明します。
雇用維持して事業を存続できる
第二会社方式のメリットの一つは、従業員の雇用を維持しながら事業を継続できる点です。企業が破産した場合、従業員は解雇され、取引先との契約も失われるため、事業の再建が困難になります。しかし、第二会社方式では、優良事業を新会社に引き継ぐことで、従業員の雇用を守りながら経営を続けられます。
この手法を適用することで、事業のノウハウや顧客との関係性を維持しながら、経営の立て直しを図ることが可能です。また、従業員のモチベーション低下を防ぎ、円滑な事業運営を継続できる点も大きな利点です。ただし、全従業員の雇用を保証できるわけではないため、労働条件の調整や社内の合意形成が必要になります。
不採算部門を整理して収益性の高い事業のみ残せる
第二会社方式では、不採算部門を切り離し、収益性の高い事業のみを残すことが可能です。経営難に陥った企業の多くは、複数の事業を抱えていますが、中には赤字を出し続ける部門も含まれています。これらの事業を新会社に移転せず、旧会社に残して清算することで、経営の効率化が図れます。
この方法を活用することで、不要なコストを削減し、成長が見込まれる事業に経営資源を集中させることができます。また、新会社が身軽な財務体質となるため、金融機関や投資家の評価を得やすくなり、資金調達の面でも有利になります。ただし、不採算部門の整理にあたっては、債権者や取引先との調整が必要となるため、適切な手続きを踏むことが求められます。
倒産を回避しながら経営を立て直せる
第二会社方式は、法的な倒産手続きを回避しながら企業の再建を進められる点が大きな利点です。破産や民事再生を選択すると、企業の信用が失われ、取引先や金融機関との関係が悪化するリスクがあります。しかし第二会社方式では、事業を存続させながら債務整理を行うため、取引の継続や信用力の維持が可能です。
この方法を適用すれば、金融機関や取引先に対して「再建の可能性がある企業」としての信頼を維持できるため、追加融資の可能性も残されます。また、事業継続により、既存の顧客基盤を活かした収益の確保が可能になります。ただし、債権者の合意形成が不可欠であり、事前の説明や調整が不十分な場合には、法的リスクが生じる可能性もあるため、慎重な対応が必要です。
第二会社方式のデメリット
第二会社方式は、事業を存続しながら債務整理を進められる有効な手法ですが、実行にはいくつかの注意点があります。ここでは、第二会社方式の主なデメリットについて解説し、リスクを最小限に抑えるためのポイントを説明します。
債権者や取引先からの理解を得るのが難しい
第二会社方式は、金融機関や取引先にとって「債務だけを切り離し、事業を新会社に移す手法」と映ることが多く、債権者の理解を得ることが難しい点が大きな課題です。債務を整理する目的で実行されるため、旧会社に残された債権者は債務の一部または全額を回収できない可能性があります。
このため、債権者の不信感を招き、交渉が難航するケースが少なくありません。特に、取引先の売掛債権や金融機関の貸付金が事実上回収不能となる場合、関係悪化につながる恐れがあります。事業の継続には、新会社と取引を継続してもらうための説明と交渉が重要です。旧会社に残る債権をどのように処理するのか、債権者に具体的な提案を示しながら進める必要があります。
また、債権者への説明不足や不誠実な対応は、トラブルの要因となりかねません。スムーズに実行するためには、事前に債権者との調整を行い、一定の合意を得ることが不可欠です。
法的なリスク(債権者からの否認権行使)がある
第二会社方式では、旧会社から新会社へ資産が移転するため、債権者から「不当な財産移転」とみなされるリスクが伴います。特に、旧会社の債務整理が進む中で、債権者が否認権を行使することで、新会社への事業譲渡や会社分割が無効となる可能性があります。
否認権とは、倒産手続きにおいて債権者が不利になるような財産処分を取り消せる権利です。例えば、資産を低価格で新会社に移転した場合や、特定の債権者だけを優遇する取引が行われた場合、裁判所がその取引を無効にすることがあります。事業譲渡や会社分割を行う際は、公正な評価額で取引を行い、適正な手続きを経ることが重要です。
このリスクを回避するためには、債権者との事前調整をしっかり行い、合意形成を図ることが求められます。また、専門家のアドバイスを受けながら、適切な価格で資産を移転し、不正とみなされないよう注意する必要があります。
税務処理の負担や金融機関の対応次第で困難になるおそれがある
第二会社方式では、税務処理の負担や金融機関の対応次第で実行が困難になる可能性があります。特に、債務免除益の課税が大きな問題となり、計画通りに再建が進まないこともあります。
債務免除益とは、金融機関や取引先が旧会社の債務を免除した際に発生する会計上の利益で、これに対して法人税が課される可能性があります。また、金融機関が新会社への融資に消極的な場合、事業継続に必要な資金が確保できないリスクもあります。
これらの課題については、税理士や弁護士などの専門家と事前に相談し、適切な対策を講じることが重要です。(詳細な税務処理のポイントについては後述します)
債務免除益や税務処理のポイント
第二会社方式では、債務免除益の発生や税務処理が重要な課題となります。適切な会計処理を行わなければ、想定外の税負担が発生し、再建計画が頓挫する可能性があります。ここでは、債務免除益の課税関係、繰越欠損金の活用方法、グループ法人税制や寄附金認定の影響について詳しく解説いたします。
債務免除益の課税関係と会計処理を正しく理解する
債務免除益とは、企業が金融機関や取引先から債務の一部を免除された際に発生する利益のことであり、法人税の課税対象となります。適切な処理を行わなければ、清算段階で多額の税負担が発生する恐れがあります。
この税負担を抑えるためには、事前に繰越欠損金の適用可否を確認し、課税所得を圧縮することが重要です。また、債務免除益の発生時期や適用税率についても注意が必要であり、税務上の影響をシミュレーションしておくことが求められます。適切な会計処理を行うことで、税負担を軽減し、円滑な再建を進めることが可能です。
繰越欠損金を活用して税負担を最小限に抑える
債務免除益に対する課税負担を軽減するためには、繰越欠損金の活用が有効な手段となります。繰越欠損金とは、過去の赤字を翌期以降の所得と相殺できる制度であり、債務免除益による課税所得の増加を抑える役割を果たします。
この制度を適用することで、税負担を大幅に軽減できますが、適用には一定の条件があります。例えば、税務上の適格要件を満たしているかどうかを事前に確認することが重要です。また、税法改正の影響で適用可能な期間が変更される可能性もあるため、専門家と相談しながら進める必要があります。繰越欠損金を適切に活用することで、財務負担を抑えながら、スムーズな事業再生を実現できます。
グループ法人税制や寄附金認定の影響を考慮する
第二会社方式を適用する際には、グループ法人税制の適用や寄附金認定の影響を慎重に考慮する必要があります。グループ法人税制を活用することで、親会社と子会社間での税負担を調整できるため、適切な税務戦略を立てることが可能です。
一方で、債務免除が寄附金とみなされる場合、課税関係が複雑になるリスクがあります。特に、親会社が子会社の債務を免除する場合、税務当局から寄附金認定を受け、損金算入が制限される可能性があります。このような税制の影響を適切に分析し、最適な再生計画を策定することが求められます。専門家と連携し、事前にシミュレーションを行うことで、税負担を抑えながら事業の再建を進めることができます。
金融機関や債権者との交渉の注意点
第二会社方式を成功させるためには、金融機関や債権者との適切な交渉が不可欠です。債権者の理解と協力を得られなければ、スムーズな事業移転が難しくなり、再建計画そのものが頓挫する可能性があります。ここでは、第二会社方式を実行する際の金融機関や債権者との交渉における重要なポイントを解説します。
第二会社設立の目的と事業計画を明確に説明する
金融機関や債権者に対し、第二会社方式を採用する理由や目的を明確に説明することが重要です。経営再建の成功には、関係者の理解と協力が不可欠であり、納得のいく事業計画を提示しなければ、支援を得ることは難しくなります。
事業計画を説明する際は、単に「事業を存続させたい」という意向を示すだけでなく、どの事業を新会社に移すのか、その事業の収益性はどうか、今後の成長戦略は何かといった具体的な内容を明確にすることが求められます。特に、旧会社と異なる経営方針を打ち出し、事業の再生可能性を証明することが、金融機関や債権者の信頼を得る鍵となります。
また、事業計画の実現可能性を高めるため、収益モデルの根拠や市場環境の分析、競争優位性について具体的なデータを提示することが望ましいです。事業計画の説得力が高まれば、金融機関からの新規融資の可能性が広がり、取引先との関係も円滑に進めることができます。
既存債務の整理方法や返済計画を具体的に提示する
金融機関や債権者に対して、旧会社に残る債務の整理方法や返済計画を明確に示すことが求められます。債権者は、第二会社方式の実行により自身の債権がどのように処理されるのかを最も重要視するため、納得のいく説明ができなければ、交渉が難航する可能性があります。
特に、債務の一部を新会社で引き継ぐのか、旧会社に残す債務の返済計画はどうするのか、金融機関の追加融資は可能かといった点を明確にし、金融機関や取引先に対し、再建計画が現実的であることを証明することが必要です。
また、既存債務の整理方法には、リスケジュール(返済条件の見直し)、債務免除、債務カットといった選択肢があり、それぞれ金融機関との交渉次第で柔軟に決定できます。適切なスキームを選択し、債権者にとっても納得できる内容にすることで、円滑な債務整理が可能になります。
このように、債権者との信頼関係を築くためには、事業の収益性と資金計画を示しながら、現実的な債務整理の方法を提案することが不可欠です。
新会社の信用力を高めるための対策を講じる
金融機関や取引先と良好な関係を築くためには、新会社の信用力を高めることが不可欠です。企業が第二会社方式を適用する際、旧会社の経営破綻が影響を及ぼし、新会社の信用が低下する可能性があります。そのため、新会社の安定性を示す具体的な対策が求められます。
信用力を高める方法として、スポンサー企業の確保、財務基盤の強化、経営陣の刷新が挙げられます。スポンサー企業が関与することで、新会社の経営基盤が安定し、金融機関や取引先の信頼を得やすくなります。また、資本金の増強や適切な資本政策を実施することで、企業の財務体質を健全に保つことが可能です。
さらに、経営陣の変更やガバナンスの強化を行うことで、旧会社とは異なる経営方針を打ち出し、取引先の不安を払拭できます。特に、経営者の交代や外部の専門家の招聘は、企業の信頼回復につながる有効な手段となります。
このように、新会社の信用力を高めるためには、資本政策や経営体制の見直しを含めた具体的な施策を講じることが重要です。適切な対策を実施することで、金融機関や取引先の信頼を確保し、事業の安定した再建を実現できます。
まとめ|第二会社方式の適用を検討する際は、専門家への相談を
第二会社方式は、企業の財務負担を軽減しながら事業を存続させる有効な手法です。適用にあたっては、適切なスキームの選択、金融機関や債権者との交渉、税務処理の検討が不可欠となります。
特に、債権者の理解を得ること、適切な税務対策を講じること、新会社の信用力を高めることが成功の鍵となります。これらの要素を踏まえ、慎重に計画を進めることで、企業は健全な財務体質のもとで事業再建を実現できます。
第二会社方式の適用を検討する際には、専門家のアドバイスを受けながら、最適な手続きを選択することが重要です。適切な準備と戦略的な対応を行うことで、事業の持続可能性を高め、企業の新たな成長を目指せます。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。