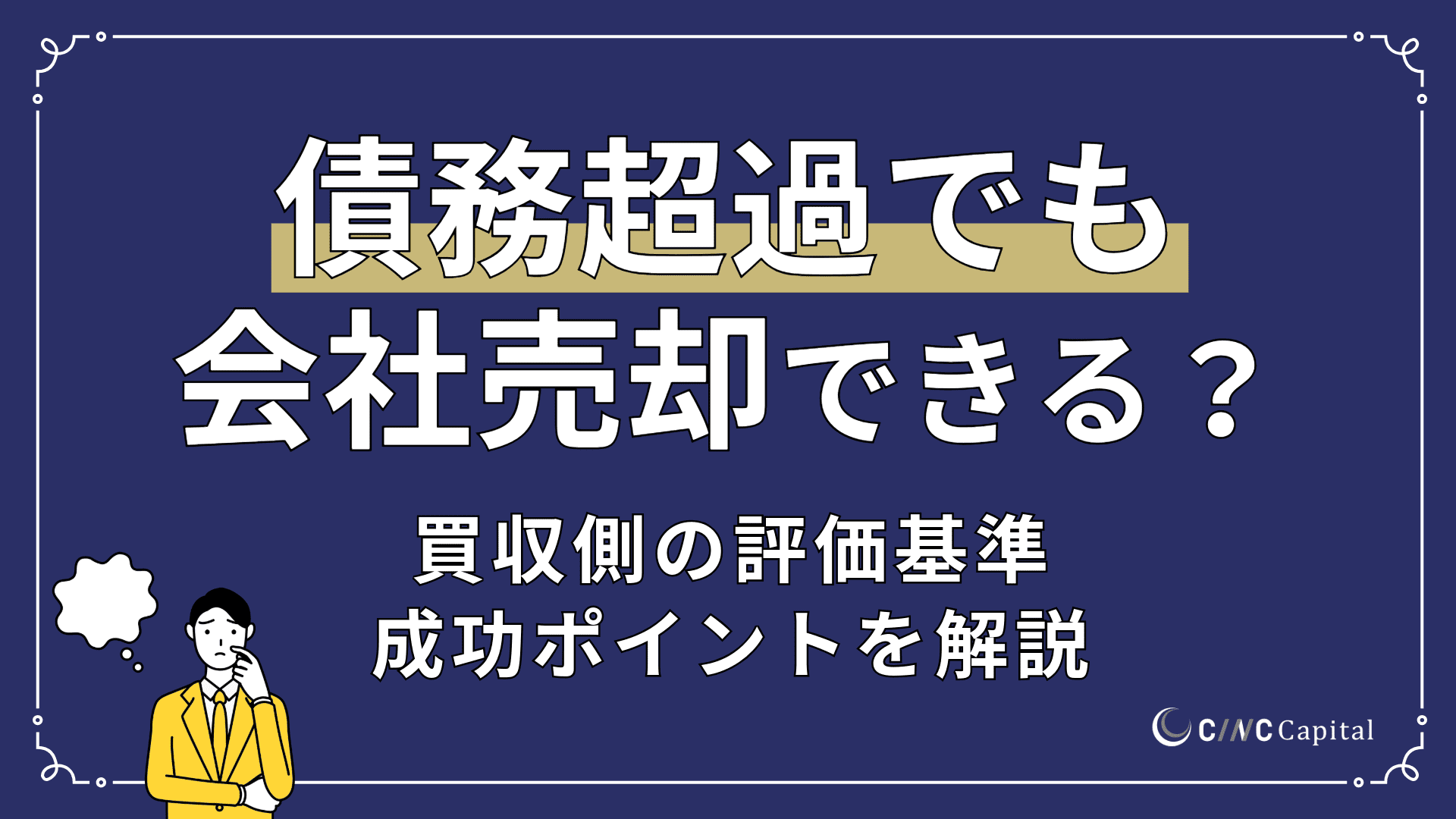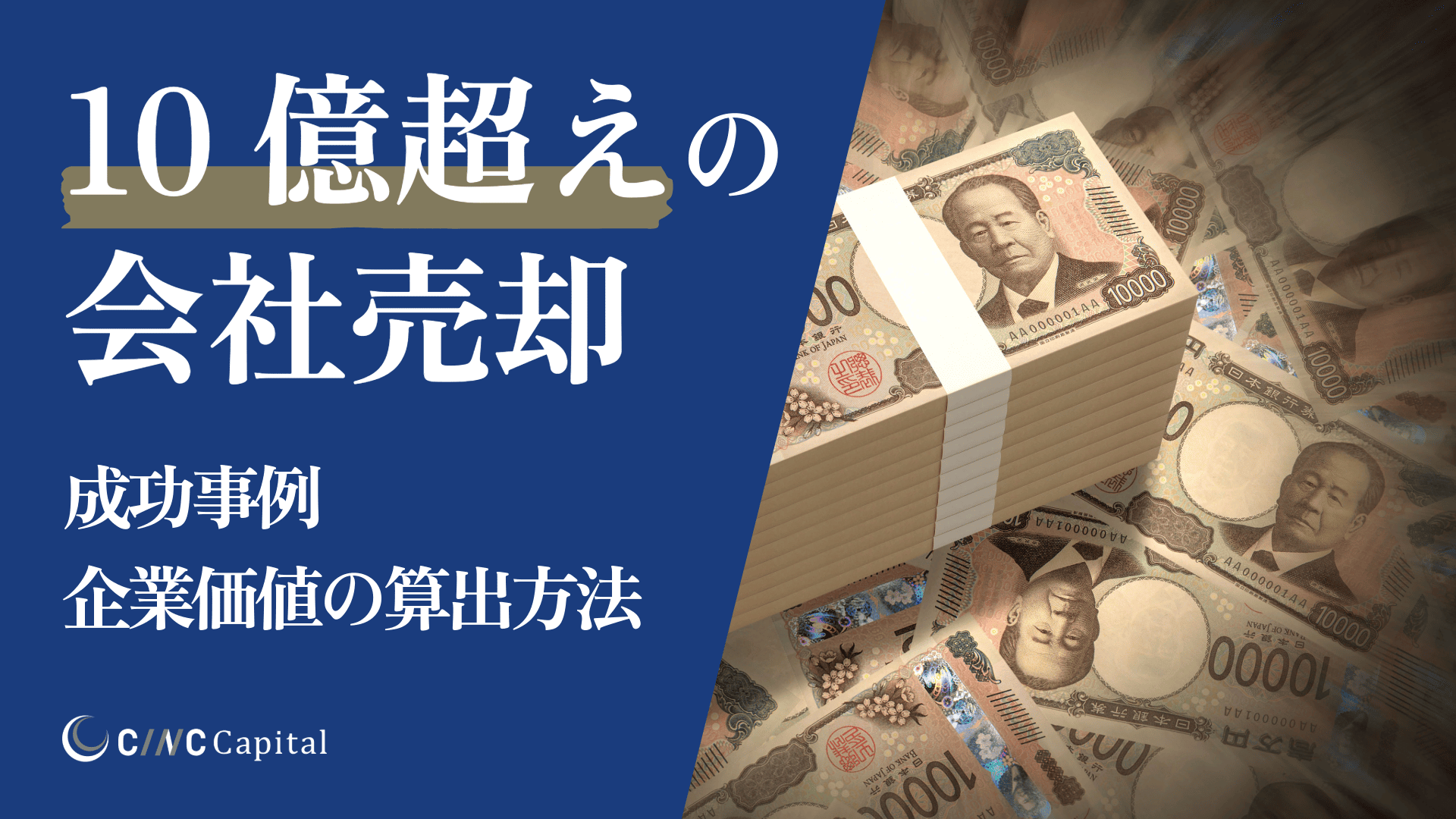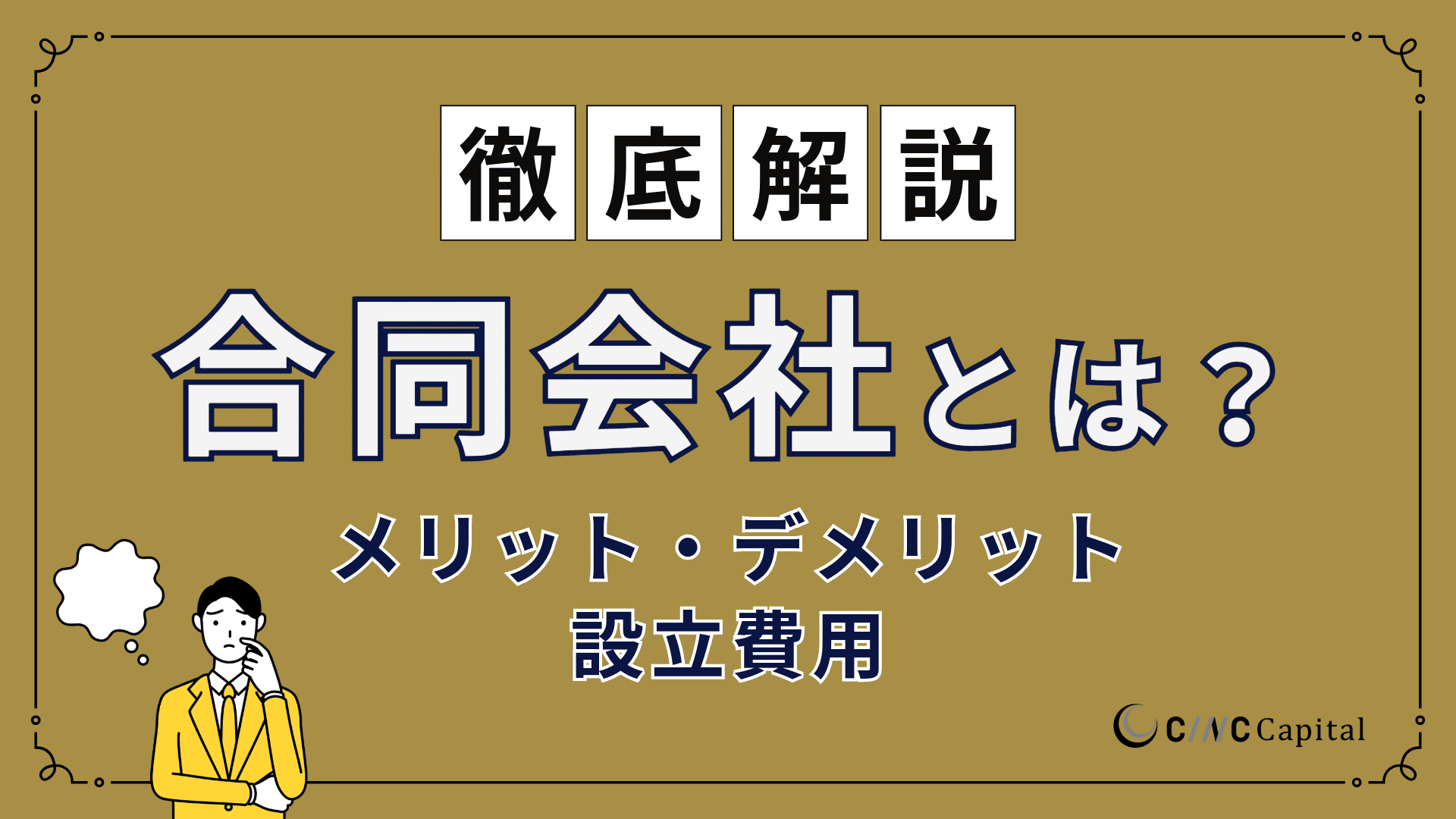CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
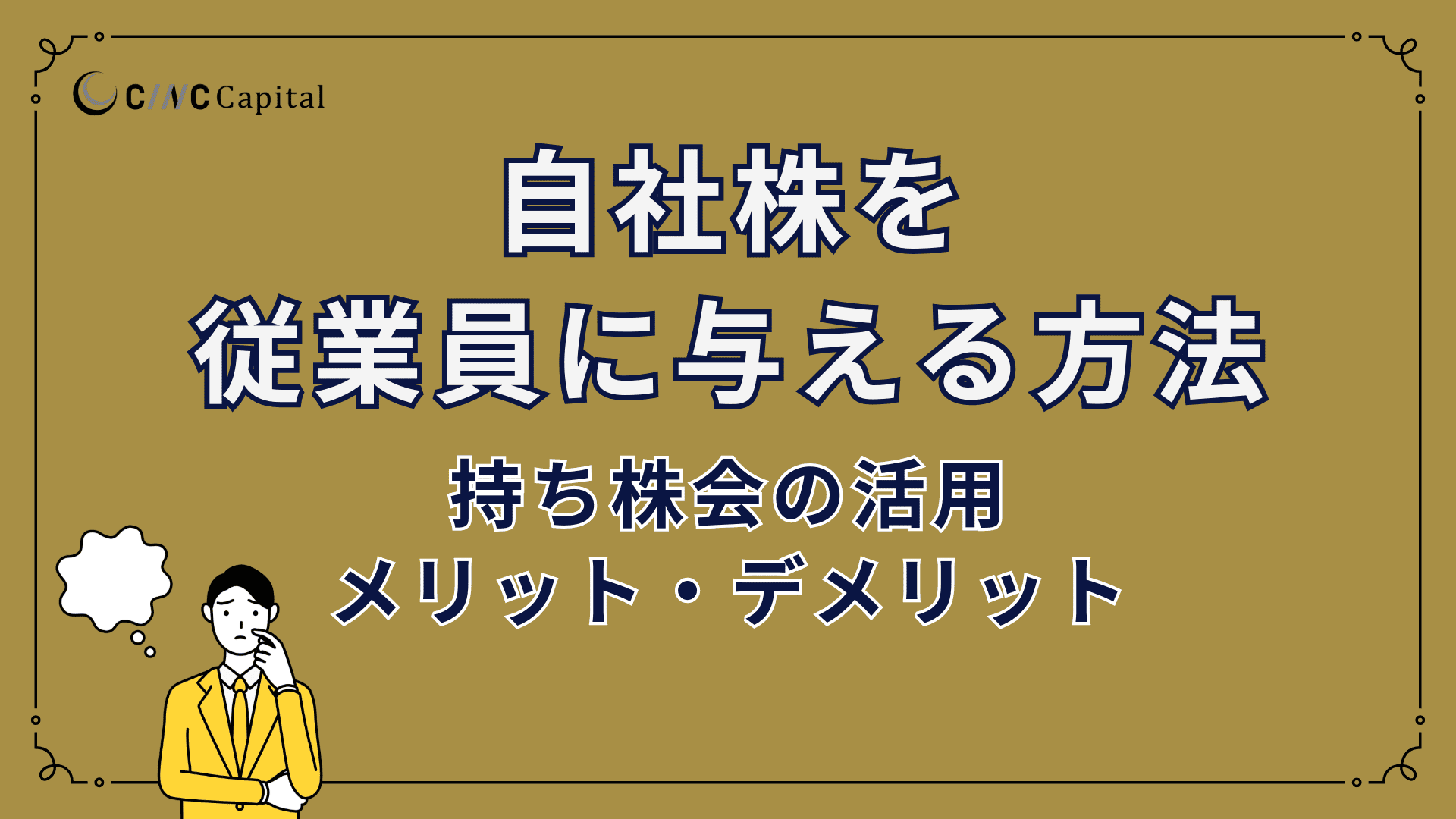
売却 / 会社売却
- 最終更新日2025.09.17
会社が自社株を従業員に売却する方法と注意点!従業員持株会を活用するメリットとデメリットも解説
多くの企業が自社株を従業員に売却することで得られるメリットに魅力を感じており、従業員持株会への関心は年々増えています。
しかし、自社株の売却や従業員持株会を魅力に感じていても、その詳細についてご存知でない方は多いです。
本記事では、自社株を従業員に売却する方法と注意点を解説します。さらに従業員持株会を活用するメリットとデメリットも併せてお伝えします。
目次
自社株を従業員に売却する方法
自社株を従業員に売却する方法にはいくつかの選択肢があります。どの方法を選ぶかは目的や状況に応じて異なるため、自社に合った方法を選択することが大切です。
- 従業員持株会への譲渡
- 個別の従業員への売却
- ストックオプションの付与
ここでは代表的な3つの売却方法について解説します。
従業員持株会への譲渡
従業員持株会は、会社と従業員の間に立ち、株式の取引を仲介する組織です。
会社は持株会に株式を譲渡し、従業員は毎月の給与から一定額を天引きする形で積み立てを行い、定期的に株式を購入します。安定した株主を確保でき、株式の分散の防止や経営者の会社支配権の維持の効果があります。
また、従業員の経営参画意識も高まります。持株会を通じた譲渡は、株式の分配と管理が一元化されるため、事務手続きの効率化にもつながります。
個別の従業員への売却
会社が特定の従業員に対して直接自社株を売却する方法もあります。主に役員や幹部社員など、会社への貢献度が高い人材や、長期的に会社の成長を支える重要なポジションにある従業員を対象とすることが多いです。
売買価格や条件は当事者間の合意によって決定され、場合によっては市場価格よりも優遇された条件で提供されることもあります。この方法は手続きがシンプルである反面、売却対象者の選定基準や価格設定の公平性に配慮する必要があります。
また、税務上の取り扱いにも注意が必要で、適正な価格での取引であることを説明できる資料を準備しておくことが大切です。
▶ 自社株を個別の従業員に売却する場合は、信頼関係や条件面の調整も含めて、非常に繊細な対応が求められます。さらに、株価の評価や制度の設計、売却後の経営権のあり方など、検討すべきことは多岐にわたります。
こうした実務の全体像を整理しておきたい方のために、M&Aアドバイザーが監修した「資料・動画の厳選3点セット」をご用意しました。
M&Aや事業承継を体系的に理解するための入門資料として、経営者の方々にご好評いただいています。
ストックオプションの付与
ストックオプションとは?
会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。
株価が権利行使価格を上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることができる。
【引用】厚生労働省「調査の結果」
権利付与時点では株式の購入は行われず、一定期間後に従業員が権利を行使することで初めて株式の取得が可能になります。即時の資金流出がなく、将来的に安定した株主を獲得できるメリットがあります。
業績が向上し株価が上昇した場合、権利行使価格と市場価格の差額が従業員の利益となるため、会社の成長に対するインセンティブとして機能します。長期的な視点での経営参画意識を高め、優秀な人材の定着にも効果的です。
会社の持ち株を従業員持株会に売却するメリット
従業員持株会を活用することは、会社と従業員の両方にさまざまなメリットをもたらします。ここでは会社の持ち株を従業員持株会に売却するメリットについて解説します。
事業承継がしやすくなる
後継者問題を抱える中小企業にとって、従業員持株会は事業承継の選択肢の一つとなります。創業者が保有する株式を従業員持株会に段階的に売却することで、一部の所有権移転が実現します。
特に、親族内に適切な後継者がいない場合や、外部へのM&Aではなく企業文化や経営理念を維持したい場合の選択肢となります。ただし、実務上は持株会への売却だけでなく、経営幹部への集中的な株式譲渡などと組み合わせて活用されることが多いです。
また、創業者にとっては株式売却で、現金による資金化が可能となり、相続税対策としても機能します。計画的な株式移転によって、経営の安定性を保ちながら世代交代を進められる点も大きな利点です。
従業員のモチベーション向上につながる
従業員が自社株を保有することで「自分たちの会社」という当事者意識が生まれ、業績向上への意欲が高まります。株主として配当を受け取ることで、会社の業績が自分の利益に直結するという実感が生まれ、長期的な視点での貢献意識が形成されます。
また、経営情報の共有機会が増えることで、経営課題への理解が深まり、全社一丸となった取り組みが可能になります。人材確保が困難な時代において、従業員が株主として経営に参画できる環境は、優秀な人材の採用・定着にも寄与します。
安定株主を確保できる
従業員は「会社の事業や将来性を理解している投資家」という立ち位置となり、短期的な株価変動に左右されにくい安定した株主となります。
敵対的買収※のリスクを低減し、長期的な経営戦略に基づいた意思決定が可能です。特に上場企業では、市場の短期的な評価に振り回されず、本来の企業価値向上に集中できる環境が整います。
※敵対的買収…敵対的買収とは、買収対象企業の経営陣や取締役会の同意を得ずに、株式市場で直接株式を購入することで企業の支配権を獲得しようとする行為です。買収側は株主に直接買付提案を行い、現経営陣の意向に反して買収を進めるため、企業防衛策が大切になります。
会社の持ち株を従業員持株会に売却するデメリット
会社の持ち株を従業員持株会に売却することには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、持ち株を従業員持株会に売却する際のデメリットについて解説していきます。
経営権が分散する
従業員持株会への株式売却を進めると、経営者や創業家の持株比率が低下し、経営の意思決定における影響力が弱まる可能性があります。
特に、経営方針の転換や大型投資など重要な決断を迅速に行う必要がある場合、株主の合意形成に時間がかかり、柔軟な経営が難しくなることがあります。
また、将来的に持株会の株式保有比率が高まると、経営陣の交代や取締役の選任に関しても従業員の意向を無視できなくなり、経営の自由度が制限される可能性があります。適切な持株比率のバランスを検討する必要があります。
株主間のトラブルの原因になる
従業員が株主となることで、配当政策や役員報酬、事業投資などの意思決定において利害対立が生じる可能性があります。
特に業績悪化時には、従業員株主は配当を期待する一方、経営陣は内部留保を優先したい状況が発生し、対立の火種となることがあります。これらのリスクを軽減するためのルール作りが大切です。
従業員の退職時の取り扱いを決める必要がある
従業員が退職する際の株式の取り扱いが大きな課題となります。一般的には退職時に持株会から株式を買い戻す仕組みが必要ですが、そのための資金確保が必要です。
特に多数の従業員が同時期に退職する場合や、業績悪化時には買取資金の確保が困難になる可能性があります。また、株価の算定方法によっては、退職者と会社間で評価に関する紛争が生じるリスクもあります。
さらに、上場企業でない場合、株式の流動性が低いため、公正な価格での買取制度の確立が不可欠です。これらのルールを事前に明確化し、持株会の規約に盛り込むことが重要です。
自社株を従業員持株会に売却する際の注意点
自社株を従業員持株会に売却することはメリットも多く、魅力的な戦略となり得ます。自社株の売却を成功させるためにも、いくつかポイントを押さえることが大切です。ここでは自社株を従業員持株会に売却する際の注意点について解説します。
適正な株価評価を行うようにする
従業員持株会への株式売却では、適正な株価評価が大切です。過大評価は従業員の負担増加や購入意欲の低下を招き、過小評価は税務上の問題を引き起こす可能性があります。
非上場企業の場合、税務上は原則として国税庁の財産評価基本通達に基づく評価(純資産価額方式、類似業種比準方式、またはその折衷方式)が求められますが、実務上はこれに加えて、DCF法(将来キャッシュフロー割引法)やEBITDAマルチプル法などの企業価値評価手法も参考にしながら、従業員にとって魅力的かつ税務上も説明可能な価格設定を行うことが重要です。
また、定期的な株価の見直しルールを設け、業績変動に応じて適正価格を維持する仕組みを整えることで、従業員持株会の持続的な運営が可能になります。
なお、株価算定の別記事で詳細に解説しています。こちらも併せてご覧ください。
【関連記事】株価算定とは?算出方法や費用、必要書類、流れについて徹底解説
運営規程や加入資格など制度設計を整備するようにする
従業員持株会の制度設計は将来的なトラブル防止につながります。
- 持株数の上限設定
- 拠出金額の範囲
- 配当金の取扱い
- 議決権行使の方法
など、明確なルールを定めましょう。
特に退職時の株式買取ルールについて重要です。買取価格の算定方法や買取資金の確保方法を具体的に規定します。
また、従業員持株会の運営体制(理事長・理事の選任方法や任期など)や会計処理、情報開示の方法についても詳細に定めておくことで、透明性の高い運営が可能になります。
売却後の経営への影響を想定しておくようにする
従業員持株会への株式売却は、会社の所有構造を変え、経営に影響を与える可能性があります。
実務上は、従業員持株会への売却比率を全体の10~20%程度に抑える企業が多く、この程度であれば経営権への直接的な影響は限定的です。ただし、長期的に売却を続けると持株比率が高まり、重要な経営判断における株主総会決議などで一定の影響力を持つ可能性があります。
特に、特別決議を要する事項(合併、事業譲渡、定款変更など)では3分の1以上の株式を保有する株主が拒否権を持つため、売却比率の上限設定を事前に検討しておくことが重要です。
また、従業員が株主となることで、配当政策や役員報酬への関心が高まり、従来の経営判断に影響を与えることも考えられます。さらに、情報開示の範囲拡大や、従業員からの質問・要望への対応など、コミュニケーションコストの増加も想定されます。これらの変化に対応するため、段階的な株式売却計画を立て、各段階での経営への影響を予測しておくことが大切です。
自社株を従業員持株会に売却するための基礎知識
ここでは、自社株売却に関する基本的な知識と手続きをご紹介します。自社株を売却する際に知っておくべきことは、「売却できるタイミング」「売却手続きの流れ」です。各ポイントについて詳しく解説します。
売却できるタイミング
自社株の従業員持株会への売却タイミングは、企業の状況や目的によって異なります。業績が安定または成長している時期が望ましく、急激な業績悪化が見込まれる時期は避けるべきです。また、創業者が引退を考える前から段階的に売却を始めるのが事業承継の観点からは効果的です。組織変更や増資など会社の重要な節目に合わせて実施することも一つの選択肢です。
売却手続きの流れ
従業員持株会への自社株売却は、まず従業員持株会の設立から始まります。この従業員持株会の設立を含め、以下の流れで手続きをしていきます。
従業員持株会の設立
従業員持株会の設立では、以下の手続きを行います。
- 規約作成
- 証券会社の選定
- 法人登記手続き(任意団体の場合は不要)
売却準備
会社の持ち株の売却を行います。
- 売却株式数と価格の決定
- 取締役会での承認取得
従業員への案内
従業員持株会の設立および持株会加入者の募集の内容を周知し、売買の準備を行います。
- 説明会の開催
- 加入者の募集
- 運営体制の整備
株式売買手続き
株式の売買に必要な手続きを行います。
- 売買契約の締結
- 株式の名義書換
- 売買代金の決済
従業員持株会の運営開始
従業員持株会の運営に伴い、定期的に以下の対応を行います。
- 取得株式の加入者持分への割当
- 月次での積立金徴収と株式購入
- 年次総会による運営状況報告
従業員持株会からの売却と個別保有の場合の違い
従業員持株会からの売却と個別保有の場合では、手続きや税金面で大きな違いがあります。持株会を通じた売却では、持株会の規約に従って売却の申し出を行い、運営委託会社を通じて手続きが進められます。
一方、個別保有株式の売却は証券会社の口座を通じて自ら売買することになります。税金面では、持株会からの売却は源泉徴収されることが多いのに対し、個別保有の場合は確定申告が必要です。
また、持株会では売却のタイミングが限定されることが多く、個別保有と比べて流動性が低いという特徴があります。さらに、個別保有の場合は売買手数料が発生することもあるため、コスト面での違いも考慮が必要です。
従業員持株会からの売却はインサイダー取引になる?
従業員持株会からの株式売却もインサイダー取引規制※の対象となります。自社の重要事実(業績予想の大幅修正や大型M&Aなど)を知った役職員は、その情報が公表されるまで自社株の売買はできません。
ただし、持株会における定期的な積立購入や、あらかじめ決められたルールに基づく売却(例:毎月一定日に一定数を売却)は「計画的売買」として例外的に認められることがあります。
日本取引所グループは以下のように回答しております。
Q6. 役員(従業員)持株会
私は上場会社の役員(従業員)で、未公表の重要事実を知っています。役員(従業員)持株会で自社の株式を毎月買い付ける場合や、持株会から株式を引き出して売却する場合はインサイダー取引になりますか。
A6. 一定の計画に従い毎月行う定時定額の買付け(各役員・従業員の1回あたりの拠出額が100万円未満)はインサイダー取引規制の適用除外です。したがって、このような自社の株式の買付けであれば、未公表の重要事実を知っていても可能であり、インサイダー取引規制違反に問われることはありません。ただし、未公表の重要事実を知りながら行う持株会拠出額の増加や新規加入はインサイダー取引規制の対象となります。一方で、持株会から引き出した株式の売付けは、インサイダー取引規制の適用除外とはされていません。
重要なのは、売却前に自社の未公表の重要事実を知っているかどうかであり、知っている場合は売却を控えるべきです。
※インサイダー取引…企業の未公開重要情報を知った関係者が、その情報を利用して株取引を行う違法行為です。
退職時の自社株の取り扱い
退職時の自社株の取り扱いは、会社の規約によって異なります。多くの場合、退職者は従業員持株会を脱退し、保有する株式については以下の選択肢に分類できます。
- 現物株として引き出す
- 売却して現金化する
- 一部は現物株として残し一部は売却する
現物株として引き出す場合は、自分の証券口座に移管することになります。売却する場合は、売却益に対して譲渡所得税が課税されますが、従業員持株会で購入した時期や価格によっては損失が発生することもあります。
また、退職時に必ず全株を売却しなければならない規約の会社もありますので、事前に人事部や従業員持株会の担当者に確認することが必要です。
まとめ|従業員持株会で自社株を売却してもらうことはメリットが豊富
多くの企業から注目を集めている従業員持株会について解説いたしました。自社株を従業員に売却するメリットは多いです。
- 事業承継が可能になる
- 従業員のモチベーション向上につながる
- 安定株主を確保できる
以下のメリットが魅力的に感じる方はぜひ手続きを始めることをおすすめします。