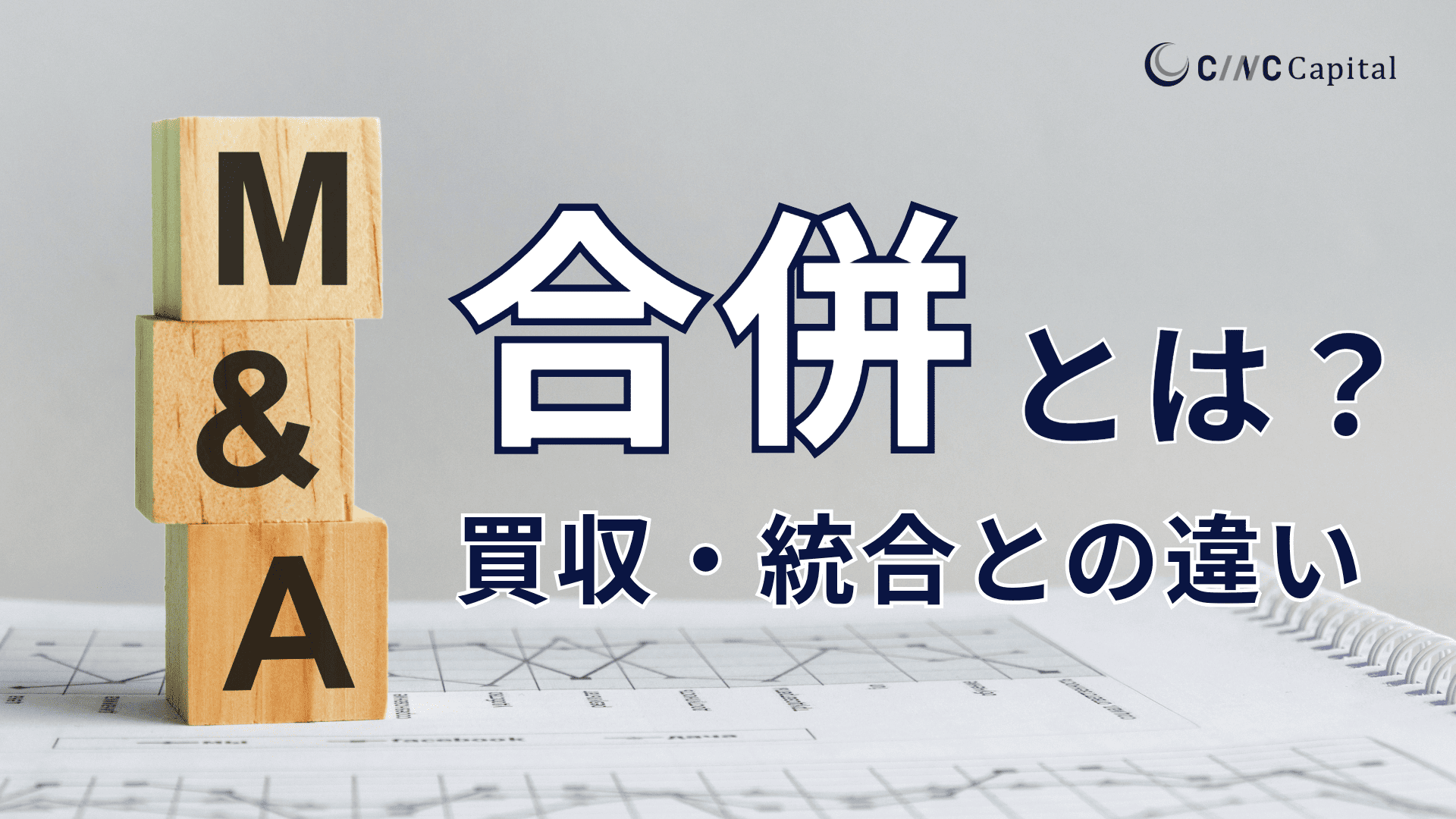CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
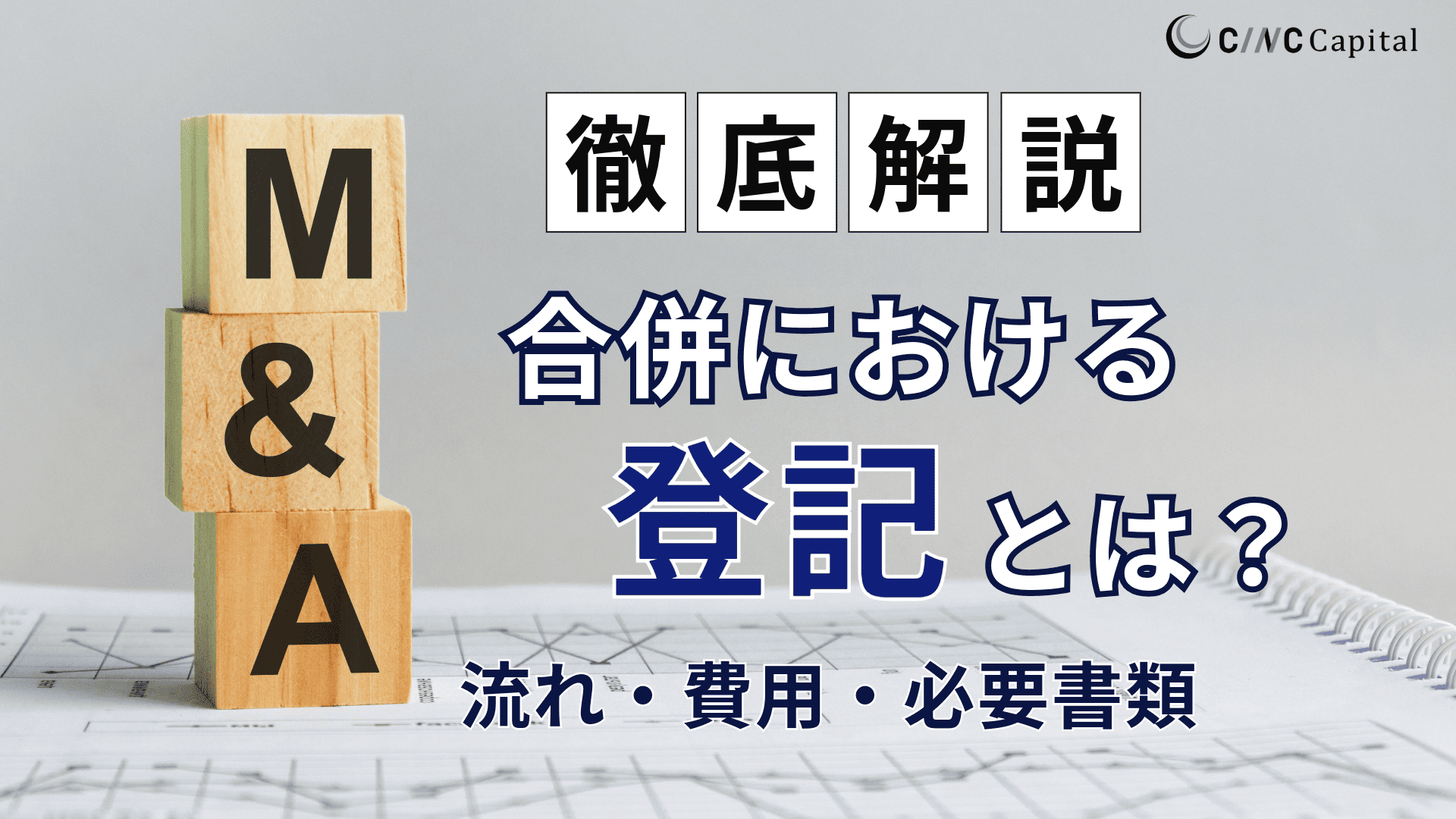
M&A / スキーム
- 公開日2025.09.29
合併における登記とは?手続きの流れや必要書類、費用を解説
合併登記の手続きについて悩んでいませんか?
「何から着手すればいいのか分からない」「必要書類や流れが把握できず不安」と考えている方も少なくありません。
本記事では、合併の基本的な種類から、登記の流れ、必要な書類、かかる費用までを詳しく解説します。
目次
合併とは?
会社の合併とは、複数の法人を統合し、1つの会社として再編する手続きを指します。
合併を実施することで、経営資源の統合や業務効率の向上、企業価値の増大が可能です。
例えば、技術力のある企業と販売力のある企業が合併すれば、相互補完によるシナジー効果が期待されます。
このように、合併は企業の成長戦略の一環として重要な役割を果たします。
合併の種類
会社の合併には大きく2つの種類があります。
どちらの形式を選ぶかによって、登記手続きや関係者の対応が変わるため、それぞれの特徴を正しく理解しておきましょう。
以下で、「吸収合併」と「新設合併」の特徴と違いを解説します。
吸収合併
吸収合併とは、一方の会社が存続し、他方が消滅する形で行われる合併です。
存続会社は消滅会社のすべての権利義務を「包括承継(こうほうしょうけい)」と呼ばれる方法で引き継ぎます。
これは契約や申請を個別に行うことなく、法律の効果によって自動的に引き継がれる仕組みです。
例えば、規模の大きな企業が小規模な企業を吸収するケースが典型例です。
スムーズに経営統合ができるため、手続きや実務の負担が比較的少ない点がメリットです。
新設合併
新設合併とは、複数の会社がともに消滅し、新たに別の会社を設立して統合する方法です。
新設会社がすべての権利義務を引き継ぐため、当該会社にとって対等な統合と見なされやすく、従業員や取引先への心理的負担が小さくなる傾向があります。
例えば、同等規模の企業同士が新たなブランドとして再出発する際に適しています。
一方で、設立登記が必要になるなど、手続きの負担が大きくなる点は注意が必要です。
合併における登記手続きとは?
会社の合併を実施する際には、法的な効力を持たせるために登記手続きが必要です。
なぜなら、登記は会社の状態や法的変動を公的に証明し、第三者にも通知する役割を果たすからです。
例えば、吸収合併であれば存続会社が変更登記を行い、消滅会社が解散登記を行います。新設合併では、新たに設立する会社の設立登記と、各当事会社の解散登記が求められます。
これらの登記は、合併の効力が発生した日から2週間以内に完了しなければなりません。
期限を過ぎると、法的効力が認められないリスクが生じるため注意が必要です。
このように、合併登記は法務的にも実務的にも極めて重要な工程であり、正確かつ迅速に進めることが不可欠です。
合併における登記の流れ・スケジュール
合併を行う際には、契約から登記まで多くの手続きを順を追って進める必要があります。
それぞれの工程で法定の期限や必要書類が異なるため、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。
本章では、合併成立までに必要な7つのステップを紹介します。
合併契約の締結
合併を行うためには、まず当該会社間で合併契約を締結します。
なぜなら、合併契約は存続会社や消滅会社、対価、効力発生日などを明確にする基本文書だからです。
例えば、吸収合併であれば、存続会社がどのような形で事業を引き継ぐかを定める必要があります。
この契約をもとに株主総会や登記などの手続きを進めていくため、慎重に作成し、取締役会で承認を得なければなりません。
株主総会の承認決議
合併契約を締結した後は、各社においてその契約内容を株主総会で承認する必要があります。
これは、合併が会社の組織や財産、経営権に大きな影響を与える重大な事項であり、株主の意思を正式に確認する手続きが法的に義務付けられているためです。
株主総会では「特別決議」と呼ばれる手続きが必要です。
これは出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得るもので、通常の決議よりも厳格な条件が設けられています。
一定の条件を満たす場合には「簡易合併」として、株主総会の承認を省略することができます。
例えば、存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合などが該当します。
この制度により、形式的な手続きを省略し、スムーズな合併を実現できる仕組みも用意されています。
債権者の保護手続き
合併によって会社が他社の債務を承継する場合、債権者にとって不利益が生じる可能性があります。
例えば、債務の返済能力に不安を感じる場合や、契約上の条件が変わることで影響を受ける場合などが該当します。
こうしたリスクに対応するため、会社法では、効力発生日の1か月以上前に官報公告や個別通知を通じて、債権者に異議申し立ての機会を与えることが義務付けられています。
万が一、異議が出された場合には、その債権者に対して弁済や担保の提供、もしくは合併によって債権が害されないことの証明が必要です。
なお、実務上では債権者から異議が出されるケースもあります。
その場合、会社は債務の弁済や担保の提供を行うか、もしくは裁判所を通じて「債権者を害するおそれがない」とする旨の証明を提出する必要があります。
対応が遅れると登記申請の時期に影響するため、異議申立てが想定される債権者には事前説明や丁寧な対応を行うことが重要です。
株主の保護手続き
自己の保有株式を会社に買い取ってもらう「株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)」が認められています。
これは、合併に反対する株主が、自身の株式を会社に売却し、資本から離脱する権利です。
会社は合併の内容を事前に通知または公告し、そのうえで反対する株主から所定の期間内に請求があった場合には、適正な価格で株式を買い取らなければなりません。
買い取りに応じることで、少数株主にとって不利益の少ない形での退出が可能となります。
この制度は、合併手続きにおける公正性と透明性を高めるとともに、株主間の信頼維持にも寄与する重要な仕組みです。
合併に関する情報の事前開示・事後開示
合併を適切に進めるには、利害関係者への情報開示が不可欠です。
会社法では、合併契約の締結後から効力発生日までの間、合併契約書や関連書類を本店に備え置き、閲覧できるようにすることが義務付けられています。
さらに、合併成立後には「事後開示書類」を作成し、効力発生日から6か月間は引き続き保管・開示する必要があります。
これにより、株主や取引先が合併の内容を正確に把握できる体制が確保されます。
株券、新株予約権証券の提出
合併に際しては、株券や新株予約権証券の提出・回収が必要となります。
これは、合併後の株主構成や権利関係を正確に把握し、不正な権利行使を防ぐために、旧証券の整理が法的に義務付けられているためです。
例えば、株券を発行している会社は、効力発生日の1か月以上前に公告を行い、あわせて各株主に個別通知を送り、株券の提出を求めなければなりません。
これにより、合併後の新しい体制下で株主の権利を適切に管理できます。
なお、紙の株券を発行していない場合であっても、発行していないことを証明する書面を登記申請時に提出する必要があります。
新株予約権証券についても同様に、発行している場合は公告と通知による提出手続きを実施し、発行していない場合はその旨を証する書面の提出が求められます。
登記申請
すべての手続きを完了したら、合併の効力発生日から2週間以内に登記を行う必要があります。
例えば、吸収合併の場合は存続会社が変更登記を行い、消滅会社は解散登記を行います。
新設合併であれば、新会社の設立登記と旧会社の解散登記を同日に申請しなければなりません。
この期限を過ぎると、法務局から登記不備として差し戻される可能性があるため、日程管理を徹底しましょう。
合併の登記に必要な書類
合併登記では、契約書や議事録などの提出が求められます。
どの書類が必要になるかは、吸収合併か新設合併か、また申請者が存続会社か消滅会社かによって異なります。
本章では、それぞれのパターンに分けて必要書類を紹介します。
【吸収合併】登記の必要書類
吸収合併の場合は、存続会社と消滅会社がそれぞれ異なる書類を準備する必要があります。
以下で、提出すべき書類を詳しく説明します。
【存続会社】登記申請の必要書類
吸収合併で存続する会社は、合併に伴う変更登記を行うために、各種の証明書類を整える必要があります。
なぜなら、法務局は合併の有効性や公告実施の事実を客観的に判断するために、複数の添付書類を求めているからです。
合併契約書、株主総会または取締役会の議事録、債権者保護手続きの公告証明書、資本金の計上証明書などが必要です。
さらに、消滅会社が株券や新株予約権証券を発行していた場合には、それらの提出公告や証明書も欠かせません。
【消滅会社】登記申請の必要書類
消滅会社は、合併により法人格を失うため、解散の登記申請を行います。
そのために必要な書類は、株主総会議事録、債権者保護公告関係書類、登記事項証明書などです。
例えば、株主総会で合併契約を承認したことを示す議事録は、合併の法的成立を裏付ける証拠として求められます。
さらに、登記手続きを代理人に任せる場合は委任状の提出も必要です。
【新設合併】登記の必要書類
新設合併では、新会社の設立登記と同時に、当該会社の解散登記が必要になります。
以下で、新会社(存続会社)の設立に必要な書類と、合併により消滅する会社の書類をそれぞれ説明します。
【存続会社】登記申請の必要書類(新設会社)
新設合併で設立される会社では、通常の設立登記に加えて合併関連書類も提出します。
なぜなら、合併によって設立される法人には、通常の会社設立とは異なる責任と承継義務が発生するためです。
例えば、定款、発起人決定書、設立時取締役の就任承諾書、合併契約書の写しなどが必要になります。
加えて、資本金の払込証明書や登録免許税の軽減を証明する書類も必要なケースがあります。
【消滅会社】登記申請の必要書類(解散する既存会社)
新設合併で消滅する会社は、合併の効力発生日に合わせて解散登記を行います。
必要書類は、合併契約承認の株主総会議事録、債権者保護手続きの書類、登記事項証明書などです。
例えば、公告を行った証明書や通知実施の報告書は、債権者保護の実施を裏付ける書類として添付します。
また、代理人が登記を行う場合には、委任状の提出が求められます。
登記にかかる費用は?
合併を行う際には、登記手続きに伴い一定の費用が発生します。
特に注意すべきなのが、法務局へ納める登録免許税です。
本章では、合併時に必要となる費用のうち、登録免許税について詳しく解説します。
合併の際の登録免許税とは
合併登記には「登録免許税」がかかります。
なぜなら、登記は法的効力を得るために行う手続きであり、国に対して一定の税金を納める義務があるからです。
具体的には、吸収合併で存続会社となる法人が支払う登録免許税は、合併によって増加する資本金の金額に対して「1.5/1000」の税率が適用されます。
ただし、計算結果が3万円未満であっても、最低納付額は3万円と定められています。
一方、消滅会社には資本金の増減に関係なく一律3万円の登録免許税が課されます。
また、不動産を保有している会社が合併する場合は、別途「所有権移転登記」のための登録免許税が発生するため、合併計画の初期段階で費用感を把握しておくことが重要です。
なお、合併には登録免許税以外にもさまざまな費用が発生します。
例えば、登記手続きを専門家(司法書士など)に依頼する場合は数万円から数十万円の報酬がかかることがあります。
また、債権者保護手続きや株券公告のためには官報への公告掲載料が発生し、1件あたり約3万〜6万円程度が一般的です。
さらに、必要に応じて公証人費用や弁護士・税理士への相談料なども加算される場合があります。
事前に全体の費用感を把握しておくことが大切です。
まとめ|会社状況を理解しM&Aを実施しよう
会社の合併は、経営戦略や事業承継を円滑に進める有効な手段です。
ただし、契約や株主対応、公告、登記など多くの法的手続きを伴うため、事前準備と正確な進行が不可欠です。
本記事で紹介した登記の流れや必要書類、費用を参考にしながら、自社に最適な合併方法を検討してください。
司法書士や専門家に相談し、安心かつ確実なM&Aを目指しましょう。
CINC CapitalはM&A仲介協会会員・中小企業庁の登録支援機関です。
業界歴10年以上の専門家が、譲渡や買収の目的に応じて適切な手法をご提案します。
秘密厳守でスムーズな取引を支援します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。