CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
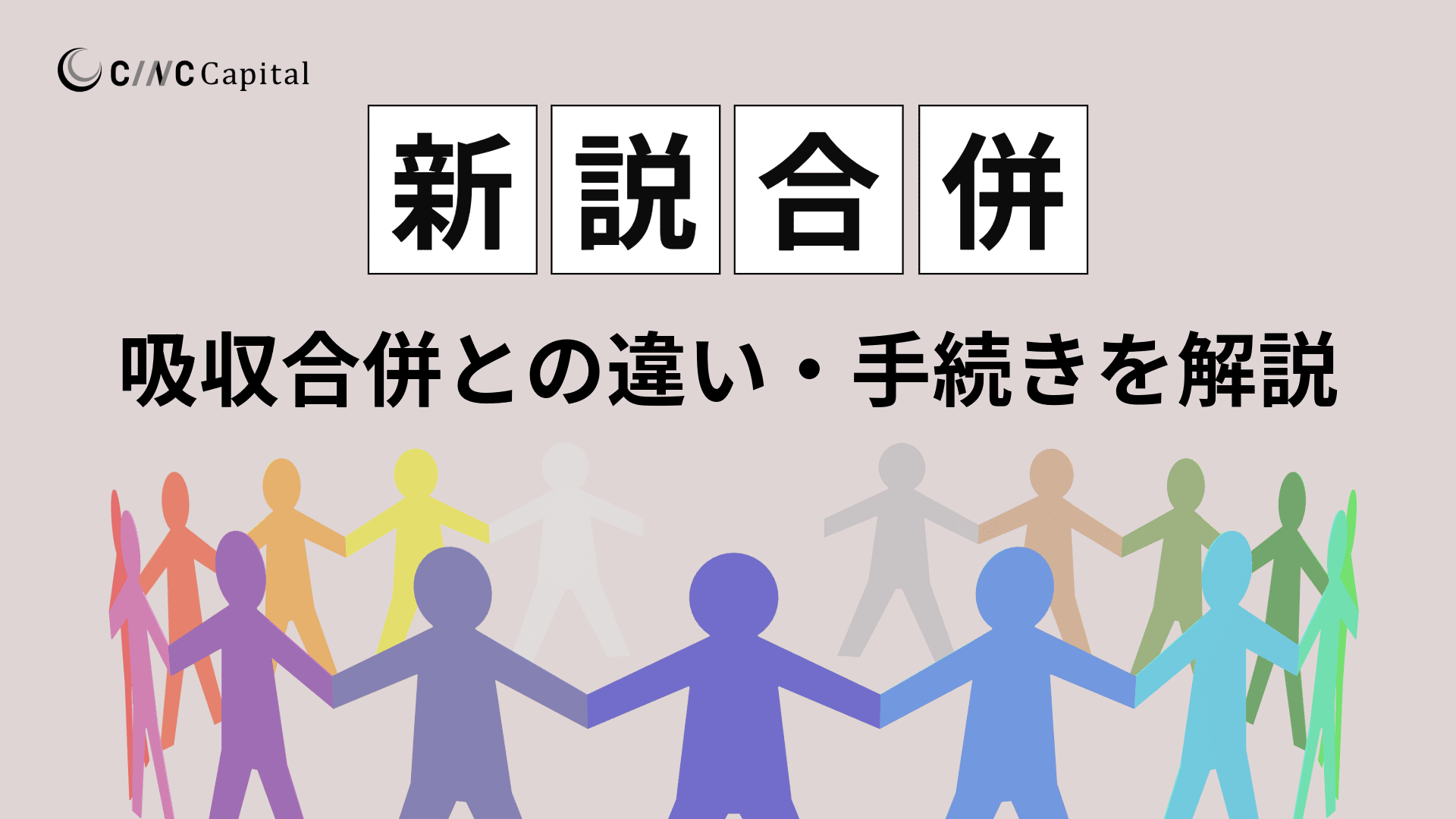
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
新設合併とは?吸収合併との違いやメリット、手続きについて解説
企業統合にはさまざまな方法があり、中でも新設合併は特に事業を対等な立場で統合できるメリットがあります。一方で、許認可の再取得や煩雑な手続きが必要になるため、慎重に進める必要があります。
本記事では、新設合併の基本的な仕組み、吸収合併との違い、メリット・デメリット、手続きの流れについて詳しく解説します。さらに、スムーズに合併を進めるためのポイントも紹介します。
目次
新設合併とは?
新設合併は、複数の企業が合併し、すべての企業が解散したうえで、新しい法人として統合する手法です。新設された会社が解散した企業の資産や負債、契約を引き継ぎます。ここでは、新設合併と吸収合併、株式移転との違いを詳しく解説します。
吸収合併との違い
吸収合併は、一方の企業が存続し、もう一方の企業が消滅する合併形式です。存続企業は消滅企業の資産・負債だけでなく、契約や従業員の雇用関係などの権利義務も包括的に引き継ぎます。そのため、手続きが比較的簡単であるという利点があります。
一方、新設合併では、すべての企業が解散し、新たな法人が設立されます。そのため、消滅企業が持っていた事業免許や許認可は自動的に新会社に引き継がれることはなく、新会社で改めて取得する必要があります。
例えば、運送業の許可、建設業の許可、酒類販売業免許などは、新会社での新規申請が必要となるケースが多いため、事前に行政機関と調整することが重要です。この違いから、新設合併よりも吸収合併が一般的に選ばれやすい傾向があります。
株式移転との違い
株式移転は、新設合併と異なり、新しい持株会社を設立し、既存企業をその傘下に置く手法です。各企業は存続するため、事業の継続性が保たれます。
一方、新設合併では企業が完全に統合されるため、ブランドや経営方針をゼロから構築する必要があります。そのため、新設合併は完全な事業統合を目指す場合に適している手法です。
新設合併と吸収合併はどっちが多い?
日本では吸収合併のほうが圧倒的に多く、新設合併はまれです。吸収合併では存続会社が法人格を維持できるため、許認可や契約の再取得が不要であり、手続きの簡略化が可能です。
一方、新設合併は新会社の設立が必要であり、行政手続きが多くなるため、実務上選ばれることは少ないです。特にM&Aでは、企業間の統合をスムーズに進める目的で、吸収合併が主流となっています。
新設合併のメリット
新設合併には、複数の企業の経営資源を統合し、シナジー効果を高めながら、より強固な組織を構築できる利点があります。特に、異なる強みを持つ企業同士が統合することで、相乗効果を生み出しやすくなります。さらに、事業規模の拡大や新たなブランド戦略の構築といった長期的な成長も期待できます。以下で、具体的なメリットについて詳しく説明します。
シナジー効果が期待できる
新設合併を行うと、企業同士の強みを組み合わせることでシナジー効果が生まれるというメリットがあります。例えば、技術力に優れた企業と販売網を持つ企業が統合すれば、新しい市場への参入が容易になります。
さらに、業務の重複を削減することで、コスト削減や効率化が進みます。こうしたシナジー効果は、競争力の向上にもつながります。企業が持つ資源を最大限に活用できるため、統合後の成長スピードを加速させることが可能です。
事業規模の拡大ができる
新設合併により、企業の規模を一気に拡大できるという利点があります。企業が大きくなると、信用力が向上し、資金調達の選択肢も広がります。また、統合後の企業は、従来よりも多くの取引先を持つことになり、市場での影響力を強めることが可能です。
さらに、統合によって異なる地域や業界への進出がスムーズになり、新規顧客の獲得につながります。こうした規模の拡大は、競争環境の変化に柔軟に対応できる企業体制を構築するうえで重要です。
新しい組織体制やブランドの構築ができる
新設合併では、経営戦略や組織体制をゼロから構築できるという点が大きな特徴です。これにより、企業文化の違いによる摩擦を最小限に抑えつつ、適切な経営方針を策定できます。さらに、企業名やブランドを一新できるため、新たな市場戦略を展開しやすくなります。
特に、老舗企業同士の合併では、ブランドイメージの刷新が消費者に好印象を与えることもあります。新会社として生まれ変わることで、競争力を高め、持続的な成長を目指せる環境が整います。
新設合併のデメリット
新設合併には多くのメリットがある一方で、慎重に検討すべきデメリットも存在します。特に、手続きの煩雑さ、許認可の移動といった課題は、実務面で大きな負担となる可能性があります。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。以下で、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
手続きが煩雑で手間がかかる
新設合併は、吸収合併に比べて手続きが多く、時間と労力を要します。新会社の設立と同時に合併を進める必要があり、それに伴い契約書の作成、株主総会の開催、公告、債権者保護手続きなど、多くの法的要件を満たす必要があります。これらの手続きには時間がかかるため、事前に専門家と連携し、スケジュール管理を徹底することが不可欠です。
許認可の移動が必要となる
新設合併では、消滅企業が持っていた許認可が自動的に新会社に引き継がれるわけではありません。そのため、新会社で改めて許認可を取得する必要が生じる場合があります。
例えば、金融業や建設業など、特定の事業を行うために必要な許認可を取得している企業が合併する場合、新会社で改めて申請手続きを行わなければなりません。許認可の再取得には時間がかかり、場合によっては事業の一時停止を余儀なくされるケースもあります。こうしたリスクを回避するためには、事前に管轄の行政機関と調整し、スムーズな移行が可能かどうかを確認しておくことが重要です。
新設合併の流れ・手続き
新設合併を実施するには、法律で定められた複数の手続きを順番に進める必要があります。主な流れとして、合併契約の締結、株主総会の決議、債権者保護手続き、新会社の設立登記などが挙げられます。各手続きを適切に進めることで、合併後のスムーズな事業運営が可能になります。以下で、各ステップを詳しく解説します。
合併契約書の作成・締結
新設合併を行うには、まず合併契約書を作成し、関係企業間で締結する必要があります。契約には、新会社の名称・所在地、合併比率、資本金、取締役構成などの詳細を記載します。これにより、合併の条件を明確にし、株主や債権者に対して透明性を確保できます。契約内容に不備があると、後のトラブルにつながるため、弁護士やM&Aアドバイザーと協力しながら慎重に作成することが重要です。
合併契約の公告・備置
合併契約を締結した後、公告と備置を行う必要があります。公告とは、官報や自社のウェブサイトなどを通じて、合併契約の内容を公に知らせる手続きです。これにより、株主や債権者が契約内容を確認し、異議を申し立てる機会を得られます。また、契約書を一定期間本社に備え置くことで、関係者が自由に閲覧できるようになります。これらの手続きは、透明性を確保し、合併に伴うリスクを低減するために欠かせません。
株主総会の特別決議
新設合併を実施するには、各企業の株主総会で特別決議を経る必要があります。この決議では、議決権を持つ株主の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成が必要です。株主にとって、新設合併は企業の存続に関わる重大な決定となるため、事前に十分な説明を行い、理解を得ることが重要です。反対意見が多い場合、合併の進行が困難になるため、経営陣は合併のメリットを明確に伝え、株主の支持を得る努力が求められます。
反対株主の株式買取請求
合併に反対する株主には、会社に対して自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できる権利があります。これを株式買取請求権と呼びます。企業は、株主総会の決議後、一定期間内に反対株主へ通知を行い、買取の手続きを進める必要があります。
株式の価格は、市場価格や会社の財務状況を考慮して決定されます。買取請求への対応を誤ると、株主とのトラブルに発展する可能性があるため、適正な評価額を設定し、誠実に対応することが求められます。
債権者保護手続き
新設合併では、消滅企業の債務が新会社に包括的に承継されるため、会社法に基づく債権者保護手続き(公告および個別催告)が義務付けられています。具体的には、官報や新聞で債権者に対して異議申し立ての機会を与える公告を行い、一定期間内に異議が出た場合は、適切な対応を取る必要があります。
例えば、債権者からの要求に応じて担保を提供する、または債務を事前に弁済するなどの措置を講じることが求められます。適切な手続きを怠ると、後々の法的トラブルにつながるため、慎重に対応することが大切です。
登記手続
法務局で新会社の設立登記を行い、同時に旧企業の解散登記を行います。登記手続きを完了することで、新会社は正式な法人格を取得し、事業を開始できる状態となります。登記には、合併契約書や株主総会議事録などの書類が必要となるため、事前に準備を整えておくことが重要です。法務手続きに不備があると、合併の進行に支障をきたす可能性があるため、専門家と連携しながら慎重に進めることが求められます。
事後開示手続き
合併後、新会社には一定期間、合併に関する情報を公開する義務があります。具体的には、合併契約の内容や財務状況を記載した書類を備え置き、関係者が閲覧できるようにする必要があります。この手続きは、合併後の透明性を確保し、利害関係者の信頼を維持するために不可欠です。
特に、合併に伴う財務の変化や、経営戦略の変更点を明確に示すことで、投資家や取引先との円滑な関係を維持できます。適切な情報開示を行うことで、合併後の経営基盤を安定させられます。
まとめ|円滑な新設合併を実施するために、M&A仲介会社に相談しよう
新設合併は、対等な企業統合を実現できる手法ですが、手続きの煩雑さや許認可の再取得が必要になる点が課題です。スムーズに進めるには、事前準備と専門家のサポートが不可欠です。
専門家に相談することで、手続きを確実に進め、リスクを最小限に抑えられます。新設合併を検討する際は、慎重な計画と適切なサポートを活用し、円滑な統合を目指しましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















