CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
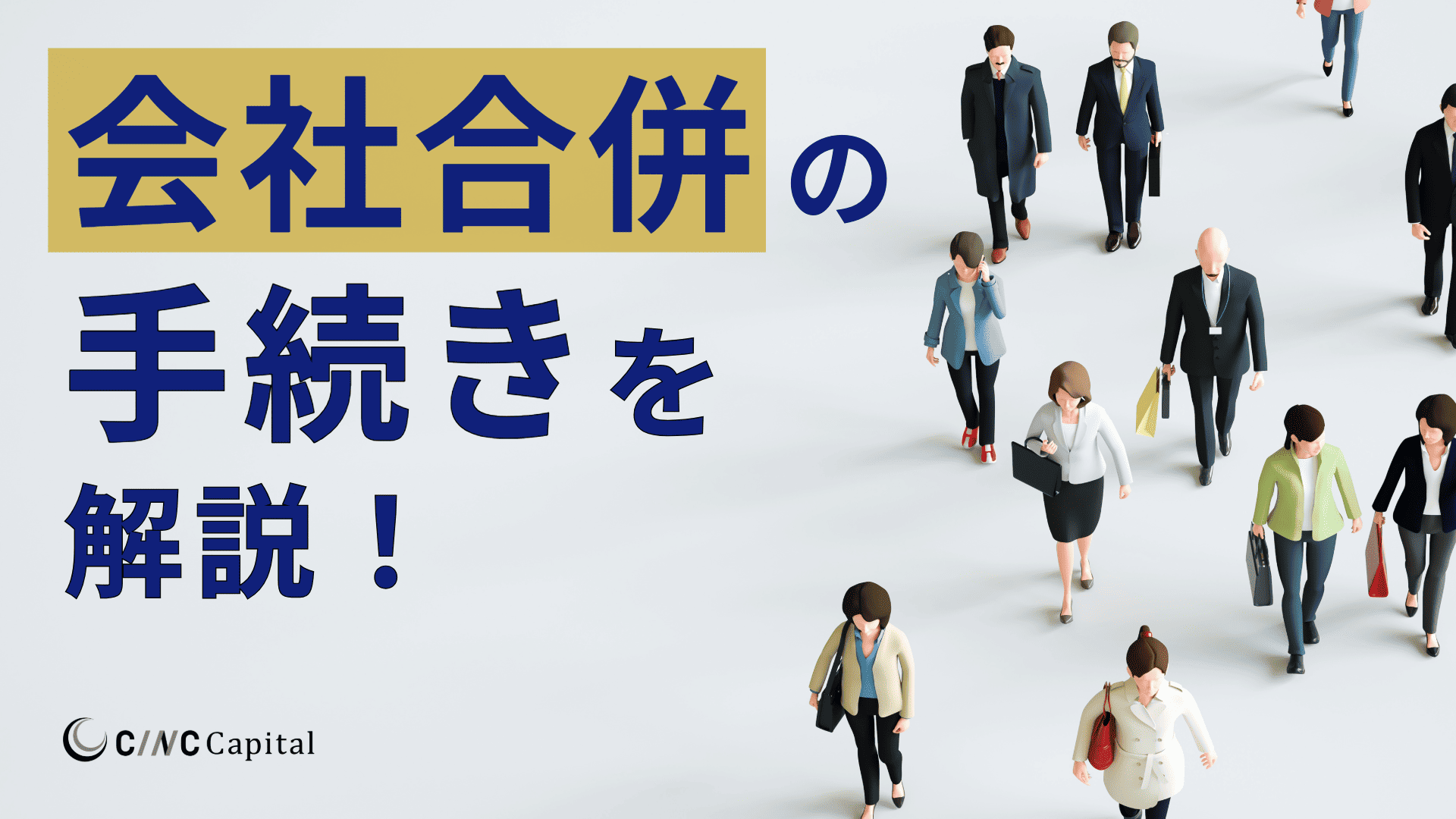
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
会社合併はどのような手続きで行う?成功させるためのポイント
会社合併はM&A手法の一種であり、企業の成長を促す手段です。自社の課題を解消し、さらなる成長を目指すため、合併を検討している企業も多くあります。
会社合併には複雑な手続きがあり、書類にも正確性が求められます。事前にどのような手続きが必要になるかを把握しておきましょう。
この記事では、会社合併の基礎知識やメリット・デメリット、各種手続きなどを解説します。
目次
会社合併の概要
会社合併には吸収合併と新設合併の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持ちます。最初に、会社合併の概要や種類をご紹介します。
会社合併とは
会社合併はM&Aのスキームの1つで、複数の企業を一つに統合することを指します。合併の手法により、「吸収合併」や「新設合併」の2種類に分けられます。
会社合併の種類
吸収合併
一つの会社に他の会社が吸収される合併の方法です。合併に伴って法人格が消えるほうを「消滅会社」、権利義務を引き継ぐほうを「存続会社」と呼びます。消滅会社の許認可などもそのまま承継できるため、スムーズに事業を開始しやすい点がメリットです。
新設合併
新設合併とは、複数の会社が合併して全く新しい会社を設立する形態です。既存の会社は消滅し、新たに設立された会社にすべての権利義務が承継されます。
吸収合併と同様に、新設合併も多くの法的手続きが必要です。ただし新設合併は、対等な関係にある会社同士の合併に適した形態であり、新たなスタートというイメージからポジティブな印象を与えやすいメリットがあります。
会社合併のメリットとデメリット
会社合併を検討する際は、メリット・デメリットを把握しておくことが大切です。主な利点や注意点を確かめていきましょう。
会社合併のメリット
会社合併により、複数企業のシナジーによる効果が期待できるのは大きな魅力です。人材やノウハウの共有が行えるほか、取引先や仕入先なども引き継ぎ可能であり、市場シェア拡大や売上向上などを狙えます。成長性や競争力が向上し、さらなる飛躍へつなげられるでしょう。
権利義務や資産などの承継を包括的に行えるのもメリットの一つです。例えば、事業譲渡によるM&Aを選んだ場合は個別承継となり、契約や許認可等の手続きが必要となります。対して、合併であれば権利義務などはまとめて引き継ぎできます。
会社合併のデメリット
会社合併は、その他のM&Aと比較すると手続きの手間がかかりやすい手法とされます。会社法に基づく正しい方法で手続きするために、M&A専門家の力を借りることがおすすめです。
また、合併後も企業文化の違いによる摩擦が起こり得る点には留意が必要です。経営統合のプロセスにも時間が求められるため、長期的な戦略を立てることが重要です。
会社合併の手続き
吸収合併と新設合併の手続きの流れはほとんど同じですが、いくつかの部分で違いがあります。以下では、基本的な会社合併の手続きについてご紹介します。
1.合併の目的の明確化
何のために会社合併を行うのかを明確にします。目的を設定することで、適切な交渉相手を絞り込みやすくなるでしょう。また、合併に向けての具体的な計画を立てやすくなります。
2.合併の計画策定
合併の目的達成のために必要な計画を立てていきます。法的な手続きには期限が定められているものもあるため、事前に把握した上でスケジュールを決めます。
3.取締役会での承認
当事会社で交渉し、条件をすり合わせて基本合意に至ります。その後、それぞれの会社で取締役会を行ってM&Aの承認を得ます。
4.合併契約書の作成
会社合併に際して合併契約書の締結を行います。合併契約書には会社によって定められた法定記載事項があり、違反のある場合は原則として合併が無効となるため注意が必要です。
吸収合併の主な法定記載事項となるのが、存続会社と消滅会社の商号や住所、合併条件、対価支払いに関する取り決め、合併の効力発生日などです。その他、当時会社で定めた任意の記載事項を記します。新設合併の法定記載事項は、消滅会社の商号や住所、新設会社の商号や発行可能株式総数、設立時の取締役や役員などさまざまです。
5.債権者保護手続き
合併に伴い、存続会社・消滅会社の債権者保護手続きを行う必要があります。合併を実施する点や異議申し立て可能な点などを公告しなくてはいけません。異議申し立て期間は1カ月以上設けることも決まっているため、公告のタイミングに気をつけましょう。
6.反対株主の株式買取請求の手続き
会社合併に反対の株主は、会社に対して株式の買取請求を行う権利があります。当事会社は、株主が株式買取請求権を行使できるように配慮し、通知もしくは公告を行います。
また、株式は適正価格での売却が必要です。そのため、専門家による株価の鑑定を実施するケースもあります。
7.株主総会での承認
合併の効力発生日の前日までに株主総会を開催し、特別決議で承認を得なければいけません。ただし、吸収合併は一定の条件を満たす場合に「簡易手続」や「略式手続」を利用することで、株主総会における承認を省略可能です。一方で、新設合併は「簡易手続」や「略式手続」は認められていません。
簡易手続の条件は、消滅会社の株主に対して交付される対価が基準となります。対価の合計が存続会社の純資産5分の1を超えないことが条件です。略式手続は、当事会社の片方が議決権90%を持つ「特別支配関係」にある場合に行えます。
8.合併の登記
合併契約書に記載の効力発生日が来たら、合併の効力が発生します。また、効力発生日から決められた期間中は「事後開示書類」の備置が必要です。
会社合併を成功させるポイント
会社合併を成功に導くためには、どのような点を意識しておけば良いのでしょうか。以下では、会社合併を行う上で知っておきたい成功のポイントを解説します。
必要書類を早めに用意する
会社合併を実施する際は、合併契約書や事前開示書類など、さまざまな書類を用意しなければなりません。また、存続会社や消滅会社の登記手続きを行う際には、多くの書類が必要となります。どのような書類か必要かを確認して、正確な内容のものを準備しましょう。
従業員への影響に配慮する
合併における従業員への影響は少なくありません。従業員の不利益にならないよう、慎重に契約関係をすり合わせることが求められます。
また、無理に変革を推し進めるとモチベーション低下につながり、離職を招いてしまうことも考えられます。事前の丁寧な説明や、個別のフォローをしっかりと行うことも重要です。
デューデリジェンスへの丁寧な対応
会社合併は資産の包括的な承継が可能な一方、見えない負債を抱えてしまうリスクがあります。事前のデューデリジェンスで、相手企業の実態を徹底調査することが大切です。
具体的には、相手企業の事業の状態、必要な許認可の有無、財務・法務の状況、人事・労務の課題、社員の意見など、必要な分野について丁寧な調査を行います。
専門家への相談
会社合併をはじめとするM&Aでは、専門的な知識を問われる状況が多くなります。自社にとって適切なM&Aスキームや合併の相手となる企業の選定、計画立案、各種書類作成、デューデリジェンスなど、多岐にわたる場面で専門家の知見を借りることになるでしょう。合併を検討している場合、まずはM&A仲介会社をはじめとする専門家に相談することがおすすめです。
まとめ|会社合併の手続きや特徴を理解し、専門家とともに成功させましょう
会社合併の手続きは煩雑であり、自社の人材のみで正確に遂行するのは難しいケースがあります。M&Aの専門知識を持つプロの業者に依頼し、サポートを受けるのが望ましいでしょう。M&A仲介会社には深い知見を持つアドバイザーが集まっており、安心して任せられるのがメリットです。無料相談を行っているところもあるため、まずは自社の状況や希望などを伝えてアドバイスをもらいましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、会社合併のご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















