CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
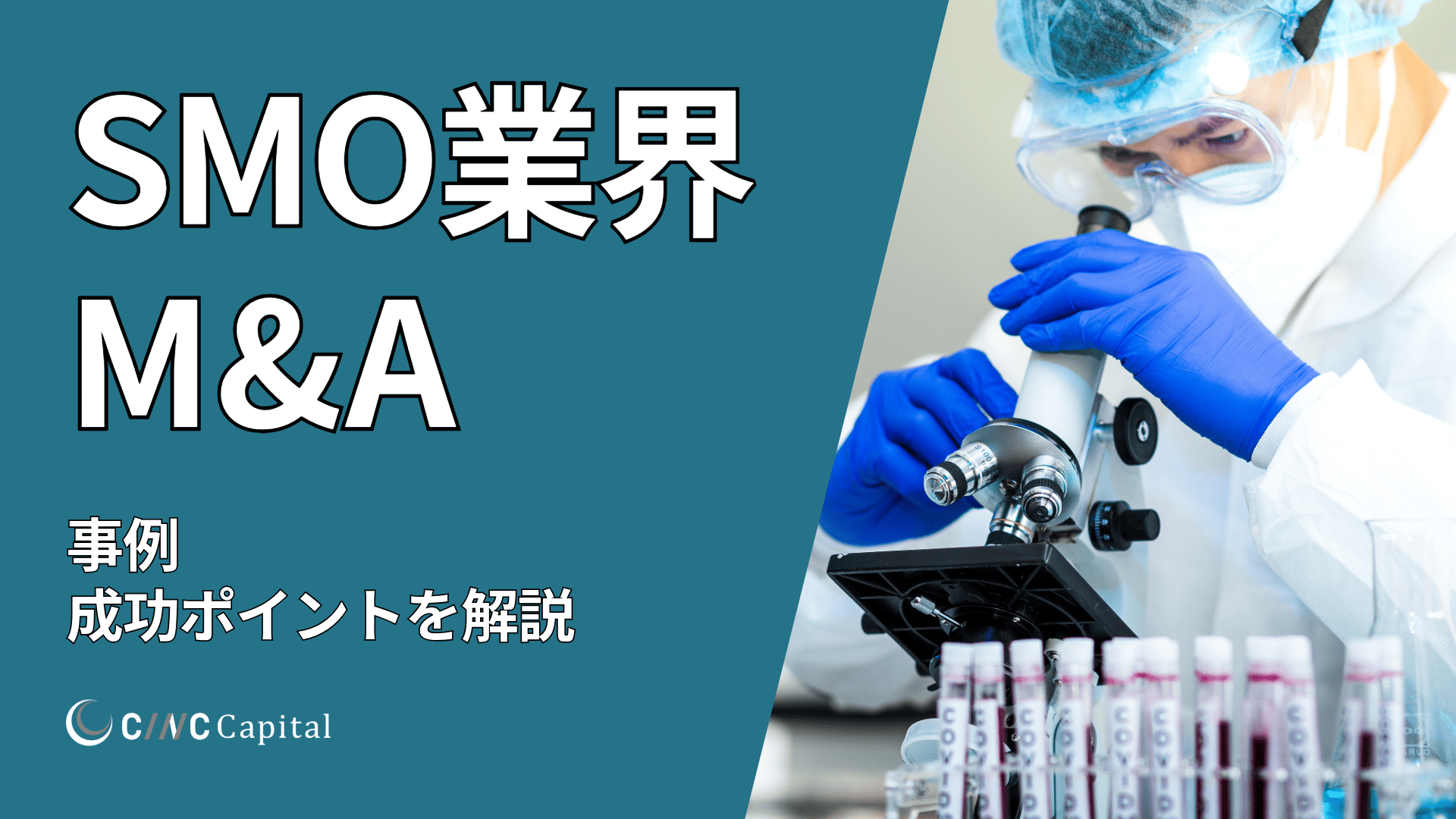
業種
- 公開日2025.09.30
SMO業界のM&A動向は?事例や成功のポイントを解説【2025年】
SMO業界(治験施設支援機関)の今後について、不安や疑問を抱えていませんか。
医療業界では変化が続いており、治験支援に関わる企業には成長性の見極めやM&Aの判断が一層重要になっています。
本記事では、2025年時点におけるSMO業界のM&A動向や成功ポイントを詳しく解説します。
目次
SMO業界の市場動向
日本のSMO市場は2020年代に入り成長が続いており、2023年の市場規模は約400億〜475億円と推定されています。
これは、製薬企業による治験業務の外部委託や国際共同治験の増加が背景です。
さらに医薬品開発の高度化により、SMOの役割も拡大しています。
市場ではEP綜合、シミック、エムスリー、アイロムなど大手による寡占化が進行中で、中小SMOの統合が活発に行われ、業界再編が加速しています。
SMO業界が抱えている課題
SMO業界は治験を支える重要な役割を担っていますが、近年は業務効率や品質、人材確保に関する課題が表面化しています。
本章では、SMO業界が抱えている課題を3つに分けて見ていきましょう。
業務の属人化による品質リスク
SMOの業務は、個々のCRC(治験コーディネーター)のスキルや経験に依存する傾向が強く、業務の属人化が進んでいます。
このような状況では、業務の標準化が難しくなり、治験の品質や進捗管理にばらつきが生じるリスクがあります。
また、CRCの退職や異動により、業務の引き継ぎが円滑に行われない場合、治験の進行に支障をきたす可能性もあるでしょう。
これらの課題を解決するためには、業務プロセスの標準化やSOP(標準作業手順書)の整備、ナレッジの共有が不可欠です。
DX(デジタル化)の遅れ
治験業務のデジタル化は効率化と品質向上に不可欠ですが、SMO業界では導入が遅れているという現状があります。
特に中小SMOでは紙ベースの運用が多く、電子カルテやeConsentの普及が進んでいません。
これにより情報共有が滞り、治験の実施にも影響が出る恐れがあります。
DX推進には、導入コストやITリテラシーの向上などが課題です。
人材不足とCRC採用競争の激化
SMO業界では、治験コーディネーター(CRC)の人材不足が深刻な問題となっています。
特に、経験豊富なCRCの確保が困難であり、各SMO間での採用競争が激化しています。
この背景には、治験の増加や複雑化に伴い、CRCに求められるスキルや知識が高度化していることが挙げられます。
また、業務量の多さや給与水準の課題も、離職率の高さに影響を与えており、業界全体での人材確保と定着率向上が急務です。
SMO業界のM&A最新動向(2025年)
2025年現在、SMO業界では中小企業の買収、海外資本の参入、ヘルステック企業との提携が活発化しています。
本章では、それぞれの動向について詳しく見ていきましょう。
大手による中小SMOの買収と寡占化
近年、EP綜合やシミック、エムスリーなどの大手SMOが中小SMOを買収し、治験施設のネットワーク拡大と効率化を進めています。
エムスリーは複数のSMOを統合し、全国体制を構築しました。
業界再編が進む中、標準化や品質向上が期待される一方で、地域性や独自性の喪失も懸念されています。
海外資本による日本SMO企業の買収
2024年5月、米ブラックストーンが日本のSMO大手・アイロムグループの買収を発表しました。
非公開化により経営資源を集中し、長期的成長を目指す戦略です。
この取引は、日本の治験支援業界における象徴的なクロスボーダーM&Aとされ、今後さらに外資参入が進む可能性を示しています。
ヘルステック・ベンチャーとの提携拡大
SMO各社は、デジタル治験(DCT)や患者データの収集効率を高めるため、ヘルステック企業との提携を強化しています。
例えば、シミックホールディングスは、てんかん患者向け支援プラットフォーム「nanacara」を提供するノックオンザドア株式会社と資本業務提携を締結し、同社を子会社化しました。
この提携により、希少疾患領域における患者支援の強化や、デジタルプラットフォームを活用した治験支援の高度化が期待されています。
SMO業界でM&Aを成功させるためのポイント
SMO(治験施設支援機関)業界におけるM&Aの成功には、業界特有の課題や要件を踏まえた戦略的な取り組みが不可欠です。
本章では、SMO業界がM&Aを成功させるための主要なポイントを5つ解説していきます。
治験関連の法令・GCP対応の一元化
SMO業務には法令やGCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)に沿った高いコンプライアンスが求められます。
M&A後は業務手順や書類管理に違いが生じやすく、早期にSOP(標準作業手順書)を統一し、現場で徹底する体制整備が重要です。
製薬会社からの信頼を得るには、どの現場でも同じ基準で法令を守る体制が欠かせません。
人材・ノウハウの継承と離職防止策
統合時に待遇や評価制度が不透明だと、現場の不安を招き人材流出につながります。
これを防ぐには、処遇方針を早期に示し、キャリアパスや職場環境について丁寧に伝えることが重要です。
形式的な制度だけでなく、文化の違いに配慮した対話とサポートが、ノウハウの継承と人材の定着につながるでしょう。
M&Aの目的と相手先選定の明確化
治験市場の競争が激しくなる中、目的が曖昧なままM&Aを進めると効果は限定的です。
たとえば、疾患領域の拡大か、都市部ネットワークの補完かで適切な相手は異なります。
文化や価値観の相性も統合後に影響するため、数値だけでなく、自社の戦略に合うかどうかを見極める姿勢が重要です。
DX推進とIT基盤の再設計
治験業務では電子カルテやeConsentの活用が不可欠ですが、M&Aで異なるSMOが統合されると、システムの不整合により業務が複雑化する恐れがあります。
これを防ぐには、統合を機にIT基盤を見直し、クラウドによる一元管理や標準化を進めることが重要です。
さらに、業務そのものをデジタル化に適した形へ再設計することで、全体の競争力向上につながります。
スムーズな業務統合(PMI)とシナジー創出
M&Aを成功させるには、統合後の業務を円滑に進め、シナジーを実現することが不可欠です。
特にSMO業界では、治験支援の品質を維持しつつ、迅速な統合が求められます。
PMIでは、組織文化の融合や業務・システムの統一など、さまざまな課題に対応する必要があります。
そのためには、計画の策定や専任チームの設置、進捗管理の徹底が重要です。
SMO業界のM&A事例
ヘリオスによるアサシスのM&A
2024年4月、再生医療を手がけるヘリオスは、経営破綻した米バイオスタートアップ「アサシス」から幹細胞製品に関する特許や治験データなど、実質的な全資産を約3億4000万円で取得しました。
アサシスはARDS(急性呼吸窮迫症候群)や脳梗塞の治療法開発において有望な技術を保有しており、ヘリオスはこれまで同社の幹細胞製品の使用ライセンスを得ていました。
今回の資産取得により、将来的な特許使用料やマイルストーン支払いが不要となり、コスト面でも大きなメリットが生まれます。
また、外傷治療や動物医療への応用可能性も視野に入ることで、ヘリオスの研究開発の選択肢が広がりました。破綻企業の資産を活用した戦略的なM&Aといえます。
【出典】日本経済新聞「ヘリオス、米バイオ企業の知的財産取得 治療法開発に」
トランスジェニックによるMASCのM&A
2023年3月、創薬支援を手がけるトランスジェニックは、北海道のSMO(治験施設支援機関)である株式会社MASCの全株式を取得し、完全子会社化しました。
MASCはジェネリック医薬品メーカーなどを対象に、治験や臨床開発支援を行う企業で、地域の医療機関との信頼関係と高い専門性を持つ点が評価されました。
本件により、トランスジェニックの子会社である新薬リサーチセンターのCRO事業とのシナジーが期待され、創薬支援サービス全体の強化につながります。
株式取得は非開示ながらも、直近のMASCの純資産と経営計画に基づいて合理的に算定されたものです。地域密着型の専門機関を取り込むことで、国内における医薬品開発体制の強化が進む事例といえます。
【出典】株式会社トランスジェニック「株式会社MASCの全株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
ナチュラリによす東北薬理研のM&A
2023年4月、臨床試験支援事業を手がける株式会社ナチュラリは、福島県のSMO(治験施設支援機関)である株式会社東北薬理研の全株式を取得し、完全子会社化しました。
東北薬理研は東北地方に根ざした事業展開と医療機関との強固な信頼関係を持ち、地域密着型SMOとして安定した実績を築いています。
ナチュラリは今回のM&Aにより、同社の地域基盤を強化するとともに、東京オフィスの新設やPCR検査事業で得た経営資源を活かし、首都圏への事業拡大を図ります。
地方の実績ある医療支援企業を取り込むことで、全国展開への足がかりとする戦略的な買収といえます。
【出典】株式会社ナチュラリ「株式会社東北薬理研の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|SMO業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
SMO業界では、治験ニーズの増加やデジタル化、グローバル資本の流入により、M&Aによる再編が加速しています。
大手による中小SMOの買収や外資参入、ヘルステックとの提携は、事業拡大とサービスの高度化を進める上で重要です。
CINC CapitalはSMO業界に特化したM&A支援を行っており、豊富な実績を重ねています。専門知識を活かして企業評価から交渉まで丁寧に対応し、業界特有の課題も安心してお任せいただけます。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


















