CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
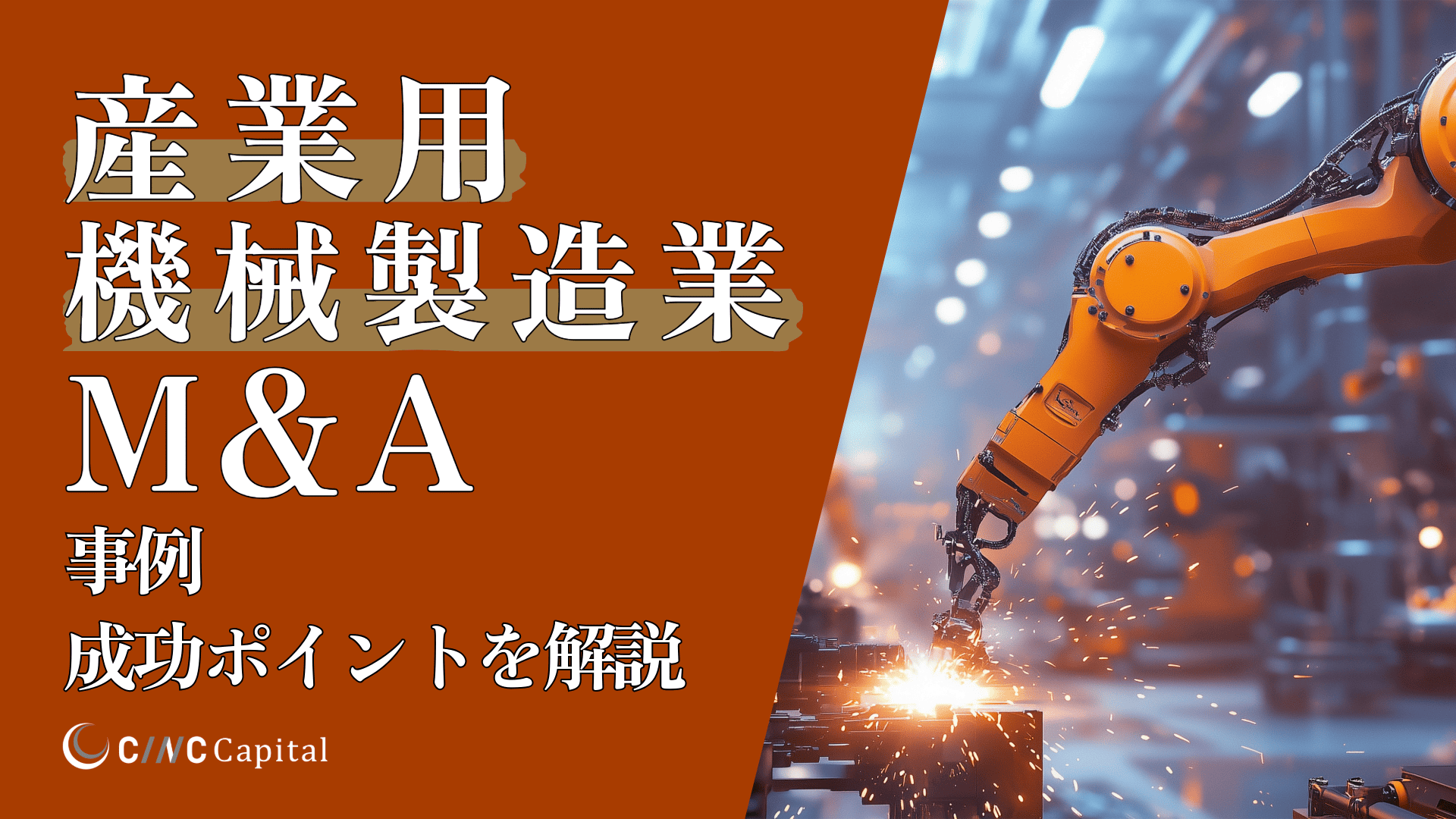
業種
- 公開日2025.09.29
産業用機械製造業のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
産業用機械製造業の事業承継や成長戦略をどう進めるべきか、お悩みではありませんか。
経営者の高齢化や後継者不足、技術継承の停滞、景気変動の影響など、業界特有の課題は深刻化しています。
本記事では、2025年時点の産業用機械製造業のM&A動向を整理し、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。
目次
産業用機械製造業の市場動向
産業用機械製造業は、日本の製造業を支える基盤産業として国内外の需要環境に左右されやすく、景気動向や設備投資の波を受けながら推移しています。
近年は新型コロナによる停滞からの回復後も、内需と外需で動きの差が続いているのが特徴です。
日本産業機械工業会の統計によると、2024年4〜9月期の産業機械受注総額は2兆8,162億円で、前年同期比+1.7%となりました。
内需は1兆8,591億円(▲5.5%)と減少する一方、外需は9,571億円(+19.3%)と増加し、国内と海外で対照的な動きが確認されています。
【出典】日本産業機械工業会「2024年9月産業機械受注状況」
産業用機械製造業が抱える課題
産業用機械製造業では、少子高齢化や後継者不足、さらに技術継承の停滞やデジタル化への対応の遅れなど、複数の課題が顕在化しています。
本章では、産業用機械製造業が直面する課題について、3つの観点から見ていきましょう。
長引く少子高齢化による技術継承の困難
日本の製造業では少子高齢化が進み、若い後継者を確保することが難しくなっています。
後継者不在率は2016年の58.7%から2022年には49.2%へと改善しましたが、依然として高い水準です。
その結果、熟練技術やノウハウが引き継がれず、事業継続への不安が強まっています。
【出典】帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査(2022)」
生産性向上に不可欠なデジタル化・IoT化への対応遅れ
製造業では人手不足や設備投資の負担が重く、デジタル化やIoTの導入が進みにくいのが現状です。
総務省 『令和6年通信利用動向調査(企業編)』によれば、IoT・AIを業務に活用している企業は資本金1億円未満で11.8%、1億円以上で21.4%と規模感で差があり、全体平均でも10%超に留まっています。
こうした導入の遅れが、生産性向上や国際競争力強化の妨げになっています。
【出典】e-Stat サイト 「通信利用動向調査 令和6年 企業編」
内外需の変動と景気依存性の高さ
産業用機械の需要は設備投資に直結しており、景気の動向に大きく左右されます。
景気が後退すると投資は急速に減少し、企業の業績や受注に直接的な影響を及ぼすのです。
内閣府の分析でも、設備投資の増減が戦後の景気拡大や縮小に大きな役割を果たしてきたことが示されています。
産業用機械製造業のM&A最新動向(2025年)
産業用機械製造業では、後継者不足や技術承継の課題に加え、競争力強化を目的とした再編の動きがあります。
本章では、産業用機械製造業におけるM&Aの最新動向について、3つの観点から解説していきます。
大型企業による工作機械メーカーの取り込み
2023年、日本電産(ニデック)が工作機械メーカーのTAKISAWAをTOB(株式公開買付け)で完全子会社化しました。
これは対象企業の経営陣の賛同を得ないまま進められたTOBであり、実質的に敵対的買収の形をとった事例として注目を集めました。
旋盤技術を中心とする工作機械分野の強化を狙った動きで、産業再編の象徴的な事例とされています。
【出典】ニデック株式会社「株式会社 TAKISAWA(証券コード:6121)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」
産業機械分野で多様な事業承継案件が活性化
関西や関東を中心に、製缶板金や発電機、特殊印刷機械などの事業承継案件が多いです。
日本M&Aセンターの公開案件でも、産業機械分野は継続的に新しい情報が掲載されています。
これは地域中小企業の承継ニーズが高まっていることを示し、国内M&A市場の活発化を裏付けているといえるでしょう。
後継者問題の解決と雇用継続
製造業界では経営者の高齢化により、後継者が見つからずに困っている企業が少なくありません。
M&Aを活用すれば、経営のバトンタッチと同時に従業員の雇用や技術が守られるケースが増えています。
これにより企業の存続が可能となり、地域経済の安定にもつながっているのです。
産業用機械製造業でM&Aをするメリット
産業用機械製造業では、後継者不足の解消や技術力の強化、販路拡大などを目的にM&Aの活用が広がっています。
本章では、産業用機械製造業におけるM&Aのメリットを5つ解説していきます。
後継者問題の解消と雇用の維持
製造業では、経営者に後継者がいないため廃業を検討するケースが少なくありません。
M&Aを利用すれば、事業承継を通じて従業員の雇用や技術を守ることができます。
これにより、地域社会や取引先への影響を最小限に抑えながら、事業を継続することが可能です。
資金力ある親企業体制で経営安定と投資機会拡大
大手企業の傘下に入ることで、資金や経営資源を活用しやすくなります。
設備投資や研究開発に十分なリソースを投入できるため、事業の成長スピードが加速します。
さらに、販路の共有や信用力の向上によって、安定した経営基盤を築くことができるでしょう。
技術・ノウハウの迅速な取得による競争力向上
M&Aでは、自社にない技術やノウハウを短期間で取り入れることができます。
これにより、製品開発のスピードが上がり、事業の幅を広げることが可能です。
新しい技術を活かすことで、市場での競争力を高められます。
販路・顧客基盤の拡大
買収を通じて取引先や販売ネットワークを引き継ぐことで、新しい市場へスムーズに進出できます。
既存の販路を活用できるため、短期間で売上を伸ばすチャンスが生まれるのです。
クロスセルを行うことで、顧客満足度を高めながら事業を拡大できます。
規模拡大によるコスト削減・調達力強化
企業規模が大きくなると、部材の一括仕入れや物流の効率化が可能です。
その結果、管理コストや運営コストを抑えることができます。
また、交渉力が増すことで仕入れ条件の改善につながり、収益性の向上が期待できるでしょう。
産業用機械製造業でM&Aをするデメリット
産業用機械製造業では、企業文化の違いや統合作業の難しさ、取引先との関係変化など、M&A特有の課題が存在します。
本章では、産業用機械製造業におけるM&Aのデメリットについて、3つの観点から解説していきます。
文化・現場摩擦による離職リスク
M&A後に企業文化が合わないと、従業員のやる気が下がり、離職につながる恐れがあります。
特に中小の製造業では社員の会社への愛着が強く、急な体制変更は不安を生みやすいです。
Bain&Companyの調査でも、文化統合の難しさがM&A失敗の大きな要因になると報告されています。
統合コスト・プロセスの複雑化
製造業のM&Aでは、設備やシステム、業務の標準化に多くの時間と費用が必要です。
EYの調査では、先進製造業で統合コストが対象企業収益の5%を超えるケースもあると示されています。
統合の規模が大きいほどコストは膨らみ、想定以上の負担になる場合があるのです。
【出典】EY Parthenon「Beyond the deal: accurately estimating M&A integration costs」
取引先離れなど顧客関係の変動リスク
M&Aによる経営体制の変化は、取引先に不安を与え、取引縮小や解消につながる可能性があります。
統合の際に平均2~5%の顧客が離れるとされ、業種によってはさらに高い割合になることもあります。
こうした顧客離れは収益に直結するため、特に注意が必要です。
産業用機械製造業でM&Aを成功させるためのポイント
産業用機械製造業では、後継者不足や技術承継の課題に加え、デジタル化や国際競争への対応も必要です。
本章では、産業用機械製造業におけるM&Aを成功に導くための具体的なポイントを5つの観点から解説していきます。
自社の技術・強みの可視化
自社の技術力や特許、独自のノウハウを分かりやすくまとめ、資料化しておくことが大切です。
これにより買い手企業にとって魅力が高まり、交渉を有利に進めやすくなります。
技術や強みを明示することが戦略的な優位性につながるでしょう。
設備・生産性の事前整備
老朽化した設備を更新したり、生産効率を改善したりしておくと、企業価値を高めることができます。
統合後の事業運営もスムーズになり、買い手に安心感を与えることが可能です。
強固な事業基盤の整備がM&A成功において重要になります。
顧客基盤の安定化と関係維持
主要な取引先との信頼関係を日頃から築いておくことは非常に重要です。
特定の顧客に依存せず、販路を分散させておくことで、M&A後の顧客離脱リスクを抑えることができます。
中小企業にとって顧客基盤の多角化は、M&Aを円滑に進める上で大きな強みとなります。
法務・財務の透明性確保
M&A前に債務や契約、税務、許認可などを整理しておくことは欠かせません。
情報をクリーンな状態にしておけば、買い手の不安を解消しやすくなります。
その結果、交渉をスムーズに進められ、取引成立の可能性も高まるのです。
人材育成と承継体制の構築
若手人材を育成し、ベテラン社員の技能をマニュアル化することは事業承継に成功に直結します。
誰が引き継いでも業務を継続できる体制を整えておけば、買い手に安心感を与えられるのです。
このような体制は、M&A後の技術継承や事業の安定運営に大きく役立つでしょう。
まとめ|産業用機械製造業のM&A成功のカギを握るのは「準備」と「戦略」
産業用機械製造業界は、少子高齢化や技術継承の停滞、デジタル化の遅れ、景気変動による需要の影響など複数の課題を抱えています。
こうした状況でM&Aは事業承継と成長戦略を実現する有効な手段です。
2025年は大手企業による買収や多様な事業承継案件の増加が目立ち、後継者問題の解決にも活用が進んでいます。
CINC Capitalは一般社団法人M&A支援機関協会(MAAA)・中小企業庁の登録支援機関です。
業界歴10年以上の専門家が、譲渡や買収の目的に応じて適切な手法をご提案します。
秘密厳守でスムーズな取引を支援します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

















