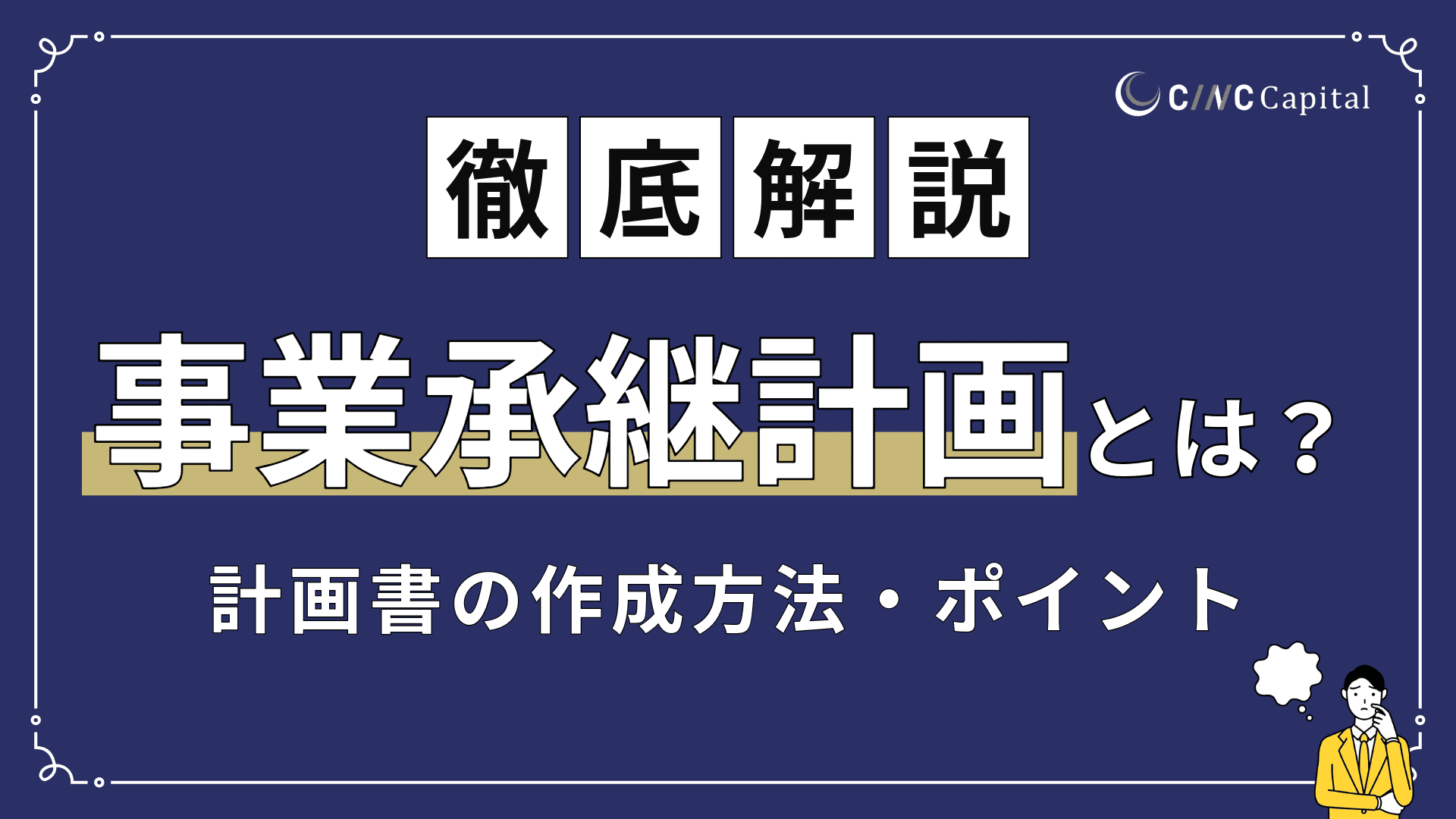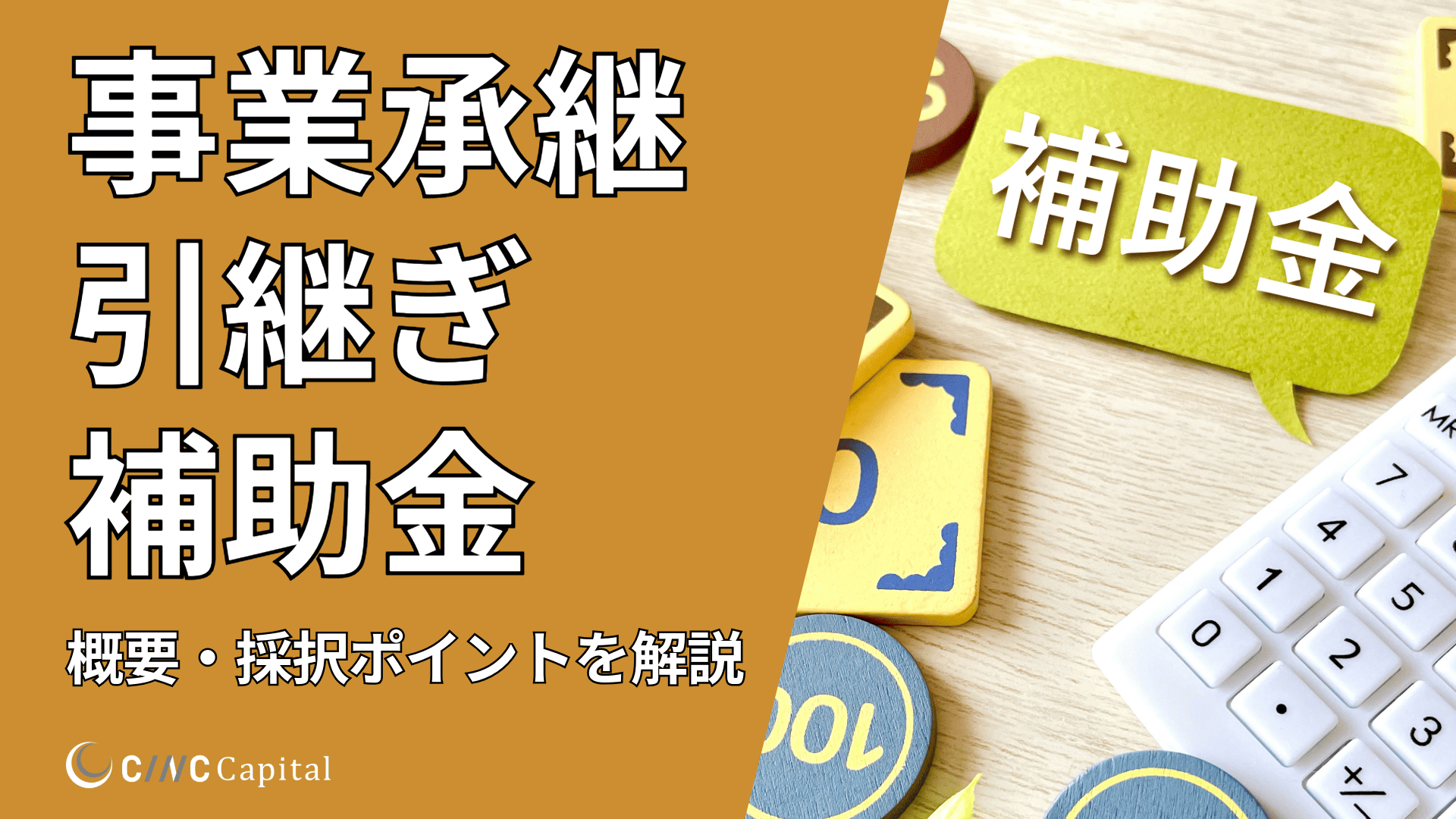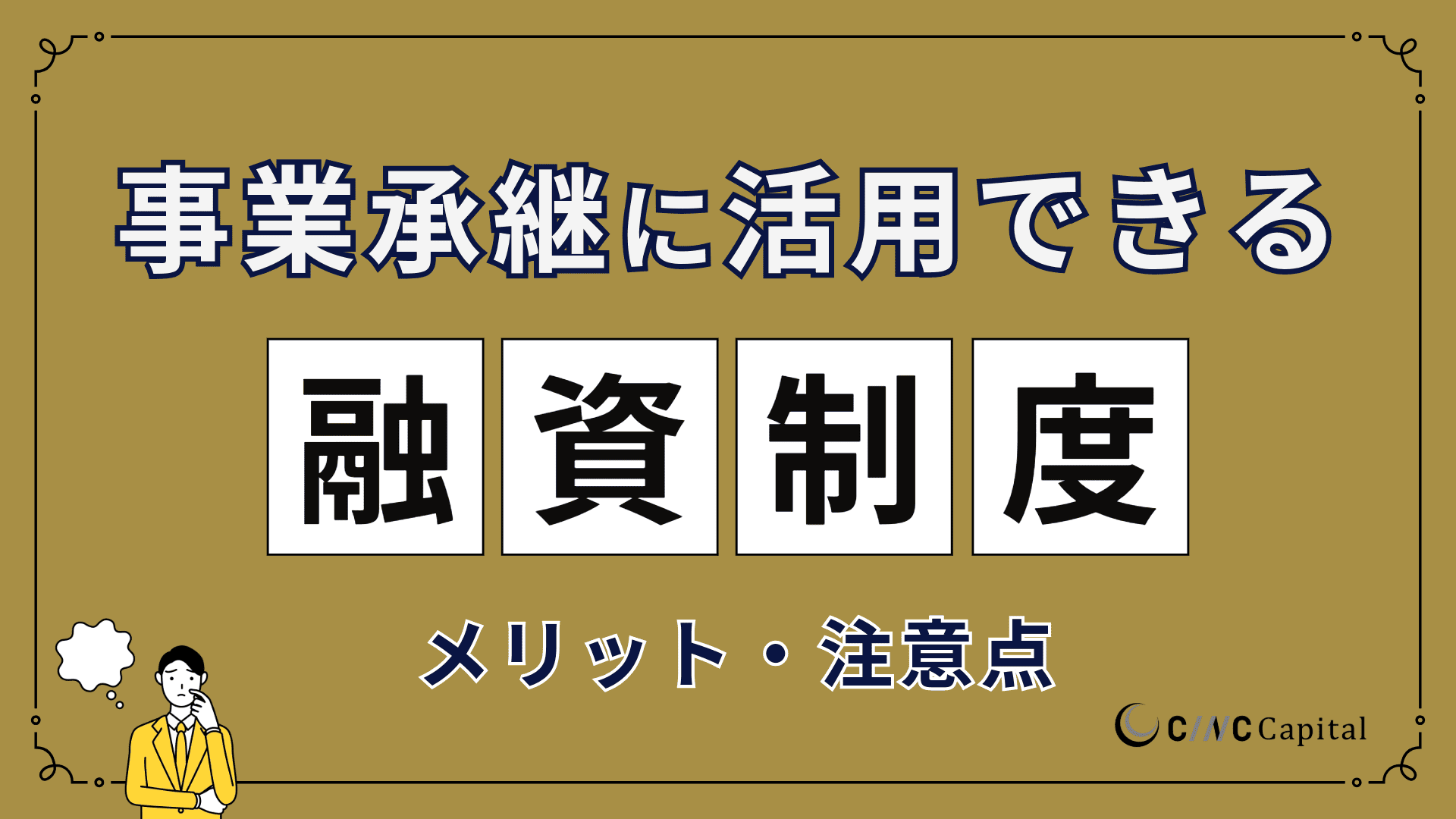CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
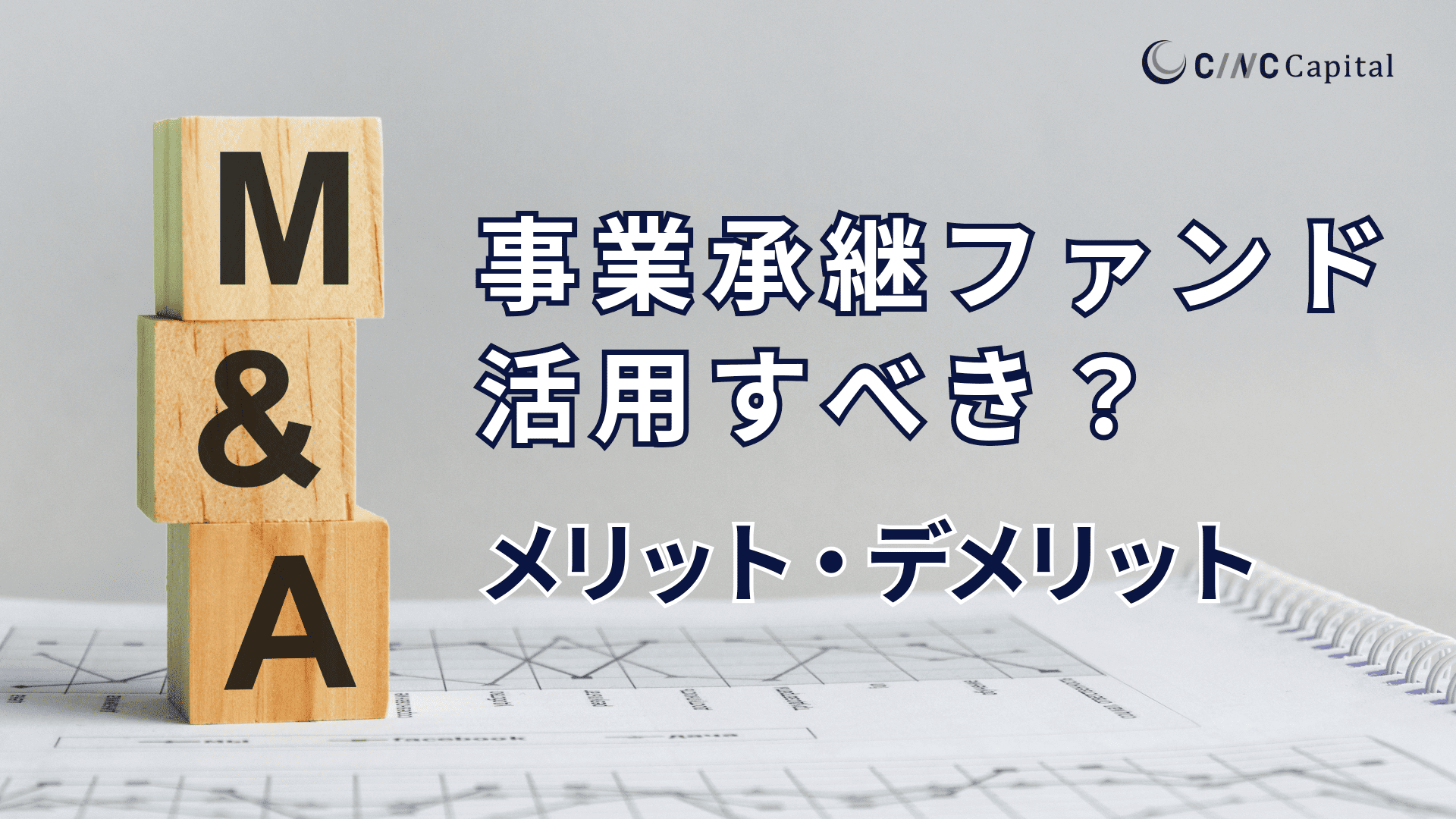
事業承継
- 最終更新日2025.07.08
事業承継ファンドとは?メリットやデメリット、活用するポイントを解説
高齢化や後継者不在による中小企業の廃業リスクが高まる中、注目を集めているのが「事業承継ファンド」です。
事業承継ファンドは、専門家が経営支援を行いながら企業を成長させ、次の担い手へとバトンを渡す新しい事業承継の形です。この記事では事業承継ファンドの仕組みやメリット・デメリット、活用時のポイントについて解説します。
目次
事業承継ファンドとは?
事業承継ファンドとは、高齢化などで後継者不在の中小企業を対象に、第三者が出資・買収し経営を引き継ぐための投資ファンドです。事業の継続と雇用維持を目的としています。
事業承継ファンドの仕組み
事業承継ファンドの仕組みは、出資者から集めた資金で後継者不在の企業を買収し、専門チームが経営支援を行いながら価値を高め、将来的に売却やIPOで利益を得る流れです。
ファンドは投資家から集めた資金で企業の株式を買い取り、専門的な経営ノウハウを提供しながら企業価値の向上を目指します。その後、価値が高まった企業を再びM&Aによって事業会社や他のファンドなどに売却することで投資リターンを得るビジネスモデルです。
なお、ファンドによる株式取得後も、状況に応じて創業者が一定期間経営に関与し続けるケースや、社内の後継者候補の育成をサポートするケースもあります。
このような形態では、ファンドの経営支援リソースを活用しながら、段階的な事業承継を進められる利点があります。
事業承継ファンドとM&Aとの違いは?
事業承継ファンドもM&Aも、どちらも株式や事業の売買を伴う点では同じM&Aの一形態ですが、買い手の性質や目的に重要な違いがあります。事業承継ファンドは、「時限的保有・成長支援型」のM&A手法です。
ファンドは通常数年程度の期間を想定して企業の株式を取得し、経営改善や業績向上を支援します。その後、企業価値が高まった段階で第三者(事業会社や他のファンドなど)に売却することで投資リターンを得ることが可能です。ファンドとの協業により、創業経営者が一定期間関与を続けながら徐々に引退準備を進められるケースもあります。
一方、事業会社への直接的なM&Aは「恒久的保有・事業統合型」の手法です。同業他社や取引先企業などが買い手となり、自社の事業との統合や相乗効果を目的として経営権を取得します。買収後は買い手企業の経営方針が適用されることが一般的で、創業者の関与は短期間の引継ぎにとどまるケースが多く見られます。
つまり、事業会社へのM&Aは買い手が自社の事業戦略に基づいて恒久的に保有することを前提とするのに対し、事業承継ファンドへのM&Aは投資ファンドが一時的に保有して企業価値を高めた後に再売却することを前提としています。企業の状況や経営者の意向、従業員への影響などを総合的に判断して、どちらの手法が適しているかを検討することが重要です。
事業承継ファンドを活用するメリット
事業承継ファンドを活用することで、後継者不在の企業でも事業の存続が可能になり、経営の安定や成長を目指せます。ここでは、事業承継ファンドを活用する主なメリットについて詳しく解説します。
後継者不在でも事業の存続が可能になる
M&Aは、後継者がいない企業でも事業を継続できる選択肢の一つです。多くの中小企業では、親族内や社内に適切な後継者が見つからず、廃業を余儀なくされるケースがあります。しかし、M&Aを活用すれば、経営権を買い手が引き継ぐため、後継者がいなくても事業の存続が可能です。
その中でも事業承継ファンドを買い手として選択した場合は、ファンドが一定期間経営に関与しながら、事業の安定化や成長支援を行います。経営の空白期間が生じることなく、従業員の雇用維持や取引先との関係維持がしやすくなる点も特徴です。
通常の事業会社への売却と比較すると、ファンドは急激な経営方針の変更を行わないケースが多く、企業文化や事業の独自性を維持しやすい点が差別化されています。
いずれにせよ、M&Aによって後継者問題を解決することで、オーナー経営者の引退計画を実現しながらも、長年培ってきた事業や従業員の雇用を守ることができます。
ファンドの経営支援により企業成長が期待できる
事業承継ファンドの活用は、単なる事業の存続にとどまらず、企業の成長機会をもたらします。ファンドには業界に精通した専門家が在籍しており、経営戦略の見直しや業務効率化、財務基盤の強化など、多方面からの支援を受けられます。
成長余力のある企業の場合、ファンドのネットワークを活用して新たな取引先を開拓したり、M&Aを活用した事業拡大を進めたりすることも可能です。自社の強みを最大限に活かしながら次の成長フェーズへと移行できる点が、事業承継ファンドの大きな魅力です。
一般的なM&Aよりも創業者が一定の関与を続けやすい
一般的な事業会社へのM&Aでは、買収後に創業者が短期間の引継ぎ期間を経て完全に退任するケースが多く見られます。一方、事業承継ファンドの場合、創業者が一定期間関与しながら、より段階的に経営移行を進めるスキームを取りやすいという特徴があります。
例えば、株式の一部をファンドに譲渡し、残りの株式は創業者が保有したまま共同経営を行う形態や、ファンドが過半数の株式を取得した後も創業者が引き続き代表取締役として経営に携わり、次世代の経営陣を育成していく形態などが可能です。
このような方法を取ることで、創業者の知見や人脈を活かしながら、より円滑な承継プロセスを実現できます。
また、創業者が一定期間経営に関与し続けることで、取引先や従業員の不安を軽減できる点もメリットの一つです。特に、創業者の個人的信頼関係で成り立っている取引や、創業者のリーダーシップに強く依存した組織文化を持つ企業にとって、段階的な移行は事業価値の毀損を防ぐ効果があります。
なお、事業会社へのM&Aでも、アーンアウト条項(業績連動型の追加支払い)を設定することで創業者の一定期間の関与を担保するケースはありますが、事業承継ファンドではより柔軟な関与形態を設計できる点が特徴的です。
事業承継ファンドを活用するデメリット
事業承継ファンドは後継者不在の企業にとって有力な選択肢ですが、デメリットも存在します。ここでは、事業承継ファンドの主なデメリットについて解説します。
必ず支援を受けられるとは限らない
事業承継ファンドはすべての企業を支援するわけではなく、財務状況や成長見込みが厳しく審査されます。業績が悪化しすぎている場合や、短期間で企業価値を向上させるのが難しいと判断された場合、支援を断られるケースがあります。そのため、事業承継ファンドの利用を検討する際には、自社の現状を客観的に把握し、改善策を講じておくことが重要です。
自社に合ったファンドを見つけるのが難しい
事業承継ファンドには多くの種類があり、それぞれ得意分野や支援方針が異なります。自社のニーズに合わないファンドを選んでしまうと、適切な支援が受けられず、事業承継がスムーズに進まない可能性があるため注意が必要です。実績や支援内容を慎重に比較し、時間をかけて理想のファンドを選定することが求められます。
経営方針が変わるおそれがある
ファンドが一定期間企業を支援した後は、投資回収のためにM&Aが実施されることが一般的です。
その際、新たな経営陣によって経営方針が変わる可能性があり、創業者の意向が必ずしも引き継がれるとは限りません。企業文化の変化や事業戦略の転換が生じるリスクがあるため、ファンドのExit戦略について事前に確認しておくことが大切です。
事業承継ファンドを活用するためのポイント
事業承継ファンドを活用する際には、自社に適した選択をすることが重要です。承継の目的や選択肢の比較、専門家の助言を活用することで、スムーズな事業承継を実現できるでしょう。ここでは、成功のためのポイントを解説します。
事業承継の目的を明確にする
事業承継を成功させるには、まず「自社の事業承継の目的」を明確にすることが大切です。経営者が「企業の成長を目指しながら経営を続けたいのか」「完全に手放して引退したいのか」など、将来のビジョンを整理すると適切な選択肢を見極めやすくなります。
事業承継ファンドの活用とM&Aの適切な比較を行う
事業承継ファンドの活用が必ずしも適切とは限りません。ほかの承継手段と比較検討し、自社にとってより良い方法を選ぶことが重要です。M&Aでは第三者へ事業を譲渡することで経営資源を活用できる一方、ファンドは一定期間の経営支援を受けながら成長を目指せます。目的に応じた選択を行いましょう。
専門家に相談しながら進める
事業承継は専門性が高く、初めての経営者にとっては判断が難しいこともあります。M&A仲介会社やアドバイザーに相談することで、より適切な承継方法を選択しやすくなるでしょう。中立的な立場の専門家の意見を参考にしながら、自社に合うファンドを選ぶことが成功のポイントです。
まとめ|事業承継の方法は最適な選択を!専門家のサポートも活用しよう
事業承継を成功させるためには、事業承継ファンドへの売却や事業会社への売却など複数の選択肢を比較し、自社にとって理想的な方法を見極めることが重要です。どの手段が適しているかは企業の状況や承継の目的によって異なるため、経営者自身が方向性を明確にし、慎重に判断する必要があります。
また、事業承継は専門的な知識や手続きが求められるため、M&A仲介会社やアドバイザーなどの専門家のサポートを活用することも有効です。第三者の視点を取り入れることで、より適切な選択ができるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。