CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
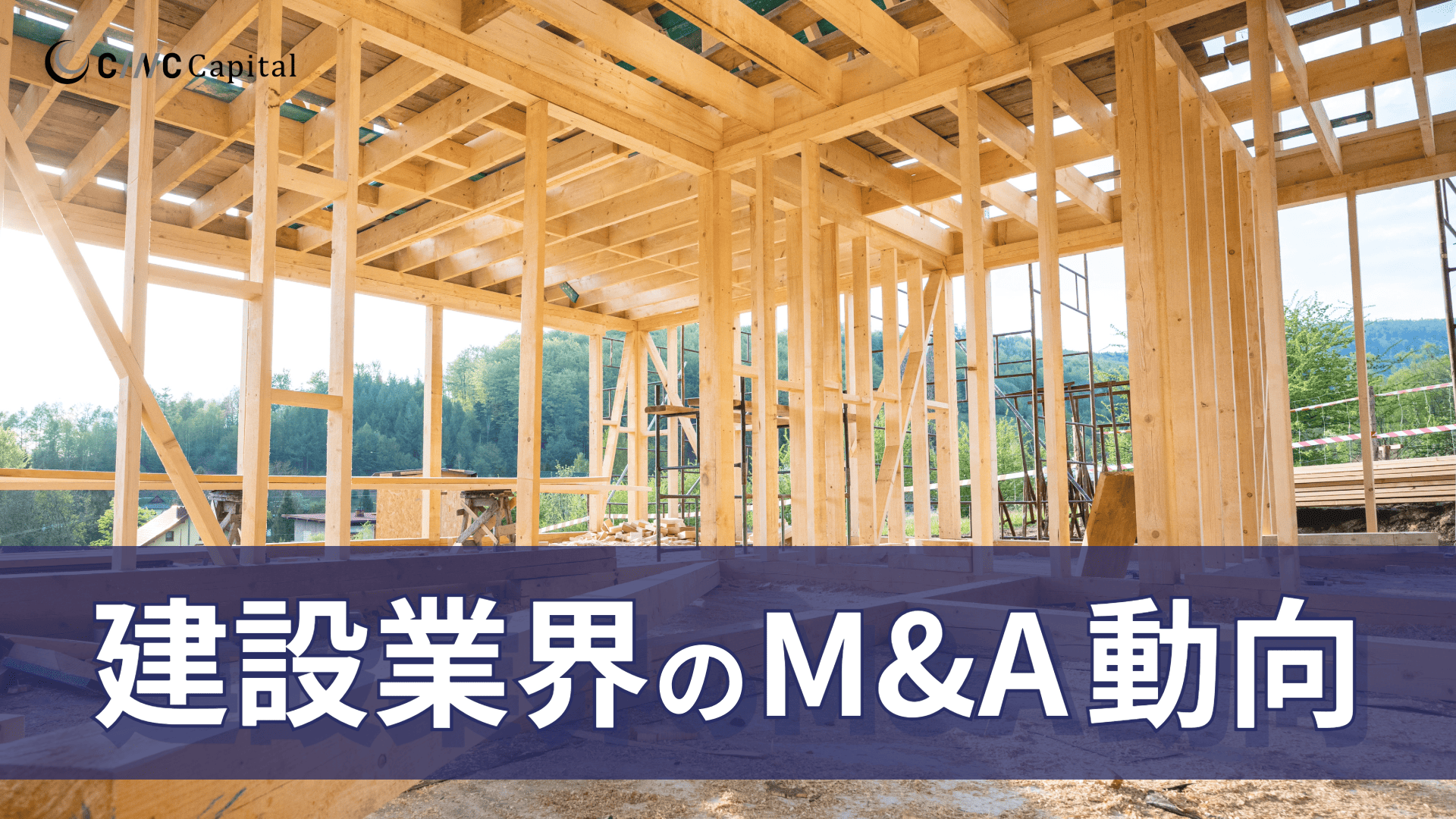
業種
- 最終更新日2025.07.08
建設業界の事業承継・M&A動向(2025年)メリット/事例/成功のポイントを解説
建設業界では、経営者の高齢化や人手不足が進行するなか、事業承継の重要性が増しています。しかし、後継者が見つからないことで廃業を選択する企業も多く、業界の大きな課題となっているのが現状です。こうした状況を打開する手段として、M&Aによる事業承継が注目されています。
適切なM&Aを活用すれば、会社の技術や人材を引き継ぎ、経営の安定化や成長のチャンスを得ることが可能です。本記事では、2025年の建設業界におけるM&Aの最新動向とその成功のポイントを解説し、企業の成長につながる戦略をご紹介します。
目次
建設業界の市場動向
建設業界は国内経済の動向に大きく左右される産業であり、近年は建設需要の回復とともに市場が拡大傾向にあります。
矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内建設8大市場の規模は前年度比104.8%の24兆2,989億円でした。
コロナ禍で延期されていた工事の再開や、工場・物流倉庫の需要増加が市場成長を後押ししました。
一方で、業界全体では資材価格や人件費の高騰が続いており、企業の利益圧迫や建設計画の見直しが課題となっています。
鉄鋼や木材価格の上昇(ウッドショック)が起こり、建設費全体の高騰を招いています。
さらに、建設業界では人手不足が深刻化しており、熟練技術者の減少が事業継続の大きなリスク要因の一つです。
【出典】株式会社矢野経済研究所「2025年国内建設8大市場に関する調査を実施」
建設業界が抱える課題
建設業界は長年にわたり成長してきましたが、現状では多くの課題を抱えています。ここでは、建設業界が直面している主要な課題について解説します。
人手不足と高齢化
建設業界では、労働力不足が深刻な問題です。特に、技術者や技能者の数が減少し、若年層の就業者の流入が少なくなっていることが問題視されています。業界全体の高齢化も進み、今後さらに若手の技術や技能を受け継ぐ人材が不足することが懸念されています。この人手不足により、業界全体の競争力が低下し、施工現場での労働負担が増大している状況です。
労働時間と賃金の問題
建設業界では、長時間労働と低賃金が問題となっています。十分な待遇を提供することが難しい場合、労働者のモチベーションや業務効率に悪影響を与えるでしょう。さらに、時間外労働の規制が厳しくなるなかで、業界全体の労働条件が改善される必要性が高まっているといえます。働き手を確保するためにも、業界のイメージ改善が求められているのが現状です。
許可の引き継ぎと管理責任者不足
建設業界の事業承継において、主な課題としては、許可の引き継ぎと経営業務の管理責任者不足が挙げられます。建設業を営むには国土交通省の許可が必要です。法人の場合は要件を満たすことで許可を引き継げますが、個人事業主の場合は許可が引き継げず、新たに申請が必要です。このため、事業承継後に営業を開始するまで時間がかかることがあります。
しかし、2019年の法改正により、相続や事業譲渡、合併によって許可を引き継ぐことが可能になりました。例えば親が亡くなった場合でも子どもが許可を引き継ぎ、事業を継続できるようになります。許可の審査期間は1〜4カ月です。
建設業界の事業承継・M&A最新動向(2025年)
建設業界では、後継者問題や業界の変化に対応するため、M&Aを活用する企業が見られます。ここでは、2025年の建設業界における主要なM&A動向について解説します。
後継者問題解消のための事業承継型M&A
建設業界では後継者不足が深刻な課題となっています。これを解消するため、事業承継型M&Aを選択するケースが見られます。特に、中小建設会社では経営者の高齢化に伴い後継者を見つけられないケースも多く、事業承継が難航中です。そのため、後継者がいない企業の中にはM&Aを活用して事業を継続し、廃業を避ける例もあるようです。今後も後継者問題を解決する手段として、M&Aが有効な選択肢の一つとなるでしょう。
異業種によるM&A
建設業界では、異業種とのM&A事例も見られます。例えば、ハウスメーカーや不動産会社が建設業の企業を買収するケースがあります。
異業種からの参入により、建設業界に新たな視点やノウハウが持ち込まれ、シナジー効果が期待されるのがメリットです。業務の効率化が進み、一貫したサービス提供も可能になります。
クロスボーダーM&A
国内市場の縮小が進むなか、海外市場への進出を目的としたクロスボーダーM&A事例も存在します。人口減少や少子高齢化の影響を受けて、国内市場での成長が難しくなっている企業が、海外の建設企業を買収する動きもあるようです。こうしたM&Aを実施することにより、企業は現地市場のニーズに対応しながら、グローバルな展開を進めやすくなります。
建設業がM&Aで売却するメリット
建設業界におけるM&Aの売却は、売り手側にもさまざまな利点があります。ここでは、売り手としてM&Aを選択することの具体的なメリットをご紹介します。
後継者問題が解消され、事業承継が円滑に進む
建設業界では後継者問題が深刻であり、多くの中小企業が事業承継に苦しんでいます。M&Aを通じて後継者不在の問題を解決し、事業承継をスムーズに行えることは大きなメリットです。従業員の雇用が守られ、取引先との関係も継続できるため、円滑な事業運営が可能になるでしょう。
売却益の享受
M&Aによって自社の株式を譲渡することで、創業者や経営者は売却益を享受できます。長年の経営努力が実を結び、売却金額としてまとまった資金を手に入れられるため、退職後の生活資金として活用できる場合もあります。
買い手の経営資源を活用し、運営コストを低減
買い手企業は売り手よりも規模が大きいケースも多いため、M&A後にはその経営資源を活用することが可能になります。例えば、建設機材や設備を共同で使用したり、企業信用を活かして価格交渉を有利に進めたりできるため、運営コストの低減が期待できます。効率的な事業運営が実現し、利益を最大化できるチャンスが広がるでしょう。
事業の成長と拡大
売却後は、買い手の資本力や人的資源を活用することで、自社では対応できなかった大型の工事や新規事業に取り組むことが可能になります。売り手が長年培ってきた技術やノウハウをさらに発展させ、会社の成長を実現できるのです。売却後も自社が成長する姿を見られることで、経営者としての達成感を得られます。
従業員の福利厚生が守られる
M&Aを選択することで従業員の雇用が維持され、福利厚生が守られる点も大きなメリットです。特に中小企業にとっては、従業員に対する給与や待遇の面で限界がある場合がありますが、買い手側の企業がこれを補完することで、従業員の生活安定が図れます。従業員のモチベーションが保たれ、事業の円滑な運営に寄与できるでしょう。
建設業がM&Aで売却を成功させるためのポイント
建設業界のM&Aを成功させるには、売却プロセスを慎重に進めることが大切です。ここでは、業界特有の注意点を押さえ、売却を成功に導くためのポイントをご紹介します。
経営資源の整理と評価
M&Aを進める前に、自社の経営資源を徹底的に整理して評価することが重要です。特に技術や人的資源といった目に見えない価値を正しく評価し、買い手に対して適切に伝えることが成功の秘訣となります。経営資源の整理が不十分だと、M&A後の統合に支障が出る可能性があるため、事前に準備しておきましょう。
従業員のフォローと条件の確約
M&A後に従業員が不安を感じ、離職することを防ぐためには、適切なフォローが欠かせません。待遇面や業務内容について確約し、買い手企業との交渉を通じて従業員が安心して働き続けられる環境を整えることが重要です。
取引先との関係継続
取引先との関係を守るために、M&A後も事業の継続性を保証することが求められます。取引先に対して、自社の存続やサービスの質が変わらないことを伝え、信頼を損なわないように配慮することが、スムーズな移行を実現します。
統合後の経営体制のすり合わせ
M&Aが成功した後は、買い手企業との経営統合がスムーズに進むように準備をしておく必要があります。事業運営における方針や社風を調整し、社員や関係者に対して明確に伝えることが、統合後のトラブルを回避するために重要です。
売却後の戦略的目標の設定
売却後も自身が関与する形で新たな戦略を模索することができる場合、M&A後に自社の成長をさらに促進するための戦略を立てることが求められます。自社の売却が、より大きな成長へのステップとなるような戦略を組み立て、具体的な目標設定を行うことが成功の要となります。
企業価値評価手法の理解と準備
建設業のM&Aにおいて不可欠なものの一つが、適切な企業価値評価の理解です。中小規模の建設会社の場合、一般的に「時価純資産+営業権法(基礎価額法)」や「マルチプル法(類似業種比準法)」によって企業価値が判断されます。
「時価純資産+営業権法」では、建設機械や不動産などの資産価値に「営業権(のれん)」を加味して企業価値を算出します。特に、施工実績や元請関係などの無形資産の評価が重視されます。
「マルチプル法」では、「EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)」の倍率を基に企業価値を算定します。建設業界の場合、3〜5倍程度の倍率が適用されることが多くなります。ただし、公共工事の受注実績や特殊技術、建設業許可の種類などによって評価が変わるため気をつけましょう。自社がどのような評価手法で査定されるかを理解し、それに応じた準備を行うことが、M&Aの成功につながります。
建設業界のM&A事例
最後に、建設業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
清水建設株式会社による丸彦渡辺建設株式会社のM&A
2023年5月、清水建設株式会社は、北海道札幌市の総合建設会社である丸彦渡辺建設株式会社の株式を過半数取得し、同社を連結子会社化しました。
丸彦渡辺建設は1918年創業の老舗で、建築・土木・リニューアル・機械設備分野を中心に、官公庁・民間双方から安定的に工事を受注してきた実績を持ちます。
清水建設は今回のM&Aを通じて、丸彦渡辺建設の地域密着型の営業基盤や人材を取り込み、建築・土木分野の事業強化を図ります。
特に北海道は、再生可能エネルギーの導入や観光資源の活用、新幹線延伸によるインフラ整備などで今後も建設需要が見込まれる地域であり、同地域でのプレゼンス向上に向けた戦略的投資と位置づけられます。大手ゼネコンによる地域有力建設会社の取り込みは、地方建設市場の競争力強化に寄与する事例といえます。
【出典】清水建設株式会社「丸彦渡辺建設株式会社の株式取得(子会社化)について」
明和工業株式会社による株式会社笠井組のM&A
2022年12月、明和工業株式会社は、新潟市を拠点とする老舗建設会社・株式会社笠井組の全株式を取得し、子会社化しました。
明和工業は水道資機材の製造施工を主力とする企業で、全国に営業拠点を持ちますが、少子化や節水志向により水道新設工事が減少する中、新たな成長分野として農業土木やエネルギー産業への進出を模索していました。
一方、笠井組は後継者不在に悩んでおり、従業員の雇用維持と事業継続の観点からグループ入りを選択。
今回のM&Aは、明和工業にとって土木工事分野の技術習得と人材確保を同時に実現する施策であり、事業多角化を通じた企業価値向上の一手と位置付けられます。地域密着型企業の承継型M&Aとしても、建設業界の今後の持続的成長における重要な一例です。
【出典】明和工業株式会社「株式会社笠井組の全株式取得について」
OCHIホールディングス株式会社による芳賀屋建設株式会社のM&A
2022年10月、建材・住宅設備機器の卸売大手であるOCHIホールディングス株式会社は、栃木県宇都宮市の建設会社・芳賀屋建設株式会社の全株式を取得し、子会社化しました。
芳賀屋建設は1931年創業、長年にわたり地域密着で建築・土木工事を手がけてきた実績を持ち、地元で確固たる信頼を築いています。
本件M&Aにより、OCHIホールディングスは関東地方におけるエンジニアリング事業を強化し、住建分野以外への事業ポートフォリオ拡大を目指す方針です。
建材卸から施工分野への展開は、商材と施工力の両面でシナジーを生み出す狙いがあり、地域建設業との提携による非住宅分野強化の好例といえます。住宅需要の変化に左右されにくい体質構築を目指す成長戦略の一環として注目される事例です。
【出典】OCHIホールディングス株式会社「芳賀屋建設株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|建設業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
建設業界におけるM&Aは、業界特有の課題を解決しながら企業の成長や競争力強化を目指せる重要な手段です。建設業許可や経営事項審査、法人化に伴う手続き、承継者選定など、事業譲渡や相続に関連する要件を正しく理解し、必要な書類を整えましょう。事前に経営状況を整理し、後継者選定や経営体制の整備などをしっかりと行い、信頼できる取引先を選ぶことも大切です。
M&Aは単なる取引ではなく、企業の未来を形作る大きな転機です。業界の動向を見据え、慎重かつ戦略的に進めることで、持続的な成長と競争力強化を実現しましょう。
建設業の事業承継やM&Aを進めるにあたっては、業界特有の事情に配慮できる仲介会社に相談することが重要です。CINC Capitalでは、建設業界特有の事情に深い理解を持つチームが、オーナー様のこれまでの歩みに寄り添いながらM&Aを支援いたします。
建設業許可のスムーズな承継や技術者の雇用継続といった業界ならではのポイントを押さえた上で、信頼できる譲渡先とのご縁をおつなぎします。

















