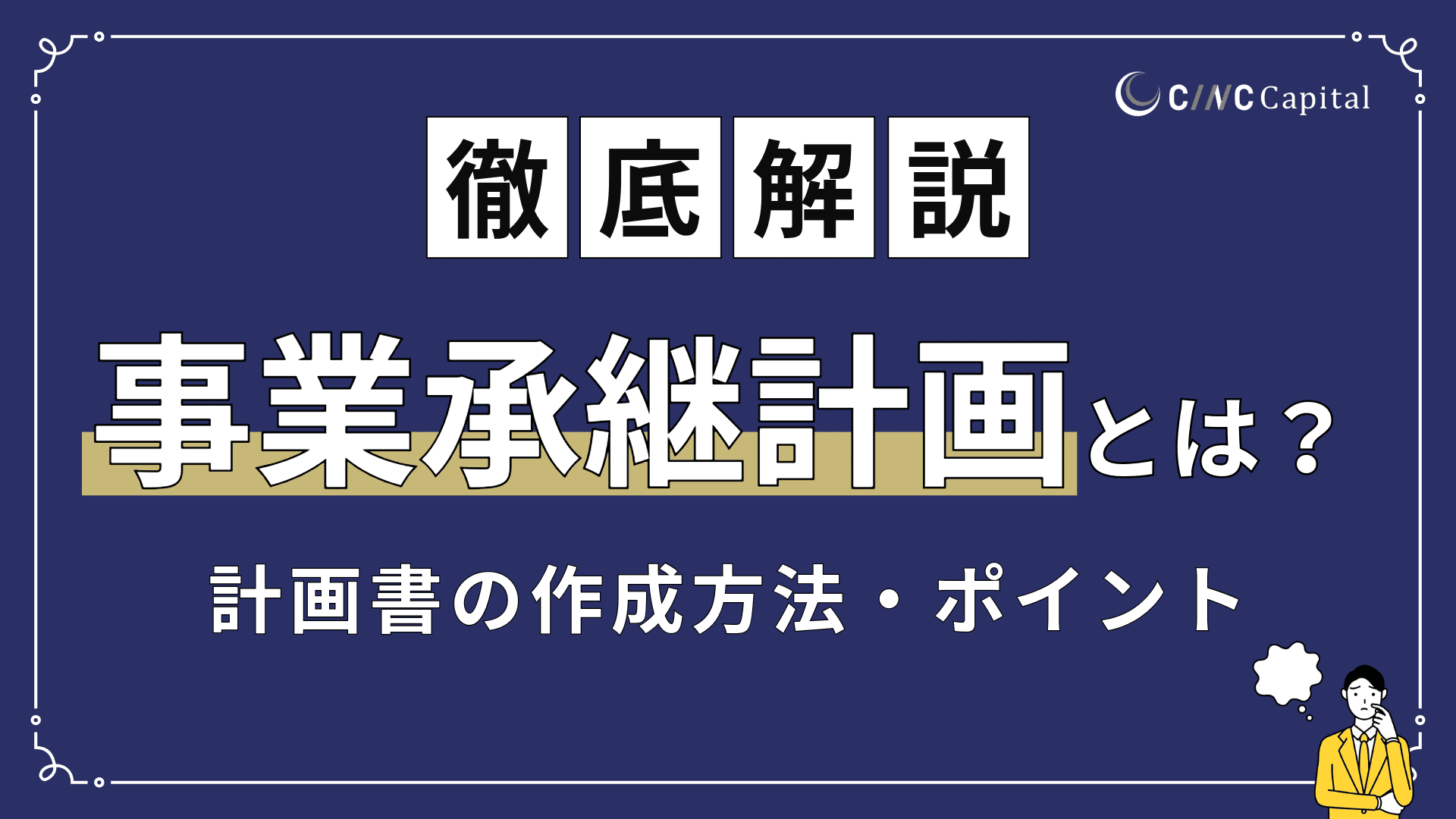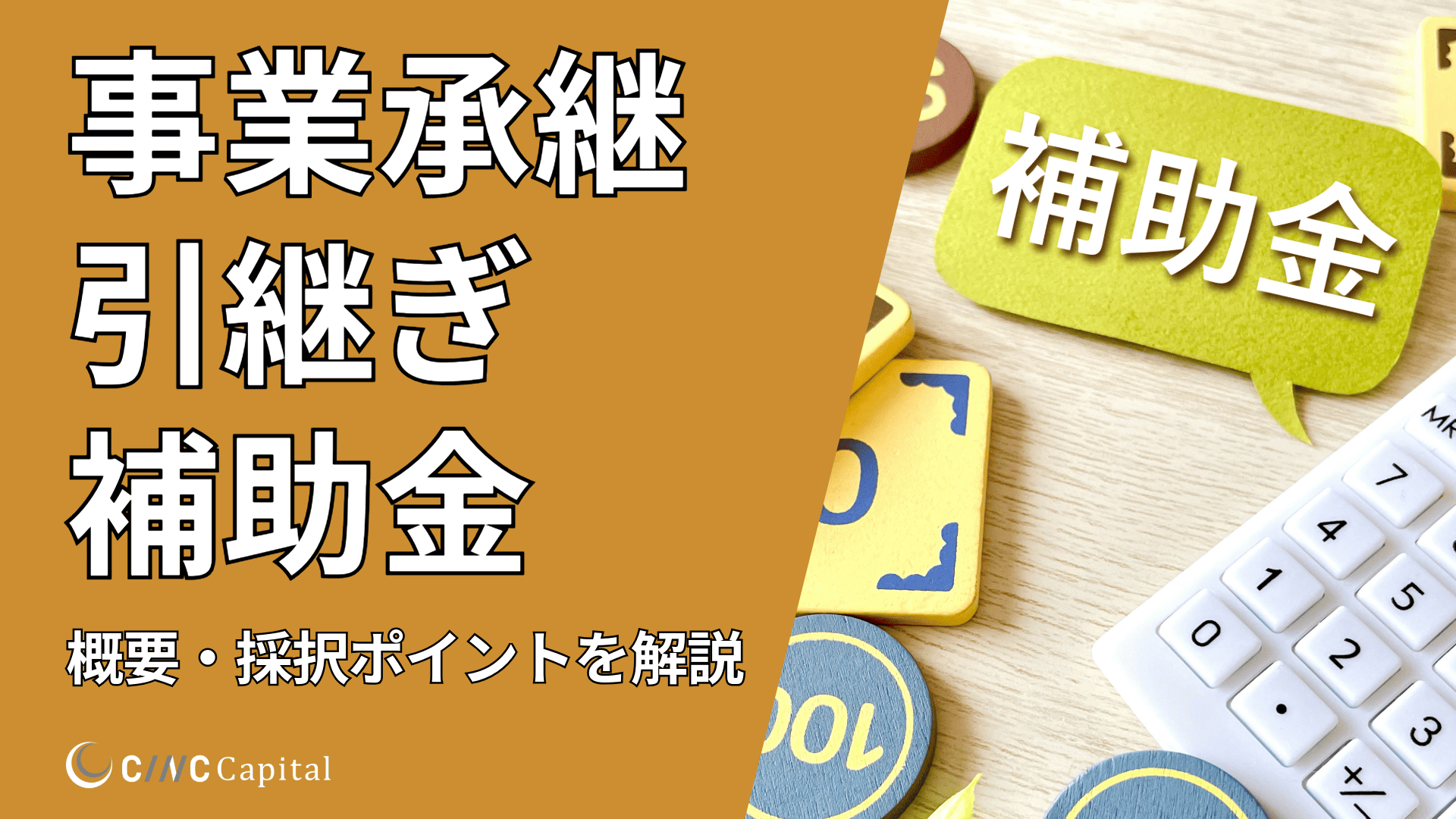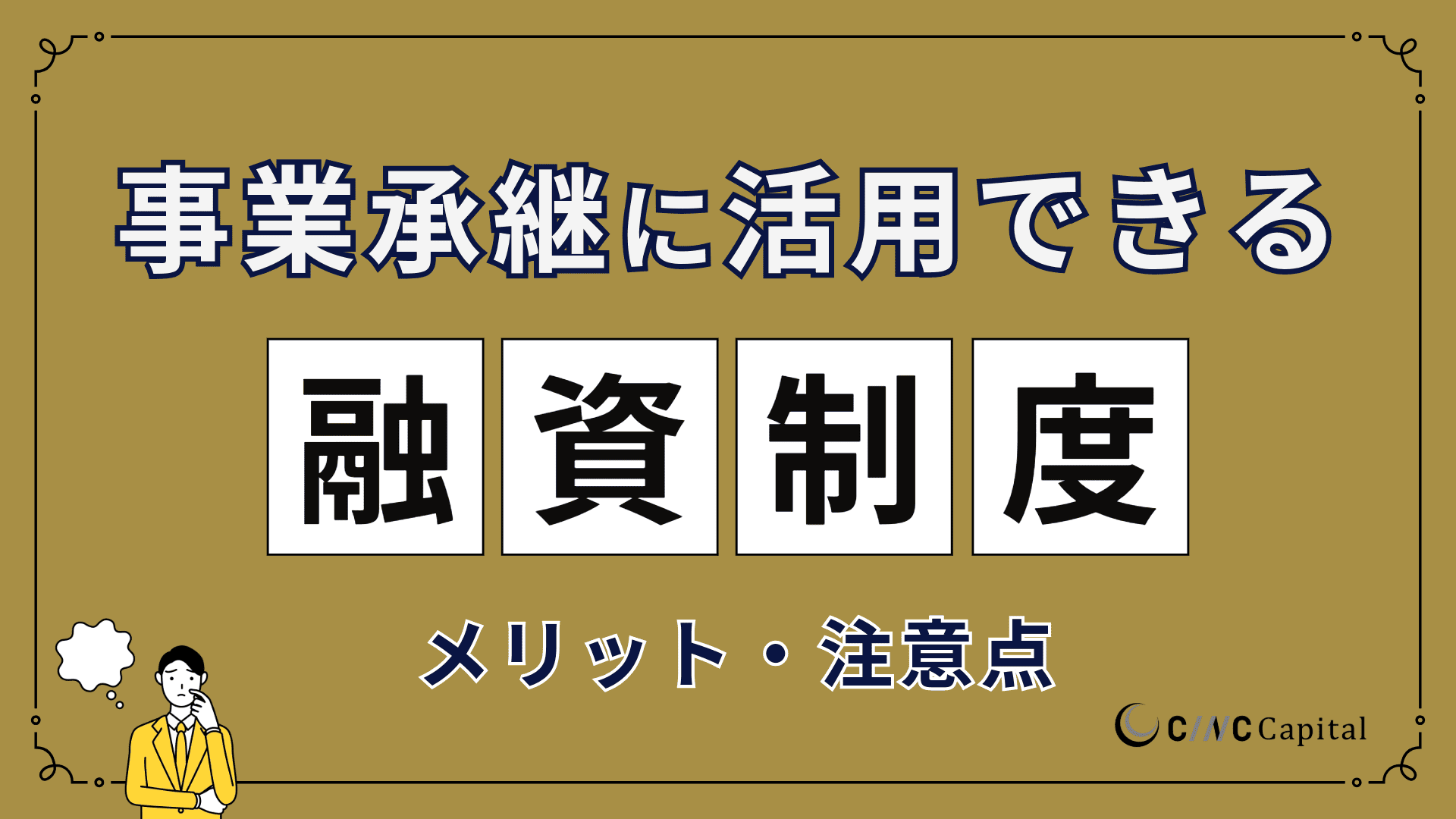CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
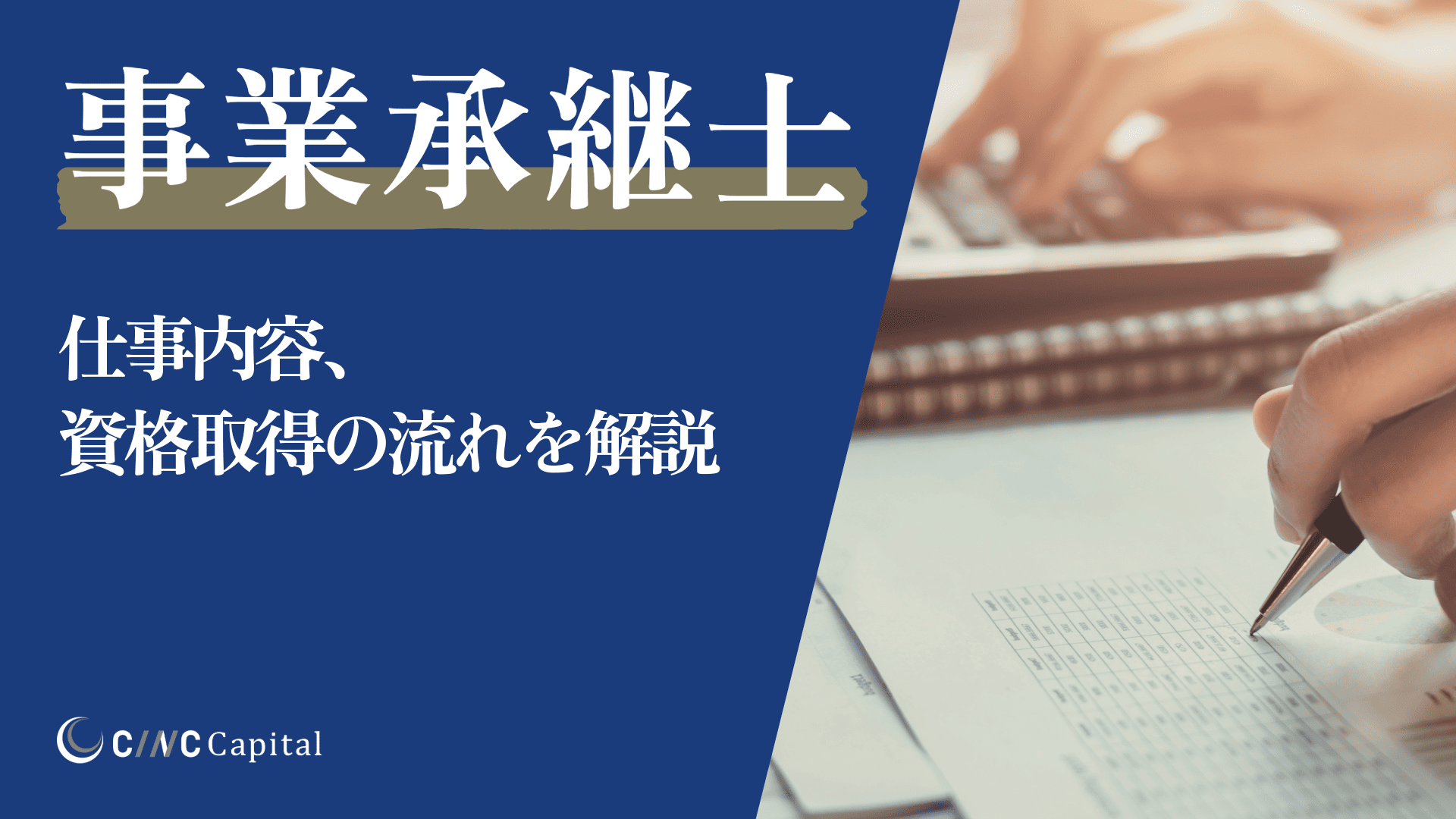
事業承継
- 最終更新日2025.07.08
事業承継士とは?仕事内容や資格を取得するメリット、取得の流れについて解説
日本の中小企業における経営者の高齢化が進む中、円滑な事業承継の重要性がますます高まっています。そんな中で注目されているのが「事業承継士」という資格です。
本記事では、事業承継士の概要から資格取得のメリット、取得の流れや活躍できる職場までをわかりやすく解説します。
目次
事業承継士とは?
事業承継士とは、事業承継に関する知識と実務能力を備えた専門家です。中小企業の円滑なM&Aなどの経営のバトンタッチをサポートする役割を担います。
受験資格・対象者
事業承継士の受験資格は、特定の学歴や実務経験がなくても誰でもチャレンジできる点が特徴です。経営者や士業、金融機関の職員など、事業承継に関心を持つ幅広い人が対象です。
特に中小企業診断士や税理士、金融業界で中小企業と関わる人にとっては、既存のスキルに事業承継の知識を加えることで、より高い専門性を発揮できます。実際に、士業や金融関係者のスキルアップとして取得されるケースが増加傾向にあります。
そのため、事業承継士は、実務経験者のみならず、今後この分野に携わりたいという志を持つ初心者にも門戸が開かれた資格といえるでしょう。
事業承継士の合格率
事業承継士の合格率は公表されていませんが、比較的合格しやすい部類に入る国家水準の民間資格です。十分な準備と学習を行えば、多くの受験者が資格取得を目指せるといえるでしょう。
ただし、講座のカリキュラムは実務を意識した内容が多く、受講だけでは対応が難しいと感じる人もいます。過去問や事例研究を活用して、知識を応用する力も問われるため、合格率の高さに安心せず、しっかりと準備することが大切です。
逆にいえば、合格後はそれだけの知識とスキルを持つ証明となるため、クライアントや他の士業との信頼関係を築く際に大きなアドバンテージとなります。
資格取得にかかる費用
事業承継士の資格取得には、受講料と受験料、入会金などを含めて約30万円の費用が必要です。これには、講義の受講料や認定試験の受験料、さらに資格認定後の協会入会金・年会費が含まれます。
|
項目 |
金額 |
|
受講料 |
330,000円 |
|
受験料 |
9,900円 |
|
入会金 |
11,000円 |
|
年会費 |
11,000円 |
|
更新料 |
3年ごとに5,500円 |
一見高額に見えるかもしれませんが、得られる知識と実務的な価値を考えると十分に見合った投資といえます。特に、士業やコンサルタントとして独立している方にとっては、報酬の単価向上にも直結するため、長期的には費用対効果の高い資格といえるでしょう。
事業承継士とほかの資格との違い
事業承継に関する資格は複数存在しますが、事業承継士はその中でも実務に強い点が特徴です。他資格との違いを比較してみましょう。
事業承継プランナーとの違い
事業承継プランナーは、主に事業承継の計画立案に特化した資格です。これに対し、事業承継士は計画立案に加え、実行段階での支援や関係者との調整まで広く対応する点が特徴です。
例えば、事業承継士は実際の後継者選定や育成、資産の移転など、より踏み込んだ支援が可能です。プランナーが「企画担当者」なら、事業承継士は「プロジェクトマネージャー」といえる存在です。
このように、理論だけでなく実務能力を評価される資格であるため、実際の支援現場で即戦力として活躍できます。
事業承継アドバイザーとの違い
事業承継アドバイザーは、主にアドバイス提供を目的とした資格です。一方、事業承継士は、アドバイスだけでなく、経営改善や後継者育成、税務対応など、より包括的な支援を行います。
実際の業務では、アドバイザーが概要的な提案を行うのに対し、事業承継士はその提案を具現化するための計画を策定し、関係者を巻き込んで実行へ導きます。
つまり、理論と実行の双方を担うポジションであり、クライアントからの信頼も厚くなりやすい点が強みです。
事業承継・M&Aエキスパート
事業承継・M&Aエキスパートは、M&Aを通じた承継を中心とした資格です。これに対し、事業承継士は親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)など、あらゆるケースに対応可能です。
そのため、M&Aに偏らず、総合的な視点で中小企業の将来を考えられる点が事業承継士の優位性といえます。事業の継続や地域経済への配慮を重視するケースでは、より幅広い視点で対応できる事業承継士の方が適しているといえるでしょう。
事業承継士の主な仕事内容
事業承継士は、中小企業の持続的な発展を支援するため、さまざまな観点から事業承継に関与します。ここでは具体的な仕事内容について見ていきましょう。
中小企業の経営者に対する事業承継のアドバイスを行う
事業承継士の主な仕事の一つが、経営者へのコンサルティングです。将来的な事業継続に不安を感じている経営者に対して、適切な承継方法やタイミング、リスク回避策などをアドバイスします。
例えば、親族内承継と第三者承継では、それぞれに必要な準備や課題が異なります。そのため、経営者の意向を尊重しつつ、事業の継続性と発展性を両立できるよう導く力が求められます。
単なる相談役ではなく、未来設計の伴走者としての役割が期待されるのが、事業承継士の特徴です。
後継者の選定や育成支援、承継計画の立案をサポートする
事業承継士は、後継者の選定や育成にも深く関わります。どのような人物が企業を継ぐべきか、その候補者が必要なスキルを習得するまでの育成計画を立て、経営者とともに実行します。
例えば、経営理念の継承やリーダーシップトレーニング、社内外との信頼関係構築といった具体的なステップを設け、計画的に引き継ぎを進めます。この支援により、事業承継後の経営の安定性が格段に向上します。
計画性に欠ける承継は、後継者の孤立や社員の離職を招くリスクがあります。そうならないためにも、事業承継士による計画的な支援が不可欠です。
税理士や弁護士など専門家と連携して承継を円滑に進める
事業承継は法務・税務・人事など多面的な課題が絡むため、事業承継士は他の専門家と連携しながら案件を進めます。税理士や弁護士とチームを組み、法的なリスク回避や節税策を検討することが一般的です。
例えば、自社株の評価と移転には高度な税務知識が必要です。また、親族間でのトラブル回避には法的アドバイスが欠かせません。事業承継士は全体のハブとして機能し、専門家の知見を最大限に活かす役割を担います。
単独で動くのではなく、チームとして顧客に最適解を提供する点が、他資格にはない事業承継士の実務的な強みです。
事業承継士の資格を取得するメリット
事業承継士の資格は単なる知識の証明ではなく、実務上の信頼性や人脈形成にも直結します。取得によって得られる具体的なメリットを紹介します。
事業承継に関する専門知識を体系的に習得できる
事業承継士の資格取得を通じて、法律・税務・財務・人事など、事業承継に必要な知識を体系的に学ぶことができます。独学では難しい範囲も、実務家による講座を通じて効果的に習得できます。
実際に講座では、事例研究やロールプレイを通じて、理論だけでなく実践に即したノウハウが得られます。これにより、現場で即活用できる力が養われ、現実の事業承継支援に自信を持って臨めます。
複雑化する事業承継の現場において、体系的な知識を持つことは大きな差別化要因になります。
中小企業支援における信頼性や専門性が高まる
事業承継士の資格を持つことで、中小企業の経営者からの信頼性が格段に高まります。資格があることで、「承継のプロ」として認識され、相談の間口が広がるのです。
とくに親族間承継や事業譲渡などセンシティブなテーマでは、知識だけでなく信頼性も重要です。資格保有者は、倫理規定や専門研修を通じてその信頼に応える準備が整っていると判断されやすくなります。
実務の現場では「誰に相談するか」が重要であり、資格がその選定基準となることも少なくありません。
士業や金融機関とのネットワークを広げやすくなる
事業承継士は資格取得後、日本事業承継協会に所属することで、全国の士業や金融機関とのネットワークを構築できます。この横のつながりが、仕事の紹介や共同支援につながることもあります。
例えば、税理士と連携して承継支援プロジェクトを行ったり、地元の金融機関から案件を紹介されたりすることも多くあります。専門家同士の横断的な関係構築は、単独で活動していた士業にとって大きなメリットです。
このネットワークがあれば、一人では対応できない複雑な案件にも対応可能となり、事業承継の現場でのプレゼンスが高まります。
事業承継士の資格取得の流れ
事業承継士の資格は、所定の講座を受講し、試験に合格し、協会に入会することで取得できます。ここではその具体的な流れを紹介します。
Step1.資格取得講座を受講する
まずは事業承継協会が提供する資格取得講座を受講します。この講座では、事業承継の基礎から実務対応まで幅広く学べます。
受講形式はオンラインが中心で、地方在住者でも受講しやすい設計になっています。約20時間程度のカリキュラムで、実践的な内容が中心です。
この講座を通じて、事業承継士として必要な知識と考え方を体系的に習得することができます。
Step2.認定試験へ受験する
講座を修了すると、認定試験の受験資格が得られます。試験は筆記形式で、主に講座内容の理解度を問われる問題が出題されます。
合格率は約60%と比較的高めですが、講座の内容をしっかり復習しておくことが合格への近道です。過去問や模擬試験を活用して、自信を持って臨みましょう。
合格後には正式に事業承継士として認定され、次のステップである協会への入会手続きに進みます。
Step3.事業承継協会への入会する
試験に合格した後は、日本事業承継協会に入会することで資格が正式に付与されます。入会後は、年会費を支払うことで継続的な研修やネットワーキング、情報提供を受けることができます。
この協会は、事業承継士同士のつながりを生み、実務での支援体制を広げる場でもあります。地域ごとの活動やセミナーも開催されており、常に最新の情報を得られるのも大きな魅力です。
資格取得後のフォロー体制が整っているため、初心者でも安心して活動をスタートできます。
事業承継士の資格が活かせる職場
事業承継士の資格は、多岐にわたる業界で活用されています。実際にどのような職場で求められているのかを見ていきましょう。
事業承継・引継ぎ支援センター
全国に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継士の活躍の場として非常に適しています。ここでは中小企業の事業承継に関する無料相談やマッチング支援を行っています。
公的機関であるため、安定した環境で実務経験を積むことができ、独立を視野に入れる人にとっても絶好のステップアップの場となります。
事業承継士としてのスキルを最大限に発揮できる実務の現場として注目されています。
M&A仲介会社
M&A仲介会社では、特に第三者承継を希望する企業に対してのマッチング支援を行う場面で、事業承継士の専門性が活かされます。
買い手・売り手の要望を的確に理解し、合意形成まで導く交渉力や調整力が求められます。こうしたスキルは、事業承継士の研修で習得できるため、現場で即戦力として評価されやすいです。
M&Aの現場で、法律や税務にも精通した人材として重宝されるのが事業承継士です。
金融機関
銀行や信用金庫といった金融機関では、事業承継相談に対応するために事業承継士の資格を持つ行員が増えています。
金融商品や融資と連携した提案を行う上で、承継の知識は非常に重要です。資格を保有していることで、企業への提案の幅が広がり、顧客からの信頼も高まります。
特に地域密着型の金融機関にとっては、事業承継支援は新たな顧客接点の創出としても位置付けられています。
会計事務所や税理士事務所
税務の専門家である税理士や会計士が、事業承継士の資格を併せ持つことで、資産の移転や自社株の評価といった複雑な案件にもワンストップで対応できるようになります。
顧客からの信頼も厚くなり、コンサルティング業務の拡張にもつながります。実際、多くの税理士がこの資格を取得し、サービスの幅を広げています。
法律事務所
遺言や相続、契約関係など、事業承継の中でも法的側面を担当する弁護士にも、この資格は有用です。事業承継士としての視点を持つことで、法律だけでなく経営や税務の観点からも総合的な支援が可能になります。
これにより、クライアントに対してより説得力のある提案ができるようになります。
法律実務と経営支援の橋渡しとして、事業承継士の資格は弁護士にも価値の高い武器となります。
まとめ|事業承継士は事業承継支援に欠かせない存在
事業承継士は、今後ますます需要が高まる中小企業の承継支援において、欠かせない存在です。資格を取得することで、知識やスキルの習得はもちろん、信頼性の向上や人脈形成にもつながります。
取得のハードルはそれほど高くなく、体系的に学べる環境が整っているため、事業承継支援に関心のある方は、ぜひ挑戦してみることをおすすめします。
実務に強いこの資格を活かして、多くの企業の未来を支える専門家を目指してみてはいかがでしょうか。